2008年08月31日
音色再考1。
今年も香川県では水不足で、取水制限などが始まっています。
ここ最近、雨の日もあるのですが、隣の県のダムから水を分けてもらっているため、自分の家の周辺に雨が降ってもたいした水不足の解消になりません。
今年は水不足がより深刻で、また給水車のお世話になる日が近いのかもしれません。
さて、話は変わりますが、4月末に行われた私の所属する社会人吹奏楽団「高松ウインドシンフォニー」の定期演奏会の録音CDが出来上がってきました。
毎年のように、録音に凹む私、今年も同じように凹ませていただきました。
自分としてはまったく納得の行かない演奏だった印象の演奏会なのですが、
本当は、自分の演奏の録音を真剣に聴く趣味などないのですが、
まあ、録音を聞いて一回は反省なんぞをしておいた方がよいだろうと。
凹むのを覚悟で、聞いてみました……

この画像は関係ない画像だったりします。↑
やっぱり凹みました…。
いや、私の音が マイクに拾われすぎです。
自分で気にするからそうなのかもしれませんが、間違いなく、音が抜けて聞こえます。
木管全体のユニゾンの時でも音が溶け合わずに私の音だけ別撮りしたように聞こえたいたりします。
いや、決してピッチが極端に悪いというわけではなく、
音程は結構いい線をいっているのですが、
音色がどうも他の楽器と溶け合う気配がありません。
私は以前から音が大きいとよく言われますが、
音量として捉えるならば、めちゃくちゃに大きいことはありえないと思います。
なぜなら、同じサックスでいくら力いっぱい吹いても、
楽器がそこそこコントロールできる人同士であれば、 音量的な差はたかが知れています。
私の音の場合、ffではなく、PPで吹いたときでも、 録音を聴くとすぐにばれる音色です。
しかも、その音色が限りなく美しい音色であれば問題は少ないのでしょうが、
限りなくチープで硬い音、しかもノイジーです。
よく、マイク乗りのいい音という言葉を聴きます。
JAZZプレーヤーの方が、よくこんな表現を使うのを耳にする気がするのですが、(PAを使用した演奏が多いためでしょうか…)
私の場合は、吹奏楽の演奏においてもマイク乗りのいい音らしく…。
もっとブレンドされる柔らかい音色を研究しなければなりません。
吹奏楽にはそぐわない、個性的な音なのかもしれません。
でも、ジャジーな音でも有りません。
ただ、以前のサクソフォン・アンサンブルコンサートでの
ボレロの冒頭のソロを思い出してみるに、
やはり私の音はPPでも限りなくマイクに拾われやすい音なのは
間違いがないようです。
ここ最近、雨の日もあるのですが、隣の県のダムから水を分けてもらっているため、自分の家の周辺に雨が降ってもたいした水不足の解消になりません。
今年は水不足がより深刻で、また給水車のお世話になる日が近いのかもしれません。
さて、話は変わりますが、4月末に行われた私の所属する社会人吹奏楽団「高松ウインドシンフォニー」の定期演奏会の録音CDが出来上がってきました。
毎年のように、録音に凹む私、今年も同じように凹ませていただきました。
自分としてはまったく納得の行かない演奏だった印象の演奏会なのですが、
本当は、自分の演奏の録音を真剣に聴く趣味などないのですが、
まあ、録音を聞いて一回は反省なんぞをしておいた方がよいだろうと。
凹むのを覚悟で、聞いてみました……
この画像は関係ない画像だったりします。↑
やっぱり凹みました…。
いや、私の音が マイクに拾われすぎです。
自分で気にするからそうなのかもしれませんが、間違いなく、音が抜けて聞こえます。
木管全体のユニゾンの時でも音が溶け合わずに私の音だけ別撮りしたように聞こえたいたりします。
いや、決してピッチが極端に悪いというわけではなく、
音程は結構いい線をいっているのですが、
音色がどうも他の楽器と溶け合う気配がありません。
私は以前から音が大きいとよく言われますが、
音量として捉えるならば、めちゃくちゃに大きいことはありえないと思います。
なぜなら、同じサックスでいくら力いっぱい吹いても、
楽器がそこそこコントロールできる人同士であれば、 音量的な差はたかが知れています。
私の音の場合、ffではなく、PPで吹いたときでも、 録音を聴くとすぐにばれる音色です。
しかも、その音色が限りなく美しい音色であれば問題は少ないのでしょうが、
限りなくチープで硬い音、しかもノイジーです。
よく、マイク乗りのいい音という言葉を聴きます。
JAZZプレーヤーの方が、よくこんな表現を使うのを耳にする気がするのですが、(PAを使用した演奏が多いためでしょうか…)
私の場合は、吹奏楽の演奏においてもマイク乗りのいい音らしく…。
もっとブレンドされる柔らかい音色を研究しなければなりません。
吹奏楽にはそぐわない、個性的な音なのかもしれません。
でも、ジャジーな音でも有りません。
ただ、以前のサクソフォン・アンサンブルコンサートでの
ボレロの冒頭のソロを思い出してみるに、
やはり私の音はPPでも限りなくマイクに拾われやすい音なのは
間違いがないようです。
2008年08月31日
いつもの。
まだまだ暑い日が続いています。台風のシーズンでもありますが、今年は台風も少ないようです。でもあまり台風を期待するのも良くないかもしれません。台風などで大きな被害が出ると、日常の生活で、いつもの生活に戻るまでには時間がかかります。見慣れた建物が無くなったり、見慣れた木々がなくなったりすることもしばしばです。
いつもの景色、いつものリズム、いつもの音、いつもの日常、いつものものは、何気なく感じていますが、こうやって災害などで、「いつもの」が失われてしまうと、初めて気づいたりします。
何気に見ている、いつものものが大切だったり、自分の中で重要な位置を占めていたりします。
そこで今日の一枚です。

French Music for Saxophone Quartet
/Aurelia Saxophone Quartet
Etcetera KTC 1104
このCDはオーレリア・サクソフォーン・カルテットのフランスものの曲の演奏を集めたアルバムです。サックス吹きには耳慣れたいつもの音楽がたくさん収録されています。
曲目は、アンダンテとスケルツォ (ボザ) 、サクソフォン四重奏曲 (デザンクロ) 、小組曲 (フランセ) 、グラーヴェとプレスト (リヴィエ) 、サクソフォン四重奏曲 (シュミット) 、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲 (ピエルネ) とまさにスタンダードなサクソフォン・カルテットと言った
曲ばかりです。逆に、日本で最近録音されたアルバムで、これだけの曲を一枚に収めたものはあまり見かけません。今から、20~30年ぐらい前はデファイエ四重奏団や、ミュールやギャルドの四重奏団による、これらの曲の録音が盛んに発売されていたのにもかかわらず、いまは、これだけの曲を取り上げる、アルバムは非常に少なくなりました。もしかしたら、サクソフォーン・アンサンブルにとってはもはや古典になった曲ということなのかもしれませんが、デザンクロや、シュミット以外の曲もまだまだサクソフォーンにとっては重要なレパートリーのはずですし、この中の曲を取り上げてCDに収録しているのはよく見かけます。でも、一気に取り上げるのは珍しくなってきています。
演奏のほうは、楽譜を丁寧に読み込んだような表現が感じられるものです。技術的には時には??と思わせる点もなきにしもあらずなのですが、その表現への取り組みは技術面を差し引いても余りある気がします。
現代曲に聴き疲れしたときも、スタンダードないつものサクソフォーン・カルテットが聞きたいときもオススメな一枚です。
いつもの景色、いつものリズム、いつもの音、いつもの日常、いつものものは、何気なく感じていますが、こうやって災害などで、「いつもの」が失われてしまうと、初めて気づいたりします。
何気に見ている、いつものものが大切だったり、自分の中で重要な位置を占めていたりします。
そこで今日の一枚です。

French Music for Saxophone Quartet
/Aurelia Saxophone Quartet
Etcetera KTC 1104
このCDはオーレリア・サクソフォーン・カルテットのフランスものの曲の演奏を集めたアルバムです。サックス吹きには耳慣れたいつもの音楽がたくさん収録されています。
曲目は、アンダンテとスケルツォ (ボザ) 、サクソフォン四重奏曲 (デザンクロ) 、小組曲 (フランセ) 、グラーヴェとプレスト (リヴィエ) 、サクソフォン四重奏曲 (シュミット) 、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲 (ピエルネ) とまさにスタンダードなサクソフォン・カルテットと言った
曲ばかりです。逆に、日本で最近録音されたアルバムで、これだけの曲を一枚に収めたものはあまり見かけません。今から、20~30年ぐらい前はデファイエ四重奏団や、ミュールやギャルドの四重奏団による、これらの曲の録音が盛んに発売されていたのにもかかわらず、いまは、これだけの曲を取り上げる、アルバムは非常に少なくなりました。もしかしたら、サクソフォーン・アンサンブルにとってはもはや古典になった曲ということなのかもしれませんが、デザンクロや、シュミット以外の曲もまだまだサクソフォーンにとっては重要なレパートリーのはずですし、この中の曲を取り上げてCDに収録しているのはよく見かけます。でも、一気に取り上げるのは珍しくなってきています。
演奏のほうは、楽譜を丁寧に読み込んだような表現が感じられるものです。技術的には時には??と思わせる点もなきにしもあらずなのですが、その表現への取り組みは技術面を差し引いても余りある気がします。
現代曲に聴き疲れしたときも、スタンダードないつものサクソフォーン・カルテットが聞きたいときもオススメな一枚です。
2008年08月30日
気をとりなおす。
明日で8月も終わります。
以前、このブログに掲載したこともありますが、使っているポータブルヘッドフォン、AKGのK26P。最近、このヘッドフォンのイヤーパッドが徐々にボロボロになってきていたのですが、今日ついに破れてヘッドフォン本体から脱落してしまいました。結構気に入って使っていただけに残念でなりません。一応、イヤーパッドの交換品を購入することが出来るものの、2000円程度。ヘッドフォン自体6000円ぐらいで購入しましたので、価格の3分の1はイヤーパッド代ということになるのでしょうか。保守部品は割高なのが常なので、仕方ないといえば仕方ないのですが…。
個々で悩みどころ。3年以上使ったヘッドフォン、買い換えてしまうのか、使い慣れたヘッドフォン、イヤーパッドを購入して交換して使用するか…。
しかし、どの道、ヘッドホンがしばらく使えない状態なのは確かなので、何となく凹みます。
まあ、いつまでもへこんでいても仕方ありません、気を取り直して生きたいと思います。私の信条というか、常に、心に留めていることは、形あるものいつかは壊れたり、無くなったりする、壊れたり無くなったりしないものは形の目に見えないものだ、というのがあるのですが、今回もそれを実践したいと思っています。
そこで今日の一枚です。

Blow!
Saxophone Music from America/Aurelia Saxophone Quartet
CHAEENGE Classics 72005
このCDはオーレリア・サクソフォーン・カルテットのライヴアルバムです。新旧様々なアメリカ名音楽が多種多彩に入ったプログラムです。
Blow!というタイトルにふさわしいようなジャケットで、どうだ!というばかりにサックス4本を持った様子が撮影されています。曲目は、ラプソディ・イン・ブルー (ガーシュウィン) 、アダージョ (バーバー) 、Four5 (ケージ)Canonic組曲(カーター) 、July(7月) (トーク) 、Blow! (ゴールドスタイン) 、カム・トゥルー (ドゥラム) 、マスター・ボップ・ブラスター (ドゥラム)となっています。
実は、この中の7月 は楽譜をみて、チャレンジしたことがあるのですが、実はこの曲俗に言うミニマル・ミュージックというもので、どのパートも同じような動きを、調を変えて何度も繰り返す、という楽譜になっています。長い音符の繰り返しなら、まだいいのですが、細かい音符を延々繰り返すと頭が多少馬鹿になってきて、何をやっているのか、楽譜のどこを吹いているのか分からなくなって各パート次々に落ちていきます。(笑)そこで、気をとりなおして、適当な小節からとりあえずリスタートするのですが、しばらくすると、また、同じように、気をとりなおしての繰り返し…。結局、3年たった今でも、我々の演奏会の曲目に加わることはありません。
多少現代曲チックな物もありますが、そう難解でも無いので、聞きやすいと思います。演奏のほうはオーレリアらしい演奏に加え、ライヴでのノリのよさが伝わってきます。特にアルバムタイトルにもなっているBlow!の後半のノリとテクニックには圧倒させられます。また、曲によってはロックを髣髴とさせるテイストのものもあり(特にボーカル入りのマスター・バップ・ブラスター)、これにも圧倒されます。
サックス・アンサンブルの熱いライヴを疑似体験してみたい方にオススメの一枚です。
以前、このブログに掲載したこともありますが、使っているポータブルヘッドフォン、AKGのK26P。最近、このヘッドフォンのイヤーパッドが徐々にボロボロになってきていたのですが、今日ついに破れてヘッドフォン本体から脱落してしまいました。結構気に入って使っていただけに残念でなりません。一応、イヤーパッドの交換品を購入することが出来るものの、2000円程度。ヘッドフォン自体6000円ぐらいで購入しましたので、価格の3分の1はイヤーパッド代ということになるのでしょうか。保守部品は割高なのが常なので、仕方ないといえば仕方ないのですが…。
個々で悩みどころ。3年以上使ったヘッドフォン、買い換えてしまうのか、使い慣れたヘッドフォン、イヤーパッドを購入して交換して使用するか…。
しかし、どの道、ヘッドホンがしばらく使えない状態なのは確かなので、何となく凹みます。
まあ、いつまでもへこんでいても仕方ありません、気を取り直して生きたいと思います。私の信条というか、常に、心に留めていることは、形あるものいつかは壊れたり、無くなったりする、壊れたり無くなったりしないものは形の目に見えないものだ、というのがあるのですが、今回もそれを実践したいと思っています。
そこで今日の一枚です。
Blow!
Saxophone Music from America/Aurelia Saxophone Quartet
CHAEENGE Classics 72005
このCDはオーレリア・サクソフォーン・カルテットのライヴアルバムです。新旧様々なアメリカ名音楽が多種多彩に入ったプログラムです。
Blow!というタイトルにふさわしいようなジャケットで、どうだ!というばかりにサックス4本を持った様子が撮影されています。曲目は、ラプソディ・イン・ブルー (ガーシュウィン) 、アダージョ (バーバー) 、Four5 (ケージ)Canonic組曲(カーター) 、July(7月) (トーク) 、Blow! (ゴールドスタイン) 、カム・トゥルー (ドゥラム) 、マスター・ボップ・ブラスター (ドゥラム)となっています。
実は、この中の7月 は楽譜をみて、チャレンジしたことがあるのですが、実はこの曲俗に言うミニマル・ミュージックというもので、どのパートも同じような動きを、調を変えて何度も繰り返す、という楽譜になっています。長い音符の繰り返しなら、まだいいのですが、細かい音符を延々繰り返すと頭が多少馬鹿になってきて、何をやっているのか、楽譜のどこを吹いているのか分からなくなって各パート次々に落ちていきます。(笑)そこで、気をとりなおして、適当な小節からとりあえずリスタートするのですが、しばらくすると、また、同じように、気をとりなおしての繰り返し…。結局、3年たった今でも、我々の演奏会の曲目に加わることはありません。
多少現代曲チックな物もありますが、そう難解でも無いので、聞きやすいと思います。演奏のほうはオーレリアらしい演奏に加え、ライヴでのノリのよさが伝わってきます。特にアルバムタイトルにもなっているBlow!の後半のノリとテクニックには圧倒させられます。また、曲によってはロックを髣髴とさせるテイストのものもあり(特にボーカル入りのマスター・バップ・ブラスター)、これにも圧倒されます。
サックス・アンサンブルの熱いライヴを疑似体験してみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月29日
様々なジャンル。
8月も残すところあと2日。終り行く夏を感じることなく、夏が終わってゆきそうです。
さて、私は音楽鑑賞と、サクソフォーンの演奏を趣味としていますが、クラシカルサクソフォーンが中心であるものの、それにこだわることなく様々な音楽を聴いています。
私が一番最初に、サクソフォーンの音源を購入したのはまだレコードがメディアとして全盛の時代。それから時代も約四半世紀が経過し、メディアがCDとなり、やがては、ネット配信という形態になりつつあります。ネット配信によって様々な音楽に触れる機会が増えた反面、特定のコアなジャンルや、クラシックはネット配信がまだまだ不足している感が否めません。やはり、自分の欲しい音源はCDで買わないと手に入らないことがまだまだあります。世界的に景気が悪くなると、レコーディングや、CDの発売が減っていくのはやっぱり仕方ないのかもしれませんが、昔に比べてクラシックの新録音が少ないのもちょっと寂しい気がしますが…。
これからも、自分が思いつくままに様々な音楽を聴いていきたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

Mysterious Morning/Quatuor de saxophones HABANERA
Alpha 010
このCDハバネラ四重奏団による現代曲ばかりを集めたものです。邦人作品も含まれています。ハバネラ四重奏団は以前にも「Grieg, Glazounov, Dvorák」というアルバムを紹介しましたが、あのアルバムから想像すると、ちょっと驚くほどの現代曲のオンパレードです。
曲目は6つのバガテル (リゲティ) 、奇妙な朝II (棚田文紀) 、ラッシュ (ドナトーニ) 、XAS (クセナキス) 、ラッシュII (ドナトーニ) 、イン・エルヴァルタン (グバイドリーナ) という、どれも難解な難曲ばかりです。
ちょっと聞いた感じでは「何じゃこりゃ?」というイメージを持ってしまいます。私自身現代曲が得意でないために、こう思ってしまうのかもしれませんが、最初は聞きづらい訳の分からない音楽だと思いました。実際、どれも無調で、旋律の無いような分かりにくい曲です。
しかし、音楽のつくりがしっかりしているせいか、現代曲が苦手な私でも、何度か聞くうちに少しずつ、聞きやすくなってきました。現代曲にありがちな、訳の分からないことを淡々と、ということだけでもなく、きっちりとしっかりした表現もなされているのだと感じる部分もあります。ただ単に聞きなれただけなのかもしれませんが。
でも、私の現代音楽が苦手なのはかわらず、いまひとつ、この音楽のよさが分からないでいるのも事実です。もろ手をあげて、この音楽はイイ!とはいえない私がいます。しかし、様々なジャンルを聞くことに抵抗は感じていませんし、また、様々なジャンルに触れることは大切だとも感じています。
サクソフォーンによる、現代曲のアンサンブルを聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、私は音楽鑑賞と、サクソフォーンの演奏を趣味としていますが、クラシカルサクソフォーンが中心であるものの、それにこだわることなく様々な音楽を聴いています。
私が一番最初に、サクソフォーンの音源を購入したのはまだレコードがメディアとして全盛の時代。それから時代も約四半世紀が経過し、メディアがCDとなり、やがては、ネット配信という形態になりつつあります。ネット配信によって様々な音楽に触れる機会が増えた反面、特定のコアなジャンルや、クラシックはネット配信がまだまだ不足している感が否めません。やはり、自分の欲しい音源はCDで買わないと手に入らないことがまだまだあります。世界的に景気が悪くなると、レコーディングや、CDの発売が減っていくのはやっぱり仕方ないのかもしれませんが、昔に比べてクラシックの新録音が少ないのもちょっと寂しい気がしますが…。
これからも、自分が思いつくままに様々な音楽を聴いていきたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

Mysterious Morning/Quatuor de saxophones HABANERA
Alpha 010
このCDハバネラ四重奏団による現代曲ばかりを集めたものです。邦人作品も含まれています。ハバネラ四重奏団は以前にも「Grieg, Glazounov, Dvorák」というアルバムを紹介しましたが、あのアルバムから想像すると、ちょっと驚くほどの現代曲のオンパレードです。
曲目は6つのバガテル (リゲティ) 、奇妙な朝II (棚田文紀) 、ラッシュ (ドナトーニ) 、XAS (クセナキス) 、ラッシュII (ドナトーニ) 、イン・エルヴァルタン (グバイドリーナ) という、どれも難解な難曲ばかりです。
ちょっと聞いた感じでは「何じゃこりゃ?」というイメージを持ってしまいます。私自身現代曲が得意でないために、こう思ってしまうのかもしれませんが、最初は聞きづらい訳の分からない音楽だと思いました。実際、どれも無調で、旋律の無いような分かりにくい曲です。
しかし、音楽のつくりがしっかりしているせいか、現代曲が苦手な私でも、何度か聞くうちに少しずつ、聞きやすくなってきました。現代曲にありがちな、訳の分からないことを淡々と、ということだけでもなく、きっちりとしっかりした表現もなされているのだと感じる部分もあります。ただ単に聞きなれただけなのかもしれませんが。
でも、私の現代音楽が苦手なのはかわらず、いまひとつ、この音楽のよさが分からないでいるのも事実です。もろ手をあげて、この音楽はイイ!とはいえない私がいます。しかし、様々なジャンルを聞くことに抵抗は感じていませんし、また、様々なジャンルに触れることは大切だとも感じています。
サクソフォーンによる、現代曲のアンサンブルを聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月28日
落ち着く。
今日も朝から雨模様。気温も低めとなりましたが、湿度が高いので、べたつく一日でした。8月もあと残すところ3日となりました。今年はいつもに比べて台風も少なく、おかげで雨も少ないので水不足が続いています。
さて、最近、平日は残業続きの仕事、休日はどこかで演奏か、そのための練習かのどちらか、という日々が続いています。まあ、何もしないで、ボーっとしているよりは充実した日々なのかもしれませんが、独身で彼女もおらず好き勝手に生きている日々にどっぷりつかっていてもいいのかと、多少不安になることもあります。
家に帰って落ち着くと、疲れと孤独感がどっと押し寄せてくることもあります。もしかしたら、それを感じなくさせるために自分で仕事や、演奏活動に追い込んでいるのかもしれません。本当は落ち着く場所が今はなくなっているのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

Domenico Scarlatti/Aurelia Saxophone Quartet
Wilke te BRUMMELSTROETE (メゾ・ソプラノ)
CHALLENGE CLASSIC CC 7204
このCDはオーレリア・サクソフォン・カルテットによる、スカルラッティのソナタを12曲とメゾ・ソプラノをくわえた作品が収められたものです。
オーレリア・サクソフォーン・カルテットは以前にもアルバムを紹介しましたので、詳しいことは割愛します。
全体は、非常に生き生きとした音楽が愛情深く奏でられているというイメージでしょうか。部分的には音程にドッキッとする部分もなきにしもあらず、ですが、それを超越した音楽性があると思います。
話は少しそれますが、サクソフォーンに関しても日本人の演奏は世界一音程に厳しい演奏ではないかと思っています。そのおかげで、美しいハーモニーを作り上げたり、歌として、楽譜を正確に表現することもできるのですが、反面、気をつけないと人間味にかけたイメージにもなりかねない気もします。昔は、バイオリンなどでは、旋律を強弱や、テンポで歌う、ということに加え、音程で歌う、ということをしていたようです。つまり、音程を微妙にあげたり、下げたりして、歌を表現するのに使っていたらしいのです。最近ではあまり激しく音程を上下させることは無いですが、確かに歌の中でも音程をほんの少し下げたり、あげたりすると、落ち着く音があったりするような気もします。私は音楽を専門的にやっていないので、楽典や、音楽理論に基づくことは分かりませんが、感覚として、なんとなくそう感じます。センスでそれができるようになるのかもしれませんが。そこに味があるのかもしれません。
そんな味、すら感じられるような演奏です。しかも、現代曲のリリースが多いサクソフォーンアンサンブルの中で、ほとんどがスカルラッティの曲からのアルバム、ほっとするというか、落ち着く一枚です。
サクソフォーンの現代曲に少々聴き疲れした方にオススメの一枚です。
さて、最近、平日は残業続きの仕事、休日はどこかで演奏か、そのための練習かのどちらか、という日々が続いています。まあ、何もしないで、ボーっとしているよりは充実した日々なのかもしれませんが、独身で彼女もおらず好き勝手に生きている日々にどっぷりつかっていてもいいのかと、多少不安になることもあります。
家に帰って落ち着くと、疲れと孤独感がどっと押し寄せてくることもあります。もしかしたら、それを感じなくさせるために自分で仕事や、演奏活動に追い込んでいるのかもしれません。本当は落ち着く場所が今はなくなっているのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

Domenico Scarlatti/Aurelia Saxophone Quartet
Wilke te BRUMMELSTROETE (メゾ・ソプラノ)
CHALLENGE CLASSIC CC 7204
このCDはオーレリア・サクソフォン・カルテットによる、スカルラッティのソナタを12曲とメゾ・ソプラノをくわえた作品が収められたものです。
オーレリア・サクソフォーン・カルテットは以前にもアルバムを紹介しましたので、詳しいことは割愛します。
全体は、非常に生き生きとした音楽が愛情深く奏でられているというイメージでしょうか。部分的には音程にドッキッとする部分もなきにしもあらず、ですが、それを超越した音楽性があると思います。
話は少しそれますが、サクソフォーンに関しても日本人の演奏は世界一音程に厳しい演奏ではないかと思っています。そのおかげで、美しいハーモニーを作り上げたり、歌として、楽譜を正確に表現することもできるのですが、反面、気をつけないと人間味にかけたイメージにもなりかねない気もします。昔は、バイオリンなどでは、旋律を強弱や、テンポで歌う、ということに加え、音程で歌う、ということをしていたようです。つまり、音程を微妙にあげたり、下げたりして、歌を表現するのに使っていたらしいのです。最近ではあまり激しく音程を上下させることは無いですが、確かに歌の中でも音程をほんの少し下げたり、あげたりすると、落ち着く音があったりするような気もします。私は音楽を専門的にやっていないので、楽典や、音楽理論に基づくことは分かりませんが、感覚として、なんとなくそう感じます。センスでそれができるようになるのかもしれませんが。そこに味があるのかもしれません。
そんな味、すら感じられるような演奏です。しかも、現代曲のリリースが多いサクソフォーンアンサンブルの中で、ほとんどがスカルラッティの曲からのアルバム、ほっとするというか、落ち着く一枚です。
サクソフォーンの現代曲に少々聴き疲れした方にオススメの一枚です。
2008年08月27日
意外な組み合わせ?でもないかも。
今日も雨模様の一日となりましたが、まだまだ蒸し暑い一日でした。それでも朝夕は、涼しくなってきています。
さて、10月にサクソフォーン・アンサンブル・コンサートを控え、何曲か編曲を依頼しました。最初に編曲をお願いした時の謝礼は、編曲者に、どれぐらい払ったらよいか率直にかつシンプルに直接聞いたところ、お金は要らないから「いちごワイン」と「讃岐うどん」を送って欲しいということでした。「いちごワイン」とは全国的にも女峰いちごという品種のいちごの生産で有名な香川県の三木町というところと、北海道でワインの生産をしている七飯町との姉妹都市縁組がもとで作られたワインです。で、このワインとうどん、何故東京に住んでいる編曲者の方がご存知かと申しますと、以前、他の曲を編曲依頼したときにお礼に送ったものがおいしかったと言うことのようです。(このときは私が発注したのではないので、何をどのようないきさつで送ったかは今回はじめて知りました。)
で、うどんを送るときにいつも少し悩むことが。普通、うどんと一緒に送るものとして香川県で代表的なものといえば醤油豆という郷土料理です。これは煎ったソラマメを甘辛い醤油タレに漬け込んでいるものなのですが、ギフトとしてうどんと抱き合わせになっている例が非常に多いのです。もちろん、すべての香川県民が醤油豆を食べているか、と言われると、そうでもないのですが、うどんに次ぐ香川の郷土料理なのは間違いないところです。
よく、うどんと出汁を一緒に送って欲しいという方はいますが、うどんとワインという組み合わせはなんとも不思議かもしれません。私なら、うどんというイメージだと、お酒はなんとなく日本酒を想像してしまいます。
でも、よくよく考えると、冷やしたワインを食前酒に冷たい「ざるうどん」や「つけうどん」を食すのも悪くは無い気がします。私は激下戸なので、試そうと言う気にも慣れませんが…。
でも、意外な組み合わせと思い込んでいるものがよく考えてみると以外にそうではなかったりすることはよくあるのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

Main Street U.S.A./New Century Saxophone Quartet
Channel Crossing CCS-9896
このCDは昨日も紹介したニュー・センチュリー・サクソフォーン・クヮルテットによるアメリカの作曲家の作品集です。
曲目はPavane (グールド)、Main Street Waltz (グールド)、Main Street March (グールド)、
Porgy and Bess Suite (ガーシュウィン)、Promenade (ガーシュウィン)、Three-Quarter Blues (ガーシュウィン) 、Merry Andrew (ガーシュウィン)、Selections from West Side Story (バーンスタイン) となっています。
特にウエストサイド物語は先日紹介したフルモーのものと比べてみると違いが楽しめて面白いかもしれません。また、こちらのウエストサイドはドラムセットが加わっていて、サクソフォーン・カルテット+ドラムという編成になっています。
私にとってはこの組み合わせは少しだけですが意外な組み合わせでした。よくよく考えると、あって何の不思議も無い編成なのかもしれませんが、それまで、カルテット+ドラムという編成を耳にしたことが無かったからかも知れません。
この団体、私が聞いてみた感想として、機能紹介した、所謂サクソフォーンのクラシックというよりは、このCDに収録されているような少しポップな曲の方がより得意なようです。機能紹介したアルバムでもその傾向がよく現れていたように思っていましたが、アメリカチックなノリのよい曲がたくさん収録されているこのCDを聞くとなおのことそう思います。
サクソフォーン・クヮルテット+ドラムという編成を聞いたみたい方、アメリカのノリのよい曲をサクソフォーンで聞いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、10月にサクソフォーン・アンサンブル・コンサートを控え、何曲か編曲を依頼しました。最初に編曲をお願いした時の謝礼は、編曲者に、どれぐらい払ったらよいか率直にかつシンプルに直接聞いたところ、お金は要らないから「いちごワイン」と「讃岐うどん」を送って欲しいということでした。「いちごワイン」とは全国的にも女峰いちごという品種のいちごの生産で有名な香川県の三木町というところと、北海道でワインの生産をしている七飯町との姉妹都市縁組がもとで作られたワインです。で、このワインとうどん、何故東京に住んでいる編曲者の方がご存知かと申しますと、以前、他の曲を編曲依頼したときにお礼に送ったものがおいしかったと言うことのようです。(このときは私が発注したのではないので、何をどのようないきさつで送ったかは今回はじめて知りました。)
で、うどんを送るときにいつも少し悩むことが。普通、うどんと一緒に送るものとして香川県で代表的なものといえば醤油豆という郷土料理です。これは煎ったソラマメを甘辛い醤油タレに漬け込んでいるものなのですが、ギフトとしてうどんと抱き合わせになっている例が非常に多いのです。もちろん、すべての香川県民が醤油豆を食べているか、と言われると、そうでもないのですが、うどんに次ぐ香川の郷土料理なのは間違いないところです。
よく、うどんと出汁を一緒に送って欲しいという方はいますが、うどんとワインという組み合わせはなんとも不思議かもしれません。私なら、うどんというイメージだと、お酒はなんとなく日本酒を想像してしまいます。
でも、よくよく考えると、冷やしたワインを食前酒に冷たい「ざるうどん」や「つけうどん」を食すのも悪くは無い気がします。私は激下戸なので、試そうと言う気にも慣れませんが…。
でも、意外な組み合わせと思い込んでいるものがよく考えてみると以外にそうではなかったりすることはよくあるのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

Main Street U.S.A./New Century Saxophone Quartet
Channel Crossing CCS-9896
このCDは昨日も紹介したニュー・センチュリー・サクソフォーン・クヮルテットによるアメリカの作曲家の作品集です。
曲目はPavane (グールド)、Main Street Waltz (グールド)、Main Street March (グールド)、
Porgy and Bess Suite (ガーシュウィン)、Promenade (ガーシュウィン)、Three-Quarter Blues (ガーシュウィン) 、Merry Andrew (ガーシュウィン)、Selections from West Side Story (バーンスタイン) となっています。
特にウエストサイド物語は先日紹介したフルモーのものと比べてみると違いが楽しめて面白いかもしれません。また、こちらのウエストサイドはドラムセットが加わっていて、サクソフォーン・カルテット+ドラムという編成になっています。
私にとってはこの組み合わせは少しだけですが意外な組み合わせでした。よくよく考えると、あって何の不思議も無い編成なのかもしれませんが、それまで、カルテット+ドラムという編成を耳にしたことが無かったからかも知れません。
この団体、私が聞いてみた感想として、機能紹介した、所謂サクソフォーンのクラシックというよりは、このCDに収録されているような少しポップな曲の方がより得意なようです。機能紹介したアルバムでもその傾向がよく現れていたように思っていましたが、アメリカチックなノリのよい曲がたくさん収録されているこのCDを聞くとなおのことそう思います。
サクソフォーン・クヮルテット+ドラムという編成を聞いたみたい方、アメリカのノリのよい曲をサクソフォーンで聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月26日
ある意味ギャンブラー。
今日は雨の一日となりました。8月もあと少しで終りに差し掛かっています。
さて、私はCDを購入するときにアマゾンの海外サイトを時々利用します。英語がからっきし駄目な私が何故英語サイトで買い物をするかというと、実はそれにはちょっとした事情があるのです。最初、私がネットを始めた頃は、海外最大のネットCDショップはCD NOWというサイトでした。そして、便利なことにこのサイトにはしばらくの間、日本語サポートが付いていたのです。そのため、発注などの手続きも、また、商品に不具合があったときも日本語で応対してもらえるというメリットがありました。ところが、数年前、日本語サポートが打ち切られ、さらにはアマゾンに統合されてしまったのです。その流れで、アマゾンには以前のCD NOWに登録していた私のIDやパスワードも引き継がれることなり、今でも理解できない英語に苦労しながら利用している状態です。慣れてしまうと、英語が理解できなくてもそんなに困ることは無いのですが、たまに品物の誤配などがあったときのことを考えるとちょっと不安ではあります。実際、以前誤配されたことがあるので、ちょっと切実かもしれません。当然、国内のアマゾンも利用していますが、輸入盤などはやはり海外のアマゾンの方が豊富だったりするので、そちらにオーダーすることも少なくありません。
さて、海外発注に限らず、ネットで、CDを探し出し購入すると言う行為はある意味ギャンブルです。購入ページに書いてある評価や感想はある程度参考になるのかもしれませんが、自分の好みに合うかどうかは聞いてみるまで分かりません。しかも、サクソフォーンアンサンブルのCDなどになると、聞いたこともない団体、聞いたことも無い曲で購入したりするわけなので、まさに賭けです。はずれを引くことが無いともいえません。でもはずれも含めて持っていることは財産ですから、全くのギャンブルというわけでもないのかもしれません。800枚のCD、LPを金額的に換算してみると、一枚2000円で計算しても、単純計算で160万円、当然、一枚3000円だったり1000円だったりするものもあるので、あくまで単純計算での話ですが。まあ、本格的な賭け事に比べて確実に手元に物が残る、というだけいいのかもしれませんが、そのおかげで逆に保管場所に頭を痛めることもあります。
さて、そこで今日の一枚です。
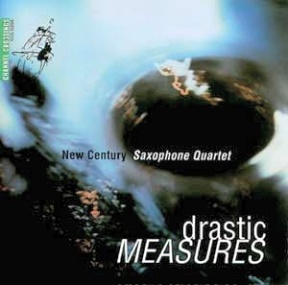
Drastic Measures/New Century Saxophone Quartet
Channnel Crossing CCS-5994
このCDはニュー・センチュリー・サクソフォーン・クヮルテットによるペックの作品をはじめとしたカルテット集です。若干、メンバーの入れ替えがあったようですが、現在も活動しているようです。私がCD NOWを利用し始めて初期の段階で購入したCDの一枚です。
曲目はDrastic Measures (ペック)、 Fantasia(スウェリンク)、Zweites Quartett fur Saxophone(ゲンツマー)、Quartett (Allegro de Concert) (フロリオ)、Zwolf Variationen in C (モーツアルト)、Petit Quatour pour Saxophones (フランセ)、The Piggly-Wiggle (バロル)となっています。
アルバムのタイトルにもなっているドラスティック・メジャーズは以前紹介したプリズム・カルテットのアルバムも持っているのですが、プリズムカルテットはクールでシャープなジャズ風に、こちらのほうは楽しくノリのよいジャズ風にという印象を受けました。
多少アンサンブルとしての音のブレンドに欠ける印象を受ける部分もありますが、カルテットとして十分に楽しめる内容のものです。
サクソフォーンを楽しむすべての方、またドラスティック・メジャーズの聴き比べをしたい方にオススメの一枚です
さて、私はCDを購入するときにアマゾンの海外サイトを時々利用します。英語がからっきし駄目な私が何故英語サイトで買い物をするかというと、実はそれにはちょっとした事情があるのです。最初、私がネットを始めた頃は、海外最大のネットCDショップはCD NOWというサイトでした。そして、便利なことにこのサイトにはしばらくの間、日本語サポートが付いていたのです。そのため、発注などの手続きも、また、商品に不具合があったときも日本語で応対してもらえるというメリットがありました。ところが、数年前、日本語サポートが打ち切られ、さらにはアマゾンに統合されてしまったのです。その流れで、アマゾンには以前のCD NOWに登録していた私のIDやパスワードも引き継がれることなり、今でも理解できない英語に苦労しながら利用している状態です。慣れてしまうと、英語が理解できなくてもそんなに困ることは無いのですが、たまに品物の誤配などがあったときのことを考えるとちょっと不安ではあります。実際、以前誤配されたことがあるので、ちょっと切実かもしれません。当然、国内のアマゾンも利用していますが、輸入盤などはやはり海外のアマゾンの方が豊富だったりするので、そちらにオーダーすることも少なくありません。
さて、海外発注に限らず、ネットで、CDを探し出し購入すると言う行為はある意味ギャンブルです。購入ページに書いてある評価や感想はある程度参考になるのかもしれませんが、自分の好みに合うかどうかは聞いてみるまで分かりません。しかも、サクソフォーンアンサンブルのCDなどになると、聞いたこともない団体、聞いたことも無い曲で購入したりするわけなので、まさに賭けです。はずれを引くことが無いともいえません。でもはずれも含めて持っていることは財産ですから、全くのギャンブルというわけでもないのかもしれません。800枚のCD、LPを金額的に換算してみると、一枚2000円で計算しても、単純計算で160万円、当然、一枚3000円だったり1000円だったりするものもあるので、あくまで単純計算での話ですが。まあ、本格的な賭け事に比べて確実に手元に物が残る、というだけいいのかもしれませんが、そのおかげで逆に保管場所に頭を痛めることもあります。
さて、そこで今日の一枚です。
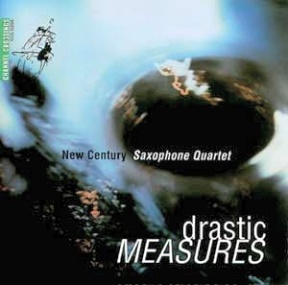
Drastic Measures/New Century Saxophone Quartet
Channnel Crossing CCS-5994
このCDはニュー・センチュリー・サクソフォーン・クヮルテットによるペックの作品をはじめとしたカルテット集です。若干、メンバーの入れ替えがあったようですが、現在も活動しているようです。私がCD NOWを利用し始めて初期の段階で購入したCDの一枚です。
曲目はDrastic Measures (ペック)、 Fantasia(スウェリンク)、Zweites Quartett fur Saxophone(ゲンツマー)、Quartett (Allegro de Concert) (フロリオ)、Zwolf Variationen in C (モーツアルト)、Petit Quatour pour Saxophones (フランセ)、The Piggly-Wiggle (バロル)となっています。
アルバムのタイトルにもなっているドラスティック・メジャーズは以前紹介したプリズム・カルテットのアルバムも持っているのですが、プリズムカルテットはクールでシャープなジャズ風に、こちらのほうは楽しくノリのよいジャズ風にという印象を受けました。
多少アンサンブルとしての音のブレンドに欠ける印象を受ける部分もありますが、カルテットとして十分に楽しめる内容のものです。
サクソフォーンを楽しむすべての方、またドラスティック・メジャーズの聴き比べをしたい方にオススメの一枚です
2008年08月25日
2008年08月25日
ジャンルを超えて。
今日も良い天気です。日中はまだまだ暑い夏の日差しですが、 夜になると、涼しい風が入るようになりました。
さて、昨日から「輸入盤クラシック・サクソフォーン企画」をはじめましたが、クラシックという定義にふと自分でも疑問を感じてしまいました。辞書とか引いてみても「古典的」というような意味しか書いてありません。サクソフォーンの音楽は比較的新しいものが多く、本来的に古典ではないのでしょうが音楽のスタイルが「古典的」ならばクラシックということなのでしょうか?となると、ジャズやポップスなどもあと500年くらいたてば、クラシックの仲間入りになるのでしょうか。いまひとつ、位置づけもあいまいです。
元々、サクソフォーンという楽器は軍楽隊や、オーケストラのために考えられ、クラシックの世界で誕生し、JAZZという新しいジャンルの中で花開いたという歴史を持っているので、そういった面では、バイオリンなどの弦楽器や、トランペットやトロンボーンといった金管楽器、さらにはフルートやクラリネットといった他の木管楽器よりもジャンルとしてはボーダレスな世界の楽器なのかもしれません。もちろん、どんな楽器でも様々なジャンルで活躍されている方は数多く存在しますが、個人的にはこのサクソフォーンのたどった歴史は、ボーダレスで、いろいろなジャンルを超えて音楽を結び付けているのだと思っています。まだまだ歴史の浅い楽器だけあって、自由度も高く、様々なことにチャレンジすることが許される楽器だとも思っています。(アマチュアの私が言うのは非常におこがましいのですが)。
そこで、今日の一枚です。

CINESAX
Jean=Yves Fourmeau Saxophone Quartet
Alain BEGHIN (打楽器)
Roger FUGEN (ドラム)
Rene Gailly CD87 159
このCDは、フルモーのカルテットによる、映画音楽集です。曲目はミッション・インポイッシブル (シフリン) をはじめとして、ピンク・パンサー (マンシーニ) 、マニックス (マンシーニ) 、ピーター・ガンのテ-マ (マンシーニ) 、ドクター・ノーのテーマ (ノーマン) 、皮の山高帽 (ジョンソン) 、雨にぬれても (バカラック) 、アマルコルド (ロータ) 、ラ・ストラーダ (ロータ) 、8 1/2 (ロータ) 、ムショーの3つの覚え書き (デレルー) 、トラヴェリング・アヴァント (アレッサンドリーニ) 、海辺の小部屋 (コスマ) 、シラノ・デ・ベルジェラク (プティ) 、42番目 (レグランド) 、アラビアのローレンス (ハール) 、ウェストサイド物語 (バーンスタイン) となっています。まさに映画音楽のオンパレードです。
映画音楽というものもやはりボーダレス感を感じます。クラシカルでもあり、ポップスでもあり、という音楽が少なくありません。たとえば、ウエストサイド物語をポップスと判断するかクラシックとするかは、微妙なところではないでしょうか。
フルモーの演奏はやはり、彼ららしい、きっちりとした演奏です。映画音楽にしてみれば、多少か堅苦しかったり、表現が蛋白だったりとしますが、クラシックの表現としては大げさなアゴーギグを排した丁寧で、すっきりした演奏とも言えると思います。
映画音楽をサクソフォーン・クヮルテットで聴いてみたい方、サクソフォーンの魅力をさらに感じたい方にオススメの一枚です。
さて、昨日から「輸入盤クラシック・サクソフォーン企画」をはじめましたが、クラシックという定義にふと自分でも疑問を感じてしまいました。辞書とか引いてみても「古典的」というような意味しか書いてありません。サクソフォーンの音楽は比較的新しいものが多く、本来的に古典ではないのでしょうが音楽のスタイルが「古典的」ならばクラシックということなのでしょうか?となると、ジャズやポップスなどもあと500年くらいたてば、クラシックの仲間入りになるのでしょうか。いまひとつ、位置づけもあいまいです。
元々、サクソフォーンという楽器は軍楽隊や、オーケストラのために考えられ、クラシックの世界で誕生し、JAZZという新しいジャンルの中で花開いたという歴史を持っているので、そういった面では、バイオリンなどの弦楽器や、トランペットやトロンボーンといった金管楽器、さらにはフルートやクラリネットといった他の木管楽器よりもジャンルとしてはボーダレスな世界の楽器なのかもしれません。もちろん、どんな楽器でも様々なジャンルで活躍されている方は数多く存在しますが、個人的にはこのサクソフォーンのたどった歴史は、ボーダレスで、いろいろなジャンルを超えて音楽を結び付けているのだと思っています。まだまだ歴史の浅い楽器だけあって、自由度も高く、様々なことにチャレンジすることが許される楽器だとも思っています。(アマチュアの私が言うのは非常におこがましいのですが)。
そこで、今日の一枚です。

CINESAX
Jean=Yves Fourmeau Saxophone Quartet
Alain BEGHIN (打楽器)
Roger FUGEN (ドラム)
Rene Gailly CD87 159
このCDは、フルモーのカルテットによる、映画音楽集です。曲目はミッション・インポイッシブル (シフリン) をはじめとして、ピンク・パンサー (マンシーニ) 、マニックス (マンシーニ) 、ピーター・ガンのテ-マ (マンシーニ) 、ドクター・ノーのテーマ (ノーマン) 、皮の山高帽 (ジョンソン) 、雨にぬれても (バカラック) 、アマルコルド (ロータ) 、ラ・ストラーダ (ロータ) 、8 1/2 (ロータ) 、ムショーの3つの覚え書き (デレルー) 、トラヴェリング・アヴァント (アレッサンドリーニ) 、海辺の小部屋 (コスマ) 、シラノ・デ・ベルジェラク (プティ) 、42番目 (レグランド) 、アラビアのローレンス (ハール) 、ウェストサイド物語 (バーンスタイン) となっています。まさに映画音楽のオンパレードです。
映画音楽というものもやはりボーダレス感を感じます。クラシカルでもあり、ポップスでもあり、という音楽が少なくありません。たとえば、ウエストサイド物語をポップスと判断するかクラシックとするかは、微妙なところではないでしょうか。
フルモーの演奏はやはり、彼ららしい、きっちりとした演奏です。映画音楽にしてみれば、多少か堅苦しかったり、表現が蛋白だったりとしますが、クラシックの表現としては大げさなアゴーギグを排した丁寧で、すっきりした演奏とも言えると思います。
映画音楽をサクソフォーン・クヮルテットで聴いてみたい方、サクソフォーンの魅力をさらに感じたい方にオススメの一枚です。
2008年08月24日
ネタ探し。
今日はよい天気です。最近の夜の涼しさから考えると、暑さのピークも峠を越え、徐々に秋へと向かっているのでしょうか?それでもまだまだ、暑い日が続きます。体調を崩さないように皆さんもお気を付けくださいね。
昨日、州崎寺までお越しいただいた方、どうもありがとうございました。他のメンバーの演奏ならともかく、私の拙い演奏に耳を傾けてくださった心温かい方々、ありがとうございました。
次の大きな目標は秋のサクソフォーン・アンサンブル・コンサート。今日もラージの練習が行われました。次の演奏会では、今よりもっとまともな演奏が出来るよう精進したいと思います。
さて、私はこの日記に日常見たちょっとしたことや、自分が感じたことを中心に書いて、そこから自分の持っている音源に自由に関連付けて、日記を書いています。日記を書き始めてから、6ヶ月以上が経過し、紹介したCDは150枚を超えることとなりました。ここを訪れてくださる皆様のおかげと思って感謝しています。
思い返せば、「展覧会の絵企画」などをやっていた日々は数ヶ月前のはずなのに、なぜか、もう遠い過去のように思えてしまいます。情報やコミュニケーションが飛び交うネットの世界では、通常の時間の感覚が変わってしまうのかもしれません。不思議なことです。
さて、私はいろいろ書いてはいますが、別にネタを探しながら歩いていると言うわけではありません。それこそ、日常のことはすべてネタにできると思って書いています。ただ、以前、私が、犯したような失敗だけはしたくないので、書く内容には最近最新の注意を払うようになりました。
音源と言えば、私は趣味でサクソフォーン(通称:サックス)という楽器を吹いているので、どうしてもその関係の音源が増えていきます。それも、一般の人がよく耳にするようなジャズやポップスのものではなく、どちらかというとクラシック寄りのものです。人によってはコアでマニアックのように思われるかもしれませんが、その道(どの道?笑)の方に比べれば、まだまだ、足元にも及びません。それでも800枚以上のCDの内、150枚近くがそんなサクソフォーンのCDやレコードだったりします。
で、この日記では、非常に紹介するのに、日々のネタを結び付けにくいものや、あまりにマニアックなものもあるので、今日から少しずつ、そんなCDを紹介していきたいと思います。国内盤よりも、輸入盤の方がよりコアなCDになると思いますので、輸入盤を中心に書いていきたいと思います。題して、「輸入盤クラシック・サクソフォーン企画」。私にとっては2度目の企画もののチャレンジになります。興味のある方、無い方、ともにごらんいただけると幸いかと存じます。
そこで今日の一枚です。
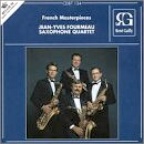
French Masterpieces
Quatuor de Saxophones Jean-Yves Fourmeau
Rene Gailly International CD87 134 (輸入盤)
このCDはジャン=イヴ・フルモーのカルテットによるサクソフォーン作品集です。フレンチ・マスターピースというだけあって、フランスのオリジナル曲が収録されています。以前、紹介した、フルモーの国内版と同じ曲目も含まれていますが、前盤と違うのはまず、病気のため惜しくも亡くなってしまったデマール氏の変わりに新たにテナーサックスにラポルト氏が参加している点でしょうか。
全体の印象としてはさすがフルモー、確実な技で聞かせるといった印象です。曲目は前述したとおりフランス物ばかりで、アンダンテとスケルツォ (ボザ) 、サクソフォン四重奏曲 (デザンクロ) 、民謡風ロンドの主題による序奏と変奏曲 (ピエルネ) 、サクソフォン四重奏曲 (デュボワ) 、グラーヴェとプレスト (リヴィエ) 、小組曲 (フランセ)となっています。
ただ、あまりにかっちりというか、きっちり吹こうとするあまり、フランセの曲の洒脱さなどは少し失われている印象も否めない感があります。ただ、デュボアの四重奏や、リヴィエのグラーヴェとプレストなどは絶品と言ってもいい演奏ではないでしょうか。
サックスはJAZZの楽器として疑わない方、また、サックスを手にしているすべての方に聞いて欲しいオススメの一枚です。
昨日、州崎寺までお越しいただいた方、どうもありがとうございました。他のメンバーの演奏ならともかく、私の拙い演奏に耳を傾けてくださった心温かい方々、ありがとうございました。
次の大きな目標は秋のサクソフォーン・アンサンブル・コンサート。今日もラージの練習が行われました。次の演奏会では、今よりもっとまともな演奏が出来るよう精進したいと思います。
さて、私はこの日記に日常見たちょっとしたことや、自分が感じたことを中心に書いて、そこから自分の持っている音源に自由に関連付けて、日記を書いています。日記を書き始めてから、6ヶ月以上が経過し、紹介したCDは150枚を超えることとなりました。ここを訪れてくださる皆様のおかげと思って感謝しています。
思い返せば、「展覧会の絵企画」などをやっていた日々は数ヶ月前のはずなのに、なぜか、もう遠い過去のように思えてしまいます。情報やコミュニケーションが飛び交うネットの世界では、通常の時間の感覚が変わってしまうのかもしれません。不思議なことです。
さて、私はいろいろ書いてはいますが、別にネタを探しながら歩いていると言うわけではありません。それこそ、日常のことはすべてネタにできると思って書いています。ただ、以前、私が、犯したような失敗だけはしたくないので、書く内容には最近最新の注意を払うようになりました。
音源と言えば、私は趣味でサクソフォーン(通称:サックス)という楽器を吹いているので、どうしてもその関係の音源が増えていきます。それも、一般の人がよく耳にするようなジャズやポップスのものではなく、どちらかというとクラシック寄りのものです。人によってはコアでマニアックのように思われるかもしれませんが、その道(どの道?笑)の方に比べれば、まだまだ、足元にも及びません。それでも800枚以上のCDの内、150枚近くがそんなサクソフォーンのCDやレコードだったりします。
で、この日記では、非常に紹介するのに、日々のネタを結び付けにくいものや、あまりにマニアックなものもあるので、今日から少しずつ、そんなCDを紹介していきたいと思います。国内盤よりも、輸入盤の方がよりコアなCDになると思いますので、輸入盤を中心に書いていきたいと思います。題して、「輸入盤クラシック・サクソフォーン企画」。私にとっては2度目の企画もののチャレンジになります。興味のある方、無い方、ともにごらんいただけると幸いかと存じます。
そこで今日の一枚です。
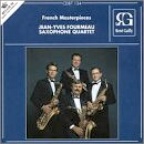
French Masterpieces
Quatuor de Saxophones Jean-Yves Fourmeau
Rene Gailly International CD87 134 (輸入盤)
このCDはジャン=イヴ・フルモーのカルテットによるサクソフォーン作品集です。フレンチ・マスターピースというだけあって、フランスのオリジナル曲が収録されています。以前、紹介した、フルモーの国内版と同じ曲目も含まれていますが、前盤と違うのはまず、病気のため惜しくも亡くなってしまったデマール氏の変わりに新たにテナーサックスにラポルト氏が参加している点でしょうか。
全体の印象としてはさすがフルモー、確実な技で聞かせるといった印象です。曲目は前述したとおりフランス物ばかりで、アンダンテとスケルツォ (ボザ) 、サクソフォン四重奏曲 (デザンクロ) 、民謡風ロンドの主題による序奏と変奏曲 (ピエルネ) 、サクソフォン四重奏曲 (デュボワ) 、グラーヴェとプレスト (リヴィエ) 、小組曲 (フランセ)となっています。
ただ、あまりにかっちりというか、きっちり吹こうとするあまり、フランセの曲の洒脱さなどは少し失われている印象も否めない感があります。ただ、デュボアの四重奏や、リヴィエのグラーヴェとプレストなどは絶品と言ってもいい演奏ではないでしょうか。
サックスはJAZZの楽器として疑わない方、また、サックスを手にしているすべての方に聞いて欲しいオススメの一枚です。
2008年08月24日
ありがとうございました。
お越しいただいた方々、
るいまま組のみなさん、
州崎寺の住職、
そして牟礼のみなさん
どうもありがとうございました。
皆様の暖かいお心遣いのおかげで、無事に演奏を終えることが出来ました。
2008年08月23日
間違ってるんだけど、それ。
今日はいよいよ、牟礼の石灯り月あかりコンサートの本番。皆さん、おヒマな方は是非夕方から牟礼の州崎寺に起こし下さい。ダッパーサクセーバーズが演奏に登場します。
実は、絶対的練習量が足りない部分があるので、楽譜を間違って吹く可能盛大。指摘されてもおかしくない間違いだけはしないように努力したいと思います。というより、間違えること自体本当はあってはならないことです。さて、話は急に変わりますが、世の中で生活していると、相手が間違っているのが分かっているのにどうしても訂正できないことがあります。それは訂正できないような場面だったり、訂正しなくても周囲は分かっていたり、相手が目上の人で訂正しにくい状況だったり、様々です。しかもちょっと言い間違えた、というのでは無く確実に間違えたまま、使い続けていることばだったりします。
私が以前、勤めていた会社の関係で結婚式に呼ばれて出席したときにある会社の専務さんが、「新郎新婦は新居に新しい生活ズックをそろえ…」と「グッズ」と「ズック」を間違えて連発。他にも、「アナログ時計」のことを「アナグロ時計」と言っている女性に何も言えなかったり、と日常の中でも結構間違ってるんだけど、それ、と思いつつも訂正できないことがよくあります。しかも間違えている本人は気にせず使ってしまっているところに逆に訂正しづらさがあったりします。
そこで今日の一枚です。

ビゼー/「アルルの女」第一組曲&第二組曲
「カルメン」組曲
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団
ダニエル・デファイエ(アルトサクソフォーン「アルルの女」ソロ)
グラモフォン(ポリドール) FOOG 27013
このCDはカラヤン&ベルリンフィルのビゼー作品の収録されたもの。ビゼーという人は夭逝だったため作品は多くありません。
サクソフォーン吹きとしてこのアルバムを聴くには理由があります。カラヤン氏はサクソフォーンのソロがある曲は必ず、ダニエル・デファイエ氏を指名して演奏していたと聴いたことがあるのですが、このアルバムも例外なく、デファイエ氏の美しい音色を聞くことができます。第二組曲の間奏曲はサクソフォーン吹きにとっては欠かすことのできない名曲となっています。
さて、問題は、この録音には明らかに楽譜の解釈に間違いがあるということです。いや、カラヤン氏に直接聞くこともできないので、「わざとそうしている」といわれればそれまでなのですが、明らかにスコアの記譜と比べると誤りの演奏になってしまいます。実は、「アルルの女」の「ファランドール」のスコアには「タンブール」という楽器の指定があるのですが、この楽器は実はプロバンス太鼓といって胴の深い革張りの太鼓なのですが、カラヤン氏は普通にタンバリンで演奏しています。昔はドイツ系の楽団や指揮者にこの間違いは多くみられたようで、その理由としてはビゼーがフランス人で、楽譜の指定楽器がすべてフランス表記であったことによるようです。たとえば、フランス表記では「コルノ」という楽器があって、これは「コルネット」のことではなく、所謂「フレンチホルン」のことなのです。
で、カラヤン盤を聞きなれた方には、他の正しくプロバンス太鼓で演奏されたものを聞くと「あれっ?」と思ってしまうでしょうし、逆に他の正しく演奏されたものを聞くと、カラヤン氏の演奏は「何じゃこれ?」ということに鳴ってしまいます。果たして、本当は間違いだったのか、意図的に楽器を変えたのか、カラヤン氏もなくなった今は確認することもできないのかもしれません。元々私などに確認のしようも無いのですが。
ただ、演奏のほうはさすがベルリンフィル、カラヤン、といったところでしょうか。非常に分かりやすい表現で楽しませてくれます。また、ダニエル・デファイエ氏のソロも絶品です。
サクソフォーンを吹くすべての方に、アルルの女の楽器解釈の違いを聞き比べてみたい方にオススメの一枚です。
実は、絶対的練習量が足りない部分があるので、楽譜を間違って吹く可能盛大。指摘されてもおかしくない間違いだけはしないように努力したいと思います。というより、間違えること自体本当はあってはならないことです。さて、話は急に変わりますが、世の中で生活していると、相手が間違っているのが分かっているのにどうしても訂正できないことがあります。それは訂正できないような場面だったり、訂正しなくても周囲は分かっていたり、相手が目上の人で訂正しにくい状況だったり、様々です。しかもちょっと言い間違えた、というのでは無く確実に間違えたまま、使い続けていることばだったりします。
私が以前、勤めていた会社の関係で結婚式に呼ばれて出席したときにある会社の専務さんが、「新郎新婦は新居に新しい生活ズックをそろえ…」と「グッズ」と「ズック」を間違えて連発。他にも、「アナログ時計」のことを「アナグロ時計」と言っている女性に何も言えなかったり、と日常の中でも結構間違ってるんだけど、それ、と思いつつも訂正できないことがよくあります。しかも間違えている本人は気にせず使ってしまっているところに逆に訂正しづらさがあったりします。
そこで今日の一枚です。

ビゼー/「アルルの女」第一組曲&第二組曲
「カルメン」組曲
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団
ダニエル・デファイエ(アルトサクソフォーン「アルルの女」ソロ)
グラモフォン(ポリドール) FOOG 27013
このCDはカラヤン&ベルリンフィルのビゼー作品の収録されたもの。ビゼーという人は夭逝だったため作品は多くありません。
サクソフォーン吹きとしてこのアルバムを聴くには理由があります。カラヤン氏はサクソフォーンのソロがある曲は必ず、ダニエル・デファイエ氏を指名して演奏していたと聴いたことがあるのですが、このアルバムも例外なく、デファイエ氏の美しい音色を聞くことができます。第二組曲の間奏曲はサクソフォーン吹きにとっては欠かすことのできない名曲となっています。
さて、問題は、この録音には明らかに楽譜の解釈に間違いがあるということです。いや、カラヤン氏に直接聞くこともできないので、「わざとそうしている」といわれればそれまでなのですが、明らかにスコアの記譜と比べると誤りの演奏になってしまいます。実は、「アルルの女」の「ファランドール」のスコアには「タンブール」という楽器の指定があるのですが、この楽器は実はプロバンス太鼓といって胴の深い革張りの太鼓なのですが、カラヤン氏は普通にタンバリンで演奏しています。昔はドイツ系の楽団や指揮者にこの間違いは多くみられたようで、その理由としてはビゼーがフランス人で、楽譜の指定楽器がすべてフランス表記であったことによるようです。たとえば、フランス表記では「コルノ」という楽器があって、これは「コルネット」のことではなく、所謂「フレンチホルン」のことなのです。
で、カラヤン盤を聞きなれた方には、他の正しくプロバンス太鼓で演奏されたものを聞くと「あれっ?」と思ってしまうでしょうし、逆に他の正しく演奏されたものを聞くと、カラヤン氏の演奏は「何じゃこれ?」ということに鳴ってしまいます。果たして、本当は間違いだったのか、意図的に楽器を変えたのか、カラヤン氏もなくなった今は確認することもできないのかもしれません。元々私などに確認のしようも無いのですが。
ただ、演奏のほうはさすがベルリンフィル、カラヤン、といったところでしょうか。非常に分かりやすい表現で楽しませてくれます。また、ダニエル・デファイエ氏のソロも絶品です。
サクソフォーンを吹くすべての方に、アルルの女の楽器解釈の違いを聞き比べてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月22日
肩がこる。
今日も朝はよい天気です。明日は、州崎寺の演奏会ですが丁度雨の予報なので少し心配です。サックスアンサンブルの日のみならず、今まで本番中が雨だったことがない石灯り月あかりコンサートなので、今回もきっと大丈夫だと信じているのですが…。
さて、私は以前から結構肩こりに悩む人なのですが、最近になって頭痛がするほど激しい肩凝りが続いています。いろいろ原因はあるのですが、ひとつは私の姿勢が余りよくないこと。これは元々小児喘息だったことが引き金になっているようで、いまだに少し猫背です。もうひとつは小児喘息だったように、呼吸器系があまり強くないこともあるようです。私の祖父は父方も母方も呼吸器系の病気が原因、引き金となってこの世の人ではなくなってしまいました。母方の祖父は戦傷も大きな原因だったのですが、父方の祖父は間違いなく肺癌だったようです。どうも私自身も遺伝的に呼吸器が弱いようで、風邪を引きやすく、疲れが呼吸系のほうに出やすいようです。
以前、医者にも言われ、実際、私は肩に力を入れすぎていることが多いようで、それが呼吸器の弱さが原因かどうかは別にして、肩が凝りやすいのは事実のようです。
いろいろ、肩肘張らずに、ということがありますが、なかなか肩の力を抜いていろいろやるのは難しいことなのかもしれません。
もうひとつ大きな原因なのは、普段の運動不足。私は自称、出不精のインドア派なので、体を普段ほとんど鍛えていません。肉体的には弱いので、ぼろぼろになるのも早いようです。また、水泳でも始めようかな、と常に思いながら全く始める気配がないのはやる気が無い証拠なのかもしれません。お金をあまりかけずに泳げる場所が無いことも原因のひとつではあるのですが。
いずれにせよ、この肩凝りを何とかしたいものです。整体やカイロプラティックに行くとよいのかもしれませんが、この状態でマッサージなどすると、熱が出そうです。やっぱり、ゆっくり温泉につかったり、泳いだりして、地道に直すしかなさそうです。
そこで今日の一枚です。

ロッシーニ序曲集
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団
グラモフォン(ポリドール) 20MG0352
これはCDでは無くLPレコードです。このレコードの時点ですでに廉価版レコードなので、元はもっと前の発売になると思いますが、私が購入したのは1985年ごろです。ちなみに録音年は1971年となっています。ステレオ録音ですが、デジタル録音ではありません。以前から書いているように現在私はLPレコードが聴けるシステム環境を持っていないので、カセットテープに録音したものを聞いています。現在では廉価版のCDが発売され、おそらく、ロッシーニとスッペの序曲が一緒になって収録されているCDになっていると思います。
カラヤンの音楽ということで、やはりあの派手さと聞きやすさからたくさん私も昔は好んで聞いていました。このレコードはロッシーニの序曲集としては当時スタンダードなものだったと記憶しています。こういうと語弊があるかもしれませんが、当時の若き日のリッカルド・ムーティの録音などに比べると格段に完成度の高い音楽と技術で聞けるものだと思います。気軽に聞けるとは言え、演奏のレベルは超一流です。
いい意味でも悪い意味でも当たり障りのない卒の無い演奏ともいえます。曲目は「どろぼうかささぎ」序曲、「絹のはしご」序曲、「セミラーミデ」序曲、「セビリャの理髪師」序曲、「アルジェのイタリア女」序曲、「ウィリアム・テル」序曲の計6曲です。今のCDの感覚だと曲数が少ない気もしますが、LPだと普通の収録時間ではないかと思います。
「ウィリアム・テル」は皆さんどこかで耳にしたことがあると思います。特に20代後半以上の年齢の方はこの曲を聞かせると、「オレ達!ひょ○きん族」のオープニング・テーマと答える方が多数いらっしゃるようです。本当はこの、ウィリアム・テルの曲の途中からのスイス軍の行進の部分なのですが。
音楽としても、カラヤンの音楽作りからも聞きやすい音楽です。まさに、肩肘張らずに、構えずに楽しめる、肩の凝らない音楽ではないかと思います。
クラシックへの入門的音楽をお探しの方、気軽にロッシーニの音楽を楽しみたい方にオススメの一枚です。
さて、私は以前から結構肩こりに悩む人なのですが、最近になって頭痛がするほど激しい肩凝りが続いています。いろいろ原因はあるのですが、ひとつは私の姿勢が余りよくないこと。これは元々小児喘息だったことが引き金になっているようで、いまだに少し猫背です。もうひとつは小児喘息だったように、呼吸器系があまり強くないこともあるようです。私の祖父は父方も母方も呼吸器系の病気が原因、引き金となってこの世の人ではなくなってしまいました。母方の祖父は戦傷も大きな原因だったのですが、父方の祖父は間違いなく肺癌だったようです。どうも私自身も遺伝的に呼吸器が弱いようで、風邪を引きやすく、疲れが呼吸系のほうに出やすいようです。
以前、医者にも言われ、実際、私は肩に力を入れすぎていることが多いようで、それが呼吸器の弱さが原因かどうかは別にして、肩が凝りやすいのは事実のようです。
いろいろ、肩肘張らずに、ということがありますが、なかなか肩の力を抜いていろいろやるのは難しいことなのかもしれません。
もうひとつ大きな原因なのは、普段の運動不足。私は自称、出不精のインドア派なので、体を普段ほとんど鍛えていません。肉体的には弱いので、ぼろぼろになるのも早いようです。また、水泳でも始めようかな、と常に思いながら全く始める気配がないのはやる気が無い証拠なのかもしれません。お金をあまりかけずに泳げる場所が無いことも原因のひとつではあるのですが。
いずれにせよ、この肩凝りを何とかしたいものです。整体やカイロプラティックに行くとよいのかもしれませんが、この状態でマッサージなどすると、熱が出そうです。やっぱり、ゆっくり温泉につかったり、泳いだりして、地道に直すしかなさそうです。
そこで今日の一枚です。
ロッシーニ序曲集
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団
グラモフォン(ポリドール) 20MG0352
これはCDでは無くLPレコードです。このレコードの時点ですでに廉価版レコードなので、元はもっと前の発売になると思いますが、私が購入したのは1985年ごろです。ちなみに録音年は1971年となっています。ステレオ録音ですが、デジタル録音ではありません。以前から書いているように現在私はLPレコードが聴けるシステム環境を持っていないので、カセットテープに録音したものを聞いています。現在では廉価版のCDが発売され、おそらく、ロッシーニとスッペの序曲が一緒になって収録されているCDになっていると思います。
カラヤンの音楽ということで、やはりあの派手さと聞きやすさからたくさん私も昔は好んで聞いていました。このレコードはロッシーニの序曲集としては当時スタンダードなものだったと記憶しています。こういうと語弊があるかもしれませんが、当時の若き日のリッカルド・ムーティの録音などに比べると格段に完成度の高い音楽と技術で聞けるものだと思います。気軽に聞けるとは言え、演奏のレベルは超一流です。
いい意味でも悪い意味でも当たり障りのない卒の無い演奏ともいえます。曲目は「どろぼうかささぎ」序曲、「絹のはしご」序曲、「セミラーミデ」序曲、「セビリャの理髪師」序曲、「アルジェのイタリア女」序曲、「ウィリアム・テル」序曲の計6曲です。今のCDの感覚だと曲数が少ない気もしますが、LPだと普通の収録時間ではないかと思います。
「ウィリアム・テル」は皆さんどこかで耳にしたことがあると思います。特に20代後半以上の年齢の方はこの曲を聞かせると、「オレ達!ひょ○きん族」のオープニング・テーマと答える方が多数いらっしゃるようです。本当はこの、ウィリアム・テルの曲の途中からのスイス軍の行進の部分なのですが。
音楽としても、カラヤンの音楽作りからも聞きやすい音楽です。まさに、肩肘張らずに、構えずに楽しめる、肩の凝らない音楽ではないかと思います。
クラシックへの入門的音楽をお探しの方、気軽にロッシーニの音楽を楽しみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月21日
編曲、原曲。
今日もよい天気ですが、夕方から次第に天気は下り坂になる模様です。次の台風も近づいています。表現はよくないかもしれませんが、今年はどうも台風の当たり年のようです。
さて、現在11月のサクソフォーン・アンサンブルの演奏会に向けてラージアンサンブルの練習のも始まっているのですが、曲を編曲して演奏する、ということに関していろいろ考えることがあります。吹奏楽などの場合、特にオーケストラの曲を編曲して演奏する機会も多いのですが、なぜかその場合、自分が演奏するとなると、吹奏楽版でいい演奏があってもオーケストラ版の原曲を参考に聞きたがる人が多いようです。かく言う私もその一人なのですが、ひとつには原曲のテイストを大切にする、ということと、編曲はあくまで編曲で大切なのは原曲、という意識があるのだと思いますが、所詮は編曲した時点で別物になっているのも事実です。吹奏楽がいつまでたってもオーケストラを超えられないのは、いまだに多くのオーケストラの編曲作品にしがみついていることと、このコンプレックスのようなオーケストラへの執着だという方もいるようですが、どうなのでしょう。私は、確かにそういった面もあるものの必ずしもそうとも言い切れないと思っています。
世の中には星の数ほど曲が存在していて、もちろん、星の数ほどその曲の編曲も存在しています。場合によっては編曲されたものの方が親しまれるようになり、有名になったものもあります。私は編曲は原曲に手を加えることによって新たな命を与えたり、新たな可能性や方向性を付加するものだと思っていますが、皆さんはいかがなのでしょうか?
そこで今日の一枚です。
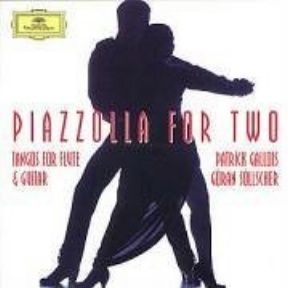
PIAZZOLLA FOR TWO
フルート:パトリック・ガロワ
ギター:イェラン・セルシェル
グラモフォン(ポリグラム) POCG-1985
このCDはパトリック・ガロワ氏によるピアソラの曲集です。
曲目はすべてピアソラの曲で、タンゴの歴史、 ブエノスアイレスの四季、 6つのタンゴ的エチュード、タンゴ第2番・タンゴ組曲からの4曲が収録されています。
タンゴの歴史などはいろいろな場面で聞くことのある曲ではないかと思いますが、オリジナルはどうもフルートとギターのための音楽だったようです。今では様々な楽器で様々な形で演奏されるために、このフルートとギターという組み合わせを聞くことが逆に少なくなってしまっているようにも思います。
演奏のほうは秀逸です。ただ、もう少しピアソラらしいごつさというか、粗野な部分というか、があってもよかったのかもしれません。もしかしたら聞く人によると、ピアソラ的ではないという人もいるかも知れません。少し控えめの表現と感じられないことも無いですが、飄々とした感じが逆にいいかもしれません。
フルートがお好きな方、ピアソラがお好きな方にオススメの一枚です。
さて、現在11月のサクソフォーン・アンサンブルの演奏会に向けてラージアンサンブルの練習のも始まっているのですが、曲を編曲して演奏する、ということに関していろいろ考えることがあります。吹奏楽などの場合、特にオーケストラの曲を編曲して演奏する機会も多いのですが、なぜかその場合、自分が演奏するとなると、吹奏楽版でいい演奏があってもオーケストラ版の原曲を参考に聞きたがる人が多いようです。かく言う私もその一人なのですが、ひとつには原曲のテイストを大切にする、ということと、編曲はあくまで編曲で大切なのは原曲、という意識があるのだと思いますが、所詮は編曲した時点で別物になっているのも事実です。吹奏楽がいつまでたってもオーケストラを超えられないのは、いまだに多くのオーケストラの編曲作品にしがみついていることと、このコンプレックスのようなオーケストラへの執着だという方もいるようですが、どうなのでしょう。私は、確かにそういった面もあるものの必ずしもそうとも言い切れないと思っています。
世の中には星の数ほど曲が存在していて、もちろん、星の数ほどその曲の編曲も存在しています。場合によっては編曲されたものの方が親しまれるようになり、有名になったものもあります。私は編曲は原曲に手を加えることによって新たな命を与えたり、新たな可能性や方向性を付加するものだと思っていますが、皆さんはいかがなのでしょうか?
そこで今日の一枚です。
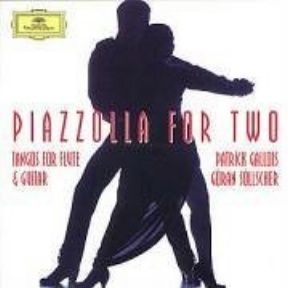
PIAZZOLLA FOR TWO
フルート:パトリック・ガロワ
ギター:イェラン・セルシェル
グラモフォン(ポリグラム) POCG-1985
このCDはパトリック・ガロワ氏によるピアソラの曲集です。
曲目はすべてピアソラの曲で、タンゴの歴史、 ブエノスアイレスの四季、 6つのタンゴ的エチュード、タンゴ第2番・タンゴ組曲からの4曲が収録されています。
タンゴの歴史などはいろいろな場面で聞くことのある曲ではないかと思いますが、オリジナルはどうもフルートとギターのための音楽だったようです。今では様々な楽器で様々な形で演奏されるために、このフルートとギターという組み合わせを聞くことが逆に少なくなってしまっているようにも思います。
演奏のほうは秀逸です。ただ、もう少しピアソラらしいごつさというか、粗野な部分というか、があってもよかったのかもしれません。もしかしたら聞く人によると、ピアソラ的ではないという人もいるかも知れません。少し控えめの表現と感じられないことも無いですが、飄々とした感じが逆にいいかもしれません。
フルートがお好きな方、ピアソラがお好きな方にオススメの一枚です。
2008年08月20日
2008年08月20日
散髪?断髪。
実は、はっきり言って私はあまり散髪をしません。面倒くさがりなので、ひどいときは3ヵ月~4ヶ月切りに行かないときもあります。最近では結構こまめに切りに行ってますが、それでも二ヶ月以上切りに行かないことがほとんどです。
別に散髪が嫌いというわけでもないのですが…。ひとつは赤ん坊の頃から通いつめている理髪店が日曜日、祭日がお休みという特殊なところであるため、休みの日に切りに行くことができなかったということもあるのですが。
ひどいときは髪が結べるぐらいまで長くなります。社会人としてどう?と感じるときもあるのですが。そういえば、高松ウインドシンフォニーの常任指揮者のU氏は高校を出てから三十年以上理髪店や美容院に行ったことが無いそうな。人に切ってもらうことも無く自分で裁縫の裁ちばさみを使って散髪するそうです。道理で髪の毛が常に多いと思いました。裁ちばさみで自分で切るって言うことは髪をすきばさみですいたことが無いってことなわけです。ちなみにこのU氏、中学の音楽の先生ですが、誰がどう見たって体育の先生に見えます。
そうそう、私の散髪の話でした。特に散髪が嫌いなわけではないので、暇ができて髪が伸びてきていて理髪店が空いていれば切りに行きます。で、ここ15年ぐらいは髪型も特に変えたことが無く、散髪屋の店長に、「いつも通り」といったらいつもの髪型に仕上げてくれます。当然ながら美容院などには行ったことがありません。そして、もうひとつ、理髪店でも、髪を洗ってもらったことがありません。必ず帰ってから自分で洗います。いつもは、演奏会の前などに切ることも多いのですが、今回の州崎寺ではまだ、髪を切るほど伸びていないので、おそらくは次のサクソフォンアンサンブルコンサートの前に切りに行くことになりそうです。
先日、髪を切った時に人に散髪というよりは断髪だな、と言われましたが、辞書で断髪の意味を調べると、散髪のことと書いてありました。なので大きな意味の違いは無いかもしれないのですが、断髪は主にちょんまげを切る、ざんぎりにするという意味があるようで、散髪には普通に髪を切るという意味合いが強いようです。そういえば、力士の引退のときは散髪式じゃなくて断髪式になっています。断髪のほうが何か強い意志を持って髪を切る、というイメージがしますが皆さんはどうなのでしょう?
でも、昔から髪を切る、ということは何らかの決意だったり、何か大きな意味があったりします。女性が一気にショートカットにしたときに「失恋でもした?」と聞くセクハラ上司は今でもよく見かけることと思います。
そこで今日の一枚です。

モダンチョキチョキズ/くまちゃん
キューンレコード KSC2-92
このCDはモダンチョキチョキズのベスト盤を除くと実質的には最後のアルバム?です。モダチョキは現在活動を休止していることになっていますが、もうあれだけのメンバーで精力的な活動をすることは不可能ではないかと思います。
曲目は、T.D.L.、エケセテネ、トムのいる木蔭、ドロンゲーム、アイ・ウィッシュ…、バブル~DJ&BGM(パート1)、林檎殺人事件、デートコース、新しとやかな獣、上辺よし子さんDJ&BGM(パート2)、くまちゃん、悲しみのマーナ、「メイド・イン・タイワン」予告編ということになっています。
林檎殺人事件などは昔、郷ひろみと樹木希林のデュエット(といっても樹木希林はほとんど歌わずに「フニフニ」行ってただけなんですが)のカバーだったり、くまちゃんなどでは財津一郎(最近ではタケモトピアノが有名ですが)が「キビしぃー」と叫んでいたりと、曲も参加メンバーも豪華です。悲しきマーナは素敵なマーナのマイナーバージョンです。また、バンクバンドとはいえないほど豪華な演奏も聴き物です。
なぜ、散髪でモダチョキか?と言われるとやっぱりチョキチョキズだからでしょう。実際ファーストアルバムでは、ジャケットに紙きりをしている濱田マリがいました。
このアルバムの最後には「メイドイン・タイワン」という次のアルバムの予告編まであるのですが、あれからもう10年、沈黙を守り続けているモダチョキです。
いろいろなことを抜きにして楽しめるアルバムです。モダチョキ好き以外の方でもオススメの一枚です。
別に散髪が嫌いというわけでもないのですが…。ひとつは赤ん坊の頃から通いつめている理髪店が日曜日、祭日がお休みという特殊なところであるため、休みの日に切りに行くことができなかったということもあるのですが。
ひどいときは髪が結べるぐらいまで長くなります。社会人としてどう?と感じるときもあるのですが。そういえば、高松ウインドシンフォニーの常任指揮者のU氏は高校を出てから三十年以上理髪店や美容院に行ったことが無いそうな。人に切ってもらうことも無く自分で裁縫の裁ちばさみを使って散髪するそうです。道理で髪の毛が常に多いと思いました。裁ちばさみで自分で切るって言うことは髪をすきばさみですいたことが無いってことなわけです。ちなみにこのU氏、中学の音楽の先生ですが、誰がどう見たって体育の先生に見えます。
そうそう、私の散髪の話でした。特に散髪が嫌いなわけではないので、暇ができて髪が伸びてきていて理髪店が空いていれば切りに行きます。で、ここ15年ぐらいは髪型も特に変えたことが無く、散髪屋の店長に、「いつも通り」といったらいつもの髪型に仕上げてくれます。当然ながら美容院などには行ったことがありません。そして、もうひとつ、理髪店でも、髪を洗ってもらったことがありません。必ず帰ってから自分で洗います。いつもは、演奏会の前などに切ることも多いのですが、今回の州崎寺ではまだ、髪を切るほど伸びていないので、おそらくは次のサクソフォンアンサンブルコンサートの前に切りに行くことになりそうです。
先日、髪を切った時に人に散髪というよりは断髪だな、と言われましたが、辞書で断髪の意味を調べると、散髪のことと書いてありました。なので大きな意味の違いは無いかもしれないのですが、断髪は主にちょんまげを切る、ざんぎりにするという意味があるようで、散髪には普通に髪を切るという意味合いが強いようです。そういえば、力士の引退のときは散髪式じゃなくて断髪式になっています。断髪のほうが何か強い意志を持って髪を切る、というイメージがしますが皆さんはどうなのでしょう?
でも、昔から髪を切る、ということは何らかの決意だったり、何か大きな意味があったりします。女性が一気にショートカットにしたときに「失恋でもした?」と聞くセクハラ上司は今でもよく見かけることと思います。
そこで今日の一枚です。

モダンチョキチョキズ/くまちゃん
キューンレコード KSC2-92
このCDはモダンチョキチョキズのベスト盤を除くと実質的には最後のアルバム?です。モダチョキは現在活動を休止していることになっていますが、もうあれだけのメンバーで精力的な活動をすることは不可能ではないかと思います。
曲目は、T.D.L.、エケセテネ、トムのいる木蔭、ドロンゲーム、アイ・ウィッシュ…、バブル~DJ&BGM(パート1)、林檎殺人事件、デートコース、新しとやかな獣、上辺よし子さんDJ&BGM(パート2)、くまちゃん、悲しみのマーナ、「メイド・イン・タイワン」予告編ということになっています。
林檎殺人事件などは昔、郷ひろみと樹木希林のデュエット(といっても樹木希林はほとんど歌わずに「フニフニ」行ってただけなんですが)のカバーだったり、くまちゃんなどでは財津一郎(最近ではタケモトピアノが有名ですが)が「キビしぃー」と叫んでいたりと、曲も参加メンバーも豪華です。悲しきマーナは素敵なマーナのマイナーバージョンです。また、バンクバンドとはいえないほど豪華な演奏も聴き物です。
なぜ、散髪でモダチョキか?と言われるとやっぱりチョキチョキズだからでしょう。実際ファーストアルバムでは、ジャケットに紙きりをしている濱田マリがいました。
このアルバムの最後には「メイドイン・タイワン」という次のアルバムの予告編まであるのですが、あれからもう10年、沈黙を守り続けているモダチョキです。
いろいろなことを抜きにして楽しめるアルバムです。モダチョキ好き以外の方でもオススメの一枚です。
2008年08月19日
たまにはお気楽に。
水不足が続いています。香川県というところは、水不足が問題になるところなので、歴史的に水不足に対する対策は様々行われていますが、大雨や洪水に対する考え方はもしかしたら他の県よりも遅れているかもしれません。どの道、大水害が起こってしまうと、最後は人間は何もできなくてただ見ているだけになるのかも知れませんが、その前にそれを防ぐための事も大切かもしれません。
さて、ここ最近、演奏会やら仕事やらで、少し神経質にもなっていた私ですが、頭痛に悩まされて今度MRIを撮ることになったりしました。肩と背中の筋肉がものすごく張っています。肩こりというにはひどすぎる張り方かもしれません。まあ、州崎寺での演奏やサクソフォンアンサンブルコンサートに向けての練習も立て込んできているので、そのせいかもしれませんが…。
肩肘張らずにもっとお気楽にしなさいというからだの信号なのでしょうか。私は割りと自分では楽天家のほうだと思っています。「まっ、いいかー。」とか、「まあ、なんとかなるでしょ。」と思うことがしばしばなのですが、他の人は私をそうは見ていないようです。私はそんなにシビアでまじめではありません(笑)。
そこで今日の一枚です。

植木等的音楽/植木等
プロデュース:大瀧詠一
ファンハウス FHCF-2236
このCDは大瀧詠一氏プロデュースの植木等氏のアルバムです。植木等氏いわく、大瀧詠一氏に乗せられて作ったアルバム。今から7年ぐらい前のアルバムになります。今は亡き、三波春夫氏が参加していたり、また谷啓氏がトロンボーンを吹いて参加していたりします。
曲目は、イヤ、どうも!(オープニング・ヴァージョン)、新二十一世紀音頭 with 三波春夫、針切じいさんのロケン・ロール(オリジナル・ヴァージョン)、FUN×4、ナイアガラ・ムーン、旅愁 with 谷啓、しかられて、花と小父さん with 裕木奈江、サーフィン伝説、針切じいさんのロケン・ロール(アルバム・ヴァージョン)、イヤ,どうも!(クロージング・ヴァージョン)と、大瀧作品のカヴァーなどを含めた11曲になっています。
まさに力の抜けた感じとおとぼけた感じが印象的な音楽ばかりです。ただ、私は聴いたことがあるのですが、無責任男のイメージとは裏腹に植木等氏はものすごく芸や自分に対してはきっちりとして厳しい方なのだそうです。つまり、あれは芸風であって中身ではないと言うことでしょうか。しかし、あれだけの無責任男の芸を極めるとは並大抵のことではないと思います。恐るべし、植木等。
力の抜けた、少し笑える楽しい音楽をお探しの方にオススメの一枚です。
さて、ここ最近、演奏会やら仕事やらで、少し神経質にもなっていた私ですが、頭痛に悩まされて今度MRIを撮ることになったりしました。肩と背中の筋肉がものすごく張っています。肩こりというにはひどすぎる張り方かもしれません。まあ、州崎寺での演奏やサクソフォンアンサンブルコンサートに向けての練習も立て込んできているので、そのせいかもしれませんが…。
肩肘張らずにもっとお気楽にしなさいというからだの信号なのでしょうか。私は割りと自分では楽天家のほうだと思っています。「まっ、いいかー。」とか、「まあ、なんとかなるでしょ。」と思うことがしばしばなのですが、他の人は私をそうは見ていないようです。私はそんなにシビアでまじめではありません(笑)。
そこで今日の一枚です。

植木等的音楽/植木等
プロデュース:大瀧詠一
ファンハウス FHCF-2236
このCDは大瀧詠一氏プロデュースの植木等氏のアルバムです。植木等氏いわく、大瀧詠一氏に乗せられて作ったアルバム。今から7年ぐらい前のアルバムになります。今は亡き、三波春夫氏が参加していたり、また谷啓氏がトロンボーンを吹いて参加していたりします。
曲目は、イヤ、どうも!(オープニング・ヴァージョン)、新二十一世紀音頭 with 三波春夫、針切じいさんのロケン・ロール(オリジナル・ヴァージョン)、FUN×4、ナイアガラ・ムーン、旅愁 with 谷啓、しかられて、花と小父さん with 裕木奈江、サーフィン伝説、針切じいさんのロケン・ロール(アルバム・ヴァージョン)、イヤ,どうも!(クロージング・ヴァージョン)と、大瀧作品のカヴァーなどを含めた11曲になっています。
まさに力の抜けた感じとおとぼけた感じが印象的な音楽ばかりです。ただ、私は聴いたことがあるのですが、無責任男のイメージとは裏腹に植木等氏はものすごく芸や自分に対してはきっちりとして厳しい方なのだそうです。つまり、あれは芸風であって中身ではないと言うことでしょうか。しかし、あれだけの無責任男の芸を極めるとは並大抵のことではないと思います。恐るべし、植木等。
力の抜けた、少し笑える楽しい音楽をお探しの方にオススメの一枚です。
2008年08月19日
このネーミング。
今日、某お店で見つけたアイス。
その名も
スペシャル・ブラックモンブラン

す、すごいです。
因みに、
モンブラン=白い山
ブラック=黒
つまり、黒い白い山だそうな…。
侮れんな…。
昨日のサクソフォンアンサンブルの練習の疲れがまだ多少残っています、ゴメンナサイ。
その名も
スペシャル・ブラックモンブラン
す、すごいです。
因みに、
モンブラン=白い山
ブラック=黒
つまり、黒い白い山だそうな…。
侮れんな…。
昨日のサクソフォンアンサンブルの練習の疲れがまだ多少残っています、ゴメンナサイ。
2008年08月18日
雨がやっぱり降らないのか。
雨が降りそうで降らない日が続いています。夜は多少涼しくなっていた気もしますが、まだまだ蒸し暑い日が続いています。
雨が降ると、やはり、鼻をはじめ体調が優れなくなってしまいます。でも、なぜか、雨の日の病院が空いていることが多いのはなぜでしょう?慢性疾患や内臓の病気でも私が体験する範囲では雨の日のほうが体調が悪くなるので、病院には大量に受診に行く人が増えるはずなのに、なぜか特に内科は雨のほうが受診者が少ないようです。
私は持病のため、月に一回は必ず病院にいきますが、雨が降ると受診しなくなるってことはやっぱり、大して具合が悪くないのに受診している人も多いのでしょうか?それとも雨が降ると出てこられないほどあまりにも具合が悪いのかどちらなんでしょう。まあ、時として、病院でお年を召した方同士が「長い間顔を見なかったけど元気だった?」「いやいや、元気だから今日病院に来た。」みたいな笑い話のような会話を聞いたりします。
そこで今日の一枚です。
グリーグ:「ペール・ギュント」付帯音楽/他
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団
LONDON (キング)KICC 9211
このCDはカラヤン&ウィーンフィルによるペールギュントをはじめとした音楽が収録されたもの。多少オムニバスっぽいところもありますが、完全な詰め込みCDというわけでもないようです。すべて1960年の録音です。カラヤンと言えばベルリンフィルという組み合わせが思い浮かびますが、当時はウィーンフィルとの録音も結構行っていたようです。
収録曲は「ペール・ギュント」付帯音楽の他にリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、チャイコフスキーの幻想交響曲「ロミオとジュリエット」が収録されています。
ペールギュントは小学校の教材に使われたりしていたので、知っている方もたくさんいらっしゃると思います。先日病院に行ったとき、「ペール・ギュント」の中の「朝」が流れていました。まさか、病院で、「山の魔王の宮殿」なんかが流れることはないと思いますが、いろいろな場面でペールギュントの朝は耳にすることがあります。
演奏はカラヤンらしい実に聞きやすい構成がなされた演奏と言えるかもしれません。ウィーン・フィルはやはり特筆すべきは私の大好きなホルンの咆哮でしょうか(笑)ティル・オイレンシュピーゲルは、ウィンナホルンの音が十分に楽しめる一曲です。アナログ時代の録音のリマスタリングですが、バランスのよい音作りで楽しむことができます。
「ペール・ギュント」を小学生の頃聞いた方、カラヤン&ウィーン・フィルの音を手軽に楽しみたい方にオススメの一枚です。
雨が降ると、やはり、鼻をはじめ体調が優れなくなってしまいます。でも、なぜか、雨の日の病院が空いていることが多いのはなぜでしょう?慢性疾患や内臓の病気でも私が体験する範囲では雨の日のほうが体調が悪くなるので、病院には大量に受診に行く人が増えるはずなのに、なぜか特に内科は雨のほうが受診者が少ないようです。
私は持病のため、月に一回は必ず病院にいきますが、雨が降ると受診しなくなるってことはやっぱり、大して具合が悪くないのに受診している人も多いのでしょうか?それとも雨が降ると出てこられないほどあまりにも具合が悪いのかどちらなんでしょう。まあ、時として、病院でお年を召した方同士が「長い間顔を見なかったけど元気だった?」「いやいや、元気だから今日病院に来た。」みたいな笑い話のような会話を聞いたりします。
そこで今日の一枚です。
グリーグ:「ペール・ギュント」付帯音楽/他
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団
LONDON (キング)KICC 9211
このCDはカラヤン&ウィーンフィルによるペールギュントをはじめとした音楽が収録されたもの。多少オムニバスっぽいところもありますが、完全な詰め込みCDというわけでもないようです。すべて1960年の録音です。カラヤンと言えばベルリンフィルという組み合わせが思い浮かびますが、当時はウィーンフィルとの録音も結構行っていたようです。
収録曲は「ペール・ギュント」付帯音楽の他にリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、チャイコフスキーの幻想交響曲「ロミオとジュリエット」が収録されています。
ペールギュントは小学校の教材に使われたりしていたので、知っている方もたくさんいらっしゃると思います。先日病院に行ったとき、「ペール・ギュント」の中の「朝」が流れていました。まさか、病院で、「山の魔王の宮殿」なんかが流れることはないと思いますが、いろいろな場面でペールギュントの朝は耳にすることがあります。
演奏はカラヤンらしい実に聞きやすい構成がなされた演奏と言えるかもしれません。ウィーン・フィルはやはり特筆すべきは私の大好きなホルンの咆哮でしょうか(笑)ティル・オイレンシュピーゲルは、ウィンナホルンの音が十分に楽しめる一曲です。アナログ時代の録音のリマスタリングですが、バランスのよい音作りで楽しむことができます。
「ペール・ギュント」を小学生の頃聞いた方、カラヤン&ウィーン・フィルの音を手軽に楽しみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月18日
アンサンブル練習。(州崎寺に向けて)
今日も纏まった雨は降らず、依然、水不足。
部屋で、巨大なヒトスジシマ蚊に大量に血液を提供しながらブログの行進となっています。
さて、今日は、午前中から、州崎寺にてサックスアンサンブルの練習。
来週が(もう今週か?!)本番なので、まさにこの時期に来て泥縄な練習が行われています。
途中、一緒に演奏をお願いするドラムのI先生(先生と呼ぶのは理由があります。実は私、高校時代この方の現代社会の授業を受けた記憶があります。)に加わっていただいての練習となりました。しかもメンバー全員とは行かず…。多方面にご迷惑をおかけしつつの本番間近の練習です。
午後からは練習場所を移し、バストロンボーンのみわてるを加えての練習。サックスと、トロンボーンのアンサンブルのあわせどころの違い等もあって非常に勉強になりました。
その後、カルテットの練習。昨日の夜に引き続きの練習なので、私も含め皆さん多少バテ気味。ただ、本番までに纏まった練習が出来るのは今日が最後ということで、バテ気味でヘタレの私をなんとか盛り建てていただきつつ、がんばって練習。
皆さん、お疲れ様でした。本番、きっといい練習が出来るはず。
州崎寺でのコンサートのご案内はこちら↓(別ウインドウが開きます。)
石あかり月あかりライブ in 洲崎寺
ところで、話はガラッと変わりますが…。
最近何故かあしたさぬき.jp内でのブログのランキングが多少、上昇気味。
一週間ちょっと前、アクセスの異常な上昇により、20位より上のランキングになって以来、以前のように70位前後に落ち着くかと思いきや、現在30から40位前後を推移中。
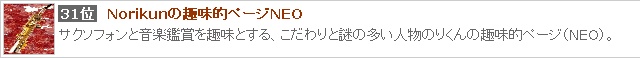
毎日、大して珍しくもないCDのジャケットを掲載しつつ、愚痴にも近い雑感をお読みいただいている奇特な方々、どうもありがとうございます。
部屋で、巨大なヒトスジシマ蚊に大量に血液を提供しながらブログの行進となっています。
さて、今日は、午前中から、州崎寺にてサックスアンサンブルの練習。
来週が(もう今週か?!)本番なので、まさにこの時期に来て泥縄な練習が行われています。
途中、一緒に演奏をお願いするドラムのI先生(先生と呼ぶのは理由があります。実は私、高校時代この方の現代社会の授業を受けた記憶があります。)に加わっていただいての練習となりました。しかもメンバー全員とは行かず…。多方面にご迷惑をおかけしつつの本番間近の練習です。
午後からは練習場所を移し、バストロンボーンのみわてるを加えての練習。サックスと、トロンボーンのアンサンブルのあわせどころの違い等もあって非常に勉強になりました。
その後、カルテットの練習。昨日の夜に引き続きの練習なので、私も含め皆さん多少バテ気味。ただ、本番までに纏まった練習が出来るのは今日が最後ということで、バテ気味でヘタレの私をなんとか盛り建てていただきつつ、がんばって練習。
皆さん、お疲れ様でした。本番、きっといい練習が出来るはず。
州崎寺でのコンサートのご案内はこちら↓(別ウインドウが開きます。)
石あかり月あかりライブ in 洲崎寺
ところで、話はガラッと変わりますが…。
最近何故かあしたさぬき.jp内でのブログのランキングが多少、上昇気味。
一週間ちょっと前、アクセスの異常な上昇により、20位より上のランキングになって以来、以前のように70位前後に落ち着くかと思いきや、現在30から40位前後を推移中。
毎日、大して珍しくもないCDのジャケットを掲載しつつ、愚痴にも近い雑感をお読みいただいている奇特な方々、どうもありがとうございます。




