2008年06月30日
我が家が一番。
さて、最近仕事で多少遅い時間に帰宅、そして、週末も土曜は出勤、日曜はサックス・アンサンブルの練習と、自宅で過ごす時間が極端に減ってしまいました。家で何か作業をしたいと思ってもなかなか出来ず、結局深夜に作業することになってしまいます。
私は本来家で過ごすことが多い生活スタイルの人間だと思いますので、ここ最近のように家に居ない時間が多いのも珍しいかもしれません。
まあ、我が家に変えるとホッとするのが事実ですが。
そこで今日の一枚です。

スメタナ/連作交響詩「わが祖国」全曲
指揮:ヴァーツラフ・ノイマン
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
コロムビア COCO-6767
このCDはスメタナの代表作でモルダウをはじめとした「わが祖国」が収録されたものです。
スメタナはチェコを代表する作曲家です(当時チェコスロバキア)。チェコスロバキアは、1620年から300年間、オーストリアのハプスブルク帝国に支配されていたという歴史があり、スメタナが生まれた1824年でもオーストリア帝国の支配下です。
帝国の支配は、厳しいく、母国語が禁じられるなど、チェコスロバキアの人々は、屈辱的迫害を受けていました。人々は、この支配から逃れ、「自分たちの国をつくりたい」という思いを強くしていきました。こうした中、スメタナが思いを込めて作った曲が、祖国の歴史と自然を歌った一連の作品で、交響詩「わが祖国」です。
この「わが祖国」は日本ではモルダウ以外あまり(というかほとんど)演奏されませんが、6つの曲があります。1:ヴィシェフラト(高い城)、2:ヴルタヴァ(モルダウ)、3:シャールカ、4:ボヘミアの森と草原より、5:ターボル、6:ブラニーク、という6曲となります。
スメタナの死後30年を経過してチェコスロバキアはついに独立を果たすわけなのですが、モルダウの美しさとは裏腹にスメタナの革命的、戦闘的音楽活動とも言える愛国心に満ちた作品です。
さて、演奏の方はチェコの名門、チェコフィルとノイマンによるもので、文句のつけ様もありません。聴いた感じともすればおとなしく物足りない演奏にも感じますが、よくよく聴くと、曲全体の構成が大きく捉えられており、しっかりと組み立てられているものであることに気づきます。ノイマンはクーベリックの後を引き継いだ生粋のチェコの指揮者ですが、クーベリックよりもさらに、洗練された音楽を作っているように思います。その分ちょっと民族色の濃い泥臭さはなくなっているのかもしれませんが、カラヤン/ベルリンフィルの演奏などに比べると、雄大で牧歌的、壮大なものが描かれていると感じます。カラヤン/ベルリンフィルなどはどちらかというと荘厳できらびやかに演奏されている気がします。
ヨーロッパでは土地か一続きになっているためにまた、日本などとは全く違った愛国心、といったものがあるのかもしれません。しかし、ヨーロッパの人が同じヨーロッパのほかの国に出かけた後で、帰ってから、「やっぱり家が一番」と言うかどうかは定かではないのですが。
モルダウを聴いてみたい方、チェコの音楽に少し触れた見たい方、また、連作交響詩「わが祖国」をモルダウだけでなく全曲聴いてみたい方にオススメの一枚です。
私は本来家で過ごすことが多い生活スタイルの人間だと思いますので、ここ最近のように家に居ない時間が多いのも珍しいかもしれません。
まあ、我が家に変えるとホッとするのが事実ですが。
そこで今日の一枚です。

スメタナ/連作交響詩「わが祖国」全曲
指揮:ヴァーツラフ・ノイマン
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
コロムビア COCO-6767
このCDはスメタナの代表作でモルダウをはじめとした「わが祖国」が収録されたものです。
スメタナはチェコを代表する作曲家です(当時チェコスロバキア)。チェコスロバキアは、1620年から300年間、オーストリアのハプスブルク帝国に支配されていたという歴史があり、スメタナが生まれた1824年でもオーストリア帝国の支配下です。
帝国の支配は、厳しいく、母国語が禁じられるなど、チェコスロバキアの人々は、屈辱的迫害を受けていました。人々は、この支配から逃れ、「自分たちの国をつくりたい」という思いを強くしていきました。こうした中、スメタナが思いを込めて作った曲が、祖国の歴史と自然を歌った一連の作品で、交響詩「わが祖国」です。
この「わが祖国」は日本ではモルダウ以外あまり(というかほとんど)演奏されませんが、6つの曲があります。1:ヴィシェフラト(高い城)、2:ヴルタヴァ(モルダウ)、3:シャールカ、4:ボヘミアの森と草原より、5:ターボル、6:ブラニーク、という6曲となります。
スメタナの死後30年を経過してチェコスロバキアはついに独立を果たすわけなのですが、モルダウの美しさとは裏腹にスメタナの革命的、戦闘的音楽活動とも言える愛国心に満ちた作品です。
さて、演奏の方はチェコの名門、チェコフィルとノイマンによるもので、文句のつけ様もありません。聴いた感じともすればおとなしく物足りない演奏にも感じますが、よくよく聴くと、曲全体の構成が大きく捉えられており、しっかりと組み立てられているものであることに気づきます。ノイマンはクーベリックの後を引き継いだ生粋のチェコの指揮者ですが、クーベリックよりもさらに、洗練された音楽を作っているように思います。その分ちょっと民族色の濃い泥臭さはなくなっているのかもしれませんが、カラヤン/ベルリンフィルの演奏などに比べると、雄大で牧歌的、壮大なものが描かれていると感じます。カラヤン/ベルリンフィルなどはどちらかというと荘厳できらびやかに演奏されている気がします。
ヨーロッパでは土地か一続きになっているためにまた、日本などとは全く違った愛国心、といったものがあるのかもしれません。しかし、ヨーロッパの人が同じヨーロッパのほかの国に出かけた後で、帰ってから、「やっぱり家が一番」と言うかどうかは定かではないのですが。
モルダウを聴いてみたい方、チェコの音楽に少し触れた見たい方、また、連作交響詩「わが祖国」をモルダウだけでなく全曲聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年06月29日
ゴンザレス。
いや、別にどこぞのドーピング問題の野球選手ではなく、リードの話。
最近、バンドレンのリードがまた劣化しているような気がしてきたので、他のリードを使ってみようと思い立って購入。

特徴としては、
カットはアンファイルド(皮が二段階にむかれていない)。
アルゼンチン産ケーン使用。
全てのリードをハンドセレクト。
リードのl強度が4分の1ごとに分類されている。

といったところなのですが、吹いてみての感想としては、
バンドレンに比較して、
低音のレスポンスが悪くなる。
比較的明るく柔らかい音色がなる。
高音は少し細く鳴る。
そして、
強度が4分の1刻みですが、ソプラノのリードは3.5と、3.75で極端に強度が違うイメージでした。バンドレンの4と3.5ぐらいの違いがあります。ただ、一箱の中でのばらつきは少ない気がします。なので、カットと強度が自分に合えば、バンドレンを使うよりお買い得かもしれません。
ただ、クラシックの場合特に世の中の大半の人々はバンドレンのリードを吹きなれているので、折角なら、バンドレント同じファイルドのカットにして、バンドレンの吹奏感に近づけると、もっと使用者が増えるのではないかと思うのですが…。
想像するに、バンドレンのリードに比べ、ケーン全体の厚みが厚く、リードの先端に、対して急な角度でカットされているため、固低音のレスポンスが悪く、高音が細く鳴るのではないかと思います。
私が次もこのリードを買うかと聞かれたら…
微妙です。
やっぱりバンドレンが慣れてるからなー。
今日は、秋のサクソフォーン・アンサンブル・コンサートに向けてのラージ練習。
皆さんお疲れ様でした。
練習の様子はおそらく、近日中のダッパー公式ブログに掲載されることでしょう。
最近、バンドレンのリードがまた劣化しているような気がしてきたので、他のリードを使ってみようと思い立って購入。

特徴としては、
カットはアンファイルド(皮が二段階にむかれていない)。
アルゼンチン産ケーン使用。
全てのリードをハンドセレクト。
リードのl強度が4分の1ごとに分類されている。

といったところなのですが、吹いてみての感想としては、
バンドレンに比較して、
低音のレスポンスが悪くなる。
比較的明るく柔らかい音色がなる。
高音は少し細く鳴る。
そして、
強度が4分の1刻みですが、ソプラノのリードは3.5と、3.75で極端に強度が違うイメージでした。バンドレンの4と3.5ぐらいの違いがあります。ただ、一箱の中でのばらつきは少ない気がします。なので、カットと強度が自分に合えば、バンドレンを使うよりお買い得かもしれません。
ただ、クラシックの場合特に世の中の大半の人々はバンドレンのリードを吹きなれているので、折角なら、バンドレント同じファイルドのカットにして、バンドレンの吹奏感に近づけると、もっと使用者が増えるのではないかと思うのですが…。
想像するに、バンドレンのリードに比べ、ケーン全体の厚みが厚く、リードの先端に、対して急な角度でカットされているため、固低音のレスポンスが悪く、高音が細く鳴るのではないかと思います。
私が次もこのリードを買うかと聞かれたら…
微妙です。
やっぱりバンドレンが慣れてるからなー。
今日は、秋のサクソフォーン・アンサンブル・コンサートに向けてのラージ練習。
皆さんお疲れ様でした。
練習の様子はおそらく、近日中のダッパー公式ブログに掲載されることでしょう。
2008年06月29日
テレビはあまり見ませんが。
私は以前から、あまりテレビを見ない人です。かといって映画も見ない人です。でも、世間の情報からはなんとか取り残されずに生きています。
テレビというメディアは確かに多くの情報を与えてくれるメディアではありますが、テレビが全てを与えてくれることなどありえません。
ある意味、テレビは、虚構とその中に存在する作られた娯楽を与えてくれるものなのかもしれません。
そこで今日の一枚。

このCDはNHKのテレビ番組、美の壷で流れた音楽を集めたものです。この番組、谷啓氏がナビゲーターを務める、美術品の鑑賞マニュアルという位置づけです。谷啓氏はコメディアン、俳優、そしてジャズトロンボーン奏者としても著名です。若い方はご存じないかもしれませんが、彼は原信夫とシャープ&譜ラッツという当時日本のJAZZ界の第一線で活躍するプレーヤー達がいたバンドにも参加しています。そして、スイングジャーナル誌にもたびたび登場するほどのプレーヤーでした。さらに、コメディーの世界ではクレイジーキャッツで活躍し、「ガチョーン」があまりにも有名です。
この美の壷、オープニングや番組中の音楽がJAZZのスタンダードナンバーで彩られているのも、なかなかです。そして、このCDは番組で使われたJAZZのスタンダードナンバーがオムニバスで収録されています。モーニンで始まり、スターダストで締めくくられています。シャボン玉ホリデー世代にもこれからJAZZを聞いてみようと思う方にもオススメの一枚です。
テレビというメディアは確かに多くの情報を与えてくれるメディアではありますが、テレビが全てを与えてくれることなどありえません。
ある意味、テレビは、虚構とその中に存在する作られた娯楽を与えてくれるものなのかもしれません。
そこで今日の一枚。

このCDはNHKのテレビ番組、美の壷で流れた音楽を集めたものです。この番組、谷啓氏がナビゲーターを務める、美術品の鑑賞マニュアルという位置づけです。谷啓氏はコメディアン、俳優、そしてジャズトロンボーン奏者としても著名です。若い方はご存じないかもしれませんが、彼は原信夫とシャープ&譜ラッツという当時日本のJAZZ界の第一線で活躍するプレーヤー達がいたバンドにも参加しています。そして、スイングジャーナル誌にもたびたび登場するほどのプレーヤーでした。さらに、コメディーの世界ではクレイジーキャッツで活躍し、「ガチョーン」があまりにも有名です。
この美の壷、オープニングや番組中の音楽がJAZZのスタンダードナンバーで彩られているのも、なかなかです。そして、このCDは番組で使われたJAZZのスタンダードナンバーがオムニバスで収録されています。モーニンで始まり、スターダストで締めくくられています。シャボン玉ホリデー世代にもこれからJAZZを聞いてみようと思う方にもオススメの一枚です。
2008年06月28日
こんな感じで。
私のCDが何故増えていくかを考えるに、おそらくこういったことが原因ではないかと…。
好きな曲や、聴いてみたい曲があったら、同じ曲でもいろんな演奏を当然集めたくなります。当然です、はい、当然。

ということで、ボレロをちょっと集めただけで10枚。こんなことになるわけですが…。
サックスのアンサンブルでも同じ曲が大量にあったり、オーケストラの曲でも同じ曲の違う演奏が大量にあったりします。
好きな曲や、聴いてみたい曲があったら、同じ曲でもいろんな演奏を当然集めたくなります。当然です、はい、当然。

ということで、ボレロをちょっと集めただけで10枚。こんなことになるわけですが…。
サックスのアンサンブルでも同じ曲が大量にあったり、オーケストラの曲でも同じ曲の違う演奏が大量にあったりします。
2008年06月27日
ビンテージな楽器。
私の楽器は当然モダンの楽器で、オールドでもビンテージでもありません。アルトサクソフォーンが、セルマーのSA80SE2W/O(ローマ数字は機種依存文字なので、アラビア数字にしてます)これは所謂シリーズ2と呼ばれているモデル。現行モデルです。最もシリーズ3が発売されているので、最新モデルというわけではありませんが。ソプラノサクソフォーンはヤナギサワのS-9930。シルバーソニックと呼ばれているモデルです。これも現行機種。
アルトサクソフォーンは購入してから既に20年が経過。ソプラノサクソフォーンも10年以上が経過しました。ただ、ビンテージになるには程遠いと思います。一番の理由は現行機種であること。ただ、セルマーのマーク6と呼ばれる、ビンテージで有名なモデルは1970年頃まで発売されていたのにも、関わらず1990年ごろにはビンテージ扱いされていましたので、よほどの名器とされているのかもしれません。
多分、ビンテージになる大前提は生産が終了していることだと思いますが…。
ただし、私はクラシックを演奏するにはオールドよりもモダンの楽器が扱いやすく向いているとも思っています。賛否両論だとは思いますが…。、
そこで今日の一枚。

オリジナル・サクソフォーン /浜松市楽器博物館コレクションシリーズ12
このCDは、浜松市楽器博物館の所蔵する歴史的なオールドの楽器で演奏された曲を収録してあります。楽器が発明された当時、楽器発明者アドルフサックスにより製作されたサクソフォーンを使っての演奏です。おそらく、この時代の楽器は今のようにオクターブキーのオートでの切り替え機構がなく、二つのオクターブキーを押し変えて切り替えていたのだと思います。ただ、古い楽器には見えるものの、発明当時からほとんど形やスタイルを変えていないのがサクソフォーンの若さというか、すごさというか…。音を聞いてみると、なるほど、モダンの楽器とはまた違った響きがします。機動性や音のクリア感は明らかにモダンの楽器には及ばないものの、木管楽器だと再認識させるような音色の柔らかさや、味のある響きはオールドならではのものだと思います。
歴史的な楽器の響きを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
アルトサクソフォーンは購入してから既に20年が経過。ソプラノサクソフォーンも10年以上が経過しました。ただ、ビンテージになるには程遠いと思います。一番の理由は現行機種であること。ただ、セルマーのマーク6と呼ばれる、ビンテージで有名なモデルは1970年頃まで発売されていたのにも、関わらず1990年ごろにはビンテージ扱いされていましたので、よほどの名器とされているのかもしれません。
多分、ビンテージになる大前提は生産が終了していることだと思いますが…。
ただし、私はクラシックを演奏するにはオールドよりもモダンの楽器が扱いやすく向いているとも思っています。賛否両論だとは思いますが…。、
そこで今日の一枚。

オリジナル・サクソフォーン /浜松市楽器博物館コレクションシリーズ12
このCDは、浜松市楽器博物館の所蔵する歴史的なオールドの楽器で演奏された曲を収録してあります。楽器が発明された当時、楽器発明者アドルフサックスにより製作されたサクソフォーンを使っての演奏です。おそらく、この時代の楽器は今のようにオクターブキーのオートでの切り替え機構がなく、二つのオクターブキーを押し変えて切り替えていたのだと思います。ただ、古い楽器には見えるものの、発明当時からほとんど形やスタイルを変えていないのがサクソフォーンの若さというか、すごさというか…。音を聞いてみると、なるほど、モダンの楽器とはまた違った響きがします。機動性や音のクリア感は明らかにモダンの楽器には及ばないものの、木管楽器だと再認識させるような音色の柔らかさや、味のある響きはオールドならではのものだと思います。
歴史的な楽器の響きを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年06月26日
お買い得とはパート2。
昨日の日記に安くなったものとしてCDを上げてみましたが、現に、私がCDを買い始めた頃クラシックのCDはほとんどが一枚3,500円。現在、クラシックのCDはほとんどが2,000円前後なので、かなり安くなっているのかもしれません。また、CDがメディアとして隆盛を極めていた1990年代にリリースされたものが、現在廉価版として再発売されるなどして、当時では信じられないような価格で手に入ったりします。
思えば一番最初に買ったのはCDではなく、LPレコードでした。その当時LPレコードは一枚2,500円前後だったと記憶しています。
そんなところで今日の一枚。

カラヤン/ロシア&フランス管弦楽名演集
ユニバーサルクラシック UCCG9070
1
組曲「展覧会の絵」(ムソルグスキー/ラヴェル編)
イタリア奇想曲op.45(チャイコフスキー)
大序曲「1812年」op.49(チャイコフスキー)
スラヴ行進曲op.31(チャイコフスキー)
2
交響組曲「シェエラザード」op.35(リムスキー=コルサコフ)
歌劇「イーゴリ公」~ダッタンの娘たちの踊り(ボロディン/リムスキー=コルサコフ,グラズノフ編)
歌劇「イーゴリ公」~ダッタン人の踊り(ボロディン/リムスキー=コルサコフ,グラズノフ編)
ディスク:3
ボレロ(ラヴェル)
交響詩「海」~3つの交響的スケッチ(ドビュッシー)
「ダフニスとクロエ」第2組曲(ラヴェル)
牧神の午後への前奏曲(ドビュッシー)
4
「アルルの女」第1組曲(ビゼー)
「アルルの女」第2組曲(ビゼー
「カルメン」組曲(ビゼー)
歌劇「ファウスト」~バレエ音楽(グノー)
歌劇「ファウスト」~ファウスト・ワルツ(グノー)
このCDはカラヤン、ベルリンフィルによる、ロシア、フランス管弦楽曲集。まさかの4枚組み。リリース当時はそれぞれ別のCDとして発売されていたものを4枚組み合わせたような形のものです。そしてお買い得、5,000円。4枚のCDで有名どころのロシアもの、フランスものの管弦楽曲が網羅されています。カラヤン帝王時代のベルリンフィルとの黄金コンビでの録音。そして、フランスものや展覧会の絵に登場するサクソフォンの演奏は全て故ダニエル・デファイエ氏。上質ですばらしい音色を聞かせてくれます。手軽にロシア、フランスものの演奏を手に入れて聞いてみたい方、デファイエのオーケストラでのソロを聞きたい方にオススメの一枚です。
思えば一番最初に買ったのはCDではなく、LPレコードでした。その当時LPレコードは一枚2,500円前後だったと記憶しています。
そんなところで今日の一枚。

カラヤン/ロシア&フランス管弦楽名演集
ユニバーサルクラシック UCCG9070
1
組曲「展覧会の絵」(ムソルグスキー/ラヴェル編)
イタリア奇想曲op.45(チャイコフスキー)
大序曲「1812年」op.49(チャイコフスキー)
スラヴ行進曲op.31(チャイコフスキー)
2
交響組曲「シェエラザード」op.35(リムスキー=コルサコフ)
歌劇「イーゴリ公」~ダッタンの娘たちの踊り(ボロディン/リムスキー=コルサコフ,グラズノフ編)
歌劇「イーゴリ公」~ダッタン人の踊り(ボロディン/リムスキー=コルサコフ,グラズノフ編)
ディスク:3
ボレロ(ラヴェル)
交響詩「海」~3つの交響的スケッチ(ドビュッシー)
「ダフニスとクロエ」第2組曲(ラヴェル)
牧神の午後への前奏曲(ドビュッシー)
4
「アルルの女」第1組曲(ビゼー)
「アルルの女」第2組曲(ビゼー
「カルメン」組曲(ビゼー)
歌劇「ファウスト」~バレエ音楽(グノー)
歌劇「ファウスト」~ファウスト・ワルツ(グノー)
このCDはカラヤン、ベルリンフィルによる、ロシア、フランス管弦楽曲集。まさかの4枚組み。リリース当時はそれぞれ別のCDとして発売されていたものを4枚組み合わせたような形のものです。そしてお買い得、5,000円。4枚のCDで有名どころのロシアもの、フランスものの管弦楽曲が網羅されています。カラヤン帝王時代のベルリンフィルとの黄金コンビでの録音。そして、フランスものや展覧会の絵に登場するサクソフォンの演奏は全て故ダニエル・デファイエ氏。上質ですばらしい音色を聞かせてくれます。手軽にロシア、フランスものの演奏を手に入れて聞いてみたい方、デファイエのオーケストラでのソロを聞きたい方にオススメの一枚です。
2008年06月25日
お買い得とは。
最近、ガソリンを初めとして様々なものの物価が高騰しています。納豆のグラム数が減少したり、菓子パンが小さくなったり、様と値段は変わらないけれど、実質的な値上げというものも多数。
値段が下がったものは果たしてあるのかどうか…。値段が下がったのは賃金やボーナスぐらいか…。
ということで、今日の一枚です。

チャイコフスキー/弦楽四重奏曲全集(2枚組)
ボロディン四重奏団
弦楽四重奏曲第1番ニ長調op.11
弦楽四重奏曲変ロ長調
弦楽六重奏曲ニ短調op.70「フィレンツェの想い出」
弦楽四重奏曲第2番ヘ長調op.22
弦楽四重奏曲第3番変ホ短調op.30
このCDはボロディン四重奏団によるチャイコフスキーの弦楽四重奏曲集。といいつつも、「フィレンツェの思い出」は、弦楽六重奏だったりします。金額的にはこれだけ盛りだくさんで2000円ぐらい。そういえば、最近CDの価格も昔に比べれば安くなったのかもしれません。
演奏の方は録音が多少古いものの、チャイコフスキーらしい情感豊かな演奏を聞かせてくれます。現代的な見通しのよいすっきりとした響きではありませんが、渋みのある、しっかり歌いこんだ演奏を聴くことが出来ます。
弦楽アンサンブルがお好きな方、チャイコフスキーの弦楽四重奏曲集をお探しの方にオススメの一枚です。
値段が下がったものは果たしてあるのかどうか…。値段が下がったのは賃金やボーナスぐらいか…。
ということで、今日の一枚です。

チャイコフスキー/弦楽四重奏曲全集(2枚組)
ボロディン四重奏団
弦楽四重奏曲第1番ニ長調op.11
弦楽四重奏曲変ロ長調
弦楽六重奏曲ニ短調op.70「フィレンツェの想い出」
弦楽四重奏曲第2番ヘ長調op.22
弦楽四重奏曲第3番変ホ短調op.30
このCDはボロディン四重奏団によるチャイコフスキーの弦楽四重奏曲集。といいつつも、「フィレンツェの思い出」は、弦楽六重奏だったりします。金額的にはこれだけ盛りだくさんで2000円ぐらい。そういえば、最近CDの価格も昔に比べれば安くなったのかもしれません。
演奏の方は録音が多少古いものの、チャイコフスキーらしい情感豊かな演奏を聞かせてくれます。現代的な見通しのよいすっきりとした響きではありませんが、渋みのある、しっかり歌いこんだ演奏を聴くことが出来ます。
弦楽アンサンブルがお好きな方、チャイコフスキーの弦楽四重奏曲集をお探しの方にオススメの一枚です。
2008年06月24日
目覚め。
最近、どんなに遅く寝ても朝6時に一旦目覚めるようになりました。やっぱり年なんでしょうか。
かといって、6時に起きるわけではなく、二度寝するわけですが…。
最近、多少睡眠不足です。にもまして、朝の目覚めがスッキリしません。
私は、今まで目覚める時はオーディオタイマーで、クラシックを爆音で鳴らすという目覚ましを行ってきましたが、最近は、爆音で鳴らす前に目覚め、うとうとしながら爆音で音楽が鳴るのを待っている状態になっています。
勿論、目覚めも最悪。
そこで今日の一枚です。

ラヴェル:ボレロ/ミュンシュ
指揮:シャルル・ミュンシュ
ボストン交響楽団
RCA R25C-1005
このCDはシャルル・ミュンシュ指揮によるラヴェルの管弦楽曲集のようなもの。現在は再販され「ボレロ~ラヴェル名曲集」としてBMGファンハウスから発売されています。曲はボレロ、スペイン狂詩曲、なき王女のためのパヴァーヌ、ラ・ヴァルス、組曲「マ・メール・ロワ」と有名どころが収録されています。
このミュンシュ盤のボレロは必ずといっていいぐらい名演ということで様々な場所に登場しています。演奏は以外にも上品というよりは元気のよいボレロ。特に後半などは溌剌としたリズム感と元気なトランペットに飾られて、何かスペイン風の舞曲というよりは、スペイン風の行進曲といった様相を呈しています。演奏自体は時代もあって、録音のせいも有るのか少し古い印象は受けますが、決して黴の生えたような演奏ではなく、今聴いても十分に楽しめる演奏です。
元気のよいボレロで朝目覚めたい方にオススメの一枚です。
かといって、6時に起きるわけではなく、二度寝するわけですが…。
最近、多少睡眠不足です。にもまして、朝の目覚めがスッキリしません。
私は、今まで目覚める時はオーディオタイマーで、クラシックを爆音で鳴らすという目覚ましを行ってきましたが、最近は、爆音で鳴らす前に目覚め、うとうとしながら爆音で音楽が鳴るのを待っている状態になっています。
勿論、目覚めも最悪。
そこで今日の一枚です。

ラヴェル:ボレロ/ミュンシュ
指揮:シャルル・ミュンシュ
ボストン交響楽団
RCA R25C-1005
このCDはシャルル・ミュンシュ指揮によるラヴェルの管弦楽曲集のようなもの。現在は再販され「ボレロ~ラヴェル名曲集」としてBMGファンハウスから発売されています。曲はボレロ、スペイン狂詩曲、なき王女のためのパヴァーヌ、ラ・ヴァルス、組曲「マ・メール・ロワ」と有名どころが収録されています。
このミュンシュ盤のボレロは必ずといっていいぐらい名演ということで様々な場所に登場しています。演奏は以外にも上品というよりは元気のよいボレロ。特に後半などは溌剌としたリズム感と元気なトランペットに飾られて、何かスペイン風の舞曲というよりは、スペイン風の行進曲といった様相を呈しています。演奏自体は時代もあって、録音のせいも有るのか少し古い印象は受けますが、決して黴の生えたような演奏ではなく、今聴いても十分に楽しめる演奏です。
元気のよいボレロで朝目覚めたい方にオススメの一枚です。
2008年06月23日
訪問演奏会。
昨日、三木町の氷上小学校に行ってきました。高松ウインドシンフォニーで、訪問演奏にお伺いしてきたのですが、やはり、小学校で演奏するって言うのは、いいですね。
私のようなヘタクソな演奏でも、小学生の皆様が目を輝かせて聞いてくれるからで、ヘタクソながらも、今まで音楽を続けて着てよかったと思う瞬間でもあります。
今日はサックスパートの楽器紹介では、ピタゴラスイッチのテーマを演奏してきました。本当は、ソプラノサックスを使う必要がない演奏会だったのですが、折角楽器紹介なので、ソプラノも持っていこうということで、ソプラノを持っていきました。
で、演奏中に「なんか音がひっくり返るなー」などと思っていたら、実は楽器の螺子が抜けてました。
これも日ごろのメンテナンスの悪さがなせる業?なのですが…。
私の楽器、折角ヤナギサワのシルバーソニック、S-9930なのに、手入れが悪いためにボロボロになりつつあります。
今回ちょっと反省。
そこで今日の一枚です。

SAX HOLIC/本多俊之
東芝EMI TOCT-9445
このCDは本多俊之氏のアルバムです。伊丹監督作品をはじめ、TVで使われていた音楽が集められた感じのアルバムになっています。どこかで少し前に聞いたことが有る曲ばかりだと思います。わたしが、持っていこうと思ったアルバム、その一です。
ソプラノ・サックスが心地いいフュージョンアルバムで、はボサノバ味のビートが楽しく効いた伊丹映画の「スーパーの女」のテーマ曲「Lady Smart」が収録され、テレビは「竜馬におまかせ」の挿入曲の、テレ朝系のモーニングワイド「スーパーモーニング」のテーマ「Sweet Vacances」が、オリジナルと再演奏バージョンの2曲で入っています。以前、ダウンタウンの浜田雅功主演「竜馬におまかせ!」は、三谷幸喜の幕末もののドラマです。なんと新鮮組だけじゃなかったんですね。このドラマの中ではなんと内藤剛がフリューゲルホルンを吹いたり、本多俊之氏がゲストで出演、番組中でバンドを率いて演奏するというシーンも。大昔の映画「ジャズ大名」を思わせます。
で、本多俊之氏の愛器、実は私の持っている楽器と同じヤナギサワのシルバーソニック。
とても同じモデルとは思えないすばらしい音に感動してしまいます。
美しいサックスの響きのフュージョンをお探しの方、本多俊之氏の演奏、音色を聞いてみたい方、また、収録曲のドラマや、映画が懐かしい方にオススメです。
私のようなヘタクソな演奏でも、小学生の皆様が目を輝かせて聞いてくれるからで、ヘタクソながらも、今まで音楽を続けて着てよかったと思う瞬間でもあります。
今日はサックスパートの楽器紹介では、ピタゴラスイッチのテーマを演奏してきました。本当は、ソプラノサックスを使う必要がない演奏会だったのですが、折角楽器紹介なので、ソプラノも持っていこうということで、ソプラノを持っていきました。
で、演奏中に「なんか音がひっくり返るなー」などと思っていたら、実は楽器の螺子が抜けてました。
これも日ごろのメンテナンスの悪さがなせる業?なのですが…。
私の楽器、折角ヤナギサワのシルバーソニック、S-9930なのに、手入れが悪いためにボロボロになりつつあります。
今回ちょっと反省。
そこで今日の一枚です。

SAX HOLIC/本多俊之
東芝EMI TOCT-9445
このCDは本多俊之氏のアルバムです。伊丹監督作品をはじめ、TVで使われていた音楽が集められた感じのアルバムになっています。どこかで少し前に聞いたことが有る曲ばかりだと思います。わたしが、持っていこうと思ったアルバム、その一です。
ソプラノ・サックスが心地いいフュージョンアルバムで、はボサノバ味のビートが楽しく効いた伊丹映画の「スーパーの女」のテーマ曲「Lady Smart」が収録され、テレビは「竜馬におまかせ」の挿入曲の、テレ朝系のモーニングワイド「スーパーモーニング」のテーマ「Sweet Vacances」が、オリジナルと再演奏バージョンの2曲で入っています。以前、ダウンタウンの浜田雅功主演「竜馬におまかせ!」は、三谷幸喜の幕末もののドラマです。なんと新鮮組だけじゃなかったんですね。このドラマの中ではなんと内藤剛がフリューゲルホルンを吹いたり、本多俊之氏がゲストで出演、番組中でバンドを率いて演奏するというシーンも。大昔の映画「ジャズ大名」を思わせます。
で、本多俊之氏の愛器、実は私の持っている楽器と同じヤナギサワのシルバーソニック。
とても同じモデルとは思えないすばらしい音に感動してしまいます。
美しいサックスの響きのフュージョンをお探しの方、本多俊之氏の演奏、音色を聞いてみたい方、また、収録曲のドラマや、映画が懐かしい方にオススメです。
2008年06月22日
収まりきらない。
さて、私は滅多に旅行にいきません。国内で一番長い旅行は5泊6日、しかも、資格取得のためにスクーリングに言っただけです。私は、元来出不精のところが有るので、旅行もめんどくさいと思っている方です。当然、海外旅行も行ってみたいとは思いながらも、今まで一度も行ったことがありません。でも、海外旅行が好きな人でも、帰ってくる度に「やっぱり我が家が一番」とつぶやいている人も少なくないような気がするのですが、それは、私の勝手な思い込みなのでしょうか。
さて、5泊6日のたびの時に、不慣れなパッキングをしたのですが、下着をはじめとした着替えなどを詰めなければなりません。もうちょっと長い一週間とかを超えるようなものだと、着替えを宿泊先で洗濯とかする気になるのかもしれませんが、5泊という微妙な日程なので、やはり、全部着替えを持っていこうと思い、詰めてみました。
ところが私は大きなバッグを持っていないので、バッグに収まりきらないという事件が発生しました。私の持っているのは3WAYバッグなのですが、容量が20リットル足らずしかありません。ネットで検索しても、この容量で行けるのはせいぜい2泊までです。そこで…圧縮袋を採用しました。荷物がかなり減りはしましたが、それでもまだパンパンです。おまけに旅行の目的がスクーリングなので、教科書や参考書も持っていかねばなりませんでしたので、別のショルダーバッグも用意。
荷物が収まりきらず、どうにもならない状態になってしまいました。 考えて解決方法として、荷物を先に別便でホテルに送ってしまうことを選択しました。到着日指定で送れば、何とかなりそうです。それにバッグ買うよりも安いし、何より行きの荷物が減らせます。これはちょっと名案。早速別のバッグに4日分だけパッキングしてクロ○コヤマトで送りました。1日分は、もし、到着が遅れても大丈夫なようにという保険の意味をこめて自分で持っていきました。本当は行ってからが一番大変だったのですが。
さて今日の一枚です。

チェリビダッケ・エディションVol.1 NO.11
チャイコフスキー/ロメオとジュリエット
バルトーク/管弦楽のための協奏曲
指揮:セルジュ・チェリビダッケ
ミュンフェン・フィルハーモニー管弦楽団
東芝EMI TOCE-11611
このCDはチェリビダッケ指揮によるチャイコフスキーのロメオとジュリエット、バルトークの通称「オケコン」を収録したもの。
バルトークは日本人にまだまだ馴染みが薄い作曲家かもしれませんが、近年、日本でも様々な曲が取り上げられています。この、管弦楽のための協奏曲は、ナチスから逃れるため1940年、アメリカへ亡命したものの、アメリカではバルトークの音楽は理解されず、また白血病にも冒されるなど苦しい生活が続くなか、そのような窮状を見かねたボストン交響楽団音楽監督のクーセヴィツキーが委嘱。2ヶ月足らずで完成されたものです。
「管弦楽のための協奏曲」という作品名から分かるように、オーケストラのひとつひとつの楽器を独奏的に扱ったつくりになっています。5楽章で構成されており、第1楽章「序奏」、第2楽章「対の遊び」、第3楽章「悲歌」、第4楽章「中断された間奏曲」、第5楽章「終曲」というタイトルがつけられています。
このチェリビダッケの演奏はライヴ録音にもかかわらず、完成度の高い演奏で、一音一音を確認するかのような、まるで音に魂や愛情を込めるような遅いテンポでよくコントロールされたものになっています。緻密で濃厚な演奏で、空間的な奥行きスラ感じられる演奏です。オーケストラ全体が一つの楽器として響く感があって、表情豊かに歌われています。(第3楽章などはさすがに遅すぎな気もしなくは無いのですが。)
チャイコフスキーの通称「ロメジュリ」はゆっくりとしたテンポで濃厚に歌い上げられていて、もう本当に凄いというか凄まじい演奏です。指揮者もオケも聴衆も完全燃焼した感覚が伝わってきます。ロメオとジュリエット、二人を取り巻く登場人物の心象風景が見事に描きだされた名演です。はじめ聴いたときにはテンポのあまりの遅さにギョッとしたほどですが、聴いていくと音楽に対する真剣さと、大きく描き出された絵画のような演奏を感じることが出来ます。クライマックスに向けてオケもティンパニーなど、マレットが折れるのではと心配するほどの強打で熱演です。(笑)
チェリビダッケという人はとかく異端児扱いされがちな人ですが、近年、死後になって録音が様々発売され、再評価されています。なかなか、既存の音楽性には収まりきらない、真摯で壮大で有りながら、顕微鏡レベルのような緻密な音楽を作り上げているように思うのは私だけでしょうか。
バルトークがお好きな方、普通の演奏とは一味違ったチャイコフスキーの「ロメジュリ」をお探しの方にオススメの一枚です。
さて、5泊6日のたびの時に、不慣れなパッキングをしたのですが、下着をはじめとした着替えなどを詰めなければなりません。もうちょっと長い一週間とかを超えるようなものだと、着替えを宿泊先で洗濯とかする気になるのかもしれませんが、5泊という微妙な日程なので、やはり、全部着替えを持っていこうと思い、詰めてみました。
ところが私は大きなバッグを持っていないので、バッグに収まりきらないという事件が発生しました。私の持っているのは3WAYバッグなのですが、容量が20リットル足らずしかありません。ネットで検索しても、この容量で行けるのはせいぜい2泊までです。そこで…圧縮袋を採用しました。荷物がかなり減りはしましたが、それでもまだパンパンです。おまけに旅行の目的がスクーリングなので、教科書や参考書も持っていかねばなりませんでしたので、別のショルダーバッグも用意。
荷物が収まりきらず、どうにもならない状態になってしまいました。 考えて解決方法として、荷物を先に別便でホテルに送ってしまうことを選択しました。到着日指定で送れば、何とかなりそうです。それにバッグ買うよりも安いし、何より行きの荷物が減らせます。これはちょっと名案。早速別のバッグに4日分だけパッキングしてクロ○コヤマトで送りました。1日分は、もし、到着が遅れても大丈夫なようにという保険の意味をこめて自分で持っていきました。本当は行ってからが一番大変だったのですが。
さて今日の一枚です。
チェリビダッケ・エディションVol.1 NO.11
チャイコフスキー/ロメオとジュリエット
バルトーク/管弦楽のための協奏曲
指揮:セルジュ・チェリビダッケ
ミュンフェン・フィルハーモニー管弦楽団
東芝EMI TOCE-11611
このCDはチェリビダッケ指揮によるチャイコフスキーのロメオとジュリエット、バルトークの通称「オケコン」を収録したもの。
バルトークは日本人にまだまだ馴染みが薄い作曲家かもしれませんが、近年、日本でも様々な曲が取り上げられています。この、管弦楽のための協奏曲は、ナチスから逃れるため1940年、アメリカへ亡命したものの、アメリカではバルトークの音楽は理解されず、また白血病にも冒されるなど苦しい生活が続くなか、そのような窮状を見かねたボストン交響楽団音楽監督のクーセヴィツキーが委嘱。2ヶ月足らずで完成されたものです。
「管弦楽のための協奏曲」という作品名から分かるように、オーケストラのひとつひとつの楽器を独奏的に扱ったつくりになっています。5楽章で構成されており、第1楽章「序奏」、第2楽章「対の遊び」、第3楽章「悲歌」、第4楽章「中断された間奏曲」、第5楽章「終曲」というタイトルがつけられています。
このチェリビダッケの演奏はライヴ録音にもかかわらず、完成度の高い演奏で、一音一音を確認するかのような、まるで音に魂や愛情を込めるような遅いテンポでよくコントロールされたものになっています。緻密で濃厚な演奏で、空間的な奥行きスラ感じられる演奏です。オーケストラ全体が一つの楽器として響く感があって、表情豊かに歌われています。(第3楽章などはさすがに遅すぎな気もしなくは無いのですが。)
チャイコフスキーの通称「ロメジュリ」はゆっくりとしたテンポで濃厚に歌い上げられていて、もう本当に凄いというか凄まじい演奏です。指揮者もオケも聴衆も完全燃焼した感覚が伝わってきます。ロメオとジュリエット、二人を取り巻く登場人物の心象風景が見事に描きだされた名演です。はじめ聴いたときにはテンポのあまりの遅さにギョッとしたほどですが、聴いていくと音楽に対する真剣さと、大きく描き出された絵画のような演奏を感じることが出来ます。クライマックスに向けてオケもティンパニーなど、マレットが折れるのではと心配するほどの強打で熱演です。(笑)
チェリビダッケという人はとかく異端児扱いされがちな人ですが、近年、死後になって録音が様々発売され、再評価されています。なかなか、既存の音楽性には収まりきらない、真摯で壮大で有りながら、顕微鏡レベルのような緻密な音楽を作り上げているように思うのは私だけでしょうか。
バルトークがお好きな方、普通の演奏とは一味違ったチャイコフスキーの「ロメジュリ」をお探しの方にオススメの一枚です。
2008年06月21日
梅雨時。夏が来れば台風?
香川県は、水不足には悩む県なのですが、雨が少ない分、同じ四国でも高知などに比べれば、台風などのときに被害が少ないようです。雨は降らないでも困りますが、降りすぎて被害を及ぼすと大変なことになります。
雨が激しいと、大変です。台風の影響を受けやすい、沖縄や、高知の方たちは大変なのだろうと思います。何年か前に、高松も床下浸水に近い状態になったのですが、丁度、大潮と雨の多い時間が重なったためのことのようでした。それ以来、水浸しになった記憶は有りません。各地で大きな被害が出ないことを祈るばかりです。
さて、大雨と言うことで、今日の一枚。

TREASURES/山下達郎
MOON RECORDS AMCM-4240
このCDは1995年にリリースされた、山下達郎氏の1983年のムーンレコード移籍後、レーベル在籍12年目にして初めてリリースされたベストアルバムです。
曲目は、高気圧ガール、スプリンクラー、ゲット・バック・イン・ラブ、風の回廊(コリドー)、アトムの子、エンドレス・ゲーム、踊ろよ,フィッシュ、ターナーの汽罐車、土曜日の恋人、ジャングル・スウィング、世界の果てまで、おやすみロージー(Angel Babyへのオマージュ)、クリスマス・イブ、さよなら夏の日、蒼氓(そうぼう)、パレードの全16曲が収録されています。
で、何故大雨でこのアルバム?ということなのですが、2曲目に収録されている「スプリンクラー」と言う曲の冒頭に激しい雨の音が収録されているからです。実はこの雨の音、「太田裕美ライブ用素材テープ」から拝借しているようで、太田裕美さんのライブを見に行った方はひょっとしたら聴いたことがある音なのかもしれません。個人的想像では太田裕美さんの「セプテンバー・レイン」なんかに使われていたのではないかと思うのですが。
他の曲もCMやいろいろな場面でよく効く達郎サウンドの曲ばかりです。尚、「パレード」は、大瀧詠一氏、伊藤銀次氏、山下達郎氏の三人が参加したアルバム、「ナイアガラ・トライアングルVol.1」に収録されていた曲で、もしかしたら、皆さんの中では、「ポンキッキーズ」の曲として認識されている方も多いのでは内科と思います。こちらに収録されているのは大瀧詠一氏によるリミックスバージョンになっています。
山下達郎氏のファンは必聴ですが、「クリスマス・イブ」など、冬向きの曲もありますが、どちらかというと夏向きの曲が多いので、これから聴く音楽として、ぴったりです。
山下達郎氏がお好きな方、これから夏に向けて、「流行りもの」ではない上質のJ-POPサウンドをお探しの方にオススメの一枚です。
雨が激しいと、大変です。台風の影響を受けやすい、沖縄や、高知の方たちは大変なのだろうと思います。何年か前に、高松も床下浸水に近い状態になったのですが、丁度、大潮と雨の多い時間が重なったためのことのようでした。それ以来、水浸しになった記憶は有りません。各地で大きな被害が出ないことを祈るばかりです。
さて、大雨と言うことで、今日の一枚。
TREASURES/山下達郎
MOON RECORDS AMCM-4240
このCDは1995年にリリースされた、山下達郎氏の1983年のムーンレコード移籍後、レーベル在籍12年目にして初めてリリースされたベストアルバムです。
曲目は、高気圧ガール、スプリンクラー、ゲット・バック・イン・ラブ、風の回廊(コリドー)、アトムの子、エンドレス・ゲーム、踊ろよ,フィッシュ、ターナーの汽罐車、土曜日の恋人、ジャングル・スウィング、世界の果てまで、おやすみロージー(Angel Babyへのオマージュ)、クリスマス・イブ、さよなら夏の日、蒼氓(そうぼう)、パレードの全16曲が収録されています。
で、何故大雨でこのアルバム?ということなのですが、2曲目に収録されている「スプリンクラー」と言う曲の冒頭に激しい雨の音が収録されているからです。実はこの雨の音、「太田裕美ライブ用素材テープ」から拝借しているようで、太田裕美さんのライブを見に行った方はひょっとしたら聴いたことがある音なのかもしれません。個人的想像では太田裕美さんの「セプテンバー・レイン」なんかに使われていたのではないかと思うのですが。
他の曲もCMやいろいろな場面でよく効く達郎サウンドの曲ばかりです。尚、「パレード」は、大瀧詠一氏、伊藤銀次氏、山下達郎氏の三人が参加したアルバム、「ナイアガラ・トライアングルVol.1」に収録されていた曲で、もしかしたら、皆さんの中では、「ポンキッキーズ」の曲として認識されている方も多いのでは内科と思います。こちらに収録されているのは大瀧詠一氏によるリミックスバージョンになっています。
山下達郎氏のファンは必聴ですが、「クリスマス・イブ」など、冬向きの曲もありますが、どちらかというと夏向きの曲が多いので、これから聴く音楽として、ぴったりです。
山下達郎氏がお好きな方、これから夏に向けて、「流行りもの」ではない上質のJ-POPサウンドをお探しの方にオススメの一枚です。
2008年06月20日
訪問演奏会に向けて。
さて、、今週末、高松ウインドシンフォニーで小学校に訪問演奏に行ってきます。去年も行ってきたのですが、感想その1としては…学校はやっぱり暑いですね。体育館での演奏だったのですが、シャツがじっとりと汗ばむぐらいでした。当然香川県の小学校の体育館には冷房設備なんぞはありません。教室にも無いぐらいなので。まあ、同じような状況の県がほとんどだとは思いますが。
ポップスや同様のほかに楽器紹介として、各パートで短い局やフレーズを吹く、というものもあります。小学校の日曜参観日なので、その一環としての演奏会という形です。この小学校には楽団で毎年訪れていて、今年で、もう10年近くになります。
余談ですが、私が小学校に入学したろには、まだ、「父親参観日」と言う言葉が残っていたりしたものですが、それが、徐々に「父兄参観日」、「日曜参観日」と呼ばれるようになってきました。「父親」が来られない子どもや、「家族(父兄)」が来られない子どもに考慮して、という理由があるようですが、そこまで腫れ物に触る教育ってどうなんだろう?と疑問に思う部分も私としては有ります。
話が元に戻りますが、訪問演奏会では、曲目を何にしようか悩んだとき、曲選びに行き詰まったときは、困ったときの「ディズニー」、困ったときの「宮崎アニメ」と言うことになりがちです。今回の選曲もそれを王道で行くものになっています。
でも、やっぱり、訪問演奏会のプログラムもちゃんとしたものを
考えて、アニメやポップス、クラシックなどをバランスよく出来ればいいと思います。そういえば、今年は純粋なクラシックの曲が一曲もなっかったかもしれません。「ディズニー」や、「宮崎アニメ」は、皆が知っていて、受け入れやすいのは事実ですが、やはり、折角演奏に行くからには子供たちにとっても、クラッシクの入り口を紹介して上げられたら、とも思います。
でも、やっぱり、「宮崎アニメ」の「久石作品」は素晴らしい曲も多いので、皆に受け入れられるのが納得できるところでもあります。
そこで今日の一枚です。

風のとおり道/高嶋ちさ子
日本コロムビア COCQ-83460
このCDは高嶋ちさ子さんによる宮崎アニメのカヴァー曲集です。高嶋ちさ子さんといえば、フジテレビの軽部真一アナウンサーとの共同プロデュースによるシリーズコンサート「ギンザめざましクラシックス」や、テレビ番組での司会やレポーターとしての出演、クラシック界で初のベストジーニスト賞授賞、2003年公開の映画「踊る大走査線THE MOVIE2」への出演等でも有名な方です。曲目は、となりのトトロより「風のとおり道」、となりのトトロより「となりのトトロ」、風の谷のナウシカ、ルパン三世「ルパン三世のテーマ」、耳をすませばより「丘の町」、もののけ姫、母をたずねて三千里より「草原のマルコ」、魔女の宅急便より「旅立ち」、魔女の宅急便より「海の見える街」、魔女の宅急便より「晴れた日に」、天空の城ラピュタより「君をのせて」、紅の豚より「帰らざる日々」となっています。ルパン三世?と思う方もいるかもしれませんが、「カリオストロの城」が宮崎アニメの原点であることを考えると、この選曲も正しいものになります。
どれも親しみの持てる曲ばかりで、編曲もあまり奇をてらったものではなく、原曲のテイストをよく伝えながらのものになっています。
家族で楽しめるバイオリンの音楽をお探しの方に、宮崎アニメの大好きな方にオススメの一枚です。
ポップスや同様のほかに楽器紹介として、各パートで短い局やフレーズを吹く、というものもあります。小学校の日曜参観日なので、その一環としての演奏会という形です。この小学校には楽団で毎年訪れていて、今年で、もう10年近くになります。
余談ですが、私が小学校に入学したろには、まだ、「父親参観日」と言う言葉が残っていたりしたものですが、それが、徐々に「父兄参観日」、「日曜参観日」と呼ばれるようになってきました。「父親」が来られない子どもや、「家族(父兄)」が来られない子どもに考慮して、という理由があるようですが、そこまで腫れ物に触る教育ってどうなんだろう?と疑問に思う部分も私としては有ります。
話が元に戻りますが、訪問演奏会では、曲目を何にしようか悩んだとき、曲選びに行き詰まったときは、困ったときの「ディズニー」、困ったときの「宮崎アニメ」と言うことになりがちです。今回の選曲もそれを王道で行くものになっています。
でも、やっぱり、訪問演奏会のプログラムもちゃんとしたものを
考えて、アニメやポップス、クラシックなどをバランスよく出来ればいいと思います。そういえば、今年は純粋なクラシックの曲が一曲もなっかったかもしれません。「ディズニー」や、「宮崎アニメ」は、皆が知っていて、受け入れやすいのは事実ですが、やはり、折角演奏に行くからには子供たちにとっても、クラッシクの入り口を紹介して上げられたら、とも思います。
でも、やっぱり、「宮崎アニメ」の「久石作品」は素晴らしい曲も多いので、皆に受け入れられるのが納得できるところでもあります。
そこで今日の一枚です。

風のとおり道/高嶋ちさ子
日本コロムビア COCQ-83460
このCDは高嶋ちさ子さんによる宮崎アニメのカヴァー曲集です。高嶋ちさ子さんといえば、フジテレビの軽部真一アナウンサーとの共同プロデュースによるシリーズコンサート「ギンザめざましクラシックス」や、テレビ番組での司会やレポーターとしての出演、クラシック界で初のベストジーニスト賞授賞、2003年公開の映画「踊る大走査線THE MOVIE2」への出演等でも有名な方です。曲目は、となりのトトロより「風のとおり道」、となりのトトロより「となりのトトロ」、風の谷のナウシカ、ルパン三世「ルパン三世のテーマ」、耳をすませばより「丘の町」、もののけ姫、母をたずねて三千里より「草原のマルコ」、魔女の宅急便より「旅立ち」、魔女の宅急便より「海の見える街」、魔女の宅急便より「晴れた日に」、天空の城ラピュタより「君をのせて」、紅の豚より「帰らざる日々」となっています。ルパン三世?と思う方もいるかもしれませんが、「カリオストロの城」が宮崎アニメの原点であることを考えると、この選曲も正しいものになります。
どれも親しみの持てる曲ばかりで、編曲もあまり奇をてらったものではなく、原曲のテイストをよく伝えながらのものになっています。
家族で楽しめるバイオリンの音楽をお探しの方に、宮崎アニメの大好きな方にオススメの一枚です。
2008年06月19日
パソコン不調気味。
さて、最近パソコンが不調です。わりと安定して動作するXPなので、極度の不調にはなっていないのですが、やはり動きが遅かったり、PCがシャットダウンできずに強制的に電源を落とすようなことが増えています。 PCの世界は進化が早く、すぐに最新だったテクノロジーが陳腐化してしまいます。買い替えの時期は、と聴くと必ず、「買おうと思ったときが買いどき」みたいなことを言われますが、自分が買った直後に新しいものが出たりすると、ちょっと悔しい気がします。
ちなみに今のスペックは、メモリが716MB、ハードディスクが40GB、CPUはPEN-Mの1.5Ghzですオフィスソフトを動かすぐらいは全く問題ありませんが、DVDをいれて、ビデオ編集とかしょうとおもうと、ちょっとスペック不足です。新しいPCが欲しいのですが、今は予算が無いので見送るしかありません。音楽編集などにも使っています。 実は自分の演奏会の録音なども、PCを使って編集編集しているのですが、現在ノートPCということもあり、サウンドデバイスを使って取り込むのもは躊躇しています。おまけにOSがちょっと不安定気味なので、新たに重いソフトを入れるのはちょっと危険です。
考えてみれば、音楽の世界にもPCが大活躍するようになりました。以前は、何千万円も出して組んでいたシンセサイザーのサンプリングシステムが、今では、数万から数十万で出来てしまいます。
また、スタジオ録音などでも、必ずミキシングやトラックダウンにPCを使用するようになりました。伴奏をPCにさせる打ち込み系の音楽もPCの力なくしては作れません。
そこで今日の一枚。
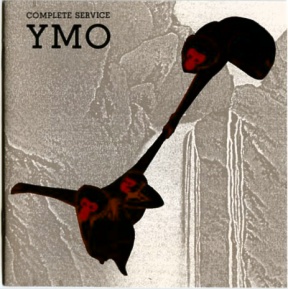
YMO/Complete Service
ALFA MUSIC ALCA-9055
このCDはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のライブを収録したもの。YMOは言わずと知れた、日本のテクノ・ポップの神様的存在です。1978年に細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏よってケ製されたテクノバンドです。彼らの当初の目的はテクノミュージックを作ることよりも、ハワイのミュージシャンであるマーティン・デニーの名曲「ファイアー・クラッカー」をシンセサイザーでカヴァーすることだったといわれています。このCDは割と活動後期のもので、「君に胸キュン」などのオヤジ・テクノ・ポップス的な曲がたくさん収録されています。
彼らはコンピューターミュージック、つまり、シーケンサー、デジタル・レコーダー、サンプラーといった、あらゆる最先端のテクノロジーをいち早く導入し、スタイルを少しずつ変貌させながら常に日本の音楽シーンをリードしてきました。しかし、1983年に突然に散開(解散じゃないのがミソ?)してしまいます。1993年に一時的に再生しました。海外への影響も絶大なものが有ります。
世代をすごした方にとっては懐かしい曲が収録されています。ただちょっと残念なことにCDとしてのオーディオ的な音質が余りよくありません。当時の録音の為か、以外にレンジの狭い、薄い音に聞こえる部分が散見しています。もちろん聴くに耐えないとか、そういう問題のレベルではなく、あくまでも音にこだわるなら、という話です。
YMO世代を懐かしみたい方、テクノ・ポップの源流を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
ちなみに今のスペックは、メモリが716MB、ハードディスクが40GB、CPUはPEN-Mの1.5Ghzですオフィスソフトを動かすぐらいは全く問題ありませんが、DVDをいれて、ビデオ編集とかしょうとおもうと、ちょっとスペック不足です。新しいPCが欲しいのですが、今は予算が無いので見送るしかありません。音楽編集などにも使っています。 実は自分の演奏会の録音なども、PCを使って編集編集しているのですが、現在ノートPCということもあり、サウンドデバイスを使って取り込むのもは躊躇しています。おまけにOSがちょっと不安定気味なので、新たに重いソフトを入れるのはちょっと危険です。
考えてみれば、音楽の世界にもPCが大活躍するようになりました。以前は、何千万円も出して組んでいたシンセサイザーのサンプリングシステムが、今では、数万から数十万で出来てしまいます。
また、スタジオ録音などでも、必ずミキシングやトラックダウンにPCを使用するようになりました。伴奏をPCにさせる打ち込み系の音楽もPCの力なくしては作れません。
そこで今日の一枚。
YMO/Complete Service
ALFA MUSIC ALCA-9055
このCDはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のライブを収録したもの。YMOは言わずと知れた、日本のテクノ・ポップの神様的存在です。1978年に細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏よってケ製されたテクノバンドです。彼らの当初の目的はテクノミュージックを作ることよりも、ハワイのミュージシャンであるマーティン・デニーの名曲「ファイアー・クラッカー」をシンセサイザーでカヴァーすることだったといわれています。このCDは割と活動後期のもので、「君に胸キュン」などのオヤジ・テクノ・ポップス的な曲がたくさん収録されています。
彼らはコンピューターミュージック、つまり、シーケンサー、デジタル・レコーダー、サンプラーといった、あらゆる最先端のテクノロジーをいち早く導入し、スタイルを少しずつ変貌させながら常に日本の音楽シーンをリードしてきました。しかし、1983年に突然に散開(解散じゃないのがミソ?)してしまいます。1993年に一時的に再生しました。海外への影響も絶大なものが有ります。
世代をすごした方にとっては懐かしい曲が収録されています。ただちょっと残念なことにCDとしてのオーディオ的な音質が余りよくありません。当時の録音の為か、以外にレンジの狭い、薄い音に聞こえる部分が散見しています。もちろん聴くに耐えないとか、そういう問題のレベルではなく、あくまでも音にこだわるなら、という話です。
YMO世代を懐かしみたい方、テクノ・ポップの源流を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年06月18日
宝島。
さて、11月にサクソフォーン・アンサンブルの演奏会をやるのですが、今年もその前に、州崎寺での演奏という大きなイベントがあります。その州崎寺での候補曲として先日上がったのが、「宝島」。数年前に秋のサクソフォーンアンサンブルコンサートで演奏したものです。」 皆さんは「宝島」と言うと、何を思い出すのでしょうか?出崎統(演出)と杉野昭夫(作画監督)によるアニメの「宝島」(「♪さあ、行こう~」のテーマソングが懐かしい)とか、その原作でもある、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説とか、あるいは、怪しげなことやアンダーグラウンドなことばかり扱っている例の雑誌とか、いろいろあると思いますが、吹奏楽をやったことがある人ならば、一番に思い出すのはやはり、ニュー・サウンズ・イン・ブラス版の「宝島」ではないかと思います。
この曲は以前この日記でも紹介したTHE SQUAREのS・P・O・R・T・STというアルバムの中の一曲を吹奏楽版にアレンジしたものです。ちなみにニュー・サウンズ・イン・ブラスとは毎年何曲かヤマハから出版される楽譜のシリーズで、岩井直溥氏を中心とした編曲者による吹奏楽用のポップスの楽譜です。この「宝島」も以前に出版されたこのニュー・サウンズ・イン・ブラスのシリーズの一曲なのですが、ちょっとラテンチックに編曲されていて、今や吹奏楽のポップスとしてのレパートリーには欠かせない存在になっています。
この楽譜、原曲のピアノ・ソロの部分が単音化されて、ほぼそのままアルト・サックス・ソロに移植されており、フラジオ奏法なども必要とするかなり難易度の高い楽譜になっています。元々、アドリブソロにはなっているのですが、楽譜には、記譜があります。
そこで今日の一枚です。

ニュー・サウンズ・イン・ブラス '87
指揮:岩井直溥
東京佼成ウインド・オーケストラ
東芝EMI CA30-1421
このCDは1987度に出版されたニュー・サウンズ・イン・ブラスの楽譜全曲を演奏したもの。毎年、佼成ウインドオーケストラの演奏でもう、30年ぐらい続いて出版されています。もちろん、「宝島」をはじめ、コパカバーナ、虹の彼方に、すべてをあなたに、ジャングル・ファンタジー、メリーゴーランド、フール・オン・ザ・ヒル、ストライク・アップ・ザ・バンド、ハレ、スタートレックといった、映画音楽、フュージョン、ポップス、JAZZなどのジャンルが収録されています。
実は「宝島」は、後年、ニュー・サウンズ・イン・ブラス25周年を記念したアルバムにも収録されているのですが、楽譜に近いアドリブソロが聞けるのは、こちらの古い盤です。編曲は真島俊夫氏です。
私は、数年前の母校の定期演奏会で、このアルト・サックスのソロを吹いたのですが、フラジオの練習に苦労しました。また、本番、マイクなどのPAを一切使わせてくれず、全て生音で吹ききるハメに。おまけに音大出身、在学者というつわもののいる金管群を相手にソロで勝負しなければならなくなり、精神的負担で髪の毛が抜けるかと思いました。結果、本番で、見事に金管群がmfの合いの手をffで吹ききってくれるという、ありがたい真っ向勝負をうけながら、何とか吹ききったのはよいのですが、フラジオは半分が不発で何を吹いたのか判らない有様に。その金管の方々に演奏後にサックスのベルをのぞかれ、「スピーカーとか入ってないよね。」(つまりPA使わなくても音がでかいってことです。)と言われる有様。後で録音を聞きましたが、ちょっと頑張って吹きすぎだったかもしれません。アルトサックス1本対金管楽器20数本の勝負には勝利したかもしれませんが。
さて、このCDの方は須川展也氏のきちんとした素晴らしいソロを聞くことが出来ます。吹奏楽でノリノリの音楽やポップスのスタンダードを聞くことが出来ます。
吹奏楽は、おもしろくないと思っている方、ポップスのBGMをお探しの方に是非聴いていただきたい、オススメの一枚です。
この曲は以前この日記でも紹介したTHE SQUAREのS・P・O・R・T・STというアルバムの中の一曲を吹奏楽版にアレンジしたものです。ちなみにニュー・サウンズ・イン・ブラスとは毎年何曲かヤマハから出版される楽譜のシリーズで、岩井直溥氏を中心とした編曲者による吹奏楽用のポップスの楽譜です。この「宝島」も以前に出版されたこのニュー・サウンズ・イン・ブラスのシリーズの一曲なのですが、ちょっとラテンチックに編曲されていて、今や吹奏楽のポップスとしてのレパートリーには欠かせない存在になっています。
この楽譜、原曲のピアノ・ソロの部分が単音化されて、ほぼそのままアルト・サックス・ソロに移植されており、フラジオ奏法なども必要とするかなり難易度の高い楽譜になっています。元々、アドリブソロにはなっているのですが、楽譜には、記譜があります。
そこで今日の一枚です。

ニュー・サウンズ・イン・ブラス '87
指揮:岩井直溥
東京佼成ウインド・オーケストラ
東芝EMI CA30-1421
このCDは1987度に出版されたニュー・サウンズ・イン・ブラスの楽譜全曲を演奏したもの。毎年、佼成ウインドオーケストラの演奏でもう、30年ぐらい続いて出版されています。もちろん、「宝島」をはじめ、コパカバーナ、虹の彼方に、すべてをあなたに、ジャングル・ファンタジー、メリーゴーランド、フール・オン・ザ・ヒル、ストライク・アップ・ザ・バンド、ハレ、スタートレックといった、映画音楽、フュージョン、ポップス、JAZZなどのジャンルが収録されています。
実は「宝島」は、後年、ニュー・サウンズ・イン・ブラス25周年を記念したアルバムにも収録されているのですが、楽譜に近いアドリブソロが聞けるのは、こちらの古い盤です。編曲は真島俊夫氏です。
私は、数年前の母校の定期演奏会で、このアルト・サックスのソロを吹いたのですが、フラジオの練習に苦労しました。また、本番、マイクなどのPAを一切使わせてくれず、全て生音で吹ききるハメに。おまけに音大出身、在学者というつわもののいる金管群を相手にソロで勝負しなければならなくなり、精神的負担で髪の毛が抜けるかと思いました。結果、本番で、見事に金管群がmfの合いの手をffで吹ききってくれるという、ありがたい真っ向勝負をうけながら、何とか吹ききったのはよいのですが、フラジオは半分が不発で何を吹いたのか判らない有様に。その金管の方々に演奏後にサックスのベルをのぞかれ、「スピーカーとか入ってないよね。」(つまりPA使わなくても音がでかいってことです。)と言われる有様。後で録音を聞きましたが、ちょっと頑張って吹きすぎだったかもしれません。アルトサックス1本対金管楽器20数本の勝負には勝利したかもしれませんが。
さて、このCDの方は須川展也氏のきちんとした素晴らしいソロを聞くことが出来ます。吹奏楽でノリノリの音楽やポップスのスタンダードを聞くことが出来ます。
吹奏楽は、おもしろくないと思っている方、ポップスのBGMをお探しの方に是非聴いていただきたい、オススメの一枚です。
2008年06月17日
マニアック。
今日もよい天気です。少し蒸し暑い感じですが、割と風があるので過ごしやすい一日になりそうです。
さて、ここ数日、「今日の一枚」でサクソフォーンアンサンブルのCDを紹介することが多かったのですが、読んでいる人はどうなのでしょう?人によってはぼちぼち飽きてきているのかもしれません。もし、私なら、所謂J-POPといわれる音楽の話が毎日延々と書いてある日記ならば、そのうち読みに行かなくなると思います。延々クラシックサクソフォーンのネタばかりでは、あまりにマニアックで、誰も読みに来ててくれなくなるかもしれません。
このブログ、普通の一般の方には、おもしろくも無いネタがほとんど思うのですが、私の日記が皆さんの感性の何かにい触れられるとよいなー、と思っています。実は、ニッチな世界のブログでありたいとも思っているのですが…。
よく、マニアックとか、オタク、とか、フリークという言葉を聞きますが、その違いに明確なものがあって使われているのでしょうか?確かに辞書や、現代用語の基礎○識や、イ○ダスを引けば、その言葉の違いも書いてあるのかもしれませんが、果たして、それが世間で通用している違いなのかどうかも明確な基準が無い限りわかりません。そういった意味では辞書も、現代○語の基礎知識もイミ○スも、言葉の入り口は教えてくれますが、生きた言葉は、やはり生きた場面で学ばなければいけない気がします。そうでなければ、正しい日本語だけど、どこか可笑しい日本語を使う外国人のようなしゃべりになってしまいます。意味の曖昧さも含めて言葉が使われていることを感じます。
ところで、人がどう言おうが、私はマニアックではありません。私の中でのマニアの認識だと、CD1000枚で済まされる世界では、有りません。ホントにマニアな人はCDを保管するために別に倉庫を借ります。オーディを聴くために家を立て直したり、新たにマンションを借りたりします。私は、とてもそんなことをしようとは思わないので、普通の音楽愛好家です。決して、マニアックな人では有りません。(笑)
そこで今日の一枚。

LEROY ANDERSON/COLLECTION
ルロイ・アンダーソン/コレクション
指揮:ルロイ・アンダーソン
このCDはルロイ・アンダーソンによる、自作自演集です。皆さんもアンダーソンの音楽はどこかで耳にしたことがあるはずです。「ラッパ吹きの休日」、「タイプライター」や、クリスマス時期になると必ずといっていいほど町に流れる「橇滑り」などが収録されています。曲目は2枚組みで全47曲。割と短い局ばかりなので、聴き疲れする事無く聞けると思います。今回はマニアックとは対極の万人に楽しめる音楽として選んでみました。(笑)
ブルー・タンゴ、ラッパ吹きの休日、春が来た、サンドペーパー・バレエ、ファントム・レジメント、レイディ・イン・ウェイティング、サラバンド、フィドル・ファドル、ザ・ガール・イン・サテン、タイプライター、ワルツィング・キャット、プリンク・プレンク・プランク、ピラミッド・ダンス、舞踏会の美女、忘れられし夢、チャイナ・ドール、ペニー・ホイッスル・ソング、ジャズ・ピチカート、ジャズ・レガート、シンコペイテッド・クロック、スコットランド組曲より「スコットランドの釣鐘草」、スコットランド組曲より「ターン・トゥ・ミー」、セレナータ、馬と馬車、トランペット吹きの子守歌、ベルの歌、サマー・スカイズ、プロムナード、橇滑り、クラリネット・キャンディ、ゴールデン・イヤーズ、レイジー・ムーン、アイ・ネヴァー・ノウ・ホエン、アリエッタ、プッシー・フット、ホーム・ストレッチ、小さなバラード、シャル・アイ・テイク・マイ・ハート、キャプテンたちと王様たち、タウン・ハウス・マシーシ、パイレート・ダンス、アイリッシュ組曲より「アイリッシュ・ウォッシャーウーマン」「ミンストレル・ボーイ」「レイクス・オブ・マロウ」「ウェアリング・オブ・ザ・グリーン」「ラスト・ローズ・オブ・サマー」「ガール・アイ・レフト・ビハインド・ミー」(流石に40曲超えると多いです。汗)が収録されています。
底抜けに楽しいアメリカ人的雰囲気のアルバムです。アンダーソンはユーモアとアイデアに溢れた楽しい作品を数多く残しています。「休日」なのにトランペット3本がせわしなく吹きまくったり(ラッパ吹きの休日)、タイプライターやサンドペーパーを楽器にしてしまったり(タイプライター、サンドペーパー・バレエ)、ヴァイオリンに猫の鳴き真似をさせたり(ワルツィング・キャット)などなど、それぞれの仕掛けも楽しめます。
家族で楽しめる音楽をお探しの方、クラシックがとっつきにくくて、入り口を探している方、楽しめるBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
さて、ここ数日、「今日の一枚」でサクソフォーンアンサンブルのCDを紹介することが多かったのですが、読んでいる人はどうなのでしょう?人によってはぼちぼち飽きてきているのかもしれません。もし、私なら、所謂J-POPといわれる音楽の話が毎日延々と書いてある日記ならば、そのうち読みに行かなくなると思います。延々クラシックサクソフォーンのネタばかりでは、あまりにマニアックで、誰も読みに来ててくれなくなるかもしれません。
このブログ、普通の一般の方には、おもしろくも無いネタがほとんど思うのですが、私の日記が皆さんの感性の何かにい触れられるとよいなー、と思っています。実は、ニッチな世界のブログでありたいとも思っているのですが…。
よく、マニアックとか、オタク、とか、フリークという言葉を聞きますが、その違いに明確なものがあって使われているのでしょうか?確かに辞書や、現代用語の基礎○識や、イ○ダスを引けば、その言葉の違いも書いてあるのかもしれませんが、果たして、それが世間で通用している違いなのかどうかも明確な基準が無い限りわかりません。そういった意味では辞書も、現代○語の基礎知識もイミ○スも、言葉の入り口は教えてくれますが、生きた言葉は、やはり生きた場面で学ばなければいけない気がします。そうでなければ、正しい日本語だけど、どこか可笑しい日本語を使う外国人のようなしゃべりになってしまいます。意味の曖昧さも含めて言葉が使われていることを感じます。
ところで、人がどう言おうが、私はマニアックではありません。私の中でのマニアの認識だと、CD1000枚で済まされる世界では、有りません。ホントにマニアな人はCDを保管するために別に倉庫を借ります。オーディを聴くために家を立て直したり、新たにマンションを借りたりします。私は、とてもそんなことをしようとは思わないので、普通の音楽愛好家です。決して、マニアックな人では有りません。(笑)
そこで今日の一枚。

LEROY ANDERSON/COLLECTION
ルロイ・アンダーソン/コレクション
指揮:ルロイ・アンダーソン
このCDはルロイ・アンダーソンによる、自作自演集です。皆さんもアンダーソンの音楽はどこかで耳にしたことがあるはずです。「ラッパ吹きの休日」、「タイプライター」や、クリスマス時期になると必ずといっていいほど町に流れる「橇滑り」などが収録されています。曲目は2枚組みで全47曲。割と短い局ばかりなので、聴き疲れする事無く聞けると思います。今回はマニアックとは対極の万人に楽しめる音楽として選んでみました。(笑)
ブルー・タンゴ、ラッパ吹きの休日、春が来た、サンドペーパー・バレエ、ファントム・レジメント、レイディ・イン・ウェイティング、サラバンド、フィドル・ファドル、ザ・ガール・イン・サテン、タイプライター、ワルツィング・キャット、プリンク・プレンク・プランク、ピラミッド・ダンス、舞踏会の美女、忘れられし夢、チャイナ・ドール、ペニー・ホイッスル・ソング、ジャズ・ピチカート、ジャズ・レガート、シンコペイテッド・クロック、スコットランド組曲より「スコットランドの釣鐘草」、スコットランド組曲より「ターン・トゥ・ミー」、セレナータ、馬と馬車、トランペット吹きの子守歌、ベルの歌、サマー・スカイズ、プロムナード、橇滑り、クラリネット・キャンディ、ゴールデン・イヤーズ、レイジー・ムーン、アイ・ネヴァー・ノウ・ホエン、アリエッタ、プッシー・フット、ホーム・ストレッチ、小さなバラード、シャル・アイ・テイク・マイ・ハート、キャプテンたちと王様たち、タウン・ハウス・マシーシ、パイレート・ダンス、アイリッシュ組曲より「アイリッシュ・ウォッシャーウーマン」「ミンストレル・ボーイ」「レイクス・オブ・マロウ」「ウェアリング・オブ・ザ・グリーン」「ラスト・ローズ・オブ・サマー」「ガール・アイ・レフト・ビハインド・ミー」(流石に40曲超えると多いです。汗)が収録されています。
底抜けに楽しいアメリカ人的雰囲気のアルバムです。アンダーソンはユーモアとアイデアに溢れた楽しい作品を数多く残しています。「休日」なのにトランペット3本がせわしなく吹きまくったり(ラッパ吹きの休日)、タイプライターやサンドペーパーを楽器にしてしまったり(タイプライター、サンドペーパー・バレエ)、ヴァイオリンに猫の鳴き真似をさせたり(ワルツィング・キャット)などなど、それぞれの仕掛けも楽しめます。
家族で楽しめる音楽をお探しの方、クラシックがとっつきにくくて、入り口を探している方、楽しめるBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
2008年06月16日
舌っ足らず。その2。
6月も既に半ばとなりました。
さて、昨日ちょっと、滑舌のことについて書きましたが、そこから、楽器の発音、タンギングのことを少し書きたいと思います。タンギングのタンというのはもちろん舌のことです。まあ、楽器を吹くときの滑舌と言ってもいいかもしれません。
このタンギング、普段しゃべっているときの発音も影響するようで、普段から、滑舌の悪いしゃべり方をしていると、楽器を吹くときにタンギングのトレーニングが余計に必要になるという話を聴いたことも有ります。真偽の程は定かではないので、なんともいえませんが、歌う代わりに楽器を鳴らしていることを考えると、あながちウソだとも言いがたいと思います。
舌のトレーニングは、なかなか難しく、実際楽器を使って今期よくやるしかないようです。綺麗に早く刻むのはやはり難しい技術なのかもしれません。このホームページにリンクを掲載させていただいている、トルヴェールクヮルテットのH先生オススメの楽器を使わないトレーニング方法は、舌を前歯の間にはさんで固定して、「トゥ」とか、「テ」とか、で着る練習をすることだそうです。舌が不自由になる分、効果が上がるようです。
私も、少しやってみましたが、歯ではさむのを止めたときの開放感は素晴らしいです。(笑)実際、自由になったときは舌がスムーズに動く感覚があるので、楽器を吹けないときには有効な練習方法なのかもしれません。
少しずつ、自分にあったトレーニング方法も見つけるとよいとは思うのですが、なかなか、自分ひとりでやっている分には、それも時間のかかる作業のようです。
そこで、今日の一枚です。

Grieg, Glazounov, Dvorák/Quatuor HABANERA
ハバネラ四重奏団
Alpha 041
このCDはフランスの若手サクソフォーン・クヮルテット、ハバネラ四重奏団の2枚目に当たるアルバムです。
Christian WIRTH, Sylvain MALÉZIEUX, Fabrizio MANCUSO, Gilles TRESSOS,という4人によって1993年に結成された、フランスで活動する団体です。オリジナルから現代曲、編曲ものといった多彩なレパートリーを持っています。現在、セルマー&ヴァンドレン・アーティストとして活動しています。(楽器はセルマー、マウスピースやリードはバンドレンという、宣伝活動を行なっているようです。)ボルドーで行なわれたロンデックス国際サクソフォーン・コンテストなどで1等を得るなど、、多くのコンクールで優秀な成績をおさめています。
曲目は、グリーグの組曲「ホルベルクの時代から」、グラズノフのサクソフォン4重奏曲 、ドヴォルザークの弦楽4重奏曲第12番「アメリカ」、といったアレンジものも含めて、正統派サクソフォン4重奏曲が集められています。ドヴォルザークのアメリカは日本でよく演奏されていた坂口新氏の編曲のものではなく、ソプラノのクリスティアン・ヴィルスによるもののようです。この「アメリカ」全曲をしっかりした団体の演奏で聴くことができるのは現在このCDぐらいでしょうか。また、昨日、八重奏で紹介したホルベルクを4人で見事に演奏しています。
演奏は、抑制されたヴィヴラートと緻密に組み立てられた音楽、高い技術力で、目のさめるような演奏です。弦楽器からの編曲にもかかわらず、タンギングも見事に処理されています。グラズノフの演奏も正統派な中に、現代的な雰囲気を感じさせる演奏です。少しーシャープに過ぎる部分も感じられますが、無理に作った印象派無く、自然に聴ける感じのどちらかといえば、クリアな演奏という感じです。
サクソフォーンを吹く全ての方、ドヴォルザークの名曲をサクソフォーンの音色で聴いてみたい方、にオススメの一枚です。
さて、昨日ちょっと、滑舌のことについて書きましたが、そこから、楽器の発音、タンギングのことを少し書きたいと思います。タンギングのタンというのはもちろん舌のことです。まあ、楽器を吹くときの滑舌と言ってもいいかもしれません。
このタンギング、普段しゃべっているときの発音も影響するようで、普段から、滑舌の悪いしゃべり方をしていると、楽器を吹くときにタンギングのトレーニングが余計に必要になるという話を聴いたことも有ります。真偽の程は定かではないので、なんともいえませんが、歌う代わりに楽器を鳴らしていることを考えると、あながちウソだとも言いがたいと思います。
舌のトレーニングは、なかなか難しく、実際楽器を使って今期よくやるしかないようです。綺麗に早く刻むのはやはり難しい技術なのかもしれません。このホームページにリンクを掲載させていただいている、トルヴェールクヮルテットのH先生オススメの楽器を使わないトレーニング方法は、舌を前歯の間にはさんで固定して、「トゥ」とか、「テ」とか、で着る練習をすることだそうです。舌が不自由になる分、効果が上がるようです。
私も、少しやってみましたが、歯ではさむのを止めたときの開放感は素晴らしいです。(笑)実際、自由になったときは舌がスムーズに動く感覚があるので、楽器を吹けないときには有効な練習方法なのかもしれません。
少しずつ、自分にあったトレーニング方法も見つけるとよいとは思うのですが、なかなか、自分ひとりでやっている分には、それも時間のかかる作業のようです。
そこで、今日の一枚です。

Grieg, Glazounov, Dvorák/Quatuor HABANERA
ハバネラ四重奏団
Alpha 041
このCDはフランスの若手サクソフォーン・クヮルテット、ハバネラ四重奏団の2枚目に当たるアルバムです。
Christian WIRTH, Sylvain MALÉZIEUX, Fabrizio MANCUSO, Gilles TRESSOS,という4人によって1993年に結成された、フランスで活動する団体です。オリジナルから現代曲、編曲ものといった多彩なレパートリーを持っています。現在、セルマー&ヴァンドレン・アーティストとして活動しています。(楽器はセルマー、マウスピースやリードはバンドレンという、宣伝活動を行なっているようです。)ボルドーで行なわれたロンデックス国際サクソフォーン・コンテストなどで1等を得るなど、、多くのコンクールで優秀な成績をおさめています。
曲目は、グリーグの組曲「ホルベルクの時代から」、グラズノフのサクソフォン4重奏曲 、ドヴォルザークの弦楽4重奏曲第12番「アメリカ」、といったアレンジものも含めて、正統派サクソフォン4重奏曲が集められています。ドヴォルザークのアメリカは日本でよく演奏されていた坂口新氏の編曲のものではなく、ソプラノのクリスティアン・ヴィルスによるもののようです。この「アメリカ」全曲をしっかりした団体の演奏で聴くことができるのは現在このCDぐらいでしょうか。また、昨日、八重奏で紹介したホルベルクを4人で見事に演奏しています。
演奏は、抑制されたヴィヴラートと緻密に組み立てられた音楽、高い技術力で、目のさめるような演奏です。弦楽器からの編曲にもかかわらず、タンギングも見事に処理されています。グラズノフの演奏も正統派な中に、現代的な雰囲気を感じさせる演奏です。少しーシャープに過ぎる部分も感じられますが、無理に作った印象派無く、自然に聴ける感じのどちらかといえば、クリアな演奏という感じです。
サクソフォーンを吹く全ての方、ドヴォルザークの名曲をサクソフォーンの音色で聴いてみたい方、にオススメの一枚です。
2008年06月15日
舌っ足らず。
今日もいいお天気になりました。梅雨が明けるまでにはまだしばらくかかるようですが、今週は比較的よいお天気が続きそうです。
さて、今朝、目が覚めると、舌が痛いのに気づきました。舌に口内炎ができたようで、他にも口の中に口内炎が出来ていました。私は疲れがたまると、口内炎がよく出来ます。こちらのほうの方言で、舌等に口内炎が出来ることを「けんびきが出来る。」といいますが、この「けんびき」がよく出来ます。
実は舌が痛いのは口内炎だけではなく、この間の日曜日の練習の時に舌を酷使したため、軽くしたが切れているようです。まあ、2~3日すれば、両方とも治ると思いますが、それまでは醤油や、暑いものがしみてちょっと痛い思いをするかもしれません。
私は、普段別に滑舌(活舌?)が悪い方でもないのですが、やはり、舌に「けんびき」ができると、舌っ足らずになってしまいます。ちなみに滑舌(かつぜつ)は、おそらく、PCでは変換出来ません。「IME」や、「ことえり」、「ATOK」などの辞書にも無いようです。もともと、ことばを仕事にする人びとの間で使われていた専門用語のようで、アナウンサーの新人研修のときになどに使われていたようです。「滑舌」と「活舌」の二通りの表記があるようで、一般的には「滑舌」が多く使われていますが最近は「闊舌」と言う表記も時々見かけます。国語辞典などにもあまり表記されているものが無いようで、辞書の説明では、「発音練習」とされているものが多い様です。しかし、現在、「滑舌が良い(悪い)」のように使われることが多く、「舌の滑らかな動き」として使われているようです。
舌の動きはトレーニングによっても、ある程度コントロールできるようですが、私はまだまだ、それが足りないのかもしれません。
プロの演奏家の方に比べると、まだまだ、舌っ足らずです。
そこで今日の一枚です。
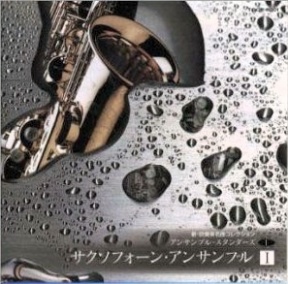
新・吹奏楽名曲コレクション
アンサンブル・スタンダーズVol.1
サクソフォーンアンサンブル1 須川展也と若き名手たち
須川 展也、大城 正司、成田 徹、
大貫 比佐志、大和田 雅洋、栄村 正吾、
二宮 和弘、平野 公崇
東芝EMI TOCF-6001
このCDはサクソフォーン八重奏で演奏された、アレンジものを集めた一枚です。須川展也と若き名手たちという、ネーミングはいかがなものかと思いますが、須川氏はサックス界のみならず、各方面でも知られた有名人ですので、こういった書き方になるのかもしれません。メンバーを見ると世代的にも、須川氏が一世代上の人物のようでもあります。しかしながら、他のメンバーの方も日本サクソフォーン界の第一線で活躍される、トッププレーヤーの方ばかりです。知名度こそ、須川氏ほどは無いかもしれませんが、素晴らしい演奏を聞かせてくれます。そういった意味ではまさに「若き名手」という言い方は正解なのかもしれません。どのくらいまでが「若き」なのかは疑問も感じますが。収録曲は、ホルベルクの組曲(グリーグ) 、古典組曲(矢代秋雄) 、序奏とアレグロ(エルガー)
ラ・ヴァルス(ラヴェル) の4曲です。
さて、演奏の方は技術的にはもう、文句のつけようがありません。しいて言うならば、もう少し、曲を吟味して練り上げた表現を
して欲しかった気もしますが、指揮者の居ない、8人という人数等を考えると、仕方の無いことかもしれません。ソリスト級の人たちの集まりだからかもしれませんが。この中のホルベルク組曲は私も1楽章と2楽章を同じ楽譜で演奏したことがありますが、結構たいへんでした。特に1楽章のアルト、テナーは延々、刻みがあって、テンポからも考えると、ダブルタンギングを必要とするのですが、それがなかなかきついことでした。まさに、舌っ足らずな演奏になってしまいながらの練習が続いた記憶があります。
サックスの八重奏の演奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、今朝、目が覚めると、舌が痛いのに気づきました。舌に口内炎ができたようで、他にも口の中に口内炎が出来ていました。私は疲れがたまると、口内炎がよく出来ます。こちらのほうの方言で、舌等に口内炎が出来ることを「けんびきが出来る。」といいますが、この「けんびき」がよく出来ます。
実は舌が痛いのは口内炎だけではなく、この間の日曜日の練習の時に舌を酷使したため、軽くしたが切れているようです。まあ、2~3日すれば、両方とも治ると思いますが、それまでは醤油や、暑いものがしみてちょっと痛い思いをするかもしれません。
私は、普段別に滑舌(活舌?)が悪い方でもないのですが、やはり、舌に「けんびき」ができると、舌っ足らずになってしまいます。ちなみに滑舌(かつぜつ)は、おそらく、PCでは変換出来ません。「IME」や、「ことえり」、「ATOK」などの辞書にも無いようです。もともと、ことばを仕事にする人びとの間で使われていた専門用語のようで、アナウンサーの新人研修のときになどに使われていたようです。「滑舌」と「活舌」の二通りの表記があるようで、一般的には「滑舌」が多く使われていますが最近は「闊舌」と言う表記も時々見かけます。国語辞典などにもあまり表記されているものが無いようで、辞書の説明では、「発音練習」とされているものが多い様です。しかし、現在、「滑舌が良い(悪い)」のように使われることが多く、「舌の滑らかな動き」として使われているようです。
舌の動きはトレーニングによっても、ある程度コントロールできるようですが、私はまだまだ、それが足りないのかもしれません。
プロの演奏家の方に比べると、まだまだ、舌っ足らずです。
そこで今日の一枚です。
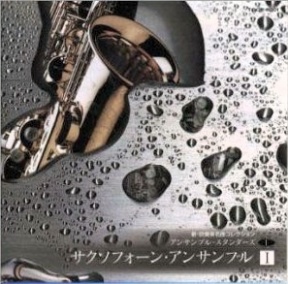
新・吹奏楽名曲コレクション
アンサンブル・スタンダーズVol.1
サクソフォーンアンサンブル1 須川展也と若き名手たち
須川 展也、大城 正司、成田 徹、
大貫 比佐志、大和田 雅洋、栄村 正吾、
二宮 和弘、平野 公崇
東芝EMI TOCF-6001
このCDはサクソフォーン八重奏で演奏された、アレンジものを集めた一枚です。須川展也と若き名手たちという、ネーミングはいかがなものかと思いますが、須川氏はサックス界のみならず、各方面でも知られた有名人ですので、こういった書き方になるのかもしれません。メンバーを見ると世代的にも、須川氏が一世代上の人物のようでもあります。しかしながら、他のメンバーの方も日本サクソフォーン界の第一線で活躍される、トッププレーヤーの方ばかりです。知名度こそ、須川氏ほどは無いかもしれませんが、素晴らしい演奏を聞かせてくれます。そういった意味ではまさに「若き名手」という言い方は正解なのかもしれません。どのくらいまでが「若き」なのかは疑問も感じますが。収録曲は、ホルベルクの組曲(グリーグ) 、古典組曲(矢代秋雄) 、序奏とアレグロ(エルガー)
ラ・ヴァルス(ラヴェル) の4曲です。
さて、演奏の方は技術的にはもう、文句のつけようがありません。しいて言うならば、もう少し、曲を吟味して練り上げた表現を
して欲しかった気もしますが、指揮者の居ない、8人という人数等を考えると、仕方の無いことかもしれません。ソリスト級の人たちの集まりだからかもしれませんが。この中のホルベルク組曲は私も1楽章と2楽章を同じ楽譜で演奏したことがありますが、結構たいへんでした。特に1楽章のアルト、テナーは延々、刻みがあって、テンポからも考えると、ダブルタンギングを必要とするのですが、それがなかなかきついことでした。まさに、舌っ足らずな演奏になってしまいながらの練習が続いた記憶があります。
サックスの八重奏の演奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年06月14日
価格相応なのか。
今日はよいお天気です。梅雨時ですが、明日も晴れるらしいです。水不足が多少懸念されますが…。
昨日、ジーンズを洗濯したのですが、夕方乾いたのを確認していると、………あ、穴が………。夏向きの色の薄めのブルージーンズなのですが、お尻のポケットの横に穴が。今まで私はジーンズを何10本もはいたと思うのですが、大抵今までのジーンズはひざから抜けて破れが広がることがほとんどでした。ひざ抜けはある程度、使い古した「いい感じ」なので穴が空いてもしばらくははけますが、お尻の周辺にあいた穴はそうはいきません。
そういえば、高校生の頃、リーバ○スの限定復刻の502XXというジーンズ(赤耳、ペーパータグというビンテージの復刻)を1万円以上出して買ったのですが、ひざ抜けしたときに祖母に思いっきり刺繍糸か何かで穴を繕われて、恥ずかしくてはけなくなりました。小さな親切、大きなお世話、というのを絵に書いたような出来事でした。あれ以来、リー○イスのジーンズでも1万を超えるような高級なジーンズは買っていません。
今回穴のあいたジーンズは実はユニ○クロ製のものです。しかもセールで3000円しなかった記憶が。うーむ、こういってしまうとなんですが、買ってから、1年足らずです。今までで穴のあいたジーンズとしては最短記録を更新してしまいました。そんなにヘビーな使い方をしていないので、これはやっぱり、モノに違いがあるのかもしれません。現に同じ頃買ったリ○バイスは、今何処も破れたりせずにはけています。
私はアパレル関係のことには疎いのでわかりませんが、決して、ユニ○ロの製品は「安かろう、悪かろう」の品ではないと思うのですが、流通の仕組みが違うとはいえ、3000円で、売るものと7000円で売るものが全く同じような素材や、手間をかけているのでは無い気がします。やっぱりいいものを作ろうとすると、それだけ手間やお金がかかるのも事実でそれが価格に反映されていても何の不思議でもありません。ただ、この世の中には俗にいう、「ぼったくる」製品も中にはあるようなので、それは賢い消費者になって選ぶ必要があるのだと思います。
価格相応な品であることも大切ですが、自分でそれを吟味して価格相応かどうかを判断することが出来るようになるのも重要なのかもしれません。
そこで今日の一枚です。
フルトヴェングラー名演集 VOL.6
ダイソー(大創産業)CD-C-25
このCDは100円ショップで購入したものです。つまり払ったお金は105円です。100円ショップには結構な種類のCDがあります。クラシックからジャズ、ポップスやムードミュージックからロック、民謡、落語、講談など様々な種類のCDが並んでいます。
ステレオ録音のものもあるのですが、このCDは音源が音源だけにモノラルです。曲目はメンデルスゾーンの真夏の世の夢から「序曲」、ロッシーニ「泥棒かささぎ」序曲、ベートーベン「エグモント」序曲、ウエーバーの「魔弾の射手」序曲、ヨハンシュトラウス2世の「蝙蝠」序曲、の全5曲です。時間がちょっと短めな気もしますが、100円のことを考えると許せる範囲かと思います。
録音の方は、どこかで演奏会のライブ録音をしたものの寄せ集めみたいなことを書いてありますが、録音データが一切記載されていないのでわかりません。ちなみに演奏団体の名前が書いていないので、ベルリンフィルかどうかも定かではありません。出来れば、100円と言う値段の制約があるにしろ、この辺のことはちゃんと書いてほしかったという希望があります。
演奏の方はフルトヴェングラーらしい、重厚で柔らかな響きに仕上げられた曲を聞くことが出来ます。歌い方や、テンポどりの仕方なども、なるほど、と思う部分があったりします。ただ、やはり、録音自体は最悪で、録音の質にこだわる方にはあまりオススメできません。イメージとしては素人がオープンリールとマイク一本で録った音という感じです。フルトヴェングラーの時代の録音でも、ベートーヴェンの交響曲などのように比較的良い音で録音されているものが数多くありますが、それと比べるべきではない録音です。
安価にフルトヴェングラーの演奏を聴いてみたい方、音質にこだわらず、とにかく、上に書いたような曲の演奏が聴きたい方に、オススメの一枚です。
昨日、ジーンズを洗濯したのですが、夕方乾いたのを確認していると、………あ、穴が………。夏向きの色の薄めのブルージーンズなのですが、お尻のポケットの横に穴が。今まで私はジーンズを何10本もはいたと思うのですが、大抵今までのジーンズはひざから抜けて破れが広がることがほとんどでした。ひざ抜けはある程度、使い古した「いい感じ」なので穴が空いてもしばらくははけますが、お尻の周辺にあいた穴はそうはいきません。
そういえば、高校生の頃、リーバ○スの限定復刻の502XXというジーンズ(赤耳、ペーパータグというビンテージの復刻)を1万円以上出して買ったのですが、ひざ抜けしたときに祖母に思いっきり刺繍糸か何かで穴を繕われて、恥ずかしくてはけなくなりました。小さな親切、大きなお世話、というのを絵に書いたような出来事でした。あれ以来、リー○イスのジーンズでも1万を超えるような高級なジーンズは買っていません。
今回穴のあいたジーンズは実はユニ○クロ製のものです。しかもセールで3000円しなかった記憶が。うーむ、こういってしまうとなんですが、買ってから、1年足らずです。今までで穴のあいたジーンズとしては最短記録を更新してしまいました。そんなにヘビーな使い方をしていないので、これはやっぱり、モノに違いがあるのかもしれません。現に同じ頃買ったリ○バイスは、今何処も破れたりせずにはけています。
私はアパレル関係のことには疎いのでわかりませんが、決して、ユニ○ロの製品は「安かろう、悪かろう」の品ではないと思うのですが、流通の仕組みが違うとはいえ、3000円で、売るものと7000円で売るものが全く同じような素材や、手間をかけているのでは無い気がします。やっぱりいいものを作ろうとすると、それだけ手間やお金がかかるのも事実でそれが価格に反映されていても何の不思議でもありません。ただ、この世の中には俗にいう、「ぼったくる」製品も中にはあるようなので、それは賢い消費者になって選ぶ必要があるのだと思います。
価格相応な品であることも大切ですが、自分でそれを吟味して価格相応かどうかを判断することが出来るようになるのも重要なのかもしれません。
そこで今日の一枚です。
フルトヴェングラー名演集 VOL.6
ダイソー(大創産業)CD-C-25
このCDは100円ショップで購入したものです。つまり払ったお金は105円です。100円ショップには結構な種類のCDがあります。クラシックからジャズ、ポップスやムードミュージックからロック、民謡、落語、講談など様々な種類のCDが並んでいます。
ステレオ録音のものもあるのですが、このCDは音源が音源だけにモノラルです。曲目はメンデルスゾーンの真夏の世の夢から「序曲」、ロッシーニ「泥棒かささぎ」序曲、ベートーベン「エグモント」序曲、ウエーバーの「魔弾の射手」序曲、ヨハンシュトラウス2世の「蝙蝠」序曲、の全5曲です。時間がちょっと短めな気もしますが、100円のことを考えると許せる範囲かと思います。
録音の方は、どこかで演奏会のライブ録音をしたものの寄せ集めみたいなことを書いてありますが、録音データが一切記載されていないのでわかりません。ちなみに演奏団体の名前が書いていないので、ベルリンフィルかどうかも定かではありません。出来れば、100円と言う値段の制約があるにしろ、この辺のことはちゃんと書いてほしかったという希望があります。
演奏の方はフルトヴェングラーらしい、重厚で柔らかな響きに仕上げられた曲を聞くことが出来ます。歌い方や、テンポどりの仕方なども、なるほど、と思う部分があったりします。ただ、やはり、録音自体は最悪で、録音の質にこだわる方にはあまりオススメできません。イメージとしては素人がオープンリールとマイク一本で録った音という感じです。フルトヴェングラーの時代の録音でも、ベートーヴェンの交響曲などのように比較的良い音で録音されているものが数多くありますが、それと比べるべきではない録音です。
安価にフルトヴェングラーの演奏を聴いてみたい方、音質にこだわらず、とにかく、上に書いたような曲の演奏が聴きたい方に、オススメの一枚です。
2008年06月13日
たまに聞きたくなる。
以前書いたことがあると思いますが、私は現在使用できる状態のレコードプレーヤーを持っていません。
それに対して、LPレコードは何枚か持っています。本当はレコードが聴けるようにレコードプレーヤーが欲しいのですが、しっかりしたレコードプレーヤーを購入するとなると、数万円以上、さらに私のプリメインアンプにはフォノイコライザーが搭載されていないので、フォノイコライザーと昇圧トランスなどを買い揃えることになります。かなりの出費、たまにレコードは聴きたくなりますが、今はCDだけで我慢しています。
一番困るのは、参考音源として聞きたいときなどにも、再生すら出来ないということ。妥協して、安いプレーヤーを買ってもいいかなと時々思うのですが、それも安物買いのなんとかという奴になりそうで躊躇してしまいます。
そこで今日の一枚です。
組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編曲)
交響詩「禿山の一夜」
指揮:ユージン・オーマンディ
フィラデルフィア管弦楽団
オーマンディ音の響宴1300 Vol.13
CBSソニー SOCT-13
これはCDではなくLPです。私がはじめて手に入れた禿山の一夜が収録されたレコードでした。この時代のフィラデルフィア管弦楽団は、黄金のフィラデルフィア・サウンドといわれた時代で、まさに輝かしくキラキラを通り越してギラギラに近い音色です。カラヤン&ベルリンフィルの演奏しか聴いたことの無いような人が、この演奏を聞くとまさに度肝を抜かれたことでしょう。冒頭のプロムナードのトランペットの音からして既にキラキラです。輝かしいことッこの上ない音色です。金粉がとびっちって来そうなくらいの勢いの音です。
さらにオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の演奏自体もまさに黄金期の時代です。オーマンディは演奏効果を上げるために部分的に楽譜を改変したり、オーケストラの編成を変更したりしていたようです。このレコードのジャケットの写真(展覧会の絵の演奏時ではないかもしれませんが)を見る限り、オーボエやフルート、ファゴットなどが4人ずつ居るという、あまり見ない木管楽器の倍管が行なわれているようです。
禿山の一夜でも同様に明るい輝かしい響きが聞かれます。しかし、只単に明るく派手な軽い演奏ではなく、しっかりとした重厚な響きとしっかりとしたアンサンブル、卓越したテクニックを聞き取ることが出来ます。
音の印象としては、ロシア(当時ソ連)のオケの対極にある最右翼的なサウンド、といったらわかりやすい表現かも(余計わかりにくい表現かも)しれません。今は聞けないので、以前レコードをカセットテープに録音したものを聞いています。
輝かしい黄金のフィラデルフィアサウンドを聴きたい方、ドイツ系のオケの音や、ロシア系のオケの音と違う響きを聴いてみたい方にオススメのレコードです。
それに対して、LPレコードは何枚か持っています。本当はレコードが聴けるようにレコードプレーヤーが欲しいのですが、しっかりしたレコードプレーヤーを購入するとなると、数万円以上、さらに私のプリメインアンプにはフォノイコライザーが搭載されていないので、フォノイコライザーと昇圧トランスなどを買い揃えることになります。かなりの出費、たまにレコードは聴きたくなりますが、今はCDだけで我慢しています。
一番困るのは、参考音源として聞きたいときなどにも、再生すら出来ないということ。妥協して、安いプレーヤーを買ってもいいかなと時々思うのですが、それも安物買いのなんとかという奴になりそうで躊躇してしまいます。
そこで今日の一枚です。
組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編曲)
交響詩「禿山の一夜」
指揮:ユージン・オーマンディ
フィラデルフィア管弦楽団
オーマンディ音の響宴1300 Vol.13
CBSソニー SOCT-13
これはCDではなくLPです。私がはじめて手に入れた禿山の一夜が収録されたレコードでした。この時代のフィラデルフィア管弦楽団は、黄金のフィラデルフィア・サウンドといわれた時代で、まさに輝かしくキラキラを通り越してギラギラに近い音色です。カラヤン&ベルリンフィルの演奏しか聴いたことの無いような人が、この演奏を聞くとまさに度肝を抜かれたことでしょう。冒頭のプロムナードのトランペットの音からして既にキラキラです。輝かしいことッこの上ない音色です。金粉がとびっちって来そうなくらいの勢いの音です。
さらにオーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団の演奏自体もまさに黄金期の時代です。オーマンディは演奏効果を上げるために部分的に楽譜を改変したり、オーケストラの編成を変更したりしていたようです。このレコードのジャケットの写真(展覧会の絵の演奏時ではないかもしれませんが)を見る限り、オーボエやフルート、ファゴットなどが4人ずつ居るという、あまり見ない木管楽器の倍管が行なわれているようです。
禿山の一夜でも同様に明るい輝かしい響きが聞かれます。しかし、只単に明るく派手な軽い演奏ではなく、しっかりとした重厚な響きとしっかりとしたアンサンブル、卓越したテクニックを聞き取ることが出来ます。
音の印象としては、ロシア(当時ソ連)のオケの対極にある最右翼的なサウンド、といったらわかりやすい表現かも(余計わかりにくい表現かも)しれません。今は聞けないので、以前レコードをカセットテープに録音したものを聞いています。
輝かしい黄金のフィラデルフィアサウンドを聴きたい方、ドイツ系のオケの音や、ロシア系のオケの音と違う響きを聴いてみたい方にオススメのレコードです。
2008年06月12日
練習。
最近、 毎週土曜日は夕方から恒例の「高松ウインドシンフォニー」練習、そして、日曜日はダッパーサクセーバーズの練習or本番というのがデフォルト化していましたが、先日のの日曜はたまま何もなく、ボーっと過ごしました。練習といえば、前回の土曜日の練習でリードを割ってしまいました。新しいリードをを選びなおす必要があります。私はアルトサックスでは、バンドレンのトラディショナルの4番を使っています。わからない方には意味不明の暗号になってしまいますが…。
次の日曜日はウインドシンフォニーの本番と、ダッパーの練習がダブルヘッダーです。
アンサンブル、と思って、よくよく考えると、自分達がいつも行なっているアンサンブルコンサートが11月にあるのですが、もう、5ヶ月しかありません。いつも練習不足の私、個人練習もほとんど出来ていません。 もうそろそろ、練習の方もきちんと計画してはじめなければ、間に合わなくなります。プログラムの詳細等が決まったら、また、こちらで紹介させていただきます。
それでは、今日の一枚です。

アルモ・サクソフォン・クヮルテット/フランスのエスプリ
中村 均一(Soprano)、遠藤 朱実(Alto)
松雪 明(Tenor)、栃尾 克樹(Baritone)
Orange Note (マイスターミュージック)ON-3013
このCDはアルモの3枚目に当たるアルバムです。タイトルどおり、フランスの作曲家による弦楽4重奏曲 (ドビュッシー)、組曲「ドリー」より (フォーレ)、サクソフォン4重奏曲 (ベルノー)の曲目が収録されています。ベルノー以外はアレンジ物で、ベルノーの作品のみサクソフォーンようのオリジナル曲です。この、ドビュッシーの曲は弦楽の演奏でもよく耳にしますが、弦楽器に近い響きがするとされているサクソフォン・クヮルテットでも、作品として仕上げるにはかなりの技術と工夫が必要な曲です。また、「ドリー」組曲は私も、同じ楽譜を手に入れて演奏したのですが、なかなか、上品で、軽やかな演奏にならない上、響きを作るためのピッチコントロールや、調による曲の捉え方が難しく、苦労しました。ちなみに私の演奏はボロボロでした。(泣)ドビュッシーは、海外のオーレリア・サクソフォーン・クヮルテットなども演奏していますが、私は、緻密さと、丁寧さ、上品さではアルモの演奏を取ると思います。ただ、少し曲を冷静に見つめすぎている感じもあるので、その点はオーレリアの演奏も捨てがたい気がします。
しかしながら、演奏はアルモらしい、しなやかで上品な表現、きっちりとした技術に裏付けられた演奏なので、素晴らしいものです。
サクソフォーンを吹く全ての方、フランス近代の音楽をサックスで聴いてみたい方、ドビュッシーがお好きな方にオススメの一枚です。
次の日曜日はウインドシンフォニーの本番と、ダッパーの練習がダブルヘッダーです。
アンサンブル、と思って、よくよく考えると、自分達がいつも行なっているアンサンブルコンサートが11月にあるのですが、もう、5ヶ月しかありません。いつも練習不足の私、個人練習もほとんど出来ていません。 もうそろそろ、練習の方もきちんと計画してはじめなければ、間に合わなくなります。プログラムの詳細等が決まったら、また、こちらで紹介させていただきます。
それでは、今日の一枚です。

アルモ・サクソフォン・クヮルテット/フランスのエスプリ
中村 均一(Soprano)、遠藤 朱実(Alto)
松雪 明(Tenor)、栃尾 克樹(Baritone)
Orange Note (マイスターミュージック)ON-3013
このCDはアルモの3枚目に当たるアルバムです。タイトルどおり、フランスの作曲家による弦楽4重奏曲 (ドビュッシー)、組曲「ドリー」より (フォーレ)、サクソフォン4重奏曲 (ベルノー)の曲目が収録されています。ベルノー以外はアレンジ物で、ベルノーの作品のみサクソフォーンようのオリジナル曲です。この、ドビュッシーの曲は弦楽の演奏でもよく耳にしますが、弦楽器に近い響きがするとされているサクソフォン・クヮルテットでも、作品として仕上げるにはかなりの技術と工夫が必要な曲です。また、「ドリー」組曲は私も、同じ楽譜を手に入れて演奏したのですが、なかなか、上品で、軽やかな演奏にならない上、響きを作るためのピッチコントロールや、調による曲の捉え方が難しく、苦労しました。ちなみに私の演奏はボロボロでした。(泣)ドビュッシーは、海外のオーレリア・サクソフォーン・クヮルテットなども演奏していますが、私は、緻密さと、丁寧さ、上品さではアルモの演奏を取ると思います。ただ、少し曲を冷静に見つめすぎている感じもあるので、その点はオーレリアの演奏も捨てがたい気がします。
しかしながら、演奏はアルモらしい、しなやかで上品な表現、きっちりとした技術に裏付けられた演奏なので、素晴らしいものです。
サクソフォーンを吹く全ての方、フランス近代の音楽をサックスで聴いてみたい方、ドビュッシーがお好きな方にオススメの一枚です。




