2008年08月17日
イラつく時。
大雨洪水注意報などが出たりするにも関わらず、雨がほとんど降りません。今日は朝から州崎寺での演奏に向けてのサクソフォンアンサンブルの練習三昧な一日でした。
さて、最近、光にも関わらず、ネットがつながりにくかったりしています。もしかしたらこちらの事情ではなく、接続先のサイトの事情なのかもしれません。
つながって欲しいときにつながらないと、少しイラつくことがあります。 そういえば何をしていてもイラつく瞬間というものがあります。自転車を走らせていても、前にいる自転車が2台で併進していてトロトロ走って道を譲らないときや、車でも道路の制限速度よりも何十キロも遅い速度で走り続ける、軽トラックなんかに出くわすとイラついたりします。自転車に乗っているときは歩行者が道路をふさいでいてもイラついたりします。私は、歩行者に後ろから自転車のベルを鳴らさないことにしています。自転車の警音器は、歩行者によけてもらう目的で鳴らすものではないことを皆さんご存知でしょうか。相手が自転車でも同様で、後ろから追い抜く目的、あるいは道をふさいでいるので、よけて欲しいという意味合いで使うものではないようです。
まあ、イラつくのもしばしの我慢なので、その辺は自分自身の心もうまくコントロールして、やり過ごすしかありませんが。
そこで今日の一枚です。
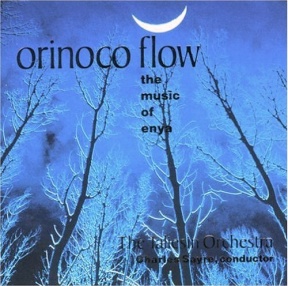
orinoco flow
オリノコ・フロウ~エンヤの音楽~
指揮:チャールズ・セイヤ(編曲)
ダリーシン管弦楽団
EASTWORLD(東芝EMI)TOCP-50437
このCDはエンヤの作品をオーケストラアレンジしたものです。人気の曲のベスト版、という感じもします。
エンヤの作品はやはりあのヴォイスサウンドが魅力なのかもしれませんが、こうやってオーケストラアレンジされると、それはそれでいい曲に感じます。やはり、しっかりしたつくりの曲というものはどんなスタイルになってもいい曲のまま、ということなのかもしれません。やはりイラつくときには落ち着けるエンヤでも聴いて落ち着くのもいいかと思います。
曲目はOrinoco Flow 8(Watermarkより)、Athair AR Neamh (The Memory of Treesより)、Memory of Trees (The Memory of Treesより)、No Holly for Miss Quinn (Shepherd Moonsより)、Lothlorien (Shepherd Moonsより)、From Where I Am (The Memory of Treesより)、Book of Days (Shepherd Moonsより)、China Roses (The Memory of Treesより)、Watermark (Watermarkより)、Bard Dance(The Celtsより)、Celts (The Celtsより)という11曲になっています。
このCD、少し残念なことは、オーディオ的にあまり音がよくないことでしょうか。ラジカセ音楽なら大丈夫なのかもしれませんが、きちんとしたオーディオシステムで聴くと、音がブーミーというか、ボンつく感じがします。それは機材の性ではなくて、録音のためのようです。せっかくのCDなのでもっと情報量の多いワイドレンジな録音でもよかったのではないかと思うのですが。
しかしながら、オーケストラアレンジのため、あのエンヤの曲に少しだけ明るさというか、楽しさのようなものが加わって、より聴きやすく、楽しめるものとなっています。
エンヤの音楽がお好きな方、少し落ち着けるBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
さて、最近、光にも関わらず、ネットがつながりにくかったりしています。もしかしたらこちらの事情ではなく、接続先のサイトの事情なのかもしれません。
つながって欲しいときにつながらないと、少しイラつくことがあります。 そういえば何をしていてもイラつく瞬間というものがあります。自転車を走らせていても、前にいる自転車が2台で併進していてトロトロ走って道を譲らないときや、車でも道路の制限速度よりも何十キロも遅い速度で走り続ける、軽トラックなんかに出くわすとイラついたりします。自転車に乗っているときは歩行者が道路をふさいでいてもイラついたりします。私は、歩行者に後ろから自転車のベルを鳴らさないことにしています。自転車の警音器は、歩行者によけてもらう目的で鳴らすものではないことを皆さんご存知でしょうか。相手が自転車でも同様で、後ろから追い抜く目的、あるいは道をふさいでいるので、よけて欲しいという意味合いで使うものではないようです。
まあ、イラつくのもしばしの我慢なので、その辺は自分自身の心もうまくコントロールして、やり過ごすしかありませんが。
そこで今日の一枚です。
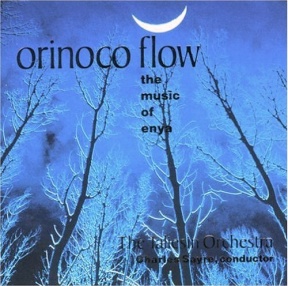
orinoco flow
オリノコ・フロウ~エンヤの音楽~
指揮:チャールズ・セイヤ(編曲)
ダリーシン管弦楽団
EASTWORLD(東芝EMI)TOCP-50437
このCDはエンヤの作品をオーケストラアレンジしたものです。人気の曲のベスト版、という感じもします。
エンヤの作品はやはりあのヴォイスサウンドが魅力なのかもしれませんが、こうやってオーケストラアレンジされると、それはそれでいい曲に感じます。やはり、しっかりしたつくりの曲というものはどんなスタイルになってもいい曲のまま、ということなのかもしれません。やはりイラつくときには落ち着けるエンヤでも聴いて落ち着くのもいいかと思います。
曲目はOrinoco Flow 8(Watermarkより)、Athair AR Neamh (The Memory of Treesより)、Memory of Trees (The Memory of Treesより)、No Holly for Miss Quinn (Shepherd Moonsより)、Lothlorien (Shepherd Moonsより)、From Where I Am (The Memory of Treesより)、Book of Days (Shepherd Moonsより)、China Roses (The Memory of Treesより)、Watermark (Watermarkより)、Bard Dance(The Celtsより)、Celts (The Celtsより)という11曲になっています。
このCD、少し残念なことは、オーディオ的にあまり音がよくないことでしょうか。ラジカセ音楽なら大丈夫なのかもしれませんが、きちんとしたオーディオシステムで聴くと、音がブーミーというか、ボンつく感じがします。それは機材の性ではなくて、録音のためのようです。せっかくのCDなのでもっと情報量の多いワイドレンジな録音でもよかったのではないかと思うのですが。
しかしながら、オーケストラアレンジのため、あのエンヤの曲に少しだけ明るさというか、楽しさのようなものが加わって、より聴きやすく、楽しめるものとなっています。
エンヤの音楽がお好きな方、少し落ち着けるBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
2008年08月16日
我慢の夏。
今日もよい天気です。夕立が降ってもバラっと降る程度で、本格的な雨になりません。立っているだけで汗ばんでくる今日この頃です。
さて、吹奏楽の中ではオーケストラ作品のアレンジ物を演奏することがよくあります。ただ、この場合やはり、サックスという楽器は耐えることが必要な楽器となってしまうような気がします。響きをブレンドさせることに徹す部分が多くストレートな音色が逆に表面に出ないようにすることもしばしばです。もしかして、そういう耐える行為がアンサンブル好きな人々を育てる土壌になっているのかもしれません。私の知る限り、サクソフォーン・アンサンブルは他の木管楽器のアンサンブルよりも活発に活動している姿をよく目にします。吹奏楽の中で耐える分、我慢する分、アンサンブルで発散する部分も多くあるのかもしれません。
それだけ、アンサンブルが完成されたものなのかもしれません。内輪で盛り上がるのが好きなだけかもしれませんが(笑)。
私も、学生時代、アンサンブルコンテストに何度か出場し、今でも一般の部で出場していますが、やはり思い出深い曲は中学生や高校生のときに演奏した曲のような気もします。それは他の曲に思い入れが無かったというのではなく、やはり、毎日のように練習した曲が体に染み付いているからなのかもしれません。あの頃吹いた曲の同じパートは今でも記憶に残っていて、楽譜が無くても演奏できます。
そこで今日の一枚です。

サキソフォンの名技
グラズノフ/サキソフォン協奏曲
グラズノフ/サキソフォン四重奏曲
レフ・ミハイロフ(アルト・ソロ、ソプラノ)
アレクサンドル・オセイチュック(アルト)
ユーリー・ヴォロンツォフ(テナー)
ウラジーミル・エリョーミン(バリトン)
メロディア (ビクター)VIC-2348
これはCDではなくLPレコードです。ミハイロフ氏のソロと彼を中心としたカルテットの演奏を聴くことが出来ます。このレフ・ミハイロフ氏は、ロシア(当時ソビエト連邦)のクラリネットとサクソフォーンのバイプレーヤのようすが、詳しいことは私は知りません。現在もご存命なのか同かも不明です。以前は、オーケストラにはサックス奏者が常任でいなかったということもあってか、クラリネット奏者がサックス奏者として活動している姿がよく見られました。現在はあまりそのような姿を見かけることもなくなりました。
さて、このグラズノフの四重奏曲は私が、高校時代に演奏した思い出の曲です。当時はリリースされている音源がこのレコードしか無く、カセットテープにダビングして、テープが擦り切れるほど聴いた記憶があります。ただ、残念なことにCD化されていないようです。(協奏曲のみはCDがあるようです)
音色は多少古い感じのサックスの音というか、フランスともアメリカとも当然、日本とも違う感覚の音色がしています。少し金属的な大人のですが、それでいて芯の通ったしっかりした太い音色です。ただし、歌い方や音楽性はすばらしい演奏です。
グラズノフのサクソフォン四重奏曲を聴いて見たい方、ロシア(ソビエト)のサクソフォーンの音色を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、吹奏楽の中ではオーケストラ作品のアレンジ物を演奏することがよくあります。ただ、この場合やはり、サックスという楽器は耐えることが必要な楽器となってしまうような気がします。響きをブレンドさせることに徹す部分が多くストレートな音色が逆に表面に出ないようにすることもしばしばです。もしかして、そういう耐える行為がアンサンブル好きな人々を育てる土壌になっているのかもしれません。私の知る限り、サクソフォーン・アンサンブルは他の木管楽器のアンサンブルよりも活発に活動している姿をよく目にします。吹奏楽の中で耐える分、我慢する分、アンサンブルで発散する部分も多くあるのかもしれません。
それだけ、アンサンブルが完成されたものなのかもしれません。内輪で盛り上がるのが好きなだけかもしれませんが(笑)。
私も、学生時代、アンサンブルコンテストに何度か出場し、今でも一般の部で出場していますが、やはり思い出深い曲は中学生や高校生のときに演奏した曲のような気もします。それは他の曲に思い入れが無かったというのではなく、やはり、毎日のように練習した曲が体に染み付いているからなのかもしれません。あの頃吹いた曲の同じパートは今でも記憶に残っていて、楽譜が無くても演奏できます。
そこで今日の一枚です。
サキソフォンの名技
グラズノフ/サキソフォン協奏曲
グラズノフ/サキソフォン四重奏曲
レフ・ミハイロフ(アルト・ソロ、ソプラノ)
アレクサンドル・オセイチュック(アルト)
ユーリー・ヴォロンツォフ(テナー)
ウラジーミル・エリョーミン(バリトン)
メロディア (ビクター)VIC-2348
これはCDではなくLPレコードです。ミハイロフ氏のソロと彼を中心としたカルテットの演奏を聴くことが出来ます。このレフ・ミハイロフ氏は、ロシア(当時ソビエト連邦)のクラリネットとサクソフォーンのバイプレーヤのようすが、詳しいことは私は知りません。現在もご存命なのか同かも不明です。以前は、オーケストラにはサックス奏者が常任でいなかったということもあってか、クラリネット奏者がサックス奏者として活動している姿がよく見られました。現在はあまりそのような姿を見かけることもなくなりました。
さて、このグラズノフの四重奏曲は私が、高校時代に演奏した思い出の曲です。当時はリリースされている音源がこのレコードしか無く、カセットテープにダビングして、テープが擦り切れるほど聴いた記憶があります。ただ、残念なことにCD化されていないようです。(協奏曲のみはCDがあるようです)
音色は多少古い感じのサックスの音というか、フランスともアメリカとも当然、日本とも違う感覚の音色がしています。少し金属的な大人のですが、それでいて芯の通ったしっかりした太い音色です。ただし、歌い方や音楽性はすばらしい演奏です。
グラズノフのサクソフォン四重奏曲を聴いて見たい方、ロシア(ソビエト)のサクソフォーンの音色を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月15日
またかい。
今日も朝から良い天気です。
さて、水不足、第三次取水制限が行われ、蛇口から出てくる水の水圧も下がったかと思う今日この頃、車を洗いたくても水不足のため、自粛しなければ当然白い目で見られそうです。まあ、またかい、という感じの水不足。深刻な問題ではありますが、何となく、世間が水不足慣れしているようでちょっと心配です。
世間はお盆で、帰省ラッシュだったり、また北京オリンピックだったりしていますが、何となく世間から取り残された感覚になっています。人付き合いの悪さと、元来の性格の悪さで、休みの日に他の人と出かけるでもなく、どこかに誘われるでもなく。
ボーっと過ごす休みになりそうです。普段、サクソフォーンアンサンブルや、吹奏楽団の練習がない時の休みはまあ、こんなものです。家でCD聞きながらボーっとしています。練習しろよ、と言われそうですが、楽器に唾でなくて汗が溜まりそうな環境。脱水になるか、Tシャツを絞ると汗が出るほど汗をかくかの選択になります。
そこで今日の一枚です。

シベリウス/カレリア組曲
グリーグ/ホルベルク組曲
指揮:サー・ネヴィル・マリナー
アカデミー・オブ・セント・
マーティン・イン・ザ・フィールズ
PHILIPS PHCP-8346
このCDは以前紹介したアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズによるシベリウスの「カレリア組曲」とグリーグの「ホルベルク組曲」が収録されたものです。以前も紹介したようにアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(日本名が「「アカデミー室内O.」)は室内楽を中心としたオーケストラとして、マリナーが創設したものです。「ホルベルク組曲」はどうも、マリナー&アカデミー室内O.お得意のレパートリーのようで、以前紹介したDVDにも収録されていました。
また、「カレリア組曲」かよ、という方、ごもっともです。しかしながら、このCDのカレリアは以前紹介した、サラステ盤、オーマンディ盤、アシュケナージ盤のまたどれとも違う魅力を持っています。まず、厳格な演奏であるにもかかわらず、上品なこと。また、歌うことに溺れず、キリッとしたしまりの演奏であることが上げられます。さすが、イギリス系のオーケストラと言ったところでしょうか。
グリーグの「ホルベルク組曲」のほうも同様、しまりのある演奏と、やわらかい響きの演奏となっています。
ほかにシベリウスの「トゥオネラの白鳥」と、グリーグの「二つの抒情的な作品」が収録されています。
さわやかなシベリウスを聞きたい方、マリナー&アカデミー室内O.の演奏を楽しみたい方にオススメの一枚です。
さて、水不足、第三次取水制限が行われ、蛇口から出てくる水の水圧も下がったかと思う今日この頃、車を洗いたくても水不足のため、自粛しなければ当然白い目で見られそうです。まあ、またかい、という感じの水不足。深刻な問題ではありますが、何となく、世間が水不足慣れしているようでちょっと心配です。
世間はお盆で、帰省ラッシュだったり、また北京オリンピックだったりしていますが、何となく世間から取り残された感覚になっています。人付き合いの悪さと、元来の性格の悪さで、休みの日に他の人と出かけるでもなく、どこかに誘われるでもなく。
ボーっと過ごす休みになりそうです。普段、サクソフォーンアンサンブルや、吹奏楽団の練習がない時の休みはまあ、こんなものです。家でCD聞きながらボーっとしています。練習しろよ、と言われそうですが、楽器に唾でなくて汗が溜まりそうな環境。脱水になるか、Tシャツを絞ると汗が出るほど汗をかくかの選択になります。
そこで今日の一枚です。

シベリウス/カレリア組曲
グリーグ/ホルベルク組曲
指揮:サー・ネヴィル・マリナー
アカデミー・オブ・セント・
マーティン・イン・ザ・フィールズ
PHILIPS PHCP-8346
このCDは以前紹介したアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズによるシベリウスの「カレリア組曲」とグリーグの「ホルベルク組曲」が収録されたものです。以前も紹介したようにアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(日本名が「「アカデミー室内O.」)は室内楽を中心としたオーケストラとして、マリナーが創設したものです。「ホルベルク組曲」はどうも、マリナー&アカデミー室内O.お得意のレパートリーのようで、以前紹介したDVDにも収録されていました。
また、「カレリア組曲」かよ、という方、ごもっともです。しかしながら、このCDのカレリアは以前紹介した、サラステ盤、オーマンディ盤、アシュケナージ盤のまたどれとも違う魅力を持っています。まず、厳格な演奏であるにもかかわらず、上品なこと。また、歌うことに溺れず、キリッとしたしまりの演奏であることが上げられます。さすが、イギリス系のオーケストラと言ったところでしょうか。
グリーグの「ホルベルク組曲」のほうも同様、しまりのある演奏と、やわらかい響きの演奏となっています。
ほかにシベリウスの「トゥオネラの白鳥」と、グリーグの「二つの抒情的な作品」が収録されています。
さわやかなシベリウスを聞きたい方、マリナー&アカデミー室内O.の演奏を楽しみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月15日
見通し、見える。
まだまだ、暑い日が続いていますが、心なしか涼しさを感じられる気もします。
さて、私は、はっきり言って体力が余りありません。持久力、瞬発力、筋力、忍耐力、運動能力、どれをとっても、まともなものがありません。元々、運動センスが無いので、球技はからっきし駄目ときています。チームプレーの競技は、他の人に迷惑がかかるので、今からはじめるのはどうかとも思うし、テニスやバトミントン、卓球などは、相手がいないとできない上に、ボールがまともに飛ばない状態では他の人に迷惑がかかります。かといって、教室とかに通うと、お金もかかるし、時間の融通が利かなくなります。
そこで、以前から、どこかに泳ぎに行こうと、ずーっとお持っていました。水泳なら、少々ヘタクソでも他人にあまり迷惑をかけないし、好きなときにプールから上がってしまえがいいし、一人で黙々と泳ぐこともできるし、全身運動だし、いいこと尽くめです。おまけに、テニスや、ゴルフなんかに比べると初心者用の道具が値段的にも安いのです。
実は私がスポーツの中で唯一まともにできるのも水泳なのです。走るのも飛ぶのも投げるのも駄目だったのですが、水泳だけは小学生の頃から、どちらかというと得意で、地区の記録会に選手として出たこともあります。
これには喘息治療の目的で小さい頃から泳ぎに行っていたことも関係しているようですが。
そこで、水泳をしようと決めたのですが、そう考えてからはや10年、当然、水着も使えなくなっています。おまけに、小学生の頃や中学生の頃と違って視力が極端に悪くなっているので、水の中では別にかまわないのですが、自ら上がったときにプールの段差や、プールサイドとプールの境がわかりづらいほどになっています。
コンタクトレンズも持っているのですが、私はハード派なので、いまさらソフトを作るのは使い捨てでも面倒だし、どの道ゴーグルは必要です。そこで、いろいろ調べて、最近、度付きのゴーグルというものが売られていて、ある程度、ゴーグルで視力の矯正ができることが判明しました。実は昔から、度付きゴーグルはあったのですが、種類も少なく、オーダーに近かったために、非常に高価な印象がありましたが、今は、パーツを自分で組み立てられるスタイルになっていて、手軽に度付きゴーグルを完成することができます。値段も私が知っていた頃と比べると、半額ぐらいでしょうか。
これで、プールからあがったときも、怖い思いをしなくてすみます。プールから上がっても見通しよし、ある程度、周りの景色や状態も見えるようになります。
仕事がおちついたらまた泳ぎに行きたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

軽騎兵/スッペ序曲集
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL5120
このCDはデュトワ/モントリオール響による、フランツ・フォン・スッペの序曲集です。
私はこれを聞くまで、スッペの序曲集といえば、カラヤン/ベルリンフィルのものしか聞いたことがありませんでした。カラヤンの演奏はいかにもドイツオケの演奏らしく、ある意味重厚な響きの上に、カラヤンらしいゴージャスさというか、一般受けする派手さが加わったような演奏だったと記憶しています。ただ、それぞれのソロなどは超一級品でした。
このデュトワの演奏を聴くと、同じ音楽でもここまで変わるか、と感じてしまいます。どちらかというと、デュトワの演奏はフランスチックで、スッペの作品にもかかわらず、オッフェンバックの曲ではないかと思うぐらい、流麗で、透明感あふれた洒落たえんそうになっています。アクセントの扱いも明らかに、ドイツ流というよりはフランス流で、非常にゴリゴリした感じが取り除かれた軽く、やわらかい演奏を感じることができます。
また、このデュトワの演奏は録音のよさもあるのか、各楽器の配置や、演奏の見通しが非常によく、各パートがきれいに見える演奏になっています。 もちろん、全体としてのまとまりもきちんとした音楽に仕上がっているのですが、それぞれのパートが何をやっているのかその気になれば、しっかりと見渡せるような演奏です。
ちょっと洒落た感じのスッペの序曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、私は、はっきり言って体力が余りありません。持久力、瞬発力、筋力、忍耐力、運動能力、どれをとっても、まともなものがありません。元々、運動センスが無いので、球技はからっきし駄目ときています。チームプレーの競技は、他の人に迷惑がかかるので、今からはじめるのはどうかとも思うし、テニスやバトミントン、卓球などは、相手がいないとできない上に、ボールがまともに飛ばない状態では他の人に迷惑がかかります。かといって、教室とかに通うと、お金もかかるし、時間の融通が利かなくなります。
そこで、以前から、どこかに泳ぎに行こうと、ずーっとお持っていました。水泳なら、少々ヘタクソでも他人にあまり迷惑をかけないし、好きなときにプールから上がってしまえがいいし、一人で黙々と泳ぐこともできるし、全身運動だし、いいこと尽くめです。おまけに、テニスや、ゴルフなんかに比べると初心者用の道具が値段的にも安いのです。
実は私がスポーツの中で唯一まともにできるのも水泳なのです。走るのも飛ぶのも投げるのも駄目だったのですが、水泳だけは小学生の頃から、どちらかというと得意で、地区の記録会に選手として出たこともあります。
これには喘息治療の目的で小さい頃から泳ぎに行っていたことも関係しているようですが。
そこで、水泳をしようと決めたのですが、そう考えてからはや10年、当然、水着も使えなくなっています。おまけに、小学生の頃や中学生の頃と違って視力が極端に悪くなっているので、水の中では別にかまわないのですが、自ら上がったときにプールの段差や、プールサイドとプールの境がわかりづらいほどになっています。
コンタクトレンズも持っているのですが、私はハード派なので、いまさらソフトを作るのは使い捨てでも面倒だし、どの道ゴーグルは必要です。そこで、いろいろ調べて、最近、度付きのゴーグルというものが売られていて、ある程度、ゴーグルで視力の矯正ができることが判明しました。実は昔から、度付きゴーグルはあったのですが、種類も少なく、オーダーに近かったために、非常に高価な印象がありましたが、今は、パーツを自分で組み立てられるスタイルになっていて、手軽に度付きゴーグルを完成することができます。値段も私が知っていた頃と比べると、半額ぐらいでしょうか。
これで、プールからあがったときも、怖い思いをしなくてすみます。プールから上がっても見通しよし、ある程度、周りの景色や状態も見えるようになります。
仕事がおちついたらまた泳ぎに行きたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

軽騎兵/スッペ序曲集
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL5120
このCDはデュトワ/モントリオール響による、フランツ・フォン・スッペの序曲集です。
私はこれを聞くまで、スッペの序曲集といえば、カラヤン/ベルリンフィルのものしか聞いたことがありませんでした。カラヤンの演奏はいかにもドイツオケの演奏らしく、ある意味重厚な響きの上に、カラヤンらしいゴージャスさというか、一般受けする派手さが加わったような演奏だったと記憶しています。ただ、それぞれのソロなどは超一級品でした。
このデュトワの演奏を聴くと、同じ音楽でもここまで変わるか、と感じてしまいます。どちらかというと、デュトワの演奏はフランスチックで、スッペの作品にもかかわらず、オッフェンバックの曲ではないかと思うぐらい、流麗で、透明感あふれた洒落たえんそうになっています。アクセントの扱いも明らかに、ドイツ流というよりはフランス流で、非常にゴリゴリした感じが取り除かれた軽く、やわらかい演奏を感じることができます。
また、このデュトワの演奏は録音のよさもあるのか、各楽器の配置や、演奏の見通しが非常によく、各パートがきれいに見える演奏になっています。 もちろん、全体としてのまとまりもきちんとした音楽に仕上がっているのですが、それぞれのパートが何をやっているのかその気になれば、しっかりと見渡せるような演奏です。
ちょっと洒落た感じのスッペの序曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月14日
バンダ。
今日は雲の出る天気になったものの、概ね青空。雨が降らないので、水不足にまっしぐらです。
最近、来年の高松ウインドシンフォニーの定期演奏会の曲目が少しずつ決まってきているのですが、候補としてレスピーギのローマの祭が上がっています。以前、ローマの松を演奏したことはありますが、バンダや影ラッパなど、結構大変だった記憶があります。(バンダ…オーケストラの編成とは別に金管の楽隊を編成してオーケストラの演奏などに加えるもの。ローマの松では二楽章でトランペットを一人、オーケストラとは離れた影で演奏させ、どこからともなくソロが聞こえると言う効果がなされ、また、終楽章では、原曲にはブッチーナ(Buccina)と呼ばれる古代ローマで使われた金管楽器の別働隊が指定されています。この楽器は水牛の角のような形状の金管楽器で、バルブやピストンもなく音は自然倍音のみしか出す事ができません。レスピーギはソプラノ2、テナー2、バス2の計6本のブッチーナを指定していますが、現実のスコアには自然倍音以外の音も記譜がされており、作曲者の意図としてはプッチーナを使う指定よりも、それをイメージした演奏にして欲しいという意図だったようです。実際にはソプラノとテナーのブッチーナパートはトランペット、そしてバスブッチーナはトロンボーンが用いられる場合が多いようです。またテナーブッチーナーパートは音域が低いためトランペットでは充分な音量を得られにくく、ホルンを用いる場合もあります。レスピーギ自身は、ソプラノとテナーについてはフリューゲルホルン、バスについてはユーフォニウム若しくはバリトンを想定していたようです。実際本物のプッチーナはレスピーギの時代にはすでに存在さえ消滅しており、松の演奏で使われたことは無いようです。)
でも、バンダを入れると、どうしてもバンダが指揮者から遠くなるので、演奏がずれるということに苦労することとなります。
そこで今日の一枚です。

レスピーギ:
「ローマの松」・「ローマの噴水」・「ローマの祭」
指揮:アルトゥーロ・トスカニーニ
NBC交響楽団
RCA (BMGジャパン)BVCC-9935
このCDはトスカニーニ指揮によるローマ三部作が収録されたものです。録音年代が今から50年以上前なので、すべてモノラル録音になっています。
演奏はまさに精緻なアンサンブルとトスカニーニのカリスマ性に支配されたものといってもいいかもしれません。余分なアゴーギグや表現に溺れる、といったことが一切無いような演奏です。それでいながらオケは非常に優秀で、要所要所のソロでは絶品の音色と表現を見せてくれます。私はどちらかというと、以前にも紹介したデュトワ/モントリオール盤が聞きなれていることもあって好みなのですが、このトスカニーニ盤もなかなかのものです。
ただ、このトスカニーニの演奏は、バンダや金管楽器がなぜか目いっぱい、ぎりぎりの音で吹ききっている感があります。堂々とした感じはあるのですが、必死さが伝わってきてしまうのが逆に少し残念な気もします。あと、ステレオ録音されていたら、この演奏はもっと色彩感あふれるものになったかもしれません。モノラルの録音でも今のステレオ録音に太刀打ちできるほど色彩感が豊かな演奏です。でも、バテもバランスも関係なく思いっきり吹いてるバンダです。ただ、オケの強奏にはこれぐらいやらないとついていけないのかもしれません。
トスカニーニの名演を聞いてみたい方、レスピーギのローマ三部作を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
最近、来年の高松ウインドシンフォニーの定期演奏会の曲目が少しずつ決まってきているのですが、候補としてレスピーギのローマの祭が上がっています。以前、ローマの松を演奏したことはありますが、バンダや影ラッパなど、結構大変だった記憶があります。(バンダ…オーケストラの編成とは別に金管の楽隊を編成してオーケストラの演奏などに加えるもの。ローマの松では二楽章でトランペットを一人、オーケストラとは離れた影で演奏させ、どこからともなくソロが聞こえると言う効果がなされ、また、終楽章では、原曲にはブッチーナ(Buccina)と呼ばれる古代ローマで使われた金管楽器の別働隊が指定されています。この楽器は水牛の角のような形状の金管楽器で、バルブやピストンもなく音は自然倍音のみしか出す事ができません。レスピーギはソプラノ2、テナー2、バス2の計6本のブッチーナを指定していますが、現実のスコアには自然倍音以外の音も記譜がされており、作曲者の意図としてはプッチーナを使う指定よりも、それをイメージした演奏にして欲しいという意図だったようです。実際にはソプラノとテナーのブッチーナパートはトランペット、そしてバスブッチーナはトロンボーンが用いられる場合が多いようです。またテナーブッチーナーパートは音域が低いためトランペットでは充分な音量を得られにくく、ホルンを用いる場合もあります。レスピーギ自身は、ソプラノとテナーについてはフリューゲルホルン、バスについてはユーフォニウム若しくはバリトンを想定していたようです。実際本物のプッチーナはレスピーギの時代にはすでに存在さえ消滅しており、松の演奏で使われたことは無いようです。)
でも、バンダを入れると、どうしてもバンダが指揮者から遠くなるので、演奏がずれるということに苦労することとなります。
そこで今日の一枚です。

レスピーギ:
「ローマの松」・「ローマの噴水」・「ローマの祭」
指揮:アルトゥーロ・トスカニーニ
NBC交響楽団
RCA (BMGジャパン)BVCC-9935
このCDはトスカニーニ指揮によるローマ三部作が収録されたものです。録音年代が今から50年以上前なので、すべてモノラル録音になっています。
演奏はまさに精緻なアンサンブルとトスカニーニのカリスマ性に支配されたものといってもいいかもしれません。余分なアゴーギグや表現に溺れる、といったことが一切無いような演奏です。それでいながらオケは非常に優秀で、要所要所のソロでは絶品の音色と表現を見せてくれます。私はどちらかというと、以前にも紹介したデュトワ/モントリオール盤が聞きなれていることもあって好みなのですが、このトスカニーニ盤もなかなかのものです。
ただ、このトスカニーニの演奏は、バンダや金管楽器がなぜか目いっぱい、ぎりぎりの音で吹ききっている感があります。堂々とした感じはあるのですが、必死さが伝わってきてしまうのが逆に少し残念な気もします。あと、ステレオ録音されていたら、この演奏はもっと色彩感あふれるものになったかもしれません。モノラルの録音でも今のステレオ録音に太刀打ちできるほど色彩感が豊かな演奏です。でも、バテもバランスも関係なく思いっきり吹いてるバンダです。ただ、オケの強奏にはこれぐらいやらないとついていけないのかもしれません。
トスカニーニの名演を聞いてみたい方、レスピーギのローマ三部作を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
Posted by のりくん at
18:27
│Comments(0)
2008年08月13日
マニアといわれてしまう瞬間。
今日もよい天気です。実は私は明日からワンテンポ遅れたお盆休み。おそらくお盆休みの後半はサクソフォーンアンサンブルの練習でサックスを吹き続けている予定です。
さて、以前にもかきましたが、私は決してマニアックな人間ではありません。ただ単に音楽が好きでCDを買って聞いて、少しいい音で聞きたいな、と思ってちょっとだけ皆さんよりも高級なオーディオシステムで聞いているだけの人なのです。で、そういうことを言うと、必ず、じゃあ、何で同じ曲のCDを大量に持ってるの?1種類で十分じゃないの?と必ず聞かれます。確かにそれで何の問題も無いのですが、演奏には好みもあったりします。また、私がCDを買うという行為は自分の演奏する曲がどんな曲か聴いてみたい、とか、好きな曲なのでいろいろな演奏を楽しみたい、というところからスタートしています。なので、同じ演奏でもいろいろな演奏を聴いて参考にしたいと思うのは普通だと思うのですが、皆さんはどうなのでしょう?
以前「展覧会の絵」企画というのをやらせていただきましたが、そのとき紹介した展覧会の絵だけでは無く、まだ、持っているものがあったのでそのあとも単体で何枚か紹介させていただきました。これは私が展覧会の絵という曲に思い入れが深く、いろいろ聞いてみたいと思ったからたくさんのCDを持っているのであって、闇雲にCDを買いあさっているわけではありません。でも、こんなことを言っても、人にはマニアックといわれてしまうのですが。
そこで今日の一枚です。

シベリウス:交響曲第一番/組曲「カレリア」
指揮:ウラディーミル・アシュケナージ
フィルハーモニア管弦楽団
F35L-50374
このCDはシベリウスの「カレリア」と交響曲一番が収録されたもの。カレリアは序曲は収録されておらず、組曲のみの収録です。
先に書いておきますが「カレリア」の入ったCDはこれを含めて4種類もっています。(笑)。
カレリアのほうは以前演奏したときに参考にと思ってこのアシュケナージ盤と以前も紹介したサラステ盤を買いました。その後買ったのがこれまた以前紹介したオーマンディ盤になります。あと、マリナー盤はいつ買ったか忘れました。
で、演奏のほうですが、よくも悪くもアシュケナージとフィルハーモニア、という感じでしょうか。私はLONDONレーベルの録音の音作りに好きなものが多いのっで、結構LONDONのものを持っていますが、これもその流れで購入した記憶があります。カレリアは全体に柔軟な響きを作り出そうという意図は感じられるのですが、逆にそれがリズムやテンポに影響して、ところどころルーズに聞こえてしまうところが少し残念かも知れません。とくに三曲目マーチ風ににその傾向が顕著です。
しかしながら強弱もよく考えられて表現されていると感じられますし、全体的には柔軟な響きの演奏だと思います。
シベリウスを聞いてみたい方、アシュケナージがお好きな方にはオススメの一枚です。
私はカラヤンの「カレリア」とか聞いたことが無いんですよね…。カラヤンはあまり好みじゃないんですが、聴き比べとして聞いてみたいなーなどと思っています。(この瞬間にマニアって言われるんだろうな…)
さて、以前にもかきましたが、私は決してマニアックな人間ではありません。ただ単に音楽が好きでCDを買って聞いて、少しいい音で聞きたいな、と思ってちょっとだけ皆さんよりも高級なオーディオシステムで聞いているだけの人なのです。で、そういうことを言うと、必ず、じゃあ、何で同じ曲のCDを大量に持ってるの?1種類で十分じゃないの?と必ず聞かれます。確かにそれで何の問題も無いのですが、演奏には好みもあったりします。また、私がCDを買うという行為は自分の演奏する曲がどんな曲か聴いてみたい、とか、好きな曲なのでいろいろな演奏を楽しみたい、というところからスタートしています。なので、同じ演奏でもいろいろな演奏を聴いて参考にしたいと思うのは普通だと思うのですが、皆さんはどうなのでしょう?
以前「展覧会の絵」企画というのをやらせていただきましたが、そのとき紹介した展覧会の絵だけでは無く、まだ、持っているものがあったのでそのあとも単体で何枚か紹介させていただきました。これは私が展覧会の絵という曲に思い入れが深く、いろいろ聞いてみたいと思ったからたくさんのCDを持っているのであって、闇雲にCDを買いあさっているわけではありません。でも、こんなことを言っても、人にはマニアックといわれてしまうのですが。
そこで今日の一枚です。

シベリウス:交響曲第一番/組曲「カレリア」
指揮:ウラディーミル・アシュケナージ
フィルハーモニア管弦楽団
F35L-50374
このCDはシベリウスの「カレリア」と交響曲一番が収録されたもの。カレリアは序曲は収録されておらず、組曲のみの収録です。
先に書いておきますが「カレリア」の入ったCDはこれを含めて4種類もっています。(笑)。
カレリアのほうは以前演奏したときに参考にと思ってこのアシュケナージ盤と以前も紹介したサラステ盤を買いました。その後買ったのがこれまた以前紹介したオーマンディ盤になります。あと、マリナー盤はいつ買ったか忘れました。
で、演奏のほうですが、よくも悪くもアシュケナージとフィルハーモニア、という感じでしょうか。私はLONDONレーベルの録音の音作りに好きなものが多いのっで、結構LONDONのものを持っていますが、これもその流れで購入した記憶があります。カレリアは全体に柔軟な響きを作り出そうという意図は感じられるのですが、逆にそれがリズムやテンポに影響して、ところどころルーズに聞こえてしまうところが少し残念かも知れません。とくに三曲目マーチ風ににその傾向が顕著です。
しかしながら強弱もよく考えられて表現されていると感じられますし、全体的には柔軟な響きの演奏だと思います。
シベリウスを聞いてみたい方、アシュケナージがお好きな方にはオススメの一枚です。
私はカラヤンの「カレリア」とか聞いたことが無いんですよね…。カラヤンはあまり好みじゃないんですが、聴き比べとして聞いてみたいなーなどと思っています。(この瞬間にマニアって言われるんだろうな…)
2008年08月12日
欲(ほっ)する。
今日も夏のよい天気です。日差しがまぶしい一日…。
私は普段、高松ウインドシンフォニーにも在籍しているので、演奏会が近づいてきたり、行事が立て込んできたりすると吹奏楽三昧となります。吹奏楽のバンドにどっぷりつかっていると、いつものようにアンサンブルの練習をすることすらもままならなくなります。、人間不思議なものでできなくなってくるとやりたくなるものです。
甘いものが太るとわかっていてもほしくなる、タバコをやめようと思ったとたん最後の一本がほしくなる(最後の一本を何本もすってたりするんですが)、外で長期滞在すると家が恋しくなる、などなど、いろいろです。別名、依存症とも言うのかもしれません。もっというと、禁断症状というやつなのかも知れません。また、体が不足しているものを欲しているのかもしれません。
とにかくソプラノサックスにしばらく触ってないことにも気づき、アンサンブルがやりたくなってきました。アンサンブルの演奏会のこともちっとも進んでいないこともあるのですが。
そこで今日の一枚です。

ザ・トルヴェール・クヮルテット
Apollon(アポロン音楽産業) APCE-5133
このCDはトルヴェール・クヮルテットのファースト・アルバム。私はこのアルバム、今でも傑作だと思っています。残念なことにアポロンは現在消滅した会社なので、このCDが今でも手に入るかどうかは不明です。(確か初期の須川氏のCDもアポロンからリリースされていたと記憶していますが、今はそのアルバムはどうなっているんでしょう?)多分、どこかのレーベルが買い取って再販されているとは思うのですが。ちなみにこれ以降、トルヴェールの演奏は主に東芝EMIから発売されるようになっています。
久しぶりにこのCDを聞いてみました。トルヴェールの演奏としても若々しさが伝わってくるような演奏でうす。路線が変わったと言う意味ではないのですが、今のトルヴェールの響きや表現とは若干違いが見られたりもします。デザンクロは攻撃的な面と協調的な面を描き出しているのは見事としかいいようがありません。私はデザンクロは今でも今でもでファイエ氏の四重奏団の演奏が最高だと思ってやまないのですが、この演奏はまた、違った演奏としてすごいと思っています。プロにとっても難曲のシュミットも曲の構造を見通しよく表現してあり、正確にそして、柔軟に表現されていると思います。当時としては珍しかったピアノ+サクソフォーン四重奏というスタイルの「ポーギーとべス」もすばらしい演奏で聞かせてくれます。
個人的な意見としては、後の「デュークエリントンの時代
から」に収録されているデザンクロよりはこちらのほうが好みです。もちろん「デューク~」の方が録音はかなり後なのですが、こちらの方はサウンドが少々シャープに傾きすぎている気もします。もちろん録音の違いもあるのかもしれません。とはいえ、どちらもすばらしい演奏には違いありません。
サクソフォーンという楽器を手にしたことのあるすべての方、サクソフォーンの魅力が知りたいと思う方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
私は普段、高松ウインドシンフォニーにも在籍しているので、演奏会が近づいてきたり、行事が立て込んできたりすると吹奏楽三昧となります。吹奏楽のバンドにどっぷりつかっていると、いつものようにアンサンブルの練習をすることすらもままならなくなります。、人間不思議なものでできなくなってくるとやりたくなるものです。
甘いものが太るとわかっていてもほしくなる、タバコをやめようと思ったとたん最後の一本がほしくなる(最後の一本を何本もすってたりするんですが)、外で長期滞在すると家が恋しくなる、などなど、いろいろです。別名、依存症とも言うのかもしれません。もっというと、禁断症状というやつなのかも知れません。また、体が不足しているものを欲しているのかもしれません。
とにかくソプラノサックスにしばらく触ってないことにも気づき、アンサンブルがやりたくなってきました。アンサンブルの演奏会のこともちっとも進んでいないこともあるのですが。
そこで今日の一枚です。

ザ・トルヴェール・クヮルテット
Apollon(アポロン音楽産業) APCE-5133
このCDはトルヴェール・クヮルテットのファースト・アルバム。私はこのアルバム、今でも傑作だと思っています。残念なことにアポロンは現在消滅した会社なので、このCDが今でも手に入るかどうかは不明です。(確か初期の須川氏のCDもアポロンからリリースされていたと記憶していますが、今はそのアルバムはどうなっているんでしょう?)多分、どこかのレーベルが買い取って再販されているとは思うのですが。ちなみにこれ以降、トルヴェールの演奏は主に東芝EMIから発売されるようになっています。
久しぶりにこのCDを聞いてみました。トルヴェールの演奏としても若々しさが伝わってくるような演奏でうす。路線が変わったと言う意味ではないのですが、今のトルヴェールの響きや表現とは若干違いが見られたりもします。デザンクロは攻撃的な面と協調的な面を描き出しているのは見事としかいいようがありません。私はデザンクロは今でも今でもでファイエ氏の四重奏団の演奏が最高だと思ってやまないのですが、この演奏はまた、違った演奏としてすごいと思っています。プロにとっても難曲のシュミットも曲の構造を見通しよく表現してあり、正確にそして、柔軟に表現されていると思います。当時としては珍しかったピアノ+サクソフォーン四重奏というスタイルの「ポーギーとべス」もすばらしい演奏で聞かせてくれます。
個人的な意見としては、後の「デュークエリントンの時代
から」に収録されているデザンクロよりはこちらのほうが好みです。もちろん「デューク~」の方が録音はかなり後なのですが、こちらの方はサウンドが少々シャープに傾きすぎている気もします。もちろん録音の違いもあるのかもしれません。とはいえ、どちらもすばらしい演奏には違いありません。
サクソフォーンという楽器を手にしたことのあるすべての方、サクソフォーンの魅力が知りたいと思う方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
2008年08月11日
夏休みといえば。
今日も蒸し暑い一日となりました。何もしていなくても、服がじっとりと汗ばんできます。
サックスの練習を平日に…と思ってもじっとりと汗ばむ上に、あまり遅い時間や早朝は音が出せない…ということを言い訳に練習が進んでいません。州崎寺までにアンサンブルが仕上がるかどうか自分でも心配になっているのでもうちょっとがんばる必要はあるのですが…。
さて、以前の日記にも書いたとおり、私は夏がはっきり言って苦手です。ただ、苦手だとばかり言ってはいられません。暑いからこそ楽しみなこともいくつかあります。
その中で私のささやかな夏の楽しみはカキ氷です。中でもミルク宇治金時が大好きです。まさに、全部乗せ、という豪華さです(笑)。ミルク、抹茶、金時餡、何をとっても私の大好きなものばかり、おまけに暑い夏に冷たい氷、とくれば、夏はやっぱりカキ氷です。少々贅沢ですが、以前は夏には2回~3回ミルク宇治金時を食べに行っていました。勿論、お気に入りの甘味処もあります。体調の関係であまり甘いものばかりは食べられないのですが、たまには贅沢しようと思って食べに行きます。でも、男一人ではちょっと食べに行きにくいので一人で行くことはありません。今は一緒に食べに行ってくれる人もいません。寂しい限りです。
去年は食べにいけず、今年もまだ食べに行っていないので、是非夏が終わるまでに行きたいと思っています。
でも、冷たいものばかり食べ過ぎると、益々体力が落ちるかもしれないので要注意です。
そこで今日の一枚です。

NHK 新ラジオ体操・みんなの体操
コロムビアミュージックエンタテインメント COCG-15355
このCDはおなじみのNHKのラジオ体操と、新しい「みんなの体操」が収録されたもの。小中学生はほとんどが明日から夏休みということもありますが、やはり、基本は体を動かして鍛えることが健康を保つ秘訣ということではないかと…。CDに収録されているのは、みんなの体操(指導入り)、みんなの体操(指導なし)、ラジオ体操 第1(指導入り)、ラジオ体操 第2(指導入り)、ラジオ体操の歌、となっています。(指導入り)というのは、よく「腕を前から上げて…」などといっている号令のことです。みんなの体操自体は私には実は全くと行っていいほどなじみがありません。やっぱり、一番なじみが深いのはラジオ体操第1でしょうか。小学校の頃、夏休みにラジオ体操に通った記憶があります。どうも、体操の内容としては、みんなの体操→第1→第2の順にハードになっているようなのですが。
健康増進に勤めたい方、みんなの体操を覚えてみたい方にオススメの一枚です。ちなみにCDを買わなくてもテレビラジオからでも録音できます。(個人で使用するには問題ないかと思います。)
サックスの練習を平日に…と思ってもじっとりと汗ばむ上に、あまり遅い時間や早朝は音が出せない…ということを言い訳に練習が進んでいません。州崎寺までにアンサンブルが仕上がるかどうか自分でも心配になっているのでもうちょっとがんばる必要はあるのですが…。
さて、以前の日記にも書いたとおり、私は夏がはっきり言って苦手です。ただ、苦手だとばかり言ってはいられません。暑いからこそ楽しみなこともいくつかあります。
その中で私のささやかな夏の楽しみはカキ氷です。中でもミルク宇治金時が大好きです。まさに、全部乗せ、という豪華さです(笑)。ミルク、抹茶、金時餡、何をとっても私の大好きなものばかり、おまけに暑い夏に冷たい氷、とくれば、夏はやっぱりカキ氷です。少々贅沢ですが、以前は夏には2回~3回ミルク宇治金時を食べに行っていました。勿論、お気に入りの甘味処もあります。体調の関係であまり甘いものばかりは食べられないのですが、たまには贅沢しようと思って食べに行きます。でも、男一人ではちょっと食べに行きにくいので一人で行くことはありません。今は一緒に食べに行ってくれる人もいません。寂しい限りです。
去年は食べにいけず、今年もまだ食べに行っていないので、是非夏が終わるまでに行きたいと思っています。
でも、冷たいものばかり食べ過ぎると、益々体力が落ちるかもしれないので要注意です。
そこで今日の一枚です。
NHK 新ラジオ体操・みんなの体操
コロムビアミュージックエンタテインメント COCG-15355
このCDはおなじみのNHKのラジオ体操と、新しい「みんなの体操」が収録されたもの。小中学生はほとんどが明日から夏休みということもありますが、やはり、基本は体を動かして鍛えることが健康を保つ秘訣ということではないかと…。CDに収録されているのは、みんなの体操(指導入り)、みんなの体操(指導なし)、ラジオ体操 第1(指導入り)、ラジオ体操 第2(指導入り)、ラジオ体操の歌、となっています。(指導入り)というのは、よく「腕を前から上げて…」などといっている号令のことです。みんなの体操自体は私には実は全くと行っていいほどなじみがありません。やっぱり、一番なじみが深いのはラジオ体操第1でしょうか。小学校の頃、夏休みにラジオ体操に通った記憶があります。どうも、体操の内容としては、みんなの体操→第1→第2の順にハードになっているようなのですが。
健康増進に勤めたい方、みんなの体操を覚えてみたい方にオススメの一枚です。ちなみにCDを買わなくてもテレビラジオからでも録音できます。(個人で使用するには問題ないかと思います。)
2008年08月10日
自分に腹が立つ、楽器を叩きつけたくなる瞬間。
今日もよい天気です。昨日は少し雲が広がり、そのためか、少し涼しくなりましたが、逆に蒸し暑くなった気もします。
州崎寺に向けての、そして秋のアンサンブルコンサートに向けての練習も佳境に入ってくる時期ですが…。
さて、 楽譜に書いてあることは、作曲者や編曲者としてはやってほしいことを記号化して書いているので、そのとおりやらなければならないのですが、作曲家や編曲者によっては、楽器の特性を理解していないと思われる楽譜を平気で書いてしまう人もいます。この楽器の特性を理解している、いないは、吹ける、吹けないのレベルの話ではなく、最終的には楽器を効果的に鳴らす、あるいは響きや効果を際立たせる、というところにかかわってきます。サックスという楽器は吹奏楽をやっている人にはなじみが深いのですが、オケやピアノ一筋で来た人ににとっては未知の楽器だったりします。あの、ラヴェルやドビュッシーでさえ、サクソフォーンの音域や特性を理解していなかったと言われています。もっとも、時代が時代だったので、仕方ない、と言えるのかもしれませんが。
しかし吹けないところがあると、自分で自分に腹が立ってきます。テンポを落としても、指が引っかかる、テンポを上げていくと、指が転ぶ…。最初のうちはがんばって根性入れてやってますが、同じところを一時間、二時間の長丁場でできるまで繰り返しやろうとすると、頭がおかしくなってきます。そのせいでなおさら吹けなくなったり、しまいには、楽器をたたきつけてやりたくなってきます。もちろん実際にたたきつけたりはしないのですが、一回、ほんとにたたきつけられたら、すっきりするだろうなー、と思ってしまいます。
まだまだ、私は修行が足りないのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

ムソルグスキー《展覧会の絵》、《はげ山の一夜》他
指揮:ワレリー・ゲルギエフ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
フィリップス(ユニバーサル・クラシック)UCCP-1053
このCDはゲルギエフとウィーンフィルによるムソルグスキー作品が収録されたものです。。展覧会の絵、ホヴァンシチナ前奏曲、はげ山の一夜、ゴパック、が収録されています。ジャケットを見て思うのですが、ムソルグスキーは、極端に原曲が演奏される機会の少ない作曲家では無いでしょうか。実際、展覧会の絵でも、元はピアノ曲にもかかわらず、いつの間にかラヴェルの編曲したオケ版のほうが多く演奏されるようになってしまい、はげ山の一夜もリムスキー=コルサコフが手をくわえたものが通常演奏されています。
はげ山の一夜は原典版も聞いたことがありますが、そちらのほうが、さらにおどろおどろしく、洗練されていないイメージでした。最後の夜明けの部分も存在しません。あれは後で、リムスキーが補筆して書き加えたものです。
さて、このCD多分、メインは「展覧会の絵」なのでしょうが、この展覧会の絵は割りと、テンポが早めに取られています。あと、盛り上がりの激しさも、かなりのものです。部分的には粗さを感じなくも無いのですが、それはそれで、味ともいるかもしれません。キエフの大門の前は隙間がなく続けられています。また、古城は他がテンポが速めな割にはゆったりとしたテンポとりがなされています。キエフの例の二分音符は一続きの旋律に扱われていますが、ティンパニの強奏によって分断されているようにも聞こえます。特筆すべきはやはりウィーンフィル独特の弦の響きと、ホルンの響きかもしれません。熱い感じの展覧会です。
ムソルグスキーの作品を聞いてみたい方、熱い展覧会を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
州崎寺に向けての、そして秋のアンサンブルコンサートに向けての練習も佳境に入ってくる時期ですが…。
さて、 楽譜に書いてあることは、作曲者や編曲者としてはやってほしいことを記号化して書いているので、そのとおりやらなければならないのですが、作曲家や編曲者によっては、楽器の特性を理解していないと思われる楽譜を平気で書いてしまう人もいます。この楽器の特性を理解している、いないは、吹ける、吹けないのレベルの話ではなく、最終的には楽器を効果的に鳴らす、あるいは響きや効果を際立たせる、というところにかかわってきます。サックスという楽器は吹奏楽をやっている人にはなじみが深いのですが、オケやピアノ一筋で来た人ににとっては未知の楽器だったりします。あの、ラヴェルやドビュッシーでさえ、サクソフォーンの音域や特性を理解していなかったと言われています。もっとも、時代が時代だったので、仕方ない、と言えるのかもしれませんが。
しかし吹けないところがあると、自分で自分に腹が立ってきます。テンポを落としても、指が引っかかる、テンポを上げていくと、指が転ぶ…。最初のうちはがんばって根性入れてやってますが、同じところを一時間、二時間の長丁場でできるまで繰り返しやろうとすると、頭がおかしくなってきます。そのせいでなおさら吹けなくなったり、しまいには、楽器をたたきつけてやりたくなってきます。もちろん実際にたたきつけたりはしないのですが、一回、ほんとにたたきつけられたら、すっきりするだろうなー、と思ってしまいます。
まだまだ、私は修行が足りないのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

ムソルグスキー《展覧会の絵》、《はげ山の一夜》他
指揮:ワレリー・ゲルギエフ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
フィリップス(ユニバーサル・クラシック)UCCP-1053
このCDはゲルギエフとウィーンフィルによるムソルグスキー作品が収録されたものです。。展覧会の絵、ホヴァンシチナ前奏曲、はげ山の一夜、ゴパック、が収録されています。ジャケットを見て思うのですが、ムソルグスキーは、極端に原曲が演奏される機会の少ない作曲家では無いでしょうか。実際、展覧会の絵でも、元はピアノ曲にもかかわらず、いつの間にかラヴェルの編曲したオケ版のほうが多く演奏されるようになってしまい、はげ山の一夜もリムスキー=コルサコフが手をくわえたものが通常演奏されています。
はげ山の一夜は原典版も聞いたことがありますが、そちらのほうが、さらにおどろおどろしく、洗練されていないイメージでした。最後の夜明けの部分も存在しません。あれは後で、リムスキーが補筆して書き加えたものです。
さて、このCD多分、メインは「展覧会の絵」なのでしょうが、この展覧会の絵は割りと、テンポが早めに取られています。あと、盛り上がりの激しさも、かなりのものです。部分的には粗さを感じなくも無いのですが、それはそれで、味ともいるかもしれません。キエフの大門の前は隙間がなく続けられています。また、古城は他がテンポが速めな割にはゆったりとしたテンポとりがなされています。キエフの例の二分音符は一続きの旋律に扱われていますが、ティンパニの強奏によって分断されているようにも聞こえます。特筆すべきはやはりウィーンフィル独特の弦の響きと、ホルンの響きかもしれません。熱い感じの展覧会です。
ムソルグスキーの作品を聞いてみたい方、熱い展覧会を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月09日
まったりできれば…。
今日は土曜日出勤。一ヶ月に1回程度ですが、土曜日に出勤しなければならない火があります。
まあ、代休が取れるのですが、一週間のうち、残業をしまくった上に、土曜日まで出勤すると、やっぱり疲れます。ゆったり、まったりといきたいのですが、そうもできません。土日はほとんどアンサンブルの練習が入っていますので、そんな余裕はまったくありません。
まったり、と言う言葉ですが、昔はそんなに使われていなかった言葉ではないでしょうか?あの、広辞苑にのったのも、第五版以降のようです。どうも語源は京都弁で「とろんと穏やかな口当たり」という、食感を表す言葉だったようです。また、「美味し○ぼ」と言うマンガがその普及の原点だったようです。この「美味○んぼ」はちょうど10数年前にもっとも流行したものなので、ちょうど、まったり、と言う言葉が社会の表舞台に登場したころと一致しています。
しかし、まったり、なんとも京都弁らしい響きの言葉だなあ、と思ってしまいます。世間の人に普通に使われるよりはできれば、京都の人に使ってもらいたい気もします。
そこで今日の一枚です。

FINO/BOSSA NOVA MAR
小野リサ他
BMGファンハウス BVC2-31006
このCDはボサ・ノヴァをテーマに10万枚以上のセールスを記録したヒット・シリーズの第2弾です。多分今は第四弾ぐらいまで出ているかと思います。
私は思うのですが、ボサ・ノヴァはなぜかまったり、というイメージに合う音楽のような気がします。特に夏の暑い日に、風の通るカフェで、ゆったりと過ごすようなさまを想像すると、いかにもまったり過ごす、という言葉がぴったりくるのではないでしょうか?
アーティストも、小野リサをはじめとして、カルロス・ジョビン、など、ボサ・ノヴァにとっては超一流な人たちのオムニバスになっています。
夏の蒸し暑い昼下がり、ちょっと風通しのよい木陰で、ゆったりしながら聴きたい音楽です。
これからの暑いシーズン、BGMとして聴く音楽をお探しの方にオススメの一枚です。
まあ、代休が取れるのですが、一週間のうち、残業をしまくった上に、土曜日まで出勤すると、やっぱり疲れます。ゆったり、まったりといきたいのですが、そうもできません。土日はほとんどアンサンブルの練習が入っていますので、そんな余裕はまったくありません。
まったり、と言う言葉ですが、昔はそんなに使われていなかった言葉ではないでしょうか?あの、広辞苑にのったのも、第五版以降のようです。どうも語源は京都弁で「とろんと穏やかな口当たり」という、食感を表す言葉だったようです。また、「美味し○ぼ」と言うマンガがその普及の原点だったようです。この「美味○んぼ」はちょうど10数年前にもっとも流行したものなので、ちょうど、まったり、と言う言葉が社会の表舞台に登場したころと一致しています。
しかし、まったり、なんとも京都弁らしい響きの言葉だなあ、と思ってしまいます。世間の人に普通に使われるよりはできれば、京都の人に使ってもらいたい気もします。
そこで今日の一枚です。

FINO/BOSSA NOVA MAR
小野リサ他
BMGファンハウス BVC2-31006
このCDはボサ・ノヴァをテーマに10万枚以上のセールスを記録したヒット・シリーズの第2弾です。多分今は第四弾ぐらいまで出ているかと思います。
私は思うのですが、ボサ・ノヴァはなぜかまったり、というイメージに合う音楽のような気がします。特に夏の暑い日に、風の通るカフェで、ゆったりと過ごすようなさまを想像すると、いかにもまったり過ごす、という言葉がぴったりくるのではないでしょうか?
アーティストも、小野リサをはじめとして、カルロス・ジョビン、など、ボサ・ノヴァにとっては超一流な人たちのオムニバスになっています。
夏の蒸し暑い昼下がり、ちょっと風通しのよい木陰で、ゆったりしながら聴きたい音楽です。
これからの暑いシーズン、BGMとして聴く音楽をお探しの方にオススメの一枚です。
2008年08月08日
アンサンブル、カルテット。
今日は少し曇り空。それでも非常に蒸し暑い日となりました。
先日、親が、手動の氷かき機を買ってきました。一緒に抹茶・苺・メロンのみつも買ってきたので、時々家でカキ氷をしています。
さて、先日ラージアンサンブルの練習も3回目を迎え、州崎寺の本番も近づいてきました。カルテットの練習もボチボチ佳境に入ってくることになります。カルテットは、サクソフォーンアンサンブルの中で最もバランスがとれ、レパートリーも多く、また、やりがいのある曲が多いのも事実。
現在練習している曲は州崎寺、秋のアンサンブルコンサートに向けてのものですが、なかなか個人練習も足りず、ボチボチやばくなってきています。
そこでで今日の一枚。
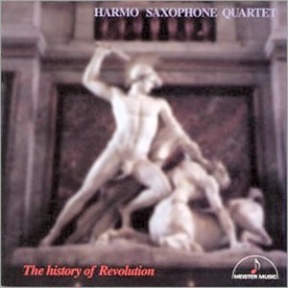
アルモ・サクソフォーン・クァルテット
革命児
Meister Music MM-1026
このCDはアルモ・サクソフォーン・クァルテットによる、5枚目のアルバムです。ピアソラの曲をはじめとして、委嘱作品などが収録されています。
曲目は、チン=チン (ピアソラ) 、天使のミロンガ (ピアソラ) 、N.R.の肖像(上野耕路、委嘱作品) 、ヴァリアシオン・ディアパソン〈Laをめぐるズレの変奏曲〉 (ロベール、委嘱作品) 、組曲 (フランセ) 、グノシェンヌ第1番 (サティ)となっています。
すばらしい演奏で、中村節、アルモ節、が十分に堪能できる演奏となっています。
サクソフォーンアンサンブルに興味のある方、中高生でサックスを吹いている方たちにオススメの一枚です。
先日、親が、手動の氷かき機を買ってきました。一緒に抹茶・苺・メロンのみつも買ってきたので、時々家でカキ氷をしています。
さて、先日ラージアンサンブルの練習も3回目を迎え、州崎寺の本番も近づいてきました。カルテットの練習もボチボチ佳境に入ってくることになります。カルテットは、サクソフォーンアンサンブルの中で最もバランスがとれ、レパートリーも多く、また、やりがいのある曲が多いのも事実。
現在練習している曲は州崎寺、秋のアンサンブルコンサートに向けてのものですが、なかなか個人練習も足りず、ボチボチやばくなってきています。
そこでで今日の一枚。
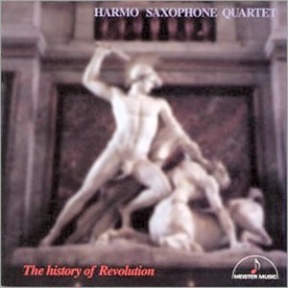
アルモ・サクソフォーン・クァルテット
革命児
Meister Music MM-1026
このCDはアルモ・サクソフォーン・クァルテットによる、5枚目のアルバムです。ピアソラの曲をはじめとして、委嘱作品などが収録されています。
曲目は、チン=チン (ピアソラ) 、天使のミロンガ (ピアソラ) 、N.R.の肖像(上野耕路、委嘱作品) 、ヴァリアシオン・ディアパソン〈Laをめぐるズレの変奏曲〉 (ロベール、委嘱作品) 、組曲 (フランセ) 、グノシェンヌ第1番 (サティ)となっています。
すばらしい演奏で、中村節、アルモ節、が十分に堪能できる演奏となっています。
サクソフォーンアンサンブルに興味のある方、中高生でサックスを吹いている方たちにオススメの一枚です。
2008年08月07日
懐かしくも新しい。
今日も熱い一日となりました。香川県では水不足に向かってまっしぐら。8月の後半に向けて本当に心配です。
先日、予約注文していたCDが届きました。私は滅多に予約してCDを買うことはないのですが、このCDは是非手に入れたかったので、予約して注文しました。
さて、最近、昔のレコードの音源や、CDの音源などを復刻して再販したり、新しくリリースしたりということをよく目にするようになりました。
手に入らなかった音源が突然、新譜として手に入ったりするので嬉しい限りなのですが、もしかして音楽業界、優良なコンテンツが枯渇していて、古いけれども良い音源を復刻しているのではないかと思ったりすることもあります。
どうも、CD自体はダウンロードという形態が主流になりつつある現在、売れる気配がないようですが…。
まあ、私としては、復刻された音源を手に入れて、オークションなどで旧盤の中古にべらぼうな値段をつけている業者を笑ってやりたい気分もありますが…。
そこで今日の一枚です。

映画「マルサの女」オリジナル・サウンドトラック/本多俊之
富士キネマ
FJCM-001
このCDは伊丹十三監督作品史上最高傑作とも言われる、「マルサの女」のオリジナル・サウンドトラックです。1987年に公開された、○○の女シリーズの第一弾でもあります。よくよく考えると、今から既に20年以上前の作品です。音楽は本多俊之氏が手がけ、彼自身もソプラノサックスで、演奏に参加しています。すばらしい音色と音楽性、抜群のテクニックです。当然、CDは絶版となり、オークションなどで中古にも数千円という値段が付けられたりしていました。今回は紙ジャケット使用でのリマスター、復刻となっています。
この音楽はいまだにテレビ番組のBGMに使われたりしていることを見ても判るように色あせない存在感を持っています。
ガサいれ、捜査といったシーンでよく流れている音楽です。
マルサの女のサントラを手に入れたい方、本多俊之の音楽を楽しんでみたい方にオススメの一枚。
先日、予約注文していたCDが届きました。私は滅多に予約してCDを買うことはないのですが、このCDは是非手に入れたかったので、予約して注文しました。
さて、最近、昔のレコードの音源や、CDの音源などを復刻して再販したり、新しくリリースしたりということをよく目にするようになりました。
手に入らなかった音源が突然、新譜として手に入ったりするので嬉しい限りなのですが、もしかして音楽業界、優良なコンテンツが枯渇していて、古いけれども良い音源を復刻しているのではないかと思ったりすることもあります。
どうも、CD自体はダウンロードという形態が主流になりつつある現在、売れる気配がないようですが…。
まあ、私としては、復刻された音源を手に入れて、オークションなどで旧盤の中古にべらぼうな値段をつけている業者を笑ってやりたい気分もありますが…。
そこで今日の一枚です。

映画「マルサの女」オリジナル・サウンドトラック/本多俊之
富士キネマ
FJCM-001
このCDは伊丹十三監督作品史上最高傑作とも言われる、「マルサの女」のオリジナル・サウンドトラックです。1987年に公開された、○○の女シリーズの第一弾でもあります。よくよく考えると、今から既に20年以上前の作品です。音楽は本多俊之氏が手がけ、彼自身もソプラノサックスで、演奏に参加しています。すばらしい音色と音楽性、抜群のテクニックです。当然、CDは絶版となり、オークションなどで中古にも数千円という値段が付けられたりしていました。今回は紙ジャケット使用でのリマスター、復刻となっています。
この音楽はいまだにテレビ番組のBGMに使われたりしていることを見ても判るように色あせない存在感を持っています。
ガサいれ、捜査といったシーンでよく流れている音楽です。
マルサの女のサントラを手に入れたい方、本多俊之の音楽を楽しんでみたい方にオススメの一枚。
2008年08月06日
楽譜、レンタル譜に怒。
さて、先日楽譜をコピーしました。コピーするといっても、普通に売っている楽譜をコピーすると、違法になりますが、我々が、依頼して書いてもらった楽譜を、書いた人の許可の下コピーしているので、間違いなく合法です。
話は少し変わりますが、楽譜は実に廃盤、絶版になるのが早いもののひとつです。初期ロットがなくなっても増刷しない、ということが普通にあります。だから、あの曲をやりたい、と思ってあわてて楽譜を探しても、そのときはすでに幻の楽譜、ということがたびたびあります。楽譜は出たときに買っておくのが鉄則なのでしょうか。しかしながら、アンサンブルの楽譜などは実に値段が高く設定されています。たかが演奏時間五分程度のカルテットの楽譜が一万円以上することもあります。出たときにすぐに買う、というわけにも行かない金額です。このことが逆に違法コピーを産んでいるような気もするのですが。できるだけ、長い間安価で出版し続けてもらえると、ユーザーとしてはありがたいのです。
コピーに対するオリジナルの保護、という面では常にいたちごっこが繰り広げられています。音楽CDもしかりなのですが、延々繰り返されるこのいたちごっこはなにか根本的な解決がないと、終わることは無いと思います。今のようにCCCDなんかで対処していてはユーザーの数を減らすだけで、何の解決にもなっていません。
楽譜の中で、レンタル譜、というあこぎな商法もあります。(言っておきますが、すべてがあこぎではないし、法律的にもレンタル譜は何の問題もありません)楽譜を貸す、ということなのですが、その楽譜はレンタルでのみ演奏が可能で、演奏回数や、試用期間などに期限がある、というシステムです。なぜか、レンタルで著作権などが保護されている上に、楽譜の印刷が不要なのにもかかわらず、売り譜よりも高額なことが多いのです。ユーザーにしてみれば、どうしても演奏したい曲ならば、借りるしかないのですが、高額なお金を払っても、財産としては残らない上に、楽譜を借りなければ、二度とその曲は演奏できません。一部、良心的な価格設定の場合もありますが、ほとんどは、なぜか「管理費が高くつく」という名目で、レンタル料が高額です。管理費が高くつくのならいっそのこと出版してくれ、と思うのですが、実情はレンタル譜のほうが違法コピーを防げる上に、出版譜の何倍も儲かる、ということが理由のようです。
こうやって見てみると、レンタル譜という産業は一部のお金持ちしか相手にしない、音楽振興なんかとは程遠い産業に見えてきます。実際、吹奏楽コンクールの自由曲などとしてはやると、たくさんの学校がレンタルするわけですが、大抵、10分足らずの曲を演奏するがために、ひどい場合は10万円近く払う必要があります。しかも、期限が過ぎるか、演奏回数が過ぎるかすると、返却しなければなりません。
私はレンタル譜にするならば、少なくとも、売り譜よりも値段が上がることの無いようにするべきだと思っています。出版社によってはよく売れる楽譜を突然レンタルにしたりするさらにあこぎなことを行っているところもあります。
そこで今日の一枚です。
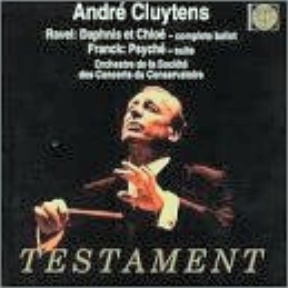
ANDRE CLUYTENS Conducts
Ravel:Daphnis et Chloe
指揮:アンドレ・クリュイタンス
パリ音楽院管弦楽団
TESTAMENT SBT 1128
このCDは巨匠クリュイタンスによるラヴェルの「ダフニスとクロエ」全曲が収録されたものです。一緒に収録されているのはフランクの交響詩「プシュケ」です。残念ながら名盤との誉れが高い東京公演のライブではありません。
実は、この通称ダフクロこれまた、楽譜がレンタルなのです。人気曲だけあってか、様々なアレンジのものが存在するようですが、大抵、レンタル代金は3万円~7万円程度です。中学校や高校では、これをコンクールの演奏に使うがために借りるところがあるかと思うと、ご愁傷さま、といった感じでしょうか。レンタル代、高すぎます。安い楽器が何か買えます。
演奏のほうは巨匠クリュイタンス、そしてパリ音楽院。演奏者の名人芸を殺すことなく、適度に手綱を緩めながら、全体の響きをまとめている印象です。ラヴェルの演奏にしては
旋律がわかりやすいのも特徴かもしれません。実はこの曲はほかにデュトワ盤なども持っているのですが、全体のラヴェルらしい雰囲気ではデュトワ盤、そして、旋律の歌い方や、管楽器の演奏クオリティの高さではクリュイタンス盤といったところでしょうか。
ダフクロ好きなすべての方に、フランス人によるフランス音楽の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
11.か
話は少し変わりますが、楽譜は実に廃盤、絶版になるのが早いもののひとつです。初期ロットがなくなっても増刷しない、ということが普通にあります。だから、あの曲をやりたい、と思ってあわてて楽譜を探しても、そのときはすでに幻の楽譜、ということがたびたびあります。楽譜は出たときに買っておくのが鉄則なのでしょうか。しかしながら、アンサンブルの楽譜などは実に値段が高く設定されています。たかが演奏時間五分程度のカルテットの楽譜が一万円以上することもあります。出たときにすぐに買う、というわけにも行かない金額です。このことが逆に違法コピーを産んでいるような気もするのですが。できるだけ、長い間安価で出版し続けてもらえると、ユーザーとしてはありがたいのです。
コピーに対するオリジナルの保護、という面では常にいたちごっこが繰り広げられています。音楽CDもしかりなのですが、延々繰り返されるこのいたちごっこはなにか根本的な解決がないと、終わることは無いと思います。今のようにCCCDなんかで対処していてはユーザーの数を減らすだけで、何の解決にもなっていません。
楽譜の中で、レンタル譜、というあこぎな商法もあります。(言っておきますが、すべてがあこぎではないし、法律的にもレンタル譜は何の問題もありません)楽譜を貸す、ということなのですが、その楽譜はレンタルでのみ演奏が可能で、演奏回数や、試用期間などに期限がある、というシステムです。なぜか、レンタルで著作権などが保護されている上に、楽譜の印刷が不要なのにもかかわらず、売り譜よりも高額なことが多いのです。ユーザーにしてみれば、どうしても演奏したい曲ならば、借りるしかないのですが、高額なお金を払っても、財産としては残らない上に、楽譜を借りなければ、二度とその曲は演奏できません。一部、良心的な価格設定の場合もありますが、ほとんどは、なぜか「管理費が高くつく」という名目で、レンタル料が高額です。管理費が高くつくのならいっそのこと出版してくれ、と思うのですが、実情はレンタル譜のほうが違法コピーを防げる上に、出版譜の何倍も儲かる、ということが理由のようです。
こうやって見てみると、レンタル譜という産業は一部のお金持ちしか相手にしない、音楽振興なんかとは程遠い産業に見えてきます。実際、吹奏楽コンクールの自由曲などとしてはやると、たくさんの学校がレンタルするわけですが、大抵、10分足らずの曲を演奏するがために、ひどい場合は10万円近く払う必要があります。しかも、期限が過ぎるか、演奏回数が過ぎるかすると、返却しなければなりません。
私はレンタル譜にするならば、少なくとも、売り譜よりも値段が上がることの無いようにするべきだと思っています。出版社によってはよく売れる楽譜を突然レンタルにしたりするさらにあこぎなことを行っているところもあります。
そこで今日の一枚です。
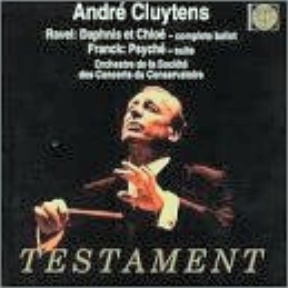
ANDRE CLUYTENS Conducts
Ravel:Daphnis et Chloe
指揮:アンドレ・クリュイタンス
パリ音楽院管弦楽団
TESTAMENT SBT 1128
このCDは巨匠クリュイタンスによるラヴェルの「ダフニスとクロエ」全曲が収録されたものです。一緒に収録されているのはフランクの交響詩「プシュケ」です。残念ながら名盤との誉れが高い東京公演のライブではありません。
実は、この通称ダフクロこれまた、楽譜がレンタルなのです。人気曲だけあってか、様々なアレンジのものが存在するようですが、大抵、レンタル代金は3万円~7万円程度です。中学校や高校では、これをコンクールの演奏に使うがために借りるところがあるかと思うと、ご愁傷さま、といった感じでしょうか。レンタル代、高すぎます。安い楽器が何か買えます。
演奏のほうは巨匠クリュイタンス、そしてパリ音楽院。演奏者の名人芸を殺すことなく、適度に手綱を緩めながら、全体の響きをまとめている印象です。ラヴェルの演奏にしては
旋律がわかりやすいのも特徴かもしれません。実はこの曲はほかにデュトワ盤なども持っているのですが、全体のラヴェルらしい雰囲気ではデュトワ盤、そして、旋律の歌い方や、管楽器の演奏クオリティの高さではクリュイタンス盤といったところでしょうか。
ダフクロ好きなすべての方に、フランス人によるフランス音楽の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
11.か
2008年08月05日
さわやかな涼を。
今日もギンギンの夏模様。
今年の夏は特に暑い夏となっています。いや、最近この話題しかないのかと言われそうですが…実際、この話題しかないほど暑い日が続いています。8月初旬とはいえ、この暑さは酷暑、猛暑であることに間違いはありません。
昔は良くしたもので、打ち水をしたり、すだれを使ったり、あるいは風鈴をつるして気分で涼めるようにしたりと、様々な工夫がなされていました。ところが現代、エアコンに頼りっきりの人がほとんど。屋上の緑地化など様々な工夫もなされてはいるようですが、もっと粋でさわやかな涼しさを感じたいものです。
そこで今日の一枚です。

シベリウス/交響曲第一番&カレリア序曲・組曲
指揮:ユージン・オーマンディ
フィラデルフィア管弦楽団
BMGファンハウス BVCC-38132
このCDはオーマンディ、フィラデルフィアの黄金サウンドによるシベリウスです。オーマンディは作曲者であるシベリウスとも親交があったといわれています。
シベリウスといえば、北欧の音楽。澄み切った空気の冷えた空気をイメージさせます。
実はこの中のカレリア組曲、演奏会のプログラムの中の一曲です。いぜん、このコーナーでもサラステ盤のCDをしょうかいしました。こちらのカレリアはサラステ盤にくらべ、スケールが大きくフィラデルフィアサウンドといわれる音の方向性も加わって、少し明るい感じがします。オーマンディ自身は楽譜に多少手を加えているようです。カレリアのバラードではホルンの配置も工夫がなされていて、あたかもエコーのように左右から聞こえるようになっています。
シベリウス自身もオーマンディによる演奏を高く評価していたようです。
黄金のフィラデルフィアサウンドがお好きな方、オーマンディによるシベリウスを聞いてみたい方、フィンランドの香りを楽しみたい方にオススメの一枚です。
16.い
今年の夏は特に暑い夏となっています。いや、最近この話題しかないのかと言われそうですが…実際、この話題しかないほど暑い日が続いています。8月初旬とはいえ、この暑さは酷暑、猛暑であることに間違いはありません。
昔は良くしたもので、打ち水をしたり、すだれを使ったり、あるいは風鈴をつるして気分で涼めるようにしたりと、様々な工夫がなされていました。ところが現代、エアコンに頼りっきりの人がほとんど。屋上の緑地化など様々な工夫もなされてはいるようですが、もっと粋でさわやかな涼しさを感じたいものです。
そこで今日の一枚です。

シベリウス/交響曲第一番&カレリア序曲・組曲
指揮:ユージン・オーマンディ
フィラデルフィア管弦楽団
BMGファンハウス BVCC-38132
このCDはオーマンディ、フィラデルフィアの黄金サウンドによるシベリウスです。オーマンディは作曲者であるシベリウスとも親交があったといわれています。
シベリウスといえば、北欧の音楽。澄み切った空気の冷えた空気をイメージさせます。
実はこの中のカレリア組曲、演奏会のプログラムの中の一曲です。いぜん、このコーナーでもサラステ盤のCDをしょうかいしました。こちらのカレリアはサラステ盤にくらべ、スケールが大きくフィラデルフィアサウンドといわれる音の方向性も加わって、少し明るい感じがします。オーマンディ自身は楽譜に多少手を加えているようです。カレリアのバラードではホルンの配置も工夫がなされていて、あたかもエコーのように左右から聞こえるようになっています。
シベリウス自身もオーマンディによる演奏を高く評価していたようです。
黄金のフィラデルフィアサウンドがお好きな方、オーマンディによるシベリウスを聞いてみたい方、フィンランドの香りを楽しみたい方にオススメの一枚です。
16.い
2008年08月04日
何かが起こる?のか。
今日も暑い一日です。7月から異常なぐらい暑い日が続いています。先日かなり激しい夕立と雷がありました。雷が激しくなると、PCは電源を落としてコンセントから抜くことになるので、作業ができなくなったりします。実はPCだけでなく、ICチップが使われている最近の家電はすべて雷にやられてしまう可能性があるので、コンセントを抜いたほうがよいそうです。もしくはサージバスターという、雷対策の機会をコンセントに取り付けるなどの対策が必要だとか。私は不意の雷に備えて、PCの電源にはサージバスター機能のついたタップを使っていますが、オーディオのほうは無防備です。どちらかというと、オーディオの方が値段的にも高級で、真空管なども使われているので、本当はそちらを気にしないといけないのかも知れません。
さて、我が家の母親は、天候が不順になると、すぐに、「地震が来るほど○○」という表現を使います。○○にはたとえば、「冬なのに暖かい日が続く、」とか、「一向に暑くない」などという言葉が続きます。天候不順が天変地異の前触れ、ということでしょうか?まさかそんなことは起こらないと思うのですが。
そこで今日の一枚です。

オルフ/世俗カンタータ「カルミナブラーナ」
ORFF/CAMINA BURANA
指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット
サンフランシスコ交響楽団
リン・ドーソン(ソプラノ)、
ジョン・ダニエッキ(テノール)、
ケヴィン・マクミラン(バリトン)
サンフランシスコ少女合唱団
サンフランシスコ少年合唱団
サンフランシスコ交響合唱団
LONDON(ポリドール)POCL-5100
このCDはブロムシュテットによるカルミナブラーナが収録されたものです。ブロムシュテット氏といえば、以前、NHK交響楽団などを指揮したりもしていました。
もともと「カルミナ・ブラーナ」とは、元々中世の詩歌集で、その中のいくつかはネウマ譜(ネウマとは中世の単旋律歌曲の記譜で使われた記号。旋律の動きや演奏上のニュアンスを視覚的に示そうとしたもの。ネウマを使った記譜法をネウマ譜といいます。9世紀ごろ現れ、音高を明示しないネウマ、音高ネウマ(ダイアステマ記譜法)を経て、やがて11世紀から譜線ネウマへと移行していきます。)もついているといいます。内容は自然讃美、愛の歌などをはじめ、酒や賭け事といったもの、諷刺ミサまであるらしく、反道徳的な側面もあるようです。このオルフの作品は、一応、筋が通るように歌を選んでいるようなのですが、原曲は特には筋もないのだそうです。
最近ではこのカルミナブラーナ、コマーシャルを初めとしてテレビ番組で耳にするようになりました。特に「衝撃の映像!」といった感じの場面ではよく流れます。それまで決然としたような場面では、お決まりのようにベートーヴェンの「運命」の冒頭が流れることが多かったのですが、最近は「カルミナ・ブラーナ」の第1曲目の冒頭が、よくBGMとして流れたりします。
演奏のほうは…もう少しいろいろやってほしかった感じもあります。なぜかブロムシュテットという方はしきしやとして、個性に欠けている気もします。逆にその中庸さ加減が、個性なのかもしれません。ある意味模範的ともいえますが、少し面白くないと感じることもあります。
ちなみにこのCD、何気にジャケットのつづりが間違っています。「CARMINA BURABA」(カルミ・ナブラーバ)と書かれています。(後にさいはんされたときは訂正されているようです。)
CMなどで最近よく聞くカルミ・ナブラーナという曲を聴いてみたい方、合唱とオケの融合した形の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、我が家の母親は、天候が不順になると、すぐに、「地震が来るほど○○」という表現を使います。○○にはたとえば、「冬なのに暖かい日が続く、」とか、「一向に暑くない」などという言葉が続きます。天候不順が天変地異の前触れ、ということでしょうか?まさかそんなことは起こらないと思うのですが。
そこで今日の一枚です。

オルフ/世俗カンタータ「カルミナブラーナ」
ORFF/CAMINA BURANA
指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット
サンフランシスコ交響楽団
リン・ドーソン(ソプラノ)、
ジョン・ダニエッキ(テノール)、
ケヴィン・マクミラン(バリトン)
サンフランシスコ少女合唱団
サンフランシスコ少年合唱団
サンフランシスコ交響合唱団
LONDON(ポリドール)POCL-5100
このCDはブロムシュテットによるカルミナブラーナが収録されたものです。ブロムシュテット氏といえば、以前、NHK交響楽団などを指揮したりもしていました。
もともと「カルミナ・ブラーナ」とは、元々中世の詩歌集で、その中のいくつかはネウマ譜(ネウマとは中世の単旋律歌曲の記譜で使われた記号。旋律の動きや演奏上のニュアンスを視覚的に示そうとしたもの。ネウマを使った記譜法をネウマ譜といいます。9世紀ごろ現れ、音高を明示しないネウマ、音高ネウマ(ダイアステマ記譜法)を経て、やがて11世紀から譜線ネウマへと移行していきます。)もついているといいます。内容は自然讃美、愛の歌などをはじめ、酒や賭け事といったもの、諷刺ミサまであるらしく、反道徳的な側面もあるようです。このオルフの作品は、一応、筋が通るように歌を選んでいるようなのですが、原曲は特には筋もないのだそうです。
最近ではこのカルミナブラーナ、コマーシャルを初めとしてテレビ番組で耳にするようになりました。特に「衝撃の映像!」といった感じの場面ではよく流れます。それまで決然としたような場面では、お決まりのようにベートーヴェンの「運命」の冒頭が流れることが多かったのですが、最近は「カルミナ・ブラーナ」の第1曲目の冒頭が、よくBGMとして流れたりします。
演奏のほうは…もう少しいろいろやってほしかった感じもあります。なぜかブロムシュテットという方はしきしやとして、個性に欠けている気もします。逆にその中庸さ加減が、個性なのかもしれません。ある意味模範的ともいえますが、少し面白くないと感じることもあります。
ちなみにこのCD、何気にジャケットのつづりが間違っています。「CARMINA BURABA」(カルミ・ナブラーバ)と書かれています。(後にさいはんされたときは訂正されているようです。)
CMなどで最近よく聞くカルミ・ナブラーナという曲を聴いてみたい方、合唱とオケの融合した形の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月03日
なつ、ナツ、夏。
今日も晴れています。昨日までの曇り空から一転、また夏の暑い日が続きそうです。またばてる日が続きます。
今日は午前中、ダッパー四重奏の練習。ところが、メンバー約一名体調不良のため、3人で練習。おだいじに~。
その後、ちょっとレッスンっぽいことを(私がレッスンできるほどの人ではないことは周知の通りなので…。)させていただいて、
お昼は、その流れで、北浜アリーのイザラムーンにて。
さて、昨日は日中車の洗車をしましたが、Tシャツを絞ったら汗が出るかと思うぐらい汗をかきました。熱中症になりそうです。
やっぱり、夏です。熱いです。しんどくなります。皆さんは夏といえば、何を思い出すでしょうか?夏休み、スイカ、花火、夏祭り、カキ氷、海水浴、マリンレジャー、などは結構定番でしょうか。私のように学生時代に吹奏楽にどっぷりはまっていた人間は、夏といえば、吹奏楽コンクール、と答えるかもしれません。定番もありますが、一口に夏、といってもいろいろあるものです。
しかしながら、やっぱり暑い夏、なつ、ナツ、夏です。
そこで今日の一枚です。

NIAGARA TRIANGLE VOL.1 30th Anniversary Edition
大瀧詠一、伊藤銀次、山下達郎
SONY SRCL-5005
このCDは、大瀧詠一のナイアガラ構想によるナナイアガラ・トライアングルとは大瀧詠一を中心として3人組(だからトライアングル)で“VOL.1”と“VOL.2”の2度にわたり組まれた企画ものです。(元はコルピックスの「ティーーンエイジ・トライアングル」がヒントとなっています)VOL.1のメンバーは大瀧詠一・山下達郎・伊藤銀次、VOL.2のメンバーは大瀧詠一・杉真理・佐野元春という、そうそうたるメンバーです。こちらはナイアガラ・トライアングルの作品第一弾です。
勿論、リリースされた当初はLPレコードだったのですが、CD化され、さらにこの盤は30th Anniversary Edition として、ボーナストラックが収録されています。因みに、私は何故か全部持っていますが…。
この第一弾は、大滝詠一が彼自身の弟分と制作したコロンビア移籍後初のアルバムとなりました。(しかし、事実上は、最後のアルバムともなってしまいました。)山下達郎プロデュースが4曲、伊藤銀次プロデュースが4曲、大瀧プロデュースが3曲の構成である。(オリジナル盤) 山下の作品は、「ドリーミング・デイ」といい、「パレード」といい、現在の彼の作風にも通じるポップな曲が楽しめる。僕の感覚から言えば、「遅すぎた別れ」は山下の作品としては異色に感じられる。伊藤の作品は、過去のリメイクが中心。「日射病」と「ココナツ・ホリデイ」、「新無頼横町」の3曲は、はっぴいえんどの解散ライヴで既に披露されていた曲を、ニューアレンジでレコーディングされたものです。「幸せにさよなら」は、書き下ろしです。シングルでは、山下達郎と大瀧詠一の両氏も加わって、3人が交代でリード・ヴォーカルを取るという物でした。(CDはボーナスで収録。) それに加え、大滝詠一作品の布谷文夫がリード・ヴォーカルを取った「ナイアガラ音頭」は、ポップスに音頭を取り込むという新しい企画で、アルバム「レッツ・オンド・アゲン」の布石ともなっています。
さて、ここで、なぜこのアルバムが夏なのかというと、やはり、「ナイアガラ音頭」に尽きると思います。そのクオリティーの高さを、こういった形にプロデュースしてしまう、大滝詠一氏の遊び心に心を奪われてしまいます。
夏を明るく、さわやかに過ごしたい方やナイアガラ好きな方にオススメの一枚です。
今日は午前中、ダッパー四重奏の練習。ところが、メンバー約一名体調不良のため、3人で練習。おだいじに~。
その後、ちょっとレッスンっぽいことを(私がレッスンできるほどの人ではないことは周知の通りなので…。)させていただいて、
お昼は、その流れで、北浜アリーのイザラムーンにて。
さて、昨日は日中車の洗車をしましたが、Tシャツを絞ったら汗が出るかと思うぐらい汗をかきました。熱中症になりそうです。
やっぱり、夏です。熱いです。しんどくなります。皆さんは夏といえば、何を思い出すでしょうか?夏休み、スイカ、花火、夏祭り、カキ氷、海水浴、マリンレジャー、などは結構定番でしょうか。私のように学生時代に吹奏楽にどっぷりはまっていた人間は、夏といえば、吹奏楽コンクール、と答えるかもしれません。定番もありますが、一口に夏、といってもいろいろあるものです。
しかしながら、やっぱり暑い夏、なつ、ナツ、夏です。
そこで今日の一枚です。

NIAGARA TRIANGLE VOL.1 30th Anniversary Edition
大瀧詠一、伊藤銀次、山下達郎
SONY SRCL-5005
このCDは、大瀧詠一のナイアガラ構想によるナナイアガラ・トライアングルとは大瀧詠一を中心として3人組(だからトライアングル)で“VOL.1”と“VOL.2”の2度にわたり組まれた企画ものです。(元はコルピックスの「ティーーンエイジ・トライアングル」がヒントとなっています)VOL.1のメンバーは大瀧詠一・山下達郎・伊藤銀次、VOL.2のメンバーは大瀧詠一・杉真理・佐野元春という、そうそうたるメンバーです。こちらはナイアガラ・トライアングルの作品第一弾です。
勿論、リリースされた当初はLPレコードだったのですが、CD化され、さらにこの盤は30th Anniversary Edition として、ボーナストラックが収録されています。因みに、私は何故か全部持っていますが…。
この第一弾は、大滝詠一が彼自身の弟分と制作したコロンビア移籍後初のアルバムとなりました。(しかし、事実上は、最後のアルバムともなってしまいました。)山下達郎プロデュースが4曲、伊藤銀次プロデュースが4曲、大瀧プロデュースが3曲の構成である。(オリジナル盤) 山下の作品は、「ドリーミング・デイ」といい、「パレード」といい、現在の彼の作風にも通じるポップな曲が楽しめる。僕の感覚から言えば、「遅すぎた別れ」は山下の作品としては異色に感じられる。伊藤の作品は、過去のリメイクが中心。「日射病」と「ココナツ・ホリデイ」、「新無頼横町」の3曲は、はっぴいえんどの解散ライヴで既に披露されていた曲を、ニューアレンジでレコーディングされたものです。「幸せにさよなら」は、書き下ろしです。シングルでは、山下達郎と大瀧詠一の両氏も加わって、3人が交代でリード・ヴォーカルを取るという物でした。(CDはボーナスで収録。) それに加え、大滝詠一作品の布谷文夫がリード・ヴォーカルを取った「ナイアガラ音頭」は、ポップスに音頭を取り込むという新しい企画で、アルバム「レッツ・オンド・アゲン」の布石ともなっています。
さて、ここで、なぜこのアルバムが夏なのかというと、やはり、「ナイアガラ音頭」に尽きると思います。そのクオリティーの高さを、こういった形にプロデュースしてしまう、大滝詠一氏の遊び心に心を奪われてしまいます。
夏を明るく、さわやかに過ごしたい方やナイアガラ好きな方にオススメの一枚です。
2008年08月02日
訳がわからない。
今日も熱い一日でした。
さて、昨日、夜に日記を改めて書き込んでいたのですが、途中、PCが固まってしまい、ほぼ、完成していた日記がパーになってしまいました。
そもそも、PCは現在、職場でも家庭でも、大量に稼動しているかと思います。でも、仕事で使うのにPCが止まるというのはどうなんでしょうか。仕事においては信頼性が高くなければならないのですが、フリーズやエラーをよく起こすWin.は問題が多いような気もします。いずれにせよ、データは何が起こるか分からないので、必ずバックアップをとる必要があるとは思うのですが、10年前に使っていたワープロなんかは、フリーズしてデータが飛ぶ、なんてことは絶対にありえませんでした。ハード、ソフト、の違いは有るのかもしれませんが、それにしても今のPCは信頼性が低すぎます。
おまけに、何故止まるのか、理由がわからないことも多いので、不安です。話によると、エラーメッセージが出る時や、画面が真っ青になるときはほとんどがWin.のOSの問題だとか。Win.が欠陥OSだと、度々批判されているのも分かる気がします。
でも、止まってしまうと、普通の人はデータの修復なんか出来ないので、バックアップをとって以降のデータは諦めるしかなくなります。あのブルーの画面に書かれた内容にも意味は有るのでしょうが、ぱっと見た感じ、意味は全く分かりません。しかも、突然起きて、一回PCを再起動すると、何の問題もなかったように動き出します。ますますもって訳がわかりません。
そこで今日の一枚です。

イーストマン・ウインド・アンサンブル/クワイエット・シティ
指揮:ドナルド・ハンスバーガー
CBS/SONY CSCR8180
このCDはイーストマン・ウインドアンサンブルによる20世紀の吹奏楽作品集です。なお、この中のクワイエット・シティはトランペットのウイントン・マルサリスがソリストとして迎えられています。
曲目はトッカータ・マルツィアーレ、吹奏楽のための変奏曲、吹奏楽のための演奏会用音楽、クワイエット・シティ、プラハのための音楽1968という曲目。この中の、プラハのための音楽1968と言う曲を名年か前、高松ウインドシンフォニーで演奏したのですが、まさに訳がわかりませんでした。不協和音と、理解に苦しむ変拍子、メロディー・ラインが曖昧な曲、と言うイメージが今でもあります。かといって調原題曲、というわけでもないのがこれまた曲者で訳がわかりません。
実際、演奏した時にも訳がわからず、かなり苦労しました。1/4音(半音の半分)なんていう、指定があったりもしたので、なおさら意味不明だった記憶があります。
とはいえ、無事に演奏することはできたので、まあ、ちゃんとした曲なんだ、ということは理解できました(笑)。もしかしたら、PCのエラーやブルーバックもそのうち理解できるのでしょうか?うーん、私には無理な気がします。
このCDにはいっている演奏はもちろん、まともに演奏できてます。個人的には、この「プラハ」よりも、ほかに入っている、「クワイエット・シティ」の方がオススメなのですが。
20世紀の吹奏楽音楽を聴いてみたい方、訳のわからないものにもチャレンジしてみたい方にオススメの一枚です。
さて、昨日、夜に日記を改めて書き込んでいたのですが、途中、PCが固まってしまい、ほぼ、完成していた日記がパーになってしまいました。

そもそも、PCは現在、職場でも家庭でも、大量に稼動しているかと思います。でも、仕事で使うのにPCが止まるというのはどうなんでしょうか。仕事においては信頼性が高くなければならないのですが、フリーズやエラーをよく起こすWin.は問題が多いような気もします。いずれにせよ、データは何が起こるか分からないので、必ずバックアップをとる必要があるとは思うのですが、10年前に使っていたワープロなんかは、フリーズしてデータが飛ぶ、なんてことは絶対にありえませんでした。ハード、ソフト、の違いは有るのかもしれませんが、それにしても今のPCは信頼性が低すぎます。
おまけに、何故止まるのか、理由がわからないことも多いので、不安です。話によると、エラーメッセージが出る時や、画面が真っ青になるときはほとんどがWin.のOSの問題だとか。Win.が欠陥OSだと、度々批判されているのも分かる気がします。
でも、止まってしまうと、普通の人はデータの修復なんか出来ないので、バックアップをとって以降のデータは諦めるしかなくなります。あのブルーの画面に書かれた内容にも意味は有るのでしょうが、ぱっと見た感じ、意味は全く分かりません。しかも、突然起きて、一回PCを再起動すると、何の問題もなかったように動き出します。ますますもって訳がわかりません。
そこで今日の一枚です。

イーストマン・ウインド・アンサンブル/クワイエット・シティ
指揮:ドナルド・ハンスバーガー
CBS/SONY CSCR8180
このCDはイーストマン・ウインドアンサンブルによる20世紀の吹奏楽作品集です。なお、この中のクワイエット・シティはトランペットのウイントン・マルサリスがソリストとして迎えられています。
曲目はトッカータ・マルツィアーレ、吹奏楽のための変奏曲、吹奏楽のための演奏会用音楽、クワイエット・シティ、プラハのための音楽1968という曲目。この中の、プラハのための音楽1968と言う曲を名年か前、高松ウインドシンフォニーで演奏したのですが、まさに訳がわかりませんでした。不協和音と、理解に苦しむ変拍子、メロディー・ラインが曖昧な曲、と言うイメージが今でもあります。かといって調原題曲、というわけでもないのがこれまた曲者で訳がわかりません。
実際、演奏した時にも訳がわからず、かなり苦労しました。1/4音(半音の半分)なんていう、指定があったりもしたので、なおさら意味不明だった記憶があります。
とはいえ、無事に演奏することはできたので、まあ、ちゃんとした曲なんだ、ということは理解できました(笑)。もしかしたら、PCのエラーやブルーバックもそのうち理解できるのでしょうか?うーん、私には無理な気がします。
このCDにはいっている演奏はもちろん、まともに演奏できてます。個人的には、この「プラハ」よりも、ほかに入っている、「クワイエット・シティ」の方がオススメなのですが。
20世紀の吹奏楽音楽を聴いてみたい方、訳のわからないものにもチャレンジしてみたい方にオススメの一枚です。
2008年08月01日
そういえば台風が来ない。
今日から八月。ますます暑い日が続いています。さて、今年はあまり台風が来ている様子がありません。台風で、香川では大きな被害は無いことが多いのですが、普段水不足を気にしている分、逆に大雨には弱い県のような気がします。
まあ、雨が降らずに水不足になるのも困るので、雨は必要なのですが、今回の台風で、しばらくは水不足の心配は必要なさそうです。香川県はため池の多い県として知られていますが、現在はかなりの水資源を四国のほかの県に頼っています。ですので、香川県だけに雨が降っても水不足が改善されず、水不足の改善のためには、高知や徳島といった隣県に雨が降ってくれなければならないのです。
でも、やはり、台風がいった後はカラッとしたいい天気、台風一過となってほしいと思うのです。
そこで今日の一枚です。
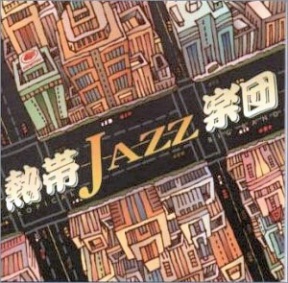
熱帯JAZZ楽団(TROPICAL JAZZ BIG BAND)3
My Favorite
ビクターエンターテインメント VICJ-6039
このCDはカルロス菅野氏が、主催するTOROPICAL BIG BANNDOのアルバム第3弾です。やっぱり、カラッとした天気暑い夏、といえばラテンを思い出してしまいます。そして、やっぱり、暑い、熱い、といえば、熱帯JAZZ楽団の音楽です。
曲はエポカ・デ・オロ、マイ・フェイヴァリット・シングス、ガット・トゥ・ビー・リアル、シング・シング・シング、ポル・ケ・ノロックス、ビター・スウィート・ボンバ(ビター・スウィート・サンバ)、ルイナス、チェリー・ピンク・アンド・アップル・ブロッサム・ホワイト、愛さずにはいられない、プレンデ・エル・フエゴ という、11曲です。
マイ・フェイヴァリット・シングスや、シング・シング・シングという、ジャズにとってはスタンダードな曲もラテンアレンジされ、熱帯JAZZらしい演奏になっています。私のお気に入りは(本当の意味でのマイ・フェイバリット・シングス?)は、やはりシング・シング・シングです。
JAZZのスタンダードをラテンらしい熱さで聞いてみたい方、また、暑い夏をカラッとより暑くすごしたい方にオススメの一枚です。
まあ、雨が降らずに水不足になるのも困るので、雨は必要なのですが、今回の台風で、しばらくは水不足の心配は必要なさそうです。香川県はため池の多い県として知られていますが、現在はかなりの水資源を四国のほかの県に頼っています。ですので、香川県だけに雨が降っても水不足が改善されず、水不足の改善のためには、高知や徳島といった隣県に雨が降ってくれなければならないのです。
でも、やはり、台風がいった後はカラッとしたいい天気、台風一過となってほしいと思うのです。
そこで今日の一枚です。
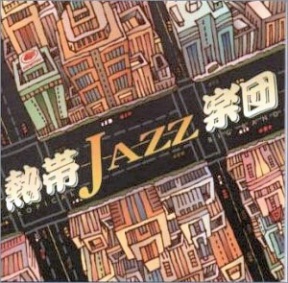
熱帯JAZZ楽団(TROPICAL JAZZ BIG BAND)3
My Favorite
ビクターエンターテインメント VICJ-6039
このCDはカルロス菅野氏が、主催するTOROPICAL BIG BANNDOのアルバム第3弾です。やっぱり、カラッとした天気暑い夏、といえばラテンを思い出してしまいます。そして、やっぱり、暑い、熱い、といえば、熱帯JAZZ楽団の音楽です。
曲はエポカ・デ・オロ、マイ・フェイヴァリット・シングス、ガット・トゥ・ビー・リアル、シング・シング・シング、ポル・ケ・ノロックス、ビター・スウィート・ボンバ(ビター・スウィート・サンバ)、ルイナス、チェリー・ピンク・アンド・アップル・ブロッサム・ホワイト、愛さずにはいられない、プレンデ・エル・フエゴ という、11曲です。
マイ・フェイヴァリット・シングスや、シング・シング・シングという、ジャズにとってはスタンダードな曲もラテンアレンジされ、熱帯JAZZらしい演奏になっています。私のお気に入りは(本当の意味でのマイ・フェイバリット・シングス?)は、やはりシング・シング・シングです。
JAZZのスタンダードをラテンらしい熱さで聞いてみたい方、また、暑い夏をカラッとより暑くすごしたい方にオススメの一枚です。




