2008年10月31日
年末が来る。
10月も今日で終り。明日からは11月。11月は祝日も多く、30日間でしかないため、すぐに12月になってしまいます。文化の秋といいますが、アンサンブルコンサートなどの演奏会やそのほかの演奏の機会も多く、秋の夜長というよりは、忙しい11月になりそうです。
さて、そろそろクリスマスなどと言ったイベントの名前がちらほら聞こえてきます。クリスマスのイベントなどで演奏する機会などはありますが、ここ数年、クリスマスのイベントやクリスマスの行事に自分で参加したことは皆無です。クリスマスプレゼントって何?と言った感覚でしょうか。まあ、クリスチャンでもないので、そんなに重要な日では無いと思うのですが。小さい頃はそれでもわくわくしていた記憶があります。甘いもの、ケーキが大好きな子どもでした。
そこで今日の一枚です。

リムスキー=コルサコフ/クリスマス・イヴ他
指揮:エルネスト・アンセルメ
スイス・ロマンド・管弦楽団
ジュネーヴ・モテット合唱団
ユニバーサルクラシック(DECCA)UCCD-3016
このCDは、アンセルメ/スイス・ロマンドによる、リムスキー=コルサコフの曲を集めたものです。当時、オーケストラの魔術師と言われ、ロシア音楽の演奏においても、人気があったアンセルメが、リムスキー=コルサコフの華麗なオーケストレーションを手兵スイス・ロマンドを率いて演奏しています。曲目的には、珍しい作品を録音したものともいえます。
曲目は、歌劇「五月の夜」序曲、組曲「皇帝サルタンの物語」op.57、組曲「クリスマス・イヴ」、ドゥビーヌシカop.62、音画「サトコ」op.5、組曲「雪娘」となっています。あまりなじみの無い曲とも言えます。
演奏は、スイスロマンドらしいヘタウマさがいい感じです。色彩感はアンセルメらしく十分に描き出されています。
実は、私はサルタン皇帝の物語の演奏を探していたのですが、条件として、アンセルメ/スイス・ロマンドのもの、聞いたことの無い曲が出来るだけたくさん収録されているもの、ステレオ録音であるもの、という条件で探していたもので、去年、やっと見つけて手に入れました。
リムスキー=コルサコフの少し耳なじみの少ない曲を聴いてみたい方、アンセルメ/スイス・ロマンドの演奏を堪能したい方にオススメの一枚です。
さて、そろそろクリスマスなどと言ったイベントの名前がちらほら聞こえてきます。クリスマスのイベントなどで演奏する機会などはありますが、ここ数年、クリスマスのイベントやクリスマスの行事に自分で参加したことは皆無です。クリスマスプレゼントって何?と言った感覚でしょうか。まあ、クリスチャンでもないので、そんなに重要な日では無いと思うのですが。小さい頃はそれでもわくわくしていた記憶があります。甘いもの、ケーキが大好きな子どもでした。
そこで今日の一枚です。

リムスキー=コルサコフ/クリスマス・イヴ他
指揮:エルネスト・アンセルメ
スイス・ロマンド・管弦楽団
ジュネーヴ・モテット合唱団
ユニバーサルクラシック(DECCA)UCCD-3016
このCDは、アンセルメ/スイス・ロマンドによる、リムスキー=コルサコフの曲を集めたものです。当時、オーケストラの魔術師と言われ、ロシア音楽の演奏においても、人気があったアンセルメが、リムスキー=コルサコフの華麗なオーケストレーションを手兵スイス・ロマンドを率いて演奏しています。曲目的には、珍しい作品を録音したものともいえます。
曲目は、歌劇「五月の夜」序曲、組曲「皇帝サルタンの物語」op.57、組曲「クリスマス・イヴ」、ドゥビーヌシカop.62、音画「サトコ」op.5、組曲「雪娘」となっています。あまりなじみの無い曲とも言えます。
演奏は、スイスロマンドらしいヘタウマさがいい感じです。色彩感はアンセルメらしく十分に描き出されています。
実は、私はサルタン皇帝の物語の演奏を探していたのですが、条件として、アンセルメ/スイス・ロマンドのもの、聞いたことの無い曲が出来るだけたくさん収録されているもの、ステレオ録音であるもの、という条件で探していたもので、去年、やっと見つけて手に入れました。
リムスキー=コルサコフの少し耳なじみの少ない曲を聴いてみたい方、アンセルメ/スイス・ロマンドの演奏を堪能したい方にオススメの一枚です。
2008年10月30日
薬の効き目、何となく。
今週末は高松ウインドシンフォニーのアンサンブルコンサート。本番です。私もサクソフォンアンサンブルで何曲か演奏してきます。
さて、最近鼻炎の時に薬を飲んでいるのですが、薬を飲んでどうか…?結論から言うと、効いた、ということになるのでしょうか。ただ、あくまで症状を抑える薬なので、鼻炎が治ってしまうことはありません。目の痒みはほとんど……取れません。鼻水のほうも完全には止まりません。ある意味、くしゃみが出そうで出ないような状態と同じで、鼻水が出そうで出ないような感覚です。症状を抑えると言う面では効いた、と言えるのでしょうが、中途半端な効き目と言えなくもありません。予防的な意味も含めて時期が来たら続けて飲まないと効果がないのかもしれませんが…。 ただ、ありがたいことに最近の薬は比較的喉の渇きや、眠気と言った副作用少ないように思います。
そこで今日の一枚です。

小田和正/自己ベスト
BMGファンハウス FHCL-2020
このCDは小田和正氏のソロによるベストアルバムです。オフコース時代のナンバーとソロ活動になってからのナンバーが収録されていますが、オフコース時代のナンバーもソロとして収録されています。ベストとはいえ、ほぼすべての曲は再レコーディング、またはリマスターしているという徹底振りが見えるCDになっています。どちらかと言うと、ベスト曲を集めた別の録音だと思ったほうがいいかもしれません。
曲目は、キラキラ、秋の気配、愛を止めないで、さよなら、Yes-No、言葉にできない、緑の日々、Oh! Yeah!、ラブ・ストーリーは突然に、my home town、風の坂道、伝えたいことがあるんだ、緑の街、風のように、woh wohk、となっています。
個人的には、オフコース時代の曲はオフコースでのほうが好きです。あのコーラスのハーモニーがより透明感というか、澄んだイメージを作り出していたと思います。もちろん、ラブストーリーは突然にや、キラキラなどはソロ活動になってからのナンバーですが。
実は私は別に小田和正氏が大好きとかそういうわけではないのですが、あの保険会社のCMを見ていて、ついつい「言葉に出来ない」が聞いてみたくなりました。本当はオフコースのバージョンを買おうと思っていたのですが、なんとなくこのソロアルバムが目について、こちらを買ってしまいました。(まさに根拠が無く、なんとなくです)
小田和正氏がオフコース時代からお好きな方、あのCMの曲や、様々なドラマの主題歌をまとめて聞いてみたいという方にオススメの一枚です。
さて、最近鼻炎の時に薬を飲んでいるのですが、薬を飲んでどうか…?結論から言うと、効いた、ということになるのでしょうか。ただ、あくまで症状を抑える薬なので、鼻炎が治ってしまうことはありません。目の痒みはほとんど……取れません。鼻水のほうも完全には止まりません。ある意味、くしゃみが出そうで出ないような状態と同じで、鼻水が出そうで出ないような感覚です。症状を抑えると言う面では効いた、と言えるのでしょうが、中途半端な効き目と言えなくもありません。予防的な意味も含めて時期が来たら続けて飲まないと効果がないのかもしれませんが…。 ただ、ありがたいことに最近の薬は比較的喉の渇きや、眠気と言った副作用少ないように思います。
そこで今日の一枚です。

小田和正/自己ベスト
BMGファンハウス FHCL-2020
このCDは小田和正氏のソロによるベストアルバムです。オフコース時代のナンバーとソロ活動になってからのナンバーが収録されていますが、オフコース時代のナンバーもソロとして収録されています。ベストとはいえ、ほぼすべての曲は再レコーディング、またはリマスターしているという徹底振りが見えるCDになっています。どちらかと言うと、ベスト曲を集めた別の録音だと思ったほうがいいかもしれません。
曲目は、キラキラ、秋の気配、愛を止めないで、さよなら、Yes-No、言葉にできない、緑の日々、Oh! Yeah!、ラブ・ストーリーは突然に、my home town、風の坂道、伝えたいことがあるんだ、緑の街、風のように、woh wohk、となっています。
個人的には、オフコース時代の曲はオフコースでのほうが好きです。あのコーラスのハーモニーがより透明感というか、澄んだイメージを作り出していたと思います。もちろん、ラブストーリーは突然にや、キラキラなどはソロ活動になってからのナンバーですが。
実は私は別に小田和正氏が大好きとかそういうわけではないのですが、あの保険会社のCMを見ていて、ついつい「言葉に出来ない」が聞いてみたくなりました。本当はオフコースのバージョンを買おうと思っていたのですが、なんとなくこのソロアルバムが目について、こちらを買ってしまいました。(まさに根拠が無く、なんとなくです)
小田和正氏がオフコース時代からお好きな方、あのCMの曲や、様々なドラマの主題歌をまとめて聞いてみたいという方にオススメの一枚です。
2008年10月29日
MRI。
先日、持病での病院の受診日に脳のMRIを撮影してきました。。最近、頭痛に悩まされており、時折激しい吐き気を伴う頭痛があるため、念のためということでMRIを撮ることにしました。結果は、MRIに異常なし、ということで、問題ありませんでした。何の頭痛なのか…。不明です。
以前、小児喘息で小児科にかかっていたころ、ずっと注射に通い、発作の苦しさに耐えられず、抗生物質を大量に摂取し、喘息の吸入薬を大量に摂取していたことを考えると、まだ、生易しいものです。
総合病院は診察を受けるために予約をしてあるのですが、予約時間から1時間以上待たされることがしょっちゅうで、診察時間は10分足らず、どんなに早くても、薬を出してもらうまでに2時間以上かかります。酷いときは5時間近くかかります。まあ、私も受診しているので、時間を遅らせている一人なのですが。
待ち時間が長いと、偉く退屈になります。本を読んだりしてもいいのですが、なんとなく病院の待合で本を読むのは私はあまり好きではないのです。
そういえば、以前は待合で音楽が流れていたのに最近は音楽が流れることもなくなりました。流れなくなった理由はわかりませんが。
そこで今日の一枚です。

バロック名曲集~パッヘルベルのカノン
指揮:リチャード・カップ
ニューヨーク・フィルハーモニア室内管弦楽団
SONY SRCR 1547
このCDはパッヘルベルのカノン、アルビノーニのアダージョなどを収録したバロックの曲集です。
曲目は、アルビノーニのアダージョ、パッヘルベルのカノン、G線上のアリア、「水上の音楽」~アレグロ、「四季」の「春」第2楽章、愛の喜び、主よ人の望みの喜びよ、羊は安らかに草を喰み、アダージョ(A.マルチェルロ)、管弦楽組曲第2番よりバディネリ(バッハ)、サラバンド(ヘンデル)、パストラーレ(コレッリ)、メヌエット(バッハ)、勝利の行進曲(カンプラ)となっています。
病院の待合で常流れている曲といえば、やはりバロック音楽でしょう。別にバロック音楽で無ければならないということは無いと思うのですが、TPOを考えるとすると、やっぱりバロック音楽やショパンなどのピアノ曲になるのではないかと思います。まあ、病院にハードロックやラップなどは似合わないと思うので、クラシックの静かな曲が流れるのは正解だと思うのですが、音楽を聴くことによる直接的な心理効果と、ノイズのマスキング効果を考えると、全く音楽が無いのもさびしい気もします。
演奏の方は可も無く不可もなく、ああ、バロックの演奏だなあ、という感じでしょうか。そつなく効けるという意味では、いい演奏といえるのかもしれません。
バロック音楽の聞きかじりをしたい方、穏やかなBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
以前、小児喘息で小児科にかかっていたころ、ずっと注射に通い、発作の苦しさに耐えられず、抗生物質を大量に摂取し、喘息の吸入薬を大量に摂取していたことを考えると、まだ、生易しいものです。
総合病院は診察を受けるために予約をしてあるのですが、予約時間から1時間以上待たされることがしょっちゅうで、診察時間は10分足らず、どんなに早くても、薬を出してもらうまでに2時間以上かかります。酷いときは5時間近くかかります。まあ、私も受診しているので、時間を遅らせている一人なのですが。
待ち時間が長いと、偉く退屈になります。本を読んだりしてもいいのですが、なんとなく病院の待合で本を読むのは私はあまり好きではないのです。
そういえば、以前は待合で音楽が流れていたのに最近は音楽が流れることもなくなりました。流れなくなった理由はわかりませんが。
そこで今日の一枚です。
バロック名曲集~パッヘルベルのカノン
指揮:リチャード・カップ
ニューヨーク・フィルハーモニア室内管弦楽団
SONY SRCR 1547
このCDはパッヘルベルのカノン、アルビノーニのアダージョなどを収録したバロックの曲集です。
曲目は、アルビノーニのアダージョ、パッヘルベルのカノン、G線上のアリア、「水上の音楽」~アレグロ、「四季」の「春」第2楽章、愛の喜び、主よ人の望みの喜びよ、羊は安らかに草を喰み、アダージョ(A.マルチェルロ)、管弦楽組曲第2番よりバディネリ(バッハ)、サラバンド(ヘンデル)、パストラーレ(コレッリ)、メヌエット(バッハ)、勝利の行進曲(カンプラ)となっています。
病院の待合で常流れている曲といえば、やはりバロック音楽でしょう。別にバロック音楽で無ければならないということは無いと思うのですが、TPOを考えるとすると、やっぱりバロック音楽やショパンなどのピアノ曲になるのではないかと思います。まあ、病院にハードロックやラップなどは似合わないと思うので、クラシックの静かな曲が流れるのは正解だと思うのですが、音楽を聴くことによる直接的な心理効果と、ノイズのマスキング効果を考えると、全く音楽が無いのもさびしい気もします。
演奏の方は可も無く不可もなく、ああ、バロックの演奏だなあ、という感じでしょうか。そつなく効けるという意味では、いい演奏といえるのかもしれません。
バロック音楽の聞きかじりをしたい方、穏やかなBGMをお探しの方にオススメの一枚です。
2008年10月28日
鼻炎、何故か鼻炎。
最近、突如として鼻炎が発症します。鼻炎が発症してしまうと、苦しくて仕方ありません。気温が急に下がったためでしょうか、ここ最近も風邪ではないのですが、鼻水が止まらなくなります。そうなると目もかゆくて仕方ありません。何か草花のアレルギーなのかもしれませんが、不明です。ただ、前日までは朝方鼻水が出ず、一日鼻水が出っぱなしということは無くても、突如として、点鼻薬のお世話になっても、鼻水が全くといっていいほど止まらなくなります。年に数回激しいアレルギー性鼻炎に悩まされています。病院の耳鼻科にいったところ、たいしたことは無い、ということでゆるい抗ヒスタミン剤を処方されて終わりだったので、病院で何とかしてもらう気はなくなりました。
話によると、ヨーグルトや、紫蘇のエキスが効く、といいますが、いずれにせよ、即効性は無いので、今すぐ、というわけには行きません。
そうなると、薬を飲んで症状を抑えて、時期が過ぎ去るのを待つしかないようです。
ところで、未だに少し判らないのはアレルギー性鼻炎で鼻水が止まらないのは耳鼻科に行くことになるのですが、目がかゆいときはやはり、眼科なのでしょうか?どちらに行くか、というよりも、どちらも関連しているので、やはり両方にカルテを持っていかなければならないのでしょうか…。そう考えるとまたまた病院にいくのも面倒になってしまいます。
一度、もっとしっかりした病院でアレルギーパッチテストとかしたほうがいいのかもしれませんが。しかし、この鼻水、鼻づまりの苦しさもさることながら、鼻水を拭く、鼻をかむという行為のために鼻の下が真っ赤になってしまいます。そのうち皮がむけてしまうでしょう。そちらの方が辛いかもしれません。鼻セレブでも買ってくるべきかどうか…。
さてそんな苦しい中ですが、今日の一枚です。

ドビュッシー/海
指揮:マイケル・ティルソン・トーマス
フィルハーモニア管弦楽団
このCDはマイケル・ティルソン・トーマスとフィルハーモニア管弦楽団によるドビュッシーの作品を2曲収めたもの。マイケル・ティルソン・トーマスは以前、ガーシュウィンのCDでも紹介しましたが、1944年ハリウッドの演劇一家に生まれ、南カリフォルニア大学に学んだ人です。1966年にバイロイト音楽祭のアシスタントをつとめ、その後ボストン響のアシスタント指揮者となります。さらにバッファローフィルの音楽監督、ロンドン響の首席指揮者などを歴任し、サンフランシスコ響の音楽監督となりました。彼は若手音楽家の育成に対しても熱心で、1988年にマイアミに若手オーケストラ楽員育成のため、ニューワールド響を創設しています。
収録されている曲はドビュッシーの「海」管弦楽のための三つの交響的素描、夜想曲の2曲です。
演奏の方は比較的明解な演奏ですっきりとしたシャープな演奏になっています。ただ、それとは逆に時折アンサンブルの粗さを感じるような部分もあって少し残念です。ただ、全体的には、よく整理されている演奏と感じます。しかしながらドビュッシーの曲自体は比較的「何処と無く漂う」ような雰囲気が必要な気もするのですが、このCDからはあまりそれは感じられないようにも思います。好みの問題かもしれません。確実なのは、テンポが時折速すぎる、と感じることがあるということです。それを若々しい演奏ととるか、深みが足りない、ととるかは好みの問題だと思います。
実は、数年前、この曲を吹奏楽で定期演奏会で演奏したのですが、その練習のときも鼻炎で苦しんでいたことがあり、それを思い出します。鼻にティッシュとかつめて練習して非常に苦しい思いもしました。
フレッシュなドビュッシーの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
話によると、ヨーグルトや、紫蘇のエキスが効く、といいますが、いずれにせよ、即効性は無いので、今すぐ、というわけには行きません。
そうなると、薬を飲んで症状を抑えて、時期が過ぎ去るのを待つしかないようです。
ところで、未だに少し判らないのはアレルギー性鼻炎で鼻水が止まらないのは耳鼻科に行くことになるのですが、目がかゆいときはやはり、眼科なのでしょうか?どちらに行くか、というよりも、どちらも関連しているので、やはり両方にカルテを持っていかなければならないのでしょうか…。そう考えるとまたまた病院にいくのも面倒になってしまいます。
一度、もっとしっかりした病院でアレルギーパッチテストとかしたほうがいいのかもしれませんが。しかし、この鼻水、鼻づまりの苦しさもさることながら、鼻水を拭く、鼻をかむという行為のために鼻の下が真っ赤になってしまいます。そのうち皮がむけてしまうでしょう。そちらの方が辛いかもしれません。鼻セレブでも買ってくるべきかどうか…。
さてそんな苦しい中ですが、今日の一枚です。

ドビュッシー/海
指揮:マイケル・ティルソン・トーマス
フィルハーモニア管弦楽団
このCDはマイケル・ティルソン・トーマスとフィルハーモニア管弦楽団によるドビュッシーの作品を2曲収めたもの。マイケル・ティルソン・トーマスは以前、ガーシュウィンのCDでも紹介しましたが、1944年ハリウッドの演劇一家に生まれ、南カリフォルニア大学に学んだ人です。1966年にバイロイト音楽祭のアシスタントをつとめ、その後ボストン響のアシスタント指揮者となります。さらにバッファローフィルの音楽監督、ロンドン響の首席指揮者などを歴任し、サンフランシスコ響の音楽監督となりました。彼は若手音楽家の育成に対しても熱心で、1988年にマイアミに若手オーケストラ楽員育成のため、ニューワールド響を創設しています。
収録されている曲はドビュッシーの「海」管弦楽のための三つの交響的素描、夜想曲の2曲です。
演奏の方は比較的明解な演奏ですっきりとしたシャープな演奏になっています。ただ、それとは逆に時折アンサンブルの粗さを感じるような部分もあって少し残念です。ただ、全体的には、よく整理されている演奏と感じます。しかしながらドビュッシーの曲自体は比較的「何処と無く漂う」ような雰囲気が必要な気もするのですが、このCDからはあまりそれは感じられないようにも思います。好みの問題かもしれません。確実なのは、テンポが時折速すぎる、と感じることがあるということです。それを若々しい演奏ととるか、深みが足りない、ととるかは好みの問題だと思います。
実は、数年前、この曲を吹奏楽で定期演奏会で演奏したのですが、その練習のときも鼻炎で苦しんでいたことがあり、それを思い出します。鼻にティッシュとかつめて練習して非常に苦しい思いもしました。
フレッシュなドビュッシーの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年10月27日
再開した途端。
今日は朝から雨模様になりました。気温も昨日に比べて、低くなっているようです。
さて、昨日から「吹奏楽無節操企画」を再開したわけですが、普段から紹介したCDに対する反響も少なく(苦笑)今回もあまり盛り上がらない感が否めません。もしかしたら曲が古すぎるのかも…。と思ったりもしますが。まあ、ほとんど毎日自己満足で書いている世界なので、反響を期待しているわけではないのですが、それでもみなさんが興味がもてるようにCDを紹介できていないかもしれないと思うと、少し反省しないといけないかも、と考えたりします。紹介するCDが悪いのか、私の紹介が悪いのか、CDはすばらしいものがほとんどだと思いますので、明らかに後者のような気もしますが。一応、「吹奏楽無節操企画」は今日でひと段落して、明日からは通常の「今日の一枚」にしたいと考えています。再開した途端に終わるわけですが…。
今日の一枚です。

ニュー・サウンズ・スペシャル
指揮:岩井直溥
東京佼成ウィンド・オーケストラ
東芝EMI TOCZ-9288
このCDはニューサウンズ・イン・ブラスの25周年を記念して作られたアルバムです。曲はすべて、ニュー・サウンズ・イン・ブラスの楽譜からセレクトされています。
ちょっと疑問に思うことは、ニューサウンズは吹奏楽でポップスを気軽に、といったようなコンセプトで作られ、楽譜と音源が毎年発売されているのですが、こうやって、ベスト版、記念版が出ても、すでに廃盤、絶版になった楽譜があったりして、演奏が非常に困難なものが存在すると言うことです。これでは、最初のコンセプトではなく、ただのCDになってしまいそうな気もします。また、CDは売られ続け、楽譜は早々に廃盤、絶版になる、という現実もあります。おそらくは、CDと楽譜の販売元、管理元が違うことが原因なのでしょうが、吹奏楽編成で、出来るポップスの楽譜を歌っているのですから、少なくともCDが手に入る段階での楽譜の廃盤、絶版はやめて欲しい気もします。最近、漸く、そのことに気づいたのか、オンデマンドの楽譜も存在するようですが、それも絶版になったものの一部に過ぎません。
私の愚痴っぽくなってしまいましたが、曲目はアフリカン・シンフォニー、追憶のテーマ、オーメンズ・オブ・ラブ、踊りあかそう、コパカバーナ、宝島、虹の彼方に、シング・シング・シング、ウス・ランパート・ストリート・パレード、A列車で行こう、ディズニー・メドレー:ミッキー・マウス・マーチ~小さな世界~ハイ・ホー~狼なんかこわくない~いつか王子様が~口笛吹いて働こう~星に願いを、ウィ・アー・オール・アローン、となっています。
ゲストミュージシャンとして、様々なミュージシャンが参加しています。伊藤たけし氏、本多俊之氏、エディ・ダニエルズ氏、ランディ・ブレッカー氏、スライド・ハンプトン氏、等々、他にもまだまだ、参加しています。なお、海外アーティストの何人かはソロだけ海外で別撮りしたものです。(ちょっと反則技のような気もしますが)ジャケットもゴールドでいかにもゴージャスな感じでよいです。
演奏の方は、まさしくニューサウンズ・イン・ブラスの集大成、といった感じです。ただ、ゲストミュージシャンの演奏は参考演奏と言うよりは、純粋に音楽として楽しむべきものになっていると思います。かなり楽譜も演奏時に改変されているようで、本来はニューサウンズはこうやって楽しむものなんだ、という主張があるのかもしれません。
今までのNSBに飽き足らない方、ジャズ好きな吹奏楽愛好者の方、また、吹奏楽なんて…、と吹奏楽をなめて見ている方にオススメの一枚です。
さて、昨日から「吹奏楽無節操企画」を再開したわけですが、普段から紹介したCDに対する反響も少なく(苦笑)今回もあまり盛り上がらない感が否めません。もしかしたら曲が古すぎるのかも…。と思ったりもしますが。まあ、ほとんど毎日自己満足で書いている世界なので、反響を期待しているわけではないのですが、それでもみなさんが興味がもてるようにCDを紹介できていないかもしれないと思うと、少し反省しないといけないかも、と考えたりします。紹介するCDが悪いのか、私の紹介が悪いのか、CDはすばらしいものがほとんどだと思いますので、明らかに後者のような気もしますが。一応、「吹奏楽無節操企画」は今日でひと段落して、明日からは通常の「今日の一枚」にしたいと考えています。再開した途端に終わるわけですが…。
今日の一枚です。
ニュー・サウンズ・スペシャル
指揮:岩井直溥
東京佼成ウィンド・オーケストラ
東芝EMI TOCZ-9288
このCDはニューサウンズ・イン・ブラスの25周年を記念して作られたアルバムです。曲はすべて、ニュー・サウンズ・イン・ブラスの楽譜からセレクトされています。
ちょっと疑問に思うことは、ニューサウンズは吹奏楽でポップスを気軽に、といったようなコンセプトで作られ、楽譜と音源が毎年発売されているのですが、こうやって、ベスト版、記念版が出ても、すでに廃盤、絶版になった楽譜があったりして、演奏が非常に困難なものが存在すると言うことです。これでは、最初のコンセプトではなく、ただのCDになってしまいそうな気もします。また、CDは売られ続け、楽譜は早々に廃盤、絶版になる、という現実もあります。おそらくは、CDと楽譜の販売元、管理元が違うことが原因なのでしょうが、吹奏楽編成で、出来るポップスの楽譜を歌っているのですから、少なくともCDが手に入る段階での楽譜の廃盤、絶版はやめて欲しい気もします。最近、漸く、そのことに気づいたのか、オンデマンドの楽譜も存在するようですが、それも絶版になったものの一部に過ぎません。
私の愚痴っぽくなってしまいましたが、曲目はアフリカン・シンフォニー、追憶のテーマ、オーメンズ・オブ・ラブ、踊りあかそう、コパカバーナ、宝島、虹の彼方に、シング・シング・シング、ウス・ランパート・ストリート・パレード、A列車で行こう、ディズニー・メドレー:ミッキー・マウス・マーチ~小さな世界~ハイ・ホー~狼なんかこわくない~いつか王子様が~口笛吹いて働こう~星に願いを、ウィ・アー・オール・アローン、となっています。
ゲストミュージシャンとして、様々なミュージシャンが参加しています。伊藤たけし氏、本多俊之氏、エディ・ダニエルズ氏、ランディ・ブレッカー氏、スライド・ハンプトン氏、等々、他にもまだまだ、参加しています。なお、海外アーティストの何人かはソロだけ海外で別撮りしたものです。(ちょっと反則技のような気もしますが)ジャケットもゴールドでいかにもゴージャスな感じでよいです。
演奏の方は、まさしくニューサウンズ・イン・ブラスの集大成、といった感じです。ただ、ゲストミュージシャンの演奏は参考演奏と言うよりは、純粋に音楽として楽しむべきものになっていると思います。かなり楽譜も演奏時に改変されているようで、本来はニューサウンズはこうやって楽しむものなんだ、という主張があるのかもしれません。
今までのNSBに飽き足らない方、ジャズ好きな吹奏楽愛好者の方、また、吹奏楽なんて…、と吹奏楽をなめて見ている方にオススメの一枚です。
2008年10月27日
今更ながら感もありますが…。
涼しくなってきました、というべきか肌寒くなってきました、というべきか…、ともかく気温が下がってきました。
皆さん風邪などひいていませんでしょうか。
さて、涼しくなってきたこの時期ですが、来週末から2泊で沖縄に行ってくる予定です。私はほとんど旅行をしない人なので、沖縄が今どんな気候なのか想像もつきませんが、28度ぐらいはありそうなので、夏服を用意していくことになりそうだ、という想像しかありません。
旅支度がある程度必要なのかもしれませんが、まだ何もしていません。何に荷物を入れていくかも未定。まあ、2泊なので、そんなに荷物もいらないと思いますが…。最近はホテルのアメニティも充実しているので、本当に手ぶらに近い状態でもOKなのかもしれません。まあ、一月ぐらい前から沖縄行きは判っていたことなので、今更騒いでも…というのもありますが。
そこで、今日の一枚です。

トルヴェールの『惑星』/"The Planets" by Trouvere
トルヴェール・クヮルテット
CD-0667
このCDはサクソフォン・アンサンブル、トルヴェール・クヮルテットの9枚目に当たるアルバムです。実は今まで、東芝EMIから発売されていたのですが、諸事情で、今回は、録音のみ東芝で発売元は変更になっているようです。実はこの楽天内のアネマジロさんのHPをはじめ様々なHPですでに紹介されているので、もっと早くに紹介しようと思ったのですが、いろいろあって今日の紹介になってしまいました。
曲目は、・惑星/グスタブ・ホルスト(arr.長生 淳)~火星(Mars)、金星(Venus)、水星(Mercury)、木星(Jupiter)、土星(Saturn)、天王星(Uranus)、海王星(Neptune)、彗星(Comets)、冥王星(Pluto)、地球(Earth)、Special Bonus トルヴェールの「木星」となっています。基本的にはホルストの惑星なのですが、編曲は自由な編曲になっていて、どちらかと言うと、「惑星」をモチーフに新たに書き上げられた曲といったほうがいいかもしれません。原曲にはない、冥王星、地球と言う曲も新たに追加されています。
演奏は、さすがトルヴェール、というべきか、トルヴェールだからこそ出来たアルバムと言うべきか、とにかくすごいです。卓越したテクニックと音楽性がすばらしいアルバムになっています。
もうひとつ、目玉はボーナストラック。聞いてびっくり、聞いて面白い、ボーナストラックになっています。
サックスを吹かれている方、それにとどまらず、すべての音楽愛好者の方に聞いていただきたいオススメの一枚です。
皆さん風邪などひいていませんでしょうか。
さて、涼しくなってきたこの時期ですが、来週末から2泊で沖縄に行ってくる予定です。私はほとんど旅行をしない人なので、沖縄が今どんな気候なのか想像もつきませんが、28度ぐらいはありそうなので、夏服を用意していくことになりそうだ、という想像しかありません。
旅支度がある程度必要なのかもしれませんが、まだ何もしていません。何に荷物を入れていくかも未定。まあ、2泊なので、そんなに荷物もいらないと思いますが…。最近はホテルのアメニティも充実しているので、本当に手ぶらに近い状態でもOKなのかもしれません。まあ、一月ぐらい前から沖縄行きは判っていたことなので、今更騒いでも…というのもありますが。
そこで、今日の一枚です。
トルヴェールの『惑星』/"The Planets" by Trouvere
トルヴェール・クヮルテット
CD-0667
このCDはサクソフォン・アンサンブル、トルヴェール・クヮルテットの9枚目に当たるアルバムです。実は今まで、東芝EMIから発売されていたのですが、諸事情で、今回は、録音のみ東芝で発売元は変更になっているようです。実はこの楽天内のアネマジロさんのHPをはじめ様々なHPですでに紹介されているので、もっと早くに紹介しようと思ったのですが、いろいろあって今日の紹介になってしまいました。
曲目は、・惑星/グスタブ・ホルスト(arr.長生 淳)~火星(Mars)、金星(Venus)、水星(Mercury)、木星(Jupiter)、土星(Saturn)、天王星(Uranus)、海王星(Neptune)、彗星(Comets)、冥王星(Pluto)、地球(Earth)、Special Bonus トルヴェールの「木星」となっています。基本的にはホルストの惑星なのですが、編曲は自由な編曲になっていて、どちらかと言うと、「惑星」をモチーフに新たに書き上げられた曲といったほうがいいかもしれません。原曲にはない、冥王星、地球と言う曲も新たに追加されています。
演奏は、さすがトルヴェール、というべきか、トルヴェールだからこそ出来たアルバムと言うべきか、とにかくすごいです。卓越したテクニックと音楽性がすばらしいアルバムになっています。
もうひとつ、目玉はボーナストラック。聞いてびっくり、聞いて面白い、ボーナストラックになっています。
サックスを吹かれている方、それにとどまらず、すべての音楽愛好者の方に聞いていただきたいオススメの一枚です。
2008年10月26日
久々?かな。
雨模様。しかし、早明浦ダムに雨が降らない限り、根本的な水不足解消にはなりません。
さて、サクソフォンアンサンブルコンサートが終わって早くも一週間。ダッパーでも次の演奏会やアンサンブルコンテストに向けての活動がスタートしつつあります。
来週末土曜日は、古高松コミュニティーセンターでの演奏が待っています。その次の日は高松ウインドシンフォニーのアンサンブルコンサート。
次々に本番が…。
ところで、演奏会の音源編集にかまけて、ほとんど画像を貼り付けるだけの手抜きの日記を書き続けていましたが、音の編集、ジャケットの作成がとりあえず一段落したので、久々(でもないか?)に今日の一枚を再開します。
まだまだ続く、吹奏楽無節操企画。
そこで今日の一枚です。
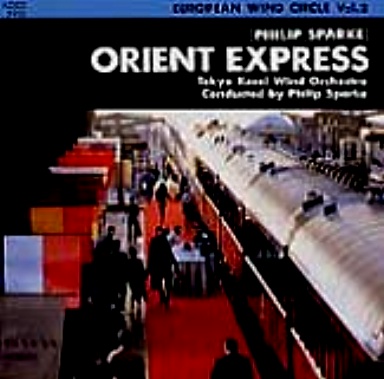
オリエント急行
指揮:フィリップ・スパーク
東京佼成ウインドオーケストラ
佼成出版社 KOCD-3902
このCDは、東京佼成ウインドと作曲者自身の指揮による、フィリップ・スパークの自作自演集です。
曲目は、祝典のための音楽、ジュビリー序曲、山の歌、コンサート・プレリュード、ファンファーレ、ロマンス、フィナーレ、オリエント急行、長く白い雲のたなびく国“アオテアロア”となっています。
このCDのタイトルにもなっている、オリエント急行は、アガサクリスティーの推理小説「オリエント急行殺人事件」でも有名ですが、19世紀末、ヨーロッパ人がパリからコンスタンチノープルへと走らせた幻の豪華列車だ。後年、空路の発達等で、この路線も一時は廃止されてしまいましたが、1980年代にに復活し、現在は、ロンドン・ヴィクトリア駅からパリ経由でベネチア・サンタマリア駅までを結ぶ定期列車として運行しています。豪華な内装と一流レストラン並みの食事は往年のヨーロッパ社交界のサロンを彷彿とさせるつくりになっています。
このスパーク作曲の曲は、元は、金管バンド用に書かれ、彼自身の手によって、吹奏楽版に編曲されました。描写的に書かれた曲で、駅の場面から始まり、警笛を鳴らした蒸気機関車が、ゆっくりと動き出し、やがて軽快に走り、さまざまな風景が通り過ぎて行き、また、駅に到着するというスタイルで書かれています。(まるでオネゲルの「パシフィック231」のような曲ですが…)
演奏は自作自演集ということで作曲者の意図をストレートに伝えているものになっていると思います。
スパークの曲を聴いてみたい方、スパークの吹奏楽の演奏をするときの参考演奏としてオススメの一枚です。
さて、サクソフォンアンサンブルコンサートが終わって早くも一週間。ダッパーでも次の演奏会やアンサンブルコンテストに向けての活動がスタートしつつあります。
来週末土曜日は、古高松コミュニティーセンターでの演奏が待っています。その次の日は高松ウインドシンフォニーのアンサンブルコンサート。
次々に本番が…。
ところで、演奏会の音源編集にかまけて、ほとんど画像を貼り付けるだけの手抜きの日記を書き続けていましたが、音の編集、ジャケットの作成がとりあえず一段落したので、久々(でもないか?)に今日の一枚を再開します。
まだまだ続く、吹奏楽無節操企画。
そこで今日の一枚です。
オリエント急行
指揮:フィリップ・スパーク
東京佼成ウインドオーケストラ
佼成出版社 KOCD-3902
このCDは、東京佼成ウインドと作曲者自身の指揮による、フィリップ・スパークの自作自演集です。
曲目は、祝典のための音楽、ジュビリー序曲、山の歌、コンサート・プレリュード、ファンファーレ、ロマンス、フィナーレ、オリエント急行、長く白い雲のたなびく国“アオテアロア”となっています。
このCDのタイトルにもなっている、オリエント急行は、アガサクリスティーの推理小説「オリエント急行殺人事件」でも有名ですが、19世紀末、ヨーロッパ人がパリからコンスタンチノープルへと走らせた幻の豪華列車だ。後年、空路の発達等で、この路線も一時は廃止されてしまいましたが、1980年代にに復活し、現在は、ロンドン・ヴィクトリア駅からパリ経由でベネチア・サンタマリア駅までを結ぶ定期列車として運行しています。豪華な内装と一流レストラン並みの食事は往年のヨーロッパ社交界のサロンを彷彿とさせるつくりになっています。
このスパーク作曲の曲は、元は、金管バンド用に書かれ、彼自身の手によって、吹奏楽版に編曲されました。描写的に書かれた曲で、駅の場面から始まり、警笛を鳴らした蒸気機関車が、ゆっくりと動き出し、やがて軽快に走り、さまざまな風景が通り過ぎて行き、また、駅に到着するというスタイルで書かれています。(まるでオネゲルの「パシフィック231」のような曲ですが…)
演奏は自作自演集ということで作曲者の意図をストレートに伝えているものになっていると思います。
スパークの曲を聴いてみたい方、スパークの吹奏楽の演奏をするときの参考演奏としてオススメの一枚です。
2008年10月25日
音源編集中3。
ちょっと、他の用件で楽譜を書く必要が出来たので、一旦作業をとめる必要が…。
今回もジャケットをちょこっとだけ公開。

音の方は焼付けのための原盤が完成。
あとは、一枚一枚等倍速で音楽用CDRで焼いていく作業です。
今回もジャケットをちょこっとだけ公開。
音の方は焼付けのための原盤が完成。
あとは、一枚一枚等倍速で音楽用CDRで焼いていく作業です。
2008年10月24日
音源編集中2。
依然、サクソフォーンアンサンブルコンサート2008の音源の編集中です。
問題。
これは↓演奏会のうちの何の曲の波形でしょう。

※答えは一番下に…。
音を整える作業を続けています。クラシカルな演奏会で、釣りマイクでホールでの録音。
そんなにリバーブする必要も特になく、
若干低音が不足気味であるものの、ことさらにイコライジングすることもなく、オーバーレベルや音の歪みに注意しつつ、余分な部分を切りとって編集していきます。
今回は拍手をほとんどカットしませんでした。そのため、おそらくCDが二枚組みになりそうです。
まだ、編集作業、
ラベルのデザイン、
そしてラベルの印刷、
ラベルのカット、ラベルのセット、
配布
という作業です。
あと2週間ぐらいかかりそうです。
……
……
……
答えは…。
東回りの風の1曲目As I walked outでした。
問題。
これは↓演奏会のうちの何の曲の波形でしょう。
※答えは一番下に…。
音を整える作業を続けています。クラシカルな演奏会で、釣りマイクでホールでの録音。
そんなにリバーブする必要も特になく、
若干低音が不足気味であるものの、ことさらにイコライジングすることもなく、オーバーレベルや音の歪みに注意しつつ、余分な部分を切りとって編集していきます。
今回は拍手をほとんどカットしませんでした。そのため、おそらくCDが二枚組みになりそうです。
まだ、編集作業、
ラベルのデザイン、
そしてラベルの印刷、
ラベルのカット、ラベルのセット、
配布
という作業です。
あと2週間ぐらいかかりそうです。
……
……
……
答えは…。
東回りの風の1曲目As I walked outでした。
2008年10月23日
音源編集中。
サクソフォン・アンサンブル・コンサート2008が終了し、既に3日。現在、録音された音源から出演された皆さんにCDを配るべく編集中。
既に何度となく録音を聞きました。最初の数回は編集のために聞きながらも自分の演奏に凹み続けていましたが、漸くそれも脱脂、一つの音源として編集できる状態になってきました。
CDが完成するまでには数十回から数百回演奏を聴くことになります。
並行してジャケット作りにも入っていますが…。ちょっこっとだけジャケットを公開(モザイクつきですが…)
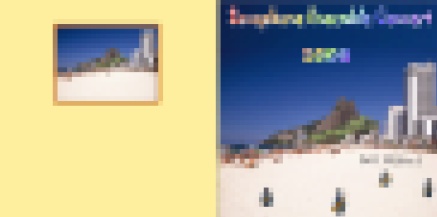
いつもながら、何をするのにもたいしたことが出来ず中途半端なものばかり…。
色々な素質がある人がうらやましいと思う今日この頃です。
既に何度となく録音を聞きました。最初の数回は編集のために聞きながらも自分の演奏に凹み続けていましたが、漸くそれも脱脂、一つの音源として編集できる状態になってきました。
CDが完成するまでには数十回から数百回演奏を聴くことになります。
並行してジャケット作りにも入っていますが…。ちょっこっとだけジャケットを公開(モザイクつきですが…)
いつもながら、何をするのにもたいしたことが出来ず中途半端なものばかり…。
色々な素質がある人がうらやましいと思う今日この頃です。
Posted by のりくん at
01:06
│Comments(0)
2008年10月22日
音響機器の弱点。
サクソフォンアンサンブルコンサートが終了し、現在録音の編集作業に入っています。仕事が結構忙しかったりするので
さて、私は若干いいオーディオ機器を持っています。本当のマニアの方にしてみたらまだまだエントリークラスのチープなシステムだと思いますが、それなりにこだわった機器を集めてシステムを組んでいます。私の持っている機器の中で、マランツのCD-Rがあるのですが、このCD-R、購入当時かなり優れものでした。今では別の意味でも優れものというか、貴重品です。というのも、このCD-R、業務用のためにコピーガード機能をキャンセルしてダビングが出来るのです。つまり市販のCDソフトを何度でも子、孫、ひ孫とダビングできます。私は自分で録音したコンサートの音源の編集するのに使っているので、悪用はしていませんが、やろうと思うと悪用も出来ます。さらに、CCCD(所謂コピーコントロールCD)のダビングも何の問題もありません。なぜなら、PCのようにPCドライブで読み込みしないで、CDプレーヤーからの音楽情報のデジタルデータのみをCDRに送ることが出来るため、PCのように勝手に変なプログラムが起動したりすることがないのです。で、コピーで出来上がったCDはもちろん、CCCDがキャンセルされたものになります。要は音楽用のCDプレーヤーで読めれば、普通のCDとして焼直すことが出来るのです。私は悪用していないので、このようなことはやりませんが、こうやって見ても如何にCCCDというシステムが馬鹿らしいものかが見て取れます。何のコピー対策にもなっていない上に、激悪な音質、おまけに動作保障されていないので、CDプレーヤーで再生されない可能性や、酷いときはCDプレーヤーが破損するということまで起こりうるCCCD。各社、いまさらのように止めるといっているようですが…。遅すぎです。
さて、そんな最強のように思えるCD-Rなのですが、弱点が。それは一般の民生機でも同じですが、まず、埃に弱いこと。これは読み取りレンズが汚れると、特にCD-Rはディスクを読んでくれなくなります。先日もこの状態に陥りあわててクリーニングディスクにてクリーニングしました。もうひとつは熱の問題。私の部屋にはエアコンがありません。なので、夏はかなりの高温多湿になります。当然、デジタル機器は湿度にも弱いのですが、それよりも直接的には熱です。放熱が悪いと、動作が不安定になる傾向があるようです。そして、もうひとつの弱点は動作音のでかさ。これは業務用だからなのかどうかわかりませんが、書き込みの動作音がかなり派手です。普通の民生機のCD-Rと比べても、比べ物にならないくらい、派手です。当然、録音現場に持ち込んで直接CD-Rに焼き付けたいときでも、マイクと離さないと確実に動作音を拾います。
しかし、動作音以外のことはどの音響機器にとっても弱点になります。出来れば、部屋をサッシにしてエアコンを導入したいのですが、そこまでするなら、新しいプレーヤーとか買ってしまうだろうなー、と今は思っています。
さて、「吹奏楽無節操企画」第4日目です。それでは今日の一枚です。
吹奏楽ベストセレクション’92
指揮:汐澤安彦
シエナ・ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ-9189
このCDは、1992年の新曲を主に収録した吹奏楽曲集です。コンセプトとしては、コンクールや演奏会に使える曲をということのようです。
曲目は、ヨークシャー序曲(P.スパーク)、ファンファーレと祝典の讃歌(P.ラヴェンダー)、スピリット・レイク序曲(シェルドン)、交響組曲「ロビンフッド」(M.カーメン、P.ラヴェンダー編)、クラリナンド(R.コメロ)、 ミラージュI(真島俊夫)、海賊たちの上陸(R.シェルドン)、ロスト・クリーク・アドヴェンチャー(E.ハックビー)、ユングフラウへの前奏曲(森田一浩)、ハイランド・ラプソディ(ヴァン=デル=ロースト)サーカスの思い出(G.ペーター)、セレブレイションズ(J.ズデクリック)となっています。
交響組曲は以前の日記にも書いたように、高松ウインドシンフォニーの演奏会でも演奏したことがあります。このCD全編を通して、この曲のみがアレンジ物ということになります。
演奏の方は、どうなんでしょう、録音のためなのかどうなのかはよくはわかりませんが、いまひとつ音がクリアに聞こえてこない気もします。決して演奏がまずいとか、響きが悪いとか言う感じではないのですが、音が前に出てこないというか、音がはっきりしない感じです。また、ソロのおとも割合全体の中に埋もれがちな気もします。バンドの本領が発揮できていないような気もして、少し残念です。
今のシエナW.O.は、あの佐渡裕氏が指揮したりしてもっと情熱的な演奏を聞かせてくれるバンドになっていると思うのですが、このCDを聞く限りは控えめで、少しパッションが足りないと言う感想を持ってしまいます。
とはいえ、演奏のクオリティは文句なしだと思うので、吹奏楽を愛好するすべての方に、また、吹奏楽部の方の資料としてオススメの一枚です。
さて、私は若干いいオーディオ機器を持っています。本当のマニアの方にしてみたらまだまだエントリークラスのチープなシステムだと思いますが、それなりにこだわった機器を集めてシステムを組んでいます。私の持っている機器の中で、マランツのCD-Rがあるのですが、このCD-R、購入当時かなり優れものでした。今では別の意味でも優れものというか、貴重品です。というのも、このCD-R、業務用のためにコピーガード機能をキャンセルしてダビングが出来るのです。つまり市販のCDソフトを何度でも子、孫、ひ孫とダビングできます。私は自分で録音したコンサートの音源の編集するのに使っているので、悪用はしていませんが、やろうと思うと悪用も出来ます。さらに、CCCD(所謂コピーコントロールCD)のダビングも何の問題もありません。なぜなら、PCのようにPCドライブで読み込みしないで、CDプレーヤーからの音楽情報のデジタルデータのみをCDRに送ることが出来るため、PCのように勝手に変なプログラムが起動したりすることがないのです。で、コピーで出来上がったCDはもちろん、CCCDがキャンセルされたものになります。要は音楽用のCDプレーヤーで読めれば、普通のCDとして焼直すことが出来るのです。私は悪用していないので、このようなことはやりませんが、こうやって見ても如何にCCCDというシステムが馬鹿らしいものかが見て取れます。何のコピー対策にもなっていない上に、激悪な音質、おまけに動作保障されていないので、CDプレーヤーで再生されない可能性や、酷いときはCDプレーヤーが破損するということまで起こりうるCCCD。各社、いまさらのように止めるといっているようですが…。遅すぎです。
さて、そんな最強のように思えるCD-Rなのですが、弱点が。それは一般の民生機でも同じですが、まず、埃に弱いこと。これは読み取りレンズが汚れると、特にCD-Rはディスクを読んでくれなくなります。先日もこの状態に陥りあわててクリーニングディスクにてクリーニングしました。もうひとつは熱の問題。私の部屋にはエアコンがありません。なので、夏はかなりの高温多湿になります。当然、デジタル機器は湿度にも弱いのですが、それよりも直接的には熱です。放熱が悪いと、動作が不安定になる傾向があるようです。そして、もうひとつの弱点は動作音のでかさ。これは業務用だからなのかどうかわかりませんが、書き込みの動作音がかなり派手です。普通の民生機のCD-Rと比べても、比べ物にならないくらい、派手です。当然、録音現場に持ち込んで直接CD-Rに焼き付けたいときでも、マイクと離さないと確実に動作音を拾います。
しかし、動作音以外のことはどの音響機器にとっても弱点になります。出来れば、部屋をサッシにしてエアコンを導入したいのですが、そこまでするなら、新しいプレーヤーとか買ってしまうだろうなー、と今は思っています。
さて、「吹奏楽無節操企画」第4日目です。それでは今日の一枚です。
吹奏楽ベストセレクション’92
指揮:汐澤安彦
シエナ・ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ-9189
このCDは、1992年の新曲を主に収録した吹奏楽曲集です。コンセプトとしては、コンクールや演奏会に使える曲をということのようです。
曲目は、ヨークシャー序曲(P.スパーク)、ファンファーレと祝典の讃歌(P.ラヴェンダー)、スピリット・レイク序曲(シェルドン)、交響組曲「ロビンフッド」(M.カーメン、P.ラヴェンダー編)、クラリナンド(R.コメロ)、 ミラージュI(真島俊夫)、海賊たちの上陸(R.シェルドン)、ロスト・クリーク・アドヴェンチャー(E.ハックビー)、ユングフラウへの前奏曲(森田一浩)、ハイランド・ラプソディ(ヴァン=デル=ロースト)サーカスの思い出(G.ペーター)、セレブレイションズ(J.ズデクリック)となっています。
交響組曲は以前の日記にも書いたように、高松ウインドシンフォニーの演奏会でも演奏したことがあります。このCD全編を通して、この曲のみがアレンジ物ということになります。
演奏の方は、どうなんでしょう、録音のためなのかどうなのかはよくはわかりませんが、いまひとつ音がクリアに聞こえてこない気もします。決して演奏がまずいとか、響きが悪いとか言う感じではないのですが、音が前に出てこないというか、音がはっきりしない感じです。また、ソロのおとも割合全体の中に埋もれがちな気もします。バンドの本領が発揮できていないような気もして、少し残念です。
今のシエナW.O.は、あの佐渡裕氏が指揮したりしてもっと情熱的な演奏を聞かせてくれるバンドになっていると思うのですが、このCDを聞く限りは控えめで、少しパッションが足りないと言う感想を持ってしまいます。
とはいえ、演奏のクオリティは文句なしだと思うので、吹奏楽を愛好するすべての方に、また、吹奏楽部の方の資料としてオススメの一枚です。
2008年10月21日
次に向けて。
サクソフォンアンサンブルコンサートも終り、次に向けてのことを考えるようになりました。次は……なんだったっけ?
いくつか御呼ばれの演奏があった気がします。
この時期になると、アンサンブルコンテストに向けての練習も本格化し始める時期です。
それとは別に、私の所属する吹奏楽団、高松ウインドシンフォニーも来年の定期演奏会にむけて本格的に始動し、それと並行して11月2日に高松ウインドシンフォニーのアンサンブルコンサートが行われるので、その練習も佳境となっています。これが終わると、年末になったような気分になります。
そろそろ年末も近づいています。テレビでは年末特番等も放送されるのでしょうか…。
そこで今日の一枚です。
マスターピース19/ドイツの巨匠たちVol.2
指揮:木村吉宏
大阪市音楽団
東芝EMI TOCZ-0019
このCDはマスターピース・シリーズの中の一枚です。元々三枚組なのですが、現在は一枚単品買いが出来るようです。演奏は大阪市音楽団、オルフの「カルミナブラーナ」を中心に5曲が収録されています。
曲目はウェーバー(サフラネク編)歌劇「オイリアンテ」序曲、ワーグナー(オニール編)楽劇「ラインの黄金」からヴァルハラ城への神々の入場、メンデルスゾーン(レットフォード編)序曲「ルイ・ブラス」、ヒンデミット(ウィルソン編)「ウェーバーの主題による交響的変容」から行進曲、オルフ(クランス編)世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」から、おお、運命の女神よ、運命の女神の痛手を、見よ、今や楽しい、踊り、森は花咲き乱れる、たとえこの世界がみな、愛の神は飛びまわる、私は僧院長さまだぞ、酒場に私がいるときには、心を天秤にかけて、いとしい人、美しい乙女に幸いあれ、おお、運命の女神よ、となっています。
カルミナ・ブラーナは原曲は合唱つきなのですが、この吹奏楽編曲の演奏では歌無しです。その点では少し残念な気もします。このカルミナ・ブラーナの「おお、運命の女神よ」はよく、TVで災害のシーンや衝撃の映像、といったときに流れています。曲のイメージが鬼気迫る感じがしているということでよく使われるのだと思います。
大阪市音楽団の演奏は、関西系のバンドらしい、重厚で柔らかな響きをしています。わりと地味な演奏にも聞こえるかもしれませんが、それだけ響きと歌を大切にした演奏であるともいえるかもしれません。
カルミナ・ブラーナを吹奏楽で聞いてみたい方、大阪市音楽団の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
いくつか御呼ばれの演奏があった気がします。
この時期になると、アンサンブルコンテストに向けての練習も本格化し始める時期です。
それとは別に、私の所属する吹奏楽団、高松ウインドシンフォニーも来年の定期演奏会にむけて本格的に始動し、それと並行して11月2日に高松ウインドシンフォニーのアンサンブルコンサートが行われるので、その練習も佳境となっています。これが終わると、年末になったような気分になります。
そろそろ年末も近づいています。テレビでは年末特番等も放送されるのでしょうか…。
そこで今日の一枚です。
マスターピース19/ドイツの巨匠たちVol.2
指揮:木村吉宏
大阪市音楽団
東芝EMI TOCZ-0019
このCDはマスターピース・シリーズの中の一枚です。元々三枚組なのですが、現在は一枚単品買いが出来るようです。演奏は大阪市音楽団、オルフの「カルミナブラーナ」を中心に5曲が収録されています。
曲目はウェーバー(サフラネク編)歌劇「オイリアンテ」序曲、ワーグナー(オニール編)楽劇「ラインの黄金」からヴァルハラ城への神々の入場、メンデルスゾーン(レットフォード編)序曲「ルイ・ブラス」、ヒンデミット(ウィルソン編)「ウェーバーの主題による交響的変容」から行進曲、オルフ(クランス編)世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」から、おお、運命の女神よ、運命の女神の痛手を、見よ、今や楽しい、踊り、森は花咲き乱れる、たとえこの世界がみな、愛の神は飛びまわる、私は僧院長さまだぞ、酒場に私がいるときには、心を天秤にかけて、いとしい人、美しい乙女に幸いあれ、おお、運命の女神よ、となっています。
カルミナ・ブラーナは原曲は合唱つきなのですが、この吹奏楽編曲の演奏では歌無しです。その点では少し残念な気もします。このカルミナ・ブラーナの「おお、運命の女神よ」はよく、TVで災害のシーンや衝撃の映像、といったときに流れています。曲のイメージが鬼気迫る感じがしているということでよく使われるのだと思います。
大阪市音楽団の演奏は、関西系のバンドらしい、重厚で柔らかな響きをしています。わりと地味な演奏にも聞こえるかもしれませんが、それだけ響きと歌を大切にした演奏であるともいえるかもしれません。
カルミナ・ブラーナを吹奏楽で聞いてみたい方、大阪市音楽団の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年10月20日
演奏会終了。
昨日10月19日日曜日に、サクソフォンアンサンブルコンサート2008が開催されました。
私もダッパーサクセーバーズの一員として参加してきました。
来場人数も320人を超え、盛会のうちに幕を閉じることが出来ました。

ご来場いただいた皆様、ありがとうございます。
そして、演奏に参加された皆様、お疲れ様でした。
出来うれば、来年も再び同じステージで一緒に演奏できることを願っています。
裏方などでお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。
さて、演奏会が終わったので、私は録音編集の作業を開始しています。
ヘッドホンの掛けすぎで耳が痛くなってしまいます。
出来るだけ、皆さんに早く届けられるよう、ガンバリマス。

私もダッパーサクセーバーズの一員として参加してきました。
来場人数も320人を超え、盛会のうちに幕を閉じることが出来ました。

ご来場いただいた皆様、ありがとうございます。
そして、演奏に参加された皆様、お疲れ様でした。
出来うれば、来年も再び同じステージで一緒に演奏できることを願っています。
裏方などでお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。
さて、演奏会が終わったので、私は録音編集の作業を開始しています。
ヘッドホンの掛けすぎで耳が痛くなってしまいます。
出来るだけ、皆さんに早く届けられるよう、ガンバリマス。
Posted by のりくん at
23:57
│Comments(0)
2008年10月20日
紅葉の季節です。
サクソフォーンアンサンブルコンサート2008も無事終了。
さて、秋も本番、様々な演奏会が目白押しのシーズンともなっています。そんな中果たして我々の演奏会を聴きに着てくれるかどうかは不安ですが、お客さんが沢山聴きに来てくれることを祈っています。私の演奏はともかくとして他の人たちの演奏はすばらしい演奏ばかりですので、是非足を運んでいただきたいと思っています。
季節の方も秋らしくなってきました。今年は果たしてキレイな紅葉が見られるのかどうか…。寒暖の差が大きいほどキレイな紅葉が見られるようですが…。
そこで今日の一枚です。

ハチャトゥリアン/バレエ「スパルタクス」抜粋
「ガイーヌ」抜粋
作曲: ハチャトゥリャン
指揮:アラム・ハチャトゥリアン
指揮:エルネスト・アンセルメ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
スイス・ロマンド管弦楽団
DECCA(ユニバーサルミュージック) 289 460 315-2
このCDは、ハチャトゥリアンの自作自演にボーナストラックのような形でアンセルメのグラズノフの四季より秋が収録されたもの。
曲目としては、バレエ「スパルタクス」~スパルタクスとフリーギアのアダージョ、エギナとバッカナーリアのヴァリエーション、情景とクロタルムスの踊り、ガディスの娘の踊りとスパルタクスの勝利、バレエ「ガイーヌ」~剣の舞、アイシェの目覚めと踊り、レズギンカ、ガイーヌのアダージョ、ゴパーク、バレエ音楽「四季」op.67となっています。
ハチャトゥリアンの自作自演の方は思いっきりのいい感じの演奏で、ウィーンフィルらしく吼えるウィンナホルン、派手な演奏、テンポや縦の線が少々ずれようが気にすることなし、といったイメージの演奏です。悪く言えば、洗練されたところが無く、パワーで押し切った演奏と言う感じもしますが、それが作曲者の意図とも取ることが出来ます。
グラズノフの「四季」はバレエ音楽で、実際には1幕4場からなる小バレエ音楽。冬に始まり秋に終わるという構成になっています。バレエとしては特定の台本を持たず、自然の情景を表現した物になっています。全体的に美しい音楽で彩られ、アンセルメの演奏もこの曲をお得意としていただけあってか、やわらかく、すばらしい演奏になっています。(スイスロマンドの音は相変わらずの感じですが 笑)しかし、以前紹介したヴィヴァルディの四季でも書いたのですが、この曲を聴いても思うのですが、西洋では、やはり、秋が一年を通して一番いい時期となっているようです。この曲を聞いてもそれをうかがうことができます。
秋のひと時紅葉を見ながら想像しながらゆっくりと聴く音楽としてオススメの一枚です。
さて、秋も本番、様々な演奏会が目白押しのシーズンともなっています。そんな中果たして我々の演奏会を聴きに着てくれるかどうかは不安ですが、お客さんが沢山聴きに来てくれることを祈っています。私の演奏はともかくとして他の人たちの演奏はすばらしい演奏ばかりですので、是非足を運んでいただきたいと思っています。
季節の方も秋らしくなってきました。今年は果たしてキレイな紅葉が見られるのかどうか…。寒暖の差が大きいほどキレイな紅葉が見られるようですが…。
そこで今日の一枚です。

ハチャトゥリアン/バレエ「スパルタクス」抜粋
「ガイーヌ」抜粋
作曲: ハチャトゥリャン
指揮:アラム・ハチャトゥリアン
指揮:エルネスト・アンセルメ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
スイス・ロマンド管弦楽団
DECCA(ユニバーサルミュージック) 289 460 315-2
このCDは、ハチャトゥリアンの自作自演にボーナストラックのような形でアンセルメのグラズノフの四季より秋が収録されたもの。
曲目としては、バレエ「スパルタクス」~スパルタクスとフリーギアのアダージョ、エギナとバッカナーリアのヴァリエーション、情景とクロタルムスの踊り、ガディスの娘の踊りとスパルタクスの勝利、バレエ「ガイーヌ」~剣の舞、アイシェの目覚めと踊り、レズギンカ、ガイーヌのアダージョ、ゴパーク、バレエ音楽「四季」op.67となっています。
ハチャトゥリアンの自作自演の方は思いっきりのいい感じの演奏で、ウィーンフィルらしく吼えるウィンナホルン、派手な演奏、テンポや縦の線が少々ずれようが気にすることなし、といったイメージの演奏です。悪く言えば、洗練されたところが無く、パワーで押し切った演奏と言う感じもしますが、それが作曲者の意図とも取ることが出来ます。
グラズノフの「四季」はバレエ音楽で、実際には1幕4場からなる小バレエ音楽。冬に始まり秋に終わるという構成になっています。バレエとしては特定の台本を持たず、自然の情景を表現した物になっています。全体的に美しい音楽で彩られ、アンセルメの演奏もこの曲をお得意としていただけあってか、やわらかく、すばらしい演奏になっています。(スイスロマンドの音は相変わらずの感じですが 笑)しかし、以前紹介したヴィヴァルディの四季でも書いたのですが、この曲を聴いても思うのですが、西洋では、やはり、秋が一年を通して一番いい時期となっているようです。この曲を聞いてもそれをうかがうことができます。
秋のひと時紅葉を見ながら想像しながらゆっくりと聴く音楽としてオススメの一枚です。
2008年10月19日
演奏会本番ですが。
本日、サクソフォーンアンサンブルコンサート2008の本番でした。といいつつ、何の関係もない記事を書こうとしている私がいます。
演奏した方々、お疲れ様でした。
そしてお越しいただいた方々、どうもありがとうございました。いつも演奏が終わるたびに、拙い演奏をお聞かせして申し訳ないと思うのですが、次の年もまた同じように思ってしまうのは学習能力がないのか、なんなのか…。
もともと、私自身はそんなに技量もなく、高い音楽性を持っているわけではないので、ダッパーのメンバーや周りの皆さんに助けられて毎年の演奏をなんとか終えることが出来ています。
で、演奏会の件はまた別に書くとして、何の関係もなく、今日も「吹奏楽無節操企画」。
そこで今日の一枚。
A.リード&佼成ウインドオーケストラ「オセロ」
指揮:アルフレッド・リード
東京佼成ウインド・オーケストラ
佼成出版社 KOCD-3006
このCDはA.リードによるシェークスピア・シリーズの第二弾、「オセロ」が収録されているものです。
すべて、アルフレッド・リードの作曲で、曲目は、セカンド・センチュリー、シンフォニック・プレリュード、カリブ舞曲、ラッシュモア、オセロ、となっています。
さて、このオセロ、良くも悪くも「ハムレット」の兄弟曲というイメージです。場合によっては「曲が変わるシリーズ」などで、お互いの曲を何のためらいもなく行ったりきたりできそうです。まあ、リードらしい曲といってしまえばそれまでなのでしょうか。
予断ですが、オセロゲームという白黒のゲームがありますが、これは、このシェークスピアのオセロから取ったネーミングだとか。ちなみに、オセロゲームの原型は、茨城県で戦後にはやっていた、碁石を使ったゲームだったようです。ご存知の方も多いと思いますが、オセロゲームは日本人の考案したゲームです。ネーミングの由来はこのシェークスピアの物語に登場するデズデモナという白人の美女を白石、オセロというムーア人(黒人)を黒石にたとえたことからのようです。
演奏の方は昨日紹介した「ハムレットへの音楽」と同様に佼成ウインドらしい演奏です。ただ、これも同様に、オセロの全曲がきちんと演奏されていると言う点では貴重な存在です。
ハムレットへの音楽同様、吹奏楽の世界に足を踏み入れたすべての方にオススメの一枚です。
演奏した方々、お疲れ様でした。
そしてお越しいただいた方々、どうもありがとうございました。いつも演奏が終わるたびに、拙い演奏をお聞かせして申し訳ないと思うのですが、次の年もまた同じように思ってしまうのは学習能力がないのか、なんなのか…。
もともと、私自身はそんなに技量もなく、高い音楽性を持っているわけではないので、ダッパーのメンバーや周りの皆さんに助けられて毎年の演奏をなんとか終えることが出来ています。
で、演奏会の件はまた別に書くとして、何の関係もなく、今日も「吹奏楽無節操企画」。
そこで今日の一枚。
A.リード&佼成ウインドオーケストラ「オセロ」
指揮:アルフレッド・リード
東京佼成ウインド・オーケストラ
佼成出版社 KOCD-3006
このCDはA.リードによるシェークスピア・シリーズの第二弾、「オセロ」が収録されているものです。
すべて、アルフレッド・リードの作曲で、曲目は、セカンド・センチュリー、シンフォニック・プレリュード、カリブ舞曲、ラッシュモア、オセロ、となっています。
さて、このオセロ、良くも悪くも「ハムレット」の兄弟曲というイメージです。場合によっては「曲が変わるシリーズ」などで、お互いの曲を何のためらいもなく行ったりきたりできそうです。まあ、リードらしい曲といってしまえばそれまでなのでしょうか。
予断ですが、オセロゲームという白黒のゲームがありますが、これは、このシェークスピアのオセロから取ったネーミングだとか。ちなみに、オセロゲームの原型は、茨城県で戦後にはやっていた、碁石を使ったゲームだったようです。ご存知の方も多いと思いますが、オセロゲームは日本人の考案したゲームです。ネーミングの由来はこのシェークスピアの物語に登場するデズデモナという白人の美女を白石、オセロというムーア人(黒人)を黒石にたとえたことからのようです。
演奏の方は昨日紹介した「ハムレットへの音楽」と同様に佼成ウインドらしい演奏です。ただ、これも同様に、オセロの全曲がきちんと演奏されていると言う点では貴重な存在です。
ハムレットへの音楽同様、吹奏楽の世界に足を踏み入れたすべての方にオススメの一枚です。
2008年10月18日
演奏会まであと…1日。
明日はいよいよ、サクソフォーンアンサンブルコンサート当日。泣いても笑っても本番です。今日は前日リハを行いました。
私自身はかなりやばい状態ですが、皆さんはきっといい演奏を聞かせてくださると思っています。
あした私の代わりにクマのぬいぐるみとか置いてあったら、敵前逃亡したとご判断下さい。
さて、今日から少しの間、「今日の一枚」を吹奏楽特集にしたいと思っています。実は私、吹奏楽を長い間やっているのにもかかわらず、吹奏楽の曲にはそれほど詳しくないのです。その原因は中学、高校の頃の恩師の先生方が、オリジナルの吹奏楽よりも、クラシックからのアレンジ物を好んだという影響が大きいと思います。ゆえに、クラシックはよく聞いても、吹奏楽のオリジナル曲にはそれほど詳しくはありません。
そこで、今回も、オリジナル、クラシックからのアレンジ、様々取り合わせて紹介していきたいと思っています。つまり、演奏が吹奏楽であればなんでもあり、ということにさせていただきます。題して、「吹奏楽無節操企画」です。
そこで今日の一枚です。
A.リード&佼成ウインドオーケストラ「ハムレット」
指揮:アルフレッド・リード
東京佼成ウインド・オーケストラ
佼成出版社 KOCD-3007
このCDはアルフレッド・リードによる自作自演集の中の一枚です。東京佼成ウインド・オーケストラは、日本を代表するプロの吹奏楽団のひとつです。録音は1987年なので、すでに17年の年月が経過しています。
曲目は、テキサスを讃えて、プレリュードとカプリッチオ、プロセルピナの丘、ハムレットへの音楽、となっています。
ハムレットへの音楽は演奏したことはないのですが、若干の思い出があります。というのも、私は中学校から吹奏楽部に入部したのですが、3つ上の姉も中学校時代吹奏楽部で、私が中学生になる前の年、姉達が吹奏楽コンクールの自由曲で演奏したのがこの曲でした。この自由曲の演奏、1楽章をばっさり切って、その間に俳優達の入場を挿入してつなぎ合わせるというとんでもない荒業が、当時のコンクールで流行していました。初めてこの曲の正しい演奏をこのCDで聴いたときは少なからず衝撃を受けた記憶があります。このハムレットへの音楽、有名なアルメニアン・ダンスパート1よりも古い作曲年代の曲になります。
吹奏楽コンクールは、課題曲を含めて12分という演奏時間の制限があるがために、このような無謀ともいえる曲のカットが登場しますが、作曲者にとっては、あまり好ましいことではないのかもしれません。
その問題はあえて、ここではあまり論じませんが、作曲者のいとも重要だと思う、とだけ言っておきたいと思います。
東京佼成ウインドオーケストラの演奏は、可もなく不可もなく、という演奏、という印象が私には強いので、なんともいえません。しかし、全曲をリードの指揮できちんと演奏しているという面では貴重な録音のひとつです。
吹奏楽の世界に足を踏み入れた人すべてにオススメの一枚です。
私自身はかなりやばい状態ですが、皆さんはきっといい演奏を聞かせてくださると思っています。
あした私の代わりにクマのぬいぐるみとか置いてあったら、敵前逃亡したとご判断下さい。
さて、今日から少しの間、「今日の一枚」を吹奏楽特集にしたいと思っています。実は私、吹奏楽を長い間やっているのにもかかわらず、吹奏楽の曲にはそれほど詳しくないのです。その原因は中学、高校の頃の恩師の先生方が、オリジナルの吹奏楽よりも、クラシックからのアレンジ物を好んだという影響が大きいと思います。ゆえに、クラシックはよく聞いても、吹奏楽のオリジナル曲にはそれほど詳しくはありません。
そこで、今回も、オリジナル、クラシックからのアレンジ、様々取り合わせて紹介していきたいと思っています。つまり、演奏が吹奏楽であればなんでもあり、ということにさせていただきます。題して、「吹奏楽無節操企画」です。
そこで今日の一枚です。
A.リード&佼成ウインドオーケストラ「ハムレット」
指揮:アルフレッド・リード
東京佼成ウインド・オーケストラ
佼成出版社 KOCD-3007
このCDはアルフレッド・リードによる自作自演集の中の一枚です。東京佼成ウインド・オーケストラは、日本を代表するプロの吹奏楽団のひとつです。録音は1987年なので、すでに17年の年月が経過しています。
曲目は、テキサスを讃えて、プレリュードとカプリッチオ、プロセルピナの丘、ハムレットへの音楽、となっています。
ハムレットへの音楽は演奏したことはないのですが、若干の思い出があります。というのも、私は中学校から吹奏楽部に入部したのですが、3つ上の姉も中学校時代吹奏楽部で、私が中学生になる前の年、姉達が吹奏楽コンクールの自由曲で演奏したのがこの曲でした。この自由曲の演奏、1楽章をばっさり切って、その間に俳優達の入場を挿入してつなぎ合わせるというとんでもない荒業が、当時のコンクールで流行していました。初めてこの曲の正しい演奏をこのCDで聴いたときは少なからず衝撃を受けた記憶があります。このハムレットへの音楽、有名なアルメニアン・ダンスパート1よりも古い作曲年代の曲になります。
吹奏楽コンクールは、課題曲を含めて12分という演奏時間の制限があるがために、このような無謀ともいえる曲のカットが登場しますが、作曲者にとっては、あまり好ましいことではないのかもしれません。
その問題はあえて、ここではあまり論じませんが、作曲者のいとも重要だと思う、とだけ言っておきたいと思います。
東京佼成ウインドオーケストラの演奏は、可もなく不可もなく、という演奏、という印象が私には強いので、なんともいえません。しかし、全曲をリードの指揮できちんと演奏しているという面では貴重な録音のひとつです。
吹奏楽の世界に足を踏み入れた人すべてにオススメの一枚です。
2008年10月17日
フォーマル、カジュアル共用。
サクソフォンアンサンブルコンサートまで……あと………2日。やばいです。
さて、私の職場は基本的に制服もなければ、決められた服装というものが存在しません。職場や部署によっては、そろいのジャージやポロシャツがあったり、ジャケットやネクタイの使用がほぼ義務付けられているところも多いようですが、基本的に自由。
医療の現場なのですが、看護師もTシャツやポロシャツだったりします。私は看護師ではないのですが、外から来たいろいろな人と会う職種であるため、ある程度服装に気を使うことになります。
ネクタイはしていませんし、カッターシャツを着ているわけでもなく、シャツにチノパン、ジャケットという一見カジュアルに見える服装で、何となく無理すればフォーマルでもいけるんじゃない?ぐらいの服装をしています。カジュアルとフォーマルの間を行く服装というのが一番微妙で難しかったりします。
そこで今日の一枚です。

ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー他
指揮:マイケル・ティルソン・トーマス
コロンビア・ジャズバンド
ニューヨーク・フィルハーモニック
ロサンジェルス・フィルハーモニック
マイケル・ティルソン・トーマス(ピアノ)
ジョージ・ガーシュウィン(1925年製ピアノロール)
CBSソニー 22DC 5519
このCDはガーシュウィン自身が演奏したものを記録したピアノロールを使ったラプソディ・イン・ブルーを使用して、伴奏をつけたものをはじめ、ガーシュウィンの作品を収録したもの。
曲目は、ラプソディ・イン・ブルー(原典版)、パリのアメリカ人、セカンド・ラプソディ(ピアノとオーケストラのための)となっています。
ガーシュウィンは、いわずと知れた、セミクラシックという領域を開拓したともいえる人物です。ガーシュウィン自身はメンデルスゾーンのような作曲家になりたい、というようなことも言っていたようです。このラプソディ・イン・ブルーはオリジナルの編成に忠実に、そして、ガーシュウィン自身のピアノロールを使用しているため、当時の演奏が復刻されたような形になっているようです。この、ガーシュウィンの系譜はのちにバーンスタインのような作曲家にもつながるもので、アメリカ音楽として、セミクラシックという分野を確立したともいえます。まにジャンルにとらわれない、という面ではクラシックとジャズの共用、当時、自由の国アメリカらしい発想の自由さを持った音楽ともいえます。
ガーシュウィンの音楽を聴いてみたい方、特に、本人の貴重なピアノ・ロールの演奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、私の職場は基本的に制服もなければ、決められた服装というものが存在しません。職場や部署によっては、そろいのジャージやポロシャツがあったり、ジャケットやネクタイの使用がほぼ義務付けられているところも多いようですが、基本的に自由。
医療の現場なのですが、看護師もTシャツやポロシャツだったりします。私は看護師ではないのですが、外から来たいろいろな人と会う職種であるため、ある程度服装に気を使うことになります。
ネクタイはしていませんし、カッターシャツを着ているわけでもなく、シャツにチノパン、ジャケットという一見カジュアルに見える服装で、何となく無理すればフォーマルでもいけるんじゃない?ぐらいの服装をしています。カジュアルとフォーマルの間を行く服装というのが一番微妙で難しかったりします。
そこで今日の一枚です。

ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー他
指揮:マイケル・ティルソン・トーマス
コロンビア・ジャズバンド
ニューヨーク・フィルハーモニック
ロサンジェルス・フィルハーモニック
マイケル・ティルソン・トーマス(ピアノ)
ジョージ・ガーシュウィン(1925年製ピアノロール)
CBSソニー 22DC 5519
このCDはガーシュウィン自身が演奏したものを記録したピアノロールを使ったラプソディ・イン・ブルーを使用して、伴奏をつけたものをはじめ、ガーシュウィンの作品を収録したもの。
曲目は、ラプソディ・イン・ブルー(原典版)、パリのアメリカ人、セカンド・ラプソディ(ピアノとオーケストラのための)となっています。
ガーシュウィンは、いわずと知れた、セミクラシックという領域を開拓したともいえる人物です。ガーシュウィン自身はメンデルスゾーンのような作曲家になりたい、というようなことも言っていたようです。このラプソディ・イン・ブルーはオリジナルの編成に忠実に、そして、ガーシュウィン自身のピアノロールを使用しているため、当時の演奏が復刻されたような形になっているようです。この、ガーシュウィンの系譜はのちにバーンスタインのような作曲家にもつながるもので、アメリカ音楽として、セミクラシックという分野を確立したともいえます。まにジャンルにとらわれない、という面ではクラシックとジャズの共用、当時、自由の国アメリカらしい発想の自由さを持った音楽ともいえます。
ガーシュウィンの音楽を聴いてみたい方、特に、本人の貴重なピアノ・ロールの演奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年10月16日
眼鏡が…。
サクソフォーンアンサンブルコンサートまであと4日となりました。昨日もカルテット、ラージの練習が行われました。
さて、私は極度の近視で眼鏡を使用しているのですが、最近目がねから何かがポロポロ落ちてくるようになりました。現在チタンフレームを使用しているのですが、どうも、つや消し仕上げのつや消しの部分が剥がれ落ちているようです。このつや消し、おそらくはラッカーなどの塗装によってつや消しにしているようなのですが、それが剥がれ落ちているためにつや消しだったフレームが逆にぴかぴかになっています。
まあ、眼鏡自体に大きな問題はないので、普通に使うのには支障がありませんが…。
そこで今日の一枚です。

ファリャ/バレエ音楽「三角帽子」全曲 バレエ音楽「恋は魔術師」全曲
指揮:jシャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
ソプラノ:コレット・ボーギー
メゾ・ソプラノ:ユゲット・トゥランジョー
ソロ・バスーン:リヒャルト・ヘーニッヒ
LONDON(ポリドール)F35L-50140
このCDはデュトワ/モントリオール響による、ファリャの作品2曲を収録したものです。
「三角帽子」は、スペインの作曲家マニュエル・デ・ファリャ(1876~1946)の作品の中で、最も有名なバレエ音楽です。もともと、バレエの作品ですが、スペインらしい色彩感や、すばらしいオーケストレーションにより、バレエでなく、純粋なクラシックのコンサートでも耳にする曲となっています。
ファリャが40歳のときかの有名なロシアバレエ団のディアギレフから依頼され、作曲した曲です。物語はスペインの小説家アラルコンが、アンダルシアの民話をもとにした小説「三角帽子」によるもので、魅力的な粉屋の女房、彼女に横恋慕する三角帽子をかぶった市長と嫉妬深い彼女の亭主が巻き起こすドタバタ喜劇です。
この曲にはアンセルメ指揮/スイス・ロマンド管弦楽団の演奏が名演と言われていますが、このデュトワ盤はオケの上手さとさらに洗練された響きでアンセルメ盤の上を言っているかもしれません。ただ、アンセルメ盤はアンセルメ盤で味があっていいのかもしれません。
実はこのCD、CDというメディアが発売されてからまだ数年目でなんとクラシックのCDが一般的に3500円の時代のものです。で、買って間もない頃、CDのケースが割れてしまいました。当時、ケースもひとつ300円ぐらいした記憶があります。ケースが割れたときはショックでした。そんな思い出があります。
ファリャのスペイン色の豊かな色彩感あふれる音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、私は極度の近視で眼鏡を使用しているのですが、最近目がねから何かがポロポロ落ちてくるようになりました。現在チタンフレームを使用しているのですが、どうも、つや消し仕上げのつや消しの部分が剥がれ落ちているようです。このつや消し、おそらくはラッカーなどの塗装によってつや消しにしているようなのですが、それが剥がれ落ちているためにつや消しだったフレームが逆にぴかぴかになっています。
まあ、眼鏡自体に大きな問題はないので、普通に使うのには支障がありませんが…。
そこで今日の一枚です。

ファリャ/バレエ音楽「三角帽子」全曲 バレエ音楽「恋は魔術師」全曲
指揮:jシャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
ソプラノ:コレット・ボーギー
メゾ・ソプラノ:ユゲット・トゥランジョー
ソロ・バスーン:リヒャルト・ヘーニッヒ
LONDON(ポリドール)F35L-50140
このCDはデュトワ/モントリオール響による、ファリャの作品2曲を収録したものです。
「三角帽子」は、スペインの作曲家マニュエル・デ・ファリャ(1876~1946)の作品の中で、最も有名なバレエ音楽です。もともと、バレエの作品ですが、スペインらしい色彩感や、すばらしいオーケストレーションにより、バレエでなく、純粋なクラシックのコンサートでも耳にする曲となっています。
ファリャが40歳のときかの有名なロシアバレエ団のディアギレフから依頼され、作曲した曲です。物語はスペインの小説家アラルコンが、アンダルシアの民話をもとにした小説「三角帽子」によるもので、魅力的な粉屋の女房、彼女に横恋慕する三角帽子をかぶった市長と嫉妬深い彼女の亭主が巻き起こすドタバタ喜劇です。
この曲にはアンセルメ指揮/スイス・ロマンド管弦楽団の演奏が名演と言われていますが、このデュトワ盤はオケの上手さとさらに洗練された響きでアンセルメ盤の上を言っているかもしれません。ただ、アンセルメ盤はアンセルメ盤で味があっていいのかもしれません。
実はこのCD、CDというメディアが発売されてからまだ数年目でなんとクラシックのCDが一般的に3500円の時代のものです。で、買って間もない頃、CDのケースが割れてしまいました。当時、ケースもひとつ300円ぐらいした記憶があります。ケースが割れたときはショックでした。そんな思い出があります。
ファリャのスペイン色の豊かな色彩感あふれる音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年10月15日
本当に吹けるのか?
季節はすっかり秋で朝晩、肌寒いぐらいになってきました。ボチボチ、寝るときに毛布を出してもいいかもしれません。今までは当然夏物のタオルケット布団。私は結構な暑がりなのです。
さて、先日からも書いているように、サクソフォンアンサンブルコンサートまであとわずか、あと4日となってしまいました。カウントダウン状態です。実は今回の選曲も結構ハードで、まだまだ十分にふけない場所があったりします。あと、4日間の間に何とかしなければならないのですが、本当に大丈夫か自信は全くありません。
しかし、いい演奏はしたいのでがんばるしかありません。
そこで今日の一枚です。
吹奏楽名曲コレクション33
サクソフォーン・アンサンブル・名曲集2
キャトル・ロゾー・サクソフォーン・アンサンブル
東芝EMI TOCZ-9197
このCDはキャトル・ロゾーによるサクソフォーンアンサンブル曲集です。
曲目は、セレナード (原博)、半音階的ワルツ (ヴェローヌ)、アンダンテとスケルツェット (ランティエ)、ブタド (シモニ)、サクソフォン4重奏曲より 第3楽章「蝶々」 (ジャンジャン)、サクソフォン4重奏曲第1番より アレグロ・ドゥ・コンセール (サンジュレ)、組曲 (アプシル)、小組曲 (フランセ)、序奏とスケルツォ (クレリス)、サクソフォン4重奏曲 (デザンクロ) となっています。
個人的な好みかもしれませんが、デザンクロの演奏はこれより前に録音されているものの演奏の方が私は好きです。また、原博氏のセレナードは私も演奏したいと思ったのですが、楽譜がセット販売のものに含まれていて、金柑アンサンブルなどの必要無い楽譜を大量に一緒に買わなければなりません。金額も20万円位します。なので、あきらめました。
この中に入っている、半音階的ワルツは我々が昔、演奏会のアンコールにしようとして、やめた曲。これにもいきさつがあって、アンコールを何にしようか演奏会の直前に決めようとしていて、O本師匠がこの曲ぐらいだったら簡単、という言葉を信じて、一度やってみたのですが、見事に直前に練習したぐらいでは無理なことに気づき、他の曲と差し替えた記憶があります。ちょっと我々にとってはいわくつきの曲です。
キャトル・ロゾーの音色としてはこれ以前のものの方が私は好きなのですが、サンジュレーのルフェーブル版の音源などが、収録されているという点では貴重な録音です。
サクソフォーンを吹いている中高生の方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
さて、先日からも書いているように、サクソフォンアンサンブルコンサートまであとわずか、あと4日となってしまいました。カウントダウン状態です。実は今回の選曲も結構ハードで、まだまだ十分にふけない場所があったりします。あと、4日間の間に何とかしなければならないのですが、本当に大丈夫か自信は全くありません。
しかし、いい演奏はしたいのでがんばるしかありません。
そこで今日の一枚です。
吹奏楽名曲コレクション33
サクソフォーン・アンサンブル・名曲集2
キャトル・ロゾー・サクソフォーン・アンサンブル
東芝EMI TOCZ-9197
このCDはキャトル・ロゾーによるサクソフォーンアンサンブル曲集です。
曲目は、セレナード (原博)、半音階的ワルツ (ヴェローヌ)、アンダンテとスケルツェット (ランティエ)、ブタド (シモニ)、サクソフォン4重奏曲より 第3楽章「蝶々」 (ジャンジャン)、サクソフォン4重奏曲第1番より アレグロ・ドゥ・コンセール (サンジュレ)、組曲 (アプシル)、小組曲 (フランセ)、序奏とスケルツォ (クレリス)、サクソフォン4重奏曲 (デザンクロ) となっています。
個人的な好みかもしれませんが、デザンクロの演奏はこれより前に録音されているものの演奏の方が私は好きです。また、原博氏のセレナードは私も演奏したいと思ったのですが、楽譜がセット販売のものに含まれていて、金柑アンサンブルなどの必要無い楽譜を大量に一緒に買わなければなりません。金額も20万円位します。なので、あきらめました。
この中に入っている、半音階的ワルツは我々が昔、演奏会のアンコールにしようとして、やめた曲。これにもいきさつがあって、アンコールを何にしようか演奏会の直前に決めようとしていて、O本師匠がこの曲ぐらいだったら簡単、という言葉を信じて、一度やってみたのですが、見事に直前に練習したぐらいでは無理なことに気づき、他の曲と差し替えた記憶があります。ちょっと我々にとってはいわくつきの曲です。
キャトル・ロゾーの音色としてはこれ以前のものの方が私は好きなのですが、サンジュレーのルフェーブル版の音源などが、収録されているという点では貴重な録音です。
サクソフォーンを吹いている中高生の方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
2008年10月14日
サクソフォーンアンサンブルコンサート2008のご案内
さて、いよいよ、今週末の日曜に、サクソフォーンアンサンブルコンサート2008が開催されます。
今回も、幕前演奏あり、カルテットあり、クインテットあり、そしてラージありと、ダッパーをはじめ様々な団体の演奏が盛りだくさんの演奏会となっています。
本番も迫ってきましたので、演奏会のご案内をさせていただきます。

日時:2008年10月19日(日) 13:30開場、14:00開演
場所:アルファあなぶきホール、小ホール(香川県県民ホール、アクトホール)
曲目:
・アンダンテとスケルツォ/ボザ
・民謡風ロンドの主題による序奏と変奏/ピエルネ
・東回りの風/織田英子
・フライミー・トゥ・ザ・ムーン/バート・ハワード
・キャラバンの到着/ミシェル・ルグラン
・タンゴの歴史/ピアソラ
・ダンシング・クィーン/アバ
・イパネマの娘/アントニオ・カルロス・ジョビン
・カンタベリーコラール/ヤン・ヴァン・デル・ロースト
・ニュルンベルクのマイスタージンガーより前奏曲/ワーグナー
他
入場無料
当日、お時間のある方は是非アルファあなぶきホール(小ホール)お越しくださいませ。
今回も、幕前演奏あり、カルテットあり、クインテットあり、そしてラージありと、ダッパーをはじめ様々な団体の演奏が盛りだくさんの演奏会となっています。
本番も迫ってきましたので、演奏会のご案内をさせていただきます。
日時:2008年10月19日(日) 13:30開場、14:00開演
場所:アルファあなぶきホール、小ホール(香川県県民ホール、アクトホール)
曲目:
・アンダンテとスケルツォ/ボザ
・民謡風ロンドの主題による序奏と変奏/ピエルネ
・東回りの風/織田英子
・フライミー・トゥ・ザ・ムーン/バート・ハワード
・キャラバンの到着/ミシェル・ルグラン
・タンゴの歴史/ピアソラ
・ダンシング・クィーン/アバ
・イパネマの娘/アントニオ・カルロス・ジョビン
・カンタベリーコラール/ヤン・ヴァン・デル・ロースト
・ニュルンベルクのマイスタージンガーより前奏曲/ワーグナー
他
入場無料
当日、お時間のある方は是非アルファあなぶきホール(小ホール)お越しくださいませ。




