2008年04月30日
成功すると。

まあ、失敗っぽい出来上がりだった似非蒸しパンですが、
一応、レシピなんぞを。
ホットケーキミックス 200g
卵 1個
牛乳 150cc
マヨネーズ 適量
チョコレート(板チョコもしくは、チョコチップ) 適量
空の牛乳パック×2個
まず、卵、牛乳、マヨネーズはしっかり混ぜます。で、そこにホットケーキミックスを投入。
ゴムべらなんかでさっくりと混ぜます。
板チョコは包丁で刻むなどして細かくしてください。甘さを抑えたいときは、ブラックチョコか、最近流行のカカオ80パーセントとかのチョコレートを使うと良いかもしれません。チョコレートの量もお好みで。
混ぜあがったものを、お玉ですくい、牛乳パックへ。
お玉で一杯入れたらチョコレートを振り入れます。これを何回か繰り返して、いきます。
今回は牛乳パック2個分なので、計るのが面倒な時は片方に一杯入れてはもう片方に一杯という風にしていくと、
同じぐらいの量に仕上がると思います。
で、注ぎ終わったら、牛乳パックの上の方をカット。
経験上、溢れる恐れがあるので、電子レンジに収まる範囲で出来るだけ上の方を切りましょう。
切ったら、ラップを着せて電子レンジへ。
加熱時間は、電子レンジの出力にもよりますが、大抵は3~5分くらいだと思います。
心配な時は竹串などで、具合を見てください。
で、出来上がったら1~2分放置。熱が取れたら、牛乳パックを破って開きます。
で、一応出来上がり。
牛乳パックが無い時は深めの器にラップを敷いてミックスを流し込むと良いと思います。実際、今回やってみました。
ただ、牛乳パックよりも加熱時間は短めでも良いようです。
加熱しすぎて多少ぱさぱさになりました。
いや、ぱさぱさになった要因は他にもあって、実は、卵がLサイズだったので、牛乳を多少控えたのですが、それがまずかったようです。
チョコレートではなく、ラムレーズンやナッツを入れてもいいかもしれません。
また、混ぜる時に抹茶を振りいれて、ゆで小豆なんかを入れると、抹茶味の和風のケーキが出来上がると思います。
2008年04月30日
近づく夏。
今日も暖かい一日でした。さすがに夕方になると少し冷えてきますが、それでも、春を過ぎてもう夏がすぐそこまで来ている気がします。まだ梅雨も迎えていませんが。
私は、夏が苦手です。というのも、暑さに極端に弱いからです。夏になれば、睡眠時間も減り続け、日差しに焼かれながらフラフラする日が続きます。
まあ、夏は夏で、いいこともあるのはあるのですが。
そこで今日の一枚。
MASTER PIECE "吹奏楽:スペインの巨匠達"
指揮:林 紀人
シエナ・ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ-0008
このCDは東芝EMIの吹奏楽MASTER PIECEシリーズの8枚目のCDです。今はおそらく単品発売されていますが、当時は3枚セットで売られていたものを買いました。ジャケットには一面のひまわり畑の中に小さな建物の建っている写真が使われています。
で、シエナ・ウインドオーケストラはCl.の近藤さんが以前在籍していたバンドです。去年、退団されて、いまは自衛隊にいらっしゃいます。なので、おそらくはこのCDにも参加されていると思います。(昨日確認するのを忘れてしまったので、真偽は定かではありません)そして、このCDのなかに収録されているアルベニスの組曲「スペインの歌よりコルドバ」は機能演奏した曲でもあります。
このCDを聞くと、我々もこれぐらいの演奏が出来れば…。というような土台無理なことを考えてしまいます。昨日近藤さんは別の曲のソリストだったので我々の演奏を聞いていらっしゃったかどうかは不明ですが、もし聞かれていたらどう思われたのだろうか、と多少ビクビクしてしまいます。
吹奏楽に編曲された、アルベニス、ファリャの作品を聴いてみたい方におオススメの一枚です。
明日は20回記念定期演奏会続編をお送りいたします。(笑)
私は、夏が苦手です。というのも、暑さに極端に弱いからです。夏になれば、睡眠時間も減り続け、日差しに焼かれながらフラフラする日が続きます。
まあ、夏は夏で、いいこともあるのはあるのですが。
そこで今日の一枚。
MASTER PIECE "吹奏楽:スペインの巨匠達"
指揮:林 紀人
シエナ・ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ-0008
このCDは東芝EMIの吹奏楽MASTER PIECEシリーズの8枚目のCDです。今はおそらく単品発売されていますが、当時は3枚セットで売られていたものを買いました。ジャケットには一面のひまわり畑の中に小さな建物の建っている写真が使われています。
で、シエナ・ウインドオーケストラはCl.の近藤さんが以前在籍していたバンドです。去年、退団されて、いまは自衛隊にいらっしゃいます。なので、おそらくはこのCDにも参加されていると思います。(昨日確認するのを忘れてしまったので、真偽は定かではありません)そして、このCDのなかに収録されているアルベニスの組曲「スペインの歌よりコルドバ」は機能演奏した曲でもあります。
このCDを聞くと、我々もこれぐらいの演奏が出来れば…。というような土台無理なことを考えてしまいます。昨日近藤さんは別の曲のソリストだったので我々の演奏を聞いていらっしゃったかどうかは不明ですが、もし聞かれていたらどう思われたのだろうか、と多少ビクビクしてしまいます。
吹奏楽に編曲された、アルベニス、ファリャの作品を聴いてみたい方におオススメの一枚です。
明日は20回記念定期演奏会続編をお送りいたします。(笑)
2008年04月29日
大失敗…なのか。
今日は午前中は、久々に車の洗車。
珍しく3週間以上洗車せずに、鳥の糞もほったらかしだったので、少々念入りに洗車。
といってもいつものテキトーさ加減なので、綺麗さもたかが知れていますが。
で、午後から、まだまだあまっているホットケーキミックスを使って似非蒸しパンを作ってみましたが…。

ホットケーキミックスに混ぜるものは、ホットケーキミックスの裏に書いてあるホットケーキの配合を基準にします。
で、それに…本来はサラダ油とかでしょうが、ここはいつものマヨネーズ。
ここからがポイントですが、このミックスを空の牛乳パックに流し込んでは、チョコチップ、流し込んではチョコチップを繰り返します。
で、テキトーな量を入れたら、牛乳パックの上の方は電子レンジに入るぐらいの高さにカット。
ただ、ミックスをどうも入れすぎたようです。膨らむことを想像して多少少なめに入れたものの、想像以上に膨らんだため、ミックスが溢れて、電子レンジ内が大変なことに。
一応、牛乳パックに残ったまともな部分だけ切り取って完成品ということで…。
珍しく3週間以上洗車せずに、鳥の糞もほったらかしだったので、少々念入りに洗車。
といってもいつものテキトーさ加減なので、綺麗さもたかが知れていますが。
で、午後から、まだまだあまっているホットケーキミックスを使って似非蒸しパンを作ってみましたが…。

ホットケーキミックスに混ぜるものは、ホットケーキミックスの裏に書いてあるホットケーキの配合を基準にします。
で、それに…本来はサラダ油とかでしょうが、ここはいつものマヨネーズ。
ここからがポイントですが、このミックスを空の牛乳パックに流し込んでは、チョコチップ、流し込んではチョコチップを繰り返します。
で、テキトーな量を入れたら、牛乳パックの上の方は電子レンジに入るぐらいの高さにカット。
ただ、ミックスをどうも入れすぎたようです。膨らむことを想像して多少少なめに入れたものの、想像以上に膨らんだため、ミックスが溢れて、電子レンジ内が大変なことに。
一応、牛乳パックに残ったまともな部分だけ切り取って完成品ということで…。
2008年04月29日
いよいよ本番という時。
今日も比較的天気が良い一日となりました。先日も書きましたが、演奏会の当日も天気が良いことをいつも願っています。天気もそうですが、本当にいい本番、いい一日にしたい、それが本番に対する切なる私の願です。自分自身にとっても、一緒に演奏する人間にっても、聴きに来てくださる方々にとっても、いい演奏会にしたいと思うのが常。もちろん、本番の醍醐味もしっかり味わいたいという思いも忘れずに、ですが。
さて、そこで今日の一枚。

寺井尚子/ライヴ
ONE VOICE (ビデオアーツ)VACV-1039
このCDはJAZZバイオリニスト、寺井尚子さんのライヴ・アルバム。2000年に行なわれた「プリンセス T」ツアーの愛知芸術劇場での演奏の録音です。
昨日、熱帯JAZZ楽団のライヴ・アルバムを紹介しましたが、このCDもそれに負けず劣らず熱い演奏を繰り広げています。さらに、客席と、ステージとの距離がより近い感覚うける録音です。
このアルバムの中で私の一押しは誰がなんと言おうと、「スペイン」。この曲はチック・コリアの作曲によるものですが、さまざまなアーティストが、カバー、編曲している名曲です。曲自体もスパ二ッシュなテイストが熱いものですが、演奏自体もライヴならではの熱さがあります。
バイオリンはクラシックの楽器だと信じて疑わない方、熱いテイストの「スペイン」を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、そこで今日の一枚。

寺井尚子/ライヴ
ONE VOICE (ビデオアーツ)VACV-1039
このCDはJAZZバイオリニスト、寺井尚子さんのライヴ・アルバム。2000年に行なわれた「プリンセス T」ツアーの愛知芸術劇場での演奏の録音です。
昨日、熱帯JAZZ楽団のライヴ・アルバムを紹介しましたが、このCDもそれに負けず劣らず熱い演奏を繰り広げています。さらに、客席と、ステージとの距離がより近い感覚うける録音です。
このアルバムの中で私の一押しは誰がなんと言おうと、「スペイン」。この曲はチック・コリアの作曲によるものですが、さまざまなアーティストが、カバー、編曲している名曲です。曲自体もスパ二ッシュなテイストが熱いものですが、演奏自体もライヴならではの熱さがあります。
バイオリンはクラシックの楽器だと信じて疑わない方、熱いテイストの「スペイン」を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年04月28日
人間業とは。
先日、高松ウインドシンフォニーで「動物の謝肉祭」の「白鳥」のソロを吹きました。
自分で吹いていて、自分の音色に凹んでしまうわけですが…。
サクソフォーンを趣味で吹き続けることはや○十年。へたっぴなので、色々課題は多いのですが、最近いつも思うのは音色と、全音域での音色の統一感。
良い音色を目指すのは当たり前なのですが、それに加えて、全ての音域で統一された音色が持てることが最近どれほど難しく重要なことかと感じています。
そもそも、ロングトーンをはじめとした基礎練習が不足しているので、音色の統一どころか、もっともっと基礎的な部分をクリアしなければならないのが事実なのですが…。
そこで今日の一枚。
「Saxophone For A Lady」
BIS CD-1020
このアルバムは、クロード・ドゥラングルによる、ドビュッシーやラヴェルの作品が収録されたもの。ドゥラングルの控え目なビブラートと、ストレートで上品な音色で聴くと、またミュールらの演奏とは違う趣で聞こえてくるのが不思議です。しかし、ドゥラングルの演奏を聴くと、いつも思うのはその徹底的ともいえる、音色のコントロール。プロの演奏やCDでも、特に低音のコントロールに関しては音色の変化が聞いて取れるものも多い中、ドゥラングルの演奏だけは、徹底して、低音でも同じ音色に統一されています。低い音域でも音色が変わらないので、どこか不思議な感覚すら覚えるほど。楽譜を見ると音を聴くと確かに、低い音域にも関わらず、まるで中音域のように飄々とコントロールしているかのような演奏です。
ドゥラングルの端正で飄々としながら、柔らかく美しい演奏が聞けるオススメの一枚です。
自分で吹いていて、自分の音色に凹んでしまうわけですが…。
サクソフォーンを趣味で吹き続けることはや○十年。へたっぴなので、色々課題は多いのですが、最近いつも思うのは音色と、全音域での音色の統一感。
良い音色を目指すのは当たり前なのですが、それに加えて、全ての音域で統一された音色が持てることが最近どれほど難しく重要なことかと感じています。
そもそも、ロングトーンをはじめとした基礎練習が不足しているので、音色の統一どころか、もっともっと基礎的な部分をクリアしなければならないのが事実なのですが…。
そこで今日の一枚。
「Saxophone For A Lady」
BIS CD-1020
このアルバムは、クロード・ドゥラングルによる、ドビュッシーやラヴェルの作品が収録されたもの。ドゥラングルの控え目なビブラートと、ストレートで上品な音色で聴くと、またミュールらの演奏とは違う趣で聞こえてくるのが不思議です。しかし、ドゥラングルの演奏を聴くと、いつも思うのはその徹底的ともいえる、音色のコントロール。プロの演奏やCDでも、特に低音のコントロールに関しては音色の変化が聞いて取れるものも多い中、ドゥラングルの演奏だけは、徹底して、低音でも同じ音色に統一されています。低い音域でも音色が変わらないので、どこか不思議な感覚すら覚えるほど。楽譜を見ると音を聴くと確かに、低い音域にも関わらず、まるで中音域のように飄々とコントロールしているかのような演奏です。
ドゥラングルの端正で飄々としながら、柔らかく美しい演奏が聞けるオススメの一枚です。
2008年04月28日
本番への意気込み。
今日はサクソフォーンアンサンブルの練習。朝から夕方まで練習でした。
直近の本番は一般には非公開なのですが、5月の1日。平日の夕方からです。
本番が迫ってくるにしたがって焦りの色が濃く現れてきますが、それも限界があって、最終的には諦めに似た感覚に落ちいたりもします。本番を恐がる人もいますが、私は基本的に本番が一番楽しいと思っています。
よく、回りの人たちは、本番が終わった後にいいお酒が飲めるようにいい演奏をしましょう、とか、本番後のお酒を楽しみに演奏してます、みたいなことを言うのですが、私はちょっと違います。
まず、私は下戸なのでお酒が飲めません。飲んでも美味しいと思ったこともありません。まあ、お酒と言う言葉は、ものの例えと解釈しても、やはり一番は自分も満足した演奏が出来て、お客さんにも喜んでもらえた時が一番だと思っています。演奏会の後で、「今日の演奏は素晴らしかったです、」などと聞くと、涙を流したくなるほど嬉しくなります。
そして、それを目指すために一生懸命で練習しています。本番で失敗することが無い様、普段に精一杯失敗をしながら、自分達の音楽を表現するために、日夜トレーニングをする必要があるわけです。本番のステージでは、それを十分に発揮できる演奏にしたいと願っています。演奏者としても、音楽を伝える人間としてもです。
そこに本番でしかありえない、会場の人たちとの対話や、感覚のシェアがあると思っています。ライブならではの醍醐味です。
でも、意気込みだけは立派にもかかわらず、毎年なかなか到達できない部分でもあります。
そこで今日の一枚です。

ライヴ・イン・ヨコハマ/熱帯JAZZ楽団
(Tropical Jazz Big Band)
ビクターエンターテイメント VICJ-60168
このCDはTropical Jazz Big Bandの横浜ランドマークホールでのライヴ録音です。
当然ながらスタジオ録音とはまたちがった熱気と雰囲気が伝わってきます。また、ライヴでありながらも演奏的にも破綻したところが無く、スタジオ録音に勝るとも劣らない演奏。
クラシックのライブ録音の中には場合によっては何箇所かでの公演の中からいい部分だけをつなぎ合わせたりすることをしますが、その点、JAZZのライヴ場合はホントに会場で一発録音のことが多いようです。ただ、スタジオ録音の方はJAZZの場合、奏者が一人ずつ、別々に演奏し、後でディレクターやミキサーの手によってトラックダウンし、曲に仕上げることがJAZZの場合は多いようです。
クラシックのオケなどはまずそういう録音はしないと思いますが。
演奏の方はとにかく熱い演奏。皆、ノリノリで、会場にいたならば、もっと、もっと熱かったであろうことを予感させます。また、録音も秀逸で、ライヴ録音にありがちな各楽器や、ソロが何をしているかわからなくなる、という現象も見られません。これはもしかしたら、奏者の方が秀逸なためかもしれませんが。
これから、夏に向けてのノリノリな曲をお探しの方、ラテン系のJAZZバンドをお探しの方にお勧めの一枚です。
直近の本番は一般には非公開なのですが、5月の1日。平日の夕方からです。
本番が迫ってくるにしたがって焦りの色が濃く現れてきますが、それも限界があって、最終的には諦めに似た感覚に落ちいたりもします。本番を恐がる人もいますが、私は基本的に本番が一番楽しいと思っています。
よく、回りの人たちは、本番が終わった後にいいお酒が飲めるようにいい演奏をしましょう、とか、本番後のお酒を楽しみに演奏してます、みたいなことを言うのですが、私はちょっと違います。
まず、私は下戸なのでお酒が飲めません。飲んでも美味しいと思ったこともありません。まあ、お酒と言う言葉は、ものの例えと解釈しても、やはり一番は自分も満足した演奏が出来て、お客さんにも喜んでもらえた時が一番だと思っています。演奏会の後で、「今日の演奏は素晴らしかったです、」などと聞くと、涙を流したくなるほど嬉しくなります。
そして、それを目指すために一生懸命で練習しています。本番で失敗することが無い様、普段に精一杯失敗をしながら、自分達の音楽を表現するために、日夜トレーニングをする必要があるわけです。本番のステージでは、それを十分に発揮できる演奏にしたいと願っています。演奏者としても、音楽を伝える人間としてもです。
そこに本番でしかありえない、会場の人たちとの対話や、感覚のシェアがあると思っています。ライブならではの醍醐味です。
でも、意気込みだけは立派にもかかわらず、毎年なかなか到達できない部分でもあります。
そこで今日の一枚です。

ライヴ・イン・ヨコハマ/熱帯JAZZ楽団
(Tropical Jazz Big Band)
ビクターエンターテイメント VICJ-60168
このCDはTropical Jazz Big Bandの横浜ランドマークホールでのライヴ録音です。
当然ながらスタジオ録音とはまたちがった熱気と雰囲気が伝わってきます。また、ライヴでありながらも演奏的にも破綻したところが無く、スタジオ録音に勝るとも劣らない演奏。
クラシックのライブ録音の中には場合によっては何箇所かでの公演の中からいい部分だけをつなぎ合わせたりすることをしますが、その点、JAZZのライヴ場合はホントに会場で一発録音のことが多いようです。ただ、スタジオ録音の方はJAZZの場合、奏者が一人ずつ、別々に演奏し、後でディレクターやミキサーの手によってトラックダウンし、曲に仕上げることがJAZZの場合は多いようです。
クラシックのオケなどはまずそういう録音はしないと思いますが。
演奏の方はとにかく熱い演奏。皆、ノリノリで、会場にいたならば、もっと、もっと熱かったであろうことを予感させます。また、録音も秀逸で、ライヴ録音にありがちな各楽器や、ソロが何をしているかわからなくなる、という現象も見られません。これはもしかしたら、奏者の方が秀逸なためかもしれませんが。
これから、夏に向けてのノリノリな曲をお探しの方、ラテン系のJAZZバンドをお探しの方にお勧めの一枚です。
2008年04月27日
迫る本番。(もう終わったけど)
高松ウインドシンフォニーの定期演奏会が終わってから早一週間。私が始めてウインドシンフォニーの定期演奏会に参加した時は、シベリウスの「カレリア」組曲や、P.スパークの「ドラゴンの年」などを演奏した記憶があります。もちろん、その年の吹奏楽コンクール課題曲も演奏しました。
当時、課題曲は楽譜の頒布開始がその年の4月でした。そして、その当時うちの団の定期演奏会は4月の第1週目の日曜日と決まっていたため、当時おそらくどこよりも早く課題曲を全曲演奏するアマチュアの吹奏楽団だったはずです。練習できる日数は4日から5日くらいでした。今は、前年の12月末には楽譜が手元に届くので、それを考えると、当時は無謀なことをしていたんだと思います。
しかし、定期演奏会の日程が迫ってくると、精神的にも、肉体的にも追い詰められてきます。時間的余裕もなくなり、定演のことばかりを考えるようになってしまいます。ソロで落っこちる夢に何度うなされたことか。
さて、そこで今日の一枚。
シベリウス/交響曲第2番&カレリア、フィンランディア
指揮:ユッカ=ペッカ・サラステ
フィンランド放送交響楽団
RCA BMGビクター R32C-114
このCDは、シベリウス作品の王道を行く、演奏者、曲目によるアルバム。「カレリア」は、序曲と組曲が収録されています。
交響曲第一番はシベリウス初の本格的な交響曲と位置付けられるものです。
私は、「カレリア」組曲には思い出があります。私の高校時代の吹奏楽部顧問で恩師のI先生。今回も高松ウインドシンフォニーの演奏会でタクトをとっていただきましたが、このI先生がよく、吹奏楽でこの曲を取り上げていました。 そして、私が高松ウインドシンフォニーに入団した時の定期演奏会でもこの曲をI先生の指揮で演奏しました。
多分、I先生、お好きな曲なんだと思います。私の経験上、クラリネットを吹く吹奏楽の指揮者の方はお好きな方がなぜか多いようです。もちろん、オケではなく、吹奏楽で演奏して、という話ですが。
サラステの演奏は、この後、ライブ録音されたシベリウス交響曲全集を名盤と言う方が多いようです。私は聴いたことがないのでなんともいえませんが。演奏は全身にエネルギーがみなぎるような若々しさを感じるもの。しかし、荒さは無く、しっかりとしたバランスで整えられています。多少、表現が淡白に感じるところもありますが、全体の構造はしっかりと作られていると思います。
派手な演奏ではありませんが、力強さと、しなやかさ、北欧の澄んだ空気を感じさせるような演奏です。
因みに、「フィンランディア」は映画「ダイハード2」の中で使われた曲です。(飛行機が下りてくるシーン)
「フィンランディア」が聞いてみたい方、シベリウスの曲をちょっとしっかり聞いてみたい方、北欧の音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
当時、課題曲は楽譜の頒布開始がその年の4月でした。そして、その当時うちの団の定期演奏会は4月の第1週目の日曜日と決まっていたため、当時おそらくどこよりも早く課題曲を全曲演奏するアマチュアの吹奏楽団だったはずです。練習できる日数は4日から5日くらいでした。今は、前年の12月末には楽譜が手元に届くので、それを考えると、当時は無謀なことをしていたんだと思います。
しかし、定期演奏会の日程が迫ってくると、精神的にも、肉体的にも追い詰められてきます。時間的余裕もなくなり、定演のことばかりを考えるようになってしまいます。ソロで落っこちる夢に何度うなされたことか。
さて、そこで今日の一枚。
シベリウス/交響曲第2番&カレリア、フィンランディア
指揮:ユッカ=ペッカ・サラステ
フィンランド放送交響楽団
RCA BMGビクター R32C-114
このCDは、シベリウス作品の王道を行く、演奏者、曲目によるアルバム。「カレリア」は、序曲と組曲が収録されています。
交響曲第一番はシベリウス初の本格的な交響曲と位置付けられるものです。
私は、「カレリア」組曲には思い出があります。私の高校時代の吹奏楽部顧問で恩師のI先生。今回も高松ウインドシンフォニーの演奏会でタクトをとっていただきましたが、このI先生がよく、吹奏楽でこの曲を取り上げていました。 そして、私が高松ウインドシンフォニーに入団した時の定期演奏会でもこの曲をI先生の指揮で演奏しました。
多分、I先生、お好きな曲なんだと思います。私の経験上、クラリネットを吹く吹奏楽の指揮者の方はお好きな方がなぜか多いようです。もちろん、オケではなく、吹奏楽で演奏して、という話ですが。
サラステの演奏は、この後、ライブ録音されたシベリウス交響曲全集を名盤と言う方が多いようです。私は聴いたことがないのでなんともいえませんが。演奏は全身にエネルギーがみなぎるような若々しさを感じるもの。しかし、荒さは無く、しっかりとしたバランスで整えられています。多少、表現が淡白に感じるところもありますが、全体の構造はしっかりと作られていると思います。
派手な演奏ではありませんが、力強さと、しなやかさ、北欧の澄んだ空気を感じさせるような演奏です。
因みに、「フィンランディア」は映画「ダイハード2」の中で使われた曲です。(飛行機が下りてくるシーン)
「フィンランディア」が聞いてみたい方、シベリウスの曲をちょっとしっかり聞いてみたい方、北欧の音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
Posted by のりくん at
00:04
│Comments(0)
2008年04月26日
ソプラノ・サクソフォーンな訳。その2
今日もいい天気です。ゴールデンウィークの間は天気がどうなのかは判りませんが、何の行楽も予定されていない私にとってはあまり関係がありません。
先日、高松ウインドシンフォニーの演奏会が無事に終了しましたが、入場料の安いアマチュアの演奏会は手軽な反面、天気やちょっとした事情でお客さんが減ってしまうことがあるので悩みの種だったりします。これがメジャーな人の一枚2万円位するプレミア・チケットなら天気があろうが、仕事が入ろうが何とかして聴きにいくと思うのですが、我々の演奏会ではそうはいきません。
さて、昨日の続きですが、楽器を持ってアンサンブルの練習に来るように言われた私。ついでにソプラノ・サックスを返却しようと楽器を二本抱えていったのですが練習場についた途端、「何で二本も持ってきたん?アルトやいらんのに。」(注:讃岐弁、訳「何故二本も持ってきたのですか?アルトは要らないのに」)ええっ?!今何と言いました?アルトが要らないといいましたか?
実は私が加わる以前にアルトを吹いていた人がの東京から香川に帰ってきたので私はソプラノを吹く羽目に。因みにその帰ってきたアルト吹きこそ、現ダッパーの総帥、もとい代表者兼雑用係のブラックこときんじ氏。
という訳で、そのとき以来アンサンブルでソプラノを吹くようになりました。でも、当時はほとんどソプラノなんか吹いたことがなく、当然高音も出ない、口が痛い、楽譜は黒い指は回らないの状態でした。その後、楽器が鳴らしにくいのは楽器の悪さもあることに気づき、借り物だったソプラノ・サックスは返却。初代のヤ○ハ、カスタムソプラノ・サクソフォーンを購入。数年で売り払い、現在の楽器を購入いたしました。
ソプラノサックスのネタが続きましたがそこで今日の一枚。

El Amor/Albert REGNI
Albert REGNI (saxophone)
Maria REGNI, Shem GUIBBORY (violin)
Ron CARBONE (viola)
Maxine NEUMAN, Eugene MOYE (cello)
Sons of Sound SSPCD 005 (輸入盤)
このCDはニューヨーク・フィル、メトロポリタン・オペラ、ニューヨーク・シティ・バレエのサクソフォーン奏者としても活躍し、アメリカン・サクソフォン4重奏団の創設者でもあるレグニ氏のソロアルバム。ピアソラ、デュボア、ホッファーの曲が収録されています。
レグニ氏の音色は軽やかでありながら柔らかく温かなものです。純粋にクラシカルというよりは多少ポップス、セミクラシックよりの演奏なのかもしれませんが、デュボアの演奏も素晴らしいものを聞かせてくれます。全ての曲を通して、ゴリゴリとしたとんがった演奏は聞くことが出来ませんが少し飄々としていながら、しっとりとした大人の演奏を聞くことが出来ます。
私のお気に入りは、ピアソラの「逃避」とホッファーの「バロックのスタイルによる組曲」。
ピアソラのお好きな方、軽快なアメリカンスタイルのクラシカル・サクソフォーンの音色を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
先日、高松ウインドシンフォニーの演奏会が無事に終了しましたが、入場料の安いアマチュアの演奏会は手軽な反面、天気やちょっとした事情でお客さんが減ってしまうことがあるので悩みの種だったりします。これがメジャーな人の一枚2万円位するプレミア・チケットなら天気があろうが、仕事が入ろうが何とかして聴きにいくと思うのですが、我々の演奏会ではそうはいきません。
さて、昨日の続きですが、楽器を持ってアンサンブルの練習に来るように言われた私。ついでにソプラノ・サックスを返却しようと楽器を二本抱えていったのですが練習場についた途端、「何で二本も持ってきたん?アルトやいらんのに。」(注:讃岐弁、訳「何故二本も持ってきたのですか?アルトは要らないのに」)ええっ?!今何と言いました?アルトが要らないといいましたか?
実は私が加わる以前にアルトを吹いていた人がの東京から香川に帰ってきたので私はソプラノを吹く羽目に。因みにその帰ってきたアルト吹きこそ、現ダッパーの総帥、もとい代表者兼雑用係のブラックこときんじ氏。
という訳で、そのとき以来アンサンブルでソプラノを吹くようになりました。でも、当時はほとんどソプラノなんか吹いたことがなく、当然高音も出ない、口が痛い、楽譜は黒い指は回らないの状態でした。その後、楽器が鳴らしにくいのは楽器の悪さもあることに気づき、借り物だったソプラノ・サックスは返却。初代のヤ○ハ、カスタムソプラノ・サクソフォーンを購入。数年で売り払い、現在の楽器を購入いたしました。
ソプラノサックスのネタが続きましたがそこで今日の一枚。

El Amor/Albert REGNI
Albert REGNI (saxophone)
Maria REGNI, Shem GUIBBORY (violin)
Ron CARBONE (viola)
Maxine NEUMAN, Eugene MOYE (cello)
Sons of Sound SSPCD 005 (輸入盤)
このCDはニューヨーク・フィル、メトロポリタン・オペラ、ニューヨーク・シティ・バレエのサクソフォーン奏者としても活躍し、アメリカン・サクソフォン4重奏団の創設者でもあるレグニ氏のソロアルバム。ピアソラ、デュボア、ホッファーの曲が収録されています。
レグニ氏の音色は軽やかでありながら柔らかく温かなものです。純粋にクラシカルというよりは多少ポップス、セミクラシックよりの演奏なのかもしれませんが、デュボアの演奏も素晴らしいものを聞かせてくれます。全ての曲を通して、ゴリゴリとしたとんがった演奏は聞くことが出来ませんが少し飄々としていながら、しっとりとした大人の演奏を聞くことが出来ます。
私のお気に入りは、ピアソラの「逃避」とホッファーの「バロックのスタイルによる組曲」。
ピアソラのお好きな方、軽快なアメリカンスタイルのクラシカル・サクソフォーンの音色を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年04月25日
ソプラノ・サクソフォーンな訳。
定期演奏会をはじめとして、演奏会が近づいてくると、練習量は増えてきます。でも、上手くなればいいのですが、私自身は基礎練習が圧倒的に足りていないので疲れるばかりで一向に上達しません(泣)。
私はアンサンブルでは主にソプラノ、吹奏楽では主にアルトを吹くことが多いのですが。元々は昨日も書いた通りバリトンサックスを主に吹いていました。それが何故アルトやソプラノを吹くようになったかというと、まず、楽器が欲しいと思ったのですが、当時アルトサックスでも40万円を越える代物。バリトンになると物によっては100万円を超えてしまいます。なので最初買ったのはアルトでした。で社会人の楽団に入ってしばらくアルトを吹いていたのですが、ある時先輩からアンサンブルを一緒にやろうという誘いがあり、二つ返事でOKした私はそこでもしばらくはアルトを吹いていたのです。で、ソプラノは、それまでほとんど触ったことも無いほど縁の無い楽器でした。ソプラノ・サクソフォーンと言う楽器を吹くようになって買うまでして吹いているのは実は複雑な訳が。とあることで吹奏楽の中でソプラノサックスを一度だけ吹く必要が出来た時、一緒にアンサンブルをしていた先輩のつてであるところからソプラノサックスを借りたのです。でも、そのときはまだソプラノはそのときだけのものでした。ところがしばらくしてソプラノを吹いていた先輩が参加できなくなり、しばらくアンサンブルは休止状態に。で、借りたソプラノサックスもそのまま何ヶ月も抱えたままで過ごしていたのですが、あるひ突然、また先輩から連絡が。「アンサンブルをまた始めようと思うけん、楽器もって練習にきていた。」(注:讃岐弁です。訳は「アンサンブルをまた始めたいと思うので、楽器を持ってきてください。」)
当然、私はアルトサックスを抱えて練習に行こうとしましたが、はたと気づいて借りっぱなしのソプラノを返却しようと思い、アルトとソプラノの2本の楽器をかついで練習へ。その後いろいろあるので続きはまた明日に。
ということで今日の一枚。

Solitary Saxophone
Claude DELANGLE(Soprano、Alto、Baritone Saxophone)
BIS CD-640 輸入盤
このCDはサクソフォーンの無伴奏現代曲集です。クロード・ドゥラングル氏による演奏です。ドゥラングル氏といえばデファイエの後任としてパリ国立音楽院の教授に任命された人物です。ドゥラングルのレパートリの大きな部分を占めているのが現代音楽です。ドゥラングル氏の音色はミュール氏以来の、ヴィヴラートを多用した伝統的な音色とは一線を画したビブラートを控え、ストレートでありながら弾力性に富んだものです。また現代作曲家と親交があり、デニーゾフの「サクソフォン協奏曲」や当初サクソフォン以外の楽器のために書かれたやベリオの「セクエンツァIXb」などをサクソフォーンのレパートリーにするなどの功績も上げられます。
一見、伝統とは外れた現代的音色と現代奏法と思われがちなドゥラングル氏の演奏ですが、その根底にはやはりフランス流のサクソフォーンの基礎が流れているのでは無いかと思う部分も多々あります。ただ、私の知る限り、アンサンブルの活動にはあまり熱心では無いようでソリストとしてのCDは結構リリースされているものの、彼が参加したサクソフォーン・アンサンブルのCDはごく僅かしか存在しないようです。
私はソプラノサクソフォーンの演奏がじっくり聞けるCDをと思ってこれを買ったのですが、はっきり言ってその目的には不向きだったかもしれません。(笑)曲が難解なのでレベルの低い私には旋律やフレージングの参考としては不向きでした(ベリオや、武満徹、シェルシなど)。しかし、ドゥラングル氏のストレートなのに柔軟性に富んだ音色は素晴らしいものがあります。また、曲や表現による音色の使い分けという点で参考にしても勉強になるCDです。
また、このCDではソプラノ、アルト、バリトンという楽器を全て無伴奏で吹いており、飾りなしの真剣勝負と言う印象も受けるCDです。
現代曲に興味のある方、サクソフォーンの現代奏法に興味のある方、また、ドゥラングル氏の卓越した演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
私はアンサンブルでは主にソプラノ、吹奏楽では主にアルトを吹くことが多いのですが。元々は昨日も書いた通りバリトンサックスを主に吹いていました。それが何故アルトやソプラノを吹くようになったかというと、まず、楽器が欲しいと思ったのですが、当時アルトサックスでも40万円を越える代物。バリトンになると物によっては100万円を超えてしまいます。なので最初買ったのはアルトでした。で社会人の楽団に入ってしばらくアルトを吹いていたのですが、ある時先輩からアンサンブルを一緒にやろうという誘いがあり、二つ返事でOKした私はそこでもしばらくはアルトを吹いていたのです。で、ソプラノは、それまでほとんど触ったことも無いほど縁の無い楽器でした。ソプラノ・サクソフォーンと言う楽器を吹くようになって買うまでして吹いているのは実は複雑な訳が。とあることで吹奏楽の中でソプラノサックスを一度だけ吹く必要が出来た時、一緒にアンサンブルをしていた先輩のつてであるところからソプラノサックスを借りたのです。でも、そのときはまだソプラノはそのときだけのものでした。ところがしばらくしてソプラノを吹いていた先輩が参加できなくなり、しばらくアンサンブルは休止状態に。で、借りたソプラノサックスもそのまま何ヶ月も抱えたままで過ごしていたのですが、あるひ突然、また先輩から連絡が。「アンサンブルをまた始めようと思うけん、楽器もって練習にきていた。」(注:讃岐弁です。訳は「アンサンブルをまた始めたいと思うので、楽器を持ってきてください。」)
当然、私はアルトサックスを抱えて練習に行こうとしましたが、はたと気づいて借りっぱなしのソプラノを返却しようと思い、アルトとソプラノの2本の楽器をかついで練習へ。その後いろいろあるので続きはまた明日に。
ということで今日の一枚。

Solitary Saxophone
Claude DELANGLE(Soprano、Alto、Baritone Saxophone)
BIS CD-640 輸入盤
このCDはサクソフォーンの無伴奏現代曲集です。クロード・ドゥラングル氏による演奏です。ドゥラングル氏といえばデファイエの後任としてパリ国立音楽院の教授に任命された人物です。ドゥラングルのレパートリの大きな部分を占めているのが現代音楽です。ドゥラングル氏の音色はミュール氏以来の、ヴィヴラートを多用した伝統的な音色とは一線を画したビブラートを控え、ストレートでありながら弾力性に富んだものです。また現代作曲家と親交があり、デニーゾフの「サクソフォン協奏曲」や当初サクソフォン以外の楽器のために書かれたやベリオの「セクエンツァIXb」などをサクソフォーンのレパートリーにするなどの功績も上げられます。
一見、伝統とは外れた現代的音色と現代奏法と思われがちなドゥラングル氏の演奏ですが、その根底にはやはりフランス流のサクソフォーンの基礎が流れているのでは無いかと思う部分も多々あります。ただ、私の知る限り、アンサンブルの活動にはあまり熱心では無いようでソリストとしてのCDは結構リリースされているものの、彼が参加したサクソフォーン・アンサンブルのCDはごく僅かしか存在しないようです。
私はソプラノサクソフォーンの演奏がじっくり聞けるCDをと思ってこれを買ったのですが、はっきり言ってその目的には不向きだったかもしれません。(笑)曲が難解なのでレベルの低い私には旋律やフレージングの参考としては不向きでした(ベリオや、武満徹、シェルシなど)。しかし、ドゥラングル氏のストレートなのに柔軟性に富んだ音色は素晴らしいものがあります。また、曲や表現による音色の使い分けという点で参考にしても勉強になるCDです。
また、このCDではソプラノ、アルト、バリトンという楽器を全て無伴奏で吹いており、飾りなしの真剣勝負と言う印象も受けるCDです。
現代曲に興味のある方、サクソフォーンの現代奏法に興味のある方、また、ドゥラングル氏の卓越した演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年04月24日
バリトン・サクソフォーンへの興味。
今日は晴れて天気が良いのかと思いきや、夕方からは雨模様。
さて、興味の無い人には大しておもしろくも無いだろうマニアックなサックスの話をここ数日書いてきました。マニアックといってもマニアな人からは中途半端で使えない話になってしまいそうですが、それはそれで私はサックスを吹くことが好きでやっているわけで、別に知識や情報を集めて満足しているマニアではないことを知っていただいてご理解いただければと思っています。
元々興味はどこから湧いてくるのだろうかと、疑問に思ったりしますが、いま、自分が取り組んでいることに関連した領域に興味はやはり注がれることが多いようで、例えば、車が欲しいと思ってお金をためている人には将来自分が買いたいと思う車の車種や性能デザイン、などが興味の対象になったりするわけです。
同じサックスが趣味な人でもサックスの分野に関して興味のある部分はそれぞれ違っていてある人は楽器本体そのものに興味があったり、マウスピースに興味があったり、あるいは楽曲に興味があったりと様々です。それがそれぞれの得意分野になったりするということを考えると、興味を持つということは結構重要なことです。また、興味を持ったときにそこから先に進んでさらに奥深くまで掘り下げてみようという精神も大切にしたいものです。
人から見てつまらないと思うことも極めればそれなりのものになったりします。
私は割と中途半端な人なので、CDもかなり数は持っていてもジャンルはばらばら、また、数もマニアには程遠く、サックスも楽器のことやマウスピース、リードのことに興味はあるけれども、自分でさほど研究はせず、楽曲も聞く分には結構聞いても楽譜を集めるようなことはしない、という、まさにどっちつかずの似非マニアです。(笑)
私は中学校に入って初めて吹いたサックスはバリトン・サックスでした。それから、通算、6年以上バリトンサックスを吹いていました。何故、今ソプラノやアルトを吹いているのかということは別の機会に書こうと思いますが、当時の興味はやはりバリトン・サックスに関することが多かったと思います。いろいろな曲も聞こうと思いバリトンサックスのソロの曲なども探したのですが、いかんせんソロ楽器の認識があまり無い楽器なので当然曲も見つかりませんし、実際の音もなかなかレコードなどで聞くことが出来ませんでした。JAZZのジュリー・マリガンぐらいしか当時は見当がつきませんでした。
そこで今日の一枚。

NIAGARA SONGBOOK2
Romantic Inbstrumentals by
Niagara Fall of Sound Orchestral
CBS SONY (Niagaraレーベル) CSCL-1665
このCDは大瀧詠一氏の作品をインストゥルメンタルに編曲したもの。NIAGARA SONNGBOOKに続く第二弾です。このCDも元はLPとして所有していました。もちろん今でもLPは大切にとってあるのですが、プレーヤーの不調ため、現在はこのCDしか聞くことが出来ません。
今でも時々テレビの番組の中や、天気予報のBGMとしてよくこのアルバムが使われているのを聞いたりします。
このアルバムの中に入っている「恋のナックルボール」と言う曲があるのですがその曲の中になんとバリトンサックスのアドリブソロらしきソロが!!中学生当時の私は狂喜乱舞いたしました。バリトンサックスという楽器の露出自体が少ない楽器。私は嬉しさのあまり、何度も何度もレコードのそこばかり聞いた記憶があります。
いろいろな意味でも思い出のあるアルバム。バリトンサックスの音自体はJAZZな音ですが当時の私はそんなことより、バリトンサックスのソロがこんな曲にもあったという自体が悦びでした。
曲としての一押しはもちろん「恋のナックルボール」それと、冒頭のクラリネットのソロが印象的な「魔法の瞳」です。
大瀧詠一氏が大好きな方、バリトンサックス好きな方にオススメの一枚です。
さて、興味の無い人には大しておもしろくも無いだろうマニアックなサックスの話をここ数日書いてきました。マニアックといってもマニアな人からは中途半端で使えない話になってしまいそうですが、それはそれで私はサックスを吹くことが好きでやっているわけで、別に知識や情報を集めて満足しているマニアではないことを知っていただいてご理解いただければと思っています。
元々興味はどこから湧いてくるのだろうかと、疑問に思ったりしますが、いま、自分が取り組んでいることに関連した領域に興味はやはり注がれることが多いようで、例えば、車が欲しいと思ってお金をためている人には将来自分が買いたいと思う車の車種や性能デザイン、などが興味の対象になったりするわけです。
同じサックスが趣味な人でもサックスの分野に関して興味のある部分はそれぞれ違っていてある人は楽器本体そのものに興味があったり、マウスピースに興味があったり、あるいは楽曲に興味があったりと様々です。それがそれぞれの得意分野になったりするということを考えると、興味を持つということは結構重要なことです。また、興味を持ったときにそこから先に進んでさらに奥深くまで掘り下げてみようという精神も大切にしたいものです。
人から見てつまらないと思うことも極めればそれなりのものになったりします。
私は割と中途半端な人なので、CDもかなり数は持っていてもジャンルはばらばら、また、数もマニアには程遠く、サックスも楽器のことやマウスピース、リードのことに興味はあるけれども、自分でさほど研究はせず、楽曲も聞く分には結構聞いても楽譜を集めるようなことはしない、という、まさにどっちつかずの似非マニアです。(笑)
私は中学校に入って初めて吹いたサックスはバリトン・サックスでした。それから、通算、6年以上バリトンサックスを吹いていました。何故、今ソプラノやアルトを吹いているのかということは別の機会に書こうと思いますが、当時の興味はやはりバリトン・サックスに関することが多かったと思います。いろいろな曲も聞こうと思いバリトンサックスのソロの曲なども探したのですが、いかんせんソロ楽器の認識があまり無い楽器なので当然曲も見つかりませんし、実際の音もなかなかレコードなどで聞くことが出来ませんでした。JAZZのジュリー・マリガンぐらいしか当時は見当がつきませんでした。
そこで今日の一枚。

NIAGARA SONGBOOK2
Romantic Inbstrumentals by
Niagara Fall of Sound Orchestral
CBS SONY (Niagaraレーベル) CSCL-1665
このCDは大瀧詠一氏の作品をインストゥルメンタルに編曲したもの。NIAGARA SONNGBOOKに続く第二弾です。このCDも元はLPとして所有していました。もちろん今でもLPは大切にとってあるのですが、プレーヤーの不調ため、現在はこのCDしか聞くことが出来ません。
今でも時々テレビの番組の中や、天気予報のBGMとしてよくこのアルバムが使われているのを聞いたりします。
このアルバムの中に入っている「恋のナックルボール」と言う曲があるのですがその曲の中になんとバリトンサックスのアドリブソロらしきソロが!!中学生当時の私は狂喜乱舞いたしました。バリトンサックスという楽器の露出自体が少ない楽器。私は嬉しさのあまり、何度も何度もレコードのそこばかり聞いた記憶があります。
いろいろな意味でも思い出のあるアルバム。バリトンサックスの音自体はJAZZな音ですが当時の私はそんなことより、バリトンサックスのソロがこんな曲にもあったという自体が悦びでした。
曲としての一押しはもちろん「恋のナックルボール」それと、冒頭のクラリネットのソロが印象的な「魔法の瞳」です。
大瀧詠一氏が大好きな方、バリトンサックス好きな方にオススメの一枚です。
2008年04月23日
私の楽器、アルト・サクソフォーン
今日も楽器ネタです。私のアルト・サックスはフランスのH.セルマーというメーカーの物です。MADE in おフランス。そういえば、現在日常使っているものでフランス製のものはあまり見かけません。まあ、サクソフォーンという楽器が誕生して今のようになった歴史は様々言われているのでここで書くことではないと思うのですが、一つ確実にいえることは、クラシックで使われる管楽器の中では、ダントツに歴史が浅いことです。それに加え、フルートやクラリネット、オーボエなどに比べて音を出しやすく、キーの操作も機能的で扱いやすいので、サックスは易しい楽器という認識を持つ人が多いようです。
確かに、入り口は広い楽器だと思います。ただ、奥は結構深い。
どの世界でもそうですが、極めるとなると大変です。
で、私の楽器の話に戻りますが、セルマーというメーカーの楽器はサックス吹きにとっては超メジャーな楽器でこの名前を知らないとサックスを本当に吹いているのかどうかさえ、疑われてしまいます。私はそのセルマーのスーパーアクション80シリーズ2という機種の楽器を使っています。少し古い楽器なので世代的にも一世代前の楽器です。ただ、現行の機種でもあるので思いっきり古い、とかヴィンテージとかいうことではありません。同じサックスなんだからどれも同じ音だろうと考えるのは大間違いで、メーカー、機種、そして、もちろん個体差によって個性があります。5万円の楽器と100万円の楽器でどちらも同じサックスだから5万でもいいじゃない、と言われる方々、車が全部軽自動車でもいいかどうか考えてみてくださいね。楽器にも用途に応じたものと、好みに応じた個性があるのです。見た目は同じようでも作りはかなりちがう楽器もあります。
で、私の楽器は選びも吹き比べも何もせず、1点買い。というよりは実物見ずに注文買いでした。当たり外れなどきにしていなかったあの頃、良くそんな冒険をしたな、と今でも思います。当時でも40万円を超える値段だったので、いま、考えると大変です。
さて、そこで今日の一枚。
Marcel Mule Historical Recordings
Marcel MULE (ミュール)
グリーンドア音楽出版 GDCS-0006
このCDは数年前、東京に行ったときに手に入れました。購入先は銀座の山野○器。マルセル・ミュールの1930年代から1950年代にかけてのSP盤への録音を復刻編集したものです。音源としては昨日紹介したCDや、以前紹介した「サクソフォンの芸術」に収録されているものばかりですが、クリストファー野沢氏による復刻のこのアルバムは他のアルバムより鮮明にミュール氏の音色を拾っているように聴こえます。おそらく、元のSPの状態の良いものを使用しているのかもしれません。また、解説は日本サクソフォン協会の役員でミュール氏とも親交のあった松沢増保氏によるもので参考文献としての価値もあると思います。
この文章を読んでマニアックと思われる方、確かにマニアックですが、このCDに限らずミュール氏の音を是非聞いてみてください。
必ずサクソフォーン観が変わります。
ミュール氏の音色、ミュール節を思う存分楽しめる一枚です。
昨日の一枚同様、サクソフォーンを吹く、吹かないにかかわらず、サクソフォーンを愛する全ての方にまた、サクソフォーンというとJAZZの楽器と思われる方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
確かに、入り口は広い楽器だと思います。ただ、奥は結構深い。
どの世界でもそうですが、極めるとなると大変です。
で、私の楽器の話に戻りますが、セルマーというメーカーの楽器はサックス吹きにとっては超メジャーな楽器でこの名前を知らないとサックスを本当に吹いているのかどうかさえ、疑われてしまいます。私はそのセルマーのスーパーアクション80シリーズ2という機種の楽器を使っています。少し古い楽器なので世代的にも一世代前の楽器です。ただ、現行の機種でもあるので思いっきり古い、とかヴィンテージとかいうことではありません。同じサックスなんだからどれも同じ音だろうと考えるのは大間違いで、メーカー、機種、そして、もちろん個体差によって個性があります。5万円の楽器と100万円の楽器でどちらも同じサックスだから5万でもいいじゃない、と言われる方々、車が全部軽自動車でもいいかどうか考えてみてくださいね。楽器にも用途に応じたものと、好みに応じた個性があるのです。見た目は同じようでも作りはかなりちがう楽器もあります。
で、私の楽器は選びも吹き比べも何もせず、1点買い。というよりは実物見ずに注文買いでした。当たり外れなどきにしていなかったあの頃、良くそんな冒険をしたな、と今でも思います。当時でも40万円を超える値段だったので、いま、考えると大変です。
さて、そこで今日の一枚。
Marcel Mule Historical Recordings
Marcel MULE (ミュール)
グリーンドア音楽出版 GDCS-0006
このCDは数年前、東京に行ったときに手に入れました。購入先は銀座の山野○器。マルセル・ミュールの1930年代から1950年代にかけてのSP盤への録音を復刻編集したものです。音源としては昨日紹介したCDや、以前紹介した「サクソフォンの芸術」に収録されているものばかりですが、クリストファー野沢氏による復刻のこのアルバムは他のアルバムより鮮明にミュール氏の音色を拾っているように聴こえます。おそらく、元のSPの状態の良いものを使用しているのかもしれません。また、解説は日本サクソフォン協会の役員でミュール氏とも親交のあった松沢増保氏によるもので参考文献としての価値もあると思います。
この文章を読んでマニアックと思われる方、確かにマニアックですが、このCDに限らずミュール氏の音を是非聞いてみてください。
必ずサクソフォーン観が変わります。
ミュール氏の音色、ミュール節を思う存分楽しめる一枚です。
昨日の一枚同様、サクソフォーンを吹く、吹かないにかかわらず、サクソフォーンを愛する全ての方にまた、サクソフォーンというとJAZZの楽器と思われる方に是非聞いていただきたいオススメの一枚です。
2008年04月22日
頭の中は。
さて、高松ウインドシンフォニーの定期演奏会が終わりました。最近、演奏会の話題や楽器についての書き込みが多いこの日記です。それだけ演奏会のことで頭の中が一杯になっていたのかもしれません。「宇宙の音楽」の本番や、「動物の謝肉祭」の本番は死にそうでした。
でも、今日も楽器のことを書きます。(笑)
私がサックスという楽器に出会ったのは中学の吹奏楽部。当時はバリトンサックスを吹いていました。それなりに練習もしましたが、きちんとした専門の指導者がいるわけでもなく、師匠はいつも中学校の先輩でした。それは高校でも同じことで、専門の方に教えてもらう事無く、先輩に教わったことを自己流に消化していく日々でした。当時はロクに勉強もせず、頭の中は吹奏楽やサックスのことで一杯だった日々でした(笑)。
一つ悔やまれるのはいまだにきちんとした人に指導をしてもらっていないので自分のしていること、考えていることが正しいか間違っているか全くわからないことです。ヘタクソながらも中学生に教えてやってください、とか言われるのですが、我流で身に付けてきたことを果たして教えていいものか、不安です。またきちんとした教え方をされていない私は、どちらかというと教え方もヘタクソかもしれません。
で、周囲の人曰く、私の演奏にも特徴があるようで、私に教わった中学生がどうなるかというと、まず、音がでかくなります。(爆)私は表現するためには音が相手に届いてナンボだと思っているので、音を美しくするよりも楽器がきちんと鳴ることの方を重視します。もちろん、音量が増えれば、次は音色の美しさを追求しにかかるわけですが、特に中学生なんかはのびのびとしたしっかりとした音量で吹くことが大切だと思っているのです。
また、表現が大げさになります。必要以上にやるわけではないのですが、表現しているのがわかるぐらいにはいろいろなことをやる必要があります。
どちらも大は小を兼ねる、ではありませんが、大きい方が出来ると、小さい方にも対応できると思っています。MAXの音量を上げるのは苦労しますが、音量を絞ることはそれよりは楽です。ダイナミックレンジを広げるためにも、しっかりした音を出す努力をします。
まあ、故に音がでかすぎると言われて顰蹙を買うことも多いのですが。(笑)
しかし、音色を追求していないわけではありません。常に理想の音色を見つけて追求しています。
そこで今日の一枚。

Marcel Mule 'Le Patron' of the Saxophone
Marcel MULE (ミュール)
Francois COMBELLE (コンベル)
ギャルド・レピュブリケーヌ・サクソフォン4重奏団
指揮:Phillipe GAUBERT
パリ音楽院室内管弦楽団
Clarinet Classics CC-0013 (輸入盤)
このCDはマルセル・ミュールの演奏を中心に収録されたもの。SP版からの復刻音源によるもののようです。今では音源も無く、ほとんど音を聞くことの出来ないコンベル(ミュールのギャルド時代の先輩?)の音を聞くことも出来ます。ただ、コンベルとミュールの演奏は技法的にも音色的にも一線を画するものを感じます。やはり、現在のクラシカルサクソフォーンの源流とも言うべきものはミュールにあるのではないかと感じてしまいます。
ミュールの音は弦楽器にも似た太くて柔軟性に富んだ音色、しかも完璧なまでのテクニック。クラシックサクソフォーンの表現にビブラートを取り入れた人物としても有名です。弦楽器のビブラートにヒントを得たとも、jazzの技法にヒントを得たとも言われています。まさに天才のなせる技かもしれません。当時はクラシックのサックスでビブラートをかけることなど考えもしていない人が沢山いた時代のはずですが、それをやってしまうところにも凄さがあります。私の想像するに当時はまだサクソフォーンはクラシックの中ではクラリネットの親戚の楽器というぐらいしか認識が無かったのだろうと思いますが。ビブラートを禁じ手と見ていたクラシックのクラリネットの世界でも徐々にビブラートを使用する奏者が増えているようです。
まさにミュール氏自身が「私は宇宙人」と言っていたように尋常な思考ではなかったのかもしれません。頭の中で何を考えて演奏していたのか無くなった今では想像するしかありませんが。
あのチャーリーパーカーでさえ、ミュールのことを師と仰いでいたとも言われます。
確かに演奏、ビブラートをはじめとした表現は古さを感じる演奏ですが、いつ聞いても新鮮な発見があります。
サクソフォーンを吹く、吹かないにかかわらず、サクソフォーンを愛する全ての方にオススメの一枚です。
でも、今日も楽器のことを書きます。(笑)
私がサックスという楽器に出会ったのは中学の吹奏楽部。当時はバリトンサックスを吹いていました。それなりに練習もしましたが、きちんとした専門の指導者がいるわけでもなく、師匠はいつも中学校の先輩でした。それは高校でも同じことで、専門の方に教えてもらう事無く、先輩に教わったことを自己流に消化していく日々でした。当時はロクに勉強もせず、頭の中は吹奏楽やサックスのことで一杯だった日々でした(笑)。
一つ悔やまれるのはいまだにきちんとした人に指導をしてもらっていないので自分のしていること、考えていることが正しいか間違っているか全くわからないことです。ヘタクソながらも中学生に教えてやってください、とか言われるのですが、我流で身に付けてきたことを果たして教えていいものか、不安です。またきちんとした教え方をされていない私は、どちらかというと教え方もヘタクソかもしれません。
で、周囲の人曰く、私の演奏にも特徴があるようで、私に教わった中学生がどうなるかというと、まず、音がでかくなります。(爆)私は表現するためには音が相手に届いてナンボだと思っているので、音を美しくするよりも楽器がきちんと鳴ることの方を重視します。もちろん、音量が増えれば、次は音色の美しさを追求しにかかるわけですが、特に中学生なんかはのびのびとしたしっかりとした音量で吹くことが大切だと思っているのです。
また、表現が大げさになります。必要以上にやるわけではないのですが、表現しているのがわかるぐらいにはいろいろなことをやる必要があります。
どちらも大は小を兼ねる、ではありませんが、大きい方が出来ると、小さい方にも対応できると思っています。MAXの音量を上げるのは苦労しますが、音量を絞ることはそれよりは楽です。ダイナミックレンジを広げるためにも、しっかりした音を出す努力をします。
まあ、故に音がでかすぎると言われて顰蹙を買うことも多いのですが。(笑)
しかし、音色を追求していないわけではありません。常に理想の音色を見つけて追求しています。
そこで今日の一枚。

Marcel Mule 'Le Patron' of the Saxophone
Marcel MULE (ミュール)
Francois COMBELLE (コンベル)
ギャルド・レピュブリケーヌ・サクソフォン4重奏団
指揮:Phillipe GAUBERT
パリ音楽院室内管弦楽団
Clarinet Classics CC-0013 (輸入盤)
このCDはマルセル・ミュールの演奏を中心に収録されたもの。SP版からの復刻音源によるもののようです。今では音源も無く、ほとんど音を聞くことの出来ないコンベル(ミュールのギャルド時代の先輩?)の音を聞くことも出来ます。ただ、コンベルとミュールの演奏は技法的にも音色的にも一線を画するものを感じます。やはり、現在のクラシカルサクソフォーンの源流とも言うべきものはミュールにあるのではないかと感じてしまいます。
ミュールの音は弦楽器にも似た太くて柔軟性に富んだ音色、しかも完璧なまでのテクニック。クラシックサクソフォーンの表現にビブラートを取り入れた人物としても有名です。弦楽器のビブラートにヒントを得たとも、jazzの技法にヒントを得たとも言われています。まさに天才のなせる技かもしれません。当時はクラシックのサックスでビブラートをかけることなど考えもしていない人が沢山いた時代のはずですが、それをやってしまうところにも凄さがあります。私の想像するに当時はまだサクソフォーンはクラシックの中ではクラリネットの親戚の楽器というぐらいしか認識が無かったのだろうと思いますが。ビブラートを禁じ手と見ていたクラシックのクラリネットの世界でも徐々にビブラートを使用する奏者が増えているようです。
まさにミュール氏自身が「私は宇宙人」と言っていたように尋常な思考ではなかったのかもしれません。頭の中で何を考えて演奏していたのか無くなった今では想像するしかありませんが。
あのチャーリーパーカーでさえ、ミュールのことを師と仰いでいたとも言われます。
確かに演奏、ビブラートをはじめとした表現は古さを感じる演奏ですが、いつ聞いても新鮮な発見があります。
サクソフォーンを吹く、吹かないにかかわらず、サクソフォーンを愛する全ての方にオススメの一枚です。
Posted by のりくん at
00:57
│Comments(0)
2008年04月21日
危機脱出なるか、否か。
今年の演奏会も無事終了。お越しいただいた皆さん、ありがとうございました。
演奏会といえば、去年の演奏会の前のこと。楽器を借りてきました。しかもアルトサックス。持っているのに何故?といわれそうなのですが、私の楽器はあまりにも手入れが悪い上に10年近くロクにメンテナンスをしていないので音程も悪くなり、私のような週末プレーヤーには対応しきれなくなってきました。それで、アルトを使っていない人にちょっと楽器を借りてみたというわけです。ただ、借りてきた楽器も長期にわたって使用されておらず、たいしたメンテもされていないという話でしたので、これでばっちり、と言うわけではありませんでした。吹いて見て、どっちがマシかで、決めることにしたのですが、結局、自分の楽器は全く鳴らなくなり借り物の楽器で吹くこととなりました。
結局、自分の楽器は去年オーバーホール行きに。
去年は、借りてきた楽器によって危機を脱することが出来るか否か。微妙な問題だったのですが、私が、もっと腕のある人間なら腕でカバーできたのかもしれませんが、悲しいかなそんな腕は持ち合わせていないので、物に頼るしかありません。
そこで今日の一枚。
「ロビン・フッド」オリジナルサウンドトラック
ポリドール POCP-1118
このCDはケビン・コスナーが主演、ケビン・レイノルズが監督した映画ロビン・フッドのサウンドトラックです。ロビン・フッドといえばヨーロッパでは有名な英雄です。12世紀の後半にイギリスで虐げられたアングロ・サクソン系の土着民を率い、堕落していた支配者に立ち向かった謎の貴族とされています。弓の名手でシャーウッドの森を住まいとし、活躍したとされる伝説の人物です。
映画全編に使われている音楽がオリジナルサウンドトラックとして収録されています。実は何年か前の楽団の定期演奏会でこの中の曲をメドレー形式にして吹奏楽用に編曲した「交響組曲ロビン・フッド」という曲を演奏したことがあります。そのときにその参考演奏にすべく購入したCDでもあります。
映画の方は、12世紀後半という時代背景の中で繰り広げられるまさにアクション映画の様相。まさにロビン・フッド危機脱出なるか?といったストーリー。マリアンとの恋愛話もからめてストーリーが展開していきます。音楽もまさにそのもの。暗い部分、明るい部分、派手な部分、美しい部分、様々です。私は、このCDを聞いてからビデオで映画の方を見たのですが、なるほど、こんな使い方をしているのかー、と感心してしまいました。尚、音楽を手がけたのはマイケル・カーメン。「リーサル・ウェポン」や、「ダイ・ハード」でも有名な作曲家です。
そういえば、誰かが、こんなことを行ってましたが、「ロビン・フッドって、弓の名手だろ、あの子どもの頭に乗ったリンゴ射抜くやつ。」…………「それはウィリアム・テル!」
映画、ロビン・フッドガお好きな方、マイケル・カーメンの音楽を聴いてみたい方、また、サウンド・トラックを純粋に音楽として聞いてみたい方にオススメの一枚です。
演奏会といえば、去年の演奏会の前のこと。楽器を借りてきました。しかもアルトサックス。持っているのに何故?といわれそうなのですが、私の楽器はあまりにも手入れが悪い上に10年近くロクにメンテナンスをしていないので音程も悪くなり、私のような週末プレーヤーには対応しきれなくなってきました。それで、アルトを使っていない人にちょっと楽器を借りてみたというわけです。ただ、借りてきた楽器も長期にわたって使用されておらず、たいしたメンテもされていないという話でしたので、これでばっちり、と言うわけではありませんでした。吹いて見て、どっちがマシかで、決めることにしたのですが、結局、自分の楽器は全く鳴らなくなり借り物の楽器で吹くこととなりました。
結局、自分の楽器は去年オーバーホール行きに。
去年は、借りてきた楽器によって危機を脱することが出来るか否か。微妙な問題だったのですが、私が、もっと腕のある人間なら腕でカバーできたのかもしれませんが、悲しいかなそんな腕は持ち合わせていないので、物に頼るしかありません。
そこで今日の一枚。
「ロビン・フッド」オリジナルサウンドトラック
ポリドール POCP-1118
このCDはケビン・コスナーが主演、ケビン・レイノルズが監督した映画ロビン・フッドのサウンドトラックです。ロビン・フッドといえばヨーロッパでは有名な英雄です。12世紀の後半にイギリスで虐げられたアングロ・サクソン系の土着民を率い、堕落していた支配者に立ち向かった謎の貴族とされています。弓の名手でシャーウッドの森を住まいとし、活躍したとされる伝説の人物です。
映画全編に使われている音楽がオリジナルサウンドトラックとして収録されています。実は何年か前の楽団の定期演奏会でこの中の曲をメドレー形式にして吹奏楽用に編曲した「交響組曲ロビン・フッド」という曲を演奏したことがあります。そのときにその参考演奏にすべく購入したCDでもあります。
映画の方は、12世紀後半という時代背景の中で繰り広げられるまさにアクション映画の様相。まさにロビン・フッド危機脱出なるか?といったストーリー。マリアンとの恋愛話もからめてストーリーが展開していきます。音楽もまさにそのもの。暗い部分、明るい部分、派手な部分、美しい部分、様々です。私は、このCDを聞いてからビデオで映画の方を見たのですが、なるほど、こんな使い方をしているのかー、と感心してしまいました。尚、音楽を手がけたのはマイケル・カーメン。「リーサル・ウェポン」や、「ダイ・ハード」でも有名な作曲家です。
そういえば、誰かが、こんなことを行ってましたが、「ロビン・フッドって、弓の名手だろ、あの子どもの頭に乗ったリンゴ射抜くやつ。」…………「それはウィリアム・テル!」
映画、ロビン・フッドガお好きな方、マイケル・カーメンの音楽を聴いてみたい方、また、サウンド・トラックを純粋に音楽として聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年04月20日
定期演奏会終了。
本日、高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会が無事に(?)終了。
打ち上げも終り、先ほど帰宅しました。
ご来場いただいた皆様、ありがとうございます。
お手伝いいただいた方、お疲れ様でした、ありがとうございます。
そして、団員の皆様、お疲れ様でした。また、来年もよろしくお願いします。
打ち上げも終り、先ほど帰宅しました。
ご来場いただいた皆様、ありがとうございます。
お手伝いいただいた方、お疲れ様でした、ありがとうございます。
そして、団員の皆様、お疲れ様でした。また、来年もよろしくお願いします。
2008年04月20日
高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会(再)
一応、私は高松ウインドシンフォニーのふくだんちょーという役職を仰せつかっているので、
再度定期演奏会のお知らせなど。

高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽
再度定期演奏会のお知らせなど。

高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽
Posted by のりくん at
07:41
│Comments(0)
2008年04月20日
リード楽器奏者は悩むのだ。
先日、漸くリードを買いに行ってきました。本番が間近なことを考えると、今更リードを買っても間に合わないとのかもしれませんが。数年前、チャレンジャー精神を発揮して、合成樹脂製のリードで「レジェール」を購入したこともありました。管楽器をされたことの無い方は「リード」が何かもわからないと思いますが、サクソフォーンやクラリネット、オーボエや、バス-ンといった木管楽器には一般的にリード楽器と呼ばれ、リードというアイスクリームのへらを一回り小さくしたような、植物から作った板を振動させて発音しています。当然、植物である為、個体差があり、寿命があります。因みに、植物とはケーンと呼ばれる葦。葦は形状は竹に似ています。
サックス、クラリネットはシングルリードと言ってマウスピースに一枚のリードをつけて振動させます。一方、オーボエやファゴットはダブルリードと言って、マウスピースが無く、リード2枚を使って振動させています。ダブルリードはストローでつくった笛や草笛のような発音の仕組みを想像していただければよいと思います。メーカーによって違いはありますが、リードはアルトサクソフォーン用で一箱10枚入り2000円程度かなり痛い出費になります。おまけに植物なので全てが自分にあっているわけでもなく、当然当たり外れがあってそのためコスト的には私は使えるリード1枚は500円から1000円くらいとコスト計算しています。一方、ダブルリードは既製品を買うとオーボエ用で2000円くらいします。ただし、ダブルリードの方はプロとかだと、自分で削ってリードを作る人が多く、材料費はそうかかりませんが、道具が結構お高いので大変です。(アマチュアの方は既製品を買うことも多いようです。)
リードの選択は常に悩みの種です。自分がいいと思っていても客席で聞いている人にはよくないと思われるリードも存在します。そして、吹きやすい=いい音が出るではないこともあります。たまに練習の時に人に離れたとことで聞いてもらってリードを決めることもあります。神経を使います。ダブルリードの奏者はリードがもっとシビアに影響するのでもっと苦労していることと思います。
悩み多きリード選びなのです。
小難しいことをたくさん書きましたが、そこで今日の一枚。

パナシェ/ルヴァンヴェール木管五重奏団
ラヴェル/クープランの墓他
大澤明子(フルート)、成田恵子(オーボエ)
藤井洋子(クラリネット)、岡本正之(バス-ン)
藤田乙比古(ホルン)、須川展也(アルトサクソフォーン)
ALMレコード コジマ録音 ALCD-3035
このCDはラヴェルのクープランの墓を木管5重奏に編曲したものをはじめ、近代の木管五重奏作品が収録されたもの。比較的若手の日本人演奏家による演奏です。
実はクープランの墓はオーボエ吹き泣かせの曲。特にオケ版の演奏ではたった一人で難しいフレーズをしかも弱音で明瞭に吹き始めなければならないという過酷さです。もちろん、この木管5重奏の中でも同様です。
演奏は非常によく整理され、各楽器の存在が明瞭なもの。泥臭さや、こってり感はなく、軽やかな印象です。近代的な音楽なのでこの演奏や雰囲気は大正解なのでは、と思っています。しかし、叱りとしたダイナミクスもある演奏です。尚、トマジの「春」が収録されていて、演奏に著名な須川展也氏が加わっています。この曲はフランスサクソフォーン界の重鎮、ジャン・マリ・ロンデックス氏の委嘱で書かれたトマジの作品なのですが、特殊な編成のためか、あまり演奏を聞きません。
木管五重奏の近代的響きを聞きたい方、オーボエをはじめダブルリード楽器を演奏される方、木管五重奏はモーツアルトやハイドンしか聞いたことが無い、といわれる方にオススメの一枚です。
サックス、クラリネットはシングルリードと言ってマウスピースに一枚のリードをつけて振動させます。一方、オーボエやファゴットはダブルリードと言って、マウスピースが無く、リード2枚を使って振動させています。ダブルリードはストローでつくった笛や草笛のような発音の仕組みを想像していただければよいと思います。メーカーによって違いはありますが、リードはアルトサクソフォーン用で一箱10枚入り2000円程度かなり痛い出費になります。おまけに植物なので全てが自分にあっているわけでもなく、当然当たり外れがあってそのためコスト的には私は使えるリード1枚は500円から1000円くらいとコスト計算しています。一方、ダブルリードは既製品を買うとオーボエ用で2000円くらいします。ただし、ダブルリードの方はプロとかだと、自分で削ってリードを作る人が多く、材料費はそうかかりませんが、道具が結構お高いので大変です。(アマチュアの方は既製品を買うことも多いようです。)
リードの選択は常に悩みの種です。自分がいいと思っていても客席で聞いている人にはよくないと思われるリードも存在します。そして、吹きやすい=いい音が出るではないこともあります。たまに練習の時に人に離れたとことで聞いてもらってリードを決めることもあります。神経を使います。ダブルリードの奏者はリードがもっとシビアに影響するのでもっと苦労していることと思います。
悩み多きリード選びなのです。
小難しいことをたくさん書きましたが、そこで今日の一枚。

パナシェ/ルヴァンヴェール木管五重奏団
ラヴェル/クープランの墓他
大澤明子(フルート)、成田恵子(オーボエ)
藤井洋子(クラリネット)、岡本正之(バス-ン)
藤田乙比古(ホルン)、須川展也(アルトサクソフォーン)
ALMレコード コジマ録音 ALCD-3035
このCDはラヴェルのクープランの墓を木管5重奏に編曲したものをはじめ、近代の木管五重奏作品が収録されたもの。比較的若手の日本人演奏家による演奏です。
実はクープランの墓はオーボエ吹き泣かせの曲。特にオケ版の演奏ではたった一人で難しいフレーズをしかも弱音で明瞭に吹き始めなければならないという過酷さです。もちろん、この木管5重奏の中でも同様です。
演奏は非常によく整理され、各楽器の存在が明瞭なもの。泥臭さや、こってり感はなく、軽やかな印象です。近代的な音楽なのでこの演奏や雰囲気は大正解なのでは、と思っています。しかし、叱りとしたダイナミクスもある演奏です。尚、トマジの「春」が収録されていて、演奏に著名な須川展也氏が加わっています。この曲はフランスサクソフォーン界の重鎮、ジャン・マリ・ロンデックス氏の委嘱で書かれたトマジの作品なのですが、特殊な編成のためか、あまり演奏を聞きません。
木管五重奏の近代的響きを聞きたい方、オーボエをはじめダブルリード楽器を演奏される方、木管五重奏はモーツアルトやハイドンしか聞いたことが無い、といわれる方にオススメの一枚です。
2008年04月19日
思いではいろいろ。パート2
最近の話題を見ていただいてもわかるように定期演奏会が間際になってきました。毎年ハードな時期です。私は中学校の吹奏楽部に入ってそのときから吹奏楽に触れサクソフォーンという楽器に出会いました。
中学校や高校の先輩や同級生の中にはプロのミュージシャンになった方々も何人かいらっしゃいます。でも、私はプロのミュージシャンになって自分が成功するとはとても思えなかったので、高校生のとき以来、音楽は趣味と決めてサックスを吹いています。
吹奏楽といえば、特に学生さんにとっては年一回の吹奏楽コンクールがやはりメイン・イベントになるのでしょうか。私もかつてはそうでしたが、コンクールに向かってガリガリやると、それだけに終始してしまいそうな自分がいるので吹奏楽コンクールにはもう出ないだろうと思います。大所帯で出るコンクールはメンバー全員の意識統一が重要だと思うのでそこに神経をあまり使いたくないのです。いい演奏をもっと楽しく出来る様にしたいと思っています。
吹奏楽コンクールはコンクールでいろいろな思い出があるのですが。
そういう面で私の所属する楽団は吹奏楽コンクールに基本的に出ない団体なので私としてはいいと思っています。コンクールに出るよりは福祉関係の施設や学校(特に僻地の)にボランティアで訪問演奏に行くとか、中学生などと一緒に演奏する、といったことの方が楽しいと思っています。
でもウチの楽団のあの選曲のハードさには時々参ってしまいます。良かったら一度HPで演奏曲目なんかを覗いてみてください。
恐ろしいことになってます。毎年。
そこで今日の一枚。
ヴェルディ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:ジュゼッペ・シノーポリ
フィリップス 32CD-145 411 469-2
このCDはシノーポリによるヴェルディのオペラ序曲&前奏曲集です。シノーポリは、2001年、ベルリン・ドイツ・オペラでヴェルディの「アイーダ」を指揮中、第3幕ので倒れ急逝してしまった指揮者です。イタリアオペラのが十八番だった指揮者でもありました。
このCDの中に収録されている「シチリア島の夕べの祈り」序曲には少し、いや、かなり思い出があります。中学校の時と、今の楽団と両方で演奏しました。途中、チェロのソロがアルトサクソフォーンのソロとして編曲されており、ソロを吹いた思い出があります。
(残念ながら、あまりいい演奏だったとは自分ではいえないものでしたが。)また、「運命の力」序曲も今の楽団で演奏しました。
このシノーポリの演奏は少しゆったりしたテンポでどっしりと構えてゆったりと歌わせる感じの演奏になっています。演奏もウィーン・フィルで秀逸。ウィーン・フィル独特の重厚な響きで聞くことが出来ます。欲を言うならもっとイタリアオペラらしくもっと陽性の明るい響きがしてもいいかなという気がしますが、この演奏はこの演奏で味わい深いものがあります。決してパワーやスピードで押し切ってしまわないところがまた素晴らしい演奏と言えるかもしれません。
イタリアオペラの序曲を聞いてみたい方、これからオペラを聞こうと思っているけれども、その前に何かオペラに関係するものを聞いておきたいという方、吹奏楽で演奏した思い出のある方などにオススメの一枚です。
中学校や高校の先輩や同級生の中にはプロのミュージシャンになった方々も何人かいらっしゃいます。でも、私はプロのミュージシャンになって自分が成功するとはとても思えなかったので、高校生のとき以来、音楽は趣味と決めてサックスを吹いています。
吹奏楽といえば、特に学生さんにとっては年一回の吹奏楽コンクールがやはりメイン・イベントになるのでしょうか。私もかつてはそうでしたが、コンクールに向かってガリガリやると、それだけに終始してしまいそうな自分がいるので吹奏楽コンクールにはもう出ないだろうと思います。大所帯で出るコンクールはメンバー全員の意識統一が重要だと思うのでそこに神経をあまり使いたくないのです。いい演奏をもっと楽しく出来る様にしたいと思っています。
吹奏楽コンクールはコンクールでいろいろな思い出があるのですが。
そういう面で私の所属する楽団は吹奏楽コンクールに基本的に出ない団体なので私としてはいいと思っています。コンクールに出るよりは福祉関係の施設や学校(特に僻地の)にボランティアで訪問演奏に行くとか、中学生などと一緒に演奏する、といったことの方が楽しいと思っています。
でもウチの楽団のあの選曲のハードさには時々参ってしまいます。良かったら一度HPで演奏曲目なんかを覗いてみてください。
恐ろしいことになってます。毎年。
そこで今日の一枚。
ヴェルディ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:ジュゼッペ・シノーポリ
フィリップス 32CD-145 411 469-2
このCDはシノーポリによるヴェルディのオペラ序曲&前奏曲集です。シノーポリは、2001年、ベルリン・ドイツ・オペラでヴェルディの「アイーダ」を指揮中、第3幕ので倒れ急逝してしまった指揮者です。イタリアオペラのが十八番だった指揮者でもありました。
このCDの中に収録されている「シチリア島の夕べの祈り」序曲には少し、いや、かなり思い出があります。中学校の時と、今の楽団と両方で演奏しました。途中、チェロのソロがアルトサクソフォーンのソロとして編曲されており、ソロを吹いた思い出があります。
(残念ながら、あまりいい演奏だったとは自分ではいえないものでしたが。)また、「運命の力」序曲も今の楽団で演奏しました。
このシノーポリの演奏は少しゆったりしたテンポでどっしりと構えてゆったりと歌わせる感じの演奏になっています。演奏もウィーン・フィルで秀逸。ウィーン・フィル独特の重厚な響きで聞くことが出来ます。欲を言うならもっとイタリアオペラらしくもっと陽性の明るい響きがしてもいいかなという気がしますが、この演奏はこの演奏で味わい深いものがあります。決してパワーやスピードで押し切ってしまわないところがまた素晴らしい演奏と言えるかもしれません。
イタリアオペラの序曲を聞いてみたい方、これからオペラを聞こうと思っているけれども、その前に何かオペラに関係するものを聞いておきたいという方、吹奏楽で演奏した思い出のある方などにオススメの一枚です。
2008年04月18日
思い出はいろいろ。
いよいよ、高松ウインドシンフォニー定期演奏会まであと3日。この時期になると、毎年、朝から夕方まで練習というパターンが増えてきます。4月20日が定期演奏会、5月にはまた、ダッパーサクセーバーズで出演するステージが別にあるので、平行して練習をしていかなければなりません。
毎度、毎度のことながら、間際の追い込みです。もう少し早く取り掛かればといつも思うのですが、団員の中には極端に腰を挙げるのが重い人もいてなかなか練習に皆が集まってこないのが現状です。
といいつつも、演奏がいいものに出来るといいのですが…。
毎年、「去年の演奏会は結構ボロボロの演奏をしてしまった私なので今年はちょっと頑張らねば」とは思っているのですが。まあ、満足の行く演奏会だったという人もいるので思いでは人それぞれかもしれません。
今年こそはいい思い出の残る演奏会にしようと頑張っています。(でも毎年そう思っているのですが…。)
そこで今日の一枚。
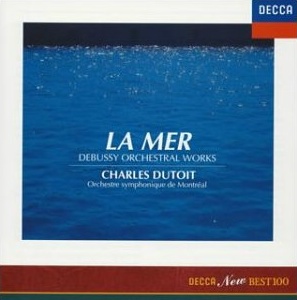
ドビュッシー/海-3つの交響的スケッチ
バレエ音楽「遊戯」、交響的断章「聖セバスチャンの殉教」
牧神の午後への前奏曲
シャルル・デュトワ指揮:モントリオール交響楽団
ティモシー・ハッヂンズ(フルート、牧神)
LONDON(ポリドール) POCL-1044
(リンク先のCDは再販されたDECCAニューベスト盤ですが、内容は同一のものです。)
このCDは、ドビュッシーの「海」がメインで収録されたもの。この曲は数年前、高松ウインドシンフォニー定期演奏会のメインの曲はこの曲として吹奏楽編曲版を全曲演奏しました。もちろん、このCDはオケによる原曲版です。私としてはかなり難易度が高い曲でした。おまけに自然気胸になって息がものすごく吸いにくい、吐きにくいの状態で本番を迎えてしまったので大変でした。
このCDの演奏はというと、極めて、秀逸、テンポがつくり辛く難しい2楽章も速めに流すテンポで上品で美しく仕上げています。全体に流麗で洒脱な演奏です。カラヤンの演奏やバーンスタインの演奏はかなりテンポが遅いので、それを聞いている方はビックリする早さです。遅い演奏は遅い演奏でじっくりと聞けてよいのですが、
このCDのテンポだと、はつらつとしていながら上品な演奏に聞こえます。
一緒に収録されている曲も素晴らしいです。私の一押しは牧神の午後への前奏曲です。尚、私が持っているものは初回限定番らしく、ピクチャーレーベルで、おまけとして海の画集がついています。
ドビュッシーの管弦楽音楽が聞いてみたい方、「海」の曲を聞いてみたい方、「海」を吹奏楽ではきいたことがあるけれど原曲を聞いたことは無いと言われる方にオススメの一枚です。
毎度、毎度のことながら、間際の追い込みです。もう少し早く取り掛かればといつも思うのですが、団員の中には極端に腰を挙げるのが重い人もいてなかなか練習に皆が集まってこないのが現状です。
といいつつも、演奏がいいものに出来るといいのですが…。
毎年、「去年の演奏会は結構ボロボロの演奏をしてしまった私なので今年はちょっと頑張らねば」とは思っているのですが。まあ、満足の行く演奏会だったという人もいるので思いでは人それぞれかもしれません。
今年こそはいい思い出の残る演奏会にしようと頑張っています。(でも毎年そう思っているのですが…。)
そこで今日の一枚。
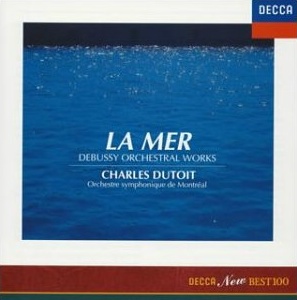
ドビュッシー/海-3つの交響的スケッチ
バレエ音楽「遊戯」、交響的断章「聖セバスチャンの殉教」
牧神の午後への前奏曲
シャルル・デュトワ指揮:モントリオール交響楽団
ティモシー・ハッヂンズ(フルート、牧神)
LONDON(ポリドール) POCL-1044
(リンク先のCDは再販されたDECCAニューベスト盤ですが、内容は同一のものです。)
このCDは、ドビュッシーの「海」がメインで収録されたもの。この曲は数年前、高松ウインドシンフォニー定期演奏会のメインの曲はこの曲として吹奏楽編曲版を全曲演奏しました。もちろん、このCDはオケによる原曲版です。私としてはかなり難易度が高い曲でした。おまけに自然気胸になって息がものすごく吸いにくい、吐きにくいの状態で本番を迎えてしまったので大変でした。
このCDの演奏はというと、極めて、秀逸、テンポがつくり辛く難しい2楽章も速めに流すテンポで上品で美しく仕上げています。全体に流麗で洒脱な演奏です。カラヤンの演奏やバーンスタインの演奏はかなりテンポが遅いので、それを聞いている方はビックリする早さです。遅い演奏は遅い演奏でじっくりと聞けてよいのですが、
このCDのテンポだと、はつらつとしていながら上品な演奏に聞こえます。
一緒に収録されている曲も素晴らしいです。私の一押しは牧神の午後への前奏曲です。尚、私が持っているものは初回限定番らしく、ピクチャーレーベルで、おまけとして海の画集がついています。
ドビュッシーの管弦楽音楽が聞いてみたい方、「海」の曲を聞いてみたい方、「海」を吹奏楽ではきいたことがあるけれど原曲を聞いたことは無いと言われる方にオススメの一枚です。
2008年04月17日
間違えた、第24回定期演奏会
定期演奏会の記事を書きましたが…
チラシが…
去年の奴でした。
本当はこっちです。
↓

高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽
チラシが…
去年の奴でした。
本当はこっちです。
↓

高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽
Posted by のりくん at
20:46
│Comments(0)
2008年04月17日
第24回定期演奏会。
いよいよ、今週末、私の所属する社会人吹奏楽団、高松ウインドシンフォニーの第24回定期演奏会が行われます。
色々なハプニングやトラブルもあり、練習不足名部分があることも否めませんが、団員一同、一生懸命演奏することとなると思いますので、お時間の許す方はアルファあなぶきホール・大ホールまでお越し下さい。

高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽
色々なハプニングやトラブルもあり、練習不足名部分があることも否めませんが、団員一同、一生懸命演奏することとなると思いますので、お時間の許す方はアルファあなぶきホール・大ホールまでお越し下さい。
高松ウインドシンフォニー第24回定期演奏会
とき :2008年4月20日(日) 13:30会場 14:00開演
ところ :アルファあなぶきホール・大ホール(県民ホール・大ホール)
入場料 :一般・1000円、学生・500円
指揮 :岡田誠司・石川孝司・内井規文
曲目 :2008年度吹奏楽コンクール課題曲(中学高校の部全曲)、ウルトラ大行進、宇宙の音楽




