2008年10月01日
軽快に走ろう。
まだまだ続く水不足。秋の水不足というものを私も体験したことがありませんが、今年は本当にやばそうです。果たして台風が恵みの雨をもたらすのか、それとも被害を残すのか…。
さて、先日愛車ソリオの走行距離が1万キロを超え、その記念というわけでもないのですが、キリがいいのでエンジンオイルの交換に行ってきました。前の車、ワゴンRワイドに乗っていたときはターボ車ということもあって、一般的なエンジンオイルよりはちょっとだけグレードの高いオイルを入れてましたが、今回の車はターボもないので、燃費重視の一般的なエンジンオイルにしました。
エンジンオイルを入れ替えるといつも感じることですが、意外なことにハンドル操作が軽やかになる気がします。車の主動力はエンジンであることを改めて感じさせられます。快適になった車で行くところは………。
職場…。
寂しい限りです。
そこで今日の一枚です。

LUPIN THE THIRD JAZZ~the 3rd~
大野雄二トリオ
VAP VPCG-84728
このCDも昨日にひきつづき、このルパン三世をはじめとして、「犬神家の一族」、「人間の証明」、「小さな旅」、「水もれ甲介」などの作曲を手がけた大野雄二自身のトリオによる「ルパン三世」の音楽のジャズ・アルバムです。このシリーズでは第三作目にあたるアルバムになります。
曲目はTheme From Lupin 3(Funky&Pop version)、Woman from Memphis、Treasures of Time(Funky&Pop version)、Mayflower、Tell Me Baby、Zenigata Rock、The Third、Hey!Mr.Lucky、Memory of Smileとなっています。1曲目のTheme From Lupin 3(Funky&Pop version)の通りにシリーズで最も軽快なアップテンポのアルバムに仕上がっているようです。シリーズ二作目よりもさらに万人に受け入れられやすいというか、アルバム自体が聴きやすくなっているようなイメージもあります。おそらく、ノリのよさと、適度に緩急のある楽曲を収録しているため、そう感じるのではないかと思います。
車などで聞くと、ノリのよい軽快な走りを誘ってくれそうなアルバムです。
ルパン三世好きの世代の方、また、ジャズにこれからはまろうとしている若い世代の方々、ドライブのお供にもオススメの一枚です。
さて、先日愛車ソリオの走行距離が1万キロを超え、その記念というわけでもないのですが、キリがいいのでエンジンオイルの交換に行ってきました。前の車、ワゴンRワイドに乗っていたときはターボ車ということもあって、一般的なエンジンオイルよりはちょっとだけグレードの高いオイルを入れてましたが、今回の車はターボもないので、燃費重視の一般的なエンジンオイルにしました。
エンジンオイルを入れ替えるといつも感じることですが、意外なことにハンドル操作が軽やかになる気がします。車の主動力はエンジンであることを改めて感じさせられます。快適になった車で行くところは………。
職場…。
寂しい限りです。
そこで今日の一枚です。

LUPIN THE THIRD JAZZ~the 3rd~
大野雄二トリオ
VAP VPCG-84728
このCDも昨日にひきつづき、このルパン三世をはじめとして、「犬神家の一族」、「人間の証明」、「小さな旅」、「水もれ甲介」などの作曲を手がけた大野雄二自身のトリオによる「ルパン三世」の音楽のジャズ・アルバムです。このシリーズでは第三作目にあたるアルバムになります。
曲目はTheme From Lupin 3(Funky&Pop version)、Woman from Memphis、Treasures of Time(Funky&Pop version)、Mayflower、Tell Me Baby、Zenigata Rock、The Third、Hey!Mr.Lucky、Memory of Smileとなっています。1曲目のTheme From Lupin 3(Funky&Pop version)の通りにシリーズで最も軽快なアップテンポのアルバムに仕上がっているようです。シリーズ二作目よりもさらに万人に受け入れられやすいというか、アルバム自体が聴きやすくなっているようなイメージもあります。おそらく、ノリのよさと、適度に緩急のある楽曲を収録しているため、そう感じるのではないかと思います。
車などで聞くと、ノリのよい軽快な走りを誘ってくれそうなアルバムです。
ルパン三世好きの世代の方、また、ジャズにこれからはまろうとしている若い世代の方々、ドライブのお供にもオススメの一枚です。
2008年09月30日
秋の夜長。
まだまだ水不足が続いています。このままだと本当に深刻な状況になりそうです。
さて、この数日間、朝夕がかなり涼しくなってきました。まさに季節は秋の様相を呈しています。秋の夜長を楽しむといえば、私はやはり読書と音楽鑑賞でしょうか…。
本当はサクソフォンアンサンブルの練習とかも出来るといいのですが、夜はなかなか難しい状況です。
人によってはお酒をちびちびとやりながら、音楽を聴いたり月を眺めたり、ということも楽しめるのかもしれませんが、私は激下戸なので、お酒の楽しみ方もいまひとつよく理解できません。
そこで今日の一枚です。

LUPIN THE THIRD 「JAZZ」
大野雄二トリオ
VAP VPCG-84680
このCDは「ルパン三世」をはじめ、「犬神家の一族」「人間の証明」「小さな旅」「水もれ甲介」などの音楽を手掛けた作曲家、大野雄二自身のトリオによる「ルパン三世」の楽曲を取り上げたもの。ルパンと言えども、れっきとしたJAZZアルバムです。
曲目は、Theme From Lupin 3(Full size version)、O Meu A Mor、Love Theme、Members Only、Zenigata March、Funny Walk、Fire Treasure、Manhattan Joke、Love Squallと、映画やTVで聞いたルパン三世の曲ばかりとなっています。
JAZZトリオだけに、演奏のほうはやや渋め。派手なルパン三世というイメージはありませんが、大人のルパン三世といったイメージでしょうか。しっかりとJAZZしてます。派手なスウィング調の演奏ではありませんが、まさに、秋の夜長にゆっくりと読書などしながら聴くと良い感じでは内でしょうか。
ルパン三世を大好きで大人になった方、また、しっかりとJAZZされているCDでもあるのでJAZZ初心者の入門用としてもお勧めの一枚です。
さて、この数日間、朝夕がかなり涼しくなってきました。まさに季節は秋の様相を呈しています。秋の夜長を楽しむといえば、私はやはり読書と音楽鑑賞でしょうか…。
本当はサクソフォンアンサンブルの練習とかも出来るといいのですが、夜はなかなか難しい状況です。
人によってはお酒をちびちびとやりながら、音楽を聴いたり月を眺めたり、ということも楽しめるのかもしれませんが、私は激下戸なので、お酒の楽しみ方もいまひとつよく理解できません。
そこで今日の一枚です。

LUPIN THE THIRD 「JAZZ」
大野雄二トリオ
VAP VPCG-84680
このCDは「ルパン三世」をはじめ、「犬神家の一族」「人間の証明」「小さな旅」「水もれ甲介」などの音楽を手掛けた作曲家、大野雄二自身のトリオによる「ルパン三世」の楽曲を取り上げたもの。ルパンと言えども、れっきとしたJAZZアルバムです。
曲目は、Theme From Lupin 3(Full size version)、O Meu A Mor、Love Theme、Members Only、Zenigata March、Funny Walk、Fire Treasure、Manhattan Joke、Love Squallと、映画やTVで聞いたルパン三世の曲ばかりとなっています。
JAZZトリオだけに、演奏のほうはやや渋め。派手なルパン三世というイメージはありませんが、大人のルパン三世といったイメージでしょうか。しっかりとJAZZしてます。派手なスウィング調の演奏ではありませんが、まさに、秋の夜長にゆっくりと読書などしながら聴くと良い感じでは内でしょうか。
ルパン三世を大好きで大人になった方、また、しっかりとJAZZされているCDでもあるのでJAZZ初心者の入門用としてもお勧めの一枚です。
2008年09月29日
台風が来ませんが…。
台風らしい台風がやってきません。他の各地では前回の台風で水害まで起きたようですが、水不足を根本的に解決できるような雨は降っていません。
台風になると被害が出たりもするので、あまり台風を期待するというのも不謹慎なのかもしれませんが、台風に期待するしかないほど、水不足が深刻です。でも、やはり台風というのは災害として捉えていなければならないのかもしれません。
台風によって停電になって、その上に浸水が起こったりするとはっきり言ってパニックです。
そこで今日の一枚です。

グローフェ 組曲「グランド・キャニオン」
バーンスタイン シンフォニック・ダンス「ウエスト・サイド物語」
指揮:レナード・バーンスタイン
ニューヨーク・フィルハーモニック
CBS/SONY 20AC 1570
これはLPレコードです。現在、これに他のガーシュウィンの曲が加えられたような形でCDも出ているようです。シンフォニック・ダンスのほうは、先日紹介したCDの中に全く同じ演奏が収録されています。
さて、グランド・キャニオンですが、以前、ドラティ/デトロイト響のものを紹介しましたが、私が聞いたのはこのレコードが最初でした。ドラティ盤に比べて、多少、線が細いと言うか、盛り上がりに欠けると言う印象はありますが、以外にもそのあっさりとした味付けに良さを感じる部分もあります。「日の出」の部分などはそのよさが顕著に現れているのか、盛り上げ方も見事です。
で、やはり台風からイメージするのは「豪雨」の場面ですが、このバーンスタイン盤は多少、平坦というか、力強さに欠けるかもしれません。盛り上がってきたな、と思ったらあれ?終了ですか?見たいなイメージが無きにしも非ずです。
しかし、全体的に良くまとめられた構成で、きちんと組曲として捉えようとする姿勢もうかがえます。シンフォニック・ダンスのほうは先日書いた通りなのでそちらをご参照ください。
LPで曲数が少ないため、この2曲のみの収録となっています。
バーンスタインによる自作自演を含めたアメリカ音楽を楽しみたい方、グローフェの「グランド・キャニオン」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
台風になると被害が出たりもするので、あまり台風を期待するというのも不謹慎なのかもしれませんが、台風に期待するしかないほど、水不足が深刻です。でも、やはり台風というのは災害として捉えていなければならないのかもしれません。
台風によって停電になって、その上に浸水が起こったりするとはっきり言ってパニックです。
そこで今日の一枚です。

グローフェ 組曲「グランド・キャニオン」
バーンスタイン シンフォニック・ダンス「ウエスト・サイド物語」
指揮:レナード・バーンスタイン
ニューヨーク・フィルハーモニック
CBS/SONY 20AC 1570
これはLPレコードです。現在、これに他のガーシュウィンの曲が加えられたような形でCDも出ているようです。シンフォニック・ダンスのほうは、先日紹介したCDの中に全く同じ演奏が収録されています。
さて、グランド・キャニオンですが、以前、ドラティ/デトロイト響のものを紹介しましたが、私が聞いたのはこのレコードが最初でした。ドラティ盤に比べて、多少、線が細いと言うか、盛り上がりに欠けると言う印象はありますが、以外にもそのあっさりとした味付けに良さを感じる部分もあります。「日の出」の部分などはそのよさが顕著に現れているのか、盛り上げ方も見事です。
で、やはり台風からイメージするのは「豪雨」の場面ですが、このバーンスタイン盤は多少、平坦というか、力強さに欠けるかもしれません。盛り上がってきたな、と思ったらあれ?終了ですか?見たいなイメージが無きにしも非ずです。
しかし、全体的に良くまとめられた構成で、きちんと組曲として捉えようとする姿勢もうかがえます。シンフォニック・ダンスのほうは先日書いた通りなのでそちらをご参照ください。
LPで曲数が少ないため、この2曲のみの収録となっています。
バーンスタインによる自作自演を含めたアメリカ音楽を楽しみたい方、グローフェの「グランド・キャニオン」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月28日
そんな腕はありません。
続く水不足。不安定なお天気、まさに世の中どうなっているのか?などと考えてしまいます。
さて、明日さぬきに引越しをしてから、既に9ヶ月が経過しました。かなりの枚数のCDを紹介してきましたが、まだまだ紹介すべきCDは沢山残っています。出来るだけ、チマチマ、ボチボチとやっていければと思っています。ですので、
オーディオのほうもUPすべく、写真を撮るのですが、出来がイマイチでなかなか上手くいきません。プロの写真家はそれなりにちゃんとした道具も持っていますので、きれいに取れるのですが、私は何も知らない素人なので、特に光の反射が起こりやすい、金属ボディのオーディオは撮り難く感じています。私はかなり前、印刷会社で働いた経験を持っているのですが、その時にいろいろな商品の撮影にも立ち会いました。結果、言えることはパンフレットに載っている商品、あれは本物ですが、偽者です。たとえば、折などに入った料理。あれは、美しい照りを出すため、ほとんどの場合、折箱に詰めたあと、上からゼラチンを流して光るようにします。また、鍋物なんかは、あったかく見えるように、ゆでた碁石なんかをなべのそこに沈めて湯気を出したりします。箱物はあらゆる角度から光を当てて、影を消したり、あるいは影を作ったりしています。自然光では絶対にえられない、陰影をライティングでつけていきます。
元々、折箱が商品なのに、中に高級料理を入れているのは大きな嘘のような気がするのですが、それは一言、「中の料理は商品には含まれていません」で片付けてあります。
まあ、商業写真でいい写真を撮るためにはある程度、絵を作る技術が必要と言うことでしょうか。私にはそんな腕はありません。
そこで今日の一枚です。

ドボルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95《新世界》より
指揮:フェレンツ・フリッチャイ
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
グラモフォン(ポリドール) MGW5107
これはLPレコードです。レコーディングが1959年となっています。録音はステレオです。
この時代はレコード、まだまだレーベルを見ながら買い、聴く楽しみがありました。レコードのレーベルはCDに比べてサイズが大きいこともあり、より、アーティスティックで、芸術性に富んだものが多かったのではないかと思います。このレーベルにも、美しい風景の写真が印刷されています。今のCDで同じような写真を載せたとしても、なぜか物足りなかったり、じっくり見ることなく終わりそうなのは私だけでしょうか。
演奏のほうは、次の時代のカラヤンとは明らかに違う響きが聴いて取れます。前の時代のフルトヴェングラー的な音の響きと言うか、密度の濃い弾力性のある重心の低い響きのようなものが感じられます。残念なことに彼は、白血病のために、50歳を迎えずしてなくなってしまいましたが、長く生きていたとしたら、カラヤンと肩を並べるか、それ以上の指揮者になっていたかも知れません。カラヤン時代になると、ベルリンフィルはよくも悪くも響きがカラヤン色一色になっていきます。それは、近代的なデジタル録音や、クラシックの大衆化には必要だったのかもしれませんが、フルトヴェングラーが守り続けたベルリンフィルの伝統の響きは失われてしまったのかもしれません。なぜか、オーケストラから懐かしい響きが感じられる、ドボルザークでもあります。
フリッチャイの指揮でのベルリンフィルの響きを聞きたい方、ドボルザークの《新世界》よりを聞いてみたい方にオススメです。(CDで他の曲とカップリングされて今は出ているようです。)
さて、明日さぬきに引越しをしてから、既に9ヶ月が経過しました。かなりの枚数のCDを紹介してきましたが、まだまだ紹介すべきCDは沢山残っています。出来るだけ、チマチマ、ボチボチとやっていければと思っています。ですので、
オーディオのほうもUPすべく、写真を撮るのですが、出来がイマイチでなかなか上手くいきません。プロの写真家はそれなりにちゃんとした道具も持っていますので、きれいに取れるのですが、私は何も知らない素人なので、特に光の反射が起こりやすい、金属ボディのオーディオは撮り難く感じています。私はかなり前、印刷会社で働いた経験を持っているのですが、その時にいろいろな商品の撮影にも立ち会いました。結果、言えることはパンフレットに載っている商品、あれは本物ですが、偽者です。たとえば、折などに入った料理。あれは、美しい照りを出すため、ほとんどの場合、折箱に詰めたあと、上からゼラチンを流して光るようにします。また、鍋物なんかは、あったかく見えるように、ゆでた碁石なんかをなべのそこに沈めて湯気を出したりします。箱物はあらゆる角度から光を当てて、影を消したり、あるいは影を作ったりしています。自然光では絶対にえられない、陰影をライティングでつけていきます。
元々、折箱が商品なのに、中に高級料理を入れているのは大きな嘘のような気がするのですが、それは一言、「中の料理は商品には含まれていません」で片付けてあります。
まあ、商業写真でいい写真を撮るためにはある程度、絵を作る技術が必要と言うことでしょうか。私にはそんな腕はありません。
そこで今日の一枚です。

ドボルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95《新世界》より
指揮:フェレンツ・フリッチャイ
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
グラモフォン(ポリドール) MGW5107
これはLPレコードです。レコーディングが1959年となっています。録音はステレオです。
この時代はレコード、まだまだレーベルを見ながら買い、聴く楽しみがありました。レコードのレーベルはCDに比べてサイズが大きいこともあり、より、アーティスティックで、芸術性に富んだものが多かったのではないかと思います。このレーベルにも、美しい風景の写真が印刷されています。今のCDで同じような写真を載せたとしても、なぜか物足りなかったり、じっくり見ることなく終わりそうなのは私だけでしょうか。
演奏のほうは、次の時代のカラヤンとは明らかに違う響きが聴いて取れます。前の時代のフルトヴェングラー的な音の響きと言うか、密度の濃い弾力性のある重心の低い響きのようなものが感じられます。残念なことに彼は、白血病のために、50歳を迎えずしてなくなってしまいましたが、長く生きていたとしたら、カラヤンと肩を並べるか、それ以上の指揮者になっていたかも知れません。カラヤン時代になると、ベルリンフィルはよくも悪くも響きがカラヤン色一色になっていきます。それは、近代的なデジタル録音や、クラシックの大衆化には必要だったのかもしれませんが、フルトヴェングラーが守り続けたベルリンフィルの伝統の響きは失われてしまったのかもしれません。なぜか、オーケストラから懐かしい響きが感じられる、ドボルザークでもあります。
フリッチャイの指揮でのベルリンフィルの響きを聞きたい方、ドボルザークの《新世界》よりを聞いてみたい方にオススメです。(CDで他の曲とカップリングされて今は出ているようです。)
2008年09月27日
視力検査。
いまだに水不足。この天気、一体どうなるのか???大丈夫なのか香川県。
さて、最近視力が低下している気がします。私は年に数度、 とある目の検査をしているので、時々視力を測っています。そこではさほど視力は低下していないようなのですが、最近景色が見えにくい気がしています。
思うのですが、あの視力検査のランドルト環、見えにくい域になってくるとほとんどカンで答えてますが、もしまぐれで3つぐらい当たったら、その視力になってしまうのでしょうか?よくわかりません。でも、あれが日本では主流の視力検査なので、きっと信頼性は高いのだろうと思います。しかし、学生時代、視力が低いと、あの視力検査のボードの前で「ハイ、ひとつ前の線まで寄って」と言われ、さらに見えない旨、伝えると、「見えるところまで寄ってきてください」と言われるのはちょっと恥ずかしかった記憶があります。何せ、一番上のでっかいのを見るがために、あのボードを見上げるほど、前まで行かなければなりませんでしたもので。今は眼科などに行くと、裸眼視力はある程度機械で正確に測れるようなので、そんなこともありませんが。
しかし、あの、「前の線まで」は中高生の頃はちょっとショックでした。
そこで今日の一枚です。

フォー・カラーズ/アルディ・サクソフォン・クヮルテット
マイスター・ミュージック MM-1110
このCDは先日紹介したアルディ・サクソフォン・クヮルテットの2枚目に当たるアルバムです。比較的民謡系というか、民族色の強い作品での構成になっています。
曲目は、民謡による3つのロンド(バルトーク)、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲(ピエルネ)、4人のコラージュ (啼鵬)、ルーマニア民謡の主題による組曲 (アプシル)、アヴェ・マリア (カッチーニ)となっています。
演奏のほうはやはり、きっちりとした端正といった印象です。ただし、民族音楽的なある意味泥臭さがもう少しあっても楽しかったかもしれません。批判的に書くと、どちらかと言えば、楽譜に書かれていることを忠実にやろうとしていることは聞いて取れるのですが、その反面、楽譜に対して近眼的になっているような気もします。たとえば、アプシルのルーマニ民謡の主題による組曲などは、私が以前紹介したジャン・リュデュー氏のカルテットの方が、民族的な風味を感じられて私は好きです。ただ、全体を通して、ハーモニーのひびかせ方や、音の処理は絶品とも言うべきもので、一聴の価値があります。たぶん、民族的な泥臭さを求めるかどうかは好みの問題なのだと思います。ただ、もうちょっと、自己主張というか、楽譜に書かれていないテイストをつけると言ったことが欲しいような気もします。
端正な演奏を聞きたい方、楽譜を見ながらの参考演奏を探している方にオススメの一枚です。
さて、最近視力が低下している気がします。私は年に数度、 とある目の検査をしているので、時々視力を測っています。そこではさほど視力は低下していないようなのですが、最近景色が見えにくい気がしています。
思うのですが、あの視力検査のランドルト環、見えにくい域になってくるとほとんどカンで答えてますが、もしまぐれで3つぐらい当たったら、その視力になってしまうのでしょうか?よくわかりません。でも、あれが日本では主流の視力検査なので、きっと信頼性は高いのだろうと思います。しかし、学生時代、視力が低いと、あの視力検査のボードの前で「ハイ、ひとつ前の線まで寄って」と言われ、さらに見えない旨、伝えると、「見えるところまで寄ってきてください」と言われるのはちょっと恥ずかしかった記憶があります。何せ、一番上のでっかいのを見るがために、あのボードを見上げるほど、前まで行かなければなりませんでしたもので。今は眼科などに行くと、裸眼視力はある程度機械で正確に測れるようなので、そんなこともありませんが。
しかし、あの、「前の線まで」は中高生の頃はちょっとショックでした。
そこで今日の一枚です。

フォー・カラーズ/アルディ・サクソフォン・クヮルテット
マイスター・ミュージック MM-1110
このCDは先日紹介したアルディ・サクソフォン・クヮルテットの2枚目に当たるアルバムです。比較的民謡系というか、民族色の強い作品での構成になっています。
曲目は、民謡による3つのロンド(バルトーク)、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲(ピエルネ)、4人のコラージュ (啼鵬)、ルーマニア民謡の主題による組曲 (アプシル)、アヴェ・マリア (カッチーニ)となっています。
演奏のほうはやはり、きっちりとした端正といった印象です。ただし、民族音楽的なある意味泥臭さがもう少しあっても楽しかったかもしれません。批判的に書くと、どちらかと言えば、楽譜に書かれていることを忠実にやろうとしていることは聞いて取れるのですが、その反面、楽譜に対して近眼的になっているような気もします。たとえば、アプシルのルーマニ民謡の主題による組曲などは、私が以前紹介したジャン・リュデュー氏のカルテットの方が、民族的な風味を感じられて私は好きです。ただ、全体を通して、ハーモニーのひびかせ方や、音の処理は絶品とも言うべきもので、一聴の価値があります。たぶん、民族的な泥臭さを求めるかどうかは好みの問題なのだと思います。ただ、もうちょっと、自己主張というか、楽譜に書かれていないテイストをつけると言ったことが欲しいような気もします。
端正な演奏を聞きたい方、楽譜を見ながらの参考演奏を探している方にオススメの一枚です。
2008年09月26日
若さと個性。
相変わらず水不足。纏まった雨が降らない日が続いています。
さて、ダッパーの一番古いホームページ、現在は一切稼動していないウェブですが、そこには今から既に10年以上前の記事や写真がアーカイブされています。今見てみると、当時は若かったなー、などと思ってしまいます。若い頃は個性を主張するために何かをやろうとしたり、奇をてらった行動に出たりすることがありますが、本当は、自分自身こそが、存在こそが個性なのですが、やはり若かりし頃にはそれをなんとか主張しようともがいたあとも見られています。
そこで今日の一枚です。

サクソフォーン・アンサンブル名曲集 1/
トルヴェール・クヮルテット
吹奏楽名曲コレクション32)
東芝EMI TOCZ-9196
このCDはトルヴェール・クヮルテットによるサクソフォンのオリジナルとアレンジ物の小品集です。「吹奏楽名曲コレクション」としてリリースされ、現在は「新・吹奏楽名曲コレクション・アンサンブル・スタンダーズ」として再プレスされています。ちなみに第二集はキャトルロゾー・サクソフォーンアンサンブルの演奏です。そちらも現在は、「新・吹奏楽名曲コレクション・アンサンブル・スタンダーズ」のシリーズで再プレスされているようです。(サクソフォーン・アンサンブルII )
曲目は、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲 (ピエルネ)、サクソフォン4重奏曲より カンツォーナ・ヴァリエ (グラズノフ)、異教徒の踊り (ショルティーノ)、グラーヴェとプレスト (リヴィエ)、カンツォーニ (フレスコバルディ)、G線上のアリア (バッハ)、ブーレ (バッハ)、フーガの技法 第9番 (バッハ)、アヴェ・ヴェルム・コルプス (モーツァルト)、前奏曲とフーガ ヘ短調 (メンデルスゾーン)
カディス~スペイン組曲より (アルベニス)、ラグタイム組曲 (フラッケンポール)(←CDのレーベルでは「ラダタイム組曲」という誤植になっていますが)の12曲です。
トルヴェールのCDとしては比較的初期の録音に当たると思いますが、カンツォーナ・ヴァリエなどは後に録音されたアルバム「マルセル・ミュールに捧ぐ」の録音と比べると、若々しさのようなものが伝わってきて面白かったりします。また、G線上のアリアは昨日紹介したアルディ・サクソフォン・クヮルテットとの演奏と比べてみると、曲の作り方の違いと言うか、音楽の方向性の違いのようなものも感じられて面白いかもしれません。(ヘタレな我々の演奏とは比べる余地がありませんが)また、サクソフォン・カルテットでは比較的よく演奏されているのにもかかわらず、録音が少ない「ラグタイム組曲」などが聴ける貴重で楽しいアルバムにもなっています。
サクソフォーン・アンサンブルの小品集を聴いてみたい方、G線上のアリアを聞いてみたい方、また、いくつかの曲を聴き比べてみたい方にオススメの一枚です。
さて、ダッパーの一番古いホームページ、現在は一切稼動していないウェブですが、そこには今から既に10年以上前の記事や写真がアーカイブされています。今見てみると、当時は若かったなー、などと思ってしまいます。若い頃は個性を主張するために何かをやろうとしたり、奇をてらった行動に出たりすることがありますが、本当は、自分自身こそが、存在こそが個性なのですが、やはり若かりし頃にはそれをなんとか主張しようともがいたあとも見られています。
そこで今日の一枚です。

サクソフォーン・アンサンブル名曲集 1/
トルヴェール・クヮルテット
吹奏楽名曲コレクション32)
東芝EMI TOCZ-9196
このCDはトルヴェール・クヮルテットによるサクソフォンのオリジナルとアレンジ物の小品集です。「吹奏楽名曲コレクション」としてリリースされ、現在は「新・吹奏楽名曲コレクション・アンサンブル・スタンダーズ」として再プレスされています。ちなみに第二集はキャトルロゾー・サクソフォーンアンサンブルの演奏です。そちらも現在は、「新・吹奏楽名曲コレクション・アンサンブル・スタンダーズ」のシリーズで再プレスされているようです。(サクソフォーン・アンサンブルII )
曲目は、民謡風ロンドの主題による前奏と変奏曲 (ピエルネ)、サクソフォン4重奏曲より カンツォーナ・ヴァリエ (グラズノフ)、異教徒の踊り (ショルティーノ)、グラーヴェとプレスト (リヴィエ)、カンツォーニ (フレスコバルディ)、G線上のアリア (バッハ)、ブーレ (バッハ)、フーガの技法 第9番 (バッハ)、アヴェ・ヴェルム・コルプス (モーツァルト)、前奏曲とフーガ ヘ短調 (メンデルスゾーン)
カディス~スペイン組曲より (アルベニス)、ラグタイム組曲 (フラッケンポール)(←CDのレーベルでは「ラダタイム組曲」という誤植になっていますが)の12曲です。
トルヴェールのCDとしては比較的初期の録音に当たると思いますが、カンツォーナ・ヴァリエなどは後に録音されたアルバム「マルセル・ミュールに捧ぐ」の録音と比べると、若々しさのようなものが伝わってきて面白かったりします。また、G線上のアリアは昨日紹介したアルディ・サクソフォン・クヮルテットとの演奏と比べてみると、曲の作り方の違いと言うか、音楽の方向性の違いのようなものも感じられて面白いかもしれません。(ヘタレな我々の演奏とは比べる余地がありませんが)また、サクソフォン・カルテットでは比較的よく演奏されているのにもかかわらず、録音が少ない「ラグタイム組曲」などが聴ける貴重で楽しいアルバムにもなっています。
サクソフォーン・アンサンブルの小品集を聴いてみたい方、G線上のアリアを聞いてみたい方、また、いくつかの曲を聴き比べてみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月25日
曲を作りあげていくには…。
水不足が続いていますが、相変わらず、雨らしい雨が降りません。9月ももう終わろうとしているのに、本当に大丈夫なのでしょうか?
さて、サクソフォーンアンサンブルコンサートに向けて練習が佳境を迎えています。先日の日曜日も午前はダッパーのカルテット、午後はラージの練習が行われました。
曲を仕上げていくということは、決して曲が吹けるようにすることではなく、表現をつけたり、皆でその表現を整えたり、曲の全体の作りを理解し、咀嚼し、自分達の表現にしていく必要があります。曲を仕上げる時に、ともすれば、楽譜の音符だけを追うことに気が行きがちですが、楽譜に書ききれていない部分までを考えて、表現を組み立てることこそが重要で曲を作り上げていくことの醍醐味なのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

air/アルディ・サクソフォーン・クヮルテット
マイスターミュージック MM 1132
このCDはアルディーサクソフォーンカルテットの3枚目のアルバムになります。クラシックから編曲した小品で構成されています。
曲目は、プレリュード~無伴奏チェロ組曲第1番より (バッハ) 、G線上のアリア (バッハ) 、ジュ・トゥ・ヴ (サティ) 、アヴェ・マリア (シューベルト) 、ヴォカリーズ (ラフマニノフ) 、カノン (パッヘルベル) 、タイム・トゥ・セイ・グッドバイ (サルトーリ) 、アリア~ゴルトベルグ組曲より (バッハ) 、喜びの島 (ドビュッシー) 、ラルゲット~弦楽セレナードより (エルガー) 、歌劇「カヴァレリア・ルスティカナ」より 間奏曲 (マスカーニ)となっています。
今日聞いても思ったことですが、やはりアルディの魅力は、ひけらかしたような派手さが無いにもかかわらず、そのしっかりとした演奏と柔らかな響きでしょうか。ただ、欲を言えば、もう少し演奏に主張と言うか、演奏者の理解している作曲者の姿のようなものが見えてくるといいような気もして、少し物足りない部分もあります。
ただ、表現をもう少しやりたいのにやらないで美しく緻密に仕上げていくという姿勢は明らかに私達にはかけている部分だと思うので非常に参考になります。また、聞いていて、聞き疲れしにくい演奏でもあります。
アルディ・サクソフォーンカルテットの演奏を聞いてみたい方、クラシックの小品をサクソフォーンの響きで楽しみたい方にオススメの一枚です。
さて、サクソフォーンアンサンブルコンサートに向けて練習が佳境を迎えています。先日の日曜日も午前はダッパーのカルテット、午後はラージの練習が行われました。
曲を仕上げていくということは、決して曲が吹けるようにすることではなく、表現をつけたり、皆でその表現を整えたり、曲の全体の作りを理解し、咀嚼し、自分達の表現にしていく必要があります。曲を仕上げる時に、ともすれば、楽譜の音符だけを追うことに気が行きがちですが、楽譜に書ききれていない部分までを考えて、表現を組み立てることこそが重要で曲を作り上げていくことの醍醐味なのかもしれません。
そこで今日の一枚です。

air/アルディ・サクソフォーン・クヮルテット
マイスターミュージック MM 1132
このCDはアルディーサクソフォーンカルテットの3枚目のアルバムになります。クラシックから編曲した小品で構成されています。
曲目は、プレリュード~無伴奏チェロ組曲第1番より (バッハ) 、G線上のアリア (バッハ) 、ジュ・トゥ・ヴ (サティ) 、アヴェ・マリア (シューベルト) 、ヴォカリーズ (ラフマニノフ) 、カノン (パッヘルベル) 、タイム・トゥ・セイ・グッドバイ (サルトーリ) 、アリア~ゴルトベルグ組曲より (バッハ) 、喜びの島 (ドビュッシー) 、ラルゲット~弦楽セレナードより (エルガー) 、歌劇「カヴァレリア・ルスティカナ」より 間奏曲 (マスカーニ)となっています。
今日聞いても思ったことですが、やはりアルディの魅力は、ひけらかしたような派手さが無いにもかかわらず、そのしっかりとした演奏と柔らかな響きでしょうか。ただ、欲を言えば、もう少し演奏に主張と言うか、演奏者の理解している作曲者の姿のようなものが見えてくるといいような気もして、少し物足りない部分もあります。
ただ、表現をもう少しやりたいのにやらないで美しく緻密に仕上げていくという姿勢は明らかに私達にはかけている部分だと思うので非常に参考になります。また、聞いていて、聞き疲れしにくい演奏でもあります。
アルディ・サクソフォーンカルテットの演奏を聞いてみたい方、クラシックの小品をサクソフォーンの響きで楽しみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月24日
捨てる神あれば、拾う神あり。
さて、私の趣味のひとつである、オーディオ。金欠病のため、機器を入れ替えたり、追加したりする余裕が今は無く、最近、いろいろなことで休日も家を空けることが多いため、オーディオをいじっている時間が減ってしまったために、以前よりこだわりがなくなってきています。とは言え、古い機材もあるので、ある程度メンテをしつつ、新しい機材と入れ替えていかないと、所詮は工業製品、寿命が着てしまいます。
思い起こせば、サブシステムのCDプレーヤーは、なんともらい物。ただでもらってきたものです。10年くらい前、知り合いが店舗のBGM用に使用していたのですが、廃業するに当たって処分するより使ってくれる人にあげたほうがいい、ということで私がもらってきました。本当は、アンプやカセットデッキもあったのですが、たくさんもらっても、私も使い切れない上に、置き場所が困るのでもらわなかったのです。
店舗のBGM用といっても始終それを使っていたわけではなくて、ほとんどは有線放送を使っていたようなので、あまり使用されていませんでした。ちなみに、業務用機器ではなく普通民生機(ビクター製)です。ただ、リモコンがなくなっていたので、ハードオフのジャンクコーナーで使えるリモコンを探してきて、使えるようにしました。リモコン代は500円ぐらいでした。
捨てる神あれば、拾う神あり、よく言ったもので、本当は捨てられる予定だったCDプレーヤーはそれから約10年、私によって使われています。古いプレーヤーで、値段もそんなに高級機というわけではないですが、サブシステムとして音楽を流しっぱなしにするのにはちょうどいいものです。何しろ、ヘビーな使い方をして、駄目になっても、元手がただ、ということを考えると惜しげが無いので、遠慮なくバンバン使うことができます。それに比べてメインシステムのほうは私にとって超高級機な上に、故障すると、製造打ち切りから時間もたっていて修理がきかない可能性があるので、注意して使っています。(CCCDなんかは怖くて絶対再生できません)
そういえば、私も捨てるつもりだったポータブルのCDプレーヤーや、MDプレーヤーを人に上げたことがあります。正確に言えば、故障していたのですが、新品を買うより安い値段で修理できたため私があげた人は今でも使っているようです。物を大切にすると言うのではないかもしれませんが、こうやって不要なものを次の人がバリバリ使ってくれると、あげたほうも嬉しくなってきます。
そこで今日の一枚です。

ウエスト・サイド物語/ファン=ズヴェーデン(バイオリン)
アムステルダム・サクソフォーン・カルテット
RCA(BMG Victor) BVCF-1538
このCDはアムステルダム・サクソフォーン・カルテットがコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートマスターでバイオリニストのファン=ズヴェーデンを迎えて演奏している、バイオリン+サクソフォーン・カルテットという珍しい編成の演奏です。
実はこのCD、5年ぐらい前に市内にあるブックオフで買ってきたものです。900円ぐらいでした。(元の値段は2500円です)別にこのCDを探していたわけでは無くて、ブックオフで立ち読みのついでにCDコーナーを物色していてたまたま見つけたものです。それ以前から存在を知っていたCDでしたが、購入していなかったので、迷わず買ってしまいました。多分、売り払った人は演奏を堪能して終わったか、興味がなくなったかだと思うのですが、私にとってはひとつの宝物になります。まさに捨てる神あれば拾う神ありです。
演奏の方は、編曲の趣向も効いていて、楽しめる内容になっています。曲目は、ウェストサイド物語より (バーンスタイン) 、パリのアメリカ人 (ガーシュウィン)の二曲だけですが、ウエストサイドの方がかなりたっぷりと録音されており、聴き応え十分です。演奏の技術も高く、ポップス向きの音色とも思えますが、それがこの選曲にあっていてなかなかいい演奏だと思います。
サクソフォーンカルテット+バイオリンという珍しい編成の音楽を聞いてみたい方、ウエストサイド物語がお好きな方にオススメの一枚です
思い起こせば、サブシステムのCDプレーヤーは、なんともらい物。ただでもらってきたものです。10年くらい前、知り合いが店舗のBGM用に使用していたのですが、廃業するに当たって処分するより使ってくれる人にあげたほうがいい、ということで私がもらってきました。本当は、アンプやカセットデッキもあったのですが、たくさんもらっても、私も使い切れない上に、置き場所が困るのでもらわなかったのです。
店舗のBGM用といっても始終それを使っていたわけではなくて、ほとんどは有線放送を使っていたようなので、あまり使用されていませんでした。ちなみに、業務用機器ではなく普通民生機(ビクター製)です。ただ、リモコンがなくなっていたので、ハードオフのジャンクコーナーで使えるリモコンを探してきて、使えるようにしました。リモコン代は500円ぐらいでした。
捨てる神あれば、拾う神あり、よく言ったもので、本当は捨てられる予定だったCDプレーヤーはそれから約10年、私によって使われています。古いプレーヤーで、値段もそんなに高級機というわけではないですが、サブシステムとして音楽を流しっぱなしにするのにはちょうどいいものです。何しろ、ヘビーな使い方をして、駄目になっても、元手がただ、ということを考えると惜しげが無いので、遠慮なくバンバン使うことができます。それに比べてメインシステムのほうは私にとって超高級機な上に、故障すると、製造打ち切りから時間もたっていて修理がきかない可能性があるので、注意して使っています。(CCCDなんかは怖くて絶対再生できません)
そういえば、私も捨てるつもりだったポータブルのCDプレーヤーや、MDプレーヤーを人に上げたことがあります。正確に言えば、故障していたのですが、新品を買うより安い値段で修理できたため私があげた人は今でも使っているようです。物を大切にすると言うのではないかもしれませんが、こうやって不要なものを次の人がバリバリ使ってくれると、あげたほうも嬉しくなってきます。
そこで今日の一枚です。

ウエスト・サイド物語/ファン=ズヴェーデン(バイオリン)
アムステルダム・サクソフォーン・カルテット
RCA(BMG Victor) BVCF-1538
このCDはアムステルダム・サクソフォーン・カルテットがコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートマスターでバイオリニストのファン=ズヴェーデンを迎えて演奏している、バイオリン+サクソフォーン・カルテットという珍しい編成の演奏です。
実はこのCD、5年ぐらい前に市内にあるブックオフで買ってきたものです。900円ぐらいでした。(元の値段は2500円です)別にこのCDを探していたわけでは無くて、ブックオフで立ち読みのついでにCDコーナーを物色していてたまたま見つけたものです。それ以前から存在を知っていたCDでしたが、購入していなかったので、迷わず買ってしまいました。多分、売り払った人は演奏を堪能して終わったか、興味がなくなったかだと思うのですが、私にとってはひとつの宝物になります。まさに捨てる神あれば拾う神ありです。
演奏の方は、編曲の趣向も効いていて、楽しめる内容になっています。曲目は、ウェストサイド物語より (バーンスタイン) 、パリのアメリカ人 (ガーシュウィン)の二曲だけですが、ウエストサイドの方がかなりたっぷりと録音されており、聴き応え十分です。演奏の技術も高く、ポップス向きの音色とも思えますが、それがこの選曲にあっていてなかなかいい演奏だと思います。
サクソフォーンカルテット+バイオリンという珍しい編成の音楽を聞いてみたい方、ウエストサイド物語がお好きな方にオススメの一枚です
2008年09月23日
鼻抜け。
月曜日が代休で休みだったことで、この3日間は連休となりました。その間もサクソフォンアンサンブル三昧となりました。
さて、サクソフォンのみならず、管楽器奏者の方なら、体験したことがあるかもしれませんが、私は時折、"鼻抜け"という現象を起こすことがあります。本来、管楽器を演奏するときは口から息をはくのですが、何故か自分の意図しない時に鼻から息が抜けてしまう現象です。どういうときに、何故起るのか詳しいことは自分自身でもわからないのですが、おそらくは鼻の奥にある、口と葉なの気道を切り替える弁のような部分が、何らかの理由でコントロールできなくなり、勝手に鼻から息が抜けてしまうようになるのだと思います。
この現象が起ると、当然口からはく息にプレスを加えられなくなりますので、楽器を吹くどころではなくなります。練習の時はまだしも、本番中にこの現象が起きるとどうしようもありません。演奏不能状態になってしまいます。
どうも体調が優れないときや、鼻炎になっているときなどは、この現象が起きやすい気がしますが、自分で予防することも出来ないので、諦めるしかない状態です。
今まで、何となくですが、カルテットのウエスト・サイドを演奏すると妙に鼻抜けを起こす確立が高いと思っているのは単に思い込みでしょうか??
まあ、実際本番で起きた時には、何とかなると思っていますが。(←絶対に鬱やパニック症候群にならない人の台詞だそうな)
そこで今日の一枚です。

バーンスタイン/ウエスト・サイド・ストーリー/
ラプソディー・イン・ブルー
指揮:レナード・バースタイン
ニューヨーク・フィル・ハーモニック(ウエスト・サイド)
コロンビア交響楽団(ラプソディ)
このCDはバーンスタインによる自作自演と、彼がピアノを弾いたガーシュウィンの曲が収録されています。すべてアメリカ音楽というくくりになるのでしょうか?
曲目は「ウエスト・サイド・ストーリー」~シンフォニック・ダンス、「キャンディード」序曲、ラプソディー・イン・ブルー、パリのアメリカ人となっています。ラプソディーイン・ブルーのみ、バーンスタインのピアノでコロンビア交響楽団の演奏です。このコロンビア響というのは私の知る限りでは、「コロンビア交響楽団」という名称は、米コロンビア(CBS)が他社との契約上正式な名称を使えない場合に使用したもので、特定のオーケストラの名称ではないようです。
この中の「ウエスト・サイド・ストーリー」~シンフォニック・ダンスは、バーンスタイン自身がオーケストラ用に編曲したものですが、どうも楽譜が2種類あるようです。私の持っているほかのバーンスタイン/ロサンゼルスフィルの演奏と比べると、明らかに、数小節分、抜けています。ロサンゼルスフィル盤のほうが後から出た楽譜で、今は、必ず、そちらのほうで演奏されているようです。このニューヨーク・フィル盤はバーンスタインがあの有名な「マンボ」の部分で、声で「マンボ!」と叫ぶ指定をしたのにもかかわらず、ニューヨーク・フィルの団員が叫ぶことを拒否し、結局録音のときには「マンボ!」が収録されていません。ボンゴのロールがむなしく聞こえています。
演奏のほうはロサンゼルス盤に比べると、上品でおとなしく、どちらかと言うとクラシック色が濃い演奏と言えるでしょうか?「キャンディード」序曲では、おそらくバーンスタインがもっとテンポを上げたくて、かなり先振りしているのにもかかわらず、楽団が付いていっていない様子が部分的に聞いて取れたりします。この時代はまだバーンスタインも分かったと言うことでしょうか?
シンフォニック・ダンスをよりクラシカルな演奏で聞きたい方、バーンスタインのピアノの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、サクソフォンのみならず、管楽器奏者の方なら、体験したことがあるかもしれませんが、私は時折、"鼻抜け"という現象を起こすことがあります。本来、管楽器を演奏するときは口から息をはくのですが、何故か自分の意図しない時に鼻から息が抜けてしまう現象です。どういうときに、何故起るのか詳しいことは自分自身でもわからないのですが、おそらくは鼻の奥にある、口と葉なの気道を切り替える弁のような部分が、何らかの理由でコントロールできなくなり、勝手に鼻から息が抜けてしまうようになるのだと思います。
この現象が起ると、当然口からはく息にプレスを加えられなくなりますので、楽器を吹くどころではなくなります。練習の時はまだしも、本番中にこの現象が起きるとどうしようもありません。演奏不能状態になってしまいます。
どうも体調が優れないときや、鼻炎になっているときなどは、この現象が起きやすい気がしますが、自分で予防することも出来ないので、諦めるしかない状態です。
今まで、何となくですが、カルテットのウエスト・サイドを演奏すると妙に鼻抜けを起こす確立が高いと思っているのは単に思い込みでしょうか??
まあ、実際本番で起きた時には、何とかなると思っていますが。(←絶対に鬱やパニック症候群にならない人の台詞だそうな)
そこで今日の一枚です。

バーンスタイン/ウエスト・サイド・ストーリー/
ラプソディー・イン・ブルー
指揮:レナード・バースタイン
ニューヨーク・フィル・ハーモニック(ウエスト・サイド)
コロンビア交響楽団(ラプソディ)
このCDはバーンスタインによる自作自演と、彼がピアノを弾いたガーシュウィンの曲が収録されています。すべてアメリカ音楽というくくりになるのでしょうか?
曲目は「ウエスト・サイド・ストーリー」~シンフォニック・ダンス、「キャンディード」序曲、ラプソディー・イン・ブルー、パリのアメリカ人となっています。ラプソディーイン・ブルーのみ、バーンスタインのピアノでコロンビア交響楽団の演奏です。このコロンビア響というのは私の知る限りでは、「コロンビア交響楽団」という名称は、米コロンビア(CBS)が他社との契約上正式な名称を使えない場合に使用したもので、特定のオーケストラの名称ではないようです。
この中の「ウエスト・サイド・ストーリー」~シンフォニック・ダンスは、バーンスタイン自身がオーケストラ用に編曲したものですが、どうも楽譜が2種類あるようです。私の持っているほかのバーンスタイン/ロサンゼルスフィルの演奏と比べると、明らかに、数小節分、抜けています。ロサンゼルスフィル盤のほうが後から出た楽譜で、今は、必ず、そちらのほうで演奏されているようです。このニューヨーク・フィル盤はバーンスタインがあの有名な「マンボ」の部分で、声で「マンボ!」と叫ぶ指定をしたのにもかかわらず、ニューヨーク・フィルの団員が叫ぶことを拒否し、結局録音のときには「マンボ!」が収録されていません。ボンゴのロールがむなしく聞こえています。
演奏のほうはロサンゼルス盤に比べると、上品でおとなしく、どちらかと言うとクラシック色が濃い演奏と言えるでしょうか?「キャンディード」序曲では、おそらくバーンスタインがもっとテンポを上げたくて、かなり先振りしているのにもかかわらず、楽団が付いていっていない様子が部分的に聞いて取れたりします。この時代はまだバーンスタインも分かったと言うことでしょうか?
シンフォニック・ダンスをよりクラシカルな演奏で聞きたい方、バーンスタインのピアノの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月22日
今回もレコードです。
さて、この飛び石連休、先日の土曜日が出勤だったため月曜を代休にして、飛び石ではなく三連休となりました。この三連休もサックスアンサンブル三昧となっています。
ところで、以前にも書いたことがありますが、現在私はLPレコードが再生できる環境を持っていません。レコードを聴こうとすると、レコードプレーヤー、トーンアーム、カートリッジ、針、フォノイコライザー、と言ったものが必要になるかと思います。実はレコードプレーヤーにつけるカートリッジには大きく分けてMM式のものと、MC式のものがあり、それに応じて、フォノイコライザーや、昇圧トランスと言ったものが必要になってきます。こうやって色々な道具や組み合わせを楽しめるところにも、レコードプレーヤー再生の趣味性の高さがうかがえると思います。CDプレーヤーなら、ディスクをセットして再生するだけですが、レコードの場合は、まず、レコード盤をクリーニングし、プレーヤーにセットして針を落とす、という儀式のような所作が必要になります。懐かしき時代の産物なのかもしれませんが…。
そこで今日の一枚です。

↑
これは再販されたCDのジャケットです。
ホルスト/組曲「惑星」、作品32
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
LONDON SLC8013
これはCDではなくLPレコードです。おそらく、日本では平原綾香の「ジュピター」の影響で「惑星」の人気が再燃したのだと思いますが、1960年代から1970年代にかけて、世界的にこの「惑星」のブームがあったようでこの時代様々な楽団、指揮者による録音がなされているようです。そのブームの火付け役のひとつにもなったのが、このカラヤン/ウィーン・フィルの「惑星」です。そういった意味ではある意味この「惑星」を世界的にメジャーな曲に押し上げた歴史的録音ともいえるのかもしれません。
さて、演奏は後に録音されたベルリン・フィルのものとは比べ物にならないぐらい速いテンポと本当にカラヤンか?と思うような曲の解釈が伺えます。想像するにカラヤン自身、この録音がこんなにも多くの人に聞かれるものになるとは思っていなかったのかもしれません。
この一曲目の「火星」は「戦争の神」とされ、五拍子で、弦楽器のコル・レーニョによって奏されています。まさにこれから戦いに向かうような雰囲気を持った曲です。バトルの前に聞くと気分が高揚するかもしれません。ただ、カラヤンのこの録音のリズムはなぜか少し変ですし、管楽器全般のバランスが非常に悪い気もします。最もこの時期この「惑星」がバレエに使用されていたようで、それを意識した演奏になっているのかもしれません。
ただ、後年のカラヤンにはあまり感じられなくなった力技と言うか、疾走感が存分に楽しめます。また、バイオリンのソロなどは豊麗で実に美しいものになっています。
ブームの火付け役となった「惑星」、少しバレエ的な「惑星」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
ところで、以前にも書いたことがありますが、現在私はLPレコードが再生できる環境を持っていません。レコードを聴こうとすると、レコードプレーヤー、トーンアーム、カートリッジ、針、フォノイコライザー、と言ったものが必要になるかと思います。実はレコードプレーヤーにつけるカートリッジには大きく分けてMM式のものと、MC式のものがあり、それに応じて、フォノイコライザーや、昇圧トランスと言ったものが必要になってきます。こうやって色々な道具や組み合わせを楽しめるところにも、レコードプレーヤー再生の趣味性の高さがうかがえると思います。CDプレーヤーなら、ディスクをセットして再生するだけですが、レコードの場合は、まず、レコード盤をクリーニングし、プレーヤーにセットして針を落とす、という儀式のような所作が必要になります。懐かしき時代の産物なのかもしれませんが…。
そこで今日の一枚です。

↑
これは再販されたCDのジャケットです。
ホルスト/組曲「惑星」、作品32
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
LONDON SLC8013
これはCDではなくLPレコードです。おそらく、日本では平原綾香の「ジュピター」の影響で「惑星」の人気が再燃したのだと思いますが、1960年代から1970年代にかけて、世界的にこの「惑星」のブームがあったようでこの時代様々な楽団、指揮者による録音がなされているようです。そのブームの火付け役のひとつにもなったのが、このカラヤン/ウィーン・フィルの「惑星」です。そういった意味ではある意味この「惑星」を世界的にメジャーな曲に押し上げた歴史的録音ともいえるのかもしれません。
さて、演奏は後に録音されたベルリン・フィルのものとは比べ物にならないぐらい速いテンポと本当にカラヤンか?と思うような曲の解釈が伺えます。想像するにカラヤン自身、この録音がこんなにも多くの人に聞かれるものになるとは思っていなかったのかもしれません。
この一曲目の「火星」は「戦争の神」とされ、五拍子で、弦楽器のコル・レーニョによって奏されています。まさにこれから戦いに向かうような雰囲気を持った曲です。バトルの前に聞くと気分が高揚するかもしれません。ただ、カラヤンのこの録音のリズムはなぜか少し変ですし、管楽器全般のバランスが非常に悪い気もします。最もこの時期この「惑星」がバレエに使用されていたようで、それを意識した演奏になっているのかもしれません。
ただ、後年のカラヤンにはあまり感じられなくなった力技と言うか、疾走感が存分に楽しめます。また、バイオリンのソロなどは豊麗で実に美しいものになっています。
ブームの火付け役となった「惑星」、少しバレエ的な「惑星」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月21日
時代を感じる。
台風が思ったより雨をもたらしてくれなかったのが気がかりです。近隣に被害がなかったのがせめてもの救いですが…。
さて、私の両親(元は祖父母)は小さなタバコ屋を経営していました。煙草や駄菓子、日用品などを少し売っていた、小さな町のたばこ屋です。コンビニエンスストアの乱立等もあって店は閉めてしまいましたが…。 昔は、そこかしこに駄菓子屋さんがあったり、丸い円筒形のポストの立った角の小さなタバコやさんが良く見られていましたが、最近はやたらに明るくて清潔そうなコンビニエンスストアばかりが目立つようになってきています。ちょっと寂しい気もしますが…。
そこで今日の一枚です。

私の声が聞こえますか/中島みゆき
ヤマハミュージック YCCW-00004
このCDは中島みゆきのファーストアルバム。CDの最終トラックには数年前、年賀状のCMでも流れていた「時代」が収録されています。もちろん、リリース当時はCDではなくアナログのLPレコードでしたが、私はLP盤のほうは持っていません。
中島みゆきと言うと、最近なら「地上の星」などが思い浮かぶ人も多いようですが、最近のように野太く歌い上げる、というイメージとは違って、もっと柔らかで静かな曲がこの当時は多かったように思います。ヤマハのポプコン出身者です。そう考えると、円広志などとも、スタートは同じなのでしょうか?
曲目は、あぶな坂、あたしのやさしい人、信じられない頃に、ボギーボビーの赤いバラ、海よ、アザミ嬢のララバイ、踊り明かそう、ひとり遊び、悲しいことはいつもある、歌をあなたに、渚便り、時代となっていますが、私のオススメはやはり、時代です。
少し昔に浸りたい方、「地上の星」を聞いて、中島みゆきの曲を聴いてみたいと思った方にオススメの一枚です。
さて、私の両親(元は祖父母)は小さなタバコ屋を経営していました。煙草や駄菓子、日用品などを少し売っていた、小さな町のたばこ屋です。コンビニエンスストアの乱立等もあって店は閉めてしまいましたが…。 昔は、そこかしこに駄菓子屋さんがあったり、丸い円筒形のポストの立った角の小さなタバコやさんが良く見られていましたが、最近はやたらに明るくて清潔そうなコンビニエンスストアばかりが目立つようになってきています。ちょっと寂しい気もしますが…。
そこで今日の一枚です。

私の声が聞こえますか/中島みゆき
ヤマハミュージック YCCW-00004
このCDは中島みゆきのファーストアルバム。CDの最終トラックには数年前、年賀状のCMでも流れていた「時代」が収録されています。もちろん、リリース当時はCDではなくアナログのLPレコードでしたが、私はLP盤のほうは持っていません。
中島みゆきと言うと、最近なら「地上の星」などが思い浮かぶ人も多いようですが、最近のように野太く歌い上げる、というイメージとは違って、もっと柔らかで静かな曲がこの当時は多かったように思います。ヤマハのポプコン出身者です。そう考えると、円広志などとも、スタートは同じなのでしょうか?
曲目は、あぶな坂、あたしのやさしい人、信じられない頃に、ボギーボビーの赤いバラ、海よ、アザミ嬢のララバイ、踊り明かそう、ひとり遊び、悲しいことはいつもある、歌をあなたに、渚便り、時代となっていますが、私のオススメはやはり、時代です。
少し昔に浸りたい方、「地上の星」を聞いて、中島みゆきの曲を聴いてみたいと思った方にオススメの一枚です。
2008年09月20日
力強さ。
最近、疲れが溜まっています。
残業続きの上に、いつまでたっても終わらない仕事をしている気分になっています。私は体力があるほうでもないので、少しずつ、溜まった疲れがいつの間にか大きな疲れとなって押し寄せてきます。
連休に休めばいいのですが、この時期、サクソフォンアンサンブルコンサートを始め、演奏会や演奏以来が目白押し。練習も含めると、休む暇もなくやってくる感覚です。ヒマをもてあましてボーっとしているのもどうかとは思いますので、色々やることがあるほうがいいのでしょうが、疲れが溜まり続けるのも問題かもしれません。
もっと人生に迫力が欲しい気もします。何が足りないのかもわかりませんが…。
まずは、体力的な力強さが足りないのかもしれません。精神、肉体ともに脆弱です。 そこで今日の一枚です。

マーラー/交響曲第5番
指揮:クリスト・フォン・ドホナーニ
クリーヴランド管弦楽団
LONDON(ポリドール) POCL-2768
このCDはドホナーニ/クリーヴランドによる俗に言う「マラ五」です。ほかの方はどうかわかりませんが、私はこの2楽章の冒頭を聞くとふつふつとこみ上げてくる怒りの感覚を思い出したりするのですが、いかがでしょう。終楽章は牧歌的に始まり、最後は喜びの中で曲は終わっていきます。感情を爆発させたような曲はオーケストラにとってもかなり体力を消耗する曲のようです。
この曲はマーラーが最も充実していた時代の作品だけに楽曲的にも充実していて、マーラーの作品の中でも人気のある曲のようです。冒頭のトランペットのソロは、あたかもメンデルスゾーンの「結婚行進曲」を思わせるリズムと音(途中までは全く同じリズムと音程です)から、いきなりマイナーコードの旋律へと向かっていて、苦悩と混迷を感じるものとなっています。
それにしてもマーラーの交響曲はベートーヴェン以上に、人間臭さというか、人間の感情がこめられた曲のような気がします。指揮者としてのマーラーも有名だったようで、今の様に、全身を使って情感豊かな指揮を最初にし始めたのもマーラーだったと言われています。それまでの指揮はどちらかというとテンポキーパー的な意味合いが強く、指揮者が体を大きく動かすことは無かったようです。しかし、今の指揮者はマーラーの指揮法に少なからぬ影響を受けていると言えます。ひとつにはマーラーの書いた曲は巨大な編成のものが多く、体を大きく使う必要が生じたと言うこともありますが、指揮者の曲に対する感情を体で表現する、という指揮者として今は常識的な行為もマーラーがいなければ、許されていなかったのかもしれません。
ドホナーニ/クリーヴランドの演奏はどちらかと言うと感情に溺れることなくクールです。クリーヴランド管弦楽団のクリアーな音色とあいまってさらにスマートな演奏になっていますが、聴きかたによっては、マーラーらしからぬさめた演奏と感じないでもありません。しかし、抑制された感情表現が音楽には必要なのだとすると、まさに正しいアプローチなのではないかと思います。
交響曲で全身で様々な感情を体験してみたい方、マーラーの交響曲を聞いてみたいと思う方の入門にオススメの一枚です。
残業続きの上に、いつまでたっても終わらない仕事をしている気分になっています。私は体力があるほうでもないので、少しずつ、溜まった疲れがいつの間にか大きな疲れとなって押し寄せてきます。
連休に休めばいいのですが、この時期、サクソフォンアンサンブルコンサートを始め、演奏会や演奏以来が目白押し。練習も含めると、休む暇もなくやってくる感覚です。ヒマをもてあましてボーっとしているのもどうかとは思いますので、色々やることがあるほうがいいのでしょうが、疲れが溜まり続けるのも問題かもしれません。
もっと人生に迫力が欲しい気もします。何が足りないのかもわかりませんが…。
まずは、体力的な力強さが足りないのかもしれません。精神、肉体ともに脆弱です。 そこで今日の一枚です。
マーラー/交響曲第5番
指揮:クリスト・フォン・ドホナーニ
クリーヴランド管弦楽団
LONDON(ポリドール) POCL-2768
このCDはドホナーニ/クリーヴランドによる俗に言う「マラ五」です。ほかの方はどうかわかりませんが、私はこの2楽章の冒頭を聞くとふつふつとこみ上げてくる怒りの感覚を思い出したりするのですが、いかがでしょう。終楽章は牧歌的に始まり、最後は喜びの中で曲は終わっていきます。感情を爆発させたような曲はオーケストラにとってもかなり体力を消耗する曲のようです。
この曲はマーラーが最も充実していた時代の作品だけに楽曲的にも充実していて、マーラーの作品の中でも人気のある曲のようです。冒頭のトランペットのソロは、あたかもメンデルスゾーンの「結婚行進曲」を思わせるリズムと音(途中までは全く同じリズムと音程です)から、いきなりマイナーコードの旋律へと向かっていて、苦悩と混迷を感じるものとなっています。
それにしてもマーラーの交響曲はベートーヴェン以上に、人間臭さというか、人間の感情がこめられた曲のような気がします。指揮者としてのマーラーも有名だったようで、今の様に、全身を使って情感豊かな指揮を最初にし始めたのもマーラーだったと言われています。それまでの指揮はどちらかというとテンポキーパー的な意味合いが強く、指揮者が体を大きく動かすことは無かったようです。しかし、今の指揮者はマーラーの指揮法に少なからぬ影響を受けていると言えます。ひとつにはマーラーの書いた曲は巨大な編成のものが多く、体を大きく使う必要が生じたと言うこともありますが、指揮者の曲に対する感情を体で表現する、という指揮者として今は常識的な行為もマーラーがいなければ、許されていなかったのかもしれません。
ドホナーニ/クリーヴランドの演奏はどちらかと言うと感情に溺れることなくクールです。クリーヴランド管弦楽団のクリアーな音色とあいまってさらにスマートな演奏になっていますが、聴きかたによっては、マーラーらしからぬさめた演奏と感じないでもありません。しかし、抑制された感情表現が音楽には必要なのだとすると、まさに正しいアプローチなのではないかと思います。
交響曲で全身で様々な感情を体験してみたい方、マーラーの交響曲を聞いてみたいと思う方の入門にオススメの一枚です。
2008年09月19日
凹む、盗難。
今日は午後から小雨がぱらつくお天気となりました。台風が近づいていますが、水不足解消の決定打になるのかどうか…。
さて、以前のこと。楽器を吹く人にとってはちょっと凹む話を聞いたことをふと思い出しました。仔細までは聞いていないので、細かいことはかけないのですが、我々の吹奏楽団の団員の一人が楽器の盗難にあったということでした。中学生時代から使っていた長い付き合いの楽器だったようで、かなり年代ものにはなっていますがそれ以上に苦楽を共にした自分の楽器です。盗難にあった本人とはまだ直接話していないのですが、かなりへこんでいることは間違いないのでは無いかと思います。次回会ったときに声のかけようも無く、いま、どうしようかと思っています。
盗難ということなのですが、正確に言うと、車上荒らしのようです。香川県でも、最近、いろいろな場所で、車上荒らしがはやっているらしく注意が必要なようです。聞いたところによると、小学校の体育館の下にある駐車場でも車上荒らしが出て、注意を呼びかけているとか。恐ろしい話です。
楽器は、盗難に合うと、まずすぐには戻ってきません。大抵は質屋、中古や、場合によってはハード・○フのようなリサイクルショップに売られることがあるようです。今回の楽器は、オーボエでサックスではなかったのですが、ダッパーサクセーバーズの某氏も以前アルトサックスを盗られて、いまだに帰ってきていません。もう20年ぐらい前の話ですが。
盗難に遭った楽器が、もし、中古やさんや、リサイクルショップで売られているのを見つけても、普通に返してもらうことはできないようです。買い取った業者は盗難の事実を知らない場合は、善意の第三者として扱われ、自分が盗られた楽器でも、自分で買い戻すことになるそうです。大抵は業者のほうも心得ていて、金額を折半してくれることもあるようですが、いずれにせよ、自分のものにもかかわらず、買い戻す、という奇妙な現象が起きます。
それと、楽器は盗難に遭う前に製造番号、メーカーなどを控えておく必要があります。これが判らないと、発見されても、自分の楽器だと立証することができなくなるので、手元に返してもらえなくなることがあるようです。
しかし、盗難は許せません。盗難で、実は価値ある楽器を二束三文で売り払われて、その金で遊びほうけているやつがいるかと思うと腹が立ってきます。
しかし、盗られた本人はものすごく凹んでいることが想像できます。見つかる確立は低いとはいえ、早く見つかることを祈るばかりです。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/祝典序曲「1812年」
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL 5014
このCDはデュトワ/モントリオールによる、チャイコフスキーの作品集のようなものです。
曲目は、序曲「1812年」、イタリア奇想曲、バレエ組曲「くるみ割り人形」、スラブ行進曲、となっています。この中のイタリア奇想曲ですが、実は、鬱傾向にあった、チャイコフスキーの心情をよく表現しているとも言われています。同性愛者だったにもかかわらず、それをひた隠しにし、女性と結婚までしたチャイコフスキーですが、その不幸な結婚と、生来の多感で傷つきやすい正確のため、かなりの躁鬱傾向を示すようになります。1880年代後半まで、妻から逃げてるように、うつ病の治療をしながら、イタリアで、かなり長期の滞在をした彼が、その時に作曲した曲とされています。元々、奇想曲とは、イタリア語のカプリッチオ、「(形式にとらわれず)気ままに」という意味から生じたもので、その意味の成すとおり、音楽形式上での意味も、愉快で気まぐれな小曲やそれらをつなぎ合わせたものという意味合いで使われています。オーケストラを対象とした大規模な管弦楽曲で、「奇想曲」の名にふさわしく、愉快で気まぐれな旋律がちりばめられいるのですが、その合間合間に覗かせるマイナーコードの旋律が、まるで躁鬱を繰り返しているチャイコフスキーの心情のようだ、というのです。不幸な結婚と、社会的な苦悩でかなり凹んでいたチャイコフスキーの姿が想像できます。
とはいえ、勇壮なファンファーレとイタリアの民謡風舞曲を元にした4つの旋律で構成されていて、全体を通して、明るく陽気な部分が始終顔を覗かせ、最後は華やかで明るく幕を閉じます。
デュトワ/モントリオールの演奏は、色彩感豊かで、繊細と言ったイメージでしょうか。ただ、「1812年」のほうは、シンセサイザーが使われており、その使い方に「??」を感じる部分が少し残念です。
チャイコフスキーの管弦楽作品を聞いてみたい方に、また、何かに落ち込んで凹んでいる方にオススメの一枚です。
さて、以前のこと。楽器を吹く人にとってはちょっと凹む話を聞いたことをふと思い出しました。仔細までは聞いていないので、細かいことはかけないのですが、我々の吹奏楽団の団員の一人が楽器の盗難にあったということでした。中学生時代から使っていた長い付き合いの楽器だったようで、かなり年代ものにはなっていますがそれ以上に苦楽を共にした自分の楽器です。盗難にあった本人とはまだ直接話していないのですが、かなりへこんでいることは間違いないのでは無いかと思います。次回会ったときに声のかけようも無く、いま、どうしようかと思っています。
盗難ということなのですが、正確に言うと、車上荒らしのようです。香川県でも、最近、いろいろな場所で、車上荒らしがはやっているらしく注意が必要なようです。聞いたところによると、小学校の体育館の下にある駐車場でも車上荒らしが出て、注意を呼びかけているとか。恐ろしい話です。
楽器は、盗難に合うと、まずすぐには戻ってきません。大抵は質屋、中古や、場合によってはハード・○フのようなリサイクルショップに売られることがあるようです。今回の楽器は、オーボエでサックスではなかったのですが、ダッパーサクセーバーズの某氏も以前アルトサックスを盗られて、いまだに帰ってきていません。もう20年ぐらい前の話ですが。
盗難に遭った楽器が、もし、中古やさんや、リサイクルショップで売られているのを見つけても、普通に返してもらうことはできないようです。買い取った業者は盗難の事実を知らない場合は、善意の第三者として扱われ、自分が盗られた楽器でも、自分で買い戻すことになるそうです。大抵は業者のほうも心得ていて、金額を折半してくれることもあるようですが、いずれにせよ、自分のものにもかかわらず、買い戻す、という奇妙な現象が起きます。
それと、楽器は盗難に遭う前に製造番号、メーカーなどを控えておく必要があります。これが判らないと、発見されても、自分の楽器だと立証することができなくなるので、手元に返してもらえなくなることがあるようです。
しかし、盗難は許せません。盗難で、実は価値ある楽器を二束三文で売り払われて、その金で遊びほうけているやつがいるかと思うと腹が立ってきます。
しかし、盗られた本人はものすごく凹んでいることが想像できます。見つかる確立は低いとはいえ、早く見つかることを祈るばかりです。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/祝典序曲「1812年」
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL 5014
このCDはデュトワ/モントリオールによる、チャイコフスキーの作品集のようなものです。
曲目は、序曲「1812年」、イタリア奇想曲、バレエ組曲「くるみ割り人形」、スラブ行進曲、となっています。この中のイタリア奇想曲ですが、実は、鬱傾向にあった、チャイコフスキーの心情をよく表現しているとも言われています。同性愛者だったにもかかわらず、それをひた隠しにし、女性と結婚までしたチャイコフスキーですが、その不幸な結婚と、生来の多感で傷つきやすい正確のため、かなりの躁鬱傾向を示すようになります。1880年代後半まで、妻から逃げてるように、うつ病の治療をしながら、イタリアで、かなり長期の滞在をした彼が、その時に作曲した曲とされています。元々、奇想曲とは、イタリア語のカプリッチオ、「(形式にとらわれず)気ままに」という意味から生じたもので、その意味の成すとおり、音楽形式上での意味も、愉快で気まぐれな小曲やそれらをつなぎ合わせたものという意味合いで使われています。オーケストラを対象とした大規模な管弦楽曲で、「奇想曲」の名にふさわしく、愉快で気まぐれな旋律がちりばめられいるのですが、その合間合間に覗かせるマイナーコードの旋律が、まるで躁鬱を繰り返しているチャイコフスキーの心情のようだ、というのです。不幸な結婚と、社会的な苦悩でかなり凹んでいたチャイコフスキーの姿が想像できます。
とはいえ、勇壮なファンファーレとイタリアの民謡風舞曲を元にした4つの旋律で構成されていて、全体を通して、明るく陽気な部分が始終顔を覗かせ、最後は華やかで明るく幕を閉じます。
デュトワ/モントリオールの演奏は、色彩感豊かで、繊細と言ったイメージでしょうか。ただ、「1812年」のほうは、シンセサイザーが使われており、その使い方に「??」を感じる部分が少し残念です。
チャイコフスキーの管弦楽作品を聞いてみたい方に、また、何かに落ち込んで凹んでいる方にオススメの一枚です。
2008年09月18日
見える?見えない。
今日は少し曇り空。少しずつ天気も悪くなっているようですが、雨は降らないようです。台風が徐々に近づきつつあります。
さて、先日ちょっとあることで簡単に視力を測ったのですが、メガネをかけた左目の矯正視力がなんと0.6しかありませんでした。わずか半年ぐらい前には0.9ぐらいあったのに…。そういえば、最近、深夜まで目を酷使していたのも確かです。メガネを変えるか、視力を回復させるかしか方法が無いのですが、メガネを変えるとお金はかかるは、今の視力のままで固定されてしまいそうになるわで、あまりよくないので、一応、疲れを取って、視力の回復をはかってみることにします。でも、そんなに日常で不自由していないので、見えると思っていたのですが、実際、計測してみると、見えないんでしょうね。視力を矯正するときに、きっちり見えてしまうと、目が疲れるので、できるだけ弱めに強制しているのですが、それでも、片目1.0ぐらいには強制しているのですが…。先日、スイミングゴーグルを探したときも、今のメガネよりは度数が弱いものを選んで、よく見えていたのですが…。まあ、大型だけに視力に加えて深視力と言うのも計測されることになるので、視力は回復させておかなければなりません。
でも、視力がすぐに回復するわけでもないので、最終的に視力が足りないようであれば、やっぱり、メガネのレンズ交換をするしかありません。体調によっても、見える、見えないがあるようですが、体調がいつもいいとは限らないので、最後は物に頼るしかないのでしょうが。
見える、見えない、視力が微妙なところなのです。
そこで今日の一枚です。

ドビュッシー/管弦楽曲集
指揮:ジャン・マルティノン
フランス国立放送管弦楽団及び合唱団
エンジェル(東芝EMI) TOCE-7037
このCDはマルティノンによるドビュッシーの管弦楽作品集です。録音年代は1970年代の前半なのですが、総合的にきっちりとまとめられた見通しのよい演奏になっています。批判的に書けば、冒険した部分の少ない演奏ともいえますが、そのきっちりとした堅実な演奏は今聞いても色あせることなく、ドビュッシーの独特の世界をよく描き出しているような気がします。
曲目は、夜想曲、交響詩「海」三つの交響的素描(スケッチ)、牧神の午後への前奏曲、「小組曲」より「小舟にて」、神聖な舞曲と世俗的な舞曲、スコットランド風行進曲となっています。さて、フランスの同じ指揮者にアンドレ・クリュイタンスがいますが、マルティノンは同じフランスの指揮者ですが、クリュイタンスのような妖艶さ、なまめかしさのようなものはあまり無いものの、精緻な演奏で、印象派の音楽を描き出そうとしている骨組みのしっかりとした演奏になっています。
ドビュッシーの管弦楽作品を聞いてみたい方、マルティノンの音楽を聴いてみたい方にオススメです。さて、「海」を聞いて、皆さんにはあの葛飾北斎の浮世絵のような海の荒々しさや、波の景色が見えるでしょうか?
さて、先日ちょっとあることで簡単に視力を測ったのですが、メガネをかけた左目の矯正視力がなんと0.6しかありませんでした。わずか半年ぐらい前には0.9ぐらいあったのに…。そういえば、最近、深夜まで目を酷使していたのも確かです。メガネを変えるか、視力を回復させるかしか方法が無いのですが、メガネを変えるとお金はかかるは、今の視力のままで固定されてしまいそうになるわで、あまりよくないので、一応、疲れを取って、視力の回復をはかってみることにします。でも、そんなに日常で不自由していないので、見えると思っていたのですが、実際、計測してみると、見えないんでしょうね。視力を矯正するときに、きっちり見えてしまうと、目が疲れるので、できるだけ弱めに強制しているのですが、それでも、片目1.0ぐらいには強制しているのですが…。先日、スイミングゴーグルを探したときも、今のメガネよりは度数が弱いものを選んで、よく見えていたのですが…。まあ、大型だけに視力に加えて深視力と言うのも計測されることになるので、視力は回復させておかなければなりません。
でも、視力がすぐに回復するわけでもないので、最終的に視力が足りないようであれば、やっぱり、メガネのレンズ交換をするしかありません。体調によっても、見える、見えないがあるようですが、体調がいつもいいとは限らないので、最後は物に頼るしかないのでしょうが。
見える、見えない、視力が微妙なところなのです。
そこで今日の一枚です。
ドビュッシー/管弦楽曲集
指揮:ジャン・マルティノン
フランス国立放送管弦楽団及び合唱団
エンジェル(東芝EMI) TOCE-7037
このCDはマルティノンによるドビュッシーの管弦楽作品集です。録音年代は1970年代の前半なのですが、総合的にきっちりとまとめられた見通しのよい演奏になっています。批判的に書けば、冒険した部分の少ない演奏ともいえますが、そのきっちりとした堅実な演奏は今聞いても色あせることなく、ドビュッシーの独特の世界をよく描き出しているような気がします。
曲目は、夜想曲、交響詩「海」三つの交響的素描(スケッチ)、牧神の午後への前奏曲、「小組曲」より「小舟にて」、神聖な舞曲と世俗的な舞曲、スコットランド風行進曲となっています。さて、フランスの同じ指揮者にアンドレ・クリュイタンスがいますが、マルティノンは同じフランスの指揮者ですが、クリュイタンスのような妖艶さ、なまめかしさのようなものはあまり無いものの、精緻な演奏で、印象派の音楽を描き出そうとしている骨組みのしっかりとした演奏になっています。
ドビュッシーの管弦楽作品を聞いてみたい方、マルティノンの音楽を聴いてみたい方にオススメです。さて、「海」を聞いて、皆さんにはあの葛飾北斎の浮世絵のような海の荒々しさや、波の景色が見えるでしょうか?
2008年09月17日
旅行、鞄の中身。
雨が降るにもかかわらず、水不足が続いています。
さて、今度11月に社員旅行に出かけることになりました。
私はまったくと言っていいほど旅慣れていないので、いつも荷物を持って行き過ぎる傾向にあります。 もともと旅行鞄もそんなにきちんとしたものをもっておらず、以前新潟にスクーリングに行く時にキャスターつきのバッグをはじめて買いました。 なにはともあれ、予算はそんなに無いので、ありあわせの鞄に荷物を詰め込んでいくことになるとは思いますが…。、 私は海外旅行の経験も無いので、一回は行ってみたいのですが、持病のために、やっておかなければならないことがあって、それも面倒だし、英語がからっきし駄目なので、海外に行くのを躊躇しています。パスポートも当然持っていません。
そこで今日の一枚です。

アルビノーニのアダージョ
ミュンヒンガー/バロック音楽の楽しみ
カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団
KICC8214
このCDは、カール・ミュンヒンガー指揮のシュトゥットガルト室内管弦楽団によるバロックの曲集。パッヘルベルのカノンとジーグをはじめ、アルビノーニのアダージョ、バッハの曲など、有名どころが吸う曲収録されています。ミュンヒンガーといえばバロック、といえるぐらい有名ですが、何故かバロック音楽、小品が多いからか、何故だかわかりませんが、オケの場合、オムニバスのCDが多いような気がします。まあ、商業的な視点から見ると、やはり売れる企画を考えないといけないので、有名どころのバロック音楽を人くくりにしているのだとは思いますが。まさに詰め込んだ感じの出来上がりになることが多い気がします。
バロックの入門用としてオススメの一枚です。
さて、今度11月に社員旅行に出かけることになりました。
私はまったくと言っていいほど旅慣れていないので、いつも荷物を持って行き過ぎる傾向にあります。 もともと旅行鞄もそんなにきちんとしたものをもっておらず、以前新潟にスクーリングに行く時にキャスターつきのバッグをはじめて買いました。 なにはともあれ、予算はそんなに無いので、ありあわせの鞄に荷物を詰め込んでいくことになるとは思いますが…。、 私は海外旅行の経験も無いので、一回は行ってみたいのですが、持病のために、やっておかなければならないことがあって、それも面倒だし、英語がからっきし駄目なので、海外に行くのを躊躇しています。パスポートも当然持っていません。
そこで今日の一枚です。
アルビノーニのアダージョ
ミュンヒンガー/バロック音楽の楽しみ
カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団
KICC8214
このCDは、カール・ミュンヒンガー指揮のシュトゥットガルト室内管弦楽団によるバロックの曲集。パッヘルベルのカノンとジーグをはじめ、アルビノーニのアダージョ、バッハの曲など、有名どころが吸う曲収録されています。ミュンヒンガーといえばバロック、といえるぐらい有名ですが、何故かバロック音楽、小品が多いからか、何故だかわかりませんが、オケの場合、オムニバスのCDが多いような気がします。まあ、商業的な視点から見ると、やはり売れる企画を考えないといけないので、有名どころのバロック音楽を人くくりにしているのだとは思いますが。まさに詰め込んだ感じの出来上がりになることが多い気がします。
バロックの入門用としてオススメの一枚です。
2008年09月16日
からっと。
ここ数日、日中は暑さがあるものの陽が落ちると少し涼しくなってきました。雨さえ降らなければ、日中も八月に比べると、湿度が下がり、からっとした感じになっています。
さて、私は以前、普段は図書館通いをしていたのですが、市立の図書館が文書整理という訳のわからない作業のために、1週間もお休みすることがありました。その時は県立図書館に通っていました。市立図書館は自転車で楽に行ける距離なのですが、県立図書館はさすがに少し遠く、車で行ったりしていました。何度か自転車で行きましたが、結構時間を食ってしまいます。せっかくこの天気なので、自転車で走ったほうが気持ちよいとは思うのですが、体力と時間の節約のために、ガソリン代を使っていました。
夏の暑さが苦手な私にとっては、この時期が待ち遠しくてたまりませんでした。ただし、アレルギーっぽい体質で、呼吸器の弱い私は、逆にこの時期になると鼻炎の再発におびえることになります。春と同じように季節の変わり目は体調を崩しやすいのですが、それに加えて、夏の暑さでバテた体には、この急激な気候の変化は厳しきものがあるのかもしれません。特に体の弱っている高齢の方などは要注意です。
でも、からっとした、この晴れの日に、サイクリングに行ったり、公園で寝転んだり、キャンプに行ったりしたいものですね。予算も時間も不足している私なのですが。
からっとした天気になって気持ちが晴れることだけでも満喫したいと思います。
さて、そこで今日の一枚です。

マンボ天国
東京パノラマ マンボ ボーイズ
テイチク TECN-30093
このCDは「平成に甦る昭和マンボ野郎!」こと東京パノラママンボボーイズのデビューアルバムです。この東京パノラママンボボーイズ、残念ながら、1993年に解散してしまいました。
曲はマンボ・ボンド、マンボのビート、スピーク・アップ・マンボ、マンボ・マニア、ワン・レイニーナイト・イン東京、グリーン・オニオン、ヒット・ザ・ボンゴ、チャ・チャ・チック、パチンコ、赤坂の夜は更けて、ピーター・ガン、ザ・グース、夏の夜のサンバ、コーヒー・ルンバ、マンボ・メドレー:マンボ~エル・マンボ~マンボ第8番~南京豆売り~セレソ・ローサ~ティコ・ティコ、コセ・コセ・コセ、大学マンボ、パトリシア、ネグラ・ミ・チャチャチャ、タブー、キー・ハンター(非情のライセンス)、サーフ・バード、太陽の彼方に、ボンゴ天国、ティン・ティン・ディオ
となっています。マンボ以外の曲からのアレンジも含まれていますが、まさに、昭和30年代を髣髴とさせるような曲の数々です。
演奏のほうもトランペットのエリック・宮城をはじめとした名だたるミュージシャンが参加していて、かなりクオリティの高いものになっています。
からっとしたこの時期ノリノリのマンボを聴いてみたい方、昭和30年代の高級クラブに思いを馳せたい方にオススメの一枚です。
さて、私は以前、普段は図書館通いをしていたのですが、市立の図書館が文書整理という訳のわからない作業のために、1週間もお休みすることがありました。その時は県立図書館に通っていました。市立図書館は自転車で楽に行ける距離なのですが、県立図書館はさすがに少し遠く、車で行ったりしていました。何度か自転車で行きましたが、結構時間を食ってしまいます。せっかくこの天気なので、自転車で走ったほうが気持ちよいとは思うのですが、体力と時間の節約のために、ガソリン代を使っていました。
夏の暑さが苦手な私にとっては、この時期が待ち遠しくてたまりませんでした。ただし、アレルギーっぽい体質で、呼吸器の弱い私は、逆にこの時期になると鼻炎の再発におびえることになります。春と同じように季節の変わり目は体調を崩しやすいのですが、それに加えて、夏の暑さでバテた体には、この急激な気候の変化は厳しきものがあるのかもしれません。特に体の弱っている高齢の方などは要注意です。
でも、からっとした、この晴れの日に、サイクリングに行ったり、公園で寝転んだり、キャンプに行ったりしたいものですね。予算も時間も不足している私なのですが。
からっとした天気になって気持ちが晴れることだけでも満喫したいと思います。
さて、そこで今日の一枚です。

マンボ天国
東京パノラマ マンボ ボーイズ
テイチク TECN-30093
このCDは「平成に甦る昭和マンボ野郎!」こと東京パノラママンボボーイズのデビューアルバムです。この東京パノラママンボボーイズ、残念ながら、1993年に解散してしまいました。
曲はマンボ・ボンド、マンボのビート、スピーク・アップ・マンボ、マンボ・マニア、ワン・レイニーナイト・イン東京、グリーン・オニオン、ヒット・ザ・ボンゴ、チャ・チャ・チック、パチンコ、赤坂の夜は更けて、ピーター・ガン、ザ・グース、夏の夜のサンバ、コーヒー・ルンバ、マンボ・メドレー:マンボ~エル・マンボ~マンボ第8番~南京豆売り~セレソ・ローサ~ティコ・ティコ、コセ・コセ・コセ、大学マンボ、パトリシア、ネグラ・ミ・チャチャチャ、タブー、キー・ハンター(非情のライセンス)、サーフ・バード、太陽の彼方に、ボンゴ天国、ティン・ティン・ディオ
となっています。マンボ以外の曲からのアレンジも含まれていますが、まさに、昭和30年代を髣髴とさせるような曲の数々です。
演奏のほうもトランペットのエリック・宮城をはじめとした名だたるミュージシャンが参加していて、かなりクオリティの高いものになっています。
からっとしたこの時期ノリノリのマンボを聴いてみたい方、昭和30年代の高級クラブに思いを馳せたい方にオススメの一枚です。
2008年09月15日
見通し、見える。
まだまだ、暑い日が続いていますが、心なしか涼しさを感じられる気もします。
さて、私は、はっきり言って体力が余りありません。持久力、瞬発力、筋力、忍耐力、運動能力、どれをとっても、まともなものがありません。元々、運動センスが無いので、球技はからっきし駄目ときています。チームプレーの競技は、他の人に迷惑がかかるので、今からはじめるのはどうかとも思うし、テニスやバトミントン、卓球などは、相手がいないとできない上に、ボールがまともに飛ばない状態では他の人に迷惑がかかります。かといって、教室とかに通うと、お金もかかるし、時間の融通が利かなくなります。
そこで、以前から、どこかに泳ぎに行こうと、ずーっとお持っていました。水泳なら、少々ヘタクソでも他人にあまり迷惑をかけないし、好きなときにプールから上がってしまえがいいし、一人で黙々と泳ぐこともできるし、全身運動だし、いいこと尽くめです。おまけに、テニスや、ゴルフなんかに比べると初心者用の道具が値段的にも安いのです。
実は私がスポーツの中で唯一まともにできるのも水泳なのです。走るのも飛ぶのも投げるのも駄目だったのですが、水泳だけは小学生の頃から、どちらかというと得意で、地区の記録会に選手として出たこともあります。
これには喘息治療の目的で小さい頃から泳ぎに行っていたことも関係しているようですが。
そこで、水泳をしようと決めたのですが、そう考えてからはや10年、当然、水着も使えなくなっています。おまけに、小学生の頃や中学生の頃と違って視力が極端に悪くなっているので、水の中では別にかまわないのですが、自ら上がったときにプールの段差や、プールサイドとプールの境がわかりづらいほどになっています。
コンタクトレンズも持っているのですが、私はハード派なので、いまさらソフトを作るのは使い捨てでも面倒だし、どの道ゴーグルは必要です。そこで、いろいろ調べて、最近、度付きのゴーグルというものが売られていて、ある程度、ゴーグルで視力の矯正ができることが判明しました。実は昔から、度付きゴーグルはあったのですが、種類も少なく、オーダーに近かったために、非常に高価な印象がありましたが、今は、パーツを自分で組み立てられるスタイルになっていて、手軽に度付きゴーグルを完成することができます。値段も私が知っていた頃と比べると、半額ぐらいでしょうか。
これで、プールからあがったときも、怖い思いをしなくてすみます。プールから上がっても見通しよし、ある程度、周りの景色や状態も見えるようになります。
仕事がおちついたらまた泳ぎに行きたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

軽騎兵/スッペ序曲集
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL5120
このCDはデュトワ/モントリオール響による、フランツ・フォン・スッペの序曲集です。
私はこれを聞くまで、スッペの序曲集といえば、カラヤン/ベルリンフィルのものしか聞いたことがありませんでした。カラヤンの演奏はいかにもドイツオケの演奏らしく、ある意味重厚な響きの上に、カラヤンらしいゴージャスさというか、一般受けする派手さが加わったような演奏だったと記憶しています。ただ、それぞれのソロなどは超一級品でした。
このデュトワの演奏を聴くと、同じ音楽でもここまで変わるか、と感じてしまいます。どちらかというと、デュトワの演奏はフランスチックで、スッペの作品にもかかわらず、オッフェンバックの曲ではないかと思うぐらい、流麗で、透明感あふれた洒落たえんそうになっています。アクセントの扱いも明らかに、ドイツ流というよりはフランス流で、非常にゴリゴリした感じが取り除かれた軽く、やわらかい演奏を感じることができます。
また、このデュトワの演奏は録音のよさもあるのか、各楽器の配置や、演奏の見通しが非常によく、各パートがきれいに見える演奏になっています。 もちろん、全体としてのまとまりもきちんとした音楽に仕上がっているのですが、それぞれのパートが何をやっているのかその気になれば、しっかりと見渡せるような演奏です。
ちょっと洒落た感じのスッペの序曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、私は、はっきり言って体力が余りありません。持久力、瞬発力、筋力、忍耐力、運動能力、どれをとっても、まともなものがありません。元々、運動センスが無いので、球技はからっきし駄目ときています。チームプレーの競技は、他の人に迷惑がかかるので、今からはじめるのはどうかとも思うし、テニスやバトミントン、卓球などは、相手がいないとできない上に、ボールがまともに飛ばない状態では他の人に迷惑がかかります。かといって、教室とかに通うと、お金もかかるし、時間の融通が利かなくなります。
そこで、以前から、どこかに泳ぎに行こうと、ずーっとお持っていました。水泳なら、少々ヘタクソでも他人にあまり迷惑をかけないし、好きなときにプールから上がってしまえがいいし、一人で黙々と泳ぐこともできるし、全身運動だし、いいこと尽くめです。おまけに、テニスや、ゴルフなんかに比べると初心者用の道具が値段的にも安いのです。
実は私がスポーツの中で唯一まともにできるのも水泳なのです。走るのも飛ぶのも投げるのも駄目だったのですが、水泳だけは小学生の頃から、どちらかというと得意で、地区の記録会に選手として出たこともあります。
これには喘息治療の目的で小さい頃から泳ぎに行っていたことも関係しているようですが。
そこで、水泳をしようと決めたのですが、そう考えてからはや10年、当然、水着も使えなくなっています。おまけに、小学生の頃や中学生の頃と違って視力が極端に悪くなっているので、水の中では別にかまわないのですが、自ら上がったときにプールの段差や、プールサイドとプールの境がわかりづらいほどになっています。
コンタクトレンズも持っているのですが、私はハード派なので、いまさらソフトを作るのは使い捨てでも面倒だし、どの道ゴーグルは必要です。そこで、いろいろ調べて、最近、度付きのゴーグルというものが売られていて、ある程度、ゴーグルで視力の矯正ができることが判明しました。実は昔から、度付きゴーグルはあったのですが、種類も少なく、オーダーに近かったために、非常に高価な印象がありましたが、今は、パーツを自分で組み立てられるスタイルになっていて、手軽に度付きゴーグルを完成することができます。値段も私が知っていた頃と比べると、半額ぐらいでしょうか。
これで、プールからあがったときも、怖い思いをしなくてすみます。プールから上がっても見通しよし、ある程度、周りの景色や状態も見えるようになります。
仕事がおちついたらまた泳ぎに行きたいと思っています。
そこで今日の一枚です。

軽騎兵/スッペ序曲集
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON(ポリドール)POCL5120
このCDはデュトワ/モントリオール響による、フランツ・フォン・スッペの序曲集です。
私はこれを聞くまで、スッペの序曲集といえば、カラヤン/ベルリンフィルのものしか聞いたことがありませんでした。カラヤンの演奏はいかにもドイツオケの演奏らしく、ある意味重厚な響きの上に、カラヤンらしいゴージャスさというか、一般受けする派手さが加わったような演奏だったと記憶しています。ただ、それぞれのソロなどは超一級品でした。
このデュトワの演奏を聴くと、同じ音楽でもここまで変わるか、と感じてしまいます。どちらかというと、デュトワの演奏はフランスチックで、スッペの作品にもかかわらず、オッフェンバックの曲ではないかと思うぐらい、流麗で、透明感あふれた洒落たえんそうになっています。アクセントの扱いも明らかに、ドイツ流というよりはフランス流で、非常にゴリゴリした感じが取り除かれた軽く、やわらかい演奏を感じることができます。
また、このデュトワの演奏は録音のよさもあるのか、各楽器の配置や、演奏の見通しが非常によく、各パートがきれいに見える演奏になっています。 もちろん、全体としてのまとまりもきちんとした音楽に仕上がっているのですが、それぞれのパートが何をやっているのかその気になれば、しっかりと見渡せるような演奏です。
ちょっと洒落た感じのスッペの序曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年09月14日
世代、いまどき。
水不足、まだまだ深刻な状況は続いています。
さて、私の部屋のCDラックにあるCDをまた今日から穿り返しえ生きたいと思っています。
ところで、私の所属するサクソフォーン・アンサンブル、ダッパーサクセーバーズの練習時に、なつかしのアニメ等のネタがよく登場しています。 現在の大学生ぐらいの方までだと、「なんじゃ、そりゃ?」というものかもしれませんが、このあたりのアニメのネタは必ず我々より上の世代で、45歳くらいまでの方なら付いてこられるネタだと思います。ちょうど、1960年代後半から、1980年代前半にアニメを見て育った世代であれば、天才バカボンなどは「ああ、あれか、」というぐらいは知っている方がほとんどだと思います。
私が小学生になった頃、アニメといえば、やはりルパン三世(ジャケットが赤色になった第二世代のルパン)が代表的なものでしょうか。ちょうど、現在、「ヤッターマン」が放送されている時間枠で放送されていた記憶があります。小学生のわたしにとっては一週間のスタートの月曜日の憂鬱な気分を救ってくれるもののひとつだったかもしれません。(まあ、ヤッターマンもリメイクで私の世代のアニメだったりします。)
今の世代のアニメ、名探偵コナン」は見たことがあります。原作のコミックも読んだことがあるのですが、あの、「青山剛昌」という方は、すごいですね。推理小説もかなり読み込んでいる模様です。ネタ、知識として、「名探偵コナン」の中にもそれらしいことがちりばめられていたりします。子どもが夢中になるのも判る気がします。子どもの頃に見たアニメで世代がわかったりしますが、いまどきの子どもは、10年後、20年後にどのアニメが記憶に残っているのでしょうか。
そこで今日の一枚です。

「名探偵コナン」オリジナル・サウンドトラック
スーパーベスト
大野克夫バンド/大野克夫
ポリグラム POCX-1082
このCDは名探偵コナンのオリジナルサウンドトラックのベスト版です。未発表曲を含む30トラックが収録されています。
さて、この「名探偵コナン」のサウンドトラック、特にあの有名なテーマを聞いて「懐かしい」と感じた方はいらっしゃいませんでしょうか?私はテーマ曲を最初聴いたときに非常に懐かしい感覚にとらわれました。あの、サックスの使い方、ギターの旋律、まさに…
しばらくの間はその理由を探していたのですが、作曲者が大野克夫氏だということに気づいて、納得。実はあのコナン
のテーマ曲、旋律の雰囲気といい、サックスのメロディーといい、あの、「太陽にほえろ!」によくにているではありませんか。それもそのはず、大野克夫氏は太陽にほえろのテーマ曲も手がけ、自身も当時井上堯之バンドで演奏していたからなのです。この、コナンのサウンドトラックを聞いてみると、随所に太陽にほえろ!と共通するサウンドが聞けて少し楽しかったりします。ちなみに、沢田研二の「時の過ぎゆくままに」 「勝手にしやがれ」なども大野氏の作曲によるものです。
「太陽にほえろ!」を見ていた世代の方、特に名探偵コナンを見ているお子様を持っている「太陽にほえろ!」世代のお父さん、お母さん方にオススメの一枚です。
さて、私の部屋のCDラックにあるCDをまた今日から穿り返しえ生きたいと思っています。
ところで、私の所属するサクソフォーン・アンサンブル、ダッパーサクセーバーズの練習時に、なつかしのアニメ等のネタがよく登場しています。 現在の大学生ぐらいの方までだと、「なんじゃ、そりゃ?」というものかもしれませんが、このあたりのアニメのネタは必ず我々より上の世代で、45歳くらいまでの方なら付いてこられるネタだと思います。ちょうど、1960年代後半から、1980年代前半にアニメを見て育った世代であれば、天才バカボンなどは「ああ、あれか、」というぐらいは知っている方がほとんどだと思います。
私が小学生になった頃、アニメといえば、やはりルパン三世(ジャケットが赤色になった第二世代のルパン)が代表的なものでしょうか。ちょうど、現在、「ヤッターマン」が放送されている時間枠で放送されていた記憶があります。小学生のわたしにとっては一週間のスタートの月曜日の憂鬱な気分を救ってくれるもののひとつだったかもしれません。(まあ、ヤッターマンもリメイクで私の世代のアニメだったりします。)
今の世代のアニメ、名探偵コナン」は見たことがあります。原作のコミックも読んだことがあるのですが、あの、「青山剛昌」という方は、すごいですね。推理小説もかなり読み込んでいる模様です。ネタ、知識として、「名探偵コナン」の中にもそれらしいことがちりばめられていたりします。子どもが夢中になるのも判る気がします。子どもの頃に見たアニメで世代がわかったりしますが、いまどきの子どもは、10年後、20年後にどのアニメが記憶に残っているのでしょうか。
そこで今日の一枚です。

「名探偵コナン」オリジナル・サウンドトラック
スーパーベスト
大野克夫バンド/大野克夫
ポリグラム POCX-1082
このCDは名探偵コナンのオリジナルサウンドトラックのベスト版です。未発表曲を含む30トラックが収録されています。
さて、この「名探偵コナン」のサウンドトラック、特にあの有名なテーマを聞いて「懐かしい」と感じた方はいらっしゃいませんでしょうか?私はテーマ曲を最初聴いたときに非常に懐かしい感覚にとらわれました。あの、サックスの使い方、ギターの旋律、まさに…
しばらくの間はその理由を探していたのですが、作曲者が大野克夫氏だということに気づいて、納得。実はあのコナン
のテーマ曲、旋律の雰囲気といい、サックスのメロディーといい、あの、「太陽にほえろ!」によくにているではありませんか。それもそのはず、大野克夫氏は太陽にほえろのテーマ曲も手がけ、自身も当時井上堯之バンドで演奏していたからなのです。この、コナンのサウンドトラックを聞いてみると、随所に太陽にほえろ!と共通するサウンドが聞けて少し楽しかったりします。ちなみに、沢田研二の「時の過ぎゆくままに」 「勝手にしやがれ」なども大野氏の作曲によるものです。
「太陽にほえろ!」を見ていた世代の方、特に名探偵コナンを見ているお子様を持っている「太陽にほえろ!」世代のお父さん、お母さん方にオススメの一枚です。
2008年09月13日
最終回。
昨日の夜はザーッと雨が降りましたが、水不足が解消されるにはほど遠いと思われます。幸いにして、夏も過ぎ、徐々に水の使用量自体は減っているようですが、まだまだ水不足。
さて、皆さんは最終回、と聴くと何を思い出すでしょうか?世代に育った私はフランダースの犬やら、アルプスの少女ハイジやらを思い出してしまいます。
で、輸入版サックスアンサンブルCD紹介の企画、今日を持ちまして一旦終了したいと思います。別に最終回ってほどのことではなく、これからも、まだ紹介していない輸入版のCDは少しずつ紹介していきたいと思っていますし、これからもCDは増え続けると思いますので、その都度紹介していければと思っています。
これからはレギュラーの「今日の一枚」に戻って多種多用なCDを紹介していきたいと思います。
そこで今日の一枚。

Marcel Mule /... Encore!
Clarinet Classics CC 0021
このCDは、タイトルを見ても判るように、以前にも紹介した「 Marcel Mule 'Le Patron' of the Saxophone」に続く、ミュールの歴史的録音第二弾。ミュールのソロと、ミュールが参加したアンサンブルの演奏が収録されています。さすがにSPレコードからの復刻だけあってモノラル録音で、ノイズも多い録音ですが、それを置いても聞いてみる価値の高い演奏です。ミュールの演奏についてはもう何も語ることは無いと思います。
サクソフォンを愛する全ての方に、オススメの一枚です。
さて、皆さんは最終回、と聴くと何を思い出すでしょうか?世代に育った私はフランダースの犬やら、アルプスの少女ハイジやらを思い出してしまいます。
で、輸入版サックスアンサンブルCD紹介の企画、今日を持ちまして一旦終了したいと思います。別に最終回ってほどのことではなく、これからも、まだ紹介していない輸入版のCDは少しずつ紹介していきたいと思っていますし、これからもCDは増え続けると思いますので、その都度紹介していければと思っています。
これからはレギュラーの「今日の一枚」に戻って多種多用なCDを紹介していきたいと思います。
そこで今日の一枚。

Marcel Mule /... Encore!
Clarinet Classics CC 0021
このCDは、タイトルを見ても判るように、以前にも紹介した「 Marcel Mule 'Le Patron' of the Saxophone」に続く、ミュールの歴史的録音第二弾。ミュールのソロと、ミュールが参加したアンサンブルの演奏が収録されています。さすがにSPレコードからの復刻だけあってモノラル録音で、ノイズも多い録音ですが、それを置いても聞いてみる価値の高い演奏です。ミュールの演奏についてはもう何も語ることは無いと思います。
サクソフォンを愛する全ての方に、オススメの一枚です。
2008年09月11日
得意分野。
ついに9月も中旬となりましたが、水不足がまだまだ続いています。台風の季節でもありますが、それらしい雨もほとんど降りません。深刻な問題です。
さて、楽器を吹いていて思うのですが、まあ、所詮私なので、どの曲を吹こうが、どんな演奏をしようが、たいした演奏は出来ません。
ただ、自分で得意、不得意と思い込んでいる分野はあるようです。
曲の雰囲気やつくりが何となく得意、とか苦手、とか言うことがあります。
まあ、得意であろうが不得意であろうがえんそうはヘタレなわけですが…。
そこで今日の一枚です。
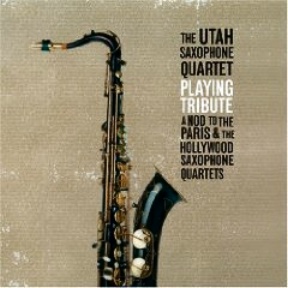
Playing Tribute A Nod to the Paris & the Hollywood Saxophone Quartets
/Utah Saxophone Quartet
このCDは、ユタ・サクソフォンカルテットによるパリ・サクソフォンカルテットと、ハリウッド・サクソフォンカルテットをトリビュートしたアルバム。曲も、フランスものと、アメリカものが中心のアルバムになっています。
ただ、どちらかというと、フランスものの方は…。アメリカものの方は、いかにもアメリカらしく個性を尊重したようなできばえ。解釈も演奏も個性的で、時々ぎょっとすることすらありますが、楽しめるものです。
アメリカの個性的なカルテットを楽しみたい方にオススメの一枚。
さて、楽器を吹いていて思うのですが、まあ、所詮私なので、どの曲を吹こうが、どんな演奏をしようが、たいした演奏は出来ません。
ただ、自分で得意、不得意と思い込んでいる分野はあるようです。
曲の雰囲気やつくりが何となく得意、とか苦手、とか言うことがあります。
まあ、得意であろうが不得意であろうがえんそうはヘタレなわけですが…。
そこで今日の一枚です。
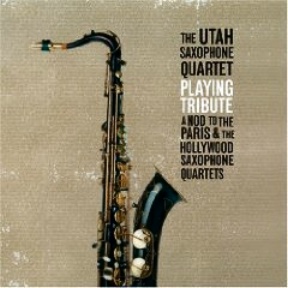
Playing Tribute A Nod to the Paris & the Hollywood Saxophone Quartets
/Utah Saxophone Quartet
このCDは、ユタ・サクソフォンカルテットによるパリ・サクソフォンカルテットと、ハリウッド・サクソフォンカルテットをトリビュートしたアルバム。曲も、フランスものと、アメリカものが中心のアルバムになっています。
ただ、どちらかというと、フランスものの方は…。アメリカものの方は、いかにもアメリカらしく個性を尊重したようなできばえ。解釈も演奏も個性的で、時々ぎょっとすることすらありますが、楽しめるものです。
アメリカの個性的なカルテットを楽しみたい方にオススメの一枚。





