2008年05月17日
忘れ物。
今日は、比較的良い天気の一日となりそうです。しかし、朝・夕はまだまだ気温が下がることが多く、風邪をひいている人もちらほら。
さて、先日忘れ物をしてしまいました。単純に勘違いして、必要なものを持っていかずに不必要なものを持っていってしまっただけなのですが、それでもちょっとへこみます。小学校の頃、期末試験の時間割を一日間違えてしまったような気分で、懐かしさもありましたが、ちょっとへこみました。
忘れ物といえば、傘が有名(?)ですが、私は乗り物などに傘を忘れたことがありません。それはなぜか。傘をめったに持たないからです。私は基本的に傘をさすのが嫌いで、めったに傘を持ち歩きません。少々の雨なら、ぬれることを良しとします。なので、雨の時に街を歩いていると、逆に何か視線が痛いことがあったりもします。傘が無くてぬれるのは私なんですが、と言いたくなることが時々ありますが、実は自意識過剰になっているだけで、街中の喧騒の中では私などは景色の隅にあるだけと思います。香川県、全く都会とは縁遠いはずなのですが。
そこで、久々に今日の一枚です。

バッハ2000
マンハッタン・ジャズ・オーケストラ
VACM-1155
このCDは、マンハッタン・ジャズ・オーケストラによるバッハの曲集です。バッハをモダンジャズにアレンジしてビッグバンドでやってしまおう、という企画のものです。2000年はバッハの没後250年に当たり、その意味もあってリリースされているようです。
ジャズにアレンジされることによってクラシカルなはずのバッハがアーバンな空気たっぷりに演奏されています。どんな形に編曲されても耐えうるバッハはやはり偉大なのでしょうか(笑)。
バッハの音楽をJAZZで聴いてみたい方、クラシックは好きだけど、ジャズはちょっと…と言う方がJAZZの入り口として聞くのにもオススメの一枚です。
さて、先日忘れ物をしてしまいました。単純に勘違いして、必要なものを持っていかずに不必要なものを持っていってしまっただけなのですが、それでもちょっとへこみます。小学校の頃、期末試験の時間割を一日間違えてしまったような気分で、懐かしさもありましたが、ちょっとへこみました。
忘れ物といえば、傘が有名(?)ですが、私は乗り物などに傘を忘れたことがありません。それはなぜか。傘をめったに持たないからです。私は基本的に傘をさすのが嫌いで、めったに傘を持ち歩きません。少々の雨なら、ぬれることを良しとします。なので、雨の時に街を歩いていると、逆に何か視線が痛いことがあったりもします。傘が無くてぬれるのは私なんですが、と言いたくなることが時々ありますが、実は自意識過剰になっているだけで、街中の喧騒の中では私などは景色の隅にあるだけと思います。香川県、全く都会とは縁遠いはずなのですが。
そこで、久々に今日の一枚です。

バッハ2000
マンハッタン・ジャズ・オーケストラ
VACM-1155
このCDは、マンハッタン・ジャズ・オーケストラによるバッハの曲集です。バッハをモダンジャズにアレンジしてビッグバンドでやってしまおう、という企画のものです。2000年はバッハの没後250年に当たり、その意味もあってリリースされているようです。
ジャズにアレンジされることによってクラシカルなはずのバッハがアーバンな空気たっぷりに演奏されています。どんな形に編曲されても耐えうるバッハはやはり偉大なのでしょうか(笑)。
バッハの音楽をJAZZで聴いてみたい方、クラシックは好きだけど、ジャズはちょっと…と言う方がJAZZの入り口として聞くのにもオススメの一枚です。
2008年05月17日
ヨンデンプラザでコンサート。
5月18日(日)に、サンポートのヨンデンプラザ前にて高松ウインドシンフォニーが演奏します。
入場は無料!(というか、半屋外なので、自由に出入りできます。)
13:00~と
15:00~の
2ステージ演奏を行います。
曲目は、
ウルトラ大行進(ウルトラマンメドレー)、銀河鉄道999~宇宙戦艦ヤマト、鉄腕アトム、ビートルズのナンバーなど。
13:00~ と、15:00~ の2ステージの演奏となります。
お時間のある方、サンポートにお越しの際は、是非お立ち寄り下さい。
2008年05月16日
マウスピースパッチ。
サクソフォーンや、クラリネットのマウスピースに歯がたがつくのを防いだり、歯のあたりを良くするために樹脂製のシールを貼ることがあります。
大抵は、管楽器店などで売っているもので、一般的には「マウスピースパッチ」とか、「マウスピースクッション」という名前で売られています。
このマウスピースパッチ、貼るか貼らないかいろいろ賛否両論で、mixiの中でもアンケートが行われたりしていました。
で、このマウスピースパッチ、貼ると音色が変わるとか、貼ることで、アンブシュアに悪影響があるなどと色々言われますが、
私は基本的に好みなのだと思っています。ただ、中高生の皆さんにはちょっと貼るのに注意して欲しいことが…。
まず、これは個人的な感想なのですが、マウスピースパッチを貼ると明らかに音がクリアでなくなる気がします。これは個人的感想なので感じ方は様々だと思うのですが、「貼るのが当たり前」と思って貼るのではなく、歯並びが悪いなどのどうしても貼らなければならない理由がある時に貼ればよいと思います。ファッションではないので、必要なければ貼らないでよいのです。そのほうがお金もかからずにすみます。
マウスピースに歯がたがつくことを気にする方も多いようですが、マウスピースは所詮消耗品です。歯がたがつかなくても未来永劫使えるものではないので、必要の無い人は貼るだけ無駄になります。
それと、これが一番のポイントなのですが、貼るときには、貼り方に注意が必要です。マウスピースパッチは、極端に言えば歯のあたる部分だけで十分です。ところが、中高生の方は、何故かマウスピースの先端に合わせて貼ろうとします。

私が以前楽器店に勤務していた頃、調整したばかりの楽器がならないといって再度楽器を調整に持ってくる中高生が時々居ました。実際に調整が短期間に狂ったりしていることも多かったのですが、その中で、楽器はどこも悪くないのに楽器がならない、という状況のことが何度かありました。
最初のうちは楽器だけ見るので、リペアマンがみてもどこもおかしくない、ということで、原因不明だったのですが、あるときふと思い立ってマウスピースとリードをチェックしてみると…
マウスピースパッチが、マウスピースの先端からはみ出て貼られていました。これは、あまりにマウスピースの先端に合わせてマウスピースパッチを貼ったために使っているうちにずれて、マウスピースの先端からマウスピースパッチがはみ出る状態になっていたためでした。
マウスピースの先端よりはみ出た部分に物があると、音は鳴りにくくなったり、ひっくり返るようになったり、あるいは鳴らなくなったりします。
原因は、マウスピースパッチはシールで貼られるものであることと、マウスピースパッチの素材が樹脂であることです。マウスピースパッチのシールは、貼り替えることを想定しているので極端に粘着力が強いものは使えません。なので、ある程度粘着力を犠牲にすることになり、ずれやすくなります。
更に、素材が樹脂なので、歯があたると、少しだけ伸びます。この、伸びてシールがずれる、ということにより、マウスピースの先端からはみ出てしまう結果に。
これを回避するために出来ることはただ一つ。マウスピースパッチをマウスピースの先端から出来るだけ遠い場所に貼ることです。そして、あまり大きな面積ではなく、小さい面積に貼ること。
また、メーカーによっても素材や粘着力に差がありますので、マウスピースパッチを使う派の方はいくつかのメーカーを試してみると良いかもしれません。(因みに、人によってはビニールテープを貼る人も居るようです)
いずれにしても分厚いマウスピースパッチはアンブシュアを崩すだけでいいことはないと思いますが。

これによってマウスピースパッチを貼ることでのトラブルは回避できます。
マウスピースパッチを貼っている方で楽器が急にならなくなった方。楽器の調整に問題がなければ、ちょっと疑ってみるといいかもしれません。
大抵は、管楽器店などで売っているもので、一般的には「マウスピースパッチ」とか、「マウスピースクッション」という名前で売られています。
このマウスピースパッチ、貼るか貼らないかいろいろ賛否両論で、mixiの中でもアンケートが行われたりしていました。
で、このマウスピースパッチ、貼ると音色が変わるとか、貼ることで、アンブシュアに悪影響があるなどと色々言われますが、
私は基本的に好みなのだと思っています。ただ、中高生の皆さんにはちょっと貼るのに注意して欲しいことが…。
まず、これは個人的な感想なのですが、マウスピースパッチを貼ると明らかに音がクリアでなくなる気がします。これは個人的感想なので感じ方は様々だと思うのですが、「貼るのが当たり前」と思って貼るのではなく、歯並びが悪いなどのどうしても貼らなければならない理由がある時に貼ればよいと思います。ファッションではないので、必要なければ貼らないでよいのです。そのほうがお金もかからずにすみます。
マウスピースに歯がたがつくことを気にする方も多いようですが、マウスピースは所詮消耗品です。歯がたがつかなくても未来永劫使えるものではないので、必要の無い人は貼るだけ無駄になります。
それと、これが一番のポイントなのですが、貼るときには、貼り方に注意が必要です。マウスピースパッチは、極端に言えば歯のあたる部分だけで十分です。ところが、中高生の方は、何故かマウスピースの先端に合わせて貼ろうとします。
私が以前楽器店に勤務していた頃、調整したばかりの楽器がならないといって再度楽器を調整に持ってくる中高生が時々居ました。実際に調整が短期間に狂ったりしていることも多かったのですが、その中で、楽器はどこも悪くないのに楽器がならない、という状況のことが何度かありました。
最初のうちは楽器だけ見るので、リペアマンがみてもどこもおかしくない、ということで、原因不明だったのですが、あるときふと思い立ってマウスピースとリードをチェックしてみると…
マウスピースパッチが、マウスピースの先端からはみ出て貼られていました。これは、あまりにマウスピースの先端に合わせてマウスピースパッチを貼ったために使っているうちにずれて、マウスピースの先端からマウスピースパッチがはみ出る状態になっていたためでした。
マウスピースの先端よりはみ出た部分に物があると、音は鳴りにくくなったり、ひっくり返るようになったり、あるいは鳴らなくなったりします。
原因は、マウスピースパッチはシールで貼られるものであることと、マウスピースパッチの素材が樹脂であることです。マウスピースパッチのシールは、貼り替えることを想定しているので極端に粘着力が強いものは使えません。なので、ある程度粘着力を犠牲にすることになり、ずれやすくなります。
更に、素材が樹脂なので、歯があたると、少しだけ伸びます。この、伸びてシールがずれる、ということにより、マウスピースの先端からはみ出てしまう結果に。
これを回避するために出来ることはただ一つ。マウスピースパッチをマウスピースの先端から出来るだけ遠い場所に貼ることです。そして、あまり大きな面積ではなく、小さい面積に貼ること。
また、メーカーによっても素材や粘着力に差がありますので、マウスピースパッチを使う派の方はいくつかのメーカーを試してみると良いかもしれません。(因みに、人によってはビニールテープを貼る人も居るようです)
いずれにしても分厚いマウスピースパッチはアンブシュアを崩すだけでいいことはないと思いますが。
これによってマウスピースパッチを貼ることでのトラブルは回避できます。
マウスピースパッチを貼っている方で楽器が急にならなくなった方。楽器の調整に問題がなければ、ちょっと疑ってみるといいかもしれません。
2008年05月15日
気軽に気楽に?
今日は昨日と違ってまずまずのお天気です。
さて、演奏会の時に、いつも困るというか、手間がかかるのが選曲。一番いいのは、自分達のやりたい曲をやって、お客さんが喜んでくれることなのですが、問題は客層なのです。我々、アンサンブルで演奏会をするときは一番のお客はやはり、吹奏楽でサックスをやっている学生さんです。で、この客層にあわせて編曲すると、どうしてもアンサンブルコンテスト向けの曲を選択せずにはいられません。
ところが、吹奏楽をやっている人間が思っているほど、アンサンブルコンテストは一般の人々に対してはメジャーではないので、当然、マニアックな選曲になってしまいます。難しいのはそのあたりの選曲のバランスを考えること。一般の方にも受け入れられやすく、しかもアンサンブルコンテストなどで取り上げられやすい曲となると、かなり曲目が限られてしまいます。
また、アンケート。演奏会でアンケートを常に採っているのですが、学生さんに良かった曲、演奏して欲しい曲など書いてもらうと、やはり、自分が演奏したことのある曲、これから演奏する曲などを書きます。これはこれでいいのですが、本来のアンケートの意味はあまり無い解答になってしまいます。
選曲をやる点でいつも悩むのがこのあたりのバランス。おまけに演奏者としてやりたい曲というのもありますので、それがからむとなおさら、選ぶ曲に制限が加わります。私自身は最近、食わず嫌いをやめて、人に言われるがままの曲を文句をいわずにやろうと決めているのですが、人はそれぞれなので、皆が私のように思ってくれるわけではありません。
そうなってくるとやはり、趣旨ごとに違う演奏会を開くのが良いかもしれません。小さい演奏会をこまめに開くと、大きい演奏会では多少マニアックになるにしても、小さい演奏会では融通も利きやすいので、客層によっていろいろに対応しても良いかもも知れません。でも、演奏するほうが大変になりますが…。
何事にしても、気楽に、気軽に楽しめることも入り口には大切なことかもしれないと思う今日この頃です。
そこで今日の一枚。

大序曲《1812年》、ダッタン人の踊り
~ロシア管弦楽曲集/ゲルギエフ
指揮:ワレリー・ゲルギエフ
サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団
サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場合唱団
オランダ王立海軍軍楽隊員
フィリップス PHCP-21033
このCDはロシアの指揮者、ゲルギエフによるロシアの管弦楽作品集。様々な曲からの抜粋や、序曲などを聞くことが出来ます。
ゲルギエフはモスクワ生まれの指揮者で、1978年にキーロフ劇場(現在のマリンスキー劇場オペラ団バレエ)デビューした人です。35歳で同劇場の芸術監督に就任後はロシア・オペラを積極的に上演しつづけています。また、ロッテルダム・フィル首席指揮者、メトロポリタン歌劇場首席客演指揮者も務めるほか、手兵マリンスキー・オペラ&バレエを引き連れ、世界で公演を行なっています。最近では、ウィーンフィルとの様々な曲の録音を行ったりもしています。
このCDの録音時はオケの名称がまだ、サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団でした。
演奏はロシアらしいエネルギーに満ちたもの。ただ、音の響きは昔のロシアの演奏に比べるとよりインターナショナル化しているように思います。
他にガイーヌから「剣の舞い」や、「ルスランとリュドミュラ」序曲なども収録されています。
大序曲「1812年」はチャイコフスキーの作品で、ポレオンに率いらたフランス軍が、ついに大国ロシアに攻め入り、統率のとれたフランス軍の攻撃に、強大なロシア軍も窮地に立たされましたが、“冬将軍”と呼ばれる大寒波の襲来により、フランス軍はついにはロシアから撤退しました。それから68年後の1880年、に全ロシア産業工芸博覧会の開会式のための音楽を依頼されたチャイコフスキーは悩んだ末、ロシア軍が歴史的勝利をおさめた1812年の戦争を、テーマに作曲しました。 大きく分けて、三つの部分で構成され、一部ではロシアの苦悩が、二部では戦闘の様子が、そして三部ではロシアの勝利が描かれています。クライマックスは何と言っても三部で、大砲の音が轟いたり(現在のコンサートではシンセサイザーなどが用いられますが、かつては実際の大砲を空砲で使っていました)、チャイムが華やかに打ち鳴らされたりします。また、フランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」のメロディに対してロシア国家で応戦し、フランス軍の敗退を描きだすといった趣向が使われています。最近では某飲料メーカーの缶コーヒーのコマーシャルや、某製薬会社の鼻炎薬のコマーシャルなどにも使われています。
大砲の轟音とともにチャイコフスキーを聴いてみたい方、ポピュラーなロシア音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
(大砲の生音が録音されているCDとしてはエリック・カンゼル指揮、シンシナティ交響楽団の演奏などもあります。)
さて、演奏会の時に、いつも困るというか、手間がかかるのが選曲。一番いいのは、自分達のやりたい曲をやって、お客さんが喜んでくれることなのですが、問題は客層なのです。我々、アンサンブルで演奏会をするときは一番のお客はやはり、吹奏楽でサックスをやっている学生さんです。で、この客層にあわせて編曲すると、どうしてもアンサンブルコンテスト向けの曲を選択せずにはいられません。
ところが、吹奏楽をやっている人間が思っているほど、アンサンブルコンテストは一般の人々に対してはメジャーではないので、当然、マニアックな選曲になってしまいます。難しいのはそのあたりの選曲のバランスを考えること。一般の方にも受け入れられやすく、しかもアンサンブルコンテストなどで取り上げられやすい曲となると、かなり曲目が限られてしまいます。
また、アンケート。演奏会でアンケートを常に採っているのですが、学生さんに良かった曲、演奏して欲しい曲など書いてもらうと、やはり、自分が演奏したことのある曲、これから演奏する曲などを書きます。これはこれでいいのですが、本来のアンケートの意味はあまり無い解答になってしまいます。
選曲をやる点でいつも悩むのがこのあたりのバランス。おまけに演奏者としてやりたい曲というのもありますので、それがからむとなおさら、選ぶ曲に制限が加わります。私自身は最近、食わず嫌いをやめて、人に言われるがままの曲を文句をいわずにやろうと決めているのですが、人はそれぞれなので、皆が私のように思ってくれるわけではありません。
そうなってくるとやはり、趣旨ごとに違う演奏会を開くのが良いかもしれません。小さい演奏会をこまめに開くと、大きい演奏会では多少マニアックになるにしても、小さい演奏会では融通も利きやすいので、客層によっていろいろに対応しても良いかもも知れません。でも、演奏するほうが大変になりますが…。
何事にしても、気楽に、気軽に楽しめることも入り口には大切なことかもしれないと思う今日この頃です。
そこで今日の一枚。

大序曲《1812年》、ダッタン人の踊り
~ロシア管弦楽曲集/ゲルギエフ
指揮:ワレリー・ゲルギエフ
サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団
サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場合唱団
オランダ王立海軍軍楽隊員
フィリップス PHCP-21033
このCDはロシアの指揮者、ゲルギエフによるロシアの管弦楽作品集。様々な曲からの抜粋や、序曲などを聞くことが出来ます。
ゲルギエフはモスクワ生まれの指揮者で、1978年にキーロフ劇場(現在のマリンスキー劇場オペラ団バレエ)デビューした人です。35歳で同劇場の芸術監督に就任後はロシア・オペラを積極的に上演しつづけています。また、ロッテルダム・フィル首席指揮者、メトロポリタン歌劇場首席客演指揮者も務めるほか、手兵マリンスキー・オペラ&バレエを引き連れ、世界で公演を行なっています。最近では、ウィーンフィルとの様々な曲の録音を行ったりもしています。
このCDの録音時はオケの名称がまだ、サンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団でした。
演奏はロシアらしいエネルギーに満ちたもの。ただ、音の響きは昔のロシアの演奏に比べるとよりインターナショナル化しているように思います。
他にガイーヌから「剣の舞い」や、「ルスランとリュドミュラ」序曲なども収録されています。
大序曲「1812年」はチャイコフスキーの作品で、ポレオンに率いらたフランス軍が、ついに大国ロシアに攻め入り、統率のとれたフランス軍の攻撃に、強大なロシア軍も窮地に立たされましたが、“冬将軍”と呼ばれる大寒波の襲来により、フランス軍はついにはロシアから撤退しました。それから68年後の1880年、に全ロシア産業工芸博覧会の開会式のための音楽を依頼されたチャイコフスキーは悩んだ末、ロシア軍が歴史的勝利をおさめた1812年の戦争を、テーマに作曲しました。 大きく分けて、三つの部分で構成され、一部ではロシアの苦悩が、二部では戦闘の様子が、そして三部ではロシアの勝利が描かれています。クライマックスは何と言っても三部で、大砲の音が轟いたり(現在のコンサートではシンセサイザーなどが用いられますが、かつては実際の大砲を空砲で使っていました)、チャイムが華やかに打ち鳴らされたりします。また、フランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」のメロディに対してロシア国家で応戦し、フランス軍の敗退を描きだすといった趣向が使われています。最近では某飲料メーカーの缶コーヒーのコマーシャルや、某製薬会社の鼻炎薬のコマーシャルなどにも使われています。
大砲の轟音とともにチャイコフスキーを聴いてみたい方、ポピュラーなロシア音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
(大砲の生音が録音されているCDとしてはエリック・カンゼル指揮、シンシナティ交響楽団の演奏などもあります。)
2008年05月15日
魔法が使いたい気分。
今日は比較的良いお天気で、気温もぐんぐん上がる一日となりました。
最近、仕事が溜まる一方です。自分の仕事の上に、他部署から押し付けられた仕事がドンドンと溜まっていきます。
おかげで残業続き。残業代が出ればいいのですが、そう簡単に残業代がつくわけでもなく、勿論サービス残業。
本当に魔法が使えて仕事がいっぺんに片付かないかと、ありもしないことを考えてみたりします。
さて、そこで本日の一枚。
VIVE LA FRANCE!
魔法使いの弟子/デュトワ/フレンチ・コンサート
LONDON (ポリドール) F32L-20312
このCDはデュトワ/モントリオール響によるフランス音楽の作品集。シャブリエの「狂詩曲スペイン」やイベールの「喜遊曲」なども収録されています。
魔法使いの弟子といえば、ディズニーのファンタジアにも取り上げられた曲です。ミッキーマウスの魔法使いの姿をどこかで見たことがあるかもしれません。ファンタジアを見た方はあの通りなのですが、ストーリーとしては魔法使いの大先生の弟子が大先生の唱える呪文を盗み聞いて大先生が留守の間に箒に呪文をかけて家事や雑用をさせてしまおうとするのですが、箒に風呂に水を汲んで入れる呪文をかけたまではいいのですが、呪文のとき方を知らない弟子は止めることが出来ず、最後にはパニックに陥ってしまいます。家中水浸しの状態。そこに大先生がようやく帰宅し、呪文を一括して水をかたずけてしまう、というものです。曲を聞くと情景が浮かんでくるようです。ディズニーがファンタジアでこれを映像化したのもわかる気がします。
このように全編、気楽に楽しめる音楽が多いアルバムです。ポップスはありませんが、まさしく、ちょっと気軽なファミリーコンサート風の選曲です。
魔法使いの弟子を聴いてみたい方、気楽にフランス音楽に触れてみたい方にオススメの一枚です。
最近、仕事が溜まる一方です。自分の仕事の上に、他部署から押し付けられた仕事がドンドンと溜まっていきます。
おかげで残業続き。残業代が出ればいいのですが、そう簡単に残業代がつくわけでもなく、勿論サービス残業。
本当に魔法が使えて仕事がいっぺんに片付かないかと、ありもしないことを考えてみたりします。
さて、そこで本日の一枚。
VIVE LA FRANCE!
魔法使いの弟子/デュトワ/フレンチ・コンサート
LONDON (ポリドール) F32L-20312
このCDはデュトワ/モントリオール響によるフランス音楽の作品集。シャブリエの「狂詩曲スペイン」やイベールの「喜遊曲」なども収録されています。
魔法使いの弟子といえば、ディズニーのファンタジアにも取り上げられた曲です。ミッキーマウスの魔法使いの姿をどこかで見たことがあるかもしれません。ファンタジアを見た方はあの通りなのですが、ストーリーとしては魔法使いの大先生の弟子が大先生の唱える呪文を盗み聞いて大先生が留守の間に箒に呪文をかけて家事や雑用をさせてしまおうとするのですが、箒に風呂に水を汲んで入れる呪文をかけたまではいいのですが、呪文のとき方を知らない弟子は止めることが出来ず、最後にはパニックに陥ってしまいます。家中水浸しの状態。そこに大先生がようやく帰宅し、呪文を一括して水をかたずけてしまう、というものです。曲を聞くと情景が浮かんでくるようです。ディズニーがファンタジアでこれを映像化したのもわかる気がします。
このように全編、気楽に楽しめる音楽が多いアルバムです。ポップスはありませんが、まさしく、ちょっと気軽なファミリーコンサート風の選曲です。
魔法使いの弟子を聴いてみたい方、気楽にフランス音楽に触れてみたい方にオススメの一枚です。
2008年05月14日
謎。
今日は雨模様。時折、激しく降っています。
さて、私の両親に、年金特別便が届きました。国会議員の怠慢を、国民に押し付けたあれです。
ところで、数年前、国会議員の方々の年金未納問題が取り沙汰されていましたが、記憶の彼方に追いやられている人も多いと思います。いまだに年金の未納者の方は居ると思います。皆さん年金払ってますか?私はとりあえず払っています。まあ、破綻するかもしれないのですが、破綻しなかったときはきちんともらえるわけで、そのために払ってます。ちょっと高くつく賭けになるかもしれませんが、まあ、ギャンブルと思えばそれもいいかと思っています。私が、ギャンブルと思っているということは堅実な方は年金を払わずにもっと他の方法を考えているのかもしれませんが、私は他の方法が浮かびません。
で、謎なのですが、お偉い議員さん方は、年金を何年~何年まで払ってませんでした、と言っていますが、そもそも「年金を何年~何年まで」と言うところにもウソとからくりがある気がします。年金は未納分のをさかのぼって払うことが可能ですが、それも2年までしかさかのぼれません。だから、未納期間が2年前までだという主張をしている議員先生がいたら、特に要チェックです。いかにも忘れてました、勘違いでしたという顔をして、実は今慌てて払っている可能性があります。
そもそも、勘違いで払わないなんて人たちに年金問題を語る資格自体無いと思うのです。国会議員たるもの、きちんと年金制度を勉強してから審議して欲しいものです。国会議員でも国民年金を払わなければいけないことなど、年金のことをちょっとかじっただけでわかる事柄です。
そんなことを忘れてました、といけしゃあしゃあという議員が悪いのか、はたまた、そんな議員を許す国民が悪いのか。あらゆる手段を使って議員になろうとする方がいるのですから、職業的にも魅力のあるものなのかもしれませんが、利権に群がる構造や、自己保身に大してはすばやく行動し、国民の声には緩慢に行動する議員がよく国会ででかい口が叩けるものだと、私はいまだに謎です。
因みに、国会にかかわらず、議員という職業は私の最も嫌う職業ではあるのですが。
まあ、これだけではなく、世の中不条理なこと、謎が多すぎると感じる今日この頃です。
そこで今日の一枚。
アガサ・クリスティー/名探偵・エルキュール・ポアロ
オリジナル・TVサウンドトラック
ヴァージンレーベル (日本クラウン)CRCL-5029
このCDはアガサ・クリスティー原作の探偵エルキュール・ポアロをイギリスのグラナダがTVシリーズで制作したもののサウンドトラックです。ご存知、ベルギー生まれの小粋で、ありながらデブでチビ、髭を炊くわけた探偵が“灰色の脳細胞”を駆使して難事件を見事に解決していくというものです。
他にも映画化、TV化されたものがありますが、おそらくこれだけたくさんのものをシリーズ化しているのはこの作品だけではないでしょうか。
で、私はアガサ・クリスティーのミステリーも好きなのですが、何より、このサウンドトラックはサックスが大活躍。(笑)主にポアロのテーマがサックスによって演奏されています。NHKで何度かこのシリーズは放映されていますので、あのエンディングに流れるサックスの演奏を聴いた方も多いはずです。私はあのサックスが聞きたくて買いました。
因みに、シャーロック・ホームズのシリーズもあり、サウンドトラックが発売されていますが、こちらはバイオリンがホームズのテーマを演奏します。
ミステリー好きの方、NHKで見て、あのサックスの演奏が聴きたいと思った方にオススメの一枚です。
5.だ
さて、私の両親に、年金特別便が届きました。国会議員の怠慢を、国民に押し付けたあれです。
ところで、数年前、国会議員の方々の年金未納問題が取り沙汰されていましたが、記憶の彼方に追いやられている人も多いと思います。いまだに年金の未納者の方は居ると思います。皆さん年金払ってますか?私はとりあえず払っています。まあ、破綻するかもしれないのですが、破綻しなかったときはきちんともらえるわけで、そのために払ってます。ちょっと高くつく賭けになるかもしれませんが、まあ、ギャンブルと思えばそれもいいかと思っています。私が、ギャンブルと思っているということは堅実な方は年金を払わずにもっと他の方法を考えているのかもしれませんが、私は他の方法が浮かびません。
で、謎なのですが、お偉い議員さん方は、年金を何年~何年まで払ってませんでした、と言っていますが、そもそも「年金を何年~何年まで」と言うところにもウソとからくりがある気がします。年金は未納分のをさかのぼって払うことが可能ですが、それも2年までしかさかのぼれません。だから、未納期間が2年前までだという主張をしている議員先生がいたら、特に要チェックです。いかにも忘れてました、勘違いでしたという顔をして、実は今慌てて払っている可能性があります。
そもそも、勘違いで払わないなんて人たちに年金問題を語る資格自体無いと思うのです。国会議員たるもの、きちんと年金制度を勉強してから審議して欲しいものです。国会議員でも国民年金を払わなければいけないことなど、年金のことをちょっとかじっただけでわかる事柄です。
そんなことを忘れてました、といけしゃあしゃあという議員が悪いのか、はたまた、そんな議員を許す国民が悪いのか。あらゆる手段を使って議員になろうとする方がいるのですから、職業的にも魅力のあるものなのかもしれませんが、利権に群がる構造や、自己保身に大してはすばやく行動し、国民の声には緩慢に行動する議員がよく国会ででかい口が叩けるものだと、私はいまだに謎です。
因みに、国会にかかわらず、議員という職業は私の最も嫌う職業ではあるのですが。
まあ、これだけではなく、世の中不条理なこと、謎が多すぎると感じる今日この頃です。
そこで今日の一枚。
アガサ・クリスティー/名探偵・エルキュール・ポアロ
オリジナル・TVサウンドトラック
ヴァージンレーベル (日本クラウン)CRCL-5029
このCDはアガサ・クリスティー原作の探偵エルキュール・ポアロをイギリスのグラナダがTVシリーズで制作したもののサウンドトラックです。ご存知、ベルギー生まれの小粋で、ありながらデブでチビ、髭を炊くわけた探偵が“灰色の脳細胞”を駆使して難事件を見事に解決していくというものです。
他にも映画化、TV化されたものがありますが、おそらくこれだけたくさんのものをシリーズ化しているのはこの作品だけではないでしょうか。
で、私はアガサ・クリスティーのミステリーも好きなのですが、何より、このサウンドトラックはサックスが大活躍。(笑)主にポアロのテーマがサックスによって演奏されています。NHKで何度かこのシリーズは放映されていますので、あのエンディングに流れるサックスの演奏を聴いた方も多いはずです。私はあのサックスが聞きたくて買いました。
因みに、シャーロック・ホームズのシリーズもあり、サウンドトラックが発売されていますが、こちらはバイオリンがホームズのテーマを演奏します。
ミステリー好きの方、NHKで見て、あのサックスの演奏が聴きたいと思った方にオススメの一枚です。
5.だ
2008年05月13日
水不足の季節は。
今日は良い天気です。後一ヶ月もすると梅雨がやってきます。やはり、雨が降ると、気持ちが落ち込んだり、体調が優れなかったりもします。たいしたものではないのですが私はいくつかの病気を持っているのですが、それらの症状も雨模様が続くと優れなかったりします。
しかし、この雨、私の住む香川県ではある意味恵みの雨なのです。香川県は昔から、年間の降水量が少なく、水不足に悩まされてきました。溜池の多さは日本のトップクラスです。今は、お隣の徳島県から「香川用水」で水を分けてもらっているので、昔ほどの水不足はありませんが、それでも何年かに一度は給水制限があったり、断水になったりします。
子どもの頃は周囲が海に囲まれた四国なので、何故海水を真水にしないのかと不思議でしたが、大量に海水を真水に帰るのにはそれなりのギミックが必要なわけで、かなり大掛かりで高度な設備が必要だと知ったのは随分後のことでした。
そんなことで水不足を懸念してはいるのですが、やはり雨模様だと鬱陶しいものです。最近は自転車で多い私なので毎日が晴天だったらいいのに、と思うこともしばしばです。
今年の梅雨はどうなるのでしょう。しとしと降る梅雨なのか、まとめて一気に降る梅雨になるのか。豪雨になると、これまた、豪雨の対策があまりなされていない香川県にとっては打撃が大きいのでそれはそれで心配です。
そこで今日の一枚。
グローフェ/組曲「グランド・キャニオン」他
指揮:アンタル・ドラティ
デトロイト交響楽団
LONDON (ポリドール)FOOL-23084
リンク先の盤は私の持っているものとは違うジャケットの廉価版です。
内容は全く同じです。
このCDはグローフェ、コープランドといったアメリカの作曲家による作品を収録したもの。グランド・キャニオンは私が中学生のときには音楽鑑賞の授業用教材として使われていた曲でもあります。
日の出、赤い砂漠、山道を行く、日没、豪雨の5曲の組曲です。
随所にジャズの手法も取り入れ、豪雨ではお目にかかるのが珍しいウインドマシーンの音も効くことが出来ます。
演奏の方はというと、ドラティらしいストレートな表現というか、小細工しない感じがこのアルバムの曲目とあっていて良いのではないかと思います。ただし、全体にシンフォニックではありますが、日の出や豪雨などは、もう少し前に進む感じがあっても良いかもしれません。豪雨ではクライマックスに雷が一発入ります。
グランド・キャニオンの演奏ではオーマンディーのフィラデルフィア盤が有名なようですが、残念ながら私は聞いたことがありません。ただ、このドラティ盤は一緒にコープランドの作品も楽しめる点でよいと思います。
クラシックの入門用の曲を探している方、アメリカの作曲家の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
しかし、この雨、私の住む香川県ではある意味恵みの雨なのです。香川県は昔から、年間の降水量が少なく、水不足に悩まされてきました。溜池の多さは日本のトップクラスです。今は、お隣の徳島県から「香川用水」で水を分けてもらっているので、昔ほどの水不足はありませんが、それでも何年かに一度は給水制限があったり、断水になったりします。
子どもの頃は周囲が海に囲まれた四国なので、何故海水を真水にしないのかと不思議でしたが、大量に海水を真水に帰るのにはそれなりのギミックが必要なわけで、かなり大掛かりで高度な設備が必要だと知ったのは随分後のことでした。
そんなことで水不足を懸念してはいるのですが、やはり雨模様だと鬱陶しいものです。最近は自転車で多い私なので毎日が晴天だったらいいのに、と思うこともしばしばです。
今年の梅雨はどうなるのでしょう。しとしと降る梅雨なのか、まとめて一気に降る梅雨になるのか。豪雨になると、これまた、豪雨の対策があまりなされていない香川県にとっては打撃が大きいのでそれはそれで心配です。
そこで今日の一枚。
グローフェ/組曲「グランド・キャニオン」他
指揮:アンタル・ドラティ
デトロイト交響楽団
LONDON (ポリドール)FOOL-23084
リンク先の盤は私の持っているものとは違うジャケットの廉価版です。
内容は全く同じです。
このCDはグローフェ、コープランドといったアメリカの作曲家による作品を収録したもの。グランド・キャニオンは私が中学生のときには音楽鑑賞の授業用教材として使われていた曲でもあります。
日の出、赤い砂漠、山道を行く、日没、豪雨の5曲の組曲です。
随所にジャズの手法も取り入れ、豪雨ではお目にかかるのが珍しいウインドマシーンの音も効くことが出来ます。
演奏の方はというと、ドラティらしいストレートな表現というか、小細工しない感じがこのアルバムの曲目とあっていて良いのではないかと思います。ただし、全体にシンフォニックではありますが、日の出や豪雨などは、もう少し前に進む感じがあっても良いかもしれません。豪雨ではクライマックスに雷が一発入ります。
グランド・キャニオンの演奏ではオーマンディーのフィラデルフィア盤が有名なようですが、残念ながら私は聞いたことがありません。ただ、このドラティ盤は一緒にコープランドの作品も楽しめる点でよいと思います。
クラシックの入門用の曲を探している方、アメリカの作曲家の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
Posted by のりくん at
00:22
│Comments(0)
2008年05月12日
肩が凝る。
以前から、肩凝りがひどい私です。首の方の筋からきているようです。最も私は顎関節症持ちなので、もしかしたらそれが一番の原因なのかもしれません。顎関節症になったら、楽器を吹くことも控えた方が良いのかもしれませんが、わたしはこの20年ばかりお構いなしに吹いて何の不都合も起きていないので、気にしていません。ただ、最近特に肩こりがひどいのはもしかしたら、顎関節症のせいかもしれないなあ、と思うようになりました。まあ、しばらく様子を見てどうしても耐えられなくなったら病院行きかも知れませんが、今のところは大丈夫です。肩こりにも慣れがあるらしく、激しい肩こりに慣れてしまうと、結構凝っていても気にしなくなります。体には当然負担をかけているので、そのうちがたが出るとは思うのですが。
他にも肩が凝る一つの原因は私の首が細さかも知れません。因みにワイシャツのサイズは首回りが37cm、袖丈が84cmです。既製品は確実にサイズがありません。最近のワイシャツはサイズがS、L、Mになっていたりするのですが、当然、そんなサイズのワイシャツは体に合いません。なのでほとんどのワイシャツはイージーオーダーか、フルオーダーになります。本来一着3000円くらいで買えるワイシャツが、オーダーのため、10000円近くに跳ね上がります。
たまに首廻りが37cmで袖丈82cmのワイシャツを見つけて買ってしのいだりしていますが、やはり、袖の長さは少し足らない感じです。袖が短いワイシャツを着るとこれまた肩が凝ります。
何かしら、既製品の窮屈さを感じてしまう出来事です。世の中既製品化され、人間まで統一規格になってしまうのではないかと思って恐ろしくなってしまいます。
さて、そこで今日の一枚。

SAXOPHONE COLOSSUS(サキソフォン・コロッサス)
SONNY ROLLINS(ソニー・ロリンズ)
ビクター VICJ-23501
このCDはいわずと知れた、JAZZテナーサックスの巨匠ソニー・ロリンズの代表作です。JAZZファンでこのアルバムを聞いたことが無ければ、おそらくモグリといわれても仕方ないかも知れないほどの有名なアルバムです。
ソニー・ロリンズのことを知らなくても1曲目の「ST.THOMAS」のメロディーを聴いたらああ、聞いたことのある曲だ、という方は少なくないはず。
JAZZファンにとってはもっとちがった意見があると思うのですが、私の聞く限りでは、無駄な力の入っていない、非常に聴きやすいアルバムだと思います。肩に力が入っていない、まさに肩の凝らない演奏です。かといって、ソニー・ロリンズという人の個性が希薄という意味ではなく、きちんとしたキャラクターをもった音色と、演奏を聞くことが出来ます。
尚、このアルバムはモノーラル録音なのですが、それを忘れさせる優秀な録音と秀逸な演奏のものだと思います。
JAZZファン、サックスファン、また、これからJAZZを聴いてみたいと思うJAZZ初心者の方にもオススメの一枚です。
他にも肩が凝る一つの原因は私の首が細さかも知れません。因みにワイシャツのサイズは首回りが37cm、袖丈が84cmです。既製品は確実にサイズがありません。最近のワイシャツはサイズがS、L、Mになっていたりするのですが、当然、そんなサイズのワイシャツは体に合いません。なのでほとんどのワイシャツはイージーオーダーか、フルオーダーになります。本来一着3000円くらいで買えるワイシャツが、オーダーのため、10000円近くに跳ね上がります。
たまに首廻りが37cmで袖丈82cmのワイシャツを見つけて買ってしのいだりしていますが、やはり、袖の長さは少し足らない感じです。袖が短いワイシャツを着るとこれまた肩が凝ります。
何かしら、既製品の窮屈さを感じてしまう出来事です。世の中既製品化され、人間まで統一規格になってしまうのではないかと思って恐ろしくなってしまいます。
さて、そこで今日の一枚。

SAXOPHONE COLOSSUS(サキソフォン・コロッサス)
SONNY ROLLINS(ソニー・ロリンズ)
ビクター VICJ-23501
このCDはいわずと知れた、JAZZテナーサックスの巨匠ソニー・ロリンズの代表作です。JAZZファンでこのアルバムを聞いたことが無ければ、おそらくモグリといわれても仕方ないかも知れないほどの有名なアルバムです。
ソニー・ロリンズのことを知らなくても1曲目の「ST.THOMAS」のメロディーを聴いたらああ、聞いたことのある曲だ、という方は少なくないはず。
JAZZファンにとってはもっとちがった意見があると思うのですが、私の聞く限りでは、無駄な力の入っていない、非常に聴きやすいアルバムだと思います。肩に力が入っていない、まさに肩の凝らない演奏です。かといって、ソニー・ロリンズという人の個性が希薄という意味ではなく、きちんとしたキャラクターをもった音色と、演奏を聞くことが出来ます。
尚、このアルバムはモノーラル録音なのですが、それを忘れさせる優秀な録音と秀逸な演奏のものだと思います。
JAZZファン、サックスファン、また、これからJAZZを聴いてみたいと思うJAZZ初心者の方にもオススメの一枚です。
2008年05月11日
バテる季節です。
今日は雨模様で少し肌寒いくらいの日となりました。昨日はかなり気温も上がったようです。この気温はもう夏です。
先日来書いてきたように私は夏の暑さが本当に苦手です。なにせ、今からもう夏バテしようかという勢いです。私は、小学校の頃は水泳が得意でプールが大好きでした。今思えば、プールに入っていると夏バテせずに済むからだったかもしれません。でも、体育の成績は常に地を這うものでした。他のスポーツは苦手でからっきし駄目だったのです。走る、打つ、投げる、どれをとってもまるっきり駄目でした。運動能力ゼロに近かったかもしれません。しかし、水泳となると全くの別物で、クラスでトップレベルに豹変しました。その理由のひとつには、小さい頃、喘息治療のため、毎週のようにプールに通っていたこともあげられるとおもいますが、それに加えて、夏の暑さを逃れるための小さい頃からのプール通いがあったかもしれません。
夏になるとなんとか、エアコン以外の方法で涼しさを感じられる努力をしてみるのですが、必ず8月末が近づいてくる頃にはバテと寝不足で目の下にクマが出来て体重も減ってしまいます。
そこで今日の一枚。

EACH TIME
大滝詠一
CBSソニー (Niagara)CSCL-1664
このCDは「ロング・バケイション」に続くオリジナル・アルバムとして84年にリリースされ、大瀧詠一氏初のオリコン・チャートで1位に輝いた作品。もちろん当時はLPレコードというメディアでした。私はオリジナルのLPも持っていますが先日来から書いているようにいまはLPが聞ける環境を持っていないのでこのCDしか聞くことが出来ません。
作詞家の松本隆氏とアルバム全曲をコラボレートした内容になっています。、サウンド的には「A LONG VACATION」よりさらに凝った作りとなっていますが、まさに大瀧ワールド、Naiagaraサウンドです。アルバムには
1.魔法の瞳
2.夏のペーパーバック
3.木の葉のスケッチ
4.恋のナックルボール
5.銀色のジェット
6.1969年のドラッグレース
7.ガラス壜の中の船
8.ペパーミント・ブルー
9.レイクサイド・ストーリー
の計9曲がクレジットされています。
「EACH TIME 20th Annniversary Edition」というアルバムが先日発売されさらにボーナストラックが収録されているようなので、これから購入される方はこちらを選んでも良いかもしれません。
ちょっぴり切ない松本氏の歌詞とNaiagaraサウンドを聴きながら木陰で涼めたら、夏も乗り切れる?かも知れません。以前に紹介した「ロング・バケイション」とともに、これからの季節に聴くのにオススメの一枚です。
先日来書いてきたように私は夏の暑さが本当に苦手です。なにせ、今からもう夏バテしようかという勢いです。私は、小学校の頃は水泳が得意でプールが大好きでした。今思えば、プールに入っていると夏バテせずに済むからだったかもしれません。でも、体育の成績は常に地を這うものでした。他のスポーツは苦手でからっきし駄目だったのです。走る、打つ、投げる、どれをとってもまるっきり駄目でした。運動能力ゼロに近かったかもしれません。しかし、水泳となると全くの別物で、クラスでトップレベルに豹変しました。その理由のひとつには、小さい頃、喘息治療のため、毎週のようにプールに通っていたこともあげられるとおもいますが、それに加えて、夏の暑さを逃れるための小さい頃からのプール通いがあったかもしれません。
夏になるとなんとか、エアコン以外の方法で涼しさを感じられる努力をしてみるのですが、必ず8月末が近づいてくる頃にはバテと寝不足で目の下にクマが出来て体重も減ってしまいます。
そこで今日の一枚。

EACH TIME
大滝詠一
CBSソニー (Niagara)CSCL-1664
このCDは「ロング・バケイション」に続くオリジナル・アルバムとして84年にリリースされ、大瀧詠一氏初のオリコン・チャートで1位に輝いた作品。もちろん当時はLPレコードというメディアでした。私はオリジナルのLPも持っていますが先日来から書いているようにいまはLPが聞ける環境を持っていないのでこのCDしか聞くことが出来ません。
作詞家の松本隆氏とアルバム全曲をコラボレートした内容になっています。、サウンド的には「A LONG VACATION」よりさらに凝った作りとなっていますが、まさに大瀧ワールド、Naiagaraサウンドです。アルバムには
1.魔法の瞳
2.夏のペーパーバック
3.木の葉のスケッチ
4.恋のナックルボール
5.銀色のジェット
6.1969年のドラッグレース
7.ガラス壜の中の船
8.ペパーミント・ブルー
9.レイクサイド・ストーリー
の計9曲がクレジットされています。
「EACH TIME 20th Annniversary Edition」というアルバムが先日発売されさらにボーナストラックが収録されているようなので、これから購入される方はこちらを選んでも良いかもしれません。
ちょっぴり切ない松本氏の歌詞とNaiagaraサウンドを聴きながら木陰で涼めたら、夏も乗り切れる?かも知れません。以前に紹介した「ロング・バケイション」とともに、これからの季節に聴くのにオススメの一枚です。
2008年05月10日
それなりの悩み。
今日は夕方より少し雨模様。小雨の降るお天気となりました。
さて、今年も私が参加する演奏会がもう既にいくつか決定しています。そう考えると今年はちょっと忙しい一年になりそうです。11月には毎年恒例のアンサンブルコンサートがあります。こちらは、クラシカルな曲や、ラージアンサンブル有り、のかなりハードな演奏会です。数年前、わざわざ編曲を依頼してビゼーの「アルルの女」をメイン曲にしたことがあります。
そこで今日の一枚。
ビゼー「アルルの女」、「カルメン」組曲
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON (ポリドール) FOOL-23021
このCDはデュトワ/モントリオール響によるビゼーの2大名曲の演奏。「アルルの女」の方は有名なアルトサックスのソロがあります。あのアルトサックスのソロがあるためにサックスを吹く人はやはりカラヤン/ベルリンフィルの演奏を愛聴している方が多いと思います。なぜなら、カラヤン/ベルリンフィルはサックスソロがあの、巨匠ダニエル・デファイエによるものだからです。
私もあのデファイエ氏の音色と演奏は素晴らしいものだと思うのですが、カラヤンの演奏は派手な演奏効果を狙いすぎのような気がしてあまり好きではありません。何よりもカラヤンの演奏、知ってか知らずかは不明ですが、明らかに楽譜の解釈が間違っています。第二組曲の最後の曲「ファランドール」の楽譜は"tamburello"という記述があるのですが、この楽器は所謂「タンバリン」のことではなくて、「プロヴァンス風太鼓」の「タンブール」と言う別の楽器です。しかしカラヤンはこれを平気でタンバリンで演奏しています。演奏効果を狙った「わざと」かもしれないのですが、曲は派手になるものの、何となく曲のイメージが損なわれている気がしてしかたありません。
デュトワの演奏は指定どおり、タンブールで演奏されています。やはり、フランス物の音楽を得意としているためでしょうか。演奏自体はデュトワらしいすっきりとした、洒脱な演奏です。人によっては物足りなさを感じるかもしれませんが、大げさなアゴーギグがない分だけ、聞きやすい演奏ともいえると思います。
オーケストラの中でのサクソフォーンの演奏を聴いてみたい方、また、ビゼーの「アルルの女」、「カルメン」を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、今年も私が参加する演奏会がもう既にいくつか決定しています。そう考えると今年はちょっと忙しい一年になりそうです。11月には毎年恒例のアンサンブルコンサートがあります。こちらは、クラシカルな曲や、ラージアンサンブル有り、のかなりハードな演奏会です。数年前、わざわざ編曲を依頼してビゼーの「アルルの女」をメイン曲にしたことがあります。
そこで今日の一枚。
ビゼー「アルルの女」、「カルメン」組曲
指揮:シャルル・デュトワ
モントリオール交響楽団
LONDON (ポリドール) FOOL-23021
このCDはデュトワ/モントリオール響によるビゼーの2大名曲の演奏。「アルルの女」の方は有名なアルトサックスのソロがあります。あのアルトサックスのソロがあるためにサックスを吹く人はやはりカラヤン/ベルリンフィルの演奏を愛聴している方が多いと思います。なぜなら、カラヤン/ベルリンフィルはサックスソロがあの、巨匠ダニエル・デファイエによるものだからです。
私もあのデファイエ氏の音色と演奏は素晴らしいものだと思うのですが、カラヤンの演奏は派手な演奏効果を狙いすぎのような気がしてあまり好きではありません。何よりもカラヤンの演奏、知ってか知らずかは不明ですが、明らかに楽譜の解釈が間違っています。第二組曲の最後の曲「ファランドール」の楽譜は"tamburello"という記述があるのですが、この楽器は所謂「タンバリン」のことではなくて、「プロヴァンス風太鼓」の「タンブール」と言う別の楽器です。しかしカラヤンはこれを平気でタンバリンで演奏しています。演奏効果を狙った「わざと」かもしれないのですが、曲は派手になるものの、何となく曲のイメージが損なわれている気がしてしかたありません。
デュトワの演奏は指定どおり、タンブールで演奏されています。やはり、フランス物の音楽を得意としているためでしょうか。演奏自体はデュトワらしいすっきりとした、洒脱な演奏です。人によっては物足りなさを感じるかもしれませんが、大げさなアゴーギグがない分だけ、聞きやすい演奏ともいえると思います。
オーケストラの中でのサクソフォーンの演奏を聴いてみたい方、また、ビゼーの「アルルの女」、「カルメン」を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年05月09日
演奏会を終えると。
今日は汗ばむほどの陽気となりました。間違いなく梅雨が、夏が近づいてきています。
さて、高松ウインドシンフォニーでは、いつも演奏会が終わるとGWに突入するため、2週間(2回分)練習がお休みになることが多いのですが、今年は少し様相が違います。連休後も行事が入っているため、お休みは1週間のみ。
ところで演奏会は意外に体力を消耗します。準備から始まって、リハ、本番、片付けという長丁場なので当然といえば当然です。そして体力だけでなく精神力もかなり消耗します。演奏会の間集中力を持続することはかなりきびしいことなのです。お酒が飲める人はお酒を飲んでその辺を解消していた利するらしいのですが、下戸な私はお酒を飲むと逆に大変なことになります。ほっとけば徐々に回復するのですが、何かしらの方法で消耗を回復したい気もします。なかなか難しいのですが。以前は本番の後、神経が高ぶって一晩寝られないこともしばしばでした。
そこで今日の一枚。

アディエマス*聖なる海の歌声
東芝EMI (ヴァージン)VJCP-25180
このCDはカール・ジェンキンスとマイク・ラトリッジによるアルバム。基本的にシンセサイザー+オーケストラ+ヴォーカルになっています。
何となく不思議なサウンドがします。民族音楽風でもあり、イージーリスニング風でもあり、電子音楽風でもあり、という非常に表現しにくい音楽です。
尚、タイトルは「聖なる海の歌声」ですが、ポール・ウィンターのようにイルカやシャチと一緒に演奏しているようなものではなく、あくまで曲のタイトルとしてのものです。なので、あのイルカミュージックが苦手な人でも、気にする事無く聴けます。
曲は何となく落ち着くものです。まさに深い海のそこにいて、明るい地上の世界を見上げるような感覚を受ける音楽です。アイリッシュミュージックのようでもあり、オリエンタルチックでもあり、純粋にクラシカルでもありといった印象です。ジャンルが無いような感覚なのですがなぜかそれが逆に懐かしいような、不思議な感覚を与えてくれます。精神を落ち着けてくれるだけではなく何か力強いものを与えてくれるアルバムのような気がします。
何かで消耗して疲れている方、また、これから、体力や精神力を使うという方にオススメの一枚です。
さて、高松ウインドシンフォニーでは、いつも演奏会が終わるとGWに突入するため、2週間(2回分)練習がお休みになることが多いのですが、今年は少し様相が違います。連休後も行事が入っているため、お休みは1週間のみ。
ところで演奏会は意外に体力を消耗します。準備から始まって、リハ、本番、片付けという長丁場なので当然といえば当然です。そして体力だけでなく精神力もかなり消耗します。演奏会の間集中力を持続することはかなりきびしいことなのです。お酒が飲める人はお酒を飲んでその辺を解消していた利するらしいのですが、下戸な私はお酒を飲むと逆に大変なことになります。ほっとけば徐々に回復するのですが、何かしらの方法で消耗を回復したい気もします。なかなか難しいのですが。以前は本番の後、神経が高ぶって一晩寝られないこともしばしばでした。
そこで今日の一枚。

アディエマス*聖なる海の歌声
東芝EMI (ヴァージン)VJCP-25180
このCDはカール・ジェンキンスとマイク・ラトリッジによるアルバム。基本的にシンセサイザー+オーケストラ+ヴォーカルになっています。
何となく不思議なサウンドがします。民族音楽風でもあり、イージーリスニング風でもあり、電子音楽風でもあり、という非常に表現しにくい音楽です。
尚、タイトルは「聖なる海の歌声」ですが、ポール・ウィンターのようにイルカやシャチと一緒に演奏しているようなものではなく、あくまで曲のタイトルとしてのものです。なので、あのイルカミュージックが苦手な人でも、気にする事無く聴けます。
曲は何となく落ち着くものです。まさに深い海のそこにいて、明るい地上の世界を見上げるような感覚を受ける音楽です。アイリッシュミュージックのようでもあり、オリエンタルチックでもあり、純粋にクラシカルでもありといった印象です。ジャンルが無いような感覚なのですがなぜかそれが逆に懐かしいような、不思議な感覚を与えてくれます。精神を落ち着けてくれるだけではなく何か力強いものを与えてくれるアルバムのような気がします。
何かで消耗して疲れている方、また、これから、体力や精神力を使うという方にオススメの一枚です。
タグ :アディエマス
2008年05月08日
アンコールとハプニング。
今日も良いお天気でした。ゴールデンウィークも終わって、今日から出勤です。
さて、演奏会にはアンコールというものがつき物です。プロの演奏会でもアンコールにこたえて1曲か2曲はプログラムに無い曲が演奏されることが多いようです。私の住む香川県では何故か演奏会の時の拍手が寒々としていて(内の団体に限らずプロオケの演奏でも)音楽を愛する人間にとってはさびしーい、結果になりがちです。以前、演奏会で最後の曲が終わって指揮者が一旦引っ込んだら拍手がやんでしまい、気まずーい空気が会場に流れました。指揮者が再登場して拍手が再開し、事なきを得たのですが、あの間の悪さはステージにいる演奏者にとっては結構耐えがたいものでした。もしかしたら、演奏がまずかったせいでアンコールが来なかったのかもしれませんが、折角アンコールも練習している手前、アンコールを演奏しないわけには行かないのです。
これは私が勝手に思うことなのですが、観客は「どうせアンコールも演奏するんだろ。」と言う気持ちで拍手を止めてしまったのではないかという気がします。それならばそれで観客のマナーの悪さを感じるのですが。
マナーといえば、この田舎では演奏会のマナーもあまり良いとは言えません。遅れてやってきて演奏中の出入りはご遠慮ください、この曲が終わるまでお待ちください、といわれたおばちゃんが何で入れてくれないんだ、とごねて扉の係の人間と押し問答になったとか、演奏中に携帯がなるわ、子どもがぎゃーぎゃー無くわ、ということが多すぎます。幸いこの間の演奏会ではそれは無かったようですが。
さて、アンコールのハプニングですが、今までの演奏会のなかでもいくつか体験したことがあります。。とあるパート全落ち事件。俗に落ちるとは、演奏中にふけない部分が出来てしまうこと。つまり、音が落ちて存在しなくなることを言います。で、そこがソロだったりすると音楽に空白が出来てしまうわけです。とくに練習量が少ないアンコールなどでは危険で今回も同じパートの人間が全員吹けずに落ちてしばし空白。(ウチのパートではありませんでしたが、いつ何時同じことをしてしまうか判らないので笑えません)
もちろん、アンコールでなくても、飛び出し、落ち、などは発生します。稀にプロの演奏会などでも同じ光景を見るぐらいなのでアマチュアの我々なんかは日常茶飯事です。本当はそれではいけないのですが、予防しても事故は起こるものなので、練習して確立を出来るだけ提げる努力しかありません。
そこで今日の一枚。
プロコフィエフ(淀彰編曲)/バレエ音楽「ロメオとジュリエット」
指揮:フレデリック・フェネル
東京佼成ウインドオーケストラ
佼成出版 KOCD-3311
このCDは1986年と1987年に新宿文化センターにて行なわれた構成ウインドオーケストラの定期公演の一部を収録したもの。他にレスピーギのローマの噴水や、コダーイのガランタ組曲なども収録されています。
演奏はどれをとっても佼成ウインドらしいすっきりとしたサウンドでクオリティーも高いものです。ライブにもかかわらず、スタジオ録音とあまりかわらないクオリティーだと思います。
ただ…プロの演奏にとっては致命的と思われるほどの事故が…あります。「ロメオとジュリエット」の曲でGP(ゼネラル・ポーズ)が存在するのですが、そこでクラリネットが一人飛び出しをやってます。飛び出しも凄いですがもっと凄いのはそれをそのまま音源にして発売してしまうところかもしれません。空白の部分なら100分の1秒あるいは1000分の1秒にオーダーで音をつないだり編集できるはずなのにそれも行なっていません。何故かは不明ですが。もし、この飛び出しをやった人がエキストラだったりしたら次から絶対に呼んでくれません。団員だったとしても周囲から非難の嵐ではなかったかと思います。結構、笑い事ですまない状態のはずです。
飛び出しのことばかり書いてしまいましたが、フレデリック・フェネル氏の指揮ということもあり、他の演奏もクオリティーの高いものになっています。因みにプロの大ミスが収録されたCDを私は他にも所有しています。(もしかしてそっちの方が聴くに耐えないかも知れませんが。)
吹奏楽がお好きな方、プロの「飛び出し」を聴いてみたい方、ローマの噴水の吹奏楽版が聞いてみたい方、演奏会で飛び出ししてしまった自分を慰め勇気付けたい方にオススメの一枚です。
さて、演奏会にはアンコールというものがつき物です。プロの演奏会でもアンコールにこたえて1曲か2曲はプログラムに無い曲が演奏されることが多いようです。私の住む香川県では何故か演奏会の時の拍手が寒々としていて(内の団体に限らずプロオケの演奏でも)音楽を愛する人間にとってはさびしーい、結果になりがちです。以前、演奏会で最後の曲が終わって指揮者が一旦引っ込んだら拍手がやんでしまい、気まずーい空気が会場に流れました。指揮者が再登場して拍手が再開し、事なきを得たのですが、あの間の悪さはステージにいる演奏者にとっては結構耐えがたいものでした。もしかしたら、演奏がまずかったせいでアンコールが来なかったのかもしれませんが、折角アンコールも練習している手前、アンコールを演奏しないわけには行かないのです。
これは私が勝手に思うことなのですが、観客は「どうせアンコールも演奏するんだろ。」と言う気持ちで拍手を止めてしまったのではないかという気がします。それならばそれで観客のマナーの悪さを感じるのですが。
マナーといえば、この田舎では演奏会のマナーもあまり良いとは言えません。遅れてやってきて演奏中の出入りはご遠慮ください、この曲が終わるまでお待ちください、といわれたおばちゃんが何で入れてくれないんだ、とごねて扉の係の人間と押し問答になったとか、演奏中に携帯がなるわ、子どもがぎゃーぎゃー無くわ、ということが多すぎます。幸いこの間の演奏会ではそれは無かったようですが。
さて、アンコールのハプニングですが、今までの演奏会のなかでもいくつか体験したことがあります。。とあるパート全落ち事件。俗に落ちるとは、演奏中にふけない部分が出来てしまうこと。つまり、音が落ちて存在しなくなることを言います。で、そこがソロだったりすると音楽に空白が出来てしまうわけです。とくに練習量が少ないアンコールなどでは危険で今回も同じパートの人間が全員吹けずに落ちてしばし空白。(ウチのパートではありませんでしたが、いつ何時同じことをしてしまうか判らないので笑えません)
もちろん、アンコールでなくても、飛び出し、落ち、などは発生します。稀にプロの演奏会などでも同じ光景を見るぐらいなのでアマチュアの我々なんかは日常茶飯事です。本当はそれではいけないのですが、予防しても事故は起こるものなので、練習して確立を出来るだけ提げる努力しかありません。
そこで今日の一枚。
プロコフィエフ(淀彰編曲)/バレエ音楽「ロメオとジュリエット」
指揮:フレデリック・フェネル
東京佼成ウインドオーケストラ
佼成出版 KOCD-3311
このCDは1986年と1987年に新宿文化センターにて行なわれた構成ウインドオーケストラの定期公演の一部を収録したもの。他にレスピーギのローマの噴水や、コダーイのガランタ組曲なども収録されています。
演奏はどれをとっても佼成ウインドらしいすっきりとしたサウンドでクオリティーも高いものです。ライブにもかかわらず、スタジオ録音とあまりかわらないクオリティーだと思います。
ただ…プロの演奏にとっては致命的と思われるほどの事故が…あります。「ロメオとジュリエット」の曲でGP(ゼネラル・ポーズ)が存在するのですが、そこでクラリネットが一人飛び出しをやってます。飛び出しも凄いですがもっと凄いのはそれをそのまま音源にして発売してしまうところかもしれません。空白の部分なら100分の1秒あるいは1000分の1秒にオーダーで音をつないだり編集できるはずなのにそれも行なっていません。何故かは不明ですが。もし、この飛び出しをやった人がエキストラだったりしたら次から絶対に呼んでくれません。団員だったとしても周囲から非難の嵐ではなかったかと思います。結構、笑い事ですまない状態のはずです。
飛び出しのことばかり書いてしまいましたが、フレデリック・フェネル氏の指揮ということもあり、他の演奏もクオリティーの高いものになっています。因みにプロの大ミスが収録されたCDを私は他にも所有しています。(もしかしてそっちの方が聴くに耐えないかも知れませんが。)
吹奏楽がお好きな方、プロの「飛び出し」を聴いてみたい方、ローマの噴水の吹奏楽版が聞いてみたい方、演奏会で飛び出ししてしまった自分を慰め勇気付けたい方にオススメの一枚です。
タグ :ロメオとジュリエットローマの噴水
2008年05月07日
分量。
一応、先日の似非蒸しパンのレシピらしきものに、分量を書いていませんでしたので…。
チョコチップ
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒(ダークラム)適量
○板チョコ一枚
ラムレーズン
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒(ダークラム)適量
○レーズン適量
抹茶&栗&あん
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒適量
○ゆで小豆缶詰小1缶
○栗の甘露煮小1瓶
○抹茶5~6グラム
ということで。
チョコチップ
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒(ダークラム)適量
○板チョコ一枚
ラムレーズン
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒(ダークラム)適量
○レーズン適量
抹茶&栗&あん
○ホットケーキミックス200グラム
○牛乳160cc
○ラム酒適量
○ゆで小豆缶詰小1缶
○栗の甘露煮小1瓶
○抹茶5~6グラム
ということで。
2008年05月07日
委嘱作品を演奏した。
昨日の夕方からの雨模様等は一転、今日はいい天気でした。外を出歩くと少し汗ばむぐらいです。
自転車で風を切って走るのが心地よい一日でしたが、結局出かけず家でゴロゴロ。
さて、昨日も書いた高松ウインドシンフォニー第20回記念演奏会でのこと。その時えんそうした委嘱作品の演奏について少し書きたいと思います。委嘱作品とは、判りやすくいえばバンドの依頼でかかれた曲です。曲を書いてもらうためにはそれなりの対価が必要なのですが、今回は、版権を買い取らない、ということで格安で書いていただきました。作曲者の田中先生が、高い値段で長大な曲を書くよりも、演奏されることが多い小品を書きたい、という希望を提示されたため、15分から、20分程度の曲となりましたが、吹奏楽の演奏会ではこれだけの長さがあれば、十分メインの曲として通用します。8分程度の曲2曲で構成されているため、吹奏楽コンクールの自由曲としても演奏してもらえそうです。どこかの出版社かた、是非出版してください。
当時、委嘱作品なので間違いなく世界初演であったのですが、曲の構成やつくりも難解な部分がなく比較的取り組みやすかったと思います。逆にこんな曲を吹奏楽コンクールの課題曲にして欲しいと、思ったほどでした。曲名は「東洋の伝説」第一楽章が「太陽礼拝」第二楽章が「北斗礼拝」というタイトルになっています。一楽章はどちらかというと邦楽チックなイメージの曲、二楽章は大陸の騎馬民族系のリズムに支配された音楽です。我々の演奏しかないので、聞いてもらうことが出来ないのが残念ですが、とてもいい曲です。もし、楽譜が出版されたら、たくさんの方に演奏してもらいたいと思います。
特に思うのですが、邦人作品の吹奏楽曲はコンクールの課題曲にとどまらず最近難解なものが多い気がします。その中では、今回の「東洋の伝説」は貴重なレパートリーになりうる曲ではないかと思います。また、フランスの出版社から出版される予定があるようです。
そこで今日の一枚。

古祀(AN ANCIENT FESTIVAL)
指揮:秋山和慶
佼成ウインドオーケストラ
佼成出版 KOCD-3075
このCDは佼成ウインドオーケストラによる邦人作品集。元々はレコードでリリースされていたものなので佼成ウインドのかなり初期の録音集のなかの一枚です。アナログ録音、デジタルリマスター盤です。既に亡くなった、兼田敏氏のシンフォニック・ヴァリエーションと保科洋氏の「古祀」が同じディスクに入っていることもおもしろい一枚です。この二人が犬猿の中だったことは吹奏楽界ではかなり有名な話なので、それを考えるとおもしろいと思います。
櫛田テツ之扶(テツの漢字が出ないので)氏の「飛鳥」などは吹奏楽をされた方なら演奏したことがある方も多いのではないでしょうか。あの、ほら貝チックなホルンとペダルティンパニを使ったティンパニーのグリッサンドは衝撃的でした。「古祀」とともに和のテイストたっぷりの曲です。
吹奏楽の「和」の曲を聴いてみたい方、以前からよく取り上げられている邦人作品を聴いてみたい方、もちろん、演奏したことがある方にもオススメの一枚です。
自転車で風を切って走るのが心地よい一日でしたが、結局出かけず家でゴロゴロ。
さて、昨日も書いた高松ウインドシンフォニー第20回記念演奏会でのこと。その時えんそうした委嘱作品の演奏について少し書きたいと思います。委嘱作品とは、判りやすくいえばバンドの依頼でかかれた曲です。曲を書いてもらうためにはそれなりの対価が必要なのですが、今回は、版権を買い取らない、ということで格安で書いていただきました。作曲者の田中先生が、高い値段で長大な曲を書くよりも、演奏されることが多い小品を書きたい、という希望を提示されたため、15分から、20分程度の曲となりましたが、吹奏楽の演奏会ではこれだけの長さがあれば、十分メインの曲として通用します。8分程度の曲2曲で構成されているため、吹奏楽コンクールの自由曲としても演奏してもらえそうです。どこかの出版社かた、是非出版してください。
当時、委嘱作品なので間違いなく世界初演であったのですが、曲の構成やつくりも難解な部分がなく比較的取り組みやすかったと思います。逆にこんな曲を吹奏楽コンクールの課題曲にして欲しいと、思ったほどでした。曲名は「東洋の伝説」第一楽章が「太陽礼拝」第二楽章が「北斗礼拝」というタイトルになっています。一楽章はどちらかというと邦楽チックなイメージの曲、二楽章は大陸の騎馬民族系のリズムに支配された音楽です。我々の演奏しかないので、聞いてもらうことが出来ないのが残念ですが、とてもいい曲です。もし、楽譜が出版されたら、たくさんの方に演奏してもらいたいと思います。
特に思うのですが、邦人作品の吹奏楽曲はコンクールの課題曲にとどまらず最近難解なものが多い気がします。その中では、今回の「東洋の伝説」は貴重なレパートリーになりうる曲ではないかと思います。また、フランスの出版社から出版される予定があるようです。
そこで今日の一枚。

古祀(AN ANCIENT FESTIVAL)
指揮:秋山和慶
佼成ウインドオーケストラ
佼成出版 KOCD-3075
このCDは佼成ウインドオーケストラによる邦人作品集。元々はレコードでリリースされていたものなので佼成ウインドのかなり初期の録音集のなかの一枚です。アナログ録音、デジタルリマスター盤です。既に亡くなった、兼田敏氏のシンフォニック・ヴァリエーションと保科洋氏の「古祀」が同じディスクに入っていることもおもしろい一枚です。この二人が犬猿の中だったことは吹奏楽界ではかなり有名な話なので、それを考えるとおもしろいと思います。
櫛田テツ之扶(テツの漢字が出ないので)氏の「飛鳥」などは吹奏楽をされた方なら演奏したことがある方も多いのではないでしょうか。あの、ほら貝チックなホルンとペダルティンパニを使ったティンパニーのグリッサンドは衝撃的でした。「古祀」とともに和のテイストたっぷりの曲です。
吹奏楽の「和」の曲を聴いてみたい方、以前からよく取り上げられている邦人作品を聴いてみたい方、もちろん、演奏したことがある方にもオススメの一枚です。
2008年05月06日
連休中。その3
今日ででGWも終わり、世間は明日からお仕事モードなのでしょうか。
さて、高松ウインドシンフォニーでは、数年前までゲストを迎えてコンチェルトを毎年のように演奏していました。ただ、最近はコンチェルトを取り上げていません。最後のコンチェルトの演奏は第20回の記念定期演奏会で、トランペットと、クラリネットのゲストをお呼びしてコンチェルトをやりました。それまでにもトランペット、クラリネット、フルート、マリンバ、トロンボーンなどの方にコンチェルトを演奏してもらいました。第20回の演奏会は記念ということでプロのミュージシャンを2人お招きしてのコンチェルトでした。トランペットは各方面でプロとして活躍している香川県出身の寺島昌夫氏、クラリネットはシエナウインドでも活躍していた近藤悟史氏でした。
吹奏楽における木管楽器のコンチェルトは特に気を使います。特にフルートやクラリネットのコンチェルトで、もとの伴奏がオーケストラで、それを編曲したものだったりすると、かなり気を使います。オーケストラと、吹奏楽では根本的なダイナミックレンジがちがいます。弱音のレンジもオケにはなかなか勝てません。弦楽器には必殺、弱音器というものもあるので吹奏楽ではかないっこ無いのです。
で、その当時のコンチェルトの本番ですが、トランペットの方は私は降り番(演奏に参加していない)だったので、聴くだけでした。感想は、本番が一番いい演奏だったな、と言うことと、プロの方も緊張しているんだな、ということでした。演奏に明らかに緊張感がありました。これも、練習のときや、リハのときを知っているから判ることだと思うのですが。でも、寺島さん、熱い、いい演奏でした。
クラリネットの方は私もステージに乗ったのですが、先日書いた通り、高校時代の恩師、I先生の指揮に緊張し、さらに弱音の発音に緊張し、さらに本番ということで緊張し、という緊張の連続でした。寿命がちぢむ思いでした。(笑)こちらも、本番の演奏が一番いよい演奏だったと思います。近藤さんは中学校の時の先輩なので、身近に凄い人がいるという思いで感激しました。
そこで今日の一枚。
ロッシーニ&クロンマー/クラリネット協奏曲
ザビーネ・マイヤー(クラリネット)
ウォルフガング・マイヤー(クラリネット)
指揮:イエルク・フェルバー
ヴェルテンブルグ室内管弦楽団
東芝EMI TOCE-6111
このCDはベルリンフィルのクラリネット奏者も勤めたことがあるザビーネ・マイヤーとその兄ウォルフガング・マイヤーがそれぞれにクラリネットソロを吹いているコンチェルトのアルバムです。
この中のロッシー二作曲の「クラリネットと管弦楽のための序奏、主題と変奏 変ロ長調」を今回の演奏会で取り上げました。このCDの中ではザビーネ・マイヤーが吹いています。
このCDの演奏の方ですが、とにかく凄い、の一言に尽きます。極端に速いテンポ、完璧なまでのフレージングと技術、何をとっても超一級品です。今回我々の演奏会にきてくださった近藤さんでさえ、あの速さでは無理、吹けない、と仰っていたほどです。
一つ、残念なのは演奏のリピートの2回目に当たる部分で明らかに演奏をつないだ後が見られること。リードを変えたのか、録音した時間が極端に違うのか判りませんが、響きが別物のようになってしまいます。リテイクを繰り返す録音現場では結構、一発撮りではないことも多いようです。
しかし、それをさしいても素晴らしい演奏です。
クラリネットを吹かれている方、クラリネットのコンチェルトを聴いてみたい方、少し上品でおしゃれな音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、高松ウインドシンフォニーでは、数年前までゲストを迎えてコンチェルトを毎年のように演奏していました。ただ、最近はコンチェルトを取り上げていません。最後のコンチェルトの演奏は第20回の記念定期演奏会で、トランペットと、クラリネットのゲストをお呼びしてコンチェルトをやりました。それまでにもトランペット、クラリネット、フルート、マリンバ、トロンボーンなどの方にコンチェルトを演奏してもらいました。第20回の演奏会は記念ということでプロのミュージシャンを2人お招きしてのコンチェルトでした。トランペットは各方面でプロとして活躍している香川県出身の寺島昌夫氏、クラリネットはシエナウインドでも活躍していた近藤悟史氏でした。
吹奏楽における木管楽器のコンチェルトは特に気を使います。特にフルートやクラリネットのコンチェルトで、もとの伴奏がオーケストラで、それを編曲したものだったりすると、かなり気を使います。オーケストラと、吹奏楽では根本的なダイナミックレンジがちがいます。弱音のレンジもオケにはなかなか勝てません。弦楽器には必殺、弱音器というものもあるので吹奏楽ではかないっこ無いのです。
で、その当時のコンチェルトの本番ですが、トランペットの方は私は降り番(演奏に参加していない)だったので、聴くだけでした。感想は、本番が一番いい演奏だったな、と言うことと、プロの方も緊張しているんだな、ということでした。演奏に明らかに緊張感がありました。これも、練習のときや、リハのときを知っているから判ることだと思うのですが。でも、寺島さん、熱い、いい演奏でした。
クラリネットの方は私もステージに乗ったのですが、先日書いた通り、高校時代の恩師、I先生の指揮に緊張し、さらに弱音の発音に緊張し、さらに本番ということで緊張し、という緊張の連続でした。寿命がちぢむ思いでした。(笑)こちらも、本番の演奏が一番いよい演奏だったと思います。近藤さんは中学校の時の先輩なので、身近に凄い人がいるという思いで感激しました。
そこで今日の一枚。
ロッシーニ&クロンマー/クラリネット協奏曲
ザビーネ・マイヤー(クラリネット)
ウォルフガング・マイヤー(クラリネット)
指揮:イエルク・フェルバー
ヴェルテンブルグ室内管弦楽団
東芝EMI TOCE-6111
このCDはベルリンフィルのクラリネット奏者も勤めたことがあるザビーネ・マイヤーとその兄ウォルフガング・マイヤーがそれぞれにクラリネットソロを吹いているコンチェルトのアルバムです。
この中のロッシー二作曲の「クラリネットと管弦楽のための序奏、主題と変奏 変ロ長調」を今回の演奏会で取り上げました。このCDの中ではザビーネ・マイヤーが吹いています。
このCDの演奏の方ですが、とにかく凄い、の一言に尽きます。極端に速いテンポ、完璧なまでのフレージングと技術、何をとっても超一級品です。今回我々の演奏会にきてくださった近藤さんでさえ、あの速さでは無理、吹けない、と仰っていたほどです。
一つ、残念なのは演奏のリピートの2回目に当たる部分で明らかに演奏をつないだ後が見られること。リードを変えたのか、録音した時間が極端に違うのか判りませんが、響きが別物のようになってしまいます。リテイクを繰り返す録音現場では結構、一発撮りではないことも多いようです。
しかし、それをさしいても素晴らしい演奏です。
クラリネットを吹かれている方、クラリネットのコンチェルトを聴いてみたい方、少し上品でおしゃれな音楽を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年05月06日
連休中。その2
今日は午後から雨模様となりました。折角昨日洗車したのですが、マーフィーの法則のごとく見事に雨模様。
昼から父親が電気屋さんに買物に行くというので車に載せていきました。目的地は春日のデオデオとヤマダ電機。電動音波歯ブラシを買うんだそうな。
結局デオデオにて、ナショナル製の電動音波歯ブラシを購入しました。電動歯ブラシって何となく磨いているという実感が無いので私は今まで使ったことが無いのですが…。父親が何故急に思い立って購入にいたったか経緯は謎です。
そんなこんなで今日の一枚。

Double Edge /村田陽一ソリッド・ブラス
このアルバムはトロンボーン奏者の村田陽一氏率いるソリッドブラスのアルバム。サム・スカンク・ファンクなどが収録されています。なんといっても魅力はホーンとドラムだけで編成されたアンサンブルであること。エレキベースを使用せずチューバがベースラインを支えていることも魅力の一つです。しかもメンバーはいずれも実力派ぞろい。ドラムは村上ポンタ秀一氏、サクソフォーンには本多雅人氏が参加。トランペットにはエリック宮城氏も参加。ファンクなノリをホーンによるアンサンブルで体験することが出来ます。
ホーンアレンジの曲がお好きな方にオススメの一枚。
昼から父親が電気屋さんに買物に行くというので車に載せていきました。目的地は春日のデオデオとヤマダ電機。電動音波歯ブラシを買うんだそうな。
結局デオデオにて、ナショナル製の電動音波歯ブラシを購入しました。電動歯ブラシって何となく磨いているという実感が無いので私は今まで使ったことが無いのですが…。父親が何故急に思い立って購入にいたったか経緯は謎です。
そんなこんなで今日の一枚。

Double Edge /村田陽一ソリッド・ブラス
このアルバムはトロンボーン奏者の村田陽一氏率いるソリッドブラスのアルバム。サム・スカンク・ファンクなどが収録されています。なんといっても魅力はホーンとドラムだけで編成されたアンサンブルであること。エレキベースを使用せずチューバがベースラインを支えていることも魅力の一つです。しかもメンバーはいずれも実力派ぞろい。ドラムは村上ポンタ秀一氏、サクソフォーンには本多雅人氏が参加。トランペットにはエリック宮城氏も参加。ファンクなノリをホーンによるアンサンブルで体験することが出来ます。
ホーンアレンジの曲がお好きな方にオススメの一枚。
2008年05月05日
リベンジ。
先日失敗してパサパサになったホットケーキミックスを使った似非蒸しパン。
本日リベンジ。
作ったのは……
チョコチップ
抹茶&栗&あん
ラムレーズン
今回の材料は……
○ホットケーキミックス(これが無いと始まりません)
○牛乳
○レーズン
○ラム酒(ダークラム)
○栗の甘露煮
○ゆで小豆
○板チョコ
○抹茶
の3種類。
チョコチップのみ牛乳パックと、紙コップにて。
後は、なんと、どんぶり鉢で作ってみました。
チョコチップは前回通り。今回は卵が少々大きくても牛乳を減らさずやりました。むしろ牛乳大目。どうも牛乳は大目の方がしっとりとした仕上がりになるようです。それと、前回よりもマヨネーズを多めに入れました。水分と脂分がある程度入ると、しっとりとした出来上がりになるはず、と思ったのですが、ビンゴ。そして更に香りとしっとり感を出すためにダークラムを少々。前回とは違ってしっとりと出来上がりました。牛乳パックに流し込んでラップをかけ電子レンジへ3分。完成。綺麗に出来ました。チョコレートをもっと細かく刻んだ方が良かったかもしれません。紙コップのも同じようにして電子レンジへ。
抹茶は、綺麗に抹茶をとくのに苦労しました。少しずつ牛乳を抹茶に足していき、抹茶を練る様にしながら溶いていきます。牛乳を規定の量まで増やし綺麗に牛乳と抹茶が溶けたら卵に入れて更に綺麗に混ぜます。そしてダークラム投入(本当は抹茶リキュールがあるといいんですが…生憎ありませんでした)。さらにマヨネーズを投入。ホットケーキミックスの粉を加えてさらに綺麗に混ぜます。その中に刻んだ栗の甘露煮を。そして、どんぶり鉢にラップを敷き、ミックスとあんこを交互に入れていきます。あんこは今回はゆで小豆の小さい缶詰を使いました。あんこを入れるときにスプーンで散らしながら振り入れるように入れます。どんぶり鉢の3分の2ぐらいまで入れればOK。ラップをかけて電子レンジへ。約4分。
ラムレーズンはダークラムにレーズンを浸します。結構大目のダークラムにレーズンをどっぷり浸しました。酒くさーと思いつつも、20分くらいつけておきます。そして、卵と牛乳を混ぜ、マヨネーズを投入。ミックスを混ぜた物をラップをひいたどんぶり鉢へ。そして、ラムレーズンとミックスを交互に入れていきます。これもどんぶりの3分の2くらいまで入れてラップをかけて電子レンジへ。約4分。
実際、味に自信はありませんが、前回よりはしっとりとうまくいった模様。見てくれもそこそこでしたが、写真を撮り忘れてしまいました。
おそらくそのうちダッパーのブログにUPされるはず。
本日リベンジ。
作ったのは……
チョコチップ
抹茶&栗&あん
ラムレーズン
今回の材料は……
○ホットケーキミックス(これが無いと始まりません)
○牛乳
○レーズン
○ラム酒(ダークラム)
○栗の甘露煮
○ゆで小豆
○板チョコ
○抹茶
の3種類。
チョコチップのみ牛乳パックと、紙コップにて。
後は、なんと、どんぶり鉢で作ってみました。
チョコチップは前回通り。今回は卵が少々大きくても牛乳を減らさずやりました。むしろ牛乳大目。どうも牛乳は大目の方がしっとりとした仕上がりになるようです。それと、前回よりもマヨネーズを多めに入れました。水分と脂分がある程度入ると、しっとりとした出来上がりになるはず、と思ったのですが、ビンゴ。そして更に香りとしっとり感を出すためにダークラムを少々。前回とは違ってしっとりと出来上がりました。牛乳パックに流し込んでラップをかけ電子レンジへ3分。完成。綺麗に出来ました。チョコレートをもっと細かく刻んだ方が良かったかもしれません。紙コップのも同じようにして電子レンジへ。
抹茶は、綺麗に抹茶をとくのに苦労しました。少しずつ牛乳を抹茶に足していき、抹茶を練る様にしながら溶いていきます。牛乳を規定の量まで増やし綺麗に牛乳と抹茶が溶けたら卵に入れて更に綺麗に混ぜます。そしてダークラム投入(本当は抹茶リキュールがあるといいんですが…生憎ありませんでした)。さらにマヨネーズを投入。ホットケーキミックスの粉を加えてさらに綺麗に混ぜます。その中に刻んだ栗の甘露煮を。そして、どんぶり鉢にラップを敷き、ミックスとあんこを交互に入れていきます。あんこは今回はゆで小豆の小さい缶詰を使いました。あんこを入れるときにスプーンで散らしながら振り入れるように入れます。どんぶり鉢の3分の2ぐらいまで入れればOK。ラップをかけて電子レンジへ。約4分。
ラムレーズンはダークラムにレーズンを浸します。結構大目のダークラムにレーズンをどっぷり浸しました。酒くさーと思いつつも、20分くらいつけておきます。そして、卵と牛乳を混ぜ、マヨネーズを投入。ミックスを混ぜた物をラップをひいたどんぶり鉢へ。そして、ラムレーズンとミックスを交互に入れていきます。これもどんぶりの3分の2くらいまで入れてラップをかけて電子レンジへ。約4分。
実際、味に自信はありませんが、前回よりはしっとりとうまくいった模様。見てくれもそこそこでしたが、写真を撮り忘れてしまいました。
おそらくそのうちダッパーのブログにUPされるはず。
2008年05月05日
最近の課題曲は難しすぎる。パート2
今日も比較的良いお天気でした。
連休で天気が良いとどこかに出かけたくなりますが、インドア派の私は家で音楽を聞いたり、楽器を拭いて(吹くんじゃなくて磨く方)みたりしています。
それでは、今日の一枚。

吹奏楽コンクール課題曲集VOL.4
1981~1985
SONY Record SRCR2208
このCDは昨日のCDと同じく全日本吹奏楽コンクール全国大会のライブ録音から、年代別に課題曲の演奏を集めたものです。機能紹介したCD同様、演奏団体もそれぞれ違います。懐かしの課題曲、「イリュージョン」、「吹奏楽のためのインヴェンション第一番」、「波の見える風景」などが収録されています。私の記憶ではこれらの課題曲の楽譜は今の課題曲のものに比べ、白く、大きい音符でかかれていました。つまり、複雑な音符が少なく、曲も短かったということです。昨日も書きましたが、それを見ても、今の課題曲は難しすぎるのだと感じます。
この時代の課題曲だった「東北地方の民謡によるコラージュ」や、「波の見える風景」などはいまや、いろいろな演奏会で演奏されたり、逆にコンクールの自由曲として取り上げられたりしています。せっかくの吹奏楽の新曲なので、コンクールだけで終わるのはもったいないと思うので、課題曲ももっといろいろな機会に演奏されるべきだとは思います。
吹奏楽部時代が懐かしい30代前半の方、昨日同様に昔の課題曲を聴いてみたい方、吹奏楽のオリジナル曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
連休で天気が良いとどこかに出かけたくなりますが、インドア派の私は家で音楽を聞いたり、楽器を拭いて(吹くんじゃなくて磨く方)みたりしています。
それでは、今日の一枚。

吹奏楽コンクール課題曲集VOL.4
1981~1985
SONY Record SRCR2208
このCDは昨日のCDと同じく全日本吹奏楽コンクール全国大会のライブ録音から、年代別に課題曲の演奏を集めたものです。機能紹介したCD同様、演奏団体もそれぞれ違います。懐かしの課題曲、「イリュージョン」、「吹奏楽のためのインヴェンション第一番」、「波の見える風景」などが収録されています。私の記憶ではこれらの課題曲の楽譜は今の課題曲のものに比べ、白く、大きい音符でかかれていました。つまり、複雑な音符が少なく、曲も短かったということです。昨日も書きましたが、それを見ても、今の課題曲は難しすぎるのだと感じます。
この時代の課題曲だった「東北地方の民謡によるコラージュ」や、「波の見える風景」などはいまや、いろいろな演奏会で演奏されたり、逆にコンクールの自由曲として取り上げられたりしています。せっかくの吹奏楽の新曲なので、コンクールだけで終わるのはもったいないと思うので、課題曲ももっといろいろな機会に演奏されるべきだとは思います。
吹奏楽部時代が懐かしい30代前半の方、昨日同様に昔の課題曲を聴いてみたい方、吹奏楽のオリジナル曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年05月04日
連休中。その1
連休本番、連休もあと3日となりました。
比較的良い天気の続くゴールデンウィークとなりそうです。
漸く炬燵を片付けて、夏モードにしました。
一応、黙々と片付けるのも何なので、音楽でも聴きながらと思いCDを適当にチョイスしました。本当にテキトーに選んだので、特に意味はないのですが…。
そこで今日の一枚。
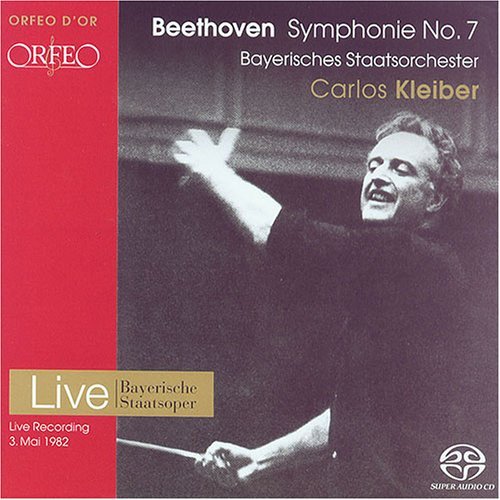
ベートーヴェン
交響曲第7番
カルロス・クライバー指揮/バイエルン国立管弦楽団
このCDは超名盤と言われている、カルロス・クライバー指揮によるベートーヴェン。1982年5月3日、カルロス・クライバーとバイエルン国立管弦楽団によって“カール・ベーム追悼”という名目で行われたコンサートのライヴです。燃え尽きるほどのライヴ感とクライバーらしいテンポ感。まさに熱演。ホールの異様ともいえる熱気が伝わってくるような演奏です。
この曲、最近では「のだめカンタービレ」の中にも登場し、1楽章の一部がかなり有名になりましたが、以前は色々なCMなどに終楽章が良く使われていた記憶があります。
TV「のだめ」の中に登場する演奏しか聞いたことの無い人には、かなり度肝を抜かれる演奏になること間違いなし。まさに熱狂のベートーヴェンです。
また、オーディオ的にも秀逸で、しかもSACDのハイブリッド版。ただし私はSACDの再生装置を持っていないので普通のCD再生しかしたことがありません。一度、SACD再生の音も聞いてみたいと思います。
熱狂的なベートーヴェンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
比較的良い天気の続くゴールデンウィークとなりそうです。
漸く炬燵を片付けて、夏モードにしました。
一応、黙々と片付けるのも何なので、音楽でも聴きながらと思いCDを適当にチョイスしました。本当にテキトーに選んだので、特に意味はないのですが…。
そこで今日の一枚。
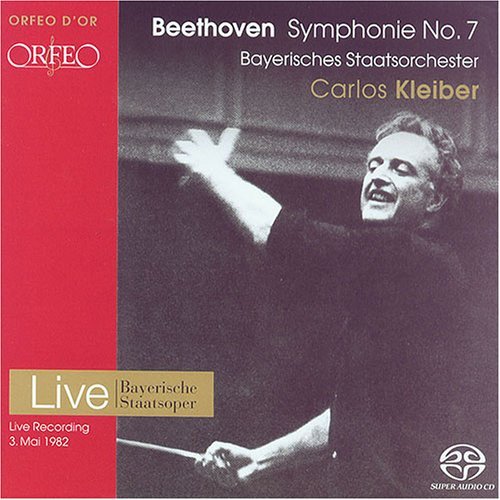
ベートーヴェン
交響曲第7番
カルロス・クライバー指揮/バイエルン国立管弦楽団
このCDは超名盤と言われている、カルロス・クライバー指揮によるベートーヴェン。1982年5月3日、カルロス・クライバーとバイエルン国立管弦楽団によって“カール・ベーム追悼”という名目で行われたコンサートのライヴです。燃え尽きるほどのライヴ感とクライバーらしいテンポ感。まさに熱演。ホールの異様ともいえる熱気が伝わってくるような演奏です。
この曲、最近では「のだめカンタービレ」の中にも登場し、1楽章の一部がかなり有名になりましたが、以前は色々なCMなどに終楽章が良く使われていた記憶があります。
TV「のだめ」の中に登場する演奏しか聞いたことの無い人には、かなり度肝を抜かれる演奏になること間違いなし。まさに熱狂のベートーヴェンです。
また、オーディオ的にも秀逸で、しかもSACDのハイブリッド版。ただし私はSACDの再生装置を持っていないので普通のCD再生しかしたことがありません。一度、SACD再生の音も聞いてみたいと思います。
熱狂的なベートーヴェンを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年05月03日
最近の課題曲は難しすぎる。
今日は良い天気の一日となりましたが、一日室内で掃除。連休にもかかわらず、ほとんど家から出ずに過ごしました。
さて、タイトルは変わりましたが、今日も定期演奏会のお話です。全日本吹奏楽コンクール課題曲の全曲演奏を今年も行ない年々、課題曲が難解で技術的にも難しくなっているような気がします。絶対に中学生向けの曲ではありません。
実際に、中高生に人気のある課題曲は最近の課題曲の中でもモティーフや仕組みがわかりやすい物である気がします。
吹奏楽コンクールに興味のない方が読むと、「何だコリャ?」なことを書いてしまいましたが、明日以降、残りの課題曲についても書いていきたいと思います。
さて、今日の一枚。

吹奏楽コンクール課題曲集VOL.3
1977~1980
SONY Record SRCR2207
このCDは全日本吹奏楽コンクール全国大会のライブ録音から、年代別に課題曲の演奏を集めたものです。当然、演奏団体もそれぞれ違います。懐かしの課題曲、「ディスコ・キッド」や「フェリスタス」、序曲「南の島から」などが収録されています。今の課題曲と比べると、明らかに技術的にも、曲の解釈も易しいものだと感じます。小難しい音楽を小手先でこねくり回すより、わかりやすい音楽を楽しく、美しく仕上げることの方が私はアマチュアのコンテスト向きだと思うのですが、いかがでしょう。今の課題曲は難しすぎます。中学生などは本番でも曲を理解できずに吹いてしまう人がたくさんいるのではないだろうかと思ってしまいます。
年代が古いことや、アマチュアのライブ録音ということもあって、完璧な演奏とはいえませんが、何ヶ月もかけて取り組んだ演奏だけあって、きっちりとした考えられた演奏になっています。
おもしろいことに、やはり、団体ごとのサウンドに特徴があったり、時代によって流行のサウンドがあったりすることが聴いてとれることでしょうか。
さて、タイトルは変わりましたが、今日も定期演奏会のお話です。全日本吹奏楽コンクール課題曲の全曲演奏を今年も行ない年々、課題曲が難解で技術的にも難しくなっているような気がします。絶対に中学生向けの曲ではありません。
実際に、中高生に人気のある課題曲は最近の課題曲の中でもモティーフや仕組みがわかりやすい物である気がします。
吹奏楽コンクールに興味のない方が読むと、「何だコリャ?」なことを書いてしまいましたが、明日以降、残りの課題曲についても書いていきたいと思います。
さて、今日の一枚。

吹奏楽コンクール課題曲集VOL.3
1977~1980
SONY Record SRCR2207
このCDは全日本吹奏楽コンクール全国大会のライブ録音から、年代別に課題曲の演奏を集めたものです。当然、演奏団体もそれぞれ違います。懐かしの課題曲、「ディスコ・キッド」や「フェリスタス」、序曲「南の島から」などが収録されています。今の課題曲と比べると、明らかに技術的にも、曲の解釈も易しいものだと感じます。小難しい音楽を小手先でこねくり回すより、わかりやすい音楽を楽しく、美しく仕上げることの方が私はアマチュアのコンテスト向きだと思うのですが、いかがでしょう。今の課題曲は難しすぎます。中学生などは本番でも曲を理解できずに吹いてしまう人がたくさんいるのではないだろうかと思ってしまいます。
年代が古いことや、アマチュアのライブ録音ということもあって、完璧な演奏とはいえませんが、何ヶ月もかけて取り組んだ演奏だけあって、きっちりとした考えられた演奏になっています。
おもしろいことに、やはり、団体ごとのサウンドに特徴があったり、時代によって流行のサウンドがあったりすることが聴いてとれることでしょうか。





