2008年07月13日
一日練習でした。
本日9時半、一宮のコミュニティーセンターに集合。
ダッパー、サックスアンサンブルでの、
まずは州崎寺に向けたカルテットの練習。
メンバーは

この人と、

この人。

そしてこの人。
でもって11時半より、再来週の26日牟礼小学校でのイベント演奏の練習。
で、加わったのが

この人。
昼食のための休憩を12時40分から20分間。
で、さらに、加わって13時より


州崎寺での大編成の練習。
その後、州崎寺での別のカルテットの練習で16時半まで。
ということで練習終了。
ダッパー、サックスアンサンブルでの、
まずは州崎寺に向けたカルテットの練習。
メンバーは
この人と、
この人。
そしてこの人。
でもって11時半より、再来週の26日牟礼小学校でのイベント演奏の練習。
で、加わったのが
この人。
昼食のための休憩を12時40分から20分間。
で、さらに、加わって13時より
州崎寺での大編成の練習。
その後、州崎寺での別のカルテットの練習で16時半まで。
ということで練習終了。
2008年07月13日
世の中と疲れ。
さて、最近たいしたこともしていないのになぜか疲れがたまっている気がします。顎関節症で、噛み合わせが悪いせいもあるのでしょうが、肩こりから来る頭痛に悩まされ、体からは何となくだるさが取れない気がします。睡眠も暑さにまいりながらも割と十分にとっているようには思うのですが、疲れが今ひとつ取りきれません。
私は、中学校の時から吹奏楽部でサックスを吹き始めました。当然、その時からアンサンブルなどもしていました。ただ、私の学生時代は、部活動などでも、漸く根性論から脱却し、効率的な練習が浸透し始めた頃でした。なので、私が中学生の頃はまだまだ、吹奏楽部であるのにもかかわらず、腹筋、走りこみ、などが日常的に行なわれていました。今は、あまり聞きません。(でも、田舎の中学校とかに行くと、いまだに本気で、腹筋や走り込みで腹式呼吸いが出来るようになる、と信じられていたりして驚きます。)もちろん、運動部でも、水分の補給を制限する、という行為が結構あたりまえに行なわれていました。
まあ、楽器の技術は向上しなくても、根性はついたので、その点は、苦しく長いロングトーンに対しても期待が持てることを考えて頑張ったり、練習の苦しさが、たいしたものではないと感じられるようになったのは根性論練習の副産物かもしれません。
近年、鬱や、統合失調症、パニック障害、などがかなりスタンダードな症状として、取り上げられるようになりました。少なくとも私が学生時代にはあまり、知られていない、ある意味世の中から排斥されタブー視されていたものかもしれません。障害者福祉の概念の変化や、病院への受診のしやすさなども手伝ってなのかもしれませんが、最近は患者さんの数も増えつづけているようです。
いまだに原因がはっきりとは解明されていないことのようですが、ストレスに対して脆弱性をもった人がかかりやすい症状状だとも言われます。しかも症状が出てしまうと、さらにストレスに対する脆弱性を持ちながら治療しなくてはならないという、二重のストレスを感じなければならないことも多いようです。その症状が有るが故に社会からのストレスが増えることも有るので、一層、本人に対しては過酷なことも続く気がします。
いろいろ考えるに、世の中が疲れているのではないか、と私は思うのです。疲れていると、いらいらしてくる、人間関係がギクシャクしてくる、そうならないために気を使い、そのためにさらに疲れてゆく、という悪循環です。また、人間関係がギクシャクしてくるために揉め事が」起らないように細かに「契約」と言う作業が必要となります。犯罪の防止云々もありますが、契約をきちんと交わすということは、責任の所在をはっきりさせることでもあり、自己責任、という面では、ある意味冷酷な結果が待っていることもあります。体は、疲れても心は、疲れないような社会になればいいのですが、とにかくストレスフルな時代になってしまいました。今あることを楽しめず、先の見えないものを追い求める社会のような気がします。
すみません、訳のわからないことを、うだうだ書きましたが、今日の一枚です。

シェパード・ムーン/エンヤ
ワーナーミュージック WMC5-450
このCDはオリノコ・フロウの爆発的ヒットで、一躍有名になったアーティスト、エンヤの3枚目に当たるアルバムです。エンヤと言う人は、シンガーソングライターと言うよりもむしろ職人的なアーティストといったほうがいいかもしれません。アルバムを制作するに当たり、ヴォイスの部分は自分の声を多重録音していく手法で作って有ります。つまり、何人で唄っているように聞こえても実は全てエンヤの声、という不思議な世界になります。録音というよりは、いかに自分の声を加工してイメージの音にミキシングしていくか、という作業のようです。
このアルバムでは、幻想的な響きに満ちているだけでなく、ケルト音楽やラテン音楽などまでも取り入れて、緩やかなメロディと見事に結うごさせています。
以前も書きましたが、私は「癒し系」と言う言葉があまり好きでは有りません。ですのでこのアルバムもひとことで癒し系、と片付けるのには抵抗があります。私はエンヤの音の作り方から考えても、緩やかな音楽の中に自分自身の内面を見せてくれる音楽なのではないかと、思っています。忙しい世の中、自分と正直に向き合う機会が少ない中で、厳しさを持って根性を入れて自分と対峙するのではなく、静かに自分の内面の世界に深く溶け込み、自分自身とどうかしていくような、そんな音楽だと思います。
疲れているときに一人でゆっくり聴くのにオススメのアルバムです。
私は、中学校の時から吹奏楽部でサックスを吹き始めました。当然、その時からアンサンブルなどもしていました。ただ、私の学生時代は、部活動などでも、漸く根性論から脱却し、効率的な練習が浸透し始めた頃でした。なので、私が中学生の頃はまだまだ、吹奏楽部であるのにもかかわらず、腹筋、走りこみ、などが日常的に行なわれていました。今は、あまり聞きません。(でも、田舎の中学校とかに行くと、いまだに本気で、腹筋や走り込みで腹式呼吸いが出来るようになる、と信じられていたりして驚きます。)もちろん、運動部でも、水分の補給を制限する、という行為が結構あたりまえに行なわれていました。
まあ、楽器の技術は向上しなくても、根性はついたので、その点は、苦しく長いロングトーンに対しても期待が持てることを考えて頑張ったり、練習の苦しさが、たいしたものではないと感じられるようになったのは根性論練習の副産物かもしれません。
近年、鬱や、統合失調症、パニック障害、などがかなりスタンダードな症状として、取り上げられるようになりました。少なくとも私が学生時代にはあまり、知られていない、ある意味世の中から排斥されタブー視されていたものかもしれません。障害者福祉の概念の変化や、病院への受診のしやすさなども手伝ってなのかもしれませんが、最近は患者さんの数も増えつづけているようです。
いまだに原因がはっきりとは解明されていないことのようですが、ストレスに対して脆弱性をもった人がかかりやすい症状状だとも言われます。しかも症状が出てしまうと、さらにストレスに対する脆弱性を持ちながら治療しなくてはならないという、二重のストレスを感じなければならないことも多いようです。その症状が有るが故に社会からのストレスが増えることも有るので、一層、本人に対しては過酷なことも続く気がします。
いろいろ考えるに、世の中が疲れているのではないか、と私は思うのです。疲れていると、いらいらしてくる、人間関係がギクシャクしてくる、そうならないために気を使い、そのためにさらに疲れてゆく、という悪循環です。また、人間関係がギクシャクしてくるために揉め事が」起らないように細かに「契約」と言う作業が必要となります。犯罪の防止云々もありますが、契約をきちんと交わすということは、責任の所在をはっきりさせることでもあり、自己責任、という面では、ある意味冷酷な結果が待っていることもあります。体は、疲れても心は、疲れないような社会になればいいのですが、とにかくストレスフルな時代になってしまいました。今あることを楽しめず、先の見えないものを追い求める社会のような気がします。
すみません、訳のわからないことを、うだうだ書きましたが、今日の一枚です。

シェパード・ムーン/エンヤ
ワーナーミュージック WMC5-450
このCDはオリノコ・フロウの爆発的ヒットで、一躍有名になったアーティスト、エンヤの3枚目に当たるアルバムです。エンヤと言う人は、シンガーソングライターと言うよりもむしろ職人的なアーティストといったほうがいいかもしれません。アルバムを制作するに当たり、ヴォイスの部分は自分の声を多重録音していく手法で作って有ります。つまり、何人で唄っているように聞こえても実は全てエンヤの声、という不思議な世界になります。録音というよりは、いかに自分の声を加工してイメージの音にミキシングしていくか、という作業のようです。
このアルバムでは、幻想的な響きに満ちているだけでなく、ケルト音楽やラテン音楽などまでも取り入れて、緩やかなメロディと見事に結うごさせています。
以前も書きましたが、私は「癒し系」と言う言葉があまり好きでは有りません。ですのでこのアルバムもひとことで癒し系、と片付けるのには抵抗があります。私はエンヤの音の作り方から考えても、緩やかな音楽の中に自分自身の内面を見せてくれる音楽なのではないかと、思っています。忙しい世の中、自分と正直に向き合う機会が少ない中で、厳しさを持って根性を入れて自分と対峙するのではなく、静かに自分の内面の世界に深く溶け込み、自分自身とどうかしていくような、そんな音楽だと思います。
疲れているときに一人でゆっくり聴くのにオススメのアルバムです。
2008年07月12日
新しいパソコン欲しくても…。
さて、諸事情により、ノートパソコンが必要になって購入したのが既に4年前。Win.XPのパソコンです。現在はメモリが756MH、しか乗っていないので、大量の画像処理や動画の処理にはストレスがあります。次回購入するとなると、やはりVistaになるのでしょうが、Vistaの使い勝手に多少使いにくさを感じているので、あまり使いたいとは思っていません。自宅でPCするにはやはり、画面が大きくてキーボードも打ちやすいデスクトップがよいとも思うので、次回はデスクトップにするかもしれませんが、兎に角予算がないので、それもずいぶん先の話になりそうです。まあ、買い換えるのは夢の話なので、しばらくは指をくわえて妄想することにします。
そこで今日の一枚です。

BACH BACHIANAS
VILLA-LOBOS/BACHIANAS BRASILEIRAS NOS.1&5
BACH/CHACONNE-AIR ON THE G
STRING AND OTHER WORKS
THE YALE CELLOS OF ALDO PARISOT
ARLEEN AUGER(SOPRANO)
DEL0S DE-3041(輸入盤)
このCDはヴィラ=ロボスのブラジル風バッハの第1番と、第5番、その他バッハの曲が何曲か収録されたものです。
実は数年前に、アンサンブルコンテストにサクソフォーン八重奏でエントリーしたことがあり、そのときの曲がこのブラジル風バッハ第1番の1楽章を編曲したものでした。
この曲は随分前になりますが、乗泉吹奏楽団のサクソフォーン八重奏がアンサンブルコンテストの全国大会で見事な演奏を披露してくれていました。(現在も、サクソフォーンアンサンブルの会、として活動されています。もちろん、本体の乗泉吹奏楽団も今でもあります。)それ以来、我々の憧れの曲でもありました。
元々、このブラジル風バッハは、「ベルリンフィルの12人のチェロ奏者達」の演奏会で取り上げられたことで、有名になったようです。12人で演奏していましたが、譜面上はチェロ8人での編成になっています。タイトルの意味としては、「もしもバッハがブラジルに生まれていたなら、こんな曲を書くかもしれない」という意味のようです。バッハの手法を使いながら、ブラジル風な曲が作られています。ヴィラ=ロボスは、ほとんど独学で作曲を学んだようですが、自国ブラジルの音楽伝統に魅了され、やがて国立音楽学校の創設にも寄与しました。彼は南北アメリカ大陸・あるいはヨーロッパで、自分の作品を指揮してまわったようなのですが、その作品には、つねに故郷への思いが現われていたようです。1西ヨーロッパのバロック時代を代表する作曲家バッハの音楽様式で、ブラジルの心を表現するという、コンセプトで、ブラジル風バッハをシリーズとして作曲しました。一つ一つが、違った楽器編成で書かれています。例えば第1番は、チェロ合奏、第5番は、ソプラノと8台のチェロのために、第6番はフルートとファゴット、第9番は無伴奏(ア・カペラ)というようになっています。
さて、この曲は、ベルリンフィルの12人のチェロ奏者達の演奏がやはり決定版なのでしょうが、私が探したときにはまだCD化されていなかったようで、見当たりませんでした。しかも、ブラジル風バッハの5番が収録されたCDは結構有るのですが、1番が収録されたものが少ない、という状況もありました。何枚かのCDの中から、在庫があって速く手に入りそうだったこのCDを購入しました。アンサンブルコンテストの演奏の参考にするためにも是非とも原曲を聴いておきたかったからです。まさに緊急を要する必要性でした。
演奏としてはやっぱりベルリンフィルの12人のチェロ奏者達の演奏の方が聴いていていいのかもしれませんが、数少ない音源、ですし、演奏も大きな破綻がなく比較的よい演奏です。
ブラジルの色彩を感じるバッハ様式(?)の音楽を聴いてみたい方、ブラジル風バッハとバッハを一緒に聞いてみたい方にお勧めの一枚です。
そこで今日の一枚です。

BACH BACHIANAS
VILLA-LOBOS/BACHIANAS BRASILEIRAS NOS.1&5
BACH/CHACONNE-AIR ON THE G
STRING AND OTHER WORKS
THE YALE CELLOS OF ALDO PARISOT
ARLEEN AUGER(SOPRANO)
DEL0S DE-3041(輸入盤)
このCDはヴィラ=ロボスのブラジル風バッハの第1番と、第5番、その他バッハの曲が何曲か収録されたものです。
実は数年前に、アンサンブルコンテストにサクソフォーン八重奏でエントリーしたことがあり、そのときの曲がこのブラジル風バッハ第1番の1楽章を編曲したものでした。
この曲は随分前になりますが、乗泉吹奏楽団のサクソフォーン八重奏がアンサンブルコンテストの全国大会で見事な演奏を披露してくれていました。(現在も、サクソフォーンアンサンブルの会、として活動されています。もちろん、本体の乗泉吹奏楽団も今でもあります。)それ以来、我々の憧れの曲でもありました。
元々、このブラジル風バッハは、「ベルリンフィルの12人のチェロ奏者達」の演奏会で取り上げられたことで、有名になったようです。12人で演奏していましたが、譜面上はチェロ8人での編成になっています。タイトルの意味としては、「もしもバッハがブラジルに生まれていたなら、こんな曲を書くかもしれない」という意味のようです。バッハの手法を使いながら、ブラジル風な曲が作られています。ヴィラ=ロボスは、ほとんど独学で作曲を学んだようですが、自国ブラジルの音楽伝統に魅了され、やがて国立音楽学校の創設にも寄与しました。彼は南北アメリカ大陸・あるいはヨーロッパで、自分の作品を指揮してまわったようなのですが、その作品には、つねに故郷への思いが現われていたようです。1西ヨーロッパのバロック時代を代表する作曲家バッハの音楽様式で、ブラジルの心を表現するという、コンセプトで、ブラジル風バッハをシリーズとして作曲しました。一つ一つが、違った楽器編成で書かれています。例えば第1番は、チェロ合奏、第5番は、ソプラノと8台のチェロのために、第6番はフルートとファゴット、第9番は無伴奏(ア・カペラ)というようになっています。
さて、この曲は、ベルリンフィルの12人のチェロ奏者達の演奏がやはり決定版なのでしょうが、私が探したときにはまだCD化されていなかったようで、見当たりませんでした。しかも、ブラジル風バッハの5番が収録されたCDは結構有るのですが、1番が収録されたものが少ない、という状況もありました。何枚かのCDの中から、在庫があって速く手に入りそうだったこのCDを購入しました。アンサンブルコンテストの演奏の参考にするためにも是非とも原曲を聴いておきたかったからです。まさに緊急を要する必要性でした。
演奏としてはやっぱりベルリンフィルの12人のチェロ奏者達の演奏の方が聴いていていいのかもしれませんが、数少ない音源、ですし、演奏も大きな破綻がなく比較的よい演奏です。
ブラジルの色彩を感じるバッハ様式(?)の音楽を聴いてみたい方、ブラジル風バッハとバッハを一緒に聞いてみたい方にお勧めの一枚です。
2008年07月11日
パワーを。
暑い日は続くし、仕事は忙しいし、体力を奪われっぱなしです。日曜日、どこかに出かけるとか、ゆっくり休むとかしてパワーを蓄えたいのですが、それもなかなか、出来ません。
週末、サックスアンサンブルの練習でパワーを蓄積できればいいのですが、最近放出する一方です。
もっと体力をつけなければ今年の夏は乗り切れないかもしれません。パワーが足りないかもしれません。
そこで今日の一枚です。

THAIKOVSKY"1812"OVERTURE・CAPRICCIO ITALIEN
チャイコフスキー序曲「1812年」、イタリア奇想曲
KUNZEL/CINCINNATI SYMPHONY ORCHESTRA
指揮:エリック・カンゼル
シンシナティ交響楽団
TELARC CD-80041
このCDはチャイコフスキーの1812年をはじめとした作品が収録されたものです。このテラークというレーベルは、アメリカのマイナーレーベルで、CDが登場した頃に発足しました。初期の段階からデジタル録音のみを行なっており、そのダイナミックレンジの広さを強調するように、大砲の実音や、雷鳴の実音を録音したCDなどをリリースしました。この、1812年はそんなテラークのキャノン砲(大砲)の実音入りの録音です。この1812年と言う曲は先日も一度紹介しました。再度復習してみると、ポレオンに率いらたフランス軍が、ついに大国ロシアに攻め入り、統率のとれたフランス軍の攻撃に、強大なロシア軍も窮地に立たされたものの、“冬将軍”と呼ばれる大寒波の襲来により、フランス軍はついにはロシアから撤退しました。それから68年後の1880年、に全ロシア産業工芸博覧会の開会式のための音楽を依頼されたチャイコフスキーは悩んだ末、ロシア軍が歴史的勝利をおさめた1812年の戦争を、テーマに作曲しました。 大きく分けて、三つの部分で構成され、一部ではロシアの苦悩が、二部では戦闘の様子が、そして三部ではロシアの勝利が描かれています。クライマックスは何と言っても三部で、大砲の音が轟いたり、教会の鐘が華やかに打ち鳴らされたりします。また、フランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」のメロディに対してロシア国家で応戦し、フランス軍の敗退を描きだすといった趣向が使われています。
盛り上がり方はまさにパワーを与えてくれる感じです。力がみなぎってくるようです。
このCDはなんと、レーベルに、キャノン砲注意という表示があります。大音響のために、スピーカーやアンプをとばす恐れがあります、というものです。テラークらしい表記なのかもしれません。
なお、このCDは旧録音ですが、1999年頃に、1812年に合唱も加えた演奏で、同じくキャノン砲の実音録音がされたカンゼル指揮のCDがリリースされているようです。(しかもSACDとのハイブリッド仕様のようです。)
本物のキャノン砲の轟音とともに、1812年を楽しみたい方、テラー
クのワイドレンジなデジタル録音を楽しみたい方にお勧めです。(聴く時は音量に気をつけましょう、笑)
週末、サックスアンサンブルの練習でパワーを蓄積できればいいのですが、最近放出する一方です。
もっと体力をつけなければ今年の夏は乗り切れないかもしれません。パワーが足りないかもしれません。
そこで今日の一枚です。

THAIKOVSKY"1812"OVERTURE・CAPRICCIO ITALIEN
チャイコフスキー序曲「1812年」、イタリア奇想曲
KUNZEL/CINCINNATI SYMPHONY ORCHESTRA
指揮:エリック・カンゼル
シンシナティ交響楽団
TELARC CD-80041
このCDはチャイコフスキーの1812年をはじめとした作品が収録されたものです。このテラークというレーベルは、アメリカのマイナーレーベルで、CDが登場した頃に発足しました。初期の段階からデジタル録音のみを行なっており、そのダイナミックレンジの広さを強調するように、大砲の実音や、雷鳴の実音を録音したCDなどをリリースしました。この、1812年はそんなテラークのキャノン砲(大砲)の実音入りの録音です。この1812年と言う曲は先日も一度紹介しました。再度復習してみると、ポレオンに率いらたフランス軍が、ついに大国ロシアに攻め入り、統率のとれたフランス軍の攻撃に、強大なロシア軍も窮地に立たされたものの、“冬将軍”と呼ばれる大寒波の襲来により、フランス軍はついにはロシアから撤退しました。それから68年後の1880年、に全ロシア産業工芸博覧会の開会式のための音楽を依頼されたチャイコフスキーは悩んだ末、ロシア軍が歴史的勝利をおさめた1812年の戦争を、テーマに作曲しました。 大きく分けて、三つの部分で構成され、一部ではロシアの苦悩が、二部では戦闘の様子が、そして三部ではロシアの勝利が描かれています。クライマックスは何と言っても三部で、大砲の音が轟いたり、教会の鐘が華やかに打ち鳴らされたりします。また、フランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」のメロディに対してロシア国家で応戦し、フランス軍の敗退を描きだすといった趣向が使われています。
盛り上がり方はまさにパワーを与えてくれる感じです。力がみなぎってくるようです。
このCDはなんと、レーベルに、キャノン砲注意という表示があります。大音響のために、スピーカーやアンプをとばす恐れがあります、というものです。テラークらしい表記なのかもしれません。
なお、このCDは旧録音ですが、1999年頃に、1812年に合唱も加えた演奏で、同じくキャノン砲の実音録音がされたカンゼル指揮のCDがリリースされているようです。(しかもSACDとのハイブリッド仕様のようです。)
本物のキャノン砲の轟音とともに、1812年を楽しみたい方、テラー
クのワイドレンジなデジタル録音を楽しみたい方にお勧めです。(聴く時は音量に気をつけましょう、笑)
2008年07月10日
久々。
7月に入ってからと言うもの、暑い日が続いています。
ダッパーではこの夏も、州崎寺での演奏に向けての練習も少しずつ始まっています。週末は必ずといっていいほど、サクソフォーンアンサンブルの練習です。
話は変わりますが、私はCDを結構持っているので、物によっては久々に聴くCDというものがしょっちゅうあります。どうやって聴くCDを決めているのかといわれるとちょっと答えには困るのですが、まあ、そのときの気分だったり、必要に刈られて(演奏するための参考としてなど)聴いたりするわけなので、別に聴く順序が決まっているわけでもなく、聴いてみて「ちがうなー。」と思ったら即座にイジェクトして、他のCDを入れてしまいます。
で、今日の一枚です。最近、少し気になっていて、聴いてみようと、棚から探して聴いてみました。

THUNDERBIRDS ARE GO
in SUPERMARIONATION and technicolor
SILVA SCREEN FILMCD 018
このCDは1「THUNDERBIRDS」のテーマなどが収録されたもの。この「サンダーバード」は、1964~66年にジェリーアンダーソンがイギリスで製作した人形特撮TVシリーズ(上のタイトルでもSUPERMARIONATION、スーパーマリオネイション)で、日本でもNHKによって1966年に全32話が放送されました。
設定としては、「サンダーバード」とは、正式名称を「国際救助隊」と言い、2065年(だったと思います、記憶が曖昧、昔は2026年とかの設定だったんですが、後に改定されたはず)戦争や国際紛争には中立を保ち出動する事無く、国際的な事故・災害の救助を行なう組織で、一つの国だけでは、対処しきれないような大事件が起こり、SOSが入ると、政治・思想・国家にかかわらず活動し解決する、というものです。南太平洋のどこかにある秘密基地にトレーシー隊長と彼の息子たちがいる本部があり、それぞれに1号から5号までのサンダーバードメカ(ロケットみたいなのや、地底ドリルみたいなやつ)を操作させて、任務に当たらせています。また、ロンドンにある支部にブロンドの美女の秘密諜報員ペネロープ(日本語吹き替えは若き日の黒柳徹子さんです。かなり有名)がいて、スパイ兵器を搭載したロールスロイスに乗っています。
この世代を過ごした人には ロイヤル・ナイツ、ビクター少年合唱隊が唄う日本語主題歌が有名ですが、実はこれはNHKの放送当時ではなく後に民放で再放送された時に作られたもののようです。なので、オリジナルスコアを集めたこのCDにも入っていません。また、現在は当時のテープが散逸しているらしく、この日本語テーマのオリジナルが残っていないようです。
そういえば、実写版にもなりました。私としては、「サンダーバード」はあの手の込んだマリオネットの作りにもかかわらず、マリオネットを感じさせない魅力だったと思うのですが。
サンダーバードを見て育った世代の人、これから実写版サンダーバードを見るに当たって、マリオネット版のサンダーバードの音楽を聴いておきたい方にオススメの一枚です。
ダッパーではこの夏も、州崎寺での演奏に向けての練習も少しずつ始まっています。週末は必ずといっていいほど、サクソフォーンアンサンブルの練習です。
話は変わりますが、私はCDを結構持っているので、物によっては久々に聴くCDというものがしょっちゅうあります。どうやって聴くCDを決めているのかといわれるとちょっと答えには困るのですが、まあ、そのときの気分だったり、必要に刈られて(演奏するための参考としてなど)聴いたりするわけなので、別に聴く順序が決まっているわけでもなく、聴いてみて「ちがうなー。」と思ったら即座にイジェクトして、他のCDを入れてしまいます。
で、今日の一枚です。最近、少し気になっていて、聴いてみようと、棚から探して聴いてみました。

THUNDERBIRDS ARE GO
in SUPERMARIONATION and technicolor
SILVA SCREEN FILMCD 018
このCDは1「THUNDERBIRDS」のテーマなどが収録されたもの。この「サンダーバード」は、1964~66年にジェリーアンダーソンがイギリスで製作した人形特撮TVシリーズ(上のタイトルでもSUPERMARIONATION、スーパーマリオネイション)で、日本でもNHKによって1966年に全32話が放送されました。
設定としては、「サンダーバード」とは、正式名称を「国際救助隊」と言い、2065年(だったと思います、記憶が曖昧、昔は2026年とかの設定だったんですが、後に改定されたはず)戦争や国際紛争には中立を保ち出動する事無く、国際的な事故・災害の救助を行なう組織で、一つの国だけでは、対処しきれないような大事件が起こり、SOSが入ると、政治・思想・国家にかかわらず活動し解決する、というものです。南太平洋のどこかにある秘密基地にトレーシー隊長と彼の息子たちがいる本部があり、それぞれに1号から5号までのサンダーバードメカ(ロケットみたいなのや、地底ドリルみたいなやつ)を操作させて、任務に当たらせています。また、ロンドンにある支部にブロンドの美女の秘密諜報員ペネロープ(日本語吹き替えは若き日の黒柳徹子さんです。かなり有名)がいて、スパイ兵器を搭載したロールスロイスに乗っています。
この世代を過ごした人には ロイヤル・ナイツ、ビクター少年合唱隊が唄う日本語主題歌が有名ですが、実はこれはNHKの放送当時ではなく後に民放で再放送された時に作られたもののようです。なので、オリジナルスコアを集めたこのCDにも入っていません。また、現在は当時のテープが散逸しているらしく、この日本語テーマのオリジナルが残っていないようです。
そういえば、実写版にもなりました。私としては、「サンダーバード」はあの手の込んだマリオネットの作りにもかかわらず、マリオネットを感じさせない魅力だったと思うのですが。
サンダーバードを見て育った世代の人、これから実写版サンダーバードを見るに当たって、マリオネット版のサンダーバードの音楽を聴いておきたい方にオススメの一枚です。
2008年07月09日
それでいいのか?本当に。
梅雨も明けて本格的な夏。これからどんどん暑くなると思います。
さて、この土曜日(7月12日)に、作曲家、田中久美子先生の書いたサクソフォーンコンチェルトが、自衛隊の演奏会で疲労されるそうです。多少興味があるのですが、生憎、私は仕事でいけません。
私の所属する吹奏楽団、高松ウインドシンフォーニーは20回の記念定期演奏会の時に、委嘱作品である、「東洋の伝説」と言う曲を演奏しました。もちろん、委嘱作品なので初公開、世界初演の曲だったわけですが、契約上版権を買い取るということをしませんでした。我々が著作権を管理できるわけも無く、格安で書いてもらったこともあり、版権、その他の権利は全て作曲家の田中先生におまかせしました。そしてなんと、田中先生の所にオファーが来て、ついにこの「東洋の伝説」がフランスの出版社から出版されることになったそうです。我々のための委嘱作品が世界に向けて出版されることになったという話題は非常に嬉しいものです。委嘱作品と言う性格上、海外で出版されようが、曲の解説やライナーノーツには必ず、「高松ウインドシンフォニー委嘱作品」という内容がクレジットされることと思います。
しかしちょっと不安だったのは、以前、田中先生がフランスの出版社からオファーが来たので演奏のサンプルを送りたい、と言っていたこと。当然、我々が初演なので、我々以外の演奏は存在しません。フランスに送られたのは我々の定期演奏会の本番の演奏でした。よくよく考えると恐ろしいことです。あの演奏で、よく出版社も出版に踏み切ったものだと思います。 演奏した我々以上に我々の演奏を聞いて出版を決めた出版社のチャレンジに拍手、という感じでしょうか。でも、田中先生の曲自体が素晴らしい曲なので、出版される、という方が正しいのかもしれません。
コンクールなんかでどんどん取り上げてもらえたら嬉しいなー、などと思っています。
でも我々の演奏、それでいいのか?と思ってしまいます。(T^T)
そこで今日の一枚です。

FRENCH & AMERICAN MUSIC
Quartetto di Sassofoni Accademia
ICARUS Nuova Era 7139(輸入盤)
このCDは1984年に結成された、イタリアのアカデミア・サクソフォン四重奏団の演奏によるものです。このアカデミア・サクソフォーン四重奏団はイタリア・サクソフォン演奏者協会の設立メンバであり、古今の曲をレパートリにとりいれているのはもちろん、モリコーネなどのイタリアの現代作曲家とも親交が深いようです。
このアルバムはタイトル通り、フランスとアメリカの作品を取り上げたアルバムになっています。曲目はフランセの「小組曲」、デザンクロの「サクソフォン四重奏曲」、ガーシュウィン・メドレー 、P.ウッズの「3つのインプロヴィゼーション」、アヨの「ジャズ組曲」、S.ジョプリンの「ジ・エンターテイナー」 同じく「イージー・ウィナーズ 」と言った曲です。
演奏の方はフランスものの方は正直言って「これでいいのか?」と言う感じです。ひどい書き方をすると、「アンサンブルコンテスト地区大会、一般の部、銀賞」みたいな演奏です。楽譜どおり吹けてもいるし、そんなに悪くも無いのですが、アナリーゼが足りないというか、そんな印象と、強音と弱音、高音の時にアンサンブルの不安定さを感じさせます。ところが、一転、アメリカもの方になると、俄然いい感じになります。楽しさが伝わってくるような演奏で、アンサンブルの破綻も見られなくなります。
どちらかというと、後半のアメリカ作品のポップな方がこの団体には向いているのかもしれません。しかし、聴いてみて、フランスものとアメリカものの差は凄いを通り越してひどい?かもしれません。でも、フランスものでおもしろくない分、アメリカもので十分に楽しませてくれるアルバムです。
アメリカ系のポップなサクソフォーンアンサンブルを聴いてみたい方におすすめの一枚です
さて、この土曜日(7月12日)に、作曲家、田中久美子先生の書いたサクソフォーンコンチェルトが、自衛隊の演奏会で疲労されるそうです。多少興味があるのですが、生憎、私は仕事でいけません。
私の所属する吹奏楽団、高松ウインドシンフォーニーは20回の記念定期演奏会の時に、委嘱作品である、「東洋の伝説」と言う曲を演奏しました。もちろん、委嘱作品なので初公開、世界初演の曲だったわけですが、契約上版権を買い取るということをしませんでした。我々が著作権を管理できるわけも無く、格安で書いてもらったこともあり、版権、その他の権利は全て作曲家の田中先生におまかせしました。そしてなんと、田中先生の所にオファーが来て、ついにこの「東洋の伝説」がフランスの出版社から出版されることになったそうです。我々のための委嘱作品が世界に向けて出版されることになったという話題は非常に嬉しいものです。委嘱作品と言う性格上、海外で出版されようが、曲の解説やライナーノーツには必ず、「高松ウインドシンフォニー委嘱作品」という内容がクレジットされることと思います。
しかしちょっと不安だったのは、以前、田中先生がフランスの出版社からオファーが来たので演奏のサンプルを送りたい、と言っていたこと。当然、我々が初演なので、我々以外の演奏は存在しません。フランスに送られたのは我々の定期演奏会の本番の演奏でした。よくよく考えると恐ろしいことです。あの演奏で、よく出版社も出版に踏み切ったものだと思います。 演奏した我々以上に我々の演奏を聞いて出版を決めた出版社のチャレンジに拍手、という感じでしょうか。でも、田中先生の曲自体が素晴らしい曲なので、出版される、という方が正しいのかもしれません。
コンクールなんかでどんどん取り上げてもらえたら嬉しいなー、などと思っています。
でも我々の演奏、それでいいのか?と思ってしまいます。(T^T)
そこで今日の一枚です。

FRENCH & AMERICAN MUSIC
Quartetto di Sassofoni Accademia
ICARUS Nuova Era 7139(輸入盤)
このCDは1984年に結成された、イタリアのアカデミア・サクソフォン四重奏団の演奏によるものです。このアカデミア・サクソフォーン四重奏団はイタリア・サクソフォン演奏者協会の設立メンバであり、古今の曲をレパートリにとりいれているのはもちろん、モリコーネなどのイタリアの現代作曲家とも親交が深いようです。
このアルバムはタイトル通り、フランスとアメリカの作品を取り上げたアルバムになっています。曲目はフランセの「小組曲」、デザンクロの「サクソフォン四重奏曲」、ガーシュウィン・メドレー 、P.ウッズの「3つのインプロヴィゼーション」、アヨの「ジャズ組曲」、S.ジョプリンの「ジ・エンターテイナー」 同じく「イージー・ウィナーズ 」と言った曲です。
演奏の方はフランスものの方は正直言って「これでいいのか?」と言う感じです。ひどい書き方をすると、「アンサンブルコンテスト地区大会、一般の部、銀賞」みたいな演奏です。楽譜どおり吹けてもいるし、そんなに悪くも無いのですが、アナリーゼが足りないというか、そんな印象と、強音と弱音、高音の時にアンサンブルの不安定さを感じさせます。ところが、一転、アメリカもの方になると、俄然いい感じになります。楽しさが伝わってくるような演奏で、アンサンブルの破綻も見られなくなります。
どちらかというと、後半のアメリカ作品のポップな方がこの団体には向いているのかもしれません。しかし、聴いてみて、フランスものとアメリカものの差は凄いを通り越してひどい?かもしれません。でも、フランスものでおもしろくない分、アメリカもので十分に楽しませてくれるアルバムです。
アメリカ系のポップなサクソフォーンアンサンブルを聴いてみたい方におすすめの一枚です
2008年07月08日
夏に。
さて、中学、高校の時代は部活に明け暮れていたので、夏の暑い時期になると、吹奏楽コンクールを思い出します。私は前職が楽器関係の職業だったので、そこでも夏になると、中高生が吹奏楽コンクールに励む姿を目にしていました。ということで、私の中では夏は吹奏楽コンクール、冬はアンサンブルコンテスト、というイメージが固定化されています。
先日、中学校にサックスを教えに行った話を書きましたが、B部門(課題曲なし、パフォーマンスありの部門で、全国大会はなし。)出場団体だったのが、少し残念です。私のコンクールの思い出の中にはやはり、課題曲が一緒にあります。いろいろな人に演奏した課題曲を聞くと年齢、世代がわかります。(笑)私は中学校の時代から現在にいたるまでほとんどの課題曲を聞いたり演奏した経験があるので、大抵の世代の人の話についていけます。高校を卒業してからもコンクールに出ないにもかかわらず、今所属している一般の吹奏楽団ではほぼ毎年、課題曲を全曲演奏しています。今年の課題曲も全曲演奏しました。
吹奏楽をやっていらししゃる方ならば、思い出の課題曲があるという方もたくさんいらしゃると思います。
そこで今日の一枚です。

吹奏楽コンクール課題曲集 Vol.5
1986~1989
SONY Record SRCR2209
このCDは1986年~1989年の4年間の吹奏楽コンクール課題曲が収録されたもの。全国大会での演奏の中から集めた演奏です。
自分がコンクールに出ていたのが何年だったかはっきりわからない、という人も曲目をみればああ、この頃か、と思えるかもしれません。吹奏楽のための「変容」、「嗚呼!」、吹奏楽のための序曲、コンサート・マーチ「テイク・オフ」、風紋、渚スコープ、コンサートマーチ’87、ムービング・オン、マーチ「ハロー! サンシャイン」、吹奏楽のための「深層の祭」、交響的舞曲、マーチ「スタウト・アンド・シンプル」、カーニバルのマーチ、風と炎の踊り、WISH for wind orchestra、行進曲「清くあれ,爽やかなれ」、ポップス・マーチ「すてきな日々」と言った曲がクレジットされています。現在はマーチの年とそうでない年が交互にやってきますが、この当時は毎年、4曲のうち2曲か1曲がマーチということになっていました。
先日教えに行った中学校は「風紋」をやるそうですが、今の中学生、今から15年以上前の課題曲をやっているなどとは思ってもいないようです。実際、「風紋」は作曲家自身(保科洋 氏)が手を加え「原典版」なども出版され、今でもいろいろなところで演奏されていたりするようです。
アマチュアの演奏ではありますが、長い時間かけて取り組んで練られた丁寧な演奏が多く、プロの演奏に勝るとも劣らないものだと思います。私は課題曲は毎年出版される吹奏楽の新曲だと思っているのですが、コンクールが終わると一気に演奏される機会を失ってしまうという悲しい運命を持っていると思ってしまうのです。折角の新曲なので「風紋」のように後々取り上げられるような曲に育って欲しいと思います。何曲かはそういった曲もあるようですが、まだまだ、曲の量に比べると忘れられていく曲も多いのではないかと思います。
そのためにも先日も書いたようにもっと取り組みやすい課題曲であってほしいとも思うのです。このCDの年代のあとぐらいから、課題曲が難しくてマニアックになっていった気がするのは私だけでしょうか?
吹奏楽コンクールで、学生時代を過ごした方、吹奏楽のオリジナル曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
先日、中学校にサックスを教えに行った話を書きましたが、B部門(課題曲なし、パフォーマンスありの部門で、全国大会はなし。)出場団体だったのが、少し残念です。私のコンクールの思い出の中にはやはり、課題曲が一緒にあります。いろいろな人に演奏した課題曲を聞くと年齢、世代がわかります。(笑)私は中学校の時代から現在にいたるまでほとんどの課題曲を聞いたり演奏した経験があるので、大抵の世代の人の話についていけます。高校を卒業してからもコンクールに出ないにもかかわらず、今所属している一般の吹奏楽団ではほぼ毎年、課題曲を全曲演奏しています。今年の課題曲も全曲演奏しました。
吹奏楽をやっていらししゃる方ならば、思い出の課題曲があるという方もたくさんいらしゃると思います。
そこで今日の一枚です。

吹奏楽コンクール課題曲集 Vol.5
1986~1989
SONY Record SRCR2209
このCDは1986年~1989年の4年間の吹奏楽コンクール課題曲が収録されたもの。全国大会での演奏の中から集めた演奏です。
自分がコンクールに出ていたのが何年だったかはっきりわからない、という人も曲目をみればああ、この頃か、と思えるかもしれません。吹奏楽のための「変容」、「嗚呼!」、吹奏楽のための序曲、コンサート・マーチ「テイク・オフ」、風紋、渚スコープ、コンサートマーチ’87、ムービング・オン、マーチ「ハロー! サンシャイン」、吹奏楽のための「深層の祭」、交響的舞曲、マーチ「スタウト・アンド・シンプル」、カーニバルのマーチ、風と炎の踊り、WISH for wind orchestra、行進曲「清くあれ,爽やかなれ」、ポップス・マーチ「すてきな日々」と言った曲がクレジットされています。現在はマーチの年とそうでない年が交互にやってきますが、この当時は毎年、4曲のうち2曲か1曲がマーチということになっていました。
先日教えに行った中学校は「風紋」をやるそうですが、今の中学生、今から15年以上前の課題曲をやっているなどとは思ってもいないようです。実際、「風紋」は作曲家自身(保科洋 氏)が手を加え「原典版」なども出版され、今でもいろいろなところで演奏されていたりするようです。
アマチュアの演奏ではありますが、長い時間かけて取り組んで練られた丁寧な演奏が多く、プロの演奏に勝るとも劣らないものだと思います。私は課題曲は毎年出版される吹奏楽の新曲だと思っているのですが、コンクールが終わると一気に演奏される機会を失ってしまうという悲しい運命を持っていると思ってしまうのです。折角の新曲なので「風紋」のように後々取り上げられるような曲に育って欲しいと思います。何曲かはそういった曲もあるようですが、まだまだ、曲の量に比べると忘れられていく曲も多いのではないかと思います。
そのためにも先日も書いたようにもっと取り組みやすい課題曲であってほしいとも思うのです。このCDの年代のあとぐらいから、課題曲が難しくてマニアックになっていった気がするのは私だけでしょうか?
吹奏楽コンクールで、学生時代を過ごした方、吹奏楽のオリジナル曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年07月07日
メジャーであってマイナー。
数年前に、テレビで吹奏楽コンクールのことが紹介されて、吹奏楽のの認知度も少し上がったようです。
さて、吹奏楽の世界では、いまだにオーケストラの曲からのアレンジが数多く存在するわけですが、その中に吹奏楽では有名でもオーケストラの世界では非常にマイナーな曲というのがいくつか存在します。吹奏楽コンクールでいくつもの学校が取り上げている曲が、実はオーケストラの世界ではほとんど取り上げられることのない曲であったりすることもしばしば。
同じ音楽の中にありながら、隣接するようなジャンルでありながら、一方ではメジャー、一方ではマイナーという不思議な現象が起こったりします。
そこで今日の一枚です。

Belkis, Queen of SHEBA & Metamorphosen
指揮:Simon, Geoffrey
Philharmonia Orchestra
Chandos CHAN-8405(輸入盤)
このCDはレスピーギの「シバの女王ベルキス」の原曲の組曲版が収録された数少ないCDの一枚です。私の知る限り、このCDを含めこの曲は2種類の演奏しかリリースされていません。一緒に12旋法によるメタモルフォーゼという曲が収録されています。
おそらくこの「ベルキス」はオケの曲としてはものすごくマイナーな曲なのでは無いかと思います。吹奏楽コンクールなどで取り上げられて、逆によく聞かれるようになるという皮肉な現象が時々起こることがありますが、これもその中の一曲といえるかもしれません。ちなみに元のバレエ曲の方は上演するのに1000人以上の出演者を要する大作です。
曲の方はレスピーギらしいオーケストレーションの曲で、旋律にも所々ローマ三部作を思わせるような部分もあります。録音の方も比較的広いレンジで捕らえられていて割合秀逸です。
ただ少し残念なのは演奏がよく練られた演奏とはいえないところでしょうか。部分的には管楽器の飛び出し、弦楽器の不安定さを感じる部分が無いとはいえません。リズム的にもしっかりとアインザッツをあわせることが必要な部分が多いのでアンサンブルとしての力量と、練習量が試されるかと思いますが、個人的にはもう少し頑張って欲しかったとも思います。
とは言え、聞くに堪えない、という演奏ではなく、十分に楽しめ、また数少ないオリジナルの録音としての資料的価値もあります。
吹奏楽コンクールなどでベルキスに思い出の深い方、レスピーギのローマ三部作以外の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
さて、吹奏楽の世界では、いまだにオーケストラの曲からのアレンジが数多く存在するわけですが、その中に吹奏楽では有名でもオーケストラの世界では非常にマイナーな曲というのがいくつか存在します。吹奏楽コンクールでいくつもの学校が取り上げている曲が、実はオーケストラの世界ではほとんど取り上げられることのない曲であったりすることもしばしば。
同じ音楽の中にありながら、隣接するようなジャンルでありながら、一方ではメジャー、一方ではマイナーという不思議な現象が起こったりします。
そこで今日の一枚です。

Belkis, Queen of SHEBA & Metamorphosen
指揮:Simon, Geoffrey
Philharmonia Orchestra
Chandos CHAN-8405(輸入盤)
このCDはレスピーギの「シバの女王ベルキス」の原曲の組曲版が収録された数少ないCDの一枚です。私の知る限り、このCDを含めこの曲は2種類の演奏しかリリースされていません。一緒に12旋法によるメタモルフォーゼという曲が収録されています。
おそらくこの「ベルキス」はオケの曲としてはものすごくマイナーな曲なのでは無いかと思います。吹奏楽コンクールなどで取り上げられて、逆によく聞かれるようになるという皮肉な現象が時々起こることがありますが、これもその中の一曲といえるかもしれません。ちなみに元のバレエ曲の方は上演するのに1000人以上の出演者を要する大作です。
曲の方はレスピーギらしいオーケストレーションの曲で、旋律にも所々ローマ三部作を思わせるような部分もあります。録音の方も比較的広いレンジで捕らえられていて割合秀逸です。
ただ少し残念なのは演奏がよく練られた演奏とはいえないところでしょうか。部分的には管楽器の飛び出し、弦楽器の不安定さを感じる部分が無いとはいえません。リズム的にもしっかりとアインザッツをあわせることが必要な部分が多いのでアンサンブルとしての力量と、練習量が試されるかと思いますが、個人的にはもう少し頑張って欲しかったとも思います。
とは言え、聞くに堪えない、という演奏ではなく、十分に楽しめ、また数少ないオリジナルの録音としての資料的価値もあります。
吹奏楽コンクールなどでベルキスに思い出の深い方、レスピーギのローマ三部作以外の曲を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年07月06日
暑いから夏なのか、夏だから暑いのか。
本当に暑くなってきました。湿度も上がって蒸し暑くなってきています。そういえば、高校生の頃、夏休みに校舎の壁を塗り替えるとかで、真夏に学校の最上階(早く言えばよく焼けた屋上の真下の部屋)のホールで窓を締め切って脱水症状になりかけながらサックスの練習をした記憶があります。自分の家も似たようなものだったので私は結構大丈夫でしたが、それでも、暑さに弱いので、さすがにばてました。
よく親に夏に「暑い」というと、「夏は暑いんがあたりまえや。」(訳:夏はあついのがあたりまえでしょう。)といわれたものですが、どうなんでしょう。冷夏だと、涼しかったりもしますが。いろいろ考えても夏だから暑いのか、暑いから夏なのかわかりにくいところもあります。鶏と卵でどちらが先か、ではありませんが、まあ、季節は4つあるので、それから考えると、夏だから暑い、が正解なのでしょうか。でも、秋になっても暑い日はあるのですが…。しかし本当にこのまま8月になると40度ぐらいになるのではないかと思うぐらい暑い日が続きます。皆さんも体調を崩さないようにお気をつけ下さい。夏ばて予防には鉄分の摂取が重要だそうです。
さて、そこで今日の一枚です。

熱帯JAZZ楽団
(TROPICAL JAZZ BIG BAND)7 ~Spain~
ビクターエンターテイメント VICJ-61118
このCDはこのCD以前も何枚か紹介してきたオルケスタデラルスにいたカルロス菅野氏が、主催するTOROPICAL BIG BANNDOのアルバム第7弾です。先日、第8弾のアルバム(~The Covers~)もリリースされました。曲目は、チュニジアの夜、エディ・パル・モンテ、スペイン、バードランド、ラ・ノーチェ・エン・エル・バリオ、グッドバイ・フィフス・アヴェニュー、パランテ・パゴサール、スイングしなけりゃ意味ないね、トロピジャム、月光価千金、といった比較的よく耳にする曲も沢山含まれています。以前も書きましたが、いかにも熱帯JAZZ楽団らしい熱気溢れる威勢のいい演奏になっています。特にスペインや、スイングしなけりゃ意味ないね、などの熱い演奏は暑さを忘れるほどの熱いラテンテイストを感じる演奏です。
もちろんただ熱いだけの演奏ではなく、素晴らしいテクニックときっちりと聞かせるアンサンブルで楽しませてくれます。
熱い演奏で暑さを吹き飛ばしたいという方にオススメの一枚です。
よく親に夏に「暑い」というと、「夏は暑いんがあたりまえや。」(訳:夏はあついのがあたりまえでしょう。)といわれたものですが、どうなんでしょう。冷夏だと、涼しかったりもしますが。いろいろ考えても夏だから暑いのか、暑いから夏なのかわかりにくいところもあります。鶏と卵でどちらが先か、ではありませんが、まあ、季節は4つあるので、それから考えると、夏だから暑い、が正解なのでしょうか。でも、秋になっても暑い日はあるのですが…。しかし本当にこのまま8月になると40度ぐらいになるのではないかと思うぐらい暑い日が続きます。皆さんも体調を崩さないようにお気をつけ下さい。夏ばて予防には鉄分の摂取が重要だそうです。
さて、そこで今日の一枚です。

熱帯JAZZ楽団
(TROPICAL JAZZ BIG BAND)7 ~Spain~
ビクターエンターテイメント VICJ-61118
このCDはこのCD以前も何枚か紹介してきたオルケスタデラルスにいたカルロス菅野氏が、主催するTOROPICAL BIG BANNDOのアルバム第7弾です。先日、第8弾のアルバム(~The Covers~)もリリースされました。曲目は、チュニジアの夜、エディ・パル・モンテ、スペイン、バードランド、ラ・ノーチェ・エン・エル・バリオ、グッドバイ・フィフス・アヴェニュー、パランテ・パゴサール、スイングしなけりゃ意味ないね、トロピジャム、月光価千金、といった比較的よく耳にする曲も沢山含まれています。以前も書きましたが、いかにも熱帯JAZZ楽団らしい熱気溢れる威勢のいい演奏になっています。特にスペインや、スイングしなけりゃ意味ないね、などの熱い演奏は暑さを忘れるほどの熱いラテンテイストを感じる演奏です。
もちろんただ熱いだけの演奏ではなく、素晴らしいテクニックときっちりと聞かせるアンサンブルで楽しませてくれます。
熱い演奏で暑さを吹き飛ばしたいという方にオススメの一枚です。
2008年07月05日
サックスを教えること、学ぶこと。
さて、たまに中学校に行って中学生にサックスを教えてくることがあります。えるといっても私は素人で、専門的なことを何一つ学んだことが無いので、たいしたことは出来ません。私はサックスに関してはレッスンや専門的指導を受けたことが一度もありません。そのため、既成概念にとらわれる事無く、いろいろ自分で考えながらやってきた反面、直接的に近道になるヒントを与えてくれる人もあまりいなかったので、かなり余計な回り道をしたのかもしれません。それで、いまだになかなか上達しないのかもしれませんが、自分が試行錯誤したことは人に教えるときは役に立ちます。
でも時々思うのですが、わざわざ回り道してもらうことも教えるときには大切なのかもしれません。間違いを体験したあとに得られた正解は本当に自分の物にすることが出来るのだと思います。
最近は学校でもどこでも、危険を回避することばかりに意識が行っているようですが、我々が子どもだった時代に同じように危険を回避していなかったからと言って、事故が多かったとも思えません。保障や賠償責任の問題で神経質になることも多いですが、自己責任とは相手に責任を問うだけでなく自分の過失を覚悟することだと思うのです。そう考えると今の学校教育は実情と逆行している部分が多いのかもしれません。そもそも先生たちが、正解を教わってきた人たちなので、間違いを体験する前に正しいことを教えてしまうのかもしれません。(全てとは言いませんが。)体験に基づかないことはなかなか、自分の物にならないと思うのですが、どうなのでしょうか。
特にサックスを教えるときは、これが正解と教えても、すぐには出来ません。それを消化して、実際に出来るようになるまでは意識を変えるほかに体に覚えさせることも必要だからです。だから、レッスンを受けても練習しない人は絶対に上手くならないと思うのです。
私はサックスをいろいろなレコードや、CD等で学びました。それはサックスの演奏に限らず、また、ジャンルに限らずです。昨日、中学生にサックスの演奏のCDを持っているかどうか聞いてみましたが、誰も持っていませんでした。私としては信じられないのですが、最近の人たちはそうなんでしょうか?自分がサックスをやっていても、J-POPのCDしか買わない、聴かないという人は多いのでしょうか?だとすると、ちょっと寂しくなってしまいます。私のように100枚を超えるようなサックスのCDを買えとは言いません。せめて、自分の理想とする音を奏でる奏者のCDぐらいは愛聴して欲しいのです。もちろん、他のジャンルや楽器の演奏も出来るだけ興味を持って聴いてほしいのですが。
そこで今日の一枚です。

バルトーク/弦楽四重奏曲全集
アルバン・ベルク四重奏団
東芝EMI TOCE-7961~63
このCDはアルバン・ベルク四重奏団の演奏によるバルトークの弦楽四重奏曲集です。1984年から1986年にかけてレコーディングされたものです。
アルバン・ベルク四重奏団は当時ウィーン音楽大学の教授を務めていた4人の若手奏者によって結成されたカルテットです。
バルトークは近年、アレンジされて吹奏楽コンクールなどでもその曲を聞くようになりましたが、日本人にとってはまだまだ馴染みの薄い作曲家かもしれません。バルトークは、シェーンベルク、ストラヴィンスキーと並ぶ20世紀前半を代表するハンガリー の作曲家で、仲のよかったコダーイと共にハンガリー、チェコ、スロヴァキアなど東欧諸国の民謡を集め、楽譜に起こし、自らの前衛的な音楽語法に取り入れて曲を作り出すという技法に特徴があります。第2次大戦中、アメリカに亡命しましたが、後年はあまり幸福な人生を送れず、最後は白血病に倒れてなくなってしまいました。
一時期、サックスのカルテットの演奏の参考に弦楽四重奏を聞いてみようと思い購入したCDです。クラシック・サックスの神様、マルセルミュールも弦楽四重奏にヒントを得て、サックス四重奏を創始したといわれていることからも、是非、弦楽四重奏を聞いておくべきだと思ったのです。
で、何故に、ベートーヴェンとかじゃなく、バルトークかというと、サックスアンサンブルが盛んに作られ始めた時代に近い作曲家だったから、という理由でした。
アルバン・ベルクの演奏はかなり厳格でシャープなイメージの演奏です。あまり贅肉を感じない演奏とも感じます。元々、バルトークの弦楽四重奏曲自体が厳格なイメージの曲なので、この辺、ぴったりはまっている演奏と感じるか厳格に過ぎてきびしすぎると感じるかはそれぞれかもしれません。
バルトークの弦楽四重奏曲を聴いてみたい方、ベートーヴェンとも、ラヴェルとも、ドビュッシーとも違う弦楽四重奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
でも時々思うのですが、わざわざ回り道してもらうことも教えるときには大切なのかもしれません。間違いを体験したあとに得られた正解は本当に自分の物にすることが出来るのだと思います。
最近は学校でもどこでも、危険を回避することばかりに意識が行っているようですが、我々が子どもだった時代に同じように危険を回避していなかったからと言って、事故が多かったとも思えません。保障や賠償責任の問題で神経質になることも多いですが、自己責任とは相手に責任を問うだけでなく自分の過失を覚悟することだと思うのです。そう考えると今の学校教育は実情と逆行している部分が多いのかもしれません。そもそも先生たちが、正解を教わってきた人たちなので、間違いを体験する前に正しいことを教えてしまうのかもしれません。(全てとは言いませんが。)体験に基づかないことはなかなか、自分の物にならないと思うのですが、どうなのでしょうか。
特にサックスを教えるときは、これが正解と教えても、すぐには出来ません。それを消化して、実際に出来るようになるまでは意識を変えるほかに体に覚えさせることも必要だからです。だから、レッスンを受けても練習しない人は絶対に上手くならないと思うのです。
私はサックスをいろいろなレコードや、CD等で学びました。それはサックスの演奏に限らず、また、ジャンルに限らずです。昨日、中学生にサックスの演奏のCDを持っているかどうか聞いてみましたが、誰も持っていませんでした。私としては信じられないのですが、最近の人たちはそうなんでしょうか?自分がサックスをやっていても、J-POPのCDしか買わない、聴かないという人は多いのでしょうか?だとすると、ちょっと寂しくなってしまいます。私のように100枚を超えるようなサックスのCDを買えとは言いません。せめて、自分の理想とする音を奏でる奏者のCDぐらいは愛聴して欲しいのです。もちろん、他のジャンルや楽器の演奏も出来るだけ興味を持って聴いてほしいのですが。
そこで今日の一枚です。

バルトーク/弦楽四重奏曲全集
アルバン・ベルク四重奏団
東芝EMI TOCE-7961~63
このCDはアルバン・ベルク四重奏団の演奏によるバルトークの弦楽四重奏曲集です。1984年から1986年にかけてレコーディングされたものです。
アルバン・ベルク四重奏団は当時ウィーン音楽大学の教授を務めていた4人の若手奏者によって結成されたカルテットです。
バルトークは近年、アレンジされて吹奏楽コンクールなどでもその曲を聞くようになりましたが、日本人にとってはまだまだ馴染みの薄い作曲家かもしれません。バルトークは、シェーンベルク、ストラヴィンスキーと並ぶ20世紀前半を代表するハンガリー の作曲家で、仲のよかったコダーイと共にハンガリー、チェコ、スロヴァキアなど東欧諸国の民謡を集め、楽譜に起こし、自らの前衛的な音楽語法に取り入れて曲を作り出すという技法に特徴があります。第2次大戦中、アメリカに亡命しましたが、後年はあまり幸福な人生を送れず、最後は白血病に倒れてなくなってしまいました。
一時期、サックスのカルテットの演奏の参考に弦楽四重奏を聞いてみようと思い購入したCDです。クラシック・サックスの神様、マルセルミュールも弦楽四重奏にヒントを得て、サックス四重奏を創始したといわれていることからも、是非、弦楽四重奏を聞いておくべきだと思ったのです。
で、何故に、ベートーヴェンとかじゃなく、バルトークかというと、サックスアンサンブルが盛んに作られ始めた時代に近い作曲家だったから、という理由でした。
アルバン・ベルクの演奏はかなり厳格でシャープなイメージの演奏です。あまり贅肉を感じない演奏とも感じます。元々、バルトークの弦楽四重奏曲自体が厳格なイメージの曲なので、この辺、ぴったりはまっている演奏と感じるか厳格に過ぎてきびしすぎると感じるかはそれぞれかもしれません。
バルトークの弦楽四重奏曲を聴いてみたい方、ベートーヴェンとも、ラヴェルとも、ドビュッシーとも違う弦楽四重奏を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年07月04日
宇治ミルク金時。
暑くなってきました。先日も日記に書きましたが、高松の商店街においしいかき氷を出してくれるお店があるので、今年の夏は誰かを誘って生きたいなと思っている今日この頃です。誘う相手が、いませんが、一緒にいってくれる人がかわいらしい女性だったらなおいいなー、などと、ありもしないことを考えてみたりもします。
カキ氷に宇治金時、ミルク金時、そして抹茶ミルク金時などと言ったメニューもあったりしますが、、考えてみると、抹茶とミルクの取り合わせは不思議です。確かに紅茶にミルクを入れてミルクティーにして飲むことはよくやりますが、普通に緑茶にミルクを入れることはありません。日本茶は抹茶でなければミルクを入れて飲むことは無いのかもしれません。当初は苦味を抑える目的の砂糖とミルクだったのかもしれませんが、不思議な組み合わせながら、抜群の組み合わせのような気がします。スター○ックスでもこの組み合わせのドリンクは世界発売されたようですし、日本だけでなく人気の飲み物なのかもしれません。(そこまで言うほどでも無いかもしれませんが)
他にも和洋折衷で不思議なものもあります。ポテトチップスのわさび味なんかも和洋折衷っぽいかもしれません。ステーキを醤油で食べるのもそうかもしれません。
考えてみれば日本人は割と海外の味などを自分たち向きにアレンジするのが上手なのかもしれません。
まあ、サックスアンサンブルで、日本民謡を演奏するようなものなのかも知れませんが。
そこで今日の一枚です。
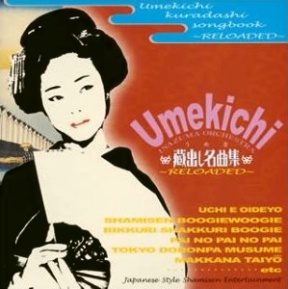
蔵出し名曲集~リローデッド~/Umekichi
DAIPRO-X(ビクター) DXCL-73
このCDは俗曲師うめ吉による不思議な和洋折衷音楽が繰り広げられているもの。
着物姿に日本髪で、三味線による俗曲(三味線弾き唄い)を唄う檜山うめ吉の演奏です。なんと寄席で年間500本の高座をこなす人気芸人である彼女が、ビッグ・バンドとダンサーを従え"Umekichi"として登場したものです。戦前・戦後の流行歌を、ビッグ・バンドをバックに純和風なヴォーカルで聴かせるというまさに古くて新しいテイストの一枚です。曲目は、家へおいでよ-COME ON A MY HOUSE-、三味線ブギウギ、買物ブギー、パイのパイのパイ、真っ赤な太陽、びっくりしゃっくりブギ、野球けん、東京ドドンパ娘、五匹の仔豚とチャールストン、ヘイヘイ・ブギ、ホームラン・ブギ、とある程度お年を召した方にとっては懐かしい曲目です。
この檜山うめ吉さんという方は最年少のプロの落語のお囃子として活動した経歴なども持つまさに実力派の方です。この不思議な和洋折衷のテイストは美空ひばりさんの出演した映画のようなテイストも感じます。まさに和洋折衷のいきな演奏です。舞台で音楽活動をする時にはダンサーを従える形で、稲妻オーケストラ&腰元ダンサーズを率いてUmekichiという名前で活躍しています。
楽しいCDなのですが、少し残念なのはオーディオ的に音のバランスが今ひとつなこと。おそらく、ラジカセ向きのバランスで録音されている気がします。しかしながら十分に楽しめるものです。
少し懐かしいでも新しいい音楽を聴いてみたい方、Umekitiを聴いてみたい方にオススメの一枚です。
カキ氷に宇治金時、ミルク金時、そして抹茶ミルク金時などと言ったメニューもあったりしますが、、考えてみると、抹茶とミルクの取り合わせは不思議です。確かに紅茶にミルクを入れてミルクティーにして飲むことはよくやりますが、普通に緑茶にミルクを入れることはありません。日本茶は抹茶でなければミルクを入れて飲むことは無いのかもしれません。当初は苦味を抑える目的の砂糖とミルクだったのかもしれませんが、不思議な組み合わせながら、抜群の組み合わせのような気がします。スター○ックスでもこの組み合わせのドリンクは世界発売されたようですし、日本だけでなく人気の飲み物なのかもしれません。(そこまで言うほどでも無いかもしれませんが)
他にも和洋折衷で不思議なものもあります。ポテトチップスのわさび味なんかも和洋折衷っぽいかもしれません。ステーキを醤油で食べるのもそうかもしれません。
考えてみれば日本人は割と海外の味などを自分たち向きにアレンジするのが上手なのかもしれません。
まあ、サックスアンサンブルで、日本民謡を演奏するようなものなのかも知れませんが。
そこで今日の一枚です。
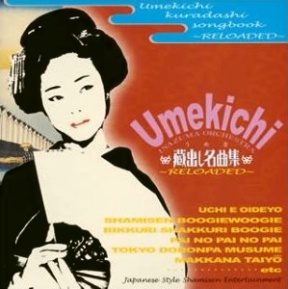
蔵出し名曲集~リローデッド~/Umekichi
DAIPRO-X(ビクター) DXCL-73
このCDは俗曲師うめ吉による不思議な和洋折衷音楽が繰り広げられているもの。
着物姿に日本髪で、三味線による俗曲(三味線弾き唄い)を唄う檜山うめ吉の演奏です。なんと寄席で年間500本の高座をこなす人気芸人である彼女が、ビッグ・バンドとダンサーを従え"Umekichi"として登場したものです。戦前・戦後の流行歌を、ビッグ・バンドをバックに純和風なヴォーカルで聴かせるというまさに古くて新しいテイストの一枚です。曲目は、家へおいでよ-COME ON A MY HOUSE-、三味線ブギウギ、買物ブギー、パイのパイのパイ、真っ赤な太陽、びっくりしゃっくりブギ、野球けん、東京ドドンパ娘、五匹の仔豚とチャールストン、ヘイヘイ・ブギ、ホームラン・ブギ、とある程度お年を召した方にとっては懐かしい曲目です。
この檜山うめ吉さんという方は最年少のプロの落語のお囃子として活動した経歴なども持つまさに実力派の方です。この不思議な和洋折衷のテイストは美空ひばりさんの出演した映画のようなテイストも感じます。まさに和洋折衷のいきな演奏です。舞台で音楽活動をする時にはダンサーを従える形で、稲妻オーケストラ&腰元ダンサーズを率いてUmekichiという名前で活躍しています。
楽しいCDなのですが、少し残念なのはオーディオ的に音のバランスが今ひとつなこと。おそらく、ラジカセ向きのバランスで録音されている気がします。しかしながら十分に楽しめるものです。
少し懐かしいでも新しいい音楽を聴いてみたい方、Umekitiを聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年07月03日
暑くなってきた。
7月に入り、暑くなってきました。私は暑さが苦手な人なので、ちょっと憂鬱になってきます。
さて、前にも書きましたが香川県、水不足になることが多い県なので、これから雨が少ないとちょっと大変なことになります。
おまけに私は暑さに弱いので、今年の夏は大変な夏になりそうな予感がしています。まあ、夏物衣料やエアコン、水着、ビールなんかは売れ行きが伸びると思うのでそういう意味では景気回復に繋がる暑さになるのかもしれませんが。
みなさんの住んでいらしゃる県ではどうなんでしょうか。まあ、先週に比べて日本全体の気温は上がっていると思うのですが、新潟に行ったときは雨が続いたにもかかわらず、本当に過ごしやすかったので、やっぱり狭い日本でも違うなー、と実感しました。
アイスクリームやかき氷が恋しい季節でもあります。数年前、地元で(といっても自転車で20分ぐらいのところ)で美味しい宇治金時を食べさせてくれる甘味処を発見したので、今年もまた行ってみたいと思っています。 私が寝ている部屋にはいまだにエアコンなんて文明の利器はなく、あったとしても築後35年以上を経過した、サッシのない木造建築にとってはエアコンは莫大な電力消費をするためだけのものに過ぎません。部屋にあるオーディオにとってもよくないのでしょうが、夏場は電源を入れるのを控えて加熱しないように気を使ったりもします。電子機器はご多分に漏れず熱には弱く、本当は最低25度以下で動かしたいのですが、環境と経済状況がそれを許してくれません。
ちなみに私の部屋は瓦がよく焼ける2階の南側なので、夏場部屋が40度近くになることもしばしばです。
本当にどうにか涼しく夏を過ごせるものは無いのでしょうか?
そこで今日の一枚です。
ヘンデル/水上の音楽/王宮の花火の音楽
指揮:カール・ミュンヒンガー
シュトゥットガルト室内管弦楽団。
LONDON (ポリドール)POCL-5033
このCDはヘンデルの2大名曲が収録されたものです。水上の音楽は作曲年や成立の過程などは不明な部分も多いのですが、、実際に、テムズ河での舟遊びの際に三回に分けて演奏されたことがわかっています。近年では、この曲を三つの組曲に分けて演奏するケースや、イギリスの大指揮者ハーティ卿が近代オーケストラ用に編曲した版など、様々なタイプの演奏が行われていますが、原点版というものの存在がありません。
王宮の花火の音楽は、 ヘンデルが64歳の時の作品とされ、「水上の音楽」と並ぶ彼の管弦楽曲の傑作といわれています。英仏和平条約調印の記念式典のために作曲されたもので、華やかな式典で演奏される音楽にふさわしく、原曲では、なんと56の管楽器と打楽器を用いるという、当時としてはとてつもない編成で書かれています。
ヘンデルは、バッハと並び称されるドイツ・バロック音楽の巨峰とされ、ヘンデルの活動の場は国際的で、後半生はイギリスに帰化し、オペラやオラトリオの作曲に情熱を傾けました。21歳のときから3年ほどイタリアに滞在し、バロック音楽の大家コレルリやスカルラッティからも、大きな影響を受けたとされています。
ミュンヒンガーといえば世界的にバロック音楽を復興した人手もあります。なんとヴィヴァルディの「四季」をはじめてレコード録音したのも彼です。その他いまや知らない人がいないほど有名になった「パッへるベルのカノン」を有名にしたのも彼の偉業といわれています。
今や、結婚式でもよく聞かれる曲ばかりとなっているので、知らず知らずのうちにバロック音楽を耳にしていることは多いのだと思います。
このCDを聴く限りでははっきりとしたなリズムの扱いと歌うことに過ぎるのを控えた非常に厳格なつくりの音楽を聞くことが出来ます。
夏のひと時に「水」、「花火」と言うキーワードだけでも涼しさを感じさせてくれますが、さらにゆったりと団扇で扇ぎながら音楽に浸るのもいいかもしれません。
夏に清涼感を感じたい方、バロック音楽を聴いてみたい方、結婚式にぴったりのクラシックをお探しの方にオススメの一枚です。
さて、前にも書きましたが香川県、水不足になることが多い県なので、これから雨が少ないとちょっと大変なことになります。
おまけに私は暑さに弱いので、今年の夏は大変な夏になりそうな予感がしています。まあ、夏物衣料やエアコン、水着、ビールなんかは売れ行きが伸びると思うのでそういう意味では景気回復に繋がる暑さになるのかもしれませんが。
みなさんの住んでいらしゃる県ではどうなんでしょうか。まあ、先週に比べて日本全体の気温は上がっていると思うのですが、新潟に行ったときは雨が続いたにもかかわらず、本当に過ごしやすかったので、やっぱり狭い日本でも違うなー、と実感しました。
アイスクリームやかき氷が恋しい季節でもあります。数年前、地元で(といっても自転車で20分ぐらいのところ)で美味しい宇治金時を食べさせてくれる甘味処を発見したので、今年もまた行ってみたいと思っています。 私が寝ている部屋にはいまだにエアコンなんて文明の利器はなく、あったとしても築後35年以上を経過した、サッシのない木造建築にとってはエアコンは莫大な電力消費をするためだけのものに過ぎません。部屋にあるオーディオにとってもよくないのでしょうが、夏場は電源を入れるのを控えて加熱しないように気を使ったりもします。電子機器はご多分に漏れず熱には弱く、本当は最低25度以下で動かしたいのですが、環境と経済状況がそれを許してくれません。
ちなみに私の部屋は瓦がよく焼ける2階の南側なので、夏場部屋が40度近くになることもしばしばです。
本当にどうにか涼しく夏を過ごせるものは無いのでしょうか?
そこで今日の一枚です。
ヘンデル/水上の音楽/王宮の花火の音楽
指揮:カール・ミュンヒンガー
シュトゥットガルト室内管弦楽団。
LONDON (ポリドール)POCL-5033
このCDはヘンデルの2大名曲が収録されたものです。水上の音楽は作曲年や成立の過程などは不明な部分も多いのですが、、実際に、テムズ河での舟遊びの際に三回に分けて演奏されたことがわかっています。近年では、この曲を三つの組曲に分けて演奏するケースや、イギリスの大指揮者ハーティ卿が近代オーケストラ用に編曲した版など、様々なタイプの演奏が行われていますが、原点版というものの存在がありません。
王宮の花火の音楽は、 ヘンデルが64歳の時の作品とされ、「水上の音楽」と並ぶ彼の管弦楽曲の傑作といわれています。英仏和平条約調印の記念式典のために作曲されたもので、華やかな式典で演奏される音楽にふさわしく、原曲では、なんと56の管楽器と打楽器を用いるという、当時としてはとてつもない編成で書かれています。
ヘンデルは、バッハと並び称されるドイツ・バロック音楽の巨峰とされ、ヘンデルの活動の場は国際的で、後半生はイギリスに帰化し、オペラやオラトリオの作曲に情熱を傾けました。21歳のときから3年ほどイタリアに滞在し、バロック音楽の大家コレルリやスカルラッティからも、大きな影響を受けたとされています。
ミュンヒンガーといえば世界的にバロック音楽を復興した人手もあります。なんとヴィヴァルディの「四季」をはじめてレコード録音したのも彼です。その他いまや知らない人がいないほど有名になった「パッへるベルのカノン」を有名にしたのも彼の偉業といわれています。
今や、結婚式でもよく聞かれる曲ばかりとなっているので、知らず知らずのうちにバロック音楽を耳にしていることは多いのだと思います。
このCDを聴く限りでははっきりとしたなリズムの扱いと歌うことに過ぎるのを控えた非常に厳格なつくりの音楽を聞くことが出来ます。
夏のひと時に「水」、「花火」と言うキーワードだけでも涼しさを感じさせてくれますが、さらにゆったりと団扇で扇ぎながら音楽に浸るのもいいかもしれません。
夏に清涼感を感じたい方、バロック音楽を聴いてみたい方、結婚式にぴったりのクラシックをお探しの方にオススメの一枚です。
2008年07月02日
平和についてちょっと考えてみた。
さて、なぜか今日少しだけ平和について考えてみようかとおもいます。いろいろな意見もあると思いますし、一概に平和といっても広範にわたる事柄なのですが、時々私は小さな平和について考えることがあります。
例えば日常の中で他の人が自分の気にいらない発言をしたとします。そのときにどうするかは人様々なのだと思いますが、ここで平和的解決とはどんな方法なのでしょうか。
ほおって置く、気にしない、という意見の方もいると思うのですが、これは一見ことを荒立てず、平和的に見えますが、何の解決にもなっていません。この考え方では北朝鮮に拉致された家族がある事実を知っていながらそのことに触れずに外交をするようなものです。
また、相手と議論する、という方もいると思いますが、私はかねてから思うのですが、日本人は非常に議論の下手な民族だと思っています。(ココで言う日本人とは国籍が日本ということではなく、古くから日本に住み、日本の文化を吸収しつづけた人をさします。)皆さんは議論をしたことがあるでしょうか?大抵の方は議論ではなく「喧嘩」をしているのではないかと思います。
かと言って欧米でバンバン行なわれるディベートの技術でもってまくし立てるのも私はあまり好きでは有りません。それは平和のための交渉ではなく、自分の意見を通すための策を弄していることに他ならない気がするからです。
私が思うのは、自分の意見をはっきりと主張しながら、相手の意見も受け入れる、ということです。この、受け入れるということが曲者で、ともすれば迎合する、ととられがちですが、相手を受容することと迎合することは明らかに違います。
我々は正義に照らしてよく物事を判断しますが、本当にそれが正義かどうかは誰が決めているのでしょう。私は誰かが自分の意見を通したり、利益を得たりする時に、他の誰かが傷ついたり、悲しんだり、不利益をこうむることがあるならばそれは本当の意味での正義では無いと思うのです。法律とは便宜上決めてある規範な訳で、それを守るから善で、守らないから悪、と言い切れないのも確かです。
私はどちらかというと極論を言う方なのでいろいろ誤解を招きやすいことも有ります。例えばこんなことを考えたりします。自衛隊は廃止。代わりに自衛隊は救急隊、レスキュー隊になる、あるいは福祉活動に従事する、というものです。自衛隊を廃止すると、一番困るのは今現在自衛官の人たちの生活な訳で、それを保障するためにもいい案だと思っています。自衛隊で国を守ることなんて到底出来ないことは子どもが考えても判ります。例えばアメリカの軍事力に対抗できるとは到底思えません。
と、まあ、いろいろなことを書いたら、訳のわからないことになってきてしまったので今日の一枚です。
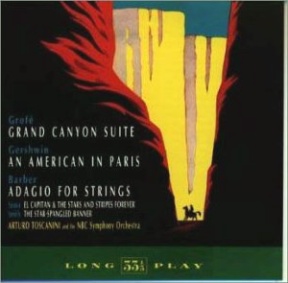
バーバーのアダージョ~アメリカ管弦楽曲集/トスカニーニ
指揮:アルトゥーロ・トスカニーニ
NBC交響楽団
BMGジャパン(RCA) BVCC-9936
このCDはトスカニーニによるアメリカ人作曲家の作品集です。
サミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージョOp.11」は映画「エレファントマン」や、「プラトーン」に使用されていました。
エレファントマンは今で言うプロテウスシンドロームという疾患の患者のことを題材に描かれた、映画で実話を元にして作られたものです。人間の内面にある様々なものを抉り出したようなものです。涙なしに見ることは出来ません。
プラトーンの方は比較的新しい映画(それでももう15年も前)なので、ご存知の方も多いと思いますが、O・ストーン監督によるベトナム戦争をテーマにした映画です。リアルな描写の中に、戦争が生み出す狂気、愚かしさ、ひいてはアメリカ大国の責任を問うものとして、評価されアカデミー作品・監督賞受賞しました。
どちらも人間の内面の部分を史実に基づいた描写の中で深くえぐりだし、その深い闇をあらわにしたような映画だったのではないかと私は思います。その2つの映画にこのバーバーのアダージョが印象的に使われていることも、なんともいえないことです。
切ないメロディーが切々と歌い上げられていく様は映画と無関係でも聴くものの涙を誘うものです。
これだけではやりきれないので、グローフェの組曲「大峡谷」、ガーシュウインのパリのアメリカ人、スーザのカピタン行進曲、星条旗よ永遠なれ、スミスの星条旗(アメリカ国歌、トスカニーニ編)
涙を流してみたい方、人間のについて平和について少し考えてみたい方、また、アメリカの作曲家による管弦楽作品を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
例えば日常の中で他の人が自分の気にいらない発言をしたとします。そのときにどうするかは人様々なのだと思いますが、ここで平和的解決とはどんな方法なのでしょうか。
ほおって置く、気にしない、という意見の方もいると思うのですが、これは一見ことを荒立てず、平和的に見えますが、何の解決にもなっていません。この考え方では北朝鮮に拉致された家族がある事実を知っていながらそのことに触れずに外交をするようなものです。
また、相手と議論する、という方もいると思いますが、私はかねてから思うのですが、日本人は非常に議論の下手な民族だと思っています。(ココで言う日本人とは国籍が日本ということではなく、古くから日本に住み、日本の文化を吸収しつづけた人をさします。)皆さんは議論をしたことがあるでしょうか?大抵の方は議論ではなく「喧嘩」をしているのではないかと思います。
かと言って欧米でバンバン行なわれるディベートの技術でもってまくし立てるのも私はあまり好きでは有りません。それは平和のための交渉ではなく、自分の意見を通すための策を弄していることに他ならない気がするからです。
私が思うのは、自分の意見をはっきりと主張しながら、相手の意見も受け入れる、ということです。この、受け入れるということが曲者で、ともすれば迎合する、ととられがちですが、相手を受容することと迎合することは明らかに違います。
我々は正義に照らしてよく物事を判断しますが、本当にそれが正義かどうかは誰が決めているのでしょう。私は誰かが自分の意見を通したり、利益を得たりする時に、他の誰かが傷ついたり、悲しんだり、不利益をこうむることがあるならばそれは本当の意味での正義では無いと思うのです。法律とは便宜上決めてある規範な訳で、それを守るから善で、守らないから悪、と言い切れないのも確かです。
私はどちらかというと極論を言う方なのでいろいろ誤解を招きやすいことも有ります。例えばこんなことを考えたりします。自衛隊は廃止。代わりに自衛隊は救急隊、レスキュー隊になる、あるいは福祉活動に従事する、というものです。自衛隊を廃止すると、一番困るのは今現在自衛官の人たちの生活な訳で、それを保障するためにもいい案だと思っています。自衛隊で国を守ることなんて到底出来ないことは子どもが考えても判ります。例えばアメリカの軍事力に対抗できるとは到底思えません。
と、まあ、いろいろなことを書いたら、訳のわからないことになってきてしまったので今日の一枚です。
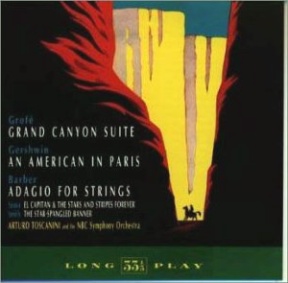
バーバーのアダージョ~アメリカ管弦楽曲集/トスカニーニ
指揮:アルトゥーロ・トスカニーニ
NBC交響楽団
BMGジャパン(RCA) BVCC-9936
このCDはトスカニーニによるアメリカ人作曲家の作品集です。
サミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージョOp.11」は映画「エレファントマン」や、「プラトーン」に使用されていました。
エレファントマンは今で言うプロテウスシンドロームという疾患の患者のことを題材に描かれた、映画で実話を元にして作られたものです。人間の内面にある様々なものを抉り出したようなものです。涙なしに見ることは出来ません。
プラトーンの方は比較的新しい映画(それでももう15年も前)なので、ご存知の方も多いと思いますが、O・ストーン監督によるベトナム戦争をテーマにした映画です。リアルな描写の中に、戦争が生み出す狂気、愚かしさ、ひいてはアメリカ大国の責任を問うものとして、評価されアカデミー作品・監督賞受賞しました。
どちらも人間の内面の部分を史実に基づいた描写の中で深くえぐりだし、その深い闇をあらわにしたような映画だったのではないかと私は思います。その2つの映画にこのバーバーのアダージョが印象的に使われていることも、なんともいえないことです。
切ないメロディーが切々と歌い上げられていく様は映画と無関係でも聴くものの涙を誘うものです。
これだけではやりきれないので、グローフェの組曲「大峡谷」、ガーシュウインのパリのアメリカ人、スーザのカピタン行進曲、星条旗よ永遠なれ、スミスの星条旗(アメリカ国歌、トスカニーニ編)
涙を流してみたい方、人間のについて平和について少し考えてみたい方、また、アメリカの作曲家による管弦楽作品を聴いてみたい方にオススメの一枚です。
2008年07月01日
下戸。
さて、私自身は下戸で一滴も飲まないのでほんとにお酒のことはわかりません。匂いをかぐだけで気分が悪くなるほど酔っ払います。(冗談ではなく)なので、お酒を買うときは人が美味しいというのを信用するしかないのも事実。自分で味見することは出来ると思うのですが、そのあと、何も出来なくなると思います。デパートなんかの試飲コーナーで喜んで飲んでいる人を見るとちょっと不思議な感じさえします。下戸なので損をしているのかはたまた酒代がかからないので特をしているのか。
でも酒の楽しさが少しでもいいのでわかってみたいと思ってあこがれることも有ります。
そこで今日の一枚です。

ストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラ
CAPRICE CAP-21384
このCDはスウェーデンのストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラの演奏の録音です。それぞれの曲を違った指揮者が指揮しており、このCDでは合計4人の指揮者が4曲を指揮しています。ところがこのストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラは残念ながら数年前に経済上の理由で解散してしまっています。この録音にはF.シュミットの「ディオニソスの祭」、I.ストラヴィンスキー「ピアノと管楽器の為の協奏曲」、ナウマン「シンフォニックウィンドオーケストラの為のファンファーレ作品25」、A.ドヴォルザーク「セレナードニ短調B77作品44」と言った作品が収録されています。
ディオニソスとはギリシャ神話での酒と演劇の神の子とです。ギリシャにはディオニソス劇場というものが遺跡として残されています。ギリシャの古代都市にはアクロポリスと劇場が必ずといっていいほどあリましたが、古代アテネの劇場はこのディオニソス劇場だったといわれています。劇場の歴史は紀元前6世紀と古く、1万5000人の観客を収容できる大きな劇場でした。観客席の最前列は貴賓席となっていたようですが、ローマ期に大改築されたので古典期の姿はあまりとどめていないようです。今でも背もたれのある大理石の席が残っているということです。
で、この演奏のギャルドとの一番大きなちがいはなんと言っても「編成」でしょうか。以前のギャルドの編成はサクソルン族を多用し、クラリネットが大量に存在するといった今ではあまり見られない編成でした。当時のフランス圏の楽団はこれが標準的だったようで、現在でもベルギーのギィデ吹奏楽団などはこの名残があるようです。しかしながら、ギャルドは近年大幅な編成改変のため他のアメリカの吹奏楽と変わらない編成になっています。
当然、編成が違うということで代替楽器での演奏や編成の圧縮というものが行なわれています。実際、聞いてみると、昔のギャルドのものに比べてモダンというか、現代的な響きのようにも思いますが、編成の小ささもあってか、音の重厚さは少し失われている気はします。一概にどちらがいいとは言えないのですが、昔のギャルドの方がよりオーケストラに近い響きだったのかもしれません。
とは言え、現在、吹奏楽コンクールなどでは間違いなくアメリカンスタイルの編成で演奏されています。そういった意味ではこの録音はある意味時代としては正しく、貴重なものなのかもしれません。
ディオニソスの酒宴が演奏されている曲なのですが、果たしてどちらの演奏がよりそれを表現しているのかと聞かれると答えには困ってしまいます。酒を飲んだ時の気持ちよさや、気持ち悪さは下戸にはなかなか理解できないのでしょうか?(笑)
ディオニソスの祭を聴いてみたい方、編成の違いをギャルドと比べてみたい方にオススメの一枚です。
でも酒の楽しさが少しでもいいのでわかってみたいと思ってあこがれることも有ります。
そこで今日の一枚です。

ストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラ
CAPRICE CAP-21384
このCDはスウェーデンのストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラの演奏の録音です。それぞれの曲を違った指揮者が指揮しており、このCDでは合計4人の指揮者が4曲を指揮しています。ところがこのストックホルム・シンフォニック・ウインド・オーケストラは残念ながら数年前に経済上の理由で解散してしまっています。この録音にはF.シュミットの「ディオニソスの祭」、I.ストラヴィンスキー「ピアノと管楽器の為の協奏曲」、ナウマン「シンフォニックウィンドオーケストラの為のファンファーレ作品25」、A.ドヴォルザーク「セレナードニ短調B77作品44」と言った作品が収録されています。
ディオニソスとはギリシャ神話での酒と演劇の神の子とです。ギリシャにはディオニソス劇場というものが遺跡として残されています。ギリシャの古代都市にはアクロポリスと劇場が必ずといっていいほどあリましたが、古代アテネの劇場はこのディオニソス劇場だったといわれています。劇場の歴史は紀元前6世紀と古く、1万5000人の観客を収容できる大きな劇場でした。観客席の最前列は貴賓席となっていたようですが、ローマ期に大改築されたので古典期の姿はあまりとどめていないようです。今でも背もたれのある大理石の席が残っているということです。
で、この演奏のギャルドとの一番大きなちがいはなんと言っても「編成」でしょうか。以前のギャルドの編成はサクソルン族を多用し、クラリネットが大量に存在するといった今ではあまり見られない編成でした。当時のフランス圏の楽団はこれが標準的だったようで、現在でもベルギーのギィデ吹奏楽団などはこの名残があるようです。しかしながら、ギャルドは近年大幅な編成改変のため他のアメリカの吹奏楽と変わらない編成になっています。
当然、編成が違うということで代替楽器での演奏や編成の圧縮というものが行なわれています。実際、聞いてみると、昔のギャルドのものに比べてモダンというか、現代的な響きのようにも思いますが、編成の小ささもあってか、音の重厚さは少し失われている気はします。一概にどちらがいいとは言えないのですが、昔のギャルドの方がよりオーケストラに近い響きだったのかもしれません。
とは言え、現在、吹奏楽コンクールなどでは間違いなくアメリカンスタイルの編成で演奏されています。そういった意味ではこの録音はある意味時代としては正しく、貴重なものなのかもしれません。
ディオニソスの酒宴が演奏されている曲なのですが、果たしてどちらの演奏がよりそれを表現しているのかと聞かれると答えには困ってしまいます。酒を飲んだ時の気持ちよさや、気持ち悪さは下戸にはなかなか理解できないのでしょうか?(笑)
ディオニソスの祭を聴いてみたい方、編成の違いをギャルドと比べてみたい方にオススメの一枚です。




