2010年07月19日
クラシックだけじゃない6枚目。
積み上げたCD上から7枚目。
暑い日が続いております。
諸事情により、連休中は外出できず、家に篭る生活。
まあ、今の私にとってはこの生活の方がお似合いなのかもしれません。
もともと、インドア派で内に篭ることが多いので、
ある意味、これが本来の自分。
棚の上に積んであるCDを聞いていくのにも絶好の機会。
そして、今日手に取った上から7枚目。
これも、多分昨日のCDと一緒に買ったはず。

クライマックス70'sルビー
オムニバス
MHCL-1692~3
このCDは1970年代の邦楽ポップスを詰め込んだ2枚組みのCD。ざっと曲目を並べてみると、
(DISC1)
01. 山口百恵/いい日 旅立ち
02. 井上陽水/夢の中へ
03. ツイスト/燃えろいい女
04. 甲斐バンド/HERO(ヒーローになる時、それは今)
05. 堀内孝雄/君のひとみは10000ボルト
06. 財津和夫/Wake Up
07. 八神純子/ポーラースター
08. 尾崎亜美/マイ・ピュア・レディ
09. 桑名正博/セクシャルバイオレット No.1
10. 南 佳孝/モンロー・ウォーク
11. 吉田美奈子/夢で逢えたら
12. はっぴいえんど/風をあつめて
13. ハイ・ファイ・セット/フィーリング
14. 小坂明子/あなた
15. 円 広志/夢想花
16. 岸田智史/きみの朝
17. さとう宗幸/青葉城恋唄
18. 加藤登紀子/知床旅情
19. 泉谷しげる/春夏秋冬
20. よしだたくろう/今日までそして明日から
(DISC2)
01. 西城秀樹/YOUNG MAN (Y.M.C.A.)
02. ピンク・レディー/サウスポー
03. 山口百恵/プレイバック part 2
04. 郷ひろみ & 樹木 希林/林檎殺人事件
05. フィンガー5/学園天国
06. キャンディーズ/微笑がえし
07. 田中星児/ビューティフル・サンデー
08. ゴダイゴ/ビューティフル・ネーム
09. 布施 明/君は薔薇より美しい
10. 原田真二/てぃーんず ぶるーす
11. 庄野真代/飛んでイスタンブール
12. 渡辺真知子/迷い道
13. 桑江知子/私のハートはストップモーション
14. 清水健太郎/失恋レストラン
15. アン・ルイス/グッド・バイ・マイ・ラブ
16. 中村雅俊/俺たちの旅
17. 山本コウタローとウィークエンド/岬めぐり
18. 松崎しげる/愛のメモリー
19. 尾崎紀世彦/また逢う日まで
20. 和田アキ子/あの鐘を鳴らすのはあなた
と、これだけの曲が詰め込まれています。
世代の方、いや、世代の方でなくとも、どこかで聞いたことがある曲が沢山あるのではないでしょうか。思えば、この時代の曲の方が、後の時代になっても聴ける曲、残る曲が多かった気がするのは私だけでしょうか?まだ、J-POPという言葉すらなかった時代の歌謡曲を聴くことが出来ます。
世代の方だけでなく、全ての方にオススメの一枚です。
暑い日が続いております。
諸事情により、連休中は外出できず、家に篭る生活。
まあ、今の私にとってはこの生活の方がお似合いなのかもしれません。
もともと、インドア派で内に篭ることが多いので、
ある意味、これが本来の自分。
棚の上に積んであるCDを聞いていくのにも絶好の機会。
そして、今日手に取った上から7枚目。
これも、多分昨日のCDと一緒に買ったはず。

クライマックス70'sルビー
オムニバス
MHCL-1692~3
このCDは1970年代の邦楽ポップスを詰め込んだ2枚組みのCD。ざっと曲目を並べてみると、
(DISC1)
01. 山口百恵/いい日 旅立ち
02. 井上陽水/夢の中へ
03. ツイスト/燃えろいい女
04. 甲斐バンド/HERO(ヒーローになる時、それは今)
05. 堀内孝雄/君のひとみは10000ボルト
06. 財津和夫/Wake Up
07. 八神純子/ポーラースター
08. 尾崎亜美/マイ・ピュア・レディ
09. 桑名正博/セクシャルバイオレット No.1
10. 南 佳孝/モンロー・ウォーク
11. 吉田美奈子/夢で逢えたら
12. はっぴいえんど/風をあつめて
13. ハイ・ファイ・セット/フィーリング
14. 小坂明子/あなた
15. 円 広志/夢想花
16. 岸田智史/きみの朝
17. さとう宗幸/青葉城恋唄
18. 加藤登紀子/知床旅情
19. 泉谷しげる/春夏秋冬
20. よしだたくろう/今日までそして明日から
(DISC2)
01. 西城秀樹/YOUNG MAN (Y.M.C.A.)
02. ピンク・レディー/サウスポー
03. 山口百恵/プレイバック part 2
04. 郷ひろみ & 樹木 希林/林檎殺人事件
05. フィンガー5/学園天国
06. キャンディーズ/微笑がえし
07. 田中星児/ビューティフル・サンデー
08. ゴダイゴ/ビューティフル・ネーム
09. 布施 明/君は薔薇より美しい
10. 原田真二/てぃーんず ぶるーす
11. 庄野真代/飛んでイスタンブール
12. 渡辺真知子/迷い道
13. 桑江知子/私のハートはストップモーション
14. 清水健太郎/失恋レストラン
15. アン・ルイス/グッド・バイ・マイ・ラブ
16. 中村雅俊/俺たちの旅
17. 山本コウタローとウィークエンド/岬めぐり
18. 松崎しげる/愛のメモリー
19. 尾崎紀世彦/また逢う日まで
20. 和田アキ子/あの鐘を鳴らすのはあなた
と、これだけの曲が詰め込まれています。
世代の方、いや、世代の方でなくとも、どこかで聞いたことがある曲が沢山あるのではないでしょうか。思えば、この時代の曲の方が、後の時代になっても聴ける曲、残る曲が多かった気がするのは私だけでしょうか?まだ、J-POPという言葉すらなかった時代の歌謡曲を聴くことが出来ます。
世代の方だけでなく、全ての方にオススメの一枚です。
2010年07月18日
クラシックだけじゃない5枚目。
積み上げられたCDも上から5枚目。
そういえば、梅雨が明けたらしいです。
夏本番、夏ばての時期がやってきます。
昔は、夏にドライブにでも出かけるか、という気分になったものですが、
最近では、ガソリンも高いし、
そもそも、休みは寝ていたいしということで、滅多にドライブ目的で
出かけることはなくなりました。
どこかに行く用事があって、初めてドライブになる、
ということがほとんどですが、
それにしてみても、一人で仕事や練習に出かけていくぐらいです。
なら、こんなCDどうして買ったの?と言われそうですが…
そこで今日の一枚です。

アラフォー・ドライブ
オムニバス
フォーライフ・ミュージックエンタテイメント
FLCF-4295
このCDは、40歳前後の世代をターゲットにした邦楽のドライブ向けミュージックのコンピレーション。
収録されている曲の世代は、結構ばらばらですが、40代位のかたなら、どこかで聞いたことがあると思われる曲が目白押し。
私の買うCDは、決してクラシックばかりではなく、欲しいと思ったものを買っています。
で、何でこのCDなんだ?と言われそうですが、たまたま、その時ノスタルジックな気分だったのかもしれません。
ちょっと懐かしいドライブミュージックをお探しの方に、オススメの一枚です。
そういえば、梅雨が明けたらしいです。
夏本番、夏ばての時期がやってきます。
昔は、夏にドライブにでも出かけるか、という気分になったものですが、
最近では、ガソリンも高いし、
そもそも、休みは寝ていたいしということで、滅多にドライブ目的で
出かけることはなくなりました。
どこかに行く用事があって、初めてドライブになる、
ということがほとんどですが、
それにしてみても、一人で仕事や練習に出かけていくぐらいです。
なら、こんなCDどうして買ったの?と言われそうですが…
そこで今日の一枚です。

アラフォー・ドライブ
オムニバス
フォーライフ・ミュージックエンタテイメント
FLCF-4295
このCDは、40歳前後の世代をターゲットにした邦楽のドライブ向けミュージックのコンピレーション。
収録されている曲の世代は、結構ばらばらですが、40代位のかたなら、どこかで聞いたことがあると思われる曲が目白押し。
私の買うCDは、決してクラシックばかりではなく、欲しいと思ったものを買っています。
で、何でこのCDなんだ?と言われそうですが、たまたま、その時ノスタルジックな気分だったのかもしれません。
ちょっと懐かしいドライブミュージックをお探しの方に、オススメの一枚です。
2010年07月17日
CD上から4枚目。
熱い日々が続くようになりました。
昨日は、午後から雷が鳴り響き、
遂に梅雨も明けるのかと思わせる天候でした。
仕事で、外出していたために、
ぬれねずみになってしまいましたが。
自宅に帰って、封を切らずにあるいは、
封を切ったけれど1っ懐古っきりきいただけという、溜まったCDを
上から順番に開封したり、明けてみたりしています。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/交響曲第6番『悲愴』
サー・ゲオルグ・ショルティ指揮
シカゴ交響楽団
ユニバーサルクラシック
UCCD 3750
このCDは、ショルティ・シカゴのコンビによるチャイコフスキー。交響曲第6番と、1812年、ロメオとジュリエットと言った序曲が収録されています。
実は、1812は私が、昔初めて聞いた演奏がまさにこれ。当時のCDは、くるみ割り人形の組曲がカップリングされており、シンフォニーはカップリングされていませんでした。個人的には、くるみ割りのカップリングの方が何となく好きですが…。
さて、肝心の演奏のほうですが、交響曲第6番は、謳わせ方でなく、少々力でねじ伏せた感もある演奏。精緻な演奏というよりは多少粗野な演奏に聞こえます。バーンスタイン指揮のものなどを聴くともっとメランコリックというか、ねちっこさのようなものを感じますが、この演奏ではそれが感じられず、少し不満残る気がします。
1812年は昔聞いたあの懐かしい響き。力強い金管と、何よりも冒頭のコラールの響き、謳わせ方は素晴らしいと思います。当時、大砲の実音の録音なども話題になりましたが、こちらの方がショルティの演奏スタイルにあっているのかもしれません。
序曲「1812年」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
昨日は、午後から雷が鳴り響き、
遂に梅雨も明けるのかと思わせる天候でした。
仕事で、外出していたために、
ぬれねずみになってしまいましたが。
自宅に帰って、封を切らずにあるいは、
封を切ったけれど1っ懐古っきりきいただけという、溜まったCDを
上から順番に開封したり、明けてみたりしています。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/交響曲第6番『悲愴』
サー・ゲオルグ・ショルティ指揮
シカゴ交響楽団
ユニバーサルクラシック
UCCD 3750
このCDは、ショルティ・シカゴのコンビによるチャイコフスキー。交響曲第6番と、1812年、ロメオとジュリエットと言った序曲が収録されています。
実は、1812は私が、昔初めて聞いた演奏がまさにこれ。当時のCDは、くるみ割り人形の組曲がカップリングされており、シンフォニーはカップリングされていませんでした。個人的には、くるみ割りのカップリングの方が何となく好きですが…。
さて、肝心の演奏のほうですが、交響曲第6番は、謳わせ方でなく、少々力でねじ伏せた感もある演奏。精緻な演奏というよりは多少粗野な演奏に聞こえます。バーンスタイン指揮のものなどを聴くともっとメランコリックというか、ねちっこさのようなものを感じますが、この演奏ではそれが感じられず、少し不満残る気がします。
1812年は昔聞いたあの懐かしい響き。力強い金管と、何よりも冒頭のコラールの響き、謳わせ方は素晴らしいと思います。当時、大砲の実音の録音なども話題になりましたが、こちらの方がショルティの演奏スタイルにあっているのかもしれません。
序曲「1812年」を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年07月16日
CD上から3枚目。
以前は、クラシックのCDは3000円~3500円ぐらいしていました。
それ以前、LPレコードでも、2000円~3000円。
ちょっとレアな録音や、盤面に高価なものを使っていると、
もっとお高いものになったりしていました。
それが、最近音楽業界も不況なのか、
CDが単に売れないのか、CDの単価がグッと下がってきました。
以前、欲しくて手に入れられなかった音源が、
最近手軽に手に入ります。
しかし、以前に比べて新しい録音がさっぱり出ません。
優秀なエンジニアが減ってしまったのか、
不況で、録音という大きな経済活動が出来なくなったのか…。
以前にせよ、CDが安くなったのはありがたいですが、
寂しい限りです。
そこで今日の一枚です。

サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン付き》
エルネスト・アンセルメ指揮
スイス・ロマンド管弦楽団
UCCD7065
ユニバーサル・ミュージック
このCDは、アンセルメとスイスロマンドのDECCA録音黄金期をささえたコンビによるサン=サーンスの交響曲第3番《オルガン付き》、フランクの交響曲第2番が収録されたもの。
もちろん、元はLPレコードで発売された音源です。当時としては、驚異のダイナミックレンジとS/N比を誇った録音でした。CDで聴く現在でも、オルガンの重低音の響きは圧巻。
アンセルメらしい色彩感豊かな演奏と相まって、また、スイスロマンド管弦楽団はどこかヘタウマな部分を感じることが多いのですが、ことこの録音に関しては、演奏もかなり秀逸。
サン=サーンスの交響曲第3番《オルガン付き》を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
それ以前、LPレコードでも、2000円~3000円。
ちょっとレアな録音や、盤面に高価なものを使っていると、
もっとお高いものになったりしていました。
それが、最近音楽業界も不況なのか、
CDが単に売れないのか、CDの単価がグッと下がってきました。
以前、欲しくて手に入れられなかった音源が、
最近手軽に手に入ります。
しかし、以前に比べて新しい録音がさっぱり出ません。
優秀なエンジニアが減ってしまったのか、
不況で、録音という大きな経済活動が出来なくなったのか…。
以前にせよ、CDが安くなったのはありがたいですが、
寂しい限りです。
そこで今日の一枚です。

サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン付き》
エルネスト・アンセルメ指揮
スイス・ロマンド管弦楽団
UCCD7065
ユニバーサル・ミュージック
このCDは、アンセルメとスイスロマンドのDECCA録音黄金期をささえたコンビによるサン=サーンスの交響曲第3番《オルガン付き》、フランクの交響曲第2番が収録されたもの。
もちろん、元はLPレコードで発売された音源です。当時としては、驚異のダイナミックレンジとS/N比を誇った録音でした。CDで聴く現在でも、オルガンの重低音の響きは圧巻。
アンセルメらしい色彩感豊かな演奏と相まって、また、スイスロマンド管弦楽団はどこかヘタウマな部分を感じることが多いのですが、ことこの録音に関しては、演奏もかなり秀逸。
サン=サーンスの交響曲第3番《オルガン付き》を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年07月15日
上から二枚目。
まだまだ、積み上げっぱなしのCD。
そういえば、ボチボチCDプレーヤーも買い替え時期が近づいているのかも知れません。
何しろ、いま使っているフィリップスのLHH-500Rは、先日見送った
MDプレーヤーよりもさらにふるいので…。
メカがいいからなのでしょう、しっかりしたパーツで組まれているためか、
修理を1度しましたが、10年以上経っていても現役でいい音です。
さすがに、今の高級機と聞き比べると古さを感じるかもしれませんが、
最近の安っぽいCDプレーヤーなら、足元にも及ばない音質だと思っています。
しかしながら、物はいつかは壊れる、ということで、ボチボチやばそうです。
近い音が鳴るCDプレーヤーを探したこともありますが、なかなか代替になるものは
見つかりませんでした。
次に買うとしたら、マランツの高級機か、あるいはヤマハのSACDぐらいかな、
と考えたりしていますが、いかんせん、高松のオーディオショップはほぼ全滅に近い状態で、
大阪ぐらいまで行かないと試聴できないのが現状。
そんなこんなで、積み上げられたCD、上から二枚目。
そこで今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番
ジョージ・セル指揮
クリーヴランド管弦楽団
SONY SBK46534
このCDは、ジョージ・セルとクリーヴランドの黄金コンビによるブラ1。何故か、のだめカンタービレの影響で、ブラ1が妙に知られる曲となってしまいましたが…。
さて、演奏のほうは、セルらしい見通しのよいすっきりとした演奏。しかしながら、テンポは速すぎることもなく、中庸なテンポ設定で、部分的にじっくりと聞かすところもあります。
ただ、ドイツの伝統的なオケに比べると、渋みというか、こくのようなものが足りない感覚もしますが、演奏は十分に整理され、しっかりと謳いこまれ、これはこのスタイルでとても素晴らしい演奏です。くせがあまりないだけに、初めて聴く方にもオススメの一枚です。
そういえば、ボチボチCDプレーヤーも買い替え時期が近づいているのかも知れません。
何しろ、いま使っているフィリップスのLHH-500Rは、先日見送った
MDプレーヤーよりもさらにふるいので…。
メカがいいからなのでしょう、しっかりしたパーツで組まれているためか、
修理を1度しましたが、10年以上経っていても現役でいい音です。
さすがに、今の高級機と聞き比べると古さを感じるかもしれませんが、
最近の安っぽいCDプレーヤーなら、足元にも及ばない音質だと思っています。
しかしながら、物はいつかは壊れる、ということで、ボチボチやばそうです。
近い音が鳴るCDプレーヤーを探したこともありますが、なかなか代替になるものは
見つかりませんでした。
次に買うとしたら、マランツの高級機か、あるいはヤマハのSACDぐらいかな、
と考えたりしていますが、いかんせん、高松のオーディオショップはほぼ全滅に近い状態で、
大阪ぐらいまで行かないと試聴できないのが現状。
そんなこんなで、積み上げられたCD、上から二枚目。
そこで今日の一枚です。

ブラームス/交響曲第1番
ジョージ・セル指揮
クリーヴランド管弦楽団
SONY SBK46534
このCDは、ジョージ・セルとクリーヴランドの黄金コンビによるブラ1。何故か、のだめカンタービレの影響で、ブラ1が妙に知られる曲となってしまいましたが…。
さて、演奏のほうは、セルらしい見通しのよいすっきりとした演奏。しかしながら、テンポは速すぎることもなく、中庸なテンポ設定で、部分的にじっくりと聞かすところもあります。
ただ、ドイツの伝統的なオケに比べると、渋みというか、こくのようなものが足りない感覚もしますが、演奏は十分に整理され、しっかりと謳いこまれ、これはこのスタイルでとても素晴らしい演奏です。くせがあまりないだけに、初めて聴く方にもオススメの一枚です。
2010年07月14日
面白くない人生。
あいも変わらず、
面白くも
楽しくもない人生です。
いろいろありましたが。
沢山CDを買い込んだにも関わらず、
封も切らずに
山積み状態。
少なくとも聞いていないCDが20枚以上あります。
折角なので、
一番上に積んであったCDを。
そこで今日の一枚です。

Flying Saxophone Circus/selmer saxharmonic
MDG 910 1625-6
このCDはselmer saxharmonicによるサクソフォンのラージアンサンブル。海外のラージアンサンブルといえば、どうしてもジャズよりの演奏だったり、なんとなく適当な部分が散見するアンサンブルだったり、縦の線や謳い方が統一されていない寄せ集め感がある演奏だったりというイメージが私には会ったのですが、このアンサンブルは一味違いました。細かいディティールまで、表現がよく統一されています。また、きちんとクラシカルな響きがします。全くタイプは違うかもしれませんが、そういった意味ではミベモル的なのかもしれません。
クラシカルなサクソフォンのラージ演奏を聞きたい方にオススメの一枚です。
面白くも
楽しくもない人生です。
いろいろありましたが。
沢山CDを買い込んだにも関わらず、
封も切らずに
山積み状態。
少なくとも聞いていないCDが20枚以上あります。
折角なので、
一番上に積んであったCDを。
そこで今日の一枚です。

Flying Saxophone Circus/selmer saxharmonic
MDG 910 1625-6
このCDはselmer saxharmonicによるサクソフォンのラージアンサンブル。海外のラージアンサンブルといえば、どうしてもジャズよりの演奏だったり、なんとなく適当な部分が散見するアンサンブルだったり、縦の線や謳い方が統一されていない寄せ集め感がある演奏だったりというイメージが私には会ったのですが、このアンサンブルは一味違いました。細かいディティールまで、表現がよく統一されています。また、きちんとクラシカルな響きがします。全くタイプは違うかもしれませんが、そういった意味ではミベモル的なのかもしれません。
クラシカルなサクソフォンのラージ演奏を聞きたい方にオススメの一枚です。
2010年02月13日
しっかりと。
アンサンブルコンテスト
四国支部大会が終了してから
はや一週間。
結果は、
そのうち、本家ダッパーブログに
掲載されると思いますので、
割愛。
アンサンブルコンテストが
終了してから
思うことは、
やはり、
自分にはまだまだ基礎的な
スキルが足りないということでしょうか。
しっかりとした演奏をするためには、
やはり基礎的な練習を
意識と目的をもって
継続的に行わなければなりません。
まだまだやらなければならないことは
沢山あります。
ヘタレサックス吹きの
私には、
なかなかたどり着けないところです。
そこで今日の一枚です。

Saxophone Classics
Diastema Saxophone Quartet
NAXOS 8.5554308
このCDは、Diastema Saxopone Quartetのおそらく、2枚目になるアルバム。1枚目のアルバムが、フランスものの、サクソフォーンの古典的オリジナル曲集だったのに対し、こちらは、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンといった作曲家の曲のアレンジものが収録されています。
演奏は、比較的大げさな表現をしない、淡白なもの。ただ、それなりに、個性や遊び心を感じる部分があり、さすがフランスのカルテットと言ったところでしょうか。演奏も見通しよく、しっかりとしています。
クラシックの古典をサクソフォンで聞いてみたい方にオススメの一枚です。
四国支部大会が終了してから
はや一週間。
結果は、
そのうち、本家ダッパーブログに
掲載されると思いますので、
割愛。
アンサンブルコンテストが
終了してから
思うことは、
やはり、
自分にはまだまだ基礎的な
スキルが足りないということでしょうか。
しっかりとした演奏をするためには、
やはり基礎的な練習を
意識と目的をもって
継続的に行わなければなりません。
まだまだやらなければならないことは
沢山あります。
ヘタレサックス吹きの
私には、
なかなかたどり着けないところです。
そこで今日の一枚です。

Saxophone Classics
Diastema Saxophone Quartet
NAXOS 8.5554308
このCDは、Diastema Saxopone Quartetのおそらく、2枚目になるアルバム。1枚目のアルバムが、フランスものの、サクソフォーンの古典的オリジナル曲集だったのに対し、こちらは、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンといった作曲家の曲のアレンジものが収録されています。
演奏は、比較的大げさな表現をしない、淡白なもの。ただ、それなりに、個性や遊び心を感じる部分があり、さすがフランスのカルテットと言ったところでしょうか。演奏も見通しよく、しっかりとしています。
クラシックの古典をサクソフォンで聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年02月03日
弦楽セレナード漬け、その5。
今日は水曜日。
週の中日ですが、
はや精神的にも
肉体的にも疲れ果てています。
しかし、本番は待ってくれません。
週末には、
アンサンブルコンテスト
四国支部大会がやってきます。
弦楽セレナード、
いい演奏が出来るといいなと思いつつ、
ここ数日の日記を書いています。
さて、そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/オーケストラ・マスターピースVOL.2
ピエール・モントゥー他指揮
ロンドン・シンフォニー他
ヴァンガードクラシック ATM-CD-1198
このCDは、チャイコフスキーの作品集。オムニバスで、演奏団体もばらばら、指揮者もばらばら、2枚組みのお買い得?CDです。さて、弦楽セレナードに限って言えば、演奏は、オーストラリア・チェンバー・オーケストラ。あまり耳なじみがないかもしれませんが、オーストラリアでは、立派にメジャーなチェンバーオケです。演奏の方は、真面目にやってます!といった感じの演奏。チェンバーオケらしい、コンパクトさと、若手の演奏家が多いためか、はつらつとした演奏が楽しめます。ただ、フレージングが、楽譜と、楽譜に書き込んだ注意書きが見えそうな感覚になるのはちょっと残念。すばらしい演奏なので、もう少し、アバウトなノリというか、ゆらぎのようなものを感じてみたい気もします。
総じて、教科書的ではありますが、演奏としては申し分ありません。
きちんとした演奏、オーストラリアのオケの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
週の中日ですが、
はや精神的にも
肉体的にも疲れ果てています。
しかし、本番は待ってくれません。
週末には、
アンサンブルコンテスト
四国支部大会がやってきます。
弦楽セレナード、
いい演奏が出来るといいなと思いつつ、
ここ数日の日記を書いています。
さて、そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/オーケストラ・マスターピースVOL.2
ピエール・モントゥー他指揮
ロンドン・シンフォニー他
ヴァンガードクラシック ATM-CD-1198
このCDは、チャイコフスキーの作品集。オムニバスで、演奏団体もばらばら、指揮者もばらばら、2枚組みのお買い得?CDです。さて、弦楽セレナードに限って言えば、演奏は、オーストラリア・チェンバー・オーケストラ。あまり耳なじみがないかもしれませんが、オーストラリアでは、立派にメジャーなチェンバーオケです。演奏の方は、真面目にやってます!といった感じの演奏。チェンバーオケらしい、コンパクトさと、若手の演奏家が多いためか、はつらつとした演奏が楽しめます。ただ、フレージングが、楽譜と、楽譜に書き込んだ注意書きが見えそうな感覚になるのはちょっと残念。すばらしい演奏なので、もう少し、アバウトなノリというか、ゆらぎのようなものを感じてみたい気もします。
総じて、教科書的ではありますが、演奏としては申し分ありません。
きちんとした演奏、オーストラリアのオケの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年02月02日
弦楽セレナード漬け、その4。
今回で、弦楽セレナード漬けも
はや4回目。
以前にも何枚か弦楽セレナードの
収録されたCDは紹介していますので、
これでおそらく10枚を超える
チャイコフスキーの弦楽セレナードを
紹介したのではないかと思います。
さて、昨日も少し書きましたが、
フルオケと弦楽アンサンブルの演奏。
私が感じるのは、一つは人数の違い。
フルオケの弦楽セクションは当然ながら
大人数。
大して、弦楽アンサンブルは、
比較的少人数。
場合によると、パート数きっちりの人数しか
いないような演奏もあるかもしれません。
オーケストラでは、不思議なことに、
管楽器を複数人数で同じパートの演奏をさせると、
倍管と言われ、少し特異に見られますが、
弦は、同じパートを何人が弾いても、
そんなことは言われません。
厳密に言えば、プルートの中で、
割合は決まっているのかもしれませんが。
人数の関係か、フルオケの弦セクションの場合は、
比較的ゆったりしたテンポの
分厚い演奏が多いようです。
カラヤン/ベルリンフィル
や、
先日紹介したミュンシュ/ボストン響
等は、その筆頭でしょうか。
対して弦楽アンサンブル
となると、
オルフェウスの演奏が典型。
もちろん、例外も多数あるとは思いますが。
そこで今日の一枚です。
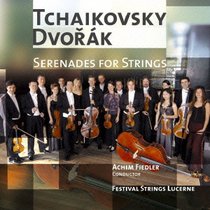
チャイコフスキー/弦楽セレナード
ドヴォルザーク/弦楽セレナード
フェスティバル・ストリングス・ルツェルン
ソニーミュージック BVCC400016
このCDは、昨年来日し、神尾真由子氏と競演したことでも話題になった、フェスティバル・ストリングス・ルツェルンのアルバム。代表的で、よくカップリングされる、2曲が収録されています。
演奏は、比較的速めのテンポの元気の良い演奏。室内楽編成だけあって、コントラバスなんかは2人しかいません。ゴリゴリ感のある分厚い響きのえんそうというわけには行きません。
ただ、場面によっては、もう少し、ゆったりとしたテンポで情感豊かな演奏を聞かせて欲しいと感じる部分もあります。
もしかしたら、もっとサロン音楽風の曲や、モーツアルト、現代曲などがあっている演奏スタイルなのかもしれないと思いました。少しモダンな響きといったら言いのでしょうか?
演奏、録音が比較的新しいのが最近の演奏を感じられる気がしていいかもしれません。
現代風のはつらつとした弦楽セレナードを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
はや4回目。
以前にも何枚か弦楽セレナードの
収録されたCDは紹介していますので、
これでおそらく10枚を超える
チャイコフスキーの弦楽セレナードを
紹介したのではないかと思います。
さて、昨日も少し書きましたが、
フルオケと弦楽アンサンブルの演奏。
私が感じるのは、一つは人数の違い。
フルオケの弦楽セクションは当然ながら
大人数。
大して、弦楽アンサンブルは、
比較的少人数。
場合によると、パート数きっちりの人数しか
いないような演奏もあるかもしれません。
オーケストラでは、不思議なことに、
管楽器を複数人数で同じパートの演奏をさせると、
倍管と言われ、少し特異に見られますが、
弦は、同じパートを何人が弾いても、
そんなことは言われません。
厳密に言えば、プルートの中で、
割合は決まっているのかもしれませんが。
人数の関係か、フルオケの弦セクションの場合は、
比較的ゆったりしたテンポの
分厚い演奏が多いようです。
カラヤン/ベルリンフィル
や、
先日紹介したミュンシュ/ボストン響
等は、その筆頭でしょうか。
対して弦楽アンサンブル
となると、
オルフェウスの演奏が典型。
もちろん、例外も多数あるとは思いますが。
そこで今日の一枚です。
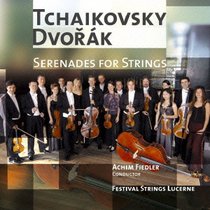
チャイコフスキー/弦楽セレナード
ドヴォルザーク/弦楽セレナード
フェスティバル・ストリングス・ルツェルン
ソニーミュージック BVCC400016
このCDは、昨年来日し、神尾真由子氏と競演したことでも話題になった、フェスティバル・ストリングス・ルツェルンのアルバム。代表的で、よくカップリングされる、2曲が収録されています。
演奏は、比較的速めのテンポの元気の良い演奏。室内楽編成だけあって、コントラバスなんかは2人しかいません。ゴリゴリ感のある分厚い響きのえんそうというわけには行きません。
ただ、場面によっては、もう少し、ゆったりとしたテンポで情感豊かな演奏を聞かせて欲しいと感じる部分もあります。
もしかしたら、もっとサロン音楽風の曲や、モーツアルト、現代曲などがあっている演奏スタイルなのかもしれないと思いました。少しモダンな響きといったら言いのでしょうか?
演奏、録音が比較的新しいのが最近の演奏を感じられる気がしていいかもしれません。
現代風のはつらつとした弦楽セレナードを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年02月01日
弦楽セレナード漬け、その3。
さて、弦楽セレナードの
音源を聴いていくと、
乱暴に言えば演奏に大きく分けて2種類があるような
気がしています。
一つは、フルオケの弦楽セクションが弾いたもの。
もう一つは、弦楽アンサンブルが弾いたもの。
どちらも同じ様に思えるかもしれませんが、
私は個人的にこの二つに違いを感じています。
次回も含め、それはおいおい、書くとして、
今回も弦楽セレナードの音源。
そこで今日の一枚です。
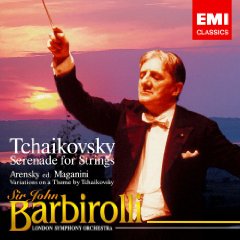
チャイコフスキー/弦楽セレナード
アレンスキー/チャイコフスキーの主題による変奏曲
ジョン・バルビローリ指揮
ロンドン交響楽団
東芝EMI TOCE-14234
このCDはバルビローリ指揮の弦楽セレナードと、アレンスキーが収録されたもの。ロンドン交響楽団の演奏。間違いなく、フルオケの弦楽セクションが大人数で弾いています。
バルビローリはイタリア人の父と、フランス人の母を持ち、イギリスで生まれた人。元はチェリスト。そのためかどうかは判りませんが、イタリア歌曲のようなこってりとした歌いまわしや、フランス流のエスプリとも取れる謡回しが各所に聞かれます。ただ、何故かそれをきっちりとしたテンポの中に無理やりのように収めていこうとする感覚を覚えるのは私だけでしょうか?また、旋律線のしっかりとした演奏を聞かせてくれますが、その反面、パート同士の間に乖離が感じられることが。このあたりは、トレードオフなのかもしれませんが、熱狂的に、この演奏をいい、と感じることは出来ませんでした。
でも、この独特の謳いまわしは、聴くと癖になるかもしれません。
バルビローリの歌を感じたい方にオススメの一枚です。
バルビローリの歌をチャイコフスキーで楽しみたい方にオススメの一枚です。
音源を聴いていくと、
乱暴に言えば演奏に大きく分けて2種類があるような
気がしています。
一つは、フルオケの弦楽セクションが弾いたもの。
もう一つは、弦楽アンサンブルが弾いたもの。
どちらも同じ様に思えるかもしれませんが、
私は個人的にこの二つに違いを感じています。
次回も含め、それはおいおい、書くとして、
今回も弦楽セレナードの音源。
そこで今日の一枚です。
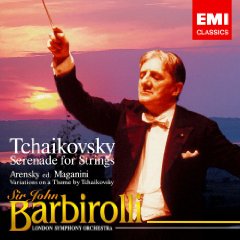
チャイコフスキー/弦楽セレナード
アレンスキー/チャイコフスキーの主題による変奏曲
ジョン・バルビローリ指揮
ロンドン交響楽団
東芝EMI TOCE-14234
このCDはバルビローリ指揮の弦楽セレナードと、アレンスキーが収録されたもの。ロンドン交響楽団の演奏。間違いなく、フルオケの弦楽セクションが大人数で弾いています。
バルビローリはイタリア人の父と、フランス人の母を持ち、イギリスで生まれた人。元はチェリスト。そのためかどうかは判りませんが、イタリア歌曲のようなこってりとした歌いまわしや、フランス流のエスプリとも取れる謡回しが各所に聞かれます。ただ、何故かそれをきっちりとしたテンポの中に無理やりのように収めていこうとする感覚を覚えるのは私だけでしょうか?また、旋律線のしっかりとした演奏を聞かせてくれますが、その反面、パート同士の間に乖離が感じられることが。このあたりは、トレードオフなのかもしれませんが、熱狂的に、この演奏をいい、と感じることは出来ませんでした。
でも、この独特の謳いまわしは、聴くと癖になるかもしれません。
バルビローリの歌を感じたい方にオススメの一枚です。
バルビローリの歌をチャイコフスキーで楽しみたい方にオススメの一枚です。
2010年01月31日
弦楽セレナード漬け、その2。
さて、
まだまだ行きます、
弦楽セレナード。
メジャーなレーベルだけではなく、
一応、マイナーレーベルや
ナクソスといった廉価版CDまで、
数多く取り揃えております(笑)。
そこで今日の一枚です。
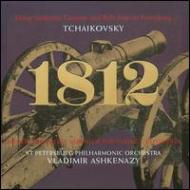
チャイコフスキー/1812年
ウラディミール・アシュケナージ指揮
サンクト・ペテルブルク・フィルハーモニー
DECCA 455 971-2
このCDは、アシュケナージが、サンクトペテルブルクフィルを指揮したチャイコフスキーの作品集。実際のところ、1812年がメインのアルバムといっても過言ではありません。その証拠に、CDのケースに、箔押しの1812の文字が入っているほどの年の入れよう。この1812年は、キャノン砲、教会の鐘などを実際に使用し、冒頭の部分も合唱で演奏されている演奏です。
それはさておき、私は何となくアシュケナージという指揮者が苦手。見通しのより、明解な音楽と評する人もいますが、私は、何故かペラペラの上っ面の音楽に聞こえてしまうことがしばしば。
また、オケの強奏部や、アタックの種類が貧弱な気がしています。柔らかいアタックを意識するあまりに、見通しが良いはずなのに、何故か音の立ち上がりに不満を感じる部分も。
ただ、アシュケナージという人の熱狂的なファン、特にピアノ演奏に関してはそうだと思いますが、そういった方も数多く存在するので、私の好みの問題なのだと思います。
また、純粋にロシアのオーケストラの弦楽セレナードが意外と新しい録音では少ないので、貴重な演奏ではあります。
ロシアのオケのチャイコフスキーをきいてみたいかたにオススメの一枚です。
まだまだ行きます、
弦楽セレナード。
メジャーなレーベルだけではなく、
一応、マイナーレーベルや
ナクソスといった廉価版CDまで、
数多く取り揃えております(笑)。
そこで今日の一枚です。
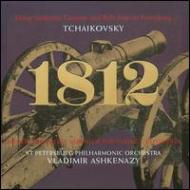
チャイコフスキー/1812年
ウラディミール・アシュケナージ指揮
サンクト・ペテルブルク・フィルハーモニー
DECCA 455 971-2
このCDは、アシュケナージが、サンクトペテルブルクフィルを指揮したチャイコフスキーの作品集。実際のところ、1812年がメインのアルバムといっても過言ではありません。その証拠に、CDのケースに、箔押しの1812の文字が入っているほどの年の入れよう。この1812年は、キャノン砲、教会の鐘などを実際に使用し、冒頭の部分も合唱で演奏されている演奏です。
それはさておき、私は何となくアシュケナージという指揮者が苦手。見通しのより、明解な音楽と評する人もいますが、私は、何故かペラペラの上っ面の音楽に聞こえてしまうことがしばしば。
また、オケの強奏部や、アタックの種類が貧弱な気がしています。柔らかいアタックを意識するあまりに、見通しが良いはずなのに、何故か音の立ち上がりに不満を感じる部分も。
ただ、アシュケナージという人の熱狂的なファン、特にピアノ演奏に関してはそうだと思いますが、そういった方も数多く存在するので、私の好みの問題なのだと思います。
また、純粋にロシアのオーケストラの弦楽セレナードが意外と新しい録音では少ないので、貴重な演奏ではあります。
ロシアのオケのチャイコフスキーをきいてみたいかたにオススメの一枚です。
2010年01月30日
弦楽セレナード漬け、その1。
ダッパーが出場する
アンサンブルコンテスト四国支部大会
まであと一週間。
当然、聴く音源も、
弦楽セレナード漬け。
以前も少し弦楽セレナーデの
音源を紹介しましたが、
実は、まだまだ持っていたり。
ということで、最近、参考にという
理由をつけて、
弦楽セレナードの音源を聞きあさっています。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/弦楽セレナード
バーバー/アダージョ、他
シャルル・ミュンシュ指揮
ボストン交響楽団
BMG BVCC20007
このCDは、自身もヴァイオリニスであった経歴を持つミュンシュ指揮の弦楽曲を中心としたアルバム。因みに、Blu-spec CDと銘打って高品位な再生が出来るCDということに成っているようです。
弦楽セレナーデは、速めのテンポ設定で、はつらつとした印象。所々、もっと謳って欲しい部分が感じられることもありますが 、逆に歌に溺れることなく、すっきりとした演奏と感じられなくもありません。ところで、この時代の指揮者は、オケの配置や、ともすれば、楽譜にかなり手を入れることがあったようで、この演奏の弦楽セレナーデも、明らかに手を入れたであろう部分が聞いて取れます。特に終楽章の最後は、ちょっとギョッとするかもしれません。
録音が古いにも関わらず、録音は、きわめてクリア。私としては、弦楽セレナードよりも、バーバーのアダージョのの方がさらに良かった気がしています。弦楽でのミュンシュの指揮を感じたい方にオススメの一枚です。
アンサンブルコンテスト四国支部大会
まであと一週間。
当然、聴く音源も、
弦楽セレナード漬け。
以前も少し弦楽セレナーデの
音源を紹介しましたが、
実は、まだまだ持っていたり。
ということで、最近、参考にという
理由をつけて、
弦楽セレナードの音源を聞きあさっています。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/弦楽セレナード
バーバー/アダージョ、他
シャルル・ミュンシュ指揮
ボストン交響楽団
BMG BVCC20007
このCDは、自身もヴァイオリニスであった経歴を持つミュンシュ指揮の弦楽曲を中心としたアルバム。因みに、Blu-spec CDと銘打って高品位な再生が出来るCDということに成っているようです。
弦楽セレナーデは、速めのテンポ設定で、はつらつとした印象。所々、もっと謳って欲しい部分が感じられることもありますが 、逆に歌に溺れることなく、すっきりとした演奏と感じられなくもありません。ところで、この時代の指揮者は、オケの配置や、ともすれば、楽譜にかなり手を入れることがあったようで、この演奏の弦楽セレナーデも、明らかに手を入れたであろう部分が聞いて取れます。特に終楽章の最後は、ちょっとギョッとするかもしれません。
録音が古いにも関わらず、録音は、きわめてクリア。私としては、弦楽セレナードよりも、バーバーのアダージョのの方がさらに良かった気がしています。弦楽でのミュンシュの指揮を感じたい方にオススメの一枚です。
2010年01月02日
練習開始。
本日、今年初めての
ダッパーの練習。
練習の詳細は本家ブログに
そのうち掲載されることと思いますので、
ほぼ割愛。
私は、別にやることもないので、
昨日から練習しても、
何のことはなかったのですが、
さすがに家庭のある人々は
そういうわけにも行かないらしいです。
本日もアンサンブルコンテストに向けての
弦楽セレナーデの練習。
そこで今日の一枚です。
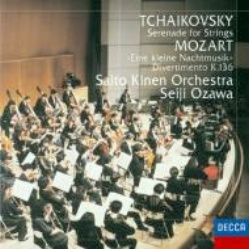
チャイコフスキー/弦楽セレナード
モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
小澤征爾 指揮
サイトウ・キネン・オーケストラ
UCCD50034 ユニバーサルミュージック
このCDは、1984年9月に斎藤秀雄の没後10年記念に弟子であった小澤征爾と秋山和慶を中心に、教え子たちなどが結集して臨時編成されたメモリアル・オーケストラである、サイトウ・キネンオーケストラによるセレナードの演奏が収録されたもの。基本的に、弦楽セクションのみの演奏物です。表現は悪いですが、世界最高の寄せ集めオーケストラ。
この演奏、間違いなく、世界最高レベル。ただ、もう少し欲を言うならば、少々ヘタクソでもいいので、熱い情熱が感じられたら最高かもしれません。
しかし、それは好みの問題で、音楽表現、技術ともに、この上の演奏はなかなか望めないであろうと負わせるほどの凄さがあります。
日本のオーケストラによる、弦楽セレナーデを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
ダッパーの練習。
練習の詳細は本家ブログに
そのうち掲載されることと思いますので、
ほぼ割愛。
私は、別にやることもないので、
昨日から練習しても、
何のことはなかったのですが、
さすがに家庭のある人々は
そういうわけにも行かないらしいです。
本日もアンサンブルコンテストに向けての
弦楽セレナーデの練習。
そこで今日の一枚です。
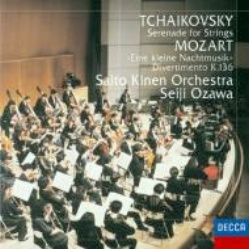
チャイコフスキー/弦楽セレナード
モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
小澤征爾 指揮
サイトウ・キネン・オーケストラ
UCCD50034 ユニバーサルミュージック
このCDは、1984年9月に斎藤秀雄の没後10年記念に弟子であった小澤征爾と秋山和慶を中心に、教え子たちなどが結集して臨時編成されたメモリアル・オーケストラである、サイトウ・キネンオーケストラによるセレナードの演奏が収録されたもの。基本的に、弦楽セクションのみの演奏物です。表現は悪いですが、世界最高の寄せ集めオーケストラ。
この演奏、間違いなく、世界最高レベル。ただ、もう少し欲を言うならば、少々ヘタクソでもいいので、熱い情熱が感じられたら最高かもしれません。
しかし、それは好みの問題で、音楽表現、技術ともに、この上の演奏はなかなか望めないであろうと負わせるほどの凄さがあります。
日本のオーケストラによる、弦楽セレナーデを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2010年01月01日
年が明けましたが。
年が明けましたが、
今年は諸事情により、年始のご挨拶は
ご遠慮させていただいております。
さて、アンサンブルコンテストの
香川県支部大会の予選が
既に11日に迫っています。
あと10日。
今年のエントリー曲は、
チャイコフスキーの
弦楽セレナーデ。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー&ドヴォルザーク
弦楽セレナード
バイエルン放送交響楽団
コリン・ディヴィス指揮
UCCP7079 ユニバーサルミュージック
このCDは、コリン・ディヴィス指揮の、バイエルン放送交響楽団による、チャイコフスキー、ドヴォルザークの弦楽セレナーデ。
比較的、ゆったりとしたテンポで、重厚な響きを聞かせてくれる演奏です。かといって、緩い演奏ではなく、技術的にも引き締まった演奏。いかにもドイツの伝統あるオケといった響きを聞かせてくれます。
ゆったり、しっかりとした弦楽セレナーデを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
今年は諸事情により、年始のご挨拶は
ご遠慮させていただいております。
さて、アンサンブルコンテストの
香川県支部大会の予選が
既に11日に迫っています。
あと10日。
今年のエントリー曲は、
チャイコフスキーの
弦楽セレナーデ。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー&ドヴォルザーク
弦楽セレナード
バイエルン放送交響楽団
コリン・ディヴィス指揮
UCCP7079 ユニバーサルミュージック
このCDは、コリン・ディヴィス指揮の、バイエルン放送交響楽団による、チャイコフスキー、ドヴォルザークの弦楽セレナーデ。
比較的、ゆったりとしたテンポで、重厚な響きを聞かせてくれる演奏です。かといって、緩い演奏ではなく、技術的にも引き締まった演奏。いかにもドイツの伝統あるオケといった響きを聞かせてくれます。
ゆったり、しっかりとした弦楽セレナーデを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年12月23日
アンサンブルコンテストに向けて。
来年の1月10日に、
アンサンブルコンテスト
香川県大会の予選が行われます。
例年だと、
一般の部は、予選無しで県大会なのですが、
近年、20を超える勢いの数の団体が
エントリーしているため、
予選をしてから
県大会を行うことに
なったようです。
今年も、
かなりの数のツワモノが
エントリーしているようなので、
ダッパーも気が抜けません。
ということで、本日もアンサンブルコンテストのための
練習。
残念ながら、都合により、
全員がそろうことは出来ませんでしたが、
それでも練習。
練習風景はそのうちダッパー公式ブログに掲載されることと
思いますので、さておき、
まあ8重奏ともなると
全員の都合をあわせるだけでも一苦労。
数の多いアンサンブルは、
練習にかかる段階で、
こんな悩みもあったりします。
そこで今日の一枚です。

SAX13 Saxofons de Barcelona
Ars Harmonica AH082
このCDは、スペインで、結成されたソプラニーノからバスまでのサクソフォンで結成されたサクソフォンアンサンブルのCD。
興味深いのは、ジャズのナンバーからグラズノフのコンチェルトまで、アレンジされたものを演奏していること。よりクラシックらしいかといわれると、演奏技術のせいなのか、主義主張のためなのか、不安定なアンサンブルに感じる点もありますが、ラージアンサンブルの響きとしては重厚で柔らかなものを感じることが出来ます。
サクソフォンのラージアンサンブルの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
アンサンブルコンテスト
香川県大会の予選が行われます。
例年だと、
一般の部は、予選無しで県大会なのですが、
近年、20を超える勢いの数の団体が
エントリーしているため、
予選をしてから
県大会を行うことに
なったようです。
今年も、
かなりの数のツワモノが
エントリーしているようなので、
ダッパーも気が抜けません。
ということで、本日もアンサンブルコンテストのための
練習。
残念ながら、都合により、
全員がそろうことは出来ませんでしたが、
それでも練習。
練習風景はそのうちダッパー公式ブログに掲載されることと
思いますので、さておき、
まあ8重奏ともなると
全員の都合をあわせるだけでも一苦労。
数の多いアンサンブルは、
練習にかかる段階で、
こんな悩みもあったりします。
そこで今日の一枚です。

SAX13 Saxofons de Barcelona
Ars Harmonica AH082
このCDは、スペインで、結成されたソプラニーノからバスまでのサクソフォンで結成されたサクソフォンアンサンブルのCD。
興味深いのは、ジャズのナンバーからグラズノフのコンチェルトまで、アレンジされたものを演奏していること。よりクラシックらしいかといわれると、演奏技術のせいなのか、主義主張のためなのか、不安定なアンサンブルに感じる点もありますが、ラージアンサンブルの響きとしては重厚で柔らかなものを感じることが出来ます。
サクソフォンのラージアンサンブルの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年11月10日
吹奏楽でも聴いてみよう。
さて、来年の4月の
高松ウインドシンフォニーの定期演奏会の
曲目が
ボチボチ決定しています。
毎年ハードな演奏曲目に
消化不良を起こしながらも
なぜかまた次の年に
ハードな曲目を選ぶという、
猿のような状態になっていますが、
まあ、それはそれで…。
そこで今日の一枚です。

白鳥の湖
フレデリック・フェネル指揮
東京佼成ウインドオーケストラ
KICC725 キング
このCDは、チャイコフスキーの「白鳥の湖」の吹奏楽編曲版の演奏です。残念ながら、全曲版でも、原調版でもありません。演奏は、佼成&フェネルの組み合わせで、どちらかというと、堅実な演奏です。派手さもなければ、ことさら地味ということもありません。同じ編曲の楽譜がレンタル譜で出版されているので、どちらかといえば、お手本演奏に近いのかもしれません。
白鳥の湖を吹奏楽で楽しんでみたい方にオススメの一枚です。
高松ウインドシンフォニーの定期演奏会の
曲目が
ボチボチ決定しています。
毎年ハードな演奏曲目に
消化不良を起こしながらも
なぜかまた次の年に
ハードな曲目を選ぶという、
猿のような状態になっていますが、
まあ、それはそれで…。
そこで今日の一枚です。

白鳥の湖
フレデリック・フェネル指揮
東京佼成ウインドオーケストラ
KICC725 キング
このCDは、チャイコフスキーの「白鳥の湖」の吹奏楽編曲版の演奏です。残念ながら、全曲版でも、原調版でもありません。演奏は、佼成&フェネルの組み合わせで、どちらかというと、堅実な演奏です。派手さもなければ、ことさら地味ということもありません。同じ編曲の楽譜がレンタル譜で出版されているので、どちらかといえば、お手本演奏に近いのかもしれません。
白鳥の湖を吹奏楽で楽しんでみたい方にオススメの一枚です。
2009年11月06日
がっつり聞きましょう。
先日来より、
サクソフォン・アンサンブル・コンサート
2009の
CD作成にかかりっきりのため、
ほとんど他のCDを聴くことが出来なくなっています。
録音をまず編集することから始まり、
CDに焼き付けて、
確認するまで、
おそらく、同じ演奏を100回ぐらいは
聞いていることになるのではないかと思います。
いくらなんでも、
これだけ聴くと、
聞きたいとか、聞きたくないという粋を超えて、
聞いているけど聞いてないような状態になってきます。
たまに、他のCDを聞かないと、
ルーチン化してしまうので、チェックにならなくなります。
つまり、やっと他のCDの登場となります。
そこで今日の一枚。

チャイコフスキ-/レエ音楽「白鳥の湖」
デュトワ指揮
モントリオール交響楽団
POCL-1245 ユニバーサルクラシック
このCDはシャルル・デュトワ指揮のモントリオール交響楽団による白鳥の湖。デュトワらしい透明感と都会的なセンスの白鳥の湖です。強奏の部分でも、決してゴリゴリの演奏ではなく、ソフトなサウンドを聞かせてくれます。ロシア的な泥臭さのようなものを臨む演奏ではありませんが、非常に上質な演奏を聞かせてくれます。
透明感溢れる都会的な白鳥の湖を聞きたい方にオススメの一枚です。
サクソフォン・アンサンブル・コンサート
2009の
CD作成にかかりっきりのため、
ほとんど他のCDを聴くことが出来なくなっています。
録音をまず編集することから始まり、
CDに焼き付けて、
確認するまで、
おそらく、同じ演奏を100回ぐらいは
聞いていることになるのではないかと思います。
いくらなんでも、
これだけ聴くと、
聞きたいとか、聞きたくないという粋を超えて、
聞いているけど聞いてないような状態になってきます。
たまに、他のCDを聞かないと、
ルーチン化してしまうので、チェックにならなくなります。
つまり、やっと他のCDの登場となります。
そこで今日の一枚。

チャイコフスキ-/レエ音楽「白鳥の湖」
デュトワ指揮
モントリオール交響楽団
POCL-1245 ユニバーサルクラシック
このCDはシャルル・デュトワ指揮のモントリオール交響楽団による白鳥の湖。デュトワらしい透明感と都会的なセンスの白鳥の湖です。強奏の部分でも、決してゴリゴリの演奏ではなく、ソフトなサウンドを聞かせてくれます。ロシア的な泥臭さのようなものを臨む演奏ではありませんが、非常に上質な演奏を聞かせてくれます。
透明感溢れる都会的な白鳥の湖を聞きたい方にオススメの一枚です。
2009年10月30日
ライトに。
今年のサクソフォンアンサンブルコンサートが
終わってから、
既に、他の場面で演奏する機会が
いくつか決まっているのですが、
最近思うのですが、
バリバリのクラシックの
アンサンブルをやる機会が
以前に比べ減ったような気が…。
いや、実際は減っていないのでしょうが
他にポップスや、
ジャジーな曲を
演奏する機会が
増えたため、
相対的に
バリバリのクラシックな
曲を演奏する機会が
減っている気がしているのかも
知れません。
まあ、
気軽にサクソフォンの音色を
楽しんでいただけるという意味では、
決してライト名曲が
悪いとはいえません。
そこで今日の一枚。

スマイル(サクソフォン・リサイタル) エイミー・ディクソン
RCA 88697203072
このCDは、シドニー生まれの、女性サクソフォニスト、エイミー・ディクソンのソロアルバム。ほぼ、クラシカルな曲が収録されていますが、バリバリのクラシックというよりは、どちらかと聞きやすいサロン音楽風のアルバムになっています。
HMVのベタ誉めレビューはさておき、テクニックもしっかりした演奏です。イージーリスニングのアルバムと言ったほうがいいのかもしれません。
BGMなどで、ライトにクラシックサクソフォーンを楽しみたい方にオススメの一枚です。
終わってから、
既に、他の場面で演奏する機会が
いくつか決まっているのですが、
最近思うのですが、
バリバリのクラシックの
アンサンブルをやる機会が
以前に比べ減ったような気が…。
いや、実際は減っていないのでしょうが
他にポップスや、
ジャジーな曲を
演奏する機会が
増えたため、
相対的に
バリバリのクラシックな
曲を演奏する機会が
減っている気がしているのかも
知れません。
まあ、
気軽にサクソフォンの音色を
楽しんでいただけるという意味では、
決してライト名曲が
悪いとはいえません。
そこで今日の一枚。

スマイル(サクソフォン・リサイタル) エイミー・ディクソン
RCA 88697203072
このCDは、シドニー生まれの、女性サクソフォニスト、エイミー・ディクソンのソロアルバム。ほぼ、クラシカルな曲が収録されていますが、バリバリのクラシックというよりは、どちらかと聞きやすいサロン音楽風のアルバムになっています。
HMVのベタ誉めレビューはさておき、テクニックもしっかりした演奏です。イージーリスニングのアルバムと言ったほうがいいのかもしれません。
BGMなどで、ライトにクラシックサクソフォーンを楽しみたい方にオススメの一枚です。
2009年10月02日
テンポについていけますように。
ついに
来週末の日曜は
サクソフォンアンサンブルコンサート2009
となります。
ゆえに、今晩も高松ウインドシンフォニーの
サクソフォンパートでの練習。
そして、明後日の日曜日も
ダッパーで練習後ら、ラージの練習です。
実は、明日の土曜日も
部屋を借りてコソ練します。
いや、ここに書いたら、
コソ練じゃなくなってしまいますが。
果たして、
あのこうもりのテンポに間に合うのか、
アルヴァマー序曲の
テンポについていけるのか。
まだまだ、
きちんとさらえていない部分が大きいので、
土曜日に一気にやっと来ます。
しかし、
風邪気味。
大丈夫なのか?!!
というところで、
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/弦楽セレナーデ他
ムラヴィンスキー指揮
レニングラード・フィル・ハーモニー
ARPCD0462
このCDは、ムラヴィンスキー指揮によるレニングラードフィルの演奏。弦楽セレナーデのほかに、イタリア奇想曲、リムスキー=コルサコフの組曲『見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語』が収録されています。鋼のように一本筋の通った響きと、一糸乱れぬ演奏を聞かせてくれます。チャイコフスキーなのに、「勝手に歌うやつは許さん!」とでもいうかのように緊張感溢れた統一感のある演奏。しかしながら、どこかにしなやかさや柔らかさを感じるという、不思議な演奏です。
しかし、このイタリア奇想曲はいくらなんでも…と思うほどテンポが速いのです。それでもオケは誰もはみ出ることなく淡々と演奏。盛り上がりというよりも、熱狂的な静寂のようなものさえ感じます。
ムラヴィンスキーのチャイコフスキーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
来週末の日曜は
サクソフォンアンサンブルコンサート2009
となります。
ゆえに、今晩も高松ウインドシンフォニーの
サクソフォンパートでの練習。
そして、明後日の日曜日も
ダッパーで練習後ら、ラージの練習です。
実は、明日の土曜日も
部屋を借りてコソ練します。
いや、ここに書いたら、
コソ練じゃなくなってしまいますが。
果たして、
あのこうもりのテンポに間に合うのか、
アルヴァマー序曲の
テンポについていけるのか。
まだまだ、
きちんとさらえていない部分が大きいので、
土曜日に一気にやっと来ます。
しかし、
風邪気味。
大丈夫なのか?!!
というところで、
そこで今日の一枚です。
チャイコフスキー/弦楽セレナーデ他
ムラヴィンスキー指揮
レニングラード・フィル・ハーモニー
ARPCD0462
このCDは、ムラヴィンスキー指揮によるレニングラードフィルの演奏。弦楽セレナーデのほかに、イタリア奇想曲、リムスキー=コルサコフの組曲『見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語』が収録されています。鋼のように一本筋の通った響きと、一糸乱れぬ演奏を聞かせてくれます。チャイコフスキーなのに、「勝手に歌うやつは許さん!」とでもいうかのように緊張感溢れた統一感のある演奏。しかしながら、どこかにしなやかさや柔らかさを感じるという、不思議な演奏です。
しかし、このイタリア奇想曲はいくらなんでも…と思うほどテンポが速いのです。それでもオケは誰もはみ出ることなく淡々と演奏。盛り上がりというよりも、熱狂的な静寂のようなものさえ感じます。
ムラヴィンスキーのチャイコフスキーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年09月23日
解釈の違い。
演奏する上で、
演奏者が変わると、
曲が変わったのかと思うほど
違った演奏に聞こえることがあります。
いかに音楽が
画一的でないものか、
また、人の個性を表すものかがよくわかります。
ダッパーでも、
人が入れ替わらなくても、
楽器の担当が入れ替わっただけで、
全く違った響きや
表現になることがあります。
音楽の妙というか
不思議というか、
それが面白さの一つでもあるのですが。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/バレエ音楽「白鳥の湖」全曲
アンドレ・プレヴィン指揮
ロンドン交響楽団
EMI TOCE-14080
このCDは、プレヴィン指揮による、白鳥の湖全曲。ロンドン交響楽団の演奏です。実は、白鳥の湖をはじめ、チャイコフスキーの三大バレエは、人気が高いためか、CDもかなりの数いろいろなものがリリースされているのですが、人気の高さゆえか逆に全曲版があまりありません。私の知る限りでは、デュトワ/モントリオール、ボニング/ナショナルフィル、フェドートフ/サンクトペテルブルク・マリンスキー、ゲルギエフ/サンクトペテルブルク・マリンスキー、スヴェトラーノフ/ソビエト国立交響楽団、アンセルメ/スイスロマンド、まあ、探せばいくつかあるのですが、この中でも、曲がカットされていたり、版の関係で割愛された曲があったりと、本当の意味での全曲版は稀少。
演奏の方は、これはバレエ音楽としてではなく管弦楽曲として楽しむための演奏のような気がします。演奏の質は上質ですが、よりチャイコフスキーらしい演奏をと思うなら、ボニングやフェドートフの方がお勧めかもしれません。よりバレエ的というならアンセルメやゲルギエフ、より流麗なといえばデュトワがオススメ。プレヴィンは、演奏はすばらしいですし、全曲収録という魅力はありますが、バレエ的かと聞かれると多少疑問も在ります。
白鳥の湖を気軽に全曲楽しんでみたい方にオススメの一枚です。
演奏者が変わると、
曲が変わったのかと思うほど
違った演奏に聞こえることがあります。
いかに音楽が
画一的でないものか、
また、人の個性を表すものかがよくわかります。
ダッパーでも、
人が入れ替わらなくても、
楽器の担当が入れ替わっただけで、
全く違った響きや
表現になることがあります。
音楽の妙というか
不思議というか、
それが面白さの一つでもあるのですが。
そこで今日の一枚です。

チャイコフスキー/バレエ音楽「白鳥の湖」全曲
アンドレ・プレヴィン指揮
ロンドン交響楽団
EMI TOCE-14080
このCDは、プレヴィン指揮による、白鳥の湖全曲。ロンドン交響楽団の演奏です。実は、白鳥の湖をはじめ、チャイコフスキーの三大バレエは、人気が高いためか、CDもかなりの数いろいろなものがリリースされているのですが、人気の高さゆえか逆に全曲版があまりありません。私の知る限りでは、デュトワ/モントリオール、ボニング/ナショナルフィル、フェドートフ/サンクトペテルブルク・マリンスキー、ゲルギエフ/サンクトペテルブルク・マリンスキー、スヴェトラーノフ/ソビエト国立交響楽団、アンセルメ/スイスロマンド、まあ、探せばいくつかあるのですが、この中でも、曲がカットされていたり、版の関係で割愛された曲があったりと、本当の意味での全曲版は稀少。
演奏の方は、これはバレエ音楽としてではなく管弦楽曲として楽しむための演奏のような気がします。演奏の質は上質ですが、よりチャイコフスキーらしい演奏をと思うなら、ボニングやフェドートフの方がお勧めかもしれません。よりバレエ的というならアンセルメやゲルギエフ、より流麗なといえばデュトワがオススメ。プレヴィンは、演奏はすばらしいですし、全曲収録という魅力はありますが、バレエ的かと聞かれると多少疑問も在ります。
白鳥の湖を気軽に全曲楽しんでみたい方にオススメの一枚です。





