2009年06月25日
ミスをものともしない。
最近、あまり生の演奏を
聞いていないと
思いつつ、
大量に購入した
CDを聞き続ける毎日です。
さて、生の演奏においても、
CDに録音された
演奏にしても、
ノンミスの演奏は、
プロの演奏でも
結構珍しかったりします。
もちろん、
スタジオや
CD録音に限定された、
環境での収録であれば、
ミスした部分を
リテイクするなどして
修正したりすることが多いのですが、
特に古めの録音などは、
環境がリテイクを許さない
事情があったのか、
修正が無理だったのか、
失敗した部分がそのまま
残されていることがあります。
生の演奏だと、
修正することは不可能なので、
ミスは聴衆に必ず伝わってしまいます。
ところが、ミスをも含めても
揺ぎ無い名演、名盤は
存在します。
CDでそんな演奏に出会ったときに
常に思うのは、
この演奏を生で聞いてみたかった、
ということ。
そこで今日の一枚です。
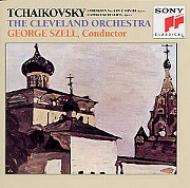
チャイコフスキー/交響曲第5番、イタリア奇想曲
ジョージ・セル指揮
クリーヴランド管弦楽団
ソニーミュージック SRCR9867
このCDは、ジョージ・セルとクリーヴランド管弦楽団による、チャイコフスキー。このコンビ、世に名盤を数多く残したコンビとしても有名です。どちらかというと、多くの演奏者が重厚でゴリゴリ感たっぷりの演奏をする中、このチャイコフスキーの5番は、驚くほど、すっきりと流麗。2楽章の旋律の美しさと、ホルンの甘美な響きが印象的です。実は、この演奏、楽譜を書き換えていると思われる節があります。指揮者の指示であるのでしょうが、どういった経緯で楽譜に手を入れたのかは、不明です。そして、クラリネットのリードミスなど、明らかに聴いて取れるミスが存在しますが、修正されておらず、そのまま。しかし、そんな些細なミスはものともしないほど、全編を通して名演といえると思います。
セルの名演を聞いてみたい方にオススメの一枚。
聞いていないと
思いつつ、
大量に購入した
CDを聞き続ける毎日です。
さて、生の演奏においても、
CDに録音された
演奏にしても、
ノンミスの演奏は、
プロの演奏でも
結構珍しかったりします。
もちろん、
スタジオや
CD録音に限定された、
環境での収録であれば、
ミスした部分を
リテイクするなどして
修正したりすることが多いのですが、
特に古めの録音などは、
環境がリテイクを許さない
事情があったのか、
修正が無理だったのか、
失敗した部分がそのまま
残されていることがあります。
生の演奏だと、
修正することは不可能なので、
ミスは聴衆に必ず伝わってしまいます。
ところが、ミスをも含めても
揺ぎ無い名演、名盤は
存在します。
CDでそんな演奏に出会ったときに
常に思うのは、
この演奏を生で聞いてみたかった、
ということ。
そこで今日の一枚です。
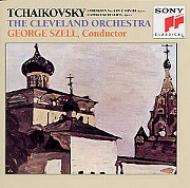
チャイコフスキー/交響曲第5番、イタリア奇想曲
ジョージ・セル指揮
クリーヴランド管弦楽団
ソニーミュージック SRCR9867
このCDは、ジョージ・セルとクリーヴランド管弦楽団による、チャイコフスキー。このコンビ、世に名盤を数多く残したコンビとしても有名です。どちらかというと、多くの演奏者が重厚でゴリゴリ感たっぷりの演奏をする中、このチャイコフスキーの5番は、驚くほど、すっきりと流麗。2楽章の旋律の美しさと、ホルンの甘美な響きが印象的です。実は、この演奏、楽譜を書き換えていると思われる節があります。指揮者の指示であるのでしょうが、どういった経緯で楽譜に手を入れたのかは、不明です。そして、クラリネットのリードミスなど、明らかに聴いて取れるミスが存在しますが、修正されておらず、そのまま。しかし、そんな些細なミスはものともしないほど、全編を通して名演といえると思います。
セルの名演を聞いてみたい方にオススメの一枚。
2009年06月21日
カルテットの個性。
本日、
サクソフォーンアンサンブルコンサート2009
ラージアンサンブルの練習。
久々に、
今年は、F庄先生を
指揮者にお迎えしての演奏会で、
明日は先生にもお越しいただいての練習。
午前中は、カルテットの練習でした。
さて、カルテットいつも思うことですが、
メンバーが一人変わるだけで
ものすごく響きが変化します。
それが
カルテットの個性となっていくのでしょうが、
面白いところでもあり、
一筋縄ではいかない大変な部分でもあります。
当然、同じ曲を演奏しても、
それぞれのカルテットによって
たとえ解釈が同じだったとしても、
響きや音のなり方に、
かなり違いが出てきます。
ましてや、解釈に違いがあれば、
それはもっと大きな変化となります。
そこで今日の一枚です。

Impression
Linos Saxophon Quartett
Musicaphon M 56861
このCDはリノス・サクソフォン・カルテットのファーストアルバム。団体の詳細についてはこちら(ただしドイツ語)。基本的にドイツ語圏のサクソフォンアンサンブルのようです。しかし、収録されている曲は、全てバリバリのフランス物。
演奏は、フランスらしいエスプリの聞いた演奏とは一味違うもの。全体を通して重厚な響きが特徴のようです。ただ、丁寧に演奏されている反面、テンポ感等があまり感じられない演奏となってしまっているのが残念な気がします。
一風変わったフランス物のサクソフォーンカルテットを聞いてみたい方にオススメの一枚。
サクソフォーンアンサンブルコンサート2009
ラージアンサンブルの練習。
久々に、
今年は、F庄先生を
指揮者にお迎えしての演奏会で、
明日は先生にもお越しいただいての練習。
午前中は、カルテットの練習でした。
さて、カルテットいつも思うことですが、
メンバーが一人変わるだけで
ものすごく響きが変化します。
それが
カルテットの個性となっていくのでしょうが、
面白いところでもあり、
一筋縄ではいかない大変な部分でもあります。
当然、同じ曲を演奏しても、
それぞれのカルテットによって
たとえ解釈が同じだったとしても、
響きや音のなり方に、
かなり違いが出てきます。
ましてや、解釈に違いがあれば、
それはもっと大きな変化となります。
そこで今日の一枚です。

Impression
Linos Saxophon Quartett
Musicaphon M 56861
このCDはリノス・サクソフォン・カルテットのファーストアルバム。団体の詳細についてはこちら(ただしドイツ語)。基本的にドイツ語圏のサクソフォンアンサンブルのようです。しかし、収録されている曲は、全てバリバリのフランス物。
演奏は、フランスらしいエスプリの聞いた演奏とは一味違うもの。全体を通して重厚な響きが特徴のようです。ただ、丁寧に演奏されている反面、テンポ感等があまり感じられない演奏となってしまっているのが残念な気がします。
一風変わったフランス物のサクソフォーンカルテットを聞いてみたい方にオススメの一枚。
2009年06月16日
小学校へ訪問演奏に。
先日もちらと書きましたが、
14日の日曜日、
午前中、某小学校に
訪問演奏に
行ってきました。
その昔、
高松ウインドシンフォニーでは、
訪問演奏のことを
「出前コンサート」と
呼んでいた記憶があります。
で、
小学校に行くたびに思うこと。
小学生、素直で
元気です。
自分が小学生の頃は、
もっともっと、
物事を
斜に見ている
ひねくれた小学生だった気がします。
訪問演奏会
続ける理由は
この小学生達に合いたいから
かも知れません。

注:この写真は定期演奏会のものです。
訪問演奏会とは無関係です。
14日の日曜日、
午前中、某小学校に
訪問演奏に
行ってきました。
その昔、
高松ウインドシンフォニーでは、
訪問演奏のことを
「出前コンサート」と
呼んでいた記憶があります。
で、
小学校に行くたびに思うこと。
小学生、素直で
元気です。
自分が小学生の頃は、
もっともっと、
物事を
斜に見ている
ひねくれた小学生だった気がします。
訪問演奏会
続ける理由は
この小学生達に合いたいから
かも知れません。
注:この写真は定期演奏会のものです。
訪問演奏会とは無関係です。
2009年06月12日
違った趣。
今年の
サクソフォン
アンサンブル
コンサートの
ラージは
メインが
「こうもり」序曲
です。
このブログでもいくつかの
演奏を
聞き比べてみたりしましたが、
やはりそれぞれ
違った趣の演奏でした。
ただ、今回聞いたものは、
ほとんどが、
ドイツ、オーストリア圏
の奏者による演奏でしたので、
趣が違いながらも、
テイストに似たものを感じる部分も
多かった気がします。
ところで、
去年は
アンサンブルコンサートで、
ニュルンベルクのマイスタージンガーより
第一幕への前奏曲
を演奏したわけですが、
これもドイツ物。
そこで今日の一枚です。

ワーグナー管弦楽曲集
アンセルメ指揮
スイス・ロマンド管弦楽団
Eloquence Australia 4800567
このCDは、エルネスト・アンセルメ指揮による、スイスロマンド管弦楽団のワーグナー管弦楽曲集。アンセルメといえば、フランスもの、ロシア物を色彩豊かに演奏する指揮者として有名ですが、ドイツ物の演奏に対しての評価はイマイチ。そんなアンセルメのワーグナー、つまり、コテコテのドイツ物。確かに、ドイツ人の指揮者の演奏のようなゴリゴリした部分というか、ゴツイ感じはあまり感じられない演奏ですが、逆に、色彩豊かで、見通しのよいスッキリした演奏を聴くことが出来ます。
色彩豊かで洒脱なワーグナーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
サクソフォン
アンサンブル
コンサートの
ラージは
メインが
「こうもり」序曲
です。
このブログでもいくつかの
演奏を
聞き比べてみたりしましたが、
やはりそれぞれ
違った趣の演奏でした。
ただ、今回聞いたものは、
ほとんどが、
ドイツ、オーストリア圏
の奏者による演奏でしたので、
趣が違いながらも、
テイストに似たものを感じる部分も
多かった気がします。
ところで、
去年は
アンサンブルコンサートで、
ニュルンベルクのマイスタージンガーより
第一幕への前奏曲
を演奏したわけですが、
これもドイツ物。
そこで今日の一枚です。

ワーグナー管弦楽曲集
アンセルメ指揮
スイス・ロマンド管弦楽団
Eloquence Australia 4800567
このCDは、エルネスト・アンセルメ指揮による、スイスロマンド管弦楽団のワーグナー管弦楽曲集。アンセルメといえば、フランスもの、ロシア物を色彩豊かに演奏する指揮者として有名ですが、ドイツ物の演奏に対しての評価はイマイチ。そんなアンセルメのワーグナー、つまり、コテコテのドイツ物。確かに、ドイツ人の指揮者の演奏のようなゴリゴリした部分というか、ゴツイ感じはあまり感じられない演奏ですが、逆に、色彩豊かで、見通しのよいスッキリした演奏を聴くことが出来ます。
色彩豊かで洒脱なワーグナーを聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年06月11日
パイレーツ。
先月から、
サクソフォン・
アンサンブル・
コンサート
のためのラージステージ練習が
始まりました。
先日出来上がっていた楽譜は、
パイレーツ・オブ・カリビアン
のみ。
これから続々楽譜が出来上がってくるので、
練習が忙しくなってきます。
そんなところで
今日の一枚です。

パイレーツ・オブ・カリビアン
呪われた海賊たち
(輸入版)
ディズニー 5008600897
このCDは、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のオリジナルサウンドトラック。第一作目のものです。ところで、私はこのCD、入手したのは、つい最近。映画が公開されたのは2003年なので、かなり遅い入手です。しかし、それには理由があります。それは、日本版のこのCDが発売された当初、エイベックスがコピーコントロールCDにしたためです。音が悪いは、場合によってはcdプレーヤーにダメージを加える可能性があるものをとても買う気がしなかったため、当時は購入を見送りました。
映画については、何も語ることは無いと思います。ディズニーの大ヒット映画です。
パイレーツ・オブ・カリビアン第一作目のサウンドトラックとしてオススメの一枚です。
サクソフォン・
アンサンブル・
コンサート
のためのラージステージ練習が
始まりました。
先日出来上がっていた楽譜は、
パイレーツ・オブ・カリビアン
のみ。
これから続々楽譜が出来上がってくるので、
練習が忙しくなってきます。
そんなところで
今日の一枚です。

パイレーツ・オブ・カリビアン
呪われた海賊たち
(輸入版)
ディズニー 5008600897
このCDは、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のオリジナルサウンドトラック。第一作目のものです。ところで、私はこのCD、入手したのは、つい最近。映画が公開されたのは2003年なので、かなり遅い入手です。しかし、それには理由があります。それは、日本版のこのCDが発売された当初、エイベックスがコピーコントロールCDにしたためです。音が悪いは、場合によってはcdプレーヤーにダメージを加える可能性があるものをとても買う気がしなかったため、当時は購入を見送りました。
映画については、何も語ることは無いと思います。ディズニーの大ヒット映画です。
パイレーツ・オブ・カリビアン第一作目のサウンドトラックとしてオススメの一枚です。
2009年06月09日
カルテットじゃなくても。
サクソフォン・アンサンブルといえば、
まず一番最初に
思い浮かべるのが、
カルテット、
というほど、
管楽器のアンサンブルとしては、
サクソフォンカルテットは
スタンダードな編成です。
とりわけ、
ソプラノ
アルト
テナー
バリトン
の四本のサクソフォーンを
使ったカルテットは、
弦楽四重奏にもたとえられるほど、
バランスの取れた編成。
サクソフォンには、
三重奏だったり、
五重奏、
六重奏という編成の曲も
あり、
特に最近は5重奏が
沢山書かれるようになって来ました。
ただ、やはり四重奏の
曲がレパートリーとしても
豊富で、
他の編成はまだまだレパートリーが
少ないのが現状です。
ましてや、三重奏となると、
レパートリーも限られてきます。
そこで今日の一枚です。

Sax at the Opera(オペラ座のサックス)
Sax allemand
Farao B108016
このCDは、サクソフォーン三重奏団、サックスアルマンドによるクラシック曲のアレンジ集。なんと、ソプラノ、アルト、バリトンという編成。カルテットに比べて物足りないんじゃないかと思って聴くと、それを見事に裏切られます。カルテットのような濃厚で重厚な響きは望めないかもしれませんが、なんとも軽やかで、軽快そのもの。見通しのよいパリッとした演奏を聴くことが出来ます。
演奏としては、かなりチャレンジャーな部分もありますが、これはこれで、バランスの良い演奏。
サクソフォン三重奏の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
6.と
まず一番最初に
思い浮かべるのが、
カルテット、
というほど、
管楽器のアンサンブルとしては、
サクソフォンカルテットは
スタンダードな編成です。
とりわけ、
ソプラノ
アルト
テナー
バリトン
の四本のサクソフォーンを
使ったカルテットは、
弦楽四重奏にもたとえられるほど、
バランスの取れた編成。
サクソフォンには、
三重奏だったり、
五重奏、
六重奏という編成の曲も
あり、
特に最近は5重奏が
沢山書かれるようになって来ました。
ただ、やはり四重奏の
曲がレパートリーとしても
豊富で、
他の編成はまだまだレパートリーが
少ないのが現状です。
ましてや、三重奏となると、
レパートリーも限られてきます。
そこで今日の一枚です。

Sax at the Opera(オペラ座のサックス)
Sax allemand
Farao B108016
このCDは、サクソフォーン三重奏団、サックスアルマンドによるクラシック曲のアレンジ集。なんと、ソプラノ、アルト、バリトンという編成。カルテットに比べて物足りないんじゃないかと思って聴くと、それを見事に裏切られます。カルテットのような濃厚で重厚な響きは望めないかもしれませんが、なんとも軽やかで、軽快そのもの。見通しのよいパリッとした演奏を聴くことが出来ます。
演奏としては、かなりチャレンジャーな部分もありますが、これはこれで、バランスの良い演奏。
サクソフォン三重奏の演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
6.と
2009年06月08日
こうもり序曲を聞き比べてみよう、佼成ウインド。
サクソフォンアンサンブル
コンサートの
参考のために
音源を
色々聞き比べているわけですが、
どれも
演奏としてはすばらしい演奏。
ただ、好みがあったり、
それぞれ個性があったりと、
様々。
同じ曲を、
同じ編成で演奏しても
それぞれ違い、
また、違った編成で
演奏すいることで
違った楽しみがあったりします。
そこで今日の一枚です。

マスターピース・シリーズ4
吹奏楽:オーストリアの巨匠たちVol.1
小田野宏之指揮 東京佼成ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ0004
このCDは、東芝より発売されたマスターピースシリーズの中の一枚。それぞれ、CDごとに、指揮者や、演奏者が違いますが、今回は、東京佼成ウインドオーケストラの演奏。そして、オーストラリアの巨匠ということで、シュトラウス、モーツアルト、スッペ、シューベルト、といった作曲家の序曲を中心とした曲が収録されています。
吹奏楽の資料的なCDとしてもオススメの一枚です。
コンサートの
参考のために
音源を
色々聞き比べているわけですが、
どれも
演奏としてはすばらしい演奏。
ただ、好みがあったり、
それぞれ個性があったりと、
様々。
同じ曲を、
同じ編成で演奏しても
それぞれ違い、
また、違った編成で
演奏すいることで
違った楽しみがあったりします。
そこで今日の一枚です。
マスターピース・シリーズ4
吹奏楽:オーストリアの巨匠たちVol.1
小田野宏之指揮 東京佼成ウインドオーケストラ
東芝EMI TOCZ0004
このCDは、東芝より発売されたマスターピースシリーズの中の一枚。それぞれ、CDごとに、指揮者や、演奏者が違いますが、今回は、東京佼成ウインドオーケストラの演奏。そして、オーストラリアの巨匠ということで、シュトラウス、モーツアルト、スッペ、シューベルト、といった作曲家の序曲を中心とした曲が収録されています。
吹奏楽の資料的なCDとしてもオススメの一枚です。
2009年06月07日
こうもり序曲を聞き比べてみよう、アンサンブル“11”。
土日が終わって、
また明日から月曜日。
鬱々とした気分になってきます。
さて、こうもり序曲の聞き比べ、
今回は特別な前置きはなく…
そこで今日の一枚です。

シュトラウス・ファミリーの音楽
アンサンブル“11”
カメラータ 28CM594
このCDは、ウィーンフィルハーモニーのメンバー11人による、シュトラウス・ファミリーの作品集。古典派のハルモニームジークを現代風に味付けした雰囲気の音楽です。さすがは、ウィーンフィルのメンバー、シュトラウス音楽の吸いも甘いも噛み分けた幹事が伝わってきます。
吹奏楽ほど、の重厚な響きはありませんが、小編成の管楽アンサンブルといった様相でしょうか。編成にサクソフォンがないのは、残念ですが、仕方ないのでしょうか、これに一人でもサクソフォンが加わると、もっといい感じになるのかも、と思うのは私だけでしょうか。
上品で洒脱な雰囲気を感じる演奏です。
ちょっとお洒落なサロン風のシュトラウスを楽しみたい方にオススメの一枚です。
また明日から月曜日。
鬱々とした気分になってきます。
さて、こうもり序曲の聞き比べ、
今回は特別な前置きはなく…
そこで今日の一枚です。

シュトラウス・ファミリーの音楽
アンサンブル“11”
カメラータ 28CM594
このCDは、ウィーンフィルハーモニーのメンバー11人による、シュトラウス・ファミリーの作品集。古典派のハルモニームジークを現代風に味付けした雰囲気の音楽です。さすがは、ウィーンフィルのメンバー、シュトラウス音楽の吸いも甘いも噛み分けた幹事が伝わってきます。
吹奏楽ほど、の重厚な響きはありませんが、小編成の管楽アンサンブルといった様相でしょうか。編成にサクソフォンがないのは、残念ですが、仕方ないのでしょうか、これに一人でもサクソフォンが加わると、もっといい感じになるのかも、と思うのは私だけでしょうか。
上品で洒脱な雰囲気を感じる演奏です。
ちょっとお洒落なサロン風のシュトラウスを楽しみたい方にオススメの一枚です。
2009年06月06日
こうもり序曲を聞き比べてみよう、ボスコフスキー。
さて、サクソフォーンアンサンブル
コンサートで演奏する、
こうもり序曲を
聞き比べているわけですが、
今回はボスコフスキー。
話が飛びますが、
ウィーンフィルのニューイヤーコンサートは、
毎年一月一日に、ウィーン楽友協会の
大ホールで行われる、演奏会で、
主にシュトラウス・ファミリーの曲が
演奏されます。
指揮者は、楽団員の投票によって
決定されることとなっているようですが、
実は、ヴィリー・ボスコフスキーは、
このニューイヤーコンサートの
指揮を1954年に亡くなった指揮者クレメンス・クラウスに代わり、
1955年から1979年までの間の実に25回もの間、
行った人物。
弾き振りを行った人物としても有名です。
そこで今日の一枚です。
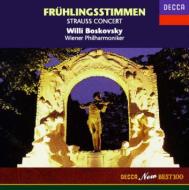
シュトラウス・コンサート
ボスコフスキー指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ユニバーサルミュージック UCCD5033
このCDはヴィリー・ボスコフスキー指揮による、ウィーンフィルの演奏するシュトラウスファミリーの曲集。もちろんこうもり序曲も収録されています。演奏は、ウィーン気質というか、楽しく洒脱という言葉がぴったりのもの。演奏を音楽を楽しむ様子が伝わってくるようです。
ボスコフスキーのウィーン気質を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
コンサートで演奏する、
こうもり序曲を
聞き比べているわけですが、
今回はボスコフスキー。
話が飛びますが、
ウィーンフィルのニューイヤーコンサートは、
毎年一月一日に、ウィーン楽友協会の
大ホールで行われる、演奏会で、
主にシュトラウス・ファミリーの曲が
演奏されます。
指揮者は、楽団員の投票によって
決定されることとなっているようですが、
実は、ヴィリー・ボスコフスキーは、
このニューイヤーコンサートの
指揮を1954年に亡くなった指揮者クレメンス・クラウスに代わり、
1955年から1979年までの間の実に25回もの間、
行った人物。
弾き振りを行った人物としても有名です。
そこで今日の一枚です。
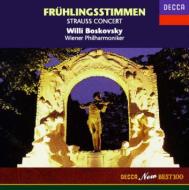
シュトラウス・コンサート
ボスコフスキー指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ユニバーサルミュージック UCCD5033
このCDはヴィリー・ボスコフスキー指揮による、ウィーンフィルの演奏するシュトラウスファミリーの曲集。もちろんこうもり序曲も収録されています。演奏は、ウィーン気質というか、楽しく洒脱という言葉がぴったりのもの。演奏を音楽を楽しむ様子が伝わってくるようです。
ボスコフスキーのウィーン気質を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年06月05日
こうもり序曲を聞き比べてみよう、カラヤン。
先日、
サクソフォン
アンサンブルコンサート
2009の
ラージステージの
練習が開始されました。
さて、
今回の演奏会の
曲目の中での
メインとも言うべき曲は
ヨハン・シュトラウス二世
の
喜歌劇「こうもり」序曲
ウィーンフィルの
ニューイヤーコンサートなどで、
よく演奏されている曲で
日本人にも比較的
なじみのある曲です。
そこで、今日の一枚です。

シュトラウス・コンサート
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
ユニバーサルクラシック UCCD9507
このCDは、カラヤンがウィーンフィルを指揮して英DECCAレーベルで録音したシュトラウス作品集。カラヤンといえば、ベルリンフィルハーモニーを思い浮かべますが、この録音が行われた時代は、盛んにウィーンフィルとの録音が行われました。私としては、この時代の録音はかなりいい演奏が多いと思っているのですが、それは好みかもしれません。ただ、同じ時代に、カラヤン、ウィーンフィルで録音された、惑星などは、世界的な大ヒットアルバムとなり、初めてクラシック界で世界的な惑星ブームを起こしたアルバムです。また、このコンビの録音によるベートーヴェンの7番なども、名盤といえる録音だと思います。
さて、肝心のこうもり序曲ですが、後年のベルリンフィルとの演奏に比べても、オケを主導しようとしている様がよく聞いて取れます。ある意味、ドライヴしているとも言えますし、逆に言えば、指揮者主導の演奏ともいえます。まだ、若々しささえ、感じる演奏です。
カラヤン、ウィーンフィルのシュトラウスを聞いてみたい方にオススメの一枚。
4.す
サクソフォン
アンサンブルコンサート
2009の
ラージステージの
練習が開始されました。
さて、
今回の演奏会の
曲目の中での
メインとも言うべき曲は
ヨハン・シュトラウス二世
の
喜歌劇「こうもり」序曲
ウィーンフィルの
ニューイヤーコンサートなどで、
よく演奏されている曲で
日本人にも比較的
なじみのある曲です。
そこで、今日の一枚です。

シュトラウス・コンサート
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
ユニバーサルクラシック UCCD9507
このCDは、カラヤンがウィーンフィルを指揮して英DECCAレーベルで録音したシュトラウス作品集。カラヤンといえば、ベルリンフィルハーモニーを思い浮かべますが、この録音が行われた時代は、盛んにウィーンフィルとの録音が行われました。私としては、この時代の録音はかなりいい演奏が多いと思っているのですが、それは好みかもしれません。ただ、同じ時代に、カラヤン、ウィーンフィルで録音された、惑星などは、世界的な大ヒットアルバムとなり、初めてクラシック界で世界的な惑星ブームを起こしたアルバムです。また、このコンビの録音によるベートーヴェンの7番なども、名盤といえる録音だと思います。
さて、肝心のこうもり序曲ですが、後年のベルリンフィルとの演奏に比べても、オケを主導しようとしている様がよく聞いて取れます。ある意味、ドライヴしているとも言えますし、逆に言えば、指揮者主導の演奏ともいえます。まだ、若々しささえ、感じる演奏です。
カラヤン、ウィーンフィルのシュトラウスを聞いてみたい方にオススメの一枚。
4.す
2009年06月02日
2008年CDプレゼント企画。
処分するはずだった、
サクソフォーン・アンサンブル
コンサート2008のCDですが、
処分するぐらいなら、欲しい
という方がいらっしゃったので、
私の独断で、
プレゼント企画を行います。
応募方法は、
1.私の過去全てのこのブログから、2009年7月末間での記事の最後に、
数字と、キーワードになる一文字をこっそり書き込みます。
数字の順番に文字を並べると、正解が現れます。
いつの記事に、いつ書き込まれるかは判りません。
また、番号が書き込まれた順番についているとは限りません。
また、キーワードの文字が何文字になるかも判りません。
2.2009年7月末までに私がキーワード終了を宣言してから、1週間を応募期間とします。
応募方法は、その時に記事に掲載します。
3.プレゼント数は、3とします。応募数は1人1限りとします。
ただし、応募数が3を下回った場合、また、正解者が3を下回った場合も、
企画を中止とします。
4.送料等は、私が負担します。ただし、国内で、郵送、宅配が利用できる場所に限ります。
5.私が勝手にやっていますので、ダッパー本隊から、企画の中止が申しだされた場合、
企画自体を中止することがあります。
以上、ご了承下さい。
試しに、一文字目を本日のブログ記事の最後に書き込みます。
他の文字も、これと同じような形にして書き込みます。
1.さ
サクソフォーン・アンサンブル
コンサート2008のCDですが、
処分するぐらいなら、欲しい
という方がいらっしゃったので、
私の独断で、
プレゼント企画を行います。
応募方法は、
1.私の過去全てのこのブログから、2009年7月末間での記事の最後に、
数字と、キーワードになる一文字をこっそり書き込みます。
数字の順番に文字を並べると、正解が現れます。
いつの記事に、いつ書き込まれるかは判りません。
また、番号が書き込まれた順番についているとは限りません。
また、キーワードの文字が何文字になるかも判りません。
2.2009年7月末までに私がキーワード終了を宣言してから、1週間を応募期間とします。
応募方法は、その時に記事に掲載します。
3.プレゼント数は、3とします。応募数は1人1限りとします。
ただし、応募数が3を下回った場合、また、正解者が3を下回った場合も、
企画を中止とします。
4.送料等は、私が負担します。ただし、国内で、郵送、宅配が利用できる場所に限ります。
5.私が勝手にやっていますので、ダッパー本隊から、企画の中止が申しだされた場合、
企画自体を中止することがあります。
以上、ご了承下さい。
試しに、一文字目を本日のブログ記事の最後に書き込みます。
他の文字も、これと同じような形にして書き込みます。
1.さ
2009年05月30日
ゴキゲンな吹奏楽を。
吹奏楽というジャンル、
クラシックから、
ポップス、
ジャズまで、
雑多なジャンルを
演奏する機会が
あります。
もちろん、
吹奏楽のためにかかれた
オリジナルの曲でも、
色々なジャンルに分類されるであろう
音楽があります。
一方で、
様々なジャンルの中から
アレンジされたものを
演奏する機会も
かなりの頻度であると思います。
どういったジャンルにでも
柔軟に対応できる編成と
言う意味なのか、
どれにも属せない、
中途半端な存在なのかは
この際考えないとして、
最近、吹奏楽の中でも、
かなりポップスや
ジャズを意識したようなアルバムが
増えた気もします。
そこで今日の一枚です。

Disney on Brass
佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ
SACDハイブリッド盤
エイベックス AVCW12652
このCDは、ディズニーオフィシャルの吹奏楽版ディズニー音楽集。コンセプトとしては、ニューサウンズ・イン・ブラスのようなものでしょうか。ディズニーメドレーなどは、まんま、NSBの楽譜が使用されています。多彩なゲストミュージシャンと、パイレーツオブカリビアンや、カーズといったゴキゲンな音楽が収録されています。
ディズニー好きのかた、ゴキゲンな吹奏楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
クラシックから、
ポップス、
ジャズまで、
雑多なジャンルを
演奏する機会が
あります。
もちろん、
吹奏楽のためにかかれた
オリジナルの曲でも、
色々なジャンルに分類されるであろう
音楽があります。
一方で、
様々なジャンルの中から
アレンジされたものを
演奏する機会も
かなりの頻度であると思います。
どういったジャンルにでも
柔軟に対応できる編成と
言う意味なのか、
どれにも属せない、
中途半端な存在なのかは
この際考えないとして、
最近、吹奏楽の中でも、
かなりポップスや
ジャズを意識したようなアルバムが
増えた気もします。
そこで今日の一枚です。

Disney on Brass
佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ
SACDハイブリッド盤
エイベックス AVCW12652
このCDは、ディズニーオフィシャルの吹奏楽版ディズニー音楽集。コンセプトとしては、ニューサウンズ・イン・ブラスのようなものでしょうか。ディズニーメドレーなどは、まんま、NSBの楽譜が使用されています。多彩なゲストミュージシャンと、パイレーツオブカリビアンや、カーズといったゴキゲンな音楽が収録されています。
ディズニー好きのかた、ゴキゲンな吹奏楽を聞いてみたい方にオススメの一枚です。
2009年05月29日
どっちかと言われたら。
週末がやってきます。
磨り減った心を癒すことが、
出来ればいいのですが、
人生に潤いも
喜びも対してない
殺伐とした今を生きている私は、
おそらくボーっとして終りでしょう。
そういえば、来週からもう6月。
梅雨がやってくると思うと、
ますます陰鬱に
なりそうです。
さて、吹奏楽経験者に
「思い出の曲は?」
と聞くと、様々な曲名が
返ってくるのですが、
「思い出の参考演奏は?」
と聞いてもやはり様々な
演奏が帰ってくる気がします。
それぞれの人が
コンクールで演奏する曲などで、
お手本にした演奏、
参考にした演奏があるようです。
その中でも、皆さんがより
多く聞いていた演奏というのも
存在するようです。
そこで今日の一枚です。

アルヴァマー序曲~ブラバン・ベスト
Sony SICC1103
このCDは、ちょっと懐かしめの吹奏楽オリジナル曲が収録されているアルバム。まさに今から20年ぐらい前、学生だった方々には懐かしい曲が収録されています。先日、別のアルバムでアルヴァマー序曲の紹介をしましたが、おそらく、昔多くの人が参考にしたであろう演奏は、どちらかと言われたら、こちらのCDに収録されているものではないでしょうか。ただし、あまりにテンポが速かったため、作曲者のバーンズが、驚いたとか。
懐かしい吹奏楽オリジナル曲を楽しみたい方にオススメの一枚です。
磨り減った心を癒すことが、
出来ればいいのですが、
人生に潤いも
喜びも対してない
殺伐とした今を生きている私は、
おそらくボーっとして終りでしょう。
そういえば、来週からもう6月。
梅雨がやってくると思うと、
ますます陰鬱に
なりそうです。
さて、吹奏楽経験者に
「思い出の曲は?」
と聞くと、様々な曲名が
返ってくるのですが、
「思い出の参考演奏は?」
と聞いてもやはり様々な
演奏が帰ってくる気がします。
それぞれの人が
コンクールで演奏する曲などで、
お手本にした演奏、
参考にした演奏があるようです。
その中でも、皆さんがより
多く聞いていた演奏というのも
存在するようです。
そこで今日の一枚です。
アルヴァマー序曲~ブラバン・ベスト
Sony SICC1103
このCDは、ちょっと懐かしめの吹奏楽オリジナル曲が収録されているアルバム。まさに今から20年ぐらい前、学生だった方々には懐かしい曲が収録されています。先日、別のアルバムでアルヴァマー序曲の紹介をしましたが、おそらく、昔多くの人が参考にしたであろう演奏は、どちらかと言われたら、こちらのCDに収録されているものではないでしょうか。ただし、あまりにテンポが速かったため、作曲者のバーンズが、驚いたとか。
懐かしい吹奏楽オリジナル曲を楽しみたい方にオススメの一枚です。
2009年05月25日
思い立って。
新型インフルエンザは、
ボチボチ、普通のインフルエンザと
同じ扱いになっていくのでしょうか。
マスクはこれから冬にかけて
よく売れることでしょう。
マスクメーカーと
薬局はかき入れ時。
さて、
私は1000枚程度のCDを
持っているわけですが、
1日1枚聞いたとしても
2年以上かけないと、
全部聴くことが出来ないという状況。
まあ、実際に何年も聞いていないCD
も実際にはあるわけです。
で、気分が向いたときに、
また、参考音源として、
聴く必要が生じたときに、
聴くことが多いのですが、
一つのCDを聴くと、
それに付随して、
同じ作曲家や、
演奏家の
CDを聞き始めることがあります。
そこで今日の一枚。

ラヴェル/ダフニスとクロエ
ユニバーサルミュージック UCCD7092
エルネスト・アンセルメ指揮
スイスロマンド管弦楽団
このCDはエルネスト・アンセルメ指揮、スイスロマンド管弦楽団による、ダフニスとクロエ。いかにも、アンセルメらしい、色彩感と、整理された音楽、そして、アナログレコード時代とは思えないほど、卓越した録音技術。現在の優秀な録音をもある意味凌駕するような録音です。さすがに、デジタル時代のダイナミックレンジの広い録音には及ばないかもしれませんが、ダイナミックレンジの狭さを補って余りある記録です。マ・メールロワの洗練された演奏にも感動。
ダフクロを聞き比べてみたい方にオススメの一枚。
ボチボチ、普通のインフルエンザと
同じ扱いになっていくのでしょうか。
マスクはこれから冬にかけて
よく売れることでしょう。
マスクメーカーと
薬局はかき入れ時。
さて、
私は1000枚程度のCDを
持っているわけですが、
1日1枚聞いたとしても
2年以上かけないと、
全部聴くことが出来ないという状況。
まあ、実際に何年も聞いていないCD
も実際にはあるわけです。
で、気分が向いたときに、
また、参考音源として、
聴く必要が生じたときに、
聴くことが多いのですが、
一つのCDを聴くと、
それに付随して、
同じ作曲家や、
演奏家の
CDを聞き始めることがあります。
そこで今日の一枚。

ラヴェル/ダフニスとクロエ
ユニバーサルミュージック UCCD7092
エルネスト・アンセルメ指揮
スイスロマンド管弦楽団
このCDはエルネスト・アンセルメ指揮、スイスロマンド管弦楽団による、ダフニスとクロエ。いかにも、アンセルメらしい、色彩感と、整理された音楽、そして、アナログレコード時代とは思えないほど、卓越した録音技術。現在の優秀な録音をもある意味凌駕するような録音です。さすがに、デジタル時代のダイナミックレンジの広い録音には及ばないかもしれませんが、ダイナミックレンジの狭さを補って余りある記録です。マ・メールロワの洗練された演奏にも感動。
ダフクロを聞き比べてみたい方にオススメの一枚。
2009年05月23日
音楽を創る技量。
サクソフォンアンサンブルコンサートに
向けた曲目も徐々に決まりつつあります。
さて、
音楽を創る
という意味では、
作曲もそうですが、
指揮者や
演奏者も
音楽を創る人たちです。
何かの曲に長期間取り組むとき、
その曲を理解しようと、
いろいろな演奏を聞いてみたり、
楽譜を細かく読んでみたり、
その作曲家のことを
調べてみたり、
と色々やりますが、
高々私ごときのやることなので、
たいしたことは出来ないのですが…。
そこで今日の一枚です。

天国と地獄
アンセルメ/フランス音楽コンサート
エルネスト・アンセルメ指揮
スイスロマンド管弦楽団
London(ユニバーサルミュージック) UCCD7033
このCDは、アンセルメ指揮、スイスロマンド管弦楽団による、フランス音楽の作品集。シャブリエや、トマ、オネゲルと言った作曲家の作品が収録されています。アンセルメの指揮によって紡ぎだされる音楽は、まさに音楽を創りだした結果そのもの。オケの技量を十分に引き出し、色彩豊かに音楽を創り出しています。
色彩豊かなフランス音楽を楽しんでみたい方にオススメの一枚です。
向けた曲目も徐々に決まりつつあります。
さて、
音楽を創る
という意味では、
作曲もそうですが、
指揮者や
演奏者も
音楽を創る人たちです。
何かの曲に長期間取り組むとき、
その曲を理解しようと、
いろいろな演奏を聞いてみたり、
楽譜を細かく読んでみたり、
その作曲家のことを
調べてみたり、
と色々やりますが、
高々私ごときのやることなので、
たいしたことは出来ないのですが…。
そこで今日の一枚です。

天国と地獄
アンセルメ/フランス音楽コンサート
エルネスト・アンセルメ指揮
スイスロマンド管弦楽団
London(ユニバーサルミュージック) UCCD7033
このCDは、アンセルメ指揮、スイスロマンド管弦楽団による、フランス音楽の作品集。シャブリエや、トマ、オネゲルと言った作曲家の作品が収録されています。アンセルメの指揮によって紡ぎだされる音楽は、まさに音楽を創りだした結果そのもの。オケの技量を十分に引き出し、色彩豊かに音楽を創り出しています。
色彩豊かなフランス音楽を楽しんでみたい方にオススメの一枚です。
2009年05月22日
真面目に練習しないと。
新型インフルエンザ、
流行るのはもう必至だと思うのですが、
なぜ、こんなにマスクがなくなるのか…。
ちょっと理解の範疇をこえています。
マスクを買い込んでいる人たちの
果たしてどのぐらいの割合の人が
マスクの正しい使用法を知っているのか…。
疑問で仕方ありません。
さて、
秋のアンサンブルコンサートに向けて、
小編成の曲が決定しつつあります。
ダッパー公式ブログにもあるように、
私の参加するカルテットは
ランティエ作曲、
アンダンテとスケルツェット。
難易度がとびきり高い曲では
ありませんが、
逆にしっかりとした
音楽づくりが
必要になっています。
もっと真面目に練習しないと。
そこで今日の一枚です。

シューベルト/交響曲第8番『未完成』
ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル
Altus ALT053
このCDは、ムラヴィンスキー指揮、レニングラードフィルの1977年日本公演のときのライヴ録音。ムラヴィンスキーの演奏で、一番残念なのは、いい録音があまりないこと。この録音は比較的よい録音ですが、それででも、ダイナミックレンジの取り方に、明らかに失敗していることが聞いて取れる部分があります。全体的に録音に雰囲気が感じられないのも残念。逆に言えば、爆音と、この上ない弱音を体験することは出来ます。
それにしても、録音の悪い中、これだけの演奏を感じて取れるムラヴィンスキーの凄さ。出来ることなら、実際の演奏を生で聞いてみたかったとつくづく思います。なにものにも譲れない、確固とした音楽性のある演奏ではないかと。
ムラヴィンスキーの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚。
流行るのはもう必至だと思うのですが、
なぜ、こんなにマスクがなくなるのか…。
ちょっと理解の範疇をこえています。
マスクを買い込んでいる人たちの
果たしてどのぐらいの割合の人が
マスクの正しい使用法を知っているのか…。
疑問で仕方ありません。
さて、
秋のアンサンブルコンサートに向けて、
小編成の曲が決定しつつあります。
ダッパー公式ブログにもあるように、
私の参加するカルテットは
ランティエ作曲、
アンダンテとスケルツェット。
難易度がとびきり高い曲では
ありませんが、
逆にしっかりとした
音楽づくりが
必要になっています。
もっと真面目に練習しないと。
そこで今日の一枚です。

シューベルト/交響曲第8番『未完成』
ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル
Altus ALT053
このCDは、ムラヴィンスキー指揮、レニングラードフィルの1977年日本公演のときのライヴ録音。ムラヴィンスキーの演奏で、一番残念なのは、いい録音があまりないこと。この録音は比較的よい録音ですが、それででも、ダイナミックレンジの取り方に、明らかに失敗していることが聞いて取れる部分があります。全体的に録音に雰囲気が感じられないのも残念。逆に言えば、爆音と、この上ない弱音を体験することは出来ます。
それにしても、録音の悪い中、これだけの演奏を感じて取れるムラヴィンスキーの凄さ。出来ることなら、実際の演奏を生で聞いてみたかったとつくづく思います。なにものにも譲れない、確固とした音楽性のある演奏ではないかと。
ムラヴィンスキーの演奏を聞いてみたい方にオススメの一枚。
2009年05月21日
懐かしくも新しい。
最近、一昔、二昔前のものが
復刻されたり、形を変えて新たに
発売されたりすることがよく
あるようです。
まあ、ガンプラやら、
マジンガーZの
こんな調合金が発売されたり、
と、
いろいろ懐かしいものが生まれているようですが、
まあ、子どもの数が減って、
玩具メーカーやら
色々なメーカーも、
子どものためだけの小品を作っていたのでは
先細りが見えているので、
こういったものを作っているのかも
知れません。
まあ、小さい頃に、見聞きしたことは
大人になっても自分の中に
残り続けているということでしょうか。
古きよきものは、
いつまでたっても
いいものであり続けるということでしょうか。
そこで今日の一枚です。

Quatuor Jean Ledieu
Polymnie POL490115
このCDは、リュデュー・サクソフォーン・カルテット最後のアルバム。テナーは、ヤン・ルマリエ氏が参加していますが、これは、このアルバムが最初で最後のようです。曲目は、パスカルや、プラネル、リュエフなど、まさにフランスのエスプリを感じさせるもの。演奏もそのものズバリ。あの、デファイエカルテットのような、まさに、ミュールからの流れを汲むようなフレンチスタイルの演奏を堪能できます。
フランス流のサクソフォーンカルテットを堪能してみたい方にオススメの一枚。
復刻されたり、形を変えて新たに
発売されたりすることがよく
あるようです。
まあ、ガンプラやら、
マジンガーZの
こんな調合金が発売されたり、
と、
いろいろ懐かしいものが生まれているようですが、
まあ、子どもの数が減って、
玩具メーカーやら
色々なメーカーも、
子どものためだけの小品を作っていたのでは
先細りが見えているので、
こういったものを作っているのかも
知れません。
まあ、小さい頃に、見聞きしたことは
大人になっても自分の中に
残り続けているということでしょうか。
古きよきものは、
いつまでたっても
いいものであり続けるということでしょうか。
そこで今日の一枚です。

Quatuor Jean Ledieu
Polymnie POL490115
このCDは、リュデュー・サクソフォーン・カルテット最後のアルバム。テナーは、ヤン・ルマリエ氏が参加していますが、これは、このアルバムが最初で最後のようです。曲目は、パスカルや、プラネル、リュエフなど、まさにフランスのエスプリを感じさせるもの。演奏もそのものズバリ。あの、デファイエカルテットのような、まさに、ミュールからの流れを汲むようなフレンチスタイルの演奏を堪能できます。
フランス流のサクソフォーンカルテットを堪能してみたい方にオススメの一枚。
2009年05月16日
姿勢悪い。
この間、
先日の
高松ウインドシンフォニー第25回定期演奏会の
写真が、WebアルバムにUPました。
で、
リハ風景を見ると…



姿勢悪っ!!!!
まあ、普段から猫背ですから…。
中高生に、偉そうには絶対に言えんな。
先日の
高松ウインドシンフォニー第25回定期演奏会の
写真が、WebアルバムにUPました。
で、
リハ風景を見ると…
姿勢悪っ!!!!
まあ、普段から猫背ですから…。
中高生に、偉そうには絶対に言えんな。
2009年05月15日
ゆったり。
最近、ストレスが溜まっていることを感じます。
目をシバシバしたくなったり、
鼻をグスグスしたくなったりと、
チックとまではいきませんが、
それに近い状態になったり、
ため息が増えたりしています。
一応、音楽を趣味にしていますが、
アクティブな趣味を全く持っていないこともあり、
どこかに気晴らしにいきたいですが、
元来出不精のため、
突然、どこに出かけようとか思い浮かばないのが現実。
結局休みの日は、
アンサンブルや吹奏楽の練習に出かけるか、
家でぼーっとして過ごすことがほとんどです。
まあ、家でゆったりできればいいのですが、
環境が変わらないので、
体の疲れは取れても、
ストレスは溜まる一方だったりします。
本当の意味でゆったりできればいいのですが。
そこで今日の一枚です。

パブロ・カザルス
コンプリートEMIレコーディングス1926-1955(9CD)
EMI 6949322
このCDはチェロの神様とも言うべき、パブロ・カザルスがEMIレーベルに残した歴史的とも言うべき録音が収録されたもの。モノラル録音ですが、脅威の9枚組み。バッハの無伴奏チェロ組曲はもちろん、数々の演奏が収録されています。カザルスは、チェロの現代奏法の始祖とも言うべき人物。また、テンポや強弱だけでなく、音程でも表現をつけていたといわれるその演奏は、不思議と、懐かしさやゆっくりとした時間の流れまでを感じさせてくれるようです。
心に沁みる演奏をお探しの方にオススメの一枚。
目をシバシバしたくなったり、
鼻をグスグスしたくなったりと、
チックとまではいきませんが、
それに近い状態になったり、
ため息が増えたりしています。
一応、音楽を趣味にしていますが、
アクティブな趣味を全く持っていないこともあり、
どこかに気晴らしにいきたいですが、
元来出不精のため、
突然、どこに出かけようとか思い浮かばないのが現実。
結局休みの日は、
アンサンブルや吹奏楽の練習に出かけるか、
家でぼーっとして過ごすことがほとんどです。
まあ、家でゆったりできればいいのですが、
環境が変わらないので、
体の疲れは取れても、
ストレスは溜まる一方だったりします。
本当の意味でゆったりできればいいのですが。
そこで今日の一枚です。

パブロ・カザルス
コンプリートEMIレコーディングス1926-1955(9CD)
EMI 6949322
このCDはチェロの神様とも言うべき、パブロ・カザルスがEMIレーベルに残した歴史的とも言うべき録音が収録されたもの。モノラル録音ですが、脅威の9枚組み。バッハの無伴奏チェロ組曲はもちろん、数々の演奏が収録されています。カザルスは、チェロの現代奏法の始祖とも言うべき人物。また、テンポや強弱だけでなく、音程でも表現をつけていたといわれるその演奏は、不思議と、懐かしさやゆっくりとした時間の流れまでを感じさせてくれるようです。
心に沁みる演奏をお探しの方にオススメの一枚。
2009年05月14日
懐かしくない。
先日来、ちょっとある曲が話題に上ることがありました。
曲名は
アルヴァマー序曲。
J.バーンズ作曲の吹奏楽曲です。
で、私の身の回りに居る吹奏楽経験者は
一様に
懐かしい
思い出深い、
昔やったことがある、
等の感想を持っているようです。
ところが、私はこの曲に対して、
何の思い入れもありません。
中学、高校、大学を通じて
一度も演奏したことすらありません。
高松ウインドシンフォニーでも、
楽譜を読んで練習したことはありますが、
本番で演奏したことはなく、
すなわち、きちんとした機会に演奏したことは
一度もないわけです。
ところが私の周囲の大半の
吹奏楽経験者の人々は
演奏した経験を持っているようです。
その違いがどこにあるのかは私自身
判りませんが、
ともかく、私が今まで
演奏したことがないことの方が、
周囲の人にしてみたら、
特異なことのようです。
そこで今日の一枚です。
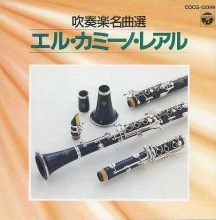
吹奏楽名曲選 エル・カミーノ・レアル
フレデリック・フェネル指揮
佼成ウインドオーケストラ
コロムビア COCG-13099
このCDは佼成ウインドオーケストラの演奏、フレデリック・フェネル氏指揮による吹奏楽のオリジナル曲集です。おそらく10年以上前のCDなので、収録されている曲は決して新しい曲ではありません。
曲目は、アルフレッド・リード/エル・カミーノ・レアル、アルフレッド・リード/小組曲、フランク・エリクソン/序曲祝典、ジェームズ・バーンズ/アルヴァマー序曲、ジョセフ・オリヴァドーティ/バラの謝肉祭、齋藤高順/交響詩「オンリー・ワン・アース」、兼田敏/吹奏楽のためのバラードI、保科洋/吹奏楽のためのカタストロフィ、となっています。
どれも結構古い曲と化しているのかもしれません。最近余り演奏されなくなってしまっている曲、昔ほど演奏されなくなった曲もある気がします。演奏の方は…うーん、しっかりとしてはいますが、あまり上質とはいえないかもしれません。
ちょっと古い吹奏楽曲が懐かしい方にオススメの一枚。
曲名は
アルヴァマー序曲。
J.バーンズ作曲の吹奏楽曲です。
で、私の身の回りに居る吹奏楽経験者は
一様に
懐かしい
思い出深い、
昔やったことがある、
等の感想を持っているようです。
ところが、私はこの曲に対して、
何の思い入れもありません。
中学、高校、大学を通じて
一度も演奏したことすらありません。
高松ウインドシンフォニーでも、
楽譜を読んで練習したことはありますが、
本番で演奏したことはなく、
すなわち、きちんとした機会に演奏したことは
一度もないわけです。
ところが私の周囲の大半の
吹奏楽経験者の人々は
演奏した経験を持っているようです。
その違いがどこにあるのかは私自身
判りませんが、
ともかく、私が今まで
演奏したことがないことの方が、
周囲の人にしてみたら、
特異なことのようです。
そこで今日の一枚です。
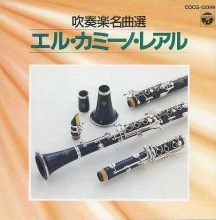
吹奏楽名曲選 エル・カミーノ・レアル
フレデリック・フェネル指揮
佼成ウインドオーケストラ
コロムビア COCG-13099
このCDは佼成ウインドオーケストラの演奏、フレデリック・フェネル氏指揮による吹奏楽のオリジナル曲集です。おそらく10年以上前のCDなので、収録されている曲は決して新しい曲ではありません。
曲目は、アルフレッド・リード/エル・カミーノ・レアル、アルフレッド・リード/小組曲、フランク・エリクソン/序曲祝典、ジェームズ・バーンズ/アルヴァマー序曲、ジョセフ・オリヴァドーティ/バラの謝肉祭、齋藤高順/交響詩「オンリー・ワン・アース」、兼田敏/吹奏楽のためのバラードI、保科洋/吹奏楽のためのカタストロフィ、となっています。
どれも結構古い曲と化しているのかもしれません。最近余り演奏されなくなってしまっている曲、昔ほど演奏されなくなった曲もある気がします。演奏の方は…うーん、しっかりとしてはいますが、あまり上質とはいえないかもしれません。
ちょっと古い吹奏楽曲が懐かしい方にオススメの一枚。





